- IFAの平均年収はどのくらいなのか知りたい
- IFAの報酬はどのように決まるのか教えてほしい
- 業務委託と正社員の報酬形態の違いを教えてほしい
IFAには業務委託を受けて働く方法と、IFA法人に正社員として所属して働く方法の2種類がある。IFAへの転職を検討する際、どちらの契約形態で働くか悩む人も多いだろう。
しかし、実際にはどのような仕組みで報酬が与えられるのだろうか。IFAへの転職を検討する上で、報酬制度については最も気になる点ともなる。
今回は、IFAの平均年収と報酬制度について詳しく見ていこう。
\120人以上のIFAの転職を支援/
IFAの報酬に関する基礎知識
IFAは、営業成果が収入へ直結する点が大きな魅力だ。しかし、実際にはどのような仕組みで報酬が与えられるのだろうか。IFAへの転職を検討する上で、報酬制度については最も気になる点だろう。
まずは、IFAが受け取るお金の流れを紹介する。
IFAが受け取るお金の流れ
個人のIFAが受け取るお金の流れは、顧客が支払う手数料から始まる。
その手数料の一部を証券会社が受け取り、残りの手数料がIFA法人に支払われ、最終的に所属するIFAにその一部が支払われるのだ。
例えば、顧客が支払った100の手数料のうち、証券会社が受け取るのは約30であり、残りの約70がIFA法人に渡る。
このIFA法人に渡る手数料から、さらに所属するIFAへと報酬が渡されるのだ。

証券会社からIFA法人に支払われる手数料の割合は、基本的にIFA法人の規模によって決まる。規模が小さい場合は還元率が65%程度だが、一定以上の規模になると75%程度が還元される。
IFA法人から所属するIFAへの還元率は、各IFA事業者によって自由に定められており、大きく異なる。
例えば、正社員とフルコミッションの業務委託に体系を分けた場合、還元率の概念がなく、固定給与で支払われる形態もあれば、高いインセンティブ率を設けているところもある。
最も高いインセンティブ率が設けられているIFA法人では、証券会社からの手数料の90%程度がIFAの報酬となるケースもある。
\120人以上のIFAの転職を支援/
IFAの報酬体系とバック率
次は、IFAの報酬体系について紹介しよう。
IFAには「業務委託型IFA」と「社員型IFA」の2種類があり、それぞれの働き方によって報酬体系が異なる。
| 業務委託型IFA | コミッション型 |
|---|---|
| ハイブリッド型(固定報酬+インセンティブ) | |
| 正社員型IFA | ハイブリッド型(固定報酬+インセンティブ) |
| 固定給 |
それぞれの報酬体系について、詳しく解説していこう。
コミッション型
コミッション型の報酬は、顧客が証券会社に支払った取引手数料の一部がIFAに還元されるものである。
手数料の還元率はIFA法人の規定や個人の経歴によって異なるが、一般的には50〜90%程度とされている。
例えば、70%の還元率で月に100万円の手数料を稼いだ場合、IFA個人には70万円の報酬が支払われる仕組みだ。
IFAの報酬について「会社員時代よりも年収がアップする」「IFAは儲からない」などと両極端のことがいわれるのは、取引手数料の多寡によって収入が大きく影響を受けるためだろう。
固定給
業務委託型IFAでは「コミッション型」や「残高フィー型」の報酬体系が採用されているが、社員型IFAでは固定給を定めていることが一般的だ。
固定給の水準はIFA法人によって異なるが、前職の年収や経験を考慮してもらえることが多い。
実質収入が青天井となる業務委託型IFAと違って、社員型IFAは前職から飛躍的に年収がアップする可能性は低いかもしれない。
ただし、収入が安定している点や営業成績が収入に直結しにくい点が大きなメリットといえる。
ハイブリッド型(固定報酬+インセンティブ)
先ほど紹介した2つの報酬形態のいいところ取りが、「ハイブリッド型」である。
この形態は、顧客から収受する手数料に基づいたインセンティブ体系が取られているが、固定給与部分があるという安心感もある。
古くからの証券会社のFA社員や外資系PBの企業形態に似ている。
固定給与は同一の法人でも人によって異なるが、概ね月額20万円から100万円程度であり、プラスでインセンティブが支払われるという形態である。
この場合のインセンティブ率は、手数料に対して30%から50%程度が一般的である。
ハイブリッド型で働くには、正社員型と業務委託型のどちらでも可能であるが、この報酬形態を採用しているIFA法人は少なく、さらに非公開求人であるケースが多い。
そのため、ハイブリッド型の求人に関心がある場合は、転職エージェントに相談することをおすすめする。
\120人以上のIFAの転職を支援/
IFAの報酬が発生するタイミングとは

IFAの報酬は、顧客が証券会社へ支払った取引手数料の一部が還元される仕組みで成り立つと説明した。
では、具体的にはどのようなタイミングで報酬が発生するのだろうか。
ここでは、報酬の対象となる手数料と報酬を受け取るタイミングを解説する
報酬の対象となる手数料
顧客が支払う手数料のうち、どれがIFAの報酬に直結するのだろうか。
以下がその一例である。
- 株式の売買で発生する取引手数料
- 投資信託・債券の販売手数料
- 投資信託を保有している間の信託報酬
- 保険商品の販売手数料
たとえば、販売手数料が3.3%(税込)の投資信託を1,000万円販売した時の報酬について考えてみよう。顧客が証券会社へ支払う購入手数料は、1,000万円×3.3%=33万円となる。
この手数料を証券会社とIFA法人で按分することになるが、割合については証券会社とIFA法人の業務委託契約の内容によって異なる。仮に販売手数料の70%がIFA法人に還元される場合は、33万円×70%=23万円1千円がIFA法人の売上となる計算だ。
ここからIFA個人に与えられる報酬についても、IFA法人とIFA個人との契約内容によって異なる。一般的には50~90%の還元率となることが多いが、IFAの業務経験を重視しているIFA法人もあるようだ。
このケースでは仮に80%の還元率とすると、23万円1千円×80%=18万4,800円がIFA個人の報酬となる。
つまり、投資信託を1,000万円販売することによって、およそ18万5千円の報酬が得られるということだ。もちろん、販売する金融商品やIFA法人との契約内容によっても手数料金額が変わってくるため、おおよその目安として捉えておこう。
また、提携する証券会社によっては売買手数料による報酬だけでなく、顧客の預かり資産残高に応じて報酬をIFAへバックしているところもある。これにより、IFAは手数料獲得のために顧客へ回転売買を勧める必要がなく、より顧客の目線に立った提案が可能となるメリットがある。
顧客へ良い提案を行い預かり資産が増加することによりIFAの報酬も増加する仕組みであるため、まさに顧客・IFA双方にwin-winな仕組みとなっているのだ。
金融機関でのノルマありきの営業に疑問を感じている人にとっては、魅力的な報酬制度といえるだろう。
IFAの報酬が発生するタイミング
IFAの報酬が発生するタイミングは、基本的にはフルコミッションの場合、顧客が手数料を支払った翌月に支払われることが多い。
例えば、IFAが顧客への提案を行い、8月に受注した場合、報酬は9月の支払日にIFAの口座に振り込まれる。
ただし、正社員の場合は毎月支払われるとは限らない。
賞与月が定められており、半年に一度、または年に一度まとめて支払われることもあるので注意が必要である。
\120人以上のIFAの転職を支援/
IFAの平均報酬

IFAの平均報酬については、公に開示されているデータが存在しない。
この理由として、IFAの業務形態が業務委託であり、専業でIFA活動のみを行う人もいれば、保険募集人や税理士として本業があり、その傍らでIFA活動を行う人もいるためである。
また、複数の証券会社と兼業している人も多く、統一したデータが存在しないことも一因である。
本段落では、アドバイザーナビが独自に行った調査や求人情報からIFAの平均年収を想定してみるので、参考にしてほしい。
業務委託IFAの平均年収
まずは、業務委託IFAの平均年収から推測してみる。
上述の通り、業務委託IFAはフルコミッション型が多く、年間手数料額が年収に直結する。
アドバイザーナビが現役IFAを対象に行ったアンケートの結果によれば、年間手数料が500万円以上3,000万円未満の人が約半数を占めていた。
これに基づくと、専業IFAの平均年収は1,000万円程度と想定される。
また、IFA法人大手の「株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル」が2021年11月に公開した決算説明資料を基に、所属するIFAの年収を推定することもできる。
「2022年3月期第2四半期 決算説明資料」によると、2022年3月期 第2四半期における金融商品仲介業での売上高は18億8,200万円となっている。
アイ・パートナーズフィナンシャルでの報酬体系は、手数料収入の90%がIFA個人へ還元される仕組みとなっており、これを第2四半期末に所属しているIFA211人で計算してみると、(18億8,200万円×90%)÷211人=約802万円。
つまり、1人あたり約800万円の年収となる計算だ。
また、アイ・パートナーズフィナンシャルは1人あたり月10万円のシステム利用料が差し引かれるため、実質は800万円-120万円(システム利用料)=680万円ほどの年収と予想される。
ただし、IFA業界の年収には大きな乖離があり、年間報酬が1億円を超える人もいれば、500万円未満の人もいるため、個人による年収の差が非常に大きい業界であると言える。
正社員型IFAの平均年収
主に集客を会社が担う正社員型のIFAで導入されている固定給与型の報酬体系は、固定給+賞与の報酬体系である。
正社員型IFAは、IFA法人からの固定給と成績を元に決められる期末手当・ボーナスを受け取る。
要するに一般的な企業と同じで、収入の幅にはある程度の限界があるのが固定給与型の報酬体系の特徴だ。
とはいえ、固定給与型の報酬体系も、年収500万円から2,000万円程度と幅広い価格帯の年収を提示する求人がネット上に掲載されている。
顧客本位の営業が体現できる上に、転勤がない環境で働くことができ、さらに金融機関と同水準の給与を受け取れるのであれば良い環境であると言えるのではないだろうか。
\120人以上のIFAの転職を支援/
IFAの契約形態の違い

報酬体系が理解できたら、次は雇用形態ごとの働き方について解説する。
先述の通り、IFAには業務委託を受けて働く方法と、IFA法人の正社員として働く方法の2種類の働き方がある。IFA法人から業務委託を受けて働く場合は、「個人事業主」として開業して働くこととなる。元々IFAとしての働き方は、この業務委託を受けて働く方法が一般的であった。
しかし最近では、IFA法人に正社員として雇用されて働く方法を選ぶ人も増えてきている。以下の表は金融庁が2018年12月に、国内で預かり資産残高の大きい金融商品仲介業者10社を対象に行った調査結果である。
| 合計 | 割合 | |
|---|---|---|
| 所属外務員との契約形態 | ||
| 正社員(固定給) | 4社 | 40.0% |
| 業務委託社員(歩合給) | 3社 | 30.0% |
| 正社員・業務委託混在 | 3社 | 30.0% |
| 契約形態別外務員数 | ||
| 正社員(固定給) | 110人 | 30.1% |
| 業務委託社員(歩合給) | 255人 | 69.9% |
表からも分かる通り、IFA法人とIFAの契約形態にはそれほど偏りはなく、正社員のIFAのみとしているところや、業務委託のみとしているところ、それぞれ混在しているところもほぼ同じ割合である。
一方、10社に所属している全体のIFAの人数割合で見たところ、業務委託を受けて働いているIFAの方が多い結果となった。これは従来、IFAは業務委託を受けて働くスタイルが一般的であったためと推測される。
では、この両者の働き方の違いにはそれぞれどのようなメリット・デメリットがあるのだろうか。以下の項目で詳しく解説していく。
\120人以上のIFAの転職を支援/
業務委託型のメリット・デメリット
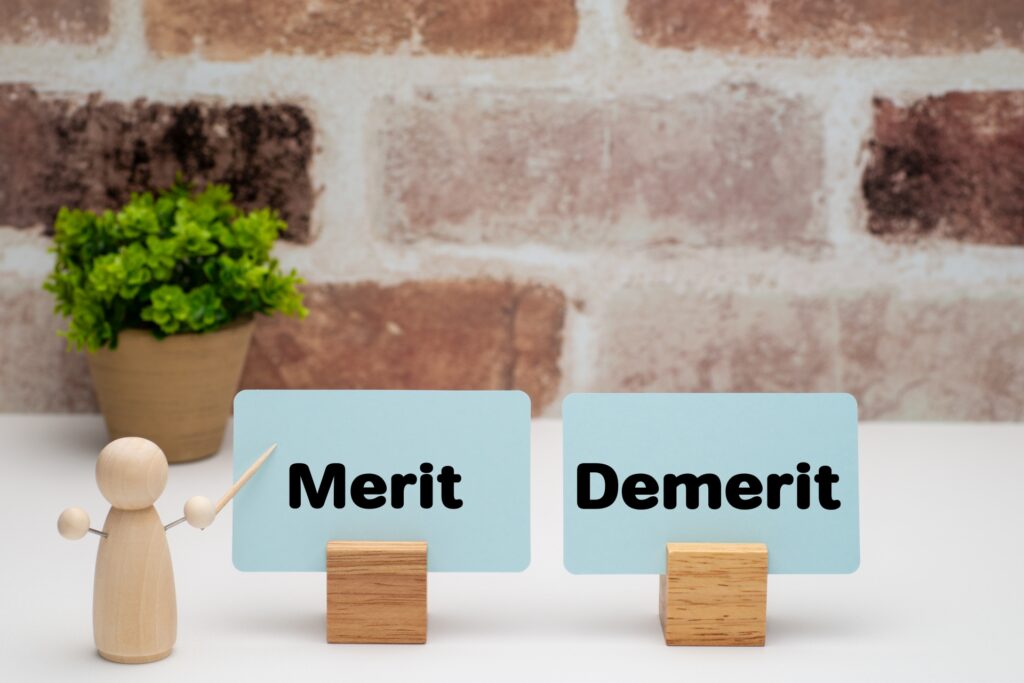
まずは業務委託型のIFAのメリット・デメリットについて見ていこう。
業務委託型IFAのメリット
- 勤務時間の拘束がない
- 契約の成果が収入に直結する
- 会社都合の転勤がない
- 顧客と長く関係を構築できる
- ノルマ営業がない
- 他の仕事と兼業できる
業務委託型IFAは「個人事業主」扱いとなるため、IFA法人による勤務時間や勤務日などの制約を受けることがない。そのため、自分のライフスタイルに合った働き方を選択することが可能だ。
IFA事務所への出社について最低頻度を定めているところもあるが、それでも週に1回、月に1回などが一般的となっている。働き方の縛りがないことから税理士や会計士、FPなどと兼業でIFAを務める人も多く、1つの働き方に捉われない自由さがあるといえる。
また業務委託型IFAは、自分が獲得した契約の成果が収入に直結することも魅力のひとつだ。会社員時代とは違い成果が目に見えて反映されるため、収入面からもやりがいを感じられる。
業務委託型IFAのデメリット
- 収入が安定しない
- 事務負担が増える
- IFA同士のつながりが希薄な場合がある
- 土日にも顧客対応が発生する
- システム利用料を求められる場合がある
一方、業務委託型IFAのデメリットとして、収入が安定しないことが挙げられる。先ほど成果が収入に直結する点をメリットとして挙げたが、これは裏返せば「成果が取れなければ収入が下がる」ということでもある。
収入を安定させるためには継続して成果を上げる必要があるため、その点を不安に感じている人も多いだろう。
また業務委託型IFAは、勤務時間を自由にコントロールできる分、土日にも顧客対応が発生することがある。自身で「土日祝日は休み」と決めていても、顧客から面談を求められれば実状として断ることは難しいだろう。
そのため、「自由に勤務時間を決められる分、つい働き詰めになってしまう」ということも起こり得るのだ。ただしこの点については、顧客に対応時間を周知するなど、ある程度コントロールすることは可能といえる。
\120人以上のIFAの転職を支援/
正社員型IFAのメリット・デメリット
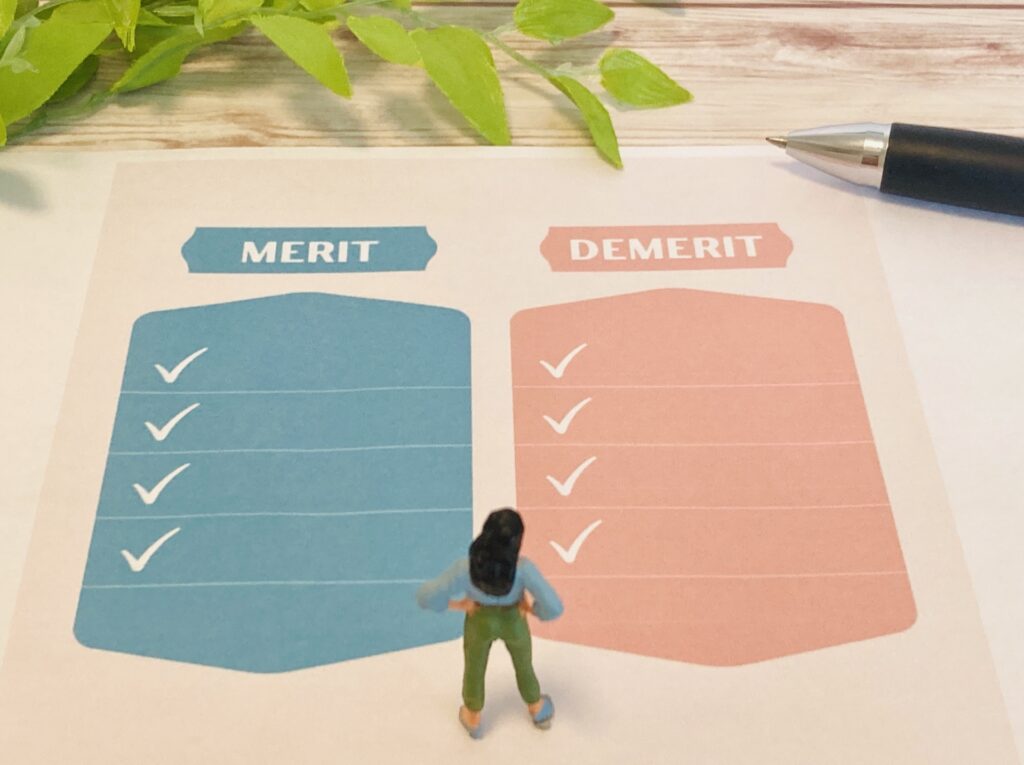
次に、正社員型IFAのメリット・デメリットについて見ていこう。
正社員型IFAのメリット
- 給与が安定している
- 休日が定められている
- 会社都合の転勤がない
- 顧客と長く関係を構築できる
- 自己啓発のサポートが受けられる
- 他のIFAと切磋琢磨できる
正社員型IFAのメリットとして、給与が月給制で安定していることが挙げられる。契約の成果が思うほど上げられない月でも定められた月給が保証されるため、生活の心配をすることは少ないだろう。
また正社員型IFAは、正社員ならではの福利厚生も享受できる。休日がしっかりと定められており、よほどのことがなければ休日に顧客対応することは少ない。
IFA法人によっては自己研鑽のためのセミナー・研修の開催や、資格取得の支援体制など、自己啓発に関するサポートが受けられるところもある。
業務委託型IFAの場合は、自分でコストをかけて自己啓発に取り組まなければいけないが、正社員型IFAの場合は会社が人材育成の支援をしてくれるのである。
正社員型IFAのデメリット
- 業務委託型に比べインセンティブが低い
- ノルマが課される場合がある
- 金融機関の職員時代と仕事内容が変わらない
- 時間が拘束される
- 会社の方針に従う必要がある
一方、正社員型IFAのデメリットとして、業務委託型IFAと比べて成果に対するインセンティブが低いことが挙げられる。手数料収入はIFA法人と按分になるため、バック率によってはそれほど収入が上がらないということもあるだろう。この点はIFA法人によって契約が異なるため、転職前に確認が必要である。
またIFA法人によっては、営業ノルマを課すところもある。真に顧客に寄り添った提案ができるIFAを目指して転職したにもかかわらず、結局はノルマ営業となってしまうこともあるため、この点についても転職前にIFA法人の方針を確認すべきだろう。
\120人以上のIFAの転職を支援/
IFAは顧客に寄り添った提案をしながら報酬を受け取ることが可能

今回は、IFAの報酬体系について解説してきた。IFAは自分の営業成果が収入に直結することが大きな魅力だ。マーケット環境によっては顧客の手控えで収入が減少してしまうデメリットもあるが、ノルマありきの営業を行わなくていい点は大きなメリットといえる。
また、提携する証券会社によっては、顧客の預かり資産に応じてIFAに報酬が与えられる仕組みを採用しているところもある。
これによって、IFAは営業成果以外にも報酬が得られることとなり、安定した収入にもつながる。IFAは手数料収入のために顧客へ回転売買を勧める必要もないため、真に顧客に寄り添った提案営業が可能となるのだ。
IFAの報酬体系や取引手数料の還元率についてはIFA法人によって異なるため、IFAへの転職を検討する際は必ずそれらの点を確認しておこう。
\120人以上のIFAの転職を支援/
おわりに

IFAに転身する上では必要な資格や雇用体系、報酬の仕組みや証券会社のアドバイザーとの違いについて理解しておくことが大切だ。
まずは証券外務員資格を取得し、金融機関である程度の実務経験を積んでから転職活動を始めよう。
IFAは雇用体系によって報酬の仕組みや働き方が大きく異なる。自分に合った雇用体系を選び、IFAとしての活躍を目指していこう。
IFAになる際に、基本的にはどこかの法人に所属する形を取ることになる。
しかし、全国には約650社ものIFA法人があり、情報を取ることや比較することが難しい。また、
「いくらぐらいの預かりがあれば良いのか?」
「金融機関時代の様なビジネスはできるのか?」
等、IFAになること自体に対する不安の声も多い。IFAへの転職に悩んでいる方は、ぜひIFA特化型の転職エージェント「アドバイザーナビ」に相談してみて欲しい。
弊社はこれまでに100名以上のIFAへの転職支援実績があり、「IFAへの転職利用満足度No.1」を獲得している。まずは情報収集をしたいといったカジュアルな形からでも無料で面談ができるので、お気軽に相談してみてほしい。
最近は異動時期や賞与の時期が近いということもあり、毎日多くのご相談をいただいている。現在、弊社代表も現場に出て転職エージェントとして面談をしているが、面談予約枠に限りがあるので早めの申し込みをおすすめする。
面談のお申し込みは下記フォームからお申し込みを。
\120人以上のIFAの転職を支援/








