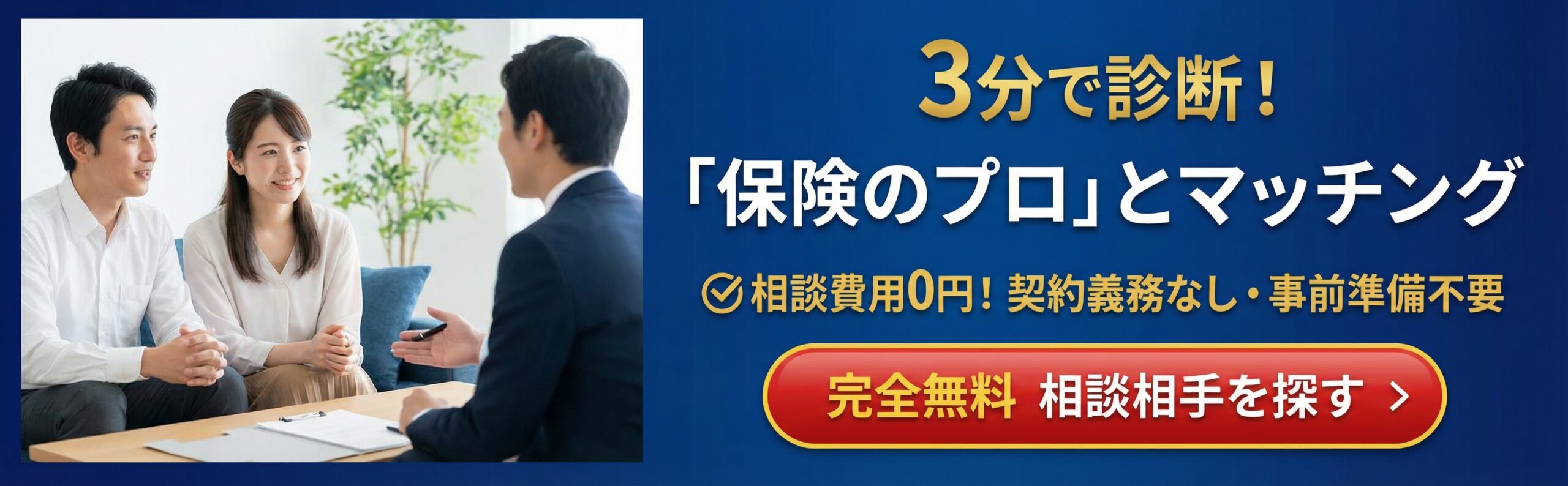「社会人になったから」「結婚したから」と、かつて加入した生命保険。毎月の保険料が銀行口座から引き落とされているものの、現在の保障内容を正確に把握できているだろうか。
日本では2人以上世帯の約9割が生命保険に加入しており、1世帯あたりの死亡保障額は平均約1,936万円、年間払込保険料は平均約35.3万円にものぼる(2024年度 生命保険文化センター調査)。決して安くない金額を支払い続けているにもかかわらず、「契約した当時のまま」放置しているケースは少なくない。
しかし、人生は変化の連続だ。結婚、出産、住宅購入、子どもの独立といったライフイベントや、医療技術の進歩によって、「本当に必要な保障」は刻々と変わる。見直しをせずにいると、無駄な保険料を払い続けたり、いざという時に保障が足りない事態に陥ったりするリスクがある。
本記事では、40代〜60代の現役世代に向けて、生命保険を見直すべき「具体的なタイミング」と、失敗しないための「判断基準」を解説する。保険は一度入って終わりではない。今の自分と家族を守るために、最適な形へアップデートしていこう。
- 今の保険が自分に合っているか判断できない
- 保険料が高く、家計の負担になっている
- 見直しをしたいが、どのタイミングですべきかわからない
- 保障を減らしてしまい、後悔しないか不安だ
生命保険見直しの目的と基本
生命保険の見直しとは、単に「安い商品に乗り換える」ことだけではない。目的は、「現在の生活状況」と「将来のリスク」に合わせて、保障のサイズと種類を最適化することにある。
保障額を増減させる、特約を付け外す、払込期間を変更するなど、手段は多岐にわたる。まずは、どのような状況で見直しが必要になるのか、その全体像を押さえておこう。
生命保険見直しが必要になる主な状況
| 分類 | 具体的なトリガー(きっかけ) |
| ライフイベント | 結婚、出産、離婚、住宅購入・完済、子どもの独立、定年退職など |
| 家計・収入の変化 | 昇給、転職による減収、独立・起業、妻(夫)の働き方の変化 |
| 健康状態の変化 | 持病の発覚、入院・手術の経験 |
| 社会環境の変化 | 公的医療保険制度の改正、新薬や治療法の登場 |
| 保険契約の節目 | 更新時期の到来、満期、解約返戻金のピーク時 |
見直しを検討すべきタイミングは、大きく分けて「自身の変化」「環境の変化」「契約の節目」の3つがある。以下のいずれかに該当する場合は、一度保険証券を取り出して確認してみることをおすすめする。
- ライフイベント: 結婚、出産、離婚、住宅購入・完済、子どもの独立、定年退職など
- 家計・収入の変化: 昇給、転職による減収、独立・起業、妻(夫)の働き方の変化
- 健康状態の変化: 持病の発覚、入院・手術の経験
- 社会環境の変化: 公的医療保険制度の改正、新薬や治療法の登場
- 保険契約の節目: 更新時期の到来、満期、解約返戻金のピーク時
これらはすべて、必要な保障額や支払える保険料が変わるサインだ。
ライフステージや家族構成の変化による保障のずれ
必要保障額(万が一の際に残すべき金額)は、家族構成によって劇的に変化する。
例えば、独身時代は「自分の葬儀代と身辺整理費用」があれば十分な場合が多い。しかし、結婚して子どもが生まれれば、「遺族の生活費」や「教育費」といった大きな保障が必要になる。逆に、子どもが独立すれば教育費の責任はなくなり、必要な死亡保障額はガクンと下がるはずだ。
よくある失敗は、以下の2パターンだ。
- 保障不足: 子どもが増えたのに、独身時代の小さな保障のまま放置している。
- 保障過多: 子どもが独立したのに、子育て期と同じ数千万円の死亡保障を維持し続けている。
世帯の平均死亡保障額が約1,936万円というデータはあるが、これはあくまで平均だ。あなたの家庭に必要な額は、あなた自身の家族構成から計算しなければならない。
医療技術や治療法の変化による保障のずれ
「昔に入った医療保険だから安心」とは限らない。医療技術の進歩により、治療のスタイル自体が変わってきているからだ。
かつては「がんは長期入院で治すもの」だったが、現在は「通院治療」や「短期入院」が主流になりつつある。生涯でがんに罹患する確率は男性約63%、女性約51%とされるが、生存率は向上しており、「仕事をしながら長く治療を続ける」リスクへの備えが重要になっている。
古い医療保険で不足しがちなポイント
- 入院給付金の限度日数が短い(現在の治療実態に合わない)
- 「入院」しないと給付金が出ない(通院治療に対応していない)
- 先進医療や高額な抗がん剤治療への備えがない
今の医療現場に合わない保険では、いざという時に経済的な支えにならない可能性がある。
保険料負担や家計状況の変化による見直しニーズ
どんなに手厚い保障でも、保険料が家計を圧迫して生活が苦しくなっては本末転倒だ。
住宅ローンの返済開始、教育費の増加、あるいは昨今の物価上昇などにより、契約当初よりも保険料の負担感が重くなっている家庭は多い。生命保険文化センターの調査では、世帯年間払込保険料の平均は約35.3万円だが、これはあくまで目安である。
もし保険料支払いのために貯蓄ができていないなら、それは「緊急時の現金不足」という別のリスクを抱えていることになる。
- ムリなく続けられるか
これを基準に、保障額を下げる、掛け捨て型に変更して保険料を抑える、といった調整が必要だ。
生命保険見直しで得られるメリットと注意点
見直しを適切に行えば、家計の無駄を省けるだけでなく、本当に守るべきリスクに対して強くなる。メリットとリスクの両面を理解しておこう。
保障内容と保障額を最適化できるメリット
| 見直しの方向性 | 具体的なアクション | 目的・効果 |
| 不要な部分を削る | 子ども独立後の過剰な「死亡保障」を解約・減額する。 | 保険料の無駄をカットする。 |
| 必要な部分を厚くする | 削って浮いた予算で、「がん」「介護」「就業不能」への備えを追加する。 | 長生きリスクや働けなくなるリスクに対応する。 |
最大のメリットは、限られた予算を有効に配分できる点だ。
- 不要な部分を削る: 子ども独立後の過剰な死亡保障を解約する。
- 必要な部分を厚くする: 削った分の保険料で、がん保障や介護保障、就業不能保障を手厚くする。
このように、ライフプランから逆算して、死亡・医療・介護・老後資金のバランスを整えることができる。公的保障(遺族年金や高額療養費制度)でカバーできる範囲を正しく知れば、民間保険で備えるべき金額は案外少なくて済むかもしれない。
保険料の削減や家計の見える化につながる効果
複数の保険会社でバラバラに加入していると、「何のためにいくら払っているか」が見えなくなりがちだ。見直しを機にこれらを一覧化し整理することで、家計の固定費を削減できる可能性がある。
見直しによる家計改善の例
- 重複していた特約を外し、月数千円の節約に成功
- 貯蓄性の低い保険を見直し、浮いたお金をつみたてNISAなどの資産形成に回す
「なんとなく不安だから」と払い続けていた月1万円は、10年で120万円になる。この資金を教育費や老後資金に回せる効果は大きい。
見直しで保障が不足するリスクとその回避
一方で、安易な見直しにはリスクもある。「節約」を意識しすぎて、必要な保障まで削ってしまっては意味がない。
避けるべき失敗例
- 保険料を減らすために死亡保障を極端に下げ、万一の際に家族が路頭に迷う。
- 解約返戻金を使い込んでしまい、老後の医療費準備がなくなる。
- 健康状態が悪化しているのに今の保険を解約してしまい、新しい保険に入れなくなる(無保険状態)。
これを避けるには、「まず必要保障額を試算し、その後に保険料を調整する」という手順を徹底することだ。また、新しい保険への乗り換え時は、新契約が成立してから古い契約を解約するのが鉄則である。
生命保険を見直す頻度とタイミングの全体イメージ
では、具体的にどのようなスパンで見直せばよいのだろうか。「イベント時の大きな見直し」と「定期的な点検」の2軸で考えるのがおすすめだ。
ライフイベント時と数年ごとの定期点検の違い
| 種類 | タイミング | 目的 |
| ① 大きな見直し | 結婚、出産、住宅購入、退職など | 人生設計の変化に合わせて、保障の土台を一から設計し直す。 |
| ② 定期点検 | 3〜5年ごと、更新時期など | 家計状況や社会制度の変化に合わせて、微調整を行う。 |
ライフイベント時は、必要保障額が数百万円〜数千万円単位で変わるため、必ず設計し直そう。一方、何もイベントがなくても、3〜5年に一度は「保険の車検」のような感覚で点検を行うのが理想だ。
見直しの優先順位を決めるための考え方
「あれもこれも」と完璧を目指すとキリがない。見直し時は、以下の優先順位を意識すると判断しやすくなる。
- 生活破綻を防ぐ保障: 世帯主の死亡、高度障害、働けなくなった時の収入保障。ここが最優先だ。
- 高額出費への備え: がん治療や先進医療、介護など、貯蓄だけでは賄いきれない出費への備え。
- 資産形成・貯蓄: 老後資金や教育資金のための積立。
まずは「生活が破綻するリスク」から守りを固め、余裕があれば貯蓄性保険や特約を検討する。この順番を守れば、大きく判断を誤ることはないだろう。
ライフステージ別にみる見直しタイミング
保険は「一度入れば安心」というものではない。独身、結婚、子育て、老後と、人生のステージが変われば、守るべき相手も必要な金額もガラリと変わるからだ。
今の契約が現在の自分に合っているか、以下のステージごとに確認していこう。
独身期の生命保険見直しポイント
「独身だから保険はいらない」と考える人もいれば、「親に言われて高額な保険に入っている」人もいるだろう。独身期は、誰のために何を残すかを冷静に判断すべき時期だ。
扶養家族の有無とローンの有無で必要保障額を決める
独身で、養うべき家族(配偶者や子ども)がおらず、住宅ローンなどの借金もない場合、高額な死亡保障は基本的に不要だ。
自分に万一のことがあったとき、最低限必要になるのは以下の費用である。
- 葬儀費用
- 身辺整理の費用
- 死後の未払い債務の清算
これらは数百万円程度で収まることが多く、貯蓄で賄えるなら死亡保険自体が不要なケースもある。
ただし、例外がある。親やきょうだいを経済的に扶養している場合や、奨学金の連帯保証人が親になっている場合だ。このケースでは、自分が亡くなることで親族に借金や生活苦を残さないよう、その分をカバーする死亡保障が必要になる。
医療保障と就業不能リスクへの備え方
独身期に最も重視すべきは「死亡保障」ではなく、「生きていくための保障」だ。
病気やケガで長期入院したり、働けなくなったりしたとき、独身者は配偶者の収入に頼ることができない。公的医療保険や高額療養費制度を使えば医療費の自己負担は抑えられるが、以下の費用は全額自己負担となる。
- 入院中の食事代
- 差額ベッド代
- 日用品費
- 休職による収入減少分
特に2人に1人ががんになるといわれる時代、若くても就業不能になるリスクはゼロではない。自分の生活を守るために、医療保険や、働けなくなった時に給付金が出る「就業不能保険」を優先して検討しよう。
結婚・出産期の見直しタイミング
結婚して家族ができると、自分だけの問題ではなくなる。配偶者やこれから生まれる子どもの生活を守る責任が生まれるからだ。
配偶者の収入と共働きかどうかによる死亡保障の考え方
「結婚したから保険に入ろう」と安易に考える前に、夫婦の働き方を確認する必要がある。
共働き夫婦の場合
どちらか一方が亡くなっても、残された側に十分な収入があり、遺族年金も入るならば、そこまで高額な死亡保障は不要かもしれない。「生活レベルを維持するための補填」と考えよう。
片働き(専業主婦・主夫世帯)の場合
大黒柱が倒れると、家計は即座に危機に陥る。そのため、世帯主には手厚い死亡保障が必要だ。一方で、専業主婦(夫)側にも保障は必要である。家事や育児の担い手が不在となれば、外食やベビーシッター、家事代行などの出費が増えるからだ。
子どもの教育費を見据えた必要保障額の増やし方
子どもが生まれると、将来の「教育費」という大きな責任が発生する。
文部科学省の調査等を参考にすると、幼稚園から大学まですべて公立でも約1,000万円、すべて私立なら約2,500万円以上の費用がかかるといわれる。これに生活費を加えた総額が、万一の際に必要な金額だ。
ここから「遺族年金」や「配偶者の収入」を差し引いた金額が、保険で準備すべき「必要保障額」となる。
おすすめなのは、子どもが独立するまでの期間だけをカバーする「収入保障保険」などだ。これは毎月お給料のように保険金が支払われるタイプで、子どもが成長するにつれて受取総額が減っていくため、保険料を合理的に抑えられる。
子育て期の見直しと教育費への備え
子育て真っ只中の時期は、人生で最も高額な保障が必要になるタイミングだ。教育費の準備と、万一の備えのバランスがカギになる。
教育費の目安から逆算した死亡保障と学資準備
教育費への備えは、2本立てで考えるのが基本だ。
- 親が生きている場合: 預貯金、学資保険、NISAなどでコツコツ積み立てる。
- 親が亡くなった場合: 死亡保険金で不足分を埋める。
「すべてを保険で貯めよう」とすると保険料が高くなりすぎて、現在の生活を圧迫してしまう。死亡保障はあくまで「不足分を補うもの」と割り切ろう。
例えば、子どもが大学を卒業するまでにあと1,000万円かかるとする。今、手元に貯金が200万円あるなら、保険で備えるべきは差額の800万円だ。このように計算すれば、無駄に大きな保険に入る必要はなくなる。
子どもの人数が増えたときの保障額の増やし方
第2子、第3子が生まれると、当然ながら必要な生活費や教育費は増える。
多くの人は第1子誕生時に保険に加入するが、第2子以降の誕生時に保障額を見直すのを忘れがちだ。子どもが増えたタイミングで、以下の対応を検討したい。
- 既存の定期保険を増額する。
- 2人目以降の教育費分として、新たに期間の短い定期保険を追加する。
逆に、上の子どもが独立したときは、その分の保障を減らすタイミングでもある。子どもの成長に合わせて、保障のサイズをこまめに調整することが大切だ。
住宅購入と住宅ローン利用時の見直し
住宅購入は、保険料を大きく節約できるチャンスでもある。「家を買ったら保険を見直せ」といわれる理由を見ていこう。
団体信用生命保険と死亡保障の役割分担
住宅ローンを組む際、ほとんどの人が「団体信用生命保険(団信)」に加入する。これは契約者が死亡・高度障害状態になったとき、住宅ローン残高がゼロになる保険だ。
つまり、万一のことがあっても、家族には「ローンのない家」が残る。これまで入っていた死亡保険に「住居費」が含まれていたなら、その分はもう不要だ。
- 見直し前: 生活費 + 教育費 + 住居費
- 住宅購入後: 生活費 + 教育費(住居費は団信でカバー)
この差額分、死亡保障額を減らせば、毎月の保険料を安くできる可能性が高い。
住宅ローン返済後を見据えた保障額の減らし方
住宅ローンを完済する頃には、子どもも独立しているケースが多いだろう。
「借金(ローン)」と「子育て」という2大責任がなくなれば、高額な死亡保障の役目は終わりだ。惰性で契約を続けず、思い切って死亡保障を減額・解約し、浮いたお金を自分たちの老後資金や医療・介護への備えにシフトしていく時期である。
子どもの独立後・セカンドライフ前後の見直し
子どもが巣立つと、家計は「攻め」から「守り」へとフェーズが変わる。自分たちの老後を最優先に考えよう。
子どもの教育費と生活費が不要になった後の保障調整
子どもが経済的に自立したら、親としての責任(死亡保障)はほぼ完了だ。
これまでかけていた数千万円の定期保険や収入保障保険は、解約または大幅な減額を検討しよう。夫婦2人が暮らしていける程度の保障、あるいは配偶者に残したい最低限の金額があれば十分なはずだ。
ここで浮いた保険料は、消費に回すのではなく、老後のための貯蓄や投資に回すのが賢明だ。
老後資金づくりへのシフトと保険の活用方法
生命保険文化センターの調査によれば、多くの人が老後の生活資金に不安を感じている。
この時期からは、死亡保障よりも「長生きリスク」への備えが重要になる。
- 個人年金保険や終身保険で、公的年金の上乗せを作る。
- ただし、予定利率の低い時期に加入した貯蓄性保険は、インフレに弱い側面もある。
保険だけで老後資金を作ることにこだわらず、iDeCoやつみたてNISAなども含めた資産運用全体の中で、保険をどう活用するか考える視点が必要だ。
退職前後・老後の見直し
現役引退は、収入構造が「給与」から「年金」に変わる大きな転換点だ。現役時代の感覚で保険料を払い続けると、家計破綻を招きかねない。
年金収入と医療費・介護費を踏まえた保障の組み立て
公的年金は原則65歳から受給となる。限られた年金収入の中から保険料を払うことになるため、固定費は極力下げるべきだ。
一方で、年齢とともに病気や介護のリスクは高まる。
- 医療保障: 公的医療保険(高齢者は自己負担割合が低い)をベースにしつつ、先進医療や長期入院など、公的保障でカバーしきれない部分を検討する。
- 介護保障: 公的介護保険だけでは不足するサービス費用や、自宅リフォーム費用などに備える。
これらを「すべて保険で」賄おうとすると保険料が高額になる。ある程度は預貯金で対応し、どうしても足りない部分を保険で補うバランス感覚が重要だ。
葬儀費用や相続対策としての死亡保障の活かし方
老後の死亡保障は、遺族の生活費というより「死後の整理資金」の意味合いが強くなる。
- 葬儀・整理費用: 200万〜300万円程度の小口の終身保険を用意しておく。
- 相続対策: 生命保険の死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠がある。現金を保険に変えておくことで、相続税の負担を減らしたり、特定の相続人に現金を渡したりできる。
老後の保険は、自分のためだけでなく、残される家族の手間や負担を減らすためのツールとして活用しよう。
保障内容から考える見直し判断のポイント
ライフステージの変化を確認したら、次は具体的な「保障の中身」にメスを入れていこう。
保険証券を見ると、さまざまな特約や難しい用語が並んでいて、「どこをどう見直せばいいかわからない」と感じるかもしれない。だが、基本的な構造さえ理解すれば、判断は難しくない。
ここでは、プロがチェックする「判断のモノサシ」を共有する。
死亡保障・医療保障・がん保障のバランス
保険には大きく分けて3つの役割がある。手元の契約が「何のための保険か」、役割ごとに整理することから始めよう。
目的ごとの保険の役割を整理する
すべてのリスクに1つの保険で備える必要はない。リスクの種類によって、適した保険商品は異なるからだ。
| リスクの種類 | 目的 | 代表的な保険 |
| 死亡保障 | 遺族の生活費、教育費、住居費の確保 | 定期保険、終身保険、収入保障保険 |
| 医療保障 | 入院・手術費、入院中の雑費(差額ベッド代など)の負担軽減 | 医療保険、医療特約 |
| がん・三大疾病 | がん診断時のまとまった資金、長期治療による収入減の補填 | がん保険、特定疾病保障保険 |
まずは、自分の契約がこの3つのどれに当たるかを分類してみよう。よくある失敗は、「死亡保障は手厚いが、働けなくなった時の保障(就業不能や介護)がまったくない」といったバランスの偏りだ。
「全部入り」を目指すと保険料が膨れ上がる。家計の予算に合わせて、「我が家は死亡保障を優先する時期」「今は医療保障を厚くしたい」といった優先度をつけることが重要だ。
現在加入している保障の重複と不足を洗い出す
次に、保険証券をすべて取り出して、以下の項目をチェックリスト形式で確認してみよう。意外な「重複」や「穴」が見つかるはずだ。
最低限確認したい4つの項目
- 保険の種類(定期、終身、医療、がんなど)
- 保険金・給付金額(入院日額5,000円、死亡時1,000万円など)
- 保険期間(いつまで保障されるか、更新はあるか)
- 保険料と払込期間(一生払い続けるのか、60歳で終わるのか)
よくある「重複」の例
- 複数の医療保険に入っていて、入院給付金が二重になっている(必要なら良いが、過剰なケースが多い)。
- 会社の団体保険で「がん診断給付金」が出ることになっているのに、個人でも高額ながん保険に入っている。
よくある「不足」の例
- 死亡保障はあるが、長期入院で働けなくなった時の保障がない。
- がん診断時の一時金はあるが、通院治療に対する給付が弱い。
重複している部分は削減候補、不足している部分は追加検討候補としてマーキングしてみよう。
公的保障や企業保障を踏まえた必要保障額の考え方
「保険でいくら備えるか」を決める前に、絶対に知っておくべきことがある。それは、私たちはすでに「最強の保険」に入っているということだ。それが公的保障(社会保険)である。
遺族年金や健康保険など公的保障の確認
民間保険の役割は、公的保障で足りない部分を埋める「上乗せ」に過ぎない。公的保障の内容を知らずに民間保険を契約するのは、冷蔵庫の中身を見ずに買い物に行くようなものだ。
- 遺族年金: 会社員(厚生年金加入者)などが亡くなった場合、条件を満たす遺族(子のある配偶者など)には「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」が支給される。これで生活費の一部は賄える。
- 高額療養費制度: 公的医療保険には、月々の医療費自己負担額に上限がある。一般的な所得(年収約370〜770万円)の70歳未満であれば、ひと月の自己負担は8〜9万円程度で済むことが多い。
「入院したら100万円かかるかも」と過剰に恐れる必要はない。まずはこの制度を前提に、それでも足りない「差額ベッド代」や「収入減」を民間保険でカバーしよう。
会社の団体保険や福利厚生でカバーされる部分の把握
会社員の場合、勤務先の福利厚生も見逃せない。給与天引きで加入している「団体保険」や「共済」はないだろうか。
会社で確認すべき保障
- 団体定期保険: 割安な掛金で大きな死亡保障に入れることが多い。
- 団体医療保険・LTD制度: 入院給付や、病気で休職した際の所得補償制度がある会社も増えている。
- 企業年金・確定拠出年金: 老後資金の積み立て状況。
注意点は、これらは「会社を辞めるとなくなる(または継続できても保険料が上がる)」場合が多いことだ。ベースとなる一生涯の保障は個人で確保し、現役時代の大きな保障は会社の団体保険で安く済ませる、という使い分けが賢い。
不足分を民間の生命保険で補う手順
ここまで情報を集めたら、ようやく「必要保障額」の計算だ。シンプルに引き算で考えよう。
必要保障額の計算ステップ
- 必要な総額を見積もる
- 万一の時の生活費(月額×年数)
- 子どもの教育費
- 葬儀・整理資金
- 「公的・企業保障 + 貯蓄」を差し引く
- 遺族年金の見込額
- 会社の死亡退職金や団体保険
- 現在の預貯金・資産
- 残った額 = 民間保険で備えるべき額
計算してみると、「あれ、数千万円もいらないな」と気づくことも多い。不足額が大きい時期だけ「定期保険」や「収入保障保険」を使い、不足額が少ないなら「貯蓄」で対応するのも一つの手だ。
教育費・老後資金を含めた家族のライフプラン整理
保障額計算の肝となるのが「教育費」と「老後資金」だ。ここはざっくりとした目安を知ることから始めよう。
教育費の目安から逆算した必要保障額の試算
「教育費がいくらかかるかわからない」という不安が、保険のかけすぎを招く。文部科学省の調査(平成30年度子供の学習費調査)などを参考に、大まかな目安を持っておこう。
- 公立高校(3年間): 約137万円
- 私立高校(3年間): 約290万円
- 私立大学文系(4年間): 約400万円(自宅通学の場合の学費目安)
例えば、「子ども2人、大学まで私立」と仮定すると、教育費だけで1人あたり1,000万円以上かかる計算になる。
この金額すべてを死亡保険で賄う必要はない。「親が元気に働いていれば給料から出す」のが基本であり、死亡保険でカバーするのは「親が亡くなって収入が途絶えた場合の不足分」だけだ。学資保険などの積立と、万一の時の死亡保障(掛け捨て)を分けて考えよう。
老後資金と医療・介護費を含めた長期的な資金計画
老後資金については、「2,000万円必要」といった言葉が独り歩きしがちだが、これも家庭による。
- 入ってくるお金: 公的年金(ねんきん定期便で確認)、退職金、企業年金
- 出ていくお金: 老後の生活費(現在の生活費×0.7〜0.8程度が目安)、医療・介護費
この差額が準備すべき老後資金だ。生命保険(個人年金や終身保険)を老後資金作りに使うメリットは、「強制的に貯まる」点と「長生きしても年金が出る(商品による)」点にある。
一方で、途中解約すると元本割れするリスクもある。流動性(現金の使いやすさ)を確保するためには、保険だけでなくiDeCoやNISAなど、他の手段と組み合わせる視点が欠かせない。
家族構成と収入に合わせた保障の優先順位付け
予算は有限だ。すべてのリスクに完璧に備えるのは不可能に近い。最後に、優先順位のつけ方を整理しよう。
一家の収入源となる人の保障を厚くする考え方
基本原則は、「経済的なダメージが大きい人」の保障を最優先にすることだ。
共働きであっても、収入の割合が「夫7:妻3」なら、夫の死亡保障を厚くする。逆に、妻の収入が家計の半分以上を支えているなら、妻の保障もしっかり確保しなければならない。
専業主婦(夫)の場合、死亡による直接的な収入減はないが、「家事・育児」という無償労働が失われる影響は甚大だ。外注費(シッター代や家事代行費)を考慮して、数百万〜1,000万円程度の保障を持っておくと安心である。
必要性の低い保障や特約を見直す基準
もし保険料を削る必要があるなら、以下の基準で見直し候補を探してみよう。
- 内容が理解できていない特約: 「よくわからないけど付いている」特約は、実は不要なことが多い。説明できないものは外す勇気を持とう。
- 貯蓄でカバーできる少額のリスク: 数万円〜数十万円程度の出費(軽い入院や通院)なら、高い保険料を払って備えるより、貯金を崩す方が合理的かもしれない。
- 公的保障と完全に被っている部分: 会社員で傷病手当金が出るのに、過剰な所得補償保険に入っているなど。
「不安だから残す」のではなく、「家計が破綻するかどうか」で判断する。これが、賢い保険見直しの鉄則だ。
お願いします。続きの「保険料と家計のバランス」および「保険期間と更新時期」について執筆する。
保険料と家計のバランスを整える見直し
「安心のため」とはいえ、毎月の保険料が生活を圧迫していては元も子もない。保険貧乏にならないためには、家計全体の中でのバランス感覚が不可欠だ。
ここでは、保険料の適正ラインと、無理なく負担を減らすための具体的なテクニックを解説する。
保険料の目安と家計に占める割合
「みんなどれくらい払っているのか?」は気になるポイントだが、隣の家とあなたの家では事情が違う。平均値はあくまで参考程度にとどめ、自分の家計にとっての適正額を見極めよう。
手取り収入に対する保険料の一般的な目安
ファイナンシャルプランナー(FP)への相談現場やマネーコラムなどでは、生命保険料(医療・がん・個人年金含む)の目安として、「手取り収入の5〜10%程度」という数字が挙げられることが多い。
一方で、生命保険文化センターの調査(2024年度)によれば、1世帯あたりの年間払込保険料は平均約35.3万円。月額にすると約3万円弱だ。
しかし、これはあくまで平均だ。独身、子育て世帯、老後世帯ですべき備えは異なる。
重要なのは「%」よりも、「保険料を払った後に、貯蓄や楽しみのためのお金が残るか」である。もし毎月の収支がトントン、あるいは赤字なら、たとえ目安の範囲内であっても保険料は「高い」と判断すべきだ。
住宅費や教育費とのバランスを見ながら決める方法
保険料は、家計の「固定費」の一部だ。住居費や教育費との兼ね合いで考えよう。
例えば、手取り30万円の家庭を想定する。
住宅ローン返済が手取りの30%(9万円)を超えている場合、家計の余力は少ない。この状態で保険料に10%(3万円)もかければ、食費や生活費が圧迫されるのは目に見えている。
バランス調整の考え方
- 住宅費が高い場合: 保険料は最低限(掛け捨て中心)に抑え、生活防衛資金を優先する。
- 教育費のピーク時: 貯蓄性保険(学資保険など)の負担が重ければ、一部を払い済み(保険料支払いを停止して契約を残す)にするなどして、キャッシュフローを改善する。
家計はトータルバランスだ。一点豪華主義にならず、全体最適を目指そう。
保険料を抑えるための見直し方法
「保険料を下げたいが、保障を減らすのは怖い」。そう思うなら、まずは「保障額」ではなく「保障の持ち方」を変えてみよう。
過剰な保障や重複している保障を削る
前章で洗い出した「重複」部分を整理するのが、最も痛みのない節約法だ。
- 特約の整理: 「なんとなく不安だから」と付けた月数百円の特約も、積み重なれば大きくなる。公的保障や貯蓄でカバーできるなら外す。
- 重複の解消: 夫婦でそれぞれ「家族特約」に入っていないか、会社の団体保険と個人の医療保険で同じような保障に入っていないか確認する。どちらか一方を解約すれば、保障レベルを落とさずにコストカットできる。
理解できない特約、請求する確率が極めて低い特約は、思い切ってリストラ対象にしよう。
定期保険と終身保険の組み合わせで負担を調整する
すべての保障を「終身保険(一生涯保障・貯蓄性あり)」で確保しようとすると、保険料は非常に高くなる。
合理的なのは、「ベースは小さく、上乗せは大きく」という組み合わせだ。
- ベース(終身保険): 葬儀代など、いつ死んでも必ず必要な最低限の額(例:200万円)。
- 上乗せ(定期保険・収入保障保険): 子育て期間中など、高額な保障が必要な時期だけ、掛け捨ての安い保険(例:3,000万円)を乗せる。
この「三角形の組み合わせ」を作ることで、必要な保障額を確保しつつ、保険料を大幅に抑えることが可能になる。
保険料の払い方を見直すポイント
保障内容を変えずに保険料を安くする「裏技」的な方法がある。それが支払方法の変更だ。
月払いと年払いの違いとメリット
多くの保険会社では、毎月払うよりも「年払い(1年分をまとめて支払い)」や「半年払い」にする方が、保険料総額が数%程度安くなる設定になっている。
資金に余裕があるなら、月払いを年払いに変更するだけで、実質的な利回りを得られるのと同じ効果がある。
ただし、一度に数万円〜数十万円が引き落とされるため、家計管理には注意が必要だ。「ボーナスで払うつもりだったが、ボーナスが減って払えない」といった事態にならないよう、計画的にプールしておく必要がある。
払込期間(短期払い・終身払い)を変えるときの注意
「いつまで払うか」も重要な要素だ。
- 短期払い(60歳払済など): 現役時代に支払いを終えるため老後は楽だが、月々の保険料は高い。
- 終身払い(一生涯払う): 月々の保険料は安いが、長生きするほど総支払額が増え、年金生活になっても支払いが続く。
目先の安さだけで「終身払い」を選ぶと、将来の自分を苦しめることになりかねない。逆に、今の家計が苦しいのに無理して「短期払い」にするのも危険だ。ライフプラン表を見ながら、老後の収支と現役時代の収支、どちらを優先するか決めよう。
保険料負担が重いときの優先順位の付け方
どうしても保険料が払えない、あるいは家計が赤字続きだという場合、どうすべきか。
生活防衛資金と保険料のバランスを決める
FPとしてのアドバイスは明確だ。「貯蓄ゼロなら、保険よりもまず現金の確保を優先せよ」である。
病気やケガのリスクに備えるのは大切だが、リストラや急な出費に対応できるのは「保険」ではなく「現金(生活防衛資金)」だ。生活防衛資金(生活費の3〜6ヶ月分程度)が貯まっていない段階で、高額な貯蓄性保険にお金を入れるのは順序が逆である。
まずは掛け捨ての安い保険で最低限のリスクヘッジをし、浮いたお金を預貯金に回して足元を固めよう。
見直し前に一度家計全体を可視化する
保険の見直しは、家計改善の入り口にすぎない。
家計簿アプリやエクセル、あるいは手書きのメモでもいい。一度、月の「収入」と「支出(固定費・変動費)」を書き出してみよう。
- スマホ代などの通信費
- 使っていないサブスクリプション
- なんとなくのコンビニ出費
これらと並べて保険料を見たとき、「この保険に月2万円払う価値が本当にあるか?」を問いかけてみる。全体を可視化することで、削るべきは保険なのか、それとも他の浪費なのかがクリアになるはずだ。
保険期間と更新時期から考える見直しのタイミング
保険商品には「有効期限」があるものと、ないものがある。この仕組みを理解していないと、「気づいたら保障が終わっていた」「保険料が勝手に倍になった」というトラブルに遭遇する。
ここでは、保険の「時間軸」に注目して見直しポイントを解説する。
定期保険と終身保険の保険期間の違い
基本中の基本だが、改めて確認しておこう。
一定期間だけ保障する定期保険の特徴
定期保険は、「10年」や「60歳まで」といった期間が決まっている保険だ。
いわゆる「掛け捨て」が多く、少ない保険料で大きな保障を買えるのが最大の特徴である。
- メリット: 割安な保険料で、子育て期の数千万円という大きな責任をカバーできる。
- 注意点: 満期が来れば保障は終了する(更新型を除く)。満期金は原則ないため、「貯金代わり」にはならない。
「子どもが独立するまでの守り」としては最強のツールだ。
生涯保障が続く終身保険の特徴と注意点
終身保険は、その名の通り一生涯保障が続く保険だ。
解約したときに「解約返戻金」が戻ってくる商品が多く、貯蓄性がある。
- メリット: 何歳で亡くなっても必ず保険金が出るため、葬儀費用や相続対策に向く。
- 注意点: 定期保険に比べて保険料が割高。途中で解約すると元本割れする期間が長い。
「一生のお守り」や「老後資金の積立」として使われるが、高額な死亡保障をこれだけで確保しようとするのはコスト的に難しい。
更新時に見直したいポイント
「更新のお知らせ」が届いたときこそ、見直しの絶好のチャンスだ。そのまま判子を押してはいけない。
更新時の保険料上昇と保障内容の見直し
「更新型」の保険(主に定期保険や医療保険の一部)は、10年などの期間ごとに契約が更新される。このとき、保険料は「更新時の年齢」で再計算されるため、ほぼ確実に上がる。
場合によっては、倍近くに跳ね上がることもある。「保険料が上がったから、とりあえずそのまま継続」するのは思考停止だ。
- 今の自分に、10年前と同じ額の保障が必要か?
- 子どもが成長した分、保障額を減らして更新できないか?
これらを検討し、必要なら「減額して更新」あるいは「更新せずに終了(他社へ乗り換え)」を選択肢に入れよう。
別商品の検討や保険料の抑え方
更新は「継続」だけが道ではない。
- 更新せずに乗り換える: 最新の保険商品は、昔の商品よりも保障範囲が広く、タバコを吸わない人向けの割引(非喫煙者割引)などが充実している場合がある。他社の見積もりと比較してみる価値はある。
- 必要な部分だけ切り出す: 「死亡保障は更新せず終了し、医療保障だけ別の単体商品で入り直す」といった分解も有効だ。
ただし、健康状態が悪化していると他社に乗り換えられないこともある。その場合は、今の契約を(多少高くても)更新する方が安全なケースもあるため、慎重な判断が必要だ。
誕生日の前後に見直すべき理由
意外と知られていないが、保険料は「1日」の違いで変わることがある。
加入年齢が保険料に与える影響
生命保険の保険料は、「契約日の年齢」で決まる。一般的に、年齢が1歳上がると死亡率や疾病リスクが上がるため、保険料も高くなる。
たかが数10円、数100円の差と思うかもしれないが、20年、30年と払い続けると、総額では数万円〜十数万円の差になることもある。
- 契約年齢の計算ルール: 「満年齢」で計算する会社が多いが、中には「保険年齢(満年齢+6ヶ月など)」という独自の基準を使う会社もあるので注意が必要だ。
誕生日前に見直しを検討するメリット
もし近々保険に入ろうと思っているなら、誕生日を迎える前に手続きを完了させるのが鉄則だ。
「誕生日まであと1週間」というタイミングなら、急いで検討する価値はある。同じ保障内容なら、少しでも若いうちに契約した方がコストパフォーマンスは良い。
ただし、「急ぐあまり、内容をよく理解せずに契約する」のは本末転倒だ。あくまで「検討中なら急ぐ」スタンスで、余裕を持って準備しておきたい。
団体保険や共済との重複を整理する
個人の保険を見直す際、盲点になりやすいのが「会社の保険」だ。
会社の団体保険・共済の内容確認項目
給与明細を見て、「団体生命」「グループ共済」などの名目で引かれている項目はないだろうか。これらは非常にコスパが良い場合が多い。
確認すべきは以下の点だ。
- 死亡時の給付額: いくら出るのか。
- 医療保障の有無: 入院いくらか。
- 配当金(割戻金): 年に一度、掛金の一部が戻ってくる制度があるか。
- 退職後の扱い: 会社を辞めたら終わるのか、個人契約として継続できるのか。
個人の生命保険と団体保障の役割分担
団体保険は「安い」が「退職するとなくなる(または高くなる)」のが一般的だ。
- 団体保険の役割: 子育て期など、現役時代に必要な「高額な上乗せ保障」を安く確保する。
- 個人保険の役割: 老後まで続く「ベースの医療・終身保障」を確保する。
「会社で入っているから全部安心」と過信せず、かといって「個人で全部入る」無駄もせず、この2つをパズルのように組み合わせるのが、賢い大人の保険戦略だ。
解約・転換・乗換え前に確認したいリスク
見直しの方向性が決まったとしても、実際に手続きをするのはちょっと待ってほしい。保険の切り替えには、特有の「落とし穴」があるからだ。
手順を間違えると、「保険に入っていない期間ができてしまった」「戻ってくるはずのお金が減ってしまった」という取り返しのつかない事態になりかねない。ここでは、実務的なリスクと回避手順を解説する。
無保険期間が生じない解約・乗換えの進め方
最も避けなければならないのは、「古い保険を解約したが、新しい保険に入れなかった(あるいは開始日が先になった)」という空白期間を作ることだ。
新しい保険の契約成立を確認してから解約する順番
保険の乗り換えには、鉄則となる順番がある。
- 新しい保険に申し込む
- 診査・告知を行い、審査結果を待つ
- 契約成立(保険証券の到着や第1回保険料の振替)を確認する
- 古い保険の解約手続きを行う
絶対にやってはいけないのが、「先に解約してから、新しい保険を探す・申し込む」ことだ。万が一、健康診断の結果などで新しい保険の審査に落ちてしまった場合、元の保険はすでに解約済みで戻れず、無保険状態になってしまう。
「契約成立」を確認してから解約する。この石橋を叩く慎重さが、あなたと家族を守る。
契約の空白期間を作らないためのチェック
審査に通っても、保障がいつから始まるか(責任開始日)には注意が必要だ。
- 解約日: 古い保険の保障が終わる日
- 責任開始日: 新しい保険の保障が始まる日
この2つの日付を確認し、1日たりとも空白(無保険期間)ができないように調整する。特に、「月末に解約し、翌月1日から新契約」とする場合、手続きのズレで空白が生じやすい。できれば数日間でも重複期間を持たせておく方が安全だ。
解約返戻金と元本割れの仕組み
貯蓄性のある保険(終身保険、養老保険、学資保険など)を見直す際は、「いつ解約するか」で手元に戻ってくる金額が大きく変わる。
解約返戻金が増える時期と減る時期の目安
解約返戻金の推移には独特のカーブがある。
- 契約初期〜中期: 支払った保険料の合計より、戻ってくる金額が少ない(元本割れ)期間が長く続く。これは、契約初期に手数料等の経費が多く引かれるためだ。
- 払込終了前後: 払込期間が終わる頃や、一定年数経過後に、ようやく返戻率が100%を超えて増え始めるケースが一般的だ。
保険証券や設計書にある「解約返戻金推移表」を必ず確認しよう。「あと1年待てば返戻金が数十万円増える」というタイミングであれば、今すぐ解約するのは損かもしれない。
貯蓄性の高い保険を解約するときの注意点
貯蓄性保険を解約するということは、「将来の貯蓄」と「一生涯の保障」の両方を手放すことを意味する。
もし「今の保険料が払えないだけ」なら、解約以外の方法も検討すべきだ。
- 払済保険(はらいずみほけん)への変更: 保険料の支払いをストップし、その時点の解約返戻金を元手に、保障額を小さくして契約を残す方法。これなら保障も貯蓄性も(小さくなるが)維持できる。
- 契約者貸付制度: 一時的にお金が必要なだけなら、解約返戻金の範囲内でお金を借りる制度を利用する。
「解約して現金化」は最終手段と考え、まずは契約を残す方法がないか模索しよう。
健康状態・年齢による加入制限リスク
「昔は簡単に入れたのに」と思っても、今のあなたの体は昔とは違うかもしれない。健康状態は、保険加入の可否を決める最大のハードルだ。
健康状態が悪化してからの見直しが難しくなる理由
生命保険の申し込み時には、過去の病歴や現在の健康状態を正直に申告する「告知義務」がある。
- 持病(糖尿病や高血圧など)がある
- 直近で入院や手術をした
- 健康診断で要再検査の指摘を受けた
これらに該当すると、「加入お断り(謝絶)」や「保険料の割増(特別条件)」となる可能性がある。「条件が悪くなるなら、今の保険を辞めなければよかった」と後悔しないためにも、新しい保険の審査結果が出るまでは、絶対に今の保険を手放してはいけない。
告知内容や診査条件が変わるタイミング
一般的に、告知が必要な期間は「過去3年以内」や「過去5年以内」の病歴であることが多い(商品による)。
もし「5年前に手術をした」という場合、もう少し待って「手術から5年以上経過」してから申し込めば、告知事項に該当せずスムーズに加入できるかもしれない。
また、年齢が高くなると、告知だけでなく医師による診査が必要になる基準(保険金額など)も厳しくなる。「健康なうち」「若いうち」の方が、見直しの選択肢は圧倒的に多いことを覚えておこう。
転換制度や特約解約を活用するときの注意点
保険会社から「今入っている保険を下取りにして、新しい保険に入りませんか?」と提案されることがある。これが「転換(てんかん)」だ。
転換を利用するメリットとデメリット
転換は、古い保険の解約返戻金(積立部分)を、新しい保険の保険料の一部に充当する仕組みだ。
- メリット: 貯まっていたお金を使うため、新規で入るより当初の月々の保険料が安く見える。
- デメリット: 実質的には「古い保険の解約」と「新しい保険の契約」のセットである。過去の有利な条件(高い予定利率など)を捨て、現在の年齢・予定利率で再契約することになる。
「保険料が変わらず保障が最新になりますよ」という言葉には注意が必要だ。その裏で、貴重な「お宝契約」が消滅していないか、よく確認してほしい。
特約だけを解約するときに確認すべき点
「主契約(ベースの保険)」は残して、「特約(オプション)」だけを解約してスリム化する場合もある。
このとき確認すべきは、「一度外したら、二度と付けられない特約ではないか」という点だ。特に、古いタイプのがん特約や医療特約の中には、現在の商品より条件が良いものが稀にある。また、特約を外すことで主契約の条件が変わらないかも、念のため確認しよう。
お宝保険や有利な旧契約を見直すときの考え方
バブル期(1990年前後)などに契約した保険は、「お宝保険」と呼ばれることがある。これらは絶対に見直してはいけないのだろうか?
予定利率が高い契約を手放すかどうかの判断軸
お宝保険が「お宝」である理由は、当時の高い「予定利率(保険会社が約束した運用利回り)」にある。例えば年利3〜5%以上で運用され続ける貯蓄性保険は、今の低金利時代には手に入らない貴重な資産だ。
判断の基準
- 維持すべき: 終身保険や個人年金など、貯蓄性が高く、高い利回りで増え続けているもの。これは「高利回りの定期預金」のようなものなので、極力キープする。
- 見直してもよい: 定期付終身保険などで、「お宝(終身)」部分は小さいのに、「掛け捨て(定期)」部分が大きく、保険料負担が重すぎる場合。この場合でも、お宝部分だけ残して掛け捨て部分を減額するなど、部分的な見直しを検討したい。
保障と貯蓄のどちらを重視するかの整理
いくらお宝保険でも、「現在の自分に必要な保障」とズレていれば意味がない。
- 「利回りは良いが、入院保障が今の医療事情に合わず、全然使えない」
- 「老後資金としては優秀だが、今の死亡保障が足りない」
この場合は、お宝保険を「貯蓄・資産運用」と割り切って残し、不足している医療保障や死亡保障を「最新の掛け捨て保険」で安く補うという「二刀流」がおすすめだ。
専門家に相談するときの選び方と準備
自分ひとりで判断するのが難しい場合、専門家の力を借りるのも賢い選択だ。しかし、専門家にも「得意分野」や「立場」がある。誰に相談するかで、提案される内容は変わってくる。
相談できる専門家の種類と特徴
大きく分けて、相談先は3つのタイプに分類できる。
保険会社の営業担当に相談する場合のポイント
特定の保険会社(「〇〇生命」など)に所属する担当者だ。
- 特徴: 自社商品についての知識が深く、手続きや保全(住所変更や給付金請求)のサポートが手厚い。
- 注意点: 当たり前だが、他社の商品は提案できない。「自社の商品の中で」最適解を探すことになるため、比較検討は自分でやる必要がある。
すでに加入している保険の内容確認や、プラン変更の相談には最もスムーズだ。
乗合代理店や保険ショップに相談する場合のポイント
街中の「〇〇保険ショップ」など、複数の保険会社の商品を扱う代理店だ。
- 特徴: 複数の会社の商品を比較しながら選べる。「医療保険はA社、がん保険はB社」といったいいとこ取りの提案が可能。
- 注意点: すべての保険会社を扱っているわけではない。また、代理店手数料の高い商品を優先して提案される可能性もゼロではない(担当者の倫理観による)。
「いろいろな会社を比較したい」という段階では非常に便利だ。
独立系ファイナンシャルプランナーに相談する場合のポイント
特定の金融機関に属さず(あるいは属していても中立的な立場で)、家計全体のアドバイスを行う専門家だ。
- 特徴: 保険だけでなく、住宅ローン、教育資金、資産運用など、ライフプラン全体から「保険の適正額」を算出してくれる。
- 注意点: 相談自体が有料(相談料がかかる)ケースと、保険販売の手数料で稼ぐ(相談無料)ケースがある。「保険を売る」ことがゴールのFPか、「家計相談」がゴールのFPか、最初に見極める必要がある。
根本的な家計の見直しや、保険以外の手段(NISAなど)も含めて相談したい場合に向いている。
無料相談サービスを利用するメリットと注意点
「相談無料」は魅力的だが、タダより高いものはないともいう。ビジネスモデルを理解して賢く使おう。
商品ラインアップと取扱会社の偏りの確認
無料相談ができる理由は、あなたが保険を契約した時に、保険会社から相談所へ「販売手数料」が入るからだ。
そのため、どうしても「契約につながる提案」になりやすい側面はある。
また、相談所によっては「提携している保険会社」に偏りがある場合もある。「全社から選べます」と言いつつ、実際には主力商品が決まっていることも多い。
「おすすめされた商品が、本当に自分にベストなのか」を一歩引いて考える冷静さを持とう。
相談のゴールを事前に明確にしておく重要性
漠然と「見直したい」と伝えると、相手も提案しづらく、一般的な(売りやすい)パッケージ商品を勧められがちだ。
- 「毎月の保険料を5,000円下げたい」
- 「老後資金を準備したいが、保険とiDeCoどちらがいいか知りたい」
- 「今の保障で、先進医療に対応できているか確認したい」
このようにゴールを明確にしておけば、的確な回答が得られ、不要な営業トークに流されることも防げる。
相談前に準備しておきたい情報
手ぶらで相談に行くのは時間の無駄だ。最低限、以下の3つを用意していこう。
現在加入している保険証券と保障内容一覧
これがなければ始まらない。「どんな保険に入っているかわからない」状態では、専門家もアドバイスのしようがない。
- 保険証券(原本またはコピー)
- 年金定期便(公的年金の見込額がわかるもの)
- 会社の福利厚生パンフレット(あれば)
これらをすべて持参し、現状を正確に把握してもらうことが第一歩だ。
家計状況とライフプランの簡単なメモ
保険は家計の一部だ。収支の状況がわからなければ、適正な保険料も算出できない。
- 世帯の手取り月収
- 毎月の生活費(ざっくりでOK)
- 現在の貯蓄額
- 今後の予定(数年後に車を買いたい、子供が私立に行くかも、など)
これらをメモにまとめておくだけで、相談の質は劇的に向上する。
重視したい項目(保険料・保障額・期間など)の整理
「何を一番大切にしたいか」という価値観も伝えておこう。
- 「とにかく月々の支払いを安くしたい」
- 「保険料が高くてもいいから、一生涯の安心が欲しい」
- 「掛け捨ては嫌だ。少しでも戻ってくるお金が欲しい」
正解は一つではない。あなたの価値観に合わせてプランを作ってもらうために、希望を言語化しておくことが大切だ。
セカンドオピニオンを取るタイミング
医師の診断にセカンドオピニオンがあるように、保険提案にもセカンドオピニオンは有効だ。
高額な保険料や長期契約を検討するとき
「月額3万円の保険」は、30年払えば「1,000万円の買い物」だ。家や車の次に高い買い物といわれる保険を、一人の担当者の意見だけで決めてしまうのはリスクがある。
特に、貯蓄性保険や外貨建て保険など、仕組みが複雑で高額な商品を勧められたときは、即決せずに持ち帰り、別のショップやFPに見せて意見を聞いてみよう。「この商品は手数料が高いから勧められているだけかも?」といった別の視点が得られるかもしれない。
提案内容に違和感があるときの確認方法
「なんとなく納得できない」「説明が難しくてよくわからない」と感じたら、それは契約すべきではないサインだ。
- メリットばかり強調して、リスク(元本割れなど)の説明が少ない。
- 「今月中に決めないと損します」と急かしてくる。
- 希望した予算を大幅に超えるプランが出てきた。
こうした違和感を感じたら、遠慮なく他社に相談しよう。本当に良い提案なら、誰に見せても「これは良いプランですね」と言われるはずだ。
ケース別に見る生命保険見直しの例
理屈はわかっても、「結局、自分の場合はどうすればいいのか」がイメージしにくいかもしれない。
ここでは、代表的な4つのモデルケースを用いて、具体的な見直しの方向性を紹介する。
※本章の内容は一般的なモデルケースに基づく一例である。実際の保険設計にあたっては、個別の家計状況や健康状態を踏まえて判断してほしい。
20代独身会社員の見直し例
【モデル像】 25歳男性、年収350万円、賃貸一人暮らし、扶養家族なし。
最低限必要な死亡保障と医療保障の考え方
独身で扶養家族がいない場合、自分に万一のことがあっても、誰かの生活が困窮することはない。したがって、数千万円もの高額な死亡保障は不要だ。
- 死亡保障: 葬儀代と身辺整理費用として、200万〜300万円程度の終身保険、または職場の団体保険で十分だ。親が自分の奨学金の連帯保証人になっている場合のみ、その残債分を上乗せする。
- 医療保障: 貯蓄が少ないうちは、病気やケガによる収入減が最大のリスクとなる。入院日額5,000円〜1万円程度の医療保険と、がん診断一時金などを、掛け捨ての安い保険で確保しておくと安心だ。
貯蓄とのバランスを重視した加入パターン
この時期に最も優先すべきは「保険」ではなく「貯蓄(資産形成)」だ。
手取り収入がまだ多くない中で、保険料にお金をかけすぎると、結婚資金や生活防衛資金が貯まらない。保険料は手取りの数%以内に抑え、余力をつみたてNISAなどの資産運用に回すのが賢明だ。「若いうちに入ると安いから」といって、無理に高額な終身保険や養老保険を契約する必要はない。
30代共働き・子どもあり世帯の見直し例
【モデル像】 35歳夫婦(世帯年収800万円)、子ども2人(3歳・0歳)、住宅ローンあり(団信加入)。
教育費と住宅ローンを踏まえた死亡保障の組み立て
人生で最も責任が重い時期だ。万一の際、遺族年金だけでは「今の生活水準」と「子どもの教育」を守りきれない可能性が高い。
- 夫の保障: 団信で住宅ローンは消えるが、生活費と教育費が残る。子どもが独立するまでの期間、月額10万〜15万円程度が受け取れる「収入保障保険」などで、合理的にカバーする。
- 妻の保障: 妻の収入が家計を支えている割合に応じて死亡保障を確保する。また、妻が亡くなった場合の家事・育児代行費用(シッター代など)への備えも必要だ。
片働き化リスクと就業不能保障の検討
盲点になりがちなのが、夫婦のどちらかが病気で働けなくなる「実質片働き」のリスクだ。
がんで長期療養となれば、収入が減るだけでなく治療費もかかる。さらに、看病のためにパートナーも時短勤務を余儀なくされるかもしれない。
死亡保障だけでなく、働けなくなった時に毎月給付金が出る「就業不能保険」や、がん診断時にまとまったお金が出る「がん保険」の重要性が高い時期だ。
40〜50代住宅ローン返済中世帯の見直し例
【モデル像】 48歳男性(既婚・子2人)、住宅ローン残高2,000万円、長男が大学生・次男が高校生。
団信を前提にした死亡保障の調整
住宅ローンの返済が進み、団信のおかげで「万一の際の住居費リスク」は減っている。また、子どもがある程度成長していれば、将来必要な教育費の総額も減ってきているはずだ。
30代で加入した「死亡保障5,000万円」といった大きな定期保険が更新時期を迎える頃だろう。そのまま更新すると保険料が跳ね上がる。
「これからの必要額」を再計算し、保障額を半分程度に減らす、あるいは払込期間を短く設定し直すなど、ダウンサイジング(縮小)を図るべきタイミングだ。
老後資金と医療・介護保障へのシフト
死亡保障を減らして浮いた保険料は、そのまま節約するのではなく「自分たちの老後」へ振り向ける。
- 老後資金: iDeCoや個人年金の積立額を増やす。
- 医療・介護: 健康リスクが高まる50代に向け、古い医療保険を最新のもの(通院保障や先進医療対応)にアップデートする。
「子供のため」から「自分たちのため」へ、保険の目的を切り替えていく。
60代前後・退職を控えた世帯の見直し例
【モデル像】 60歳夫婦、定年退職間近、子どもは独立済み。
年金収入に応じた保険料負担の見直し
給与収入がなくなり、年金生活に入ると、現役時代と同じ保険料を払い続けるのは厳しくなる。
「ねんきん定期便」で将来の受給額を確認し、保険料が家計を圧迫しないかシミュレーションしよう。
もし負担が重いなら、貯蓄性の低い特約を解約したり、払済保険(保険料支払いを止めて保障を残す)に変更したりして、固定費をスリム化する。
相続対策としての生命保険活用の検討ポイント
この時期の死亡保障は、「遺された家族の生活費」よりも「円満な相続」のために活用できる。
- 葬儀費用: 自分の死後、家族がすぐに使える現金として200万〜300万円を残す。
- 納税資金・分割対策: 生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)を活用し、現金を保険に変えておくことで相続税を抑える。また、特定の子供にお金を残したい場合にも、受取人を指定できる保険は有効だ。
生命保険見直しに関するよくある質問
最後に、保険見直しの現場でよく聞かれる疑問に回答する。
生命保険はどのくらいの頻度で見直すべきか?
ライフイベント時と数年ごとの点検の使い分け
基本は「ライフイベントがあったら必ず見直す」だ。結婚、出産、住宅購入、子供の独立、退職などのタイミングでは、責任の重さがガラリと変わるからだ。
それに加えて、大きな変化がなくても「3〜5年に一度」は定期点検を行いたい。
医療技術の進歩で古い保険が役に立たなくなっていたり、新しい商品の方が保険料が安くなっていたりすることもある。「更新のお知らせ」が届いた時も、自動更新せずに内容を確認する良い機会だ。
見直しをすると保険料は必ず安くなるのか?
保障を増やす見直しと減らす見直しの違い
見直しの目的は「最適化」であり、必ずしも「安くなる」わけではない。
例えば、子どもが生まれた時に見直せば、守るべき責任が増えるため、保険料は上がるのが自然だ。逆に、子どもが独立した後に見直せば、責任が減るため保険料は安くなるはずだ。
「安くすること」だけを目的にすると、必要な保障まで削ってしまう恐れがある。「今のリスクに見合った保険料か」という視点で判断しよう。
健康状態が悪化している場合でも見直しはできるか?
現在の契約を維持したほうがよいケースの考え方
持病があったり、直近で入院・手術をしていたりする場合、新しい保険に入れない(または条件が悪くなる)可能性がある。
この場合、安易に今の保険を解約してはいけない。今の契約は「過去の健康な状態」で加入した権利だからだ。
見直しをするなら、「解約」ではなく「特約の一部解除」や「減額」で対応しよう。どうしても新しい保障が欲しい場合は、「引受基準緩和型」などの持病がある人向けの保険もあるが、保険料は割高になるため慎重な比較が必要だ。
保険ショップや無料相談の専門家はどこまで中立なのか?
取扱保険会社の数と報酬構造を確認するポイント
多くの無料相談窓口は、保険会社からの「販売手数料」で運営されている。そのため、どうしても手数料の高い商品や、キャンペーン中の商品を勧められるバイアスがかかる可能性はゼロではない。
中立性を確認するために、以下の質問をしてみよう。
「何社くらいの保険会社の商品を比較できますか?」
「特定の商品だけでなく、メリット・デメリットを両方教えてもらえますか?」
複数の商品を比較し、デメリットも含めて説明してくれる担当者は信頼できる可能性が高い。
会社の団体保険だけで足りるかどうかの判断基準は?
団体保険の保障額と期間を確認する項目
会社の団体保険は割安で優秀だが、弱点は「退職後の保障がない(または続けられても高くなる)」ことと「パッケージ型で自由度が低い」ことだ。
確認すべきは、「その保障額で家族を守れるか」と「いつまで続くか」だ。
子どもが小さい間の死亡保障など、一時的に大きな保障が必要な部分には団体保険が最適だ。一方で、一生涯必要な医療保障や葬儀代などは、退職後も続く個人の保険で確保しておくのが安全な組み合わせといえる。
外貨建てや変額保険を見直すときの注意点は?
為替リスクや運用リスクを理解したうえで判断する
「銀行に預けるより増える」と勧められがちな外貨建て保険や変額保険。これらは投資商品としての側面が強い。
見直す(解約する)際は、「円安・円高」のタイミングや「運用実績」によって、戻ってくるお金が大きく変動する。
「今解約するといくら戻るか」「元本割れしないか」を必ず数字で確認しよう。短期的な為替変動だけで判断せず、長期的な資産運用の視点で継続か解約かを決める必要がある。
まとめ
生命保険の見直しは、単なる「節約」や「手続き」ではない。自分と家族の人生を守るための「未来の再設計」だ。
本記事のポイントを振り返る。
- 見直しの目的: 保険料を安くすることだけでなく、ライフステージの変化に合わせて「保障の過不足」をなくすこと。
- タイミング: 結婚・出産・住宅購入などのライフイベント時と、3〜5年ごとの定期点検が基本。
- 手順: いきなり解約せず、まずは公的保障や現状の契約を確認し、新しい契約が成立してから古いものを解約する。
- 視点: 独身なら医療・貯蓄、子育て期なら死亡保障、老後は医療・介護と、時期によって守りを変える。
保険は「入って終わり」の商品ではない。放置すればするほど、無駄なコストを払ったり、いざという時に役に立たなかったりするリスクが高まる。
「そういえば、どんな内容だったっけ?」と思った今が、まさに一番の見直し時だ。まずは保険証券を取り出し、現状を確認することから始めてみよう。その小さな行動が、将来のあなたと家族の安心につながるはずだ。
出典一覧
- 生命保険文化センター「2024年度 生命保険に関する全国実態調査」https://www.jili.or.jp/
- 生命保険文化センター「2022年度 生活保障に関する調査」https://www.jili.or.jp/
- 文部科学省「平成30年度子供の学習費調査」https://www.mext.go.jp/
- 国立がん研究センター「がん情報サービス」https://ganjoho.jp/
- 金融庁「公的保険について」https://www.fsa.go.jp/
- 厚生労働省「遺族年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」https://www.mhlw.go.jp/
- 日本年金機構「遺族年金」https://www.nenkin.go.jp/