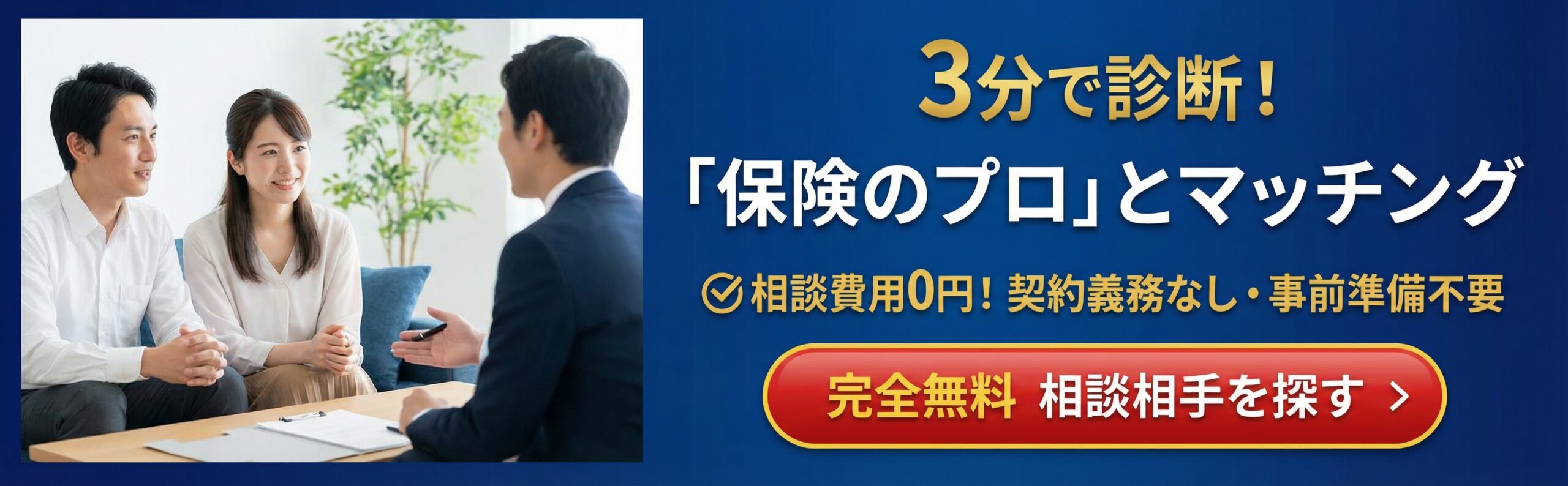- 自分に民間介護保険が必要かどうかを知りたい
- 民間介護保険のメリットとデメリットを知りたい
- 公的介護保険と民間介護保険の役割の違いがわからない
超高齢化社会の進行や、自身の親が年齢を重ねてきたことで、「介護」について考え始めたという人もいるのではないだろうか。
特に、自身や家族が介護を必要とする可能性を想定し、民間の介護保険に目を向ける方は多いだろう。
しかしながらその必要性についてまだ疑問を抱いているという方もいるはずだ。
そこで本記事では、介護保険の役割やメリット・デメリットを深堀りし、必要性について解説していく。
民間介護保険への加入を検討中の方や商品への理解を深めたい方は、ぜひ本記事を参考にしてほしい。
民間介護保が必要かを考える前に公的介護保険制度の概要とその目的を知る

民間介護保険の必要性を考える前に、まずは公的介護保険制度の特徴を把握することが重要だ。
公的制度への理解を深めた上で、民間の介護保険商品に加入すべきか検討しよう。
ここでは日本の公的介護保険制度の概要や民間介護保険との違い、制度の目的と課題について解説していく。
公的介護保険制度の概要
公的介護保険とは、介護が必要な人に介護サービスを支給するための社会保険制度のことだ。
40歳以上の人に加入義務があり、65歳以上が「第1号被保険者」、40〜64歳が「第2号被保険者」と分類される。
公的介護保険のサービスを受けるためには、「介護が必要な状態である」という要介護認定を受けなければならない。
要介護認定は、身体の状態に応じて「要支援1〜2」「要介護1〜5」の7段階に分けられている。
第1号被保険者は要介護認定を受けることでサービスを受給できる一方、第2号被保険者は特定の病気(16疾患)が原因で要介護認定を受けた場合のみ介護サービスを受給できる。
また、公的介護保険はサービス利用料金の1割(所得に応じて2〜3割)を自己負担することで、介護サービスが「現物給付」で受けられる仕組みだ。
介護施設に通ったり、自宅までヘルパーに来てもらったりする費用の負担が大幅に軽減できる。
ただし、要介護度に応じて1〜3割の自己負担でサービスを受給できる限度額が定められている。
限度額を超えた部分については全額自己負担になるため注意が必要だ。
民間介護保険との違い
公的介護保険と民間介護保険の主な違いとしては以下の点が挙げられる。
- 加入義務
- 保険給付の内容
- 給付の対象
前述の通り、公的介護保険は40歳以上になると必ず加入しなければならない。
一方の民間介護保険は任意加入であるため、必要に応じて商品を選べる点が大きな違いだ。
また、保険給付の内容も異なる。公的介護保険は「現物給付」となっており、介護サービス自体を給付する仕組みである。
一方、民間介護保険は「現金支給」となっており、一時金や年金などで給付される点も違いのひとつだ。
使い道も指定されないため、生活費に充当してもまったく問題ない。
そして給付の対象も異なっている。公的介護保険は40歳まで加入できず、40〜64歳までは特定疾病による要介護状態のみ給付される仕組みである。
一方、民間の介護保険は被保険者全員が支給を受けられ、年齢に関係なく介護に備えられる点が特徴だ。
上記の3点からも分かる通り、民間の介護保険は公的制度をカバーするための商品である。
役割を理解した上で、民間の商品に加入する必要があるかを判断しよう。
公的介護保険制度の目的と課題
公的介護保険制度は、社会全体で介護を支えるためにスタートしている。
高齢化や核家族化の進行、介護の担い手の減少など、さまざまな問題を抱える介護をサポートすることが主な目的だ。
現在、介護保険制度が直面している課題として主に以下の2点が挙げられる。
- 介護サービス給付の財源不足
- 現場の労働力不足
まず、財源不足が大きな課題のひとつだ。
今後も持続的に介護サービスを提供するためには、財源を確保する必要がある。
介護保険では、介護費用の半分が公費、残りの半分が介護保険料で賄われている。
しかし高齢化によって費用が増加傾向にあるだけでなく、保険料を支払う40歳以上の被保険者が減少していくことから財源確保が課題と言えるだろう。
また、介護の現場で働く労働力が減少している点も大きな問題として挙げられる。
介護の仕事に対して「待遇が良くない」「きつい」といった印象を抱く人が多く、担い手が減少しているのだ。
高齢化によって介護が必要な人の数が増えていく一方、現場で働く人の数は減っている。
今後も十分な介護サービスを提供していくためには、クリアしなければならない大きな課題である。
メリット・デメリットから見る民間介護保険の必要性

課題が多い公的介護保険制度を踏まえ、任意加入の民間保険でカバーしようと考えている方も多いだろう。
民間の保険には魅力的な側面と注意すべき側面の両方が存在するため、それぞれ把握した上で加入すべきか判断することが大切だ。
ここでは、民間の介護保険のメリットとデメリットを紹介する。
介護費用の自己負担額を抑制できる
メリットの1つ目は介護にかかる自己負担費用を抑えられるという点だ。
介護が必要な状態となった場合の経済的な負担を軽減できる点は大きな魅力と言えるだろう。
前述の通り、公的保険によって介護サービスにかかる自己負担は利用料の1〜3割で済む。
しかし要介護度に応じてサービス受給の限度額が定められており、限度額を超える部分は全額自己負担となってしまう。
また、40歳未満または40〜64歳で特定疾病以外の理由で要介護状態となった場合は、公的保険の対象とならない。
これらのケースでも、介護サービスの利用にかかる費用は全額自己負担だ。
民間の保険に加入していれば、保険会社所定の要介護状態となった場合に現金が支給されるため、自己負担額を軽減できる。
年齢等での給付制限もなく、公的保険による給付がされない方も保障される。
公的介護保険ではカバーできない部分を保障できる点が民間介護保険の大きな特徴だ。
資金使途を自由に選べる
2つ目のメリットは支給された資金の使い道を自由に選べる点だ。
介護サービスそのものが給付される公的保険に対し、民間保険では現金が支給される。
現金の使い道は問われないため、介護サービスを受ける目的以外に利用してもまったく問題ない。
支給された現金の使い道には、例えば以下のものがある。
- 介護サービスの利用料
- 介護用品の購入費用
- 日常生活にかかる費用
- 住宅の改修にかかる費用
介護サービスを利用するお金以外にも、車いすや杖などの介護用品を購入したり、普段の生活費に充てたりと、さまざまな使い道がある。
さらには自宅の中にある段差を解消したり、必要な場所に手すりを付けたりといった費用もかかるだろう。
状況に合わせて必要な使い道を選択できる点も、民間保険のメリットだ。
保険料負担がある
デメリットの1つ目は保険料を負担しなければならない点だ。
支払う保険料によって家計に負担がかかる可能性がある点には注意しておこう。
民間の保険には介護保険以外にも死亡保険や医療保険、子どもの学資保険などさまざまな種類がある。
すでにほかの保険に加入済みの場合、保険料だけで大きな出費になってしまう場合がある。
特に、子どもの教育資金を準備していたり、住宅ローンの支払いがまだ残っていたりすると、保険料の負担と家計のバランスを見極めることが重要だ。
ほかの保険商品との優先順位を決め、無理のない範囲で保険料を支払っていこう。
要介護状態でも必ず給付されるとは限らない
デメリットの2つ目は、要介護状態になったからといって必ずしも給付金が受け取れるとは限らない点だ。
保険金の支払い基準を満たしていない場合、年金や一時金を受け取ることはできない。
民間保険では、保険金給付の条件を公的保険に準じている場合もあれば、独自で基準を定めている場合もある。
保険会社独自の基準で給付が決まるタイプの場合、要介護状態となっても保険金がもらえない可能性があるため注意が必要だ。
また、保険金支給条件が公的介護保険に準じているタイプの商品であっても、公的保険制度改正によって給付条件が変更されるリスクもある。
想定外の事態によって保険金が給付されないリスクがあることを頭に入れておこう。
どのような人が民間の介護保険が必要か

ここまで解説してきた民間保険の特徴を踏まえ、加入すべきかどうかを悩んでいる方も多いだろう。
加入すれば介護に手厚く備えられる一方、保険料の負担がかかる。本当に必要かどうかを見極めることが重要だ。
ここでは、民間の介護保険が必要な人・必要でない人の特徴を解説していく。
民間の介護保険が必要な人
民間保険の必要性が高い人は以下のようなタイプだ。
- 貯蓄等で介護に必要な費用を準備できない
- 要介護状態となったときに頼れる家族がいない
- 64歳以下で要介護状態になるリスクに備えたい
公的保険によって自己負担が軽減されるとは言え、介護が必要な状態になるとさまざまな費用が発生する。
老後の年金や貯蓄等で介護費用をカバーできない状況であれば、介護保険への加入を検討しよう。
また、要介護状態となったときに「家族がいない」「子どもが遠方に住んでいて頼れない」というケースも民間保険加入の必要性が高い。
有料の介護サービスを利用して生活のサポートをしてもらうことになり、介護費用の負担が大きくなるためだ。
そして64歳以下で要介護状態になる可能性を考え、備えておきたい場合も民間保険をおすすめする。
公的介護保険では40〜64歳が特定疾病による要介護状態のみ対象、40歳未満は対象外となっているためだ。
上記3つのいずれかに該当する方は、民間の介護保険への加入を視野に入れてみよう。
民間の介護保険が必要でない人
一方、以下のようなタイプの人は民間保険の必要性が低い。
- 十分に貯蓄があり、介護費用も問題なく準備できる
- 要介護状態になったときに身の回りの世話をしてくれる家族がいる
民間保険は、あくまでも介護費用の不足分をカバーする役割の保険商品である。
預貯金や金融資産、老後に受け取る年金収入などが十分にあり、介護サービスの利用にかかる費用を賄えるのであれば加入の必要性は低い。
また、身近に家族が住んでいて身の回りの世話を頼めるのであれば、民間保険は不要と言えるだろう。
有料の介護サービスを利用する頻度が少なくなるため、経済的な負担を押さえ込むことができる。
しかし十分に貯蓄を備えられているつもりでも、想定外の出費や物価の高騰などで介護費用が足りなくなる可能性は考えられる。
また、家族に介護を頼むつもりであっても、大きな負担がかかる介護を家族が嫌がる可能性もあるだろう。
「貯蓄があるから」「家族に頼めるから」という理由だけで民間保険を不要と決めつけるのは危険だ。
将来の資産状況をシミュレーションしたり、家族としっかり話し合ったりして、本当に保険に加入する必要がないのかを確認しておこう。
介護保険選びのポイント
民間保険の加入を検討する上では、以下の2つのポイントを押さえることが重要となる。
- 保険期間(定期タイプ・終身タイプ)
- 保険金受取方法(年金・一時金)
まず、定期タイプと終身タイプのどちらの保険期間を選ぶか考えよう。
定期タイプは10年・15年などの保険期間を定め、保険期間中に要介護状態となった場合に保険金が給付されるタイプだ。
「公的介護保険の対象外となる65歳までを保障したい」などの場合に適している。
一方の終身タイプは保障が死亡するまで続くタイプの保険である。
一生涯にわたる保障を得られる安心感がある一方、定期タイプに比べて保険料が高めである点に注意が必要だ。
介護のリスクは年々高くなっていくことを考えると終身タイプが安心だが、保険料とのバランスを見極める必要がある。
定期タイプと終身タイプのどちらが自分に合っているか考え、適切な商品を選択しよう。
また、保険金受取方法について考えることも重要となる。
年金または一時金のどちらで受け取るかを考えよう。
年金形式で受け取る場合、所定の要介護状態にある限り保険金を受け取ることができる。
長期間にわたる介護の経済的負担をカバーできる点が魅力だ。
一方、一時金形式で受け取る場合、所定の要介護状態となったときにまとまった保険金が給付される。
施設の入所や介護用品の購入など、初期費用に使いやすいことが特徴である。
なかには年金・一時金の両方を受給できるタイプもある。
どういった形式で保険金を受け取るか考えておこう。
「生命保険ナビ」では、全国にいる保険のプロの中からあなたの希望や意向に沿った担当者とマッチングできるサービスを提供している。
専門家の適切なアドバイスにより、ライフプランに合った最適な保険と出会えるかもしれない。
「介護保険の必要性を知りたい」「自分に合う総合的な保険プランを設計したい」という方は、ぜひこの機会に「生命保険ナビ」を活用してみてはいかがだろうか。
民間介護保険は必要か?と感じたら複数の商品を比較検討してみよう

本記事では、介護保険の役割やメリット・デメリットを深堀りし、必要性について解説した。
民間の介護保険は、加入すれば介護に手厚く備えられる一方、保険料の負担がかかる。
今回解説した保険が必要な人・不要な人の特徴も参考に、自分に本当に必要かどうかを見極めることが重要となる。
このように、介護保険の必要性やどの保険を選ぶべきかについては個々の状況によるため、一概には語ることはできない。
そのため、最終決定は専門家との相談を経たうえで自身で下していただくことを強くお勧めする。
その際におすすめなのが、マッチングサービス「生命保険ナビ」である。
「生命保険ナビ」には全国の保険のプロが登録しており、あなたの希望条件や相談内容に合った担当者を簡単に見つけることができる。
一人で迷わず、専門家のアドバイスを得て、ベストな保険選びを行おう。お申込みはこちらから。