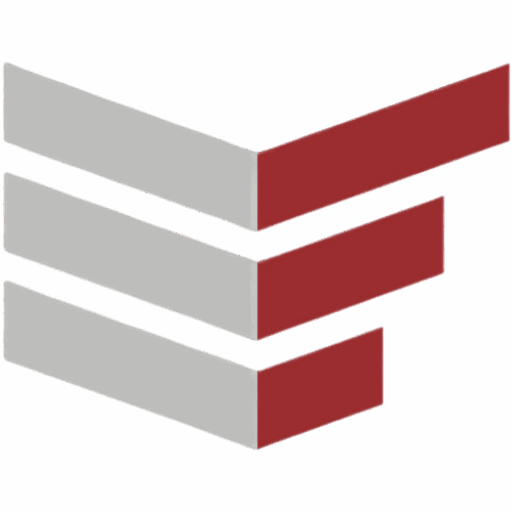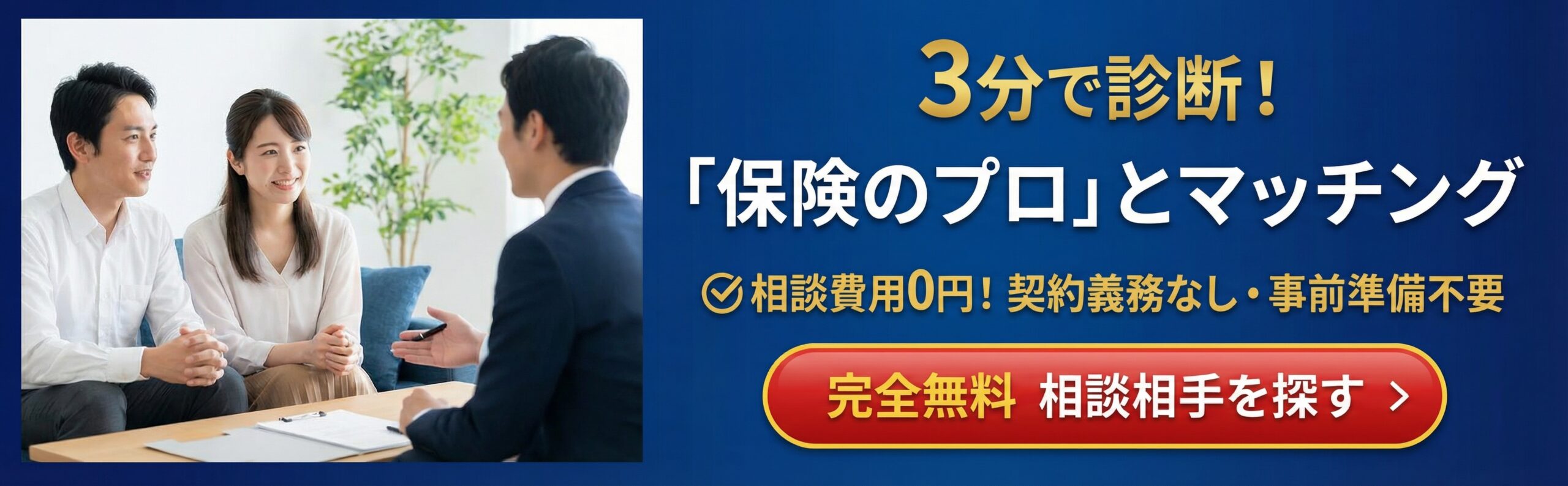- 死亡保険3000万円の月額は定期なら数千円〜、終身なら数万円〜と桁が変わり得る。
- 保険種類・年齢・保障期間の組み合わせで保険料が大きく変動するためだ。
- 以下で相場感、条件の決め方、必要保障額の計算、税金、比較方法を整理する。
子育て中で住宅ローンも抱えている。万が一のとき、家族が困らないように死亡保険を検討したい。でも、3000万円の保障を持つと月々いくらかかるのか——見当がつかない。そんな不安を抱えている人は多い。
保険料は年齢や保険の種類、保障期間によって大きく変わり、同じ3000万円でも月額数千円で済む場合もあれば、数万円になる場合もある。どこで差がつくのか、そもそも3000万円が自分に必要なのか、税金や受取方法まで含めて整理していく。
死亡保険3000万円は月額いくら?相場を先に確認
死亡保険3000万円の月額は、定期保険なら2500円〜2万円程度、終身保険なら4万円〜4万5000円程度。保険の種類や保障期間によって、桁が変わることもある。まず「どのくらいの幅があるか」を把握し、次に自分の条件を固定して比較する流れが基本だ。
2人以上世帯の生命保険加入率は89.2%、年間払込保険料の平均は35.3万円と報告されている。月額にすると約3万円弱。ただし、これは死亡保険だけでなく医療保険なども含む総額だ。死亡保険だけで月3万円を超えるようなら、家計全体で見直しを検討したい。
月額の目安レンジ(定期・終身)
30歳男性が死亡保険金3000万円の定期保険を検討する場合、保険期間によって月額2500円〜2万円程度と幅が出る。10年定期なら安く、90歳満了など長期になるほど高くなる傾向がある。
同じ30歳男性・3000万円でも、定期(55歳満了)は月額4000〜5000円程度、終身は月額4万円〜4万5000円程度。およそ10倍の差がある。終身は一生涯保障が続くため、その分だけ保険料が高くなる。
| 保険種類 | 前提条件 | 月額目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 定期保険 | 30歳男性・3000万円・期間で変動 | 2500円〜2万円程度 | 期間が長いほど高くなる |
| 定期保険(55歳満了) | 30歳男性・3000万円 | 4000〜5000円程度 | 55歳以降は保障なし |
| 終身保険 | 30歳男性・3000万円 | 4万円〜4万5000円程度 | 一生涯保障・解約返戻金あり |
保障期間で保険料が変わる
同じ3000万円の定期保険でも、保障期間が10年なのか、20年なのか、60歳満了なのかで保険料は大きく異なる。保険会社は「何年間、死亡リスクを引き受けるか」によって保険料を計算するため、期間が長くなれば月額は上がりやすい。
ここで注意したいのが「保険期間」と「払込期間」の違いだ。保険期間は「保障が続く期間」、払込期間は「保険料を払う期間」を指す。
60歳満了の定期保険でも、払込期間が55歳までなら、55歳以降は保険料を払わずに60歳まで保障が続く。この2つを混同すると、見積もり比較で条件がズレてしまう。
見積もり前に決めるべき条件
複数の保険を比較するなら、まず「揃えるべき条件」を固定しておく。以下の項目を事前にチェックリスト化しておくと、比較の事故を防げる。
- 年齢(見積もり時点の満年齢)
- 性別
- 保険種類(定期・終身・収入保障など)
- 保険金額(3000万円で固定)
- 保険期間(○年定期 or ○歳満了)
- 払込期間(保険期間と同じか、短期払いか)
- 喫煙の有無・健康状態
- 付帯する特約の有無
では、保険料が変わる要因をもう少し詳しく見てみよう。
3000万円の死亡保険の月額が決まる条件と保険料の仕組み
月額保険料を左右する主な要因は4つ。年齢・性別、保険期間と払込期間、健康状態、特約の有無だ。これを押さえておけば、見積もりの数字がなぜ違うのか説明できる。「なんとなく安い方を選ぶ」という曖昧さも減る。
年齢・性別で料率が変わる
保険料は、年齢が高いほど上がる傾向がある。死亡リスクが年齢とともに高まるためだ。同じ30歳でも、男性と女性では統計上の死亡率が異なるため、性別によっても保険料は変わる。
見積もりを取るときは「現在の満年齢」と「性別」を正確に入力する。誕生日を挟むと年齢が変わり、保険料も変わる。意外と見逃しがちだ。
保険期間と払込期間の違い
保険期間は「保障が有効な期間」、払込期間は「保険料を支払う期間」だ。この2つは一致することもあれば、異なることもある。
たとえば「60歳満了・60歳払込」なら、60歳まで保険料を払い、60歳で保障も終わる。「60歳満了・55歳払込」なら、55歳で保険料の支払いが終わり、55歳から60歳までは保険料ゼロで保障が続く。後者は月々の保険料が高くなるが、定年後の支出を減らせるメリットがある。
見積もりを比較するときは、両方の期間を揃えないと正しく比較できない。
健康状態(喫煙など)で割増の可能性
保険会社は契約時に「告知」を求める。喫煙の有無、過去の病歴、現在の治療状況などを申告し、引受可否や保険料区分が決まる仕組みだ。
非喫煙者や健康体と認定されれば、保険料が割安になる商品もある。逆に、喫煙者や持病がある場合は割増になったり、加入できなかったりするケースもある。
特約の付け方で月額が上がる
死亡保険には「主契約」と「特約」がある。主契約は死亡保障そのもの、特約は追加オプションだ。たとえば、災害死亡割増特約、リビングニーズ特約、保険料払込免除特約などがある。
特約を付けると保障は手厚くなるが、その分だけ月額が上がる。必要性を見極めずに「あったほうが安心」と付けすぎると、家計を圧迫する。判断の順序は次のとおり。
- まず主契約(死亡保障)の金額と期間を決める
- 特約の内容と費用を確認する
- 「本当に必要か」を家計と照らし合わせる
- 他の保険(医療保険など)でカバーできないか検討する
- 主契約と特約を分けて比較できるようにしておく
条件の決め方がわかったところで、次は「月額を抑えたい場合にどう設計するか」を見ていこう。
3000万円の死亡保険は定期保険で月額を抑えやすい仕組み
掛け捨てで大きな保障を持つ考え方
定期保険は満期を迎えても解約返戻金がない「掛け捨て」が基本だ。貯蓄にはならないが、その分だけ保険料が安く、同じ予算で大きな保険金額を設定できる。
「掛け捨ては損」と感じる人もいるだろう。しかし、保険の目的は「万が一のときに遺族が困らないようにする」ことだ。何事もなく満期を迎えたら、それは喜ばしいこと。保険料は「安心を買うコスト」だ。貯蓄は貯蓄、保障は保障と分けて考えると、設計がシンプルになる。
更新型は将来の保険料が上がる
定期保険には「更新型」と「全期型」がある。更新型は10年や15年ごとに契約を更新し、そのたびに保険料が再計算される。更新時の年齢で保険料が決まるため、更新後は保険料が上がる。
たとえば、30歳で加入した10年更新型の定期保険は、40歳で更新するときに40歳時点の保険料に切り替わる。50歳、60歳と更新を重ねるたびに保険料負担は増えていく。
一方、全期型は契約時に保険料が固定され、満期まで変わらない。更新型より当初の保険料は高めだが、長期で見ると総支払額が抑えられるケースもある。どちらが合うかは家計のキャッシュフローと相談だ。
子どもが独立するまでの設計例
保障期間をどう決めるか迷ったら、「いつまで保障が必要か」から逆算してみるといい。以下のような節目を基準に考えるとよい。
- 末子が大学を卒業するまで(例:22歳)
- 住宅ローンの完済時期
- 配偶者が年金を受け取り始める時期
- 自分の定年退職時期
- 子どもが経済的に独立する想定時期
- 教育費の支払いが終わる時期
幼稚園から高校まですべて公立の場合、教育費総額は約614万円とされる。大学進学まで想定するなら、国立大学でも入学金+4年授業料で約240万円が目安になる。こうした費用をカバーする期間を軸に、保障期間を設定するのが一つの考え方だ。
ネット型は保険料差が出やすい
近年はインターネットで申し込める保険(ネット型)が増えている。対面型に比べて人件費や店舗コストを抑えられるため、同じ条件でも保険料が安くなるケースがある。
ただし、ネット型が必ず安いとは限らない。対面型でも健康体割引や団体割引が適用される場合は逆転することもある。同条件で複数社から見積もりを取って比較する。シンプルだが、これが効く。詳しい比較方法は後ほど整理する。
次は、終身保険だと月額が高くなる理由を確認しよう。
3000万円の死亡保険は終身保険だと月額が高くなる理由
終身保険は「一生涯保障が続く」ことと「解約返戻金がある」ことで、定期保険より月額が高くなりやすい。同じ30歳男性・3000万円でも、定期(55歳満了)は月額4000〜5000円程度、終身は月額4万円〜4万5000円程度。およそ10倍の差がある。
終身は一生涯保障でコストが高い
定期保険は「一定期間だけ」死亡リスクを保険会社が引き受ける。終身保険は「死亡するまでずっと」引き受ける。人は必ず死亡する。だから終身保険は「いつか必ず保険金を支払う」前提になっている。
その分、保険料は高くなる。子育て中など「今だけ大きな保障が必要」という人には、終身の高い保険料は負担になりやすい。一方、相続対策や葬儀費用の準備など「一生涯の保障が必要」という目的なら、終身が選択肢に入る。
解約返戻金があると保険料は上がる
終身保険の多くは、途中で解約すると「解約返戻金」が戻ってくる。これは貯蓄性があるともいえるが、その分だけ保険料に上乗せされている構造だ。
貯蓄目的なら資産運用と比較する
「終身保険で貯蓄も兼ねたい」と考えるなら、一度立ち止まって比較したい。保障が必要なのか、資産を増やしたいのか、目的を明確にすることが先だ。
- 目的:万が一の保障が必要か、資産形成が目的か
- 流動性:いつでも引き出せるか、途中解約のペナルティはあるか
- 保障の有無:投資信託やNISAには死亡保障がない
- コスト:保険料に含まれる手数料と、投資の信託報酬を比較
- リスク:元本保証の有無、為替リスクの有無
終身保険の特性がわかったところで、次は「収入保障保険」という別の選択肢を見てみよう。
3000万円の死亡保険は収入保障保険も検討すべき選択肢
一括で3000万円を受け取る設計だけが正解ではない。「毎月〇万円を受け取る」収入保障保険という選択肢もある。時間が経つほど必要な保障額が減る家庭には、合理的な設計ができる可能性がある。
収入保障は保障総額が逓減する
収入保障保険は、被保険者が死亡すると遺族に「年金形式」で保険金が支払われる仕組みだ。たとえば「月額15万円を60歳まで」という設計なら、30歳で死亡すれば30年間受け取れるが、50歳で死亡すれば10年間しか受け取れない。
つまり、契約してから時間が経つほど、受け取れる総額は減っていく。これが「逓減」だ。子どもが成長すれば教育費の残り期間は短くなり、住宅ローンも残高が減っていく。必要保障額が時間とともに減る家庭には、逓減型が合う。
毎月の必要生活費から年金額を決める
収入保障保険の年金額は、「遺族が毎月いくら不足するか」から逆算して決める。以下のステップで考えるとよい。
Step1:遺族の月々の生活費を見積もる
二人以上世帯の消費支出は、2024年平均で月300,243円と公表されている。ただし、世帯主の死亡後は人数が減るため、7〜8割程度で見積もることが多い。
Step2:遺族年金などの公的保障を差し引く
遺族基礎年金の年金額は831,700円(令和7年4月分から)で、子の加算があれば第1・第2子は各239,300円、第3子以降は各79,800円がプラスされる。月額換算で10万円前後になるケースもある。
Step3:不足額を年金額として設定する
生活費からStep2を引いた金額が、収入保障保険で補う目安になる。
一時金受取と年金受取の違い
収入保障保険は「年金形式」で受け取るのが基本だが、一括で受け取る選択肢がある商品もある。一時金で受け取ると、年金で受け取るよりも総額が少なくなるのが一般的だ。
年金形式は「毎月の生活費を補う」イメージで、家計管理がしやすい。一時金は「まとまった支出(住宅ローンの一括返済など)に充てたい」場合に向く。どちらが合うかは、遺族の生活設計次第だ。
ここまでで保険の種類と仕組みを整理した。次は「そもそも3000万円が必要なのか」を計算で確かめる方法を見ていこう。
死亡保険3000万円が必要か計算で確かめる
3000万円という数字に根拠があるかどうか。「遺族の支出」から「公的保障と貯蓄」を差し引いて確かめてみよう。計算してみると、3000万円では足りないケースも、逆に過大なケースもある。自分の家庭に合った金額を把握しておこう。
遺族の支出(生活費・教育費・葬儀)
まず、世帯主が亡くなった後に遺族が必要とする支出を書き出してみる。
生活費:二人以上世帯の消費支出は、2024年平均で月300,243円だ。世帯主の死亡後は7〜8割程度に減ると仮定し、必要年数をかけて総額を出す。子どもが独立するまで20年なら、月24万円×12か月×20年=約5760万円といった計算になる。
教育費:幼稚園から高校まですべて公立なら約614万円、国立大学なら入学金+4年授業料で約240万円が目安だ。子どもの人数分をかけて積み上げる。
葬儀費用:自社アンケートでは葬儀費用の平均が約152万円とされている。葬儀費用が100万円以下だった人は44.6%。簡素に済ませれば100万円以下に収まることも多い。お墓の費用も考慮するなら、さらに上乗せが必要だ。
公的保障と貯蓄で差し引く
支出の総額が出たら、公的保障と現在の貯蓄を差し引く。
Step1:遺族年金を計算する
遺族基礎年金は831,700円(令和7年4月分から)、子の加算は第1・第2子が各239,300円、第3子以降が各79,800円だ。子どもが18歳になるまで受け取れる。
Step2:遺族厚生年金を確認する
会社員や公務員の配偶者は遺族厚生年金も対象になる場合がある。遺族厚生年金には中高齢寡婦加算があり、年金額は623,800円(令和7年4月分から)だ。受給要件は複雑なので、年金事務所に問い合わせてみてほしい。
Step3:貯蓄・資産を差し引く
預貯金、投資信託、退職金の見込み、配偶者の収入なども「備え」として計上できる。
必要保障額から3000万円の過不足を判断
必要保障額は「支出総額-(公的保障+貯蓄)」で計算できる。
たとえば、支出総額が7000万円、遺族年金の総額が2000万円、貯蓄が1000万円なら、必要保障額は4000万円になる。この場合、3000万円では1000万円不足する。
逆に、共働きで配偶者の収入が十分にあり、住宅ローンに団信が付いているなら、3000万円でも過大になるケースがある。世帯の普通死亡保険金額は、全体平均で1936万円と報告されている。3000万円は平均より高めの設定だ。
家計に無理のない月額上限を決める
必要保障額が決まったら、次は「月額いくらまでなら払えるか」を家計から逆算する。保険料は固定費として毎月出ていく。無理のない水準を決めておく。
住居費、食費、通信費、教育費などの固定費を一覧にし、余裕資金のなかから保険料に回せる金額を決める。保障を手厚くしたいからと月額を上げすぎると、貯蓄や教育費に回す資金が減り、別のリスクが生まれる。
必要保障額と月額上限が決まったら、税金の話も押さえておきたい。次章で整理する。
3000万円の死亡保険金の税金はどうなる?受け取りの注意
死亡保険金を受け取るとき、契約形態によって「相続税」「所得税(住民税)」「贈与税」のいずれかがかかる。税目によって負担が大きく変わる。契約時点で受取人の設定を意識しておくことだ。
死亡保険金にかかる税金は3パターン
死亡保険金の税金は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせで決まる。以下の3パターンがある。
①契約者A/被保険者A/受取人B=相続税
②契約者A/被保険者B/受取人A=所得税(+住民税)
③契約者A/被保険者B/受取人C=贈与税
夫が契約者兼被保険者で、妻が受取人なら①の相続税になる。相続税には非課税枠があるため、税負担が軽くなりやすい。
契約者・被保険者・受取人で税目が変わる
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税目 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | 相続税 |
| A | B | A | 所得税(住民税) |
| A | B | C | 贈与税 |
所得税扱いになる場合、一時所得として計算される。計算式は「(保険金-払込保険料-特別控除50万円)×1/2」だ。この金額が他の所得と合算され、所得税・住民税がかかる。
贈与税は基礎控除が110万円しかなく、税率も高いため、大きな保険金を受け取ると負担が重くなりやすい。契約形態を見直すだけで税目が変わることがあるので、加入時に確認しておきたい。
非課税枠(500万円×法定相続人)
相続税の場合、死亡保険金には非課税限度額がある。「500万円×法定相続人の数」が非課税枠だ。たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人なら、500万円×3=1500万円までは非課税になる。
請求期限と必要書類を確認する
保険金・給付金の請求には時効がある。一般的に3年とされるが、3年経過後でも請求すれば支払いに応じる旨の記載がある保険会社もある。いずれにしても、早めに請求手続きを進めておきたい。
- 請求期限:時効は3年が目安だが、早めに手続きする
- 保険会社への連絡:契約者番号や証券番号を伝える
- 必要書類:死亡診断書、戸籍謄本、受取人の本人確認書類など
- 不明な場合:保険会社のコールセンターに確認する
税金と手続きの基本がわかったところで、最後に「複数社で見積もる方法」を整理しよう。
3000万円の死亡保険は複数社で見積もって月額を最適化しよう
同じ3000万円の保障でも、保険会社によって月額は異なる。条件を揃えて複数社から見積もりを取れば、家計に合った選択がしやすくなる。保険料だけでなく、免責条件や更新条件も見比べておきたい。
条件を揃えて見積もり比較する
比較の精度を上げるには、以下の条件をすべて揃えて見積もりを取りたい。
- 保険金額:3000万円で統一
- 保険種類:定期 or 終身 or 収入保障
- 保険期間:○歳満了 or ○年定期
- 払込期間:保険期間と同一 or 短期払い
- 喫煙の有無・健康区分
- 付帯する特約の有無と内容
- 保険料の払込方法:月払い or 年払い
- リビングニーズ特約など無料特約の有無
保険料だけでなく免責と更新条件を見る
保険料が安くても、保障内容に差があれば比較にならない。以下の観点でチェックしておきたい。
- 免責期間:契約後○年以内の死亡は保険金が減額されるか
- 免責事由:自殺や犯罪行為など、保険金が支払われないケース
- 更新条件:更新時に告知が必要か、更新上限年齢は何歳か
- 支払事由:どのような状態で保険金が支払われるか
- 特約の更新:主契約と同じ条件で更新できるか
- 保険料の払込免除:どのような条件で適用されるか
安さだけで選ぶと、いざというときに「支払われなかった」というリスクがある。約款や契約のしおりを確認し、不明点は保険会社に問い合わせてみてほしい。
乗り換え時は告知と保障空白に注意
すでに死亡保険に加入していて、別の保険に乗り換えを検討している場合は、以下に気をつけたい。
まず、新しい保険の契約が成立する前に、古い保険を解約しないこと。新しい保険の審査に落ちたり、条件付きでしか加入できなかったりするケースがある。古い保険を解約してから新しい保険に入れないと、「保障の空白期間」が生まれてしまう。
新しい保険の加入時には、改めて告知が必要になる。以前の契約時と健康状態が変わっている場合、保険料が上がったり、加入できなかったりする可能性がある。乗り換えは「新契約の成立を確認してから旧契約を解約」の順序を守りたい。
全体まとめ
死亡保険3000万円の月額は、定期保険なら月額2500円〜2万円程度、終身保険なら月額4万円〜4万5000円程度と、保険の種類や保障期間によって大きく変わる。月額を抑えたいなら定期保険や収入保障保険が選択肢になり、一生涯の保障が必要なら終身保険を検討することになる。
3000万円という数字が自分に合っているかは、遺族の支出から公的保障と貯蓄を差し引いて確かめるのが基本だ。税金は契約形態で変わり、相続税なら非課税枠(500万円×法定相続人)を活用できる。
FAQ
死亡保険は団体信用生命保険(団信)があると減らせる?
住宅ローンに団信が付いている場合、ローン残高は団信でカバーされる。そのため、死亡保険で住宅ローン返済分を見込む必要がなくなり、必要保障額を減らせる可能性がある。
ただし、団信はローン残高だけをカバーするものだ。遺族の生活費や教育費は別途必要になる。「団信があるから死亡保険は不要」とは限らない。団信でカバーされる範囲を確認し、重複を点検したうえで保障額を決めるとよい。
死亡保険は生命保険料控除の対象?上限はいくら?
死亡保険の保険料は、生命保険料控除の対象になる。年末調整や確定申告で申告すると、所得税と住民税が軽減される。
控除額の上限は、新制度(2012年以後の契約など)の場合、所得税で一般・個人年金・介護医療の各4万円(合計12万円)、住民税で各2.8万円(合計7万円)とされている。旧制度(2011年以前の契約など)の場合は、所得税で一般・個人年金の各5万円(合計10万円)、住民税で各3.5万円(合計7万円)が上限だ。
なお、2026(令和8)年分から、23歳未満の扶養親族等がいる場合は一般生命保険料控除(所得税)の上限が6万円になると案内されている。子育て世帯は控除額が増える可能性があるため、今後の改正情報を確認しておきたい。
死亡保険は共済(県民共済など)とどう違う?
共済(県民共済、こくみん共済 coopなど)と民間の生命保険は、運営主体や保障の仕組みが異なる。比較するときは、以下の観点を押さえておくとよい。
- 加入条件:共済は組合員になる必要がある
- 保障内容:共済は定額のパッケージ型が多い
- 更新・年齢制限:共済は65歳以降に保障が減る商品が多い
- 割戻金:共済は決算後に掛金の一部が戻ることがある
- カスタマイズ性:民間の生命保険は特約で細かく設計できる
どちらが良いかは一概に言えないが、「大きな保障を長期間持ちたい」なら民間の生命保険、「掛金を抑えて一定の保障を持ちたい」なら共済が向くケースがある。
死亡保険の高度障害保障は付けるべき?
多くの死亡保険には、高度障害状態になった場合も保険金が支払われる「高度障害保障」が付いている。高度障害とは、両眼の視力を失う、言語機能を失う、両手足の機能を失うなど、重度の障害状態を指す。
高度障害保障があると、死亡前でも保険金を受け取れるため、介護費用や生活費に充てられる。ただし、高度障害の定義は保険会社によって異なり、すべての障害がカバーされるわけではない。約款で「どのような状態が該当するか」をチェックしておく。
死亡保険の受取人はいつ見直すべき?
受取人の設定は、契約後も変更できる。以下のようなライフイベントがあったときは、受取人の見直しを検討する。
- 結婚したとき:配偶者を受取人にするか検討
- 子どもが生まれたとき:配偶者と子どもの配分を検討
- 離婚したとき:元配偶者のままになっていないか確認
- 再婚したとき:新しい配偶者や子どもへの変更を検討
- 子どもが独立したとき:配偶者のみにするか検討
- 受取人が先に亡くなったとき:新しい受取人を指定
受取人の変更手続きは、保険会社に連絡して書類を提出するのが一般的だ。放置すると、意図しない人に保険金が渡る可能性がある。ライフイベントごとに見直す習慣をつけておくと安心だ。
出典一覧
SBIいきいき少額短期保険株式会社(i-Sedai)「死亡保険金3,000万円の保険料は月額いくら?必要保障額の目安を解説」
https://www.i-sedai.com/contents/money/M0130.html
アクサ生命保険株式会社「死亡保険の保険料は月額いくらがいい?3,000万円の保障額の場合も解説」
https://www.axa.co.jp/about-insurance/column/life02/
公益財団法人生命保険文化センター「2024(令和6)年度 生命保険に関する全国実態調査<速報版>」
https://www.jili.or.jp/files/research/zenkokujittai/pdf/r6/2024sokuhou.pdf
総務省統計局「家計調査報告〔家計収支編〕2024年(令和6年)平均結果の概要」
https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_gaikyo2024.pdf
日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html
日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
国税庁 タックスアンサー No.1750「死亡保険金を受け取ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm
国税庁 タックスアンサー No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
一般社団法人生命保険協会「東日本大震災 保険金等の請求手続きに関するQ&A」
https://www.seiho.or.jp/data/billboard/disaster01/info01/faq01/
公益財団法人生命保険文化センター「税金の負担が軽くなる『生命保険料控除』」
https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/22.html