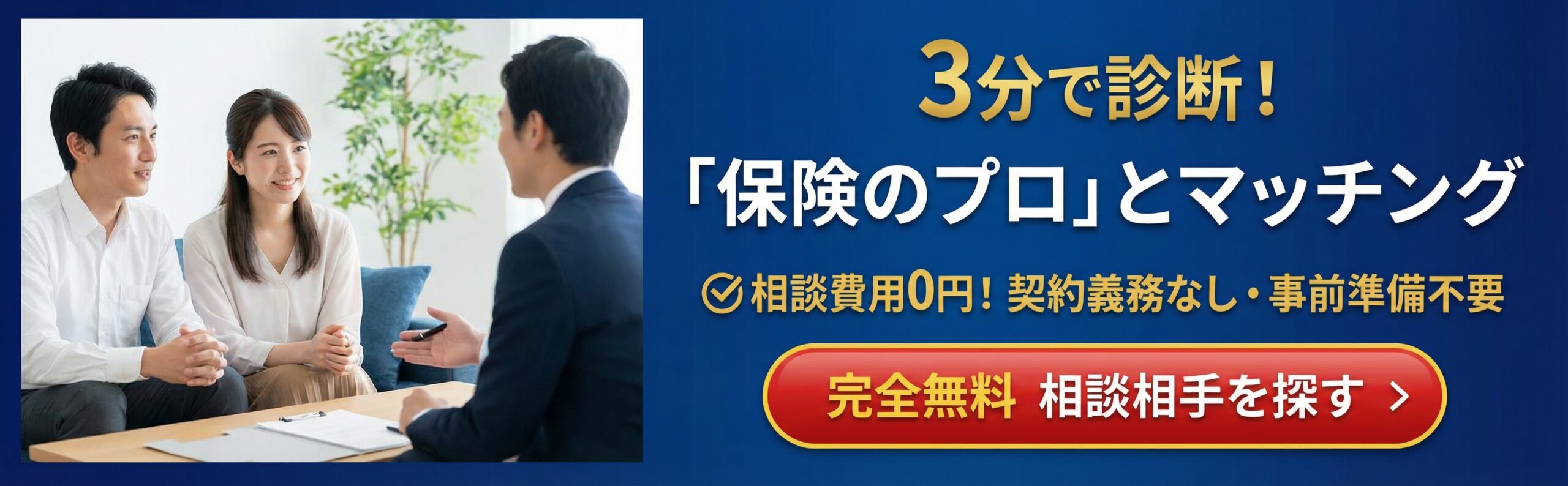現代の日本において、「がん」は非常に身近な病気である。
国立がん研究センターの統計によれば、日本人が一生のうちにがんと診断される確率は、2人に1人(男性65.5%、女性51.2% ※2019年データ)とされている。これは、もはや“他人事”ではなく、誰もが当事者となりうる「自分事」の備えが必要であることを示している。
もちろん、日本には優れた公的医療保険制度があり、高額療養費制度によって、医療機関の窓口で支払う自己負担額は一定の上限(所得に応じて変動)までに抑えられる。しかし、がん治療には公的保険が適用されない費用も多く、家計へのリスクがすべて解消されるわけではない。
具体的には、以下のような費用が自己負担としてのしかかる。
- 先進医療の技術料: 公的保険の対象外となる特定の高度医療技術。技術料は全額自己負担となり、中には300万円を超えるものもある。
- 差額ベッド代: 希望して個室や少人数部屋に入院した場合の室料。
- 諸雑費: 入院中の食事代の一部、日用品、交通費(家族の見舞い費用含む)、ウィッグ(かつら)の購入費など。
- 収入の減少: 治療のための休職や時短勤務による収入減。特に自営業者やフリーランスにとっては深刻な問題となりうる。
こうした公的保険の“穴”を埋めるために存在するのが、民間の「がん保険」である。
だが、ここで一つ大きな問題がある。「昔、勧められるがままに加入した」「若い頃に入ったきり、内容を覚えていない」――そんな“放置されたがん保険”が、現代のがん治療の実態や、現在のあなたのライフスタイルと大きくかけ離れてしまっている可能性があるのだ。
医療は日進月歩であり、10年前、20年前に主流だった治療法と、現在の治療法は大きく異なる。それに伴い、がん保険も進化を続けている。古い契約のままでは、いざという時に「期待した保障が受けられない」という事態になりかねない。
この記事は、すでに何らかのがん保険に加入している30代から60代の方々を対象に、なぜ今、がん保険の見直しが必要なのか、その理由と適切なタイミング、具体的な見直し方法、そして注意すべきデメリットまでを網羅的に解説する総合ガイドである。
不安をいたずらに煽るつもりはない。しかし、事実とデータに基づけば、「放置」は賢明な選択とは言えない。この記事を通じて、ご自身の契約内容を「棚卸し」し、必要に応じて賢く見直すための一歩を踏み出してほしい。
がん保険を見直すべき理由
なぜ、せっかく加入した がん保険をわざわざ見直す必要があるのか。それは、「医療環境の変化」と「ライフスタイルの変化」という2つの大きな変化によって、加入当時に最適だったはずの保障が、現在では不十分、あるいはズレたものになっている可能性が高いからである。
医療技術の進歩による保障不足の可能性
最大の理由は、がん治療のスタイルがこの10年、20年で劇的に変化したことである。
| 比較項目 | 昔のがん治療(イメージ) | 現在のがん治療(主流化) |
| 治療の中心 | 入院・手術 | 通院・薬物療法・放射線治療 |
| 入院期間 | 長期化(数十日〜) | 短期化(平均19.6日※、数日の場合も) |
| 主な治療法 | 開腹手術など | 手術(腹腔鏡・ロボット支援)、薬物療法(抗がん剤、分子標的薬等)、放射線治療 |
| 治療の場 | 病院(ベッドの上) | 病院(外来)、在宅(内服薬) |
◆治療スタイルの変化:入院から通院へ
ひと昔前のがん治療といえば、「長期入院をして手術を受ける」というのが一般的であった。そのため、古いタイプのがん保険は、「入院1日あたり◯万円」という入院給付金を保障の主軸に据えているものが多い。
しかし、医療技術の進歩、手術手技の向上(腹腔鏡手術やロボット支援手術など)、そして強力な副作用対策が可能な新しい抗がん剤の登場により、がん治療は大きく様変わりした。
- 入院日数の短期化: 手術のための入院は短期化し、厚生労働省の患者調査(2020年)によれば、がん(悪性新生物)の平均在院日数は約19.6日(※2020年調査時点。最新のデータではさらに短期化傾向)となっている。部位や病期によっては、数日での退院も珍しくない。
- 通院治療の主流化: 手術後や、手術が適さないケースでは、通院による薬物療法(抗がん剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬など)や放射線治療が治療の中心となりつつある。
この変化に対し、古い保険の設計は対応しきれていないケースが多い。
例えば、入院給付金1日1万円、入院3日目から支給される古い保険に加入していた場合、2泊3日で退院すると支給額はわずか1万円。さらに月2回の通院で抗がん剤治療を受けても、通院保障が付いていなければ給付金は0円。現代型の保険では、通院1日目から給付され、診断給付金として50〜100万円を受け取れる例もある。「通院保障」がそもそも付いていない、あるいは「入院後の通院のみ対象」といった制限があると、主流となりつつある通院での薬物療法がカバーされないのだ。
◆具体例:10年前の保険が役に立たなかったケース
10年前に「入院日額1万円」を主契約とする がん保険に加入したAさん。
先日、初期のがんと診断され、2泊3日の入院で手術を受けた。術後は、再発予防のために半年にわたり、月2回の通院で抗がん剤治療(点滴)を受けることになった。
Aさんの保険は「入院3日目から給付」という条件だったため、受け取れた給付金はわずか1万円(3日目1日分のみ)。その後の通院治療に対する保障は一切なかった。
実際には、通院のたびに高額な薬剤費の自己負担(高額療養費制度適用後)が発生し、治療のたびに仕事を半日休む必要もあった。交通費や雑費もかさみ、「もしものために備えていたはずの保険が、ほとんど役に立たなかった」とAさんは実感した。
◆高額治療・先進医療への対応不足
がん治療の選択肢は広がり、中には非常に高額な治療も存在する。その代表が「先進医療」である。
先進医療とは、公的医療保険の対象とするかを評価中の高度な医療技術であり、有効性や安全性は確認されているものの、保険診療との併用が認められているものである。
この先進医療にかかる「技術料」は、公的医療保険の対象外であり、全額自己負担となる。例えば、重粒子線治療や陽子線治療といった高度な放射線治療では、技術料だけで300万円を超えるケースも珍しくない(※部位や病期によっては公的保険適用となる治療法も増えている)。
近年のがん保険では、この先進医療の技術料を実費で(上限2,000万円程度まで)保障する「先進医療特約」を付加するのが一般的である。しかし、10年以上前の古い契約では、この特約自体が存在しなかったり、付加できなかったり、保障範囲が狭かったりする場合が多い。
同様に、新しい抗がん剤治療やホルモン剤治療などを受けた月に定額(10万円など)が支払われる「抗がん剤治療特約(治療給付金特約)」なども、古い保険には備わっていないことが多い。
このように、医療の進歩は喜ばしいことである反面、古い保険のままでは、その進歩した治療の恩恵を受けるための経済的障壁に対応できないリスクをはらんでいるのである。
| 保障項目 | 古いがん保険(よくある設計) | 新しいがん保険(現代の主流) |
| 主役の保障 | 入院給付金(日額◯円) | 診断給付金(一時金◯万円) |
| 入院給付 | 「入院5日目から」など免責日数あり | 「入院1日目から」「日数無制限」が主流 |
| 通院保障 | 付いていない、または「入院後の通院」のみ | 入院の有無を問わない「通院治療給付金」(外来の抗がん剤治療等も対象) |
| 高額治療 | 先進医療特約がない、または保障範囲が狭い | 先進医療特約(上限2,000万円等)が標準付加可能 |
経済的リスクへの備え(がん治療費・収入減)
| 項目 | 費用の説明 | 公的保険 |
| 治療費・薬代 | 手術、抗がん剤、放射線治療など | ○ 対象 (高額療養費制度も使える) |
| 先進医療 | 特定の高度医療の「技術料」 | ✕ 対象外 (全額自己負担) |
| 差額ベッド代 | 少人数部屋や個室を希望した場合の室料 | ✕ 対象外 (全額自己負担) |
| 入院中の食事代 | 入院中の食事療養費の一部 | ✕ 対象外 (一部自己負担) |
| 諸雑費・交通費 | ウィッグ代、日用品、家族の交通費 | ✕ 対象外 (全額自己負担) |
がん保険を見直す第二の理由は、治療にかかる「直接的な費用」と、働けなくなることによる「間接的な費用(収入減)」という、トータルの経済的リスクを正しく見積もるためである。
◆がん治療費の目安
まず、治療費そのものについて見ておきたい。厚生労働省の調査などに基づくと、がんの入院1件あたりの医療費総額(10割)は、多くのがんで60万円〜80万円前後だが、部位や治療内容によっては100万円以上になることも少なくない。
公的医療保険の自己負担は原則3割(年齢・所得による)であり、さらに高額療養費制度があるため、1ヶ月の医療費の自己負担には上限額(例えば、標準報酬月額28万~50万円の会社員なら約8万円強+α)が設定されている(※制度や上限額は将来変更される可能性がある)。
そのため、1回の入院・手術だけを見れば、自己負担は数万円〜十数万円程度で済むケースも多い。しかし、がんは治療が長期化したり、再発・転移によって入退院や通院を繰り返したりする病気である。そのたびに自己負担は発生し、トータルでの負担額は決して小さくない。
◆公的保険適用外の費用
さらに深刻なのが、先述した「先進医療」の技術料のほか、高額療養費制度の対象とならない「自費負担」の部分である。
- 差額ベッド代(1日あたり平均 約6,600円 ※2021年 厚労省調査)
- 入院中の食事代の一部
- 家族が病院に通うための交通費、遠方の場合は宿泊費
- パジャマや日用品、テレビカードなどの雑費
- 抗がん剤治療の副作用に備えるためのウィッグ(かつら)や専用下着の購入費
これらはすべて、公的保険とは別に、貯蓄や がん保険からの給付金で賄う必要がある。特に、まとまった金額が自由に使途(使いみち)を問われずに支払われる「診断給付金(一時金)」は、こうした治療費以外の諸費用や、当面の生活費に充当できるため、現代のがん保険において最も重要な保障の一つとされている。
◆収入減のリスク
| 対象者 | 公的保障(収入サポート) | リスク・注意点 |
| 会社員・公務員 | 傷病手当金 (最長1年6ヶ月、給与の約2/3) | ・給与が満額出るわけではない。 ・「約2/3」では住宅ローン等の返済が苦しくなるケースも。 |
| 自営業・フリーランス | 原則なし (国民健康保険には傷病手当金がない※) | ・働けなくなると、即「収入ゼロ」になるリスク。 ・会社員以上に手厚い備え(診断一時金)が必要。 |
見落とされがちなのが、「収入減」のリスクである。
- 会社員・公務員の場合:病気やケガで働けなくなった場合、健康保険から「傷病手当金」が支給される(最長1年6ヶ月)。支給額は、おおむね手取り月収の約2/3が目安である。しかし、これは「元の収入が満額保障されるわけではない」ことを意味する。住宅ローンや子どもの教育費の支払いがある中で、収入が2/3(あるいはそれ以下)になれば、家計が途端に苦しくなるケースは多い。
- 自営業・フリーランスの場合:国民健康保険には、基本的に「傷病手当金」の制度がない(一部組合国保などを除く)。つまり、働けなくなれば、即、収入がゼロになるリスクと隣り合わせである。
がん保険の見直しにおいては、単に「医療費がいくらかかるか」だけでなく、「治療のために働けなくなった場合、最低限の生活を維持するためにいくら必要か」という視点が不可欠である。
目安として一つの考え方は、「治療費の実費負担分 + 半年〜1年分の生活防衛資金(または収入減少分)」をカバーできるだけの診断給付金(一時金)を備えておく、ということが一つのフレームとなる。
古いがん保険を放置するリスクとメリット
ここまで読むと、「古い保険はダメで、新しい保険にすぐ乗り換えるべきだ」と感じるかもしれないが、それは早計である。見直しの本質は、「古い=即解約」ではなく、「内容を正しく把握し、残す価値と補強すべき点を見極める」ことにある。
◆古い契約を放置するリスク
まず、放置するリスクを再確認したい。
- 先進医療、通院治療、新しい抗がん剤治療など、現代の標準的な治療に対する保障が一切付いていない可能性がある。
- 再発・転移した場合の保障が手薄い、あるいは初回のみで終了してしまう。
- 治療で働けなくなった際の収入減(就労不能)に対する保障がない。
- 「上皮内新生物(ごく初期のがん)」が保障の対象外であったり、給付金が大幅に減額されたりする設計になっているかもしれない。
◆“古いがん保険”ならではのメリット
一方で、古い契約には、現在の保険商品にはない“お宝”的な有利な条件が付いている場合もある。
- 上皮内新生物への手厚い保障: 現在の保険では、上皮内新生物(ステージ0のがん)の場合、診断給付金が減額(例:悪性新生物の50%や10%)される商品も多い。しかし、昔の一部の商品には、上皮内新生物でも悪性のがんと同額(100%)の診断給付金を支払うものが存在する。
- 割安な保険料: 若い頃に「終身保障(保障が一生涯続く)」タイプで加入した場合、その保険料は加入時の年齢で固定されている。現在の年齢で新しく終身保険に入り直すよりも、保険料がかなり割安になっているケースがある。
◆重要なのは「棚卸し → 判断」
したがって、取るべき行動は「解約」ではなく、まず「棚卸し」である。
- 保障内容を洗い出す:保険証券を引っ張り出し、「いつ(診断、入院、通院、手術)」「何を(悪性、上皮内)」「いくら(一時金、日額)」もらえるのかを正確に把握する。
- 現在の治療・生活とのギャップを確認:「通院保障はあるか?」「先進医療はカバーされるか?」「上皮内新生物の扱いはどうなっているか?」「診断一時金は生活費を含めて十分か?」を自問する。
- 仕分けする:そのうえで、「残すべき有利な部分」「特約などで補強すべき足りない部分」「重複していて やめてもよい部分」を仕分けする。
この「棚卸しと判断」のプロセスこそが、がん保険見直しの核心である。
がん保険を見直すタイミングはいつ?ライフイベント別の判断基準
では、具体的にいつ、その「棚卸し」を実行すべきか。見直しにはいくつかの適切なタイミングが存在する。
長期間見直しをしていない場合
最も分かりやすい目安が「期間」である。
◆“10年前のがん保険”はほぼ別物
前章で述べた通り、がん治療の技術や薬剤は日進月歩で進化している。それに伴い、がん保険の商品内容も5年、10年単位で大きく見直されている。
保険ショップや保険会社の多くが、「加入から10年以上経過したら、一度は見直しを」というスタンスを取っているのはこのためである。10年前には一般的でなかった保障(通院治療給付金、再発時の一時金、先進医療特約など)が、今や標準装備となっているからだ。
また、がんの定義、特に「上皮内新生物」の取り扱いも、商品によって細かく変わってきている。
◆「5年ごと」を目安に
この記事では、以下のようなガイドラインを推奨したい。
- 5年以上見直していない:保障内容が現状とズレ始めている可能性がある。まずは保険証券の内容を確認する「棚卸し」を推奨する。
- 10年以上見直していない:高い確率で、現在の医療実態と保障内容に大きなギャップが生じている可能性がある。専門家(保険代理店やファイナンシャルプランナー)への相談も含め、積極的な見直しを検討すべき時期である。
ライフステージが大きく変化した場合
保険は、その時々の「生活」を守るためのものである。したがって、生活の基盤が大きく変わる「ライフイベント」の発生時は、保障内容を見直す絶好の機会である。
| ライフイベント | 見直しの視点・必要な保障 |
| 就職・独立 | 自分の収入で生活が成り立つ最低限の保障(特に自営業は手厚く)。 |
| 結婚・出産 | 家族の生活を守るため、診断給付金(一時金)の増額を検討。 |
| 住宅購入 | 治療中の「住宅ローン返済」も考慮し、収入減に備える保障を手厚くする。 |
| 子どもの独立 | 教育費の負担が終了。保障をスリム化し、保険料負担を軽減する好機。 |
| 定年退職 | 収入減に対応し保険料負担を抑えつつ、高齢化のがんリスクに備え終身保障は維持。 |
◆代表的なライフイベント
- 就職・転職・独立(起業)
- 結婚
- 妊娠・出産(家族が増える)
- 住宅購入(住宅ローンを組む)
- 子どもの独立
- 定年退職
◆イベント別の見直しの視点
- 結婚・出産:守るべき家族が増えるため、必要な保障額は大きくなる。特に、世帯収入に占める自分の収入の割合が高い(共働きなど)場合、自分ががんで休職・離職した際の「収入減」に備える必要性が高まる。診断給付金(一時金)の増額や、就労不能保障の検討が必要となる。
- 住宅購入後にがんと診断され、ローン返済+生活費+教育費をカバーするためには、診断給付金として300〜500万円の保障が目安。必要に応じて通院保障や先進医療特約も追加すると安心。「住宅ローン返済+教育費+生活費」を、治療を受けながらでも維持できるか?という視点で、診断給付金の額を見直す必要がある。
- 転職・独立:会社員から自営業・フリーランスになった場合、傷病手当金というセーフティネットがなくなる(国民健康保険の場合)。休んだ分だけ収入が途絶えるため、会社員時代よりも手厚い「収入保障」や「診断給付金」が求められる。
- 子どもの独立・定年退職:子どもが独立すれば、高額な教育費の負担は一段落する。一方で、定年退職を迎えれば現役時代ほどの収入はなくなる。この時期は、「保障額をスリムにし、保険料負担を軽減する」という視点での見直しが中心となる。ただし、がんの罹患リスクそのものは年齢とともに高まるため、必要な終身保障(入院、先進医療など)は最低限残しつつ、過剰な保障を整理していくバランス感覚が重要である。
独身時代に加入した保障額のまま、家族が増え、ローンを抱えた現在も変更していない、という方は特に注意が必要である。
定期型がん保険の更新時期
| 選択肢 | メリット | デメリット・注意点 |
| 1. そのまま更新 | ・健康状態の告知なしで保障を継続できる。 | ・保険料が大幅に上がる。 ・保障内容は古いまま。 |
| 2. 保障を減らして更新 | ・保険料の上昇を抑えられる。 | ・必要な保障まで削ってしまうリスク。 |
| 3. 終身型に切り替え | ・保険料が一生涯上がらなくなる。 | ・その時点の年齢で再計算されるため、月々の保険料は高くなる。 |
| 4. 他社の保険に乗り換え | ・現代に合った新しい保障を選べる。 | ・健康状態の告知が必要。 ・免責期間(90日)が発生する。 |
加入している がん保険が「定期型」の場合、更新時期は“強制的”な見直しのタイミングとなる。
◆定期型がん保険の仕組み
定期型とは、保障期間が5年や10年など一定期間で区切られている保険のことである。このタイプは、契約を「更新」することで保障を継続できるが、その際には以下のルールが適用される。
更新のたびに、“その時点の年齢”で保険料が再計算される。
年齢が上がれば、がんになるリスクも高まるため、同じ保障内容であっても、更新後の保険料は必ず(多くの場合、大幅に)上昇する。
◆更新時に検討すべき選択肢
保険会社から更新の案内が届いたとき、「どうせ必要だから」と自動更新に任せてしまうのは最も避けるべき対応である。その高くなった保険料を、本当に払い続ける価値があるのかを吟味する必要がある。
検討すべき選択肢は、主に以下の4つである。
| 選択肢 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| そのまま更新 | 健康告知なしで継続可能 | 保険料が上昇、保障内容は古いまま |
| 保障を減らして更新 | 保険料を抑えられる | 必要保障まで減らすリスク |
| 終身型に切り替え | 一生涯保険料固定 | 年齢により保険料高め |
| 他社新商品に乗り換え | 現代治療に合った保障 | 健康告知・免責期間あり |
- そのまま更新する:保険料は上がるが、健康状態に不安があり、新しい保険に入れない可能性がある場合に選択する。
- 保障を減らして(減額して)更新する:保険料の上昇を抑えるために、入院日額を減らす、不要な特約を外す、といった調整を行う。
- 終身型のがん保険に切り替える:この先の保険料上昇を避け、一生涯の保障を確保するために、保険料が変わらない終身型に加入し直す。
- 他社の新しいがん保険へ乗り換える:より現代の治療に合った、コストパフォーマンスの良い他社商品を探す。
定期型の更新案内は、現在の保険料負担と保障内容のバランスを再評価する絶好の機会と捉えるべきである。
がん保険見直しのメリット
見直しには手間がかかるが、それを上回る大きなメリットが存在する。主なメリットは「保障の最適化」と「保険料の適正化」である。
現代の治療環境に合った保障に更新できる
最大のメリットは、前述した「医療と保険のギャップ」を埋められることである。
◆現代型がん保険の主な保障
| 保障の種類 | 保障の役割・メリット |
| 診断給付金(一時金) | ・最も重要。がんと診断されたらまとまった金額がもらえる。 ・使途自由(治療費、生活費、諸雑費、収入減の補填に)。 |
| 治療給付金 | ・「通院」での抗がん剤・放射線治療などを「月ごと」に保障。 ・長期化する通院治療に対応できる。 |
| 先進医療特約 | ・全額自己負担となる先進医療の「技術料」(数百万円)を実費でカバー。 |
| 複数回診断給付金 | ・「再発」や「転移」の際も、2回目以降の一時金が受け取れる(※条件あり) |
近年の がん保険は、入院給付金中心の設計から、以下のような保障を組み合わせる形が主流となっている。
- 診断給付金(一時金):がんと診断確定された時点で、まとまったお金(50万、100万、200万など)が支払われる。使途が自由なため、治療費だけでなく生活費や諸雑費にも充当できる。
- 治療給付金(抗がん剤・放射線・ホルモン療法など):入院の有無にかかわらず、通院での薬物療法や放射線治療など、所定の治療を受けた「月ごと」に定額(10万円など)が支払われる。
- 通院給付金:がん治療のための通院日数に応じて支払われる。入院の有無を問わないタイプが増えている。
- 先進医療給付金(特約):全額自己負担となる先進医療の技術料を実費で保障する(上限2,000万円程度が一般的)。
- 再発・転移時の複数回診断給付金:最初の がんだけでなく、再発や転移、あるいは2回目以降の新たながんが見つかった場合でも、診断給付金が(多くは2年に1回などの条件付きで)複数回支払われる。
◆見直しによる具体的なメリット
古い保険から新しい保険へ見直す(または特約を付加する)ことにより、以下のような恩恵が期待できる。
- 通院治療に強くなる:入院日数が短くても、その後の長期にわたる通院での抗がん剤治療や放射線治療に対し、「治療給付金」や「通院給付金」で対応できるようになる。
- 高額治療の選択肢が広がる:「先進医療特約」を付加することで、いざという時に「お金がないから先進医療を諦める」という事態を避け、最善の治療を選択しやすくなる。
- まとまった資金を確保できる:「診断給付金」を手厚くすることで、治療初期にかかる費用や、治療中の収入減をカバーする当面の生活費を確保できる安心感が得られる。
現在の年齢や家族構成に見合った保障に調整可能
第二のメリットは、加入時から変化した「今の自分」に合わせて、保障内容をカスタマイズできる点である。
◆年代別の必要保障イメージ
- 20代〜30代(独身・DINKS):貯蓄がまだ十分でないケースが多い。がんによる休職が即、生活苦につながるリスクがある。保険料負担は抑えつつ、診断給付金(一時金)は手厚めに確保したい。
- 40代〜50代(子育て・ローン返済期):教育費や住宅ローンの負担が最も重い時期。世帯主が長期離脱すると家計破綻のリスクすらある。診断給付金に加え、長期治療に備えた通院・治療給付金のバランスが重要になる。
- 60代以降(リタイア期):収入が年金中心になる一方、がん罹患リスクは最も高まる。高額な保険料は払えないが、治療費で貯蓄を大きく目減りさせたくない時期。「保険料」と「最低限必要な保障(入院・先進医療など)」のバランスをシビアに判断する必要がある。
◆他の保険とのバランス調整
見直しは、他の保険との重複を整理する機会でもある。
例えば、手厚い「医療保険」に別途加入しており、入院や手術の保障はすでに十分だと判断できる場合。その場合、がん保険の方はあえて入院給付金を外し(あるいは減額し)、その分、「診断給付金」「通院・治療給付金」「先進医療特約」に重点を置く、といった戦略的な組み替えが可能になる。
場合によっては保険料負担を軽減できる
「見直すと、年齢が上がっているから保険料も高くなるのでは?」と不安に思うかもしれない。確かに保障を手厚くすれば保険料は上がるが、見直しの結果、逆に保険料負担が下がるケースもある。
◆保険料が下がるケースの例
- 保障の重複を整理した場合:「古いがん保険」+「医療保険のがん特約」+「別の医療保険」など、複数の契約で保障内容がダブっていることがある。これらを整理・統合し、自分に必要な保障だけをシンプルながん保険に集約することで、トータルの保険料が下がる場合がある。
- 貯蓄性のある商品から掛け捨て型へ切り替えた場合:古い保険の中には、死亡保障や満期金などがセットになった「貯蓄性」のある商品がある。これらは保険料が割高である。もし「貯蓄は貯蓄、保障は保障」と割り切るのであれば、保障機能に特化した安価な「掛け捨て型」のがん保険に切り替えることで、月々の保険料は大幅に下げられる可能性がある。
- 不要な特約を外した場合:がん治療とは直接関係のない特約(死亡保障、ケガの保障など)が、主契約のがん保険に付加されたままになっているケース。これらを解約し、がんに特化した保障に絞り込むことでも保険料は下がる。
ただし、見直しは「保険料を下げること」が第一目的ではない。あくまで「現在の自分にとって、過不足のない保障を、納得できる保険料で準備すること」がゴールである。年齢が上がれば、同じ保障でも新規契約の保険料は高くなるのが一般的であるため、「必ず安くなる」わけではない点は留意が必要である。
がん保険見直しのリスク・デメリット
見直しはメリットばかりではない。実行する前に知っておくべきリスクやデメリットも存在する。これらを理解せず進めると、「見直さなければよかった」という後悔につながりかねない。
保険料が上がる可能性がある
最も分かりやすいデメリットである。見直しによって保険料が上がる主な要因は2つある。
- 年齢による保険料上昇:がん保険の保険料は、加入時の年齢(と性別)で決まる。当然、年齢が上がるほど がん罹患リスクが高まるため、保険料も上昇する。例えば、30歳の時に加入した保険を解約し、50歳で同じ保障内容の保険に新規加入しようとすれば、保険料は格段に高くなる。
- 保障を手厚くすることによる上昇:古い保険にはなかった「先進医療特約」「抗がん剤治療特約」「複数回診断給付金」などを新たに追加すれば、その分だけ保険料は上乗せされる。
見直しとは、「現在の保険料」と「将来の安心(保障)」を天秤にかける作業でもある。「家計が許容できる保険料はいくらまでか」「その予算内で、どの保障を優先するか(一時金か、通院か、先進医療か)」という優先順位付けが不可欠となる。
健康状態によって新規加入できない場合がある
これが最大のリスクと言える。保険は「健康な人」が入れる商品である。
◆新規加入には“告知・審査”がある
新しい保険に加入(乗り換え)したり、特約を中途付加したりする際には、必ず現在の健康状態を保険会社に申告する「告知」が必要となる。
この告知内容(過去の病歴、現在の通院・服薬状況、健康診断での異常指摘など)に基づき、保険会社は審査を行う。その結果、
- 加入不可(謝絶): 新しい保険に一切入れない。
- 条件付き加入(特定部位不担保など):「胃のポリープで経過観察中」なら、「胃に関する保障は一定期間行いません(不担保)」といった条件付きで、ようやく加入が認められる。
◆過去にがんを経験している場合
もし過去(多くは5年以内)にがんを経験している場合、通常のがん保険や医療保険への新規加入は極めて難しくなる。
その場合の選択肢は、告知項目が簡素化された「引受基準緩和型」のがん保険・医療保険となるが、これらには以下のようなデメリットが伴う。
- 保険料が、通常の商品よりかなり割高に設定されている。
- 加入から一定期間(1年など)は、給付金が半額に削減されるなどの制限が付く。
見直しは、「健康なうち」だからこそ、多くの選択肢の中から有利なものを選べるという側面がある。健康状態に不安が出てからでは、選べる商品が限られたり、そもそも見直し自体ができなくなったりするリスクがあるのだ。
新旧契約の免責期間による保障空白に注意
がん保険には、他の医療保険などにはない特有のルールがある。それが「免責期間(待ち期間)」である。
◆がん保険の免責期間とは
多くのがん保険では、契約(責任開始日)から90日間(商品によっては3ヶ月)を免責期間と定めている。
この90日間の間に がんと診断確定された場合、保険金・給付金は一切支払われない。これは、「がんの自覚症状がある人が、慌てて保険に加入する」といった事態を防ぐためのルールである。
◆乗り換え時に起こりうる“保障の空白”
このルールを知らずに乗り換えを行うと、最悪の事態を招く可能性がある。
| 時系列 | やってはいけない行動 | 発生する事態 |
| 1日目 | 古い保険を解約 | この時点で保障がゼロになる |
| 同日 | 新しい保険に加入 | 新しい保険の「免責期間(90日)」がスタート |
| 30日目 | がんが発見・診断される | ・古い保険 → 解約済みで保障なし ・新しい保険 → 免責期間中のため保障なし |
| 結果 | どちらからも給付金が1円も支払われない |
悪い例:
- 古い がん保険を解約する。(この時点で保障がゼロになる)
- 同時に、新しい がん保険に加入する。
- 新しい保険には90日間の免責期間がある。
- もし、この90日の間に がんと診断されたら…?→ 古い保険は解約済み、新しい保険は免責期間中のため、どちらの保険からも1円も給付されない「保障の空白」状態に陥ってしまう。
◆推奨される対処法
このようなリスクを避けるため、がん保険の乗り換え(解約・新規加入)は、以下の手順を厳守すべきである。
- 古い保険は解約せず、まず新しい保険の申し込みと告知を行う。
- 新しい保険の審査が通り、契約が成立(責任が開始)する。
- 新しい保険の免責期間(90日間)が終了し、保障が確実にスタートしたことを確認する。
- この時点で初めて、古い保険を解約する。
一時的に保険料が二重払いになる期間が発生するが、「保障の空白」を作らないためには、この「二重加入期間をあえて作る」という手順が最も安全である。
がん保険見直しのポイント・比較
実際に見直しを行う際、具体的にどの部分を比較・検討すればよいのか。重要なポイントを整理する。
必要保障額と保障期間の検討
まずは「いくらの保障が」「いつまで必要か」という大枠を決める必要がある。
◆必要保障額の考え方
感覚で「一時金100万円くらい?」と決めるのではなく、以下のステップで逆算することが望ましい。
- 当面の生活費(収入減少の補填):もし がん治療で働けなくなった場合、毎月の生活費(ローン、教育費、食費など)に対して、公的給付(傷病手当金など)や家族の収入で「いくら不足するか」を計算する。
- カバーしたい期間:その不足額を、何か月分(例:半年〜1年分)保険でカバーしたいかを決める。(例:月15万円不足 × 12ヶ月 = 180万円)
- 治療費の自己負担・諸雑費:先進医療や差額ベッド代、ウィッグ代、交通費など、公的保険で賄えない費用の目安を加算する。(例:先進医療を除いても50万〜100万円程度は見ておきたい)
【計算例】
(生活費不足 180万円) + (諸雑費 70万円) = 合計 250万円
この場合、まず「診断給付金(一時金)として200万〜300万円」を確保し、それに加えて「通院治療給付金(月10万円)」や「先進医療特約(実費)」を上乗せする、といった設計イメージが湧いてくる。
◆保障期間の検討
保障がいつまで続くかも重要な選択である。
- 終身型:保障が一生涯続くタイプ。加入時の保険料は変わらないが、定期型に比べると保険料は高め。高齢になってからの がんにも備えたい人向け。
- 定期型:保障期間が10年や20年、あるいは60歳まで、と区切られているタイプ。その期間内は保険料が割安。子どもが独立するまでの間だけ手厚くしたい、など、必要な期間を絞って安く備えたい人向け。ただし、更新すると保険料が上がる点に注意が必要。
給付金の種類と受取条件の確認
「何がどうなったら、いくらもらえるのか」という給付条件は、商品ごとに細かく異なるため、徹底的に比較する必要がある。
◆代表的な給付金の種類と役割
- 診断給付金(一時金):「がんと診断確定された時」に支払われる。使途が自由で、治療費・生活費のどちらにも充てられる、がん保険の核となる保障。
- 入院給付金:がん治療目的で入院した日数に応じて支払われる。最近のがん保険では、入院日数の制限がない(無制限)商品が一般的である。
- 通院給付金:がん治療のための通院日数に応じて支払われる。
- 手術給付金・治療給付金:所定の手術や、抗がん剤・放射線・ホルモン剤治療など、特定の治療を受けたことに対して支払われる。
- 先進医療給付金:先進医療の技術料を実費(上限あり)でカバーする。
◆受取条件で比較すべきポイント
特に以下の点は、保険選びの際に差が出やすいポイントである。
- 診断給付金(一時金):
- 上皮内新生物の扱い: 悪性新生物と同額か、減額(50%や10%)か、対象外か。
- 支払回数: 1回のみか、複数回(2年に1回、1年に1回など)支払われるか。複数回の場合、再発・転移も対象か、それとも「新たな がん」でないとダメか。
- 通院給付金:
- 支払条件: 「入院後の通院」のみが対象か、「入院の有無にかかわらず外来治療」でも対象か。
- 支払限度: 1回の入院(または診断)につき何日まで、通算で何日まで、といった制限。
- 治療給付金(抗がん剤治療など):
- 支払われ方: 治療1回ごと(例:点滴1回につき)か、治療を受けた「月ごと」(例:月に1回でも受ければ10万円)か。
- 対象となる治療: 抗がん剤(飲み薬も含むか)、放射線、ホルモン剤など、対象範囲がどこまで広いか。
先進医療や上皮内新生物への保障範囲確認
細かい点に見えるが、この2つは見直しにおいて絶対に確認すべき重要項目である。
◆先進医療特約の重要性
前述の通り、先進医療の技術料は公的医療保険の対象外で、全額自己負担となる。重粒子線治療で技術料300万円超の例があること(先進医療として受けた場合)を具体例として紹介する。
これに備える「先進医療特約」は、技術料を実費で(上限2,000万円程度まで)保障してくれるにもかかわらず、保険料は月額で数百円程度と、非常にコストパフォーマンスが高い特約である。
古い保険にこの特約が付いていない場合、見直し(または中途付加)を検討する最大の動機の一つとなる。
◆上皮内新生物(上皮内がん)の扱い
上皮内新生物とは、がん細胞が臓器の表面(上皮)にとどまっており、奥深く(基底膜)まで浸潤していない、ごく初期の がん(ステージ0)を指す。転移の可能性は極めて低いとされる。
この上皮内新生物に対する保障の扱いは、保険商品によって大きく3パターンに分かれる。
- 悪性がんと同額保障:悪性新生物でも上皮内新生物でも、診断給付金を満額(100%)支払う。
- 一部保障(減額):上皮内新生物の場合は、診断給付金が減額される(例:50%、10%)。
- 対象外:上皮内新生物は保障の対象外となる。
医学の進歩により、上皮内新生物の段階で発見されるケースも増えている。自分の保険がどのタイプかは必ず確認すべきである。
皮肉なことに、この点においては「古い保険」の方が、上皮内新生物を悪性がんと区別せず「同額保障」する有利な条件になっている場合がある。その場合は、無理に新しい保険に乗り換えず、古い契約を維持したまま、不足する「先進医療」や「通院」を別の保険や特約で補う、という戦略が賢明となる。
がん保険見直しの方法
保障内容の「棚卸し」と「比較検討」を終えたら、いよいよ具体的な見直しの実行に移る。方法は一つではなく、主に4つの選択肢がある。
特約中途付加による保障の充実
最も手軽な方法が、現在の契約を維持したまま、不足している保障を「特約」として追加(中途付加)することである。
◆中途付加できる代表的な特約例
- 先進医療特約
- 抗がん剤治療特約/がん治療給付金特約
- 通院特約
- 女性特有のがん(乳がん、子宮がんなど)への保障を手厚くする特約
◆メリットと注意点
- メリット:現在の契約の有利な条件(例:上皮内新生物への同額給付、加入時年齢の安い保険料)をそのまま維持しつつ、「足りない部分だけ」をピンポイントで補強できる。
- 注意点:
- 保険会社や商品によって、中途付加できる特約は限られている。
- 特約の追加であっても、現在の健康状態の告知が必要な場合が多く、健康状態によっては付加できないこともある。
- 追加した特約の分の保険料が上乗せされる。
- 追加した特約部分にのみ、免責期間(待ち期間)が設定される場合があるため確認が必要。
一部解約・減額による保険料の抑制
これは、保障を「足す」のではなく、過剰な部分を「減らす」ことで、保険料負担を適正化する方法である。
◆一部解約・減額とは
例えば、「診断給付金300万円」で契約している終身がん保険の保険料負担が重い場合、これを「150万円」に減額し、その分、月々の保険料を安くする、といった調整である。
◆メリットとデメリット
- メリット:
- 全解約するわけではないため、有利な条件(例:上皮内同額給付)を維持したまま、保険料負担だけをコントロールできる。
- 「保障は少し減ってもいいから、とにかく保険料を下げたい」という定年後などのニーズに対応しやすい。
- デメリット:
- 当然ながら、減額した分の保障は失われる。
- 貯蓄性のある保険の場合、減額に伴い解約返戻金も減少する可能性がある。
- 一度減額した保障を、後から「やっぱり元に戻したい」と思っても、原則として元に戻すことは難しい(新規契約扱いとなる)。
他社のがん保険への乗り換え検討
現在の契約をすべて解約し、全く新しい別の保険商品(多くは他社のもの)に加入し直す、最も抜本的な見直し方法である。
◆乗り換えを検討するきっかけ
- 定期型の更新で、保険料が許容範囲を超えて大幅にアップする。
- 現在の保険では、どうしても通院治療や先進医療などの新しい保障を組み込めない。
- 複数の保険会社に契約が分散しており、保障内容が複雑になっているため、一つに整理・集約したい。
◆比較する際のチェックポイント
乗り換えはメリットも大きいが、前述の「デメリット(保険料上昇、告知、免責期間)」も伴うため、慎重な比較が求められる。
- 保険料と保障内容のバランス:新しい保険の保険料はいくらになり、それでどのような保障(診断給付金、通院、先進医療など)が得られるか。
- 上皮内新生物の扱い:現在の契約より不利(例:同額→減額)になっていないか。
- 診断給付金の支払回数・間隔:1回のみか、複数回か。
- 免責期間(待ち期間):90日間で間違いないか。
- 解約返戻金の有無:現在の契約が貯蓄性の場合、今解約すると解約返戻金がいくら戻るか(損益の確認)。
◆最大の注意点
繰り返しになるが、「新しい保険の契約が成立し、かつ免責期間(90日)が終了するのを確認してから、古い保険を解約する」という順序を絶対に守ることである。
2つ目のがん保険に追加加入
「解約」でも「乗り換え」でもなく、「上乗せ」するという選択肢である。
◆複数加入の特徴
がん保険は、治療費の実費を補填する「実損払い」ではなく、診断や入院といった事実に該当すれば定額が支払われる「給付金型」である。
そのため、仮にA社とB社の2つのがん保険に加入していれば、がんと診断された場合、A社からもB社からも(他社の保険金額を差し引かれることなく)診断給付金を受け取ることができる。
◆2つ目加入が向いているケース
この特徴を活かし、現在の契約の“弱点”を補うためだけに、2つ目のサブのがん保険に加入する方法がある。
- ケース1:古い契約の条件(上皮内同額給付、安い保険料)が非常に良いため、解約したくない。しかし、通院保障と先進医療特約だけが足りない。→ 古い契約はそのまま維持し、不足分(通院・先進医療)だけを保障する安価な2つ目の がん保険に追加加入する。
- ケース2:加入時年齢が若く保険料が安い終身契約(診断一時金100万円)をベースに持っている。子どもの教育費がピークを迎える今後10〜20年間だけ、一時金を上乗せしたい。→ ベースの終身は維持しつつ、10年定期の「診断一時金100万円」のがん保険に追加加入し、リスクの高い時期だけ保障を200万円に倍増させる。
◆注意点
もちろん、2つ加入すれば保険料負担は増える。医療保険とがん保険、あるいは がん保険同士で保障内容が過剰に重複し、家計を圧迫しては本末転倒である。「総額でいくら保険料を払うのか」「それに見合った保障額か」というバランス感覚が常に求められる。
がん保険の見直しに関するよくある質問(FAQ)
最後に、がん保険の見直しに関して寄せられがちな疑問について、Q&A形式で回答する。
古いがん保険を見直さず放置するとどうなりますか?
A. 今すぐ生活に困るわけではないが、「いざ がんになった時、期待した保障が受けられない」リスクが非常に高くなる。
医療技術や治療スタイルは変化しており、古い保険では「通院での抗がん剤治療」や「先進医療」に対応できず、給付金がほとんど支払われない可能性があるためだ。
また、上皮内新生物(ごく初期のがん)や、再発・長期治療に対する保障が不十分なままになっているケースも多い。
一方で、古い契約にしかない有利な条件(上皮内同額給付など)を知らずに放置している(あるいは安易に解約してしまう)リスクもある。どちらにせよ、まずは「内容の把握(棚卸し)」が不可欠である。
がん保険の見直しは何年ごとに行うのがベストですか?
A. 「◯年ごと」という明確な正解はないが、一般的に『ライフイベントの発生時 + 5年〜10年に一度』が目安とされている。
結婚、出産、住宅購入、転職、退職といった生活の節目は、必要な保障額が変わるため、必ず見直したいタイミングである。
それとは別に、加入から10年以上が経過している場合は、医療実態とのズレが生じている可能性が高いため、一度は専門家に相談するなどして保障内容を点検することを強く推奨する。
見直しの際、解約返戻金は受け取れるのでしょうか?
A. 「商品による」としか言えない。
現在のがん保険の多くは、保険料を安く抑えた「掛け捨て型」であり、このタイプは解約しても解約返戻金はないか、あってもごくわずかである。
一方で、古い契約の中には、死亡保障がセットになっていたり、貯蓄性を備えていたりする商品もあり、その場合は解約返戻金が受け取れる。
自分の契約がどちらのタイプか、もし返戻金があるなら今解約するといくらになるかは、保険証券を確認するか、保険会社に直接問い合わせて見積もり(試算)をもらう必要がある。
がん保険を乗り換える際の注意点には何がありますか?
A. 乗り換え(解約→新規加入)の際は、以下の点に特に注意が必要である。
- 健康状態(告知):現在の健康状態によっては、新しい保険に加入できない、または条件が付く可能性がある。
- 免責期間(保障の空白):新しい保険には約90日間の免責期間(待ち期間)がある。古い保険を先に解約すると、保障が一切ない期間が発生してしまうため、「新しい保険の免責期間終了後に、古いのを解約する」手順を守る必要がある。
- 保障内容の比較:上皮内新生物の扱いや先進医療の有無など、細かい条件が新旧でどう変わるか(不利になっていないか)を徹底的に比較する。
- 解約返戻金:現在の契約に解約返戻金がある場合、解約による損益も確認する。
過去にがんに罹った人でも保険を見直すことはできますか?
A. 非常に難しいが、選択肢はゼロではない。
残念ながら、過去にがんを経験している場合、通常のがん保険や医療保険への新規加入はほぼ不可能である。
しかし、がんの治療が終了してから一定期間(5年や10年など)が経過している場合や、がんの種類・ステージによっては、加入できる可能性が全くないわけではない(保険会社による)。
もし通常の商品が難しくても、
- 引受基準緩和型のがん保険/医療保険
- 無選択型医療保険(告知が不要なもの)
といった選択肢が残されている。ただし、これらは「保険料が割高」「加入後一定期間は保障が削減される」「特定の部位は保障されない」といった制約が付くことが一般的である。
古いがん保険をそのまま継続した方が良い場合もありますか?
A. 「ある」と明言できる。 “安易な解約はNG”である。
特に以下のようなケースでは、古い契約を維持するメリットが大きい。
- 上皮内新生物への保障が手厚い:悪性新生物と上皮内新生物を区別せず、同額(100%)の診断給付金が支払われる契約。
- 保険料が非常に割安:若い頃に加入した「終身型」の契約で、現在の年齢で入り直すよりも保険料が格段に安い場合。
こうした“お宝保険”の場合は、無理に解約・乗り換えをせず、その契約を保障のベース(土台)として維持しつつ、不足している「通院保障」や「先進医療特約」だけを、別の新しい保険(2つ目加入)や特約(中途付加)で補うという戦略が最も賢明である。
更新時に保障を減らせば保険料を抑えられますか?
A. 「抑えられる」が、注意も必要である。
10年更新などの定期型がん保険では、更新時に保険金額(例:診断給付金200万→100万)を減らしたり、不要な特約を外したり(減額・一部解約)することで、更新後の保険料上昇を抑える、あるいは下げることが可能である。
ただし、年齢が上がるほど がんの罹患リスクは高まる。そのリスクが高まる年代で保障を減らしすぎると、いざ というときに自己負担で苦しむことになりかねない。
「現在の家計状況」「他の保険(医療保険など)の保障内容」「貯蓄額」とを総合的に見て、どれだけの保障を残すべきかを判断する必要がある。
がん保険を乗り換えると新たに免責期間が発生しますか?
A. 「基本的には発生する」と考えるべきである。
がん保険特有の約90日間の免責期間(待ち期間)は、新規の契約ごとにリセットされて適用されるのが一般的である。
この期間中に診断された がんは給付対象外となるため、乗り換えの際は、古い保険の解約タイミングに細心の注意を払い、「保障の空白期間」を作らないことが鉄則である。
がん保険に2つ加入するのは賢明な選択でしょうか?
A. 「状況によっては合理的だが、保険料とのバランス次第」である。
がん保険は給付金型のため、2社から重複して給付金を受け取ることが可能である。
例えば、「古い契約の条件が良いので残したいが、保障が足りない」という場合に、不足分(先進医療や通院など)だけを2つ目の保険で補う、という使い方は非常に合理的である。
ただし、あれもこれもと保障を詰め込みすぎ、2つ(あるいは3つ)の保険料の総額が家計を圧迫してしまっては意味がない。「総額でいくらまで保険料を払えるか」という予算を決め、その中で「必要な保障額」をどう配分するかを冷静に判断することが重要である。