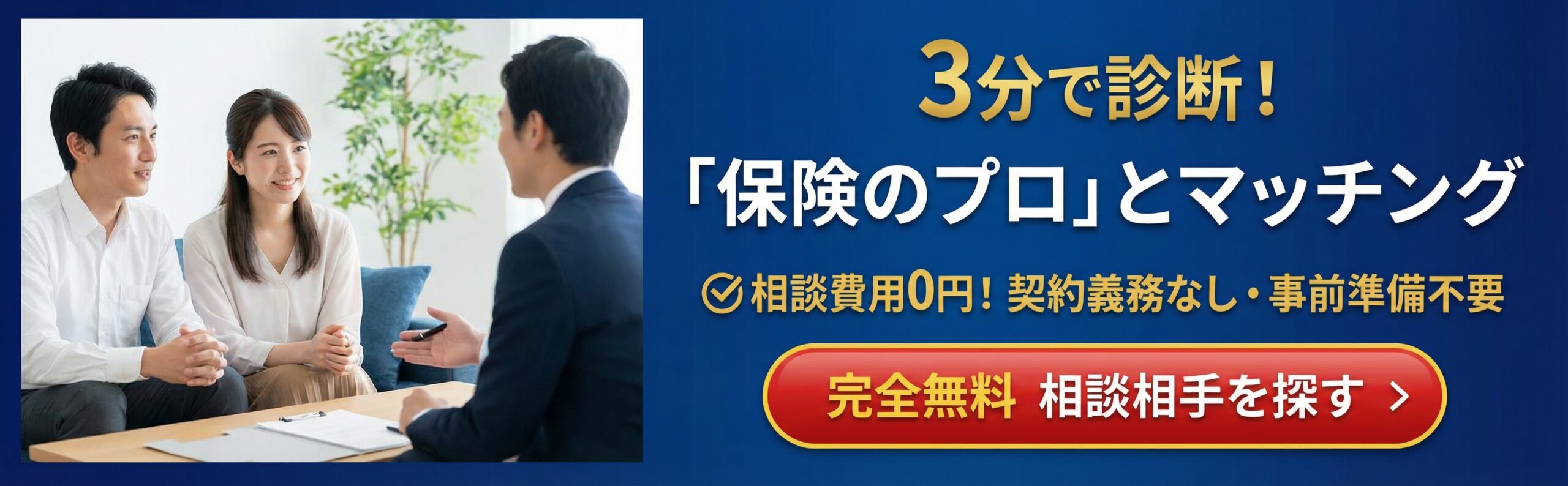「毎月の保険料が家計を圧迫しているけれど、解約すると損をしてしまう気がする」
「もっと返戻率の高い商品があるなら、乗り換えたほうがいいのだろうか」
学資保険を契約してから数年が経ち、このような悩みを抱えていないだろうか。
子供の成長や家計の変化に合わせて保険を見直すことは大切だが、学資保険に関しては「安易な乗り換え」が大きな損失につながるケースが少なくない。
一方で、今の契約内容を少し調整するだけで、受取率(返戻率)を高めたり、負担を軽くしたりできる場合もある。
重要なのは、今の契約を「やめる」か「続ける」かの二択ではなく、もっと柔軟な選択肢を知ることだ。
- 学資保険を今解約すると、どれくらい損をするのか目安がわかる
- 乗り換えのリスクと、そのまま続けたほうがよいケースが判断できる
- 特約の解除や払込方法の変更で、返戻率を上げる裏ワザがわかる
- 保険料が払えないときに、解約せずに保障を残す方法がわかる
学資保険見直しの目的と教育資金の考え方
まずは、学資保険を何のために見直すのか、その目的を整理しよう。
教育資金の準備は長期戦だ。
ゴールとなる「いつ」「いくら」必要かを確認することで、見直しの方向性が定まる。
学資保険で準備したい教育資金の目安
学資保険の最大の目的は、教育費の負担が最も大きくなる時期に現金を準備することである。
一般的に、大学入学時が費用のピークといわれている。
現在の大学費用の目安(4年間・入学金含む)は以下の通りだ。
| 進路の種類 | かかる費用の目安 |
| 国立大学 | 約243万円 |
| 公立大学 | 約254万円 |
| 私立大学(文系) | 約408万円 |
| 私立大学(理系) | 約551万円 |
※文部科学省等のデータを参考に概算。学部や生活費(仕送り)によってさらに変動する。
この金額すべてを学資保険だけで賄う必要はない。
「入学時の納付金として200万円〜300万円を確保したい」といったように、具体的な目標額を設定することが大切だ。
見直しの際は、現在の契約でこの目標額に届くのか、あるいは過剰すぎて保険料が負担になっていないかを確認しよう。
学資保険を見直すべき典型的なタイミング
ライフステージが変わるときは、お金の流れも変わる。
学資保険の見直しに適したタイミングは、主に以下の3つだ。
- 家計の収支が悪化したとき住宅購入や転職、あるいは物価高などで毎月の余裕資金が減った場合だ。無理をして払い続けて生活が破綻しては元も子もない。
- 子どもが成長して進路が見えてきたとき「私立中学受験をすることになった」「理系の大学を目指しそう」など、想定していたよりも教育費がかかりそうな場合や、逆に公立進学で余裕ができそうな場合である。
- まとまった資金が入ったときボーナスや相続などで手元資金が増えた場合、保険料を一括で支払う形に変更することで、返戻率を高められる可能性がある。
子どもの年齢と契約者の年齢が見直しに与える影響
学資保険は、契約者(親)と被保険者(子)の年齢によって条件が大きく変わる。
見直しを検討する際は、今の年齢が有利に働くか、不利に働くかを知っておく必要がある。
年齢による影響の目安
- 子どもの年齢が高い(小学生以上)積み立て期間が短くなるため、これから新しく入り直すと返戻率が低くなる傾向がある。また、加入できる商品自体が限られてくる。
- 契約者(親)の年齢が高い年齢が上がるほど死亡保障のリスクコストが上がるため、保険料が高くなりやすく、結果として返戻率が下がることが多い。
つまり、時間が経過すればするほど「良い条件での入り直し」は難しくなる。
乗り換えを検討するなら、一日でも早い判断が必要といえるだろう。
学資保険以外の教育資金の準備手段の位置づけ
かつては「教育費といえば学資保険」だったが、現在は選択肢が増えている。
それぞれの特徴を理解し、学資保険をどう位置づけるか考えることが重要だ。
- 学資保険【守り】強制的に貯蓄ができ、契約者に万一のことがあれば保険料が免除される。低リスク・低リターン。
- NISA(投資信託など)【攻め】運用成果次第で大きく増える可能性があるが、元本割れのリスクもある。使う時期が決まっている教育資金には注意が必要。
- 定期預金・国債【守り】元本保証で安全だが、金利が低くほとんど増えない。
学資保険は「できるだけ減らしたくない、最低限必要な教育資金」を確保するための土台として活用されることが多い商品だ。
ただし、商品によっては払込期間中の解約で元本割れする場合や、低解約返戻金型のように途中解約時の返戻率が低く設定されているタイプもある。
学資保険を検討する際は、元本割れの可能性や解約返戻金の推移も含めて約款・設計書を確認したうえで、「どこまでリスクを許容できるか」を踏まえて活用したい。
学資保険の乗り換えが損になりやすい理由
「今の保険より条件の良い新しい保険に乗り換えたい」
そう考えるのは自然だが、学資保険において乗り換えは基本的に「損をしやすい」アクションである。
なぜ損をしてしまうのか、その仕組みを詳しく解説する。
解約返戻金と元本割れの仕組み
学資保険を途中で解約すると、「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」が戻ってくる。
しかし、多くの場合、これまで支払った保険料の総額よりも少ない金額しか戻ってこない。
これを「元本割れ」という。
なぜ元本割れするのか
契約初期の保険料の多くは、保険会社の運営経費や、万一の際の死亡保障の備えに充てられているからだ。
積立金として貯まっていく部分は、契約から年数が経つにつれて徐々に増えていく。
特に加入から数年以内の短期で解約する場合、支払った額の5割〜7割程度しか戻らないことも珍しくない。
この「確定した損失」を取り戻すのは、新しい保険で多少返戻率が良くなったとしても容易ではないのだ。
新しい学資保険に加入できないリスク
乗り換えようとして今の保険を解約したあと、新しい保険に入れないというトラブルも起こり得る。
主な原因は健康状態だ。
学資保険の多くは、契約者(親)に「保険料払込免除特約(親が死亡・高度障害になったら保険料がタダになる機能)」がついている。
そのため、加入時には親の健康告知が必要となる。
- 過去に大きな病気をした
- 健康診断で指摘を受けた(高血圧、数値異常など)
こうした事情があると、新しい学資保険への加入を断られる可能性がある。
「解約したけれど次に入れない」という状態になれば、せっかくの保障も貯蓄機能も失ってしまう。
乗り換えても返戻率が改善しないケース
「昔に入った保険より、今の保険のほうが商品として優れているはず」と考えるのは誤解だ。
日本は長らく低金利政策が続いており、学資保険の予定利率(運用利回り)も低下傾向にある。
数年前に契約した学資保険のほうが、現在販売されている商品よりも「お宝保険(利率が良い保険)」である可能性が高い。
最新の商品パンフレットを見て「返戻率105%」と書かれていても、解約による損失を差し引いて計算すると、トータルではマイナスになるケースが大半である。
乗り換え判断で勘違いしやすいポイント
乗り換えの計算をするときに、よくある勘違いがある。
それは「これから払う保険料」と「将来受け取る満期金」だけを比較してしまうことだ。
正しい比較方法
- 今の保険を続けた場合の「将来の受取総額」
- 【今の保険の解約返戻金 + 新しい保険の満期金】の合計額
この2つを比べなければならない。
すでに支払ってしまった「過去のお金」を無視して計算すると、見かけ上は新しい保険が得に見えることがあるが、実際には解約損が大きく響いている。
冷静にシミュレーションすることが不可欠だ。
学資保険の解約リスクと元本割れの判断軸
それでは、どのような場合に解約や見直しを行うべきなのだろうか。
損をしてでも解約すべきか、踏みとどまるべきか、その判断基準を整理する。
途中解約で損失が大きくなるケース
以下のようなタイミングや条件での解約は、損失(元本割れ)が特に大きくなる。
- 加入して5年以内経費の控除割合が高く、ほとんどお金が戻ってこない可能性がある。
- 低解約返戻金型の商品保険料を安くする代わりに、払込期間中の解約返戻金を極端に低く抑えているタイプだ。これを途中で解約すると、支払額の7割程度しか戻らないこともある。
こうしたケースでは、解約は「最後の手段」と考え、他の方法(後述する「払済保険」など)を検討するのが賢明だ。
元本割れでも解約や乗り換えを急がない方がよい例
今の保険を続けるのが苦しいと感じても、もう少し我慢したほうが結果的に得をする場合がある。
- あと数年で払込期間が終わる場合ゴールが近い場合、ここから急激に返戻率が上がることがある。
- 契約日が古く、予定利率が高い場合昔の契約(特に2013年以前など)は、今ではありえない高い利回りがついていることがある。これは「金の卵」であり、手放すのは非常にもったいない。
保険証券を確認し、利率や契約日をチェックしてみよう。
解約を選ぶ前に整理したい家計と目的
「保険料が高いから解約したい」と思ったとき、一度立ち止まって家計全体を見てみよう。
- スマホ代やサブスクなど、固定費で削れるものはないか
- 使っていない車や、過剰な生命保険などはないか
学資保険は「将来の子供のための貯金」だ。
今の生活費のためにこれを崩すと、数年後の入学シーズンにさらに苦しい思いをすることになる。
他の節約で乗り切れるなら、学資保険は聖域として守ることを推奨する。
解約が合理的になりうる例外的なパターン
基本的には解約推奨ではないが、例外的に解約が正解になることもある。
- 「外貨建て」や「変額」の学資保険で、大きく利益が出ている場合為替の影響で円安が進み、解約返戻金が支払額を大幅に上回っているなら、利益確定(解約)して安全な円預金に移すのも戦略の一つだ。
- あきらかに不要な特約が大量についている場合医療特約などが手厚すぎて、貯蓄部分がほとんど増えていないような「元本割れ確定」のプランであれば、早めに損切りをして、NISAなどで運用し直すほうが合理的かもしれない。
学資保険の乗り換え前に返戻率を高める見直し方法
「今の保険を解約する」のではなく、「今の契約内容を変更する」ことで状況を改善できることがある。
これなら解約による大きな損失を避けつつ、返戻率をアップさせられるかもしれない。
特約を整理して返戻率を高める方法
学資保険には、子どもの医療保険や、親の入院保障などの「特約(オプション)」がついていることがある。
これらは安心材料だが、掛け捨ての保険料がかかるため、貯蓄性を下げる要因になる。
医療特約を外す際に確認したいポイント
医療特約を途中から「解約(外す)」ことができるか確認しよう。
特約部分の保険料がなくなれば、支払い総額が減り、結果として満期金に対する返戻率が向上する。
- 自治体の医療費助成を確認する多くの子育て世帯では、中学生や高校生まで医療費が無料・少額負担になる制度がある。公的な助成があるなら、民間の医療保険は不要かもしれない。
学資保険と医療保険を分ける場合の考え方
もし医療保障が必要だとしても、学資保険の特約ではなく、単体の「県民共済」や「コープ共済」などに加入したほうが安い場合がある。
月1,000円程度で十分な保障が得られることも多いので、学資保険は貯蓄専用にし、医療は別で入る「分離作戦」を検討してみよう。
保険料の払込方法を変えて返戻率を高める方法
支払いのサイクルを変えるだけでも、返戻率は変わる。
保険会社にとって、まとめて払ってもらうほうが運用効率が良いため、割引が適用されるからだ。
月払から年払い・一括払いに変更する際の注意点
「月払い」を「年払い(1年分まとめて)」に変更すると、一般的に1%程度保険料が安くなる。
資金に余裕があるなら、残りの期間分を全て払う「全期前納」などを検討してもよいだろう。
ただし、一度に大きな出費となるため、手元の生活防衛資金(緊急時の予備費)がなくならないよう注意が必要だ。
払込期間を短くしたときのメリットとデメリット
- 18歳払込満了 → 15歳払込満了に変更し、早く払い終える設定にすると、保険会社が運用できる期間が長くなるため、返戻率が上がることがある。
- デメリット払込期間が短くなる分、1回あたりの保険料負担は重くなる。家計に余裕がある場合の選択肢だ。
満期金や祝金の受取時期を調整する方法
受け取りのタイミングを後ろにずらすことで、受取額が増える商品もある。
進学時期に合わせた受取パターンの組み立て方
「高校入学時のお祝い金」を受け取らずに、そのまま積み立てておく(据え置く)ことができる商品がある。
据え置いている間は所定の利息がつくため、大学入学時まで待ってからまとめて受け取れば、総額が増える可能性がある。
返戻率と必要なタイミングのバランスを取る考え方
いくら増えるといっても、本当にお金が必要なときに引き出せなければ意味がない。
「入学金支払いの締切日」と「満期金の受取日」がズレていないか、早めに確認しておこう。
推薦入試などで秋口にお金が必要になるケースも増えている。
学資保険の保険料の支払いが苦しいときの見直し手段
「家計が苦しくて、今月の保険料が払えないかも……」
そんなときでも、すぐに解約ボタンを押すのは待ってほしい。
保障や契約を維持しながら、負担を軽くする救済措置がいくつか用意されている。
保障内容を見直して保険料を抑える方法
現在の契約を続けながら、ボリュームを小さくする方法だ。
学資金総額を減らすときの影響と目安
「満期金を300万円から200万円に減らす」という手続きを「減額(げんがく)」という。
減額した分だけ、毎月の保険料も安くなる。
減額された100万円分の契約は「解約」された扱いになり、その部分の解約返戻金が戻ってくることもある。
全て解約するよりは損失を抑えつつ、無理のない金額で継続できる。
払込免除特約などの見直しポイント
もし契約者(親)の収入が激減した理由が病気やケガによるものなら、「払込免除」の条件に該当していないか確認しよう。
所定の状態であれば、以後の保険料支払いが不要になり、満期金は満額受け取れる。
保険金額の減額や一部解約を活用する方法
一部だけをやめるテクニックについて、もう少し詳しく見ていく。
減額と一部解約の違いと向いているケース
- 減額将来の受取額を減らし、これからの保険料を下げること。継続前提の人に向いている。
- 一部解約特約部分だけを解約したり、積立金の一部を引き出したりすること。一時的な現金が必要な人に向いている。
どちらも「契約自体は残る」のが最大のメリットだ。
子どもの学齢ごとの減額判断の考え方
子どもが小さいうちは、これからの教育費が不透明なので、なるべく減額せずに頑張りたいところだ。
逆に高校生くらいになれば、必要な金額が見えてくる。「こんなに満期金がなくても大丈夫そう」と分かれば、減額して家計を楽にするのも合理的である。
家計全体を見直して無理のない保険料にする方法
保険料そのものだけでなく、支払い原資をどう確保するかという視点も大切だ。
他の保険・固定費の見直しとの優先順位
学資保険は「貯蓄」の性質が強いため、掛け捨ての生命保険や医療保険よりも優先して残すべき資産といえる。
見直すなら、まずはスマホ代、不要なサブスク、重複している他の保険から手をつけよう。
ボーナス払いや一時金を活用する場合の注意点
「月々の支払いを安くして、ボーナス払いを増やす」という変更も可能だ。
しかし、ボーナスは景気や業績でカットされるリスクがある。
ボーナス頼みの支払計画は、将来的に行き詰まる可能性が高いので、慎重に判断したい。
払済保険など乗り換え以外の選択肢の整理
保険料の支払いを完全にストップしたいけれど、解約して大損するのは避けたい。
そんなときに使える専門的な方法が「払済保険(はらいずみほけん)」と「契約者貸付(けいやくしゃかしつけ)」である。
払済保険に変更するメリットと注意点
「払済保険」とは、保険料の支払いを中止し、その時点での解約返戻金を元手に、保険期間を変えずに保障額を小さくして契約を続ける方法だ。
- メリット以後の保険料支払いが0円になる。契約は続くので、解約による大きな損失をある程度回避し、満期まで置くことで少し増える可能性もある。
- 注意点満期金は当初の予定より大幅に減る(例:300万→150万など)。また、特約(医療保障など)は消滅することが一般的だ。
払済保険に向くケースと向かないケース
「もうこれ以上1円も払えないが、子供が18歳になるまでお金を寝かせておける」という人には向いている。
逆に、「特約の医療保障は残したい」という人には向かない。
特約消滅や保障縮小のリスクへの備え方
払済保険にすると医療特約などが消えるため、子供の医療保障が空白になる。
自治体の助成制度を確認し、必要であれば安価な共済などに加入してカバーしよう。
契約者貸付制度を利用するときのポイント
一時的な資金不足のときは、まずご自身の保険に「契約者貸付制度」があるかを確認する方法も選択肢の一つだ。
契約者貸付は、一般的に解約返戻金の一定範囲(7〜9割程度)までを目安に借り入れでき、収入や信用情報に基づく通常のローン審査が不要なケースが多く、手続きが比較的スムーズである。
契約者貸付制度を使うべきケースと避けるべきケース
- 使うべき: 急な出費で一時的に現金が必要だが、数ヶ月以内に返済できる見込みがある場合。
- 避けるべき: 慢性的に生活費が足りない場合。借金が増えるだけで根本解決にならない。
利息負担と満期金への影響を試算する方法
ただし、契約者貸付の貸付利率は保険会社や商品によって異なり、銀行カードローン等のほうが低金利となる場合もある。
また、利息は複利で増えていき、返済しないまま放置すると満期金が大きく減ったり、解約返戻金を下回って契約が失効するおそれもある。
カードローン等を含め、各商品の金利・返済条件・保険契約への影響を比較し、無理のない返済計画のもとで借入手段を検討してほしい。
一部解約や減額で実質的に負担を軽くする方法
学資保険を残しながら不足分だけ解消する考え方
「100か0か」で考えず、柔軟に調整しよう。
例えば、「半分だけ払済保険にする(減額払済)」といった対応ができる保険会社もある。
担当者に「保険料を半額にしたいが、どのような方法があるか」と具体的に相談してみることをおすすめする。
金利や予定利率の変化を踏まえた見直し判断
経済状況の変化も、見直しの重要な判断材料だ。
特に「金利」の動きは、保険の魅力度に直結する。
予定利率が上がる局面で入り直しを検討する条件
世の中の金利が上がると、新しく発売される学資保険の「予定利率(利回り)」も上がる。
もし、数年後に金利が大幅に上昇した場合、今の低金利の契約を解約して、高金利の新しい保険に乗り換えたほうが有利になる可能性もゼロではない。
ただし、解約による元本割れのマイナスをカバーできるほどの大幅な金利上昇が必要なため、ハードルはかなり高いといえる。
預金・国債など他の手段との比較の視点
個人向け国債(変動10年)は、市場金利に連動して半年ごとに利率が見直されるため、金利上昇局面では利息も増えやすい商品だ。
固定金利の学資保険と比べると、一般的にはインフレ局面で利息が引き上げられやすい点で「インフレにある程度対応しやすい」側面がある。
一方で、物価上昇率を必ず上回るわけではなく、税金や途中換金のペナルティを考慮すると実質的にインフレに負ける可能性もある。インフレ対策として利用する際は、物価上昇率・税負担・運用期間なども含めたシミュレーションが必要だ。
インフレと教育費の上昇をどう見込むか
18年後に受け取る300万円が、今の300万円と同じ価値を持つとは限らない。
物価が上がれば、学費も値上がりする。
学資保険は金額が固定されているため、インフレには弱い商品だ。
インフレ対策として、一部をNISA(投資信託)などで運用し、資産を目減りさせない工夫も必要になってくるだろう。
税制優遇や教育資金贈与制度の活用可否
祖父母などから教育資金の一括贈与を受ける場合には、一定の要件を満たせば最大1,500万円まで贈与税が非課税となる「教育資金一括贈与の特例」を利用できる場合がある(現行制度では2026年3月31日までの時限措置。贈与者・受贈者の続柄や年齢、所得要件、対象となる支出の範囲等に注意が必要)。
こうした資金を原資に学資保険を一括払や全期前納で契約する方法もあるが、制度の期限や他の贈与制度との関係、贈与税・相続税への影響を税理士等と確認したうえで検討したい。
また、多くの学資保険は「一般生命保険料控除」の対象となり、年末調整や確定申告で所得税・住民税が軽減される可能性がある。
ただし、保険期間が5年未満の一部商品や、受取人の設定が一定の条件を満たさない契約などは控除対象外となる場合もあるため、具体的な控除可否や控除額については、生命保険料控除証明書および国税庁・保険会社の説明を必ず確認しよう。
学資保険の契約を変更・再加入するときの手順
いざ見直しを実行しようと決めたら、正しい手順で進めることが大切だ。
順番を間違えると、無保険期間ができたり、損をしたりする。
見直しに着手する前に整理しておきたい情報
手元に以下の書類を用意しよう。
- 現在の保険証券
- 年に一度届く「ご契約内容のお知らせ」
- 解約返戻金の試算表(ネットのマイページなどで確認可能)
現在の契約内容と解約返戻金の確認項目
特に「今解約したらいくら戻るか(解約返戻金額)」は正確な数字が必要だ。
電話やWebで保険会社に問い合わせて、最新の数字を確認しよう。
子どもの教育プランと必要資金の整理
「私立理系なら550万円」「自宅外通学なら仕送りがプラス400万円」など、目標額を再確認する。
今の保険で足りない分をどう補うか(新しい保険か、NISAか、預金か)を具体的にしよう。
新旧契約を比較するシミュレーション手順
感覚で決めず、数字で比較する。
旧契約の戻り額と新契約の受取総額の比較方法
計算式は以下の通りだ。
継続した場合
満期金 + お祝い金
乗り換えた場合
(今の解約返戻金 + 新しい保険の満期金) − 新しい保険の保険料総額
この2つを比べて、明らかに乗り換え側がプラスになるならGOサインだ。
総支払保険料と保障の差を可視化するポイント
金額だけでなく、保障内容(親の死亡時の免除特約の有無など)に差がないかも表にして比較しよう。
乗り換えや契約変更の進め方とスケジュール
解約の順番と新契約の申込タイミング
鉄則:新しい保険が成立してから、古い保険を解約する
基本的には、新しい保険契約が正式に成立したこと(保険証券の到着や承諾通知など)を確認してから、現在の学資保険の解約手続きを行うのが安全だ。
先に解約してしまうと、健康状態や告知内容によっては新しい保険に加入できず、教育資金の保障が一時的に途切れるおそれがある。
どうしても先に解約せざるを得ない事情がある場合は、そのリスクを十分理解したうえで、保険会社や専門家に相談した上で判断しよう。
健康状態・告知内容を踏まえたリスク管理
申し込みの際、健康状態を正直に告知しなければならない。
嘘をついて加入しても、いざというときに保険金が下りない「告知義務違反」になる。
少しでも不安がある場合は、加入前に保険会社や代理店に相談しよう。
学資保険見直しで起こりがちな失敗事例と注意点
先輩パパ・ママが陥りがちな失敗パターンを知っておけば、同じ轍を踏まずに済む。
解約を急いで再加入できず保障が空白になる失敗
「もっといい保険がある!」と意気込んで解約したものの、健康診断の結果が悪くて新しい保険に入れなかったケースだ。
再加入できないまま契約者に万一のことがあっても、教育資金は保障されない。これは最も避けるべき事態である。
元本割れ額を計算せず乗り換えて損をする失敗
新しい保険の返戻率(例えば105%)だけを見て、「今の保険(102%)よりいいじゃん!」と乗り換えるケースだ。
解約時に数万円〜数十万円の元本割れ損失が出ていることを忘れているため、トータルでは損をしている。
「サンクコスト(埋没費用)」を考慮した冷静な計算が必要だ。
返戻率だけ見て必要なタイミングに資金が足りなくなる失敗
返戻率を高くするために「22歳満期」の商品を選んだものの、実際には「18歳の大学入学時」に入学金や授業料が必要だった、というケースだ。
入学時に手元にお金がなければ、教育ローンを借りることになり、利息の支払いで保険の利益など吹き飛んでしまう。
払済保険や契約者貸付を使った後に後悔しやすいパターン
払済保険にして特約が消えた直後に子供が入院してしまったり、契約者貸付を放置して利息が膨らんだりするケースだ。
仕組みを十分に理解せずに利用すると、後で「こんなはずじゃなかった」となる。
FPや保険ショップとのコミュニケーションでよくある行き違い
相談員に「教育費を増やしたい」と伝えたら、学資保険ではなく「外貨建て終身保険」や「変額保険」を勧められ、リスクを理解せずに契約してしまうケースだ。
これらは学資保険とは全く別物(投資商品に近い)ですので、リスク許容度をしっかり伝える必要がある。
学資保険を専門家に相談するときの準備と相談先の選び方
自分だけで計算するのが難しい場合は、ファイナンシャルプランナー(FP)などの専門家を頼ろう。
ただし、相談先選びにもコツがある。
相談前に整理しておきたい数字と資料
手ぶらで相談に行っても、一般的な話しか聞けない。具体的なアドバイスをもらうために準備しよう。
保険証券・設計書・家計の収支表の準備
今の保険証券は必須だ。
さらに、ねんきん定期便や、住宅ローンの返済予定表、家計簿(月々の収支がわかるメモ)があると、家計全体の診断をしてもらえる。
教育資金以外のライフプランとの関係整理
「第2子を考えているか」「住宅購入の予定はあるか」「親の介護の可能性は」など、将来のイベントによって必要なお金は変わる。
ざっくりとした人生設計のメモを持参するとスムーズだ。
保険会社・保険ショップ・独立系FPの違い
- 保険会社(直販)自社の商品に詳しいが、他社比較はできない。
- 保険ショップ(乗り合い代理店)無料で相談でき、複数社の商品を比較できる。ただし、ショップが売りたい商品(手数料が高い商品)を勧められる可能性もゼロではない。
- 独立系FP(有料相談)相談料がかかるが、商品を売ることを目的としないため、中立的なアドバイスが期待できる。「保険に入らないほうがいい」という提案もしてくれる。
学資保険の乗り換え相談で確認したい質問リスト
相談時には以下の質問を投げかけてみてほしい。
- 「今の保険を解約して乗り換えた場合、解約損を取り戻すのに何年かかりますか」
- 「この提案商品は、学資保険ですか。それとも変額保険や外貨建てですか」
- 「元本割れのリスクは具体的にどのような状況で発生しますか」
オンライン相談や無料相談を上手に使うコツ
最近はZoomなどで気軽に相談できる。
一度の相談で即決せず、「一度持ち帰って検討します」と必ず伝えよう。
その提案書を持って、別のFPにセカンドオピニオンを求めるのも賢い方法だ。
FAQ(学資保険見直しのよくある疑問)
Q1: 今すぐ解約や乗り換えをすると具体的にいくら損をするのか、簡単に計算する方法はありますか?
手元の保険証券か、保険会社のマイページ(Web)を確認しよう。「経過年数ごとの解約返戻金額」が記載された表があるはずだ。記載がない場合は、コールセンターに電話をして「今解約したらいくら戻るか? これまでの払込総額はいくらですか?」と聞くのが最も確実で早い。
Q2: 子どもがすでに小学生・中学生になっている場合、学資保険を見直す価値はどこまで残っていますか?
見直しのメリットは限定的だ。積立期間が短いため、新たに加入しても返戻率は低くなりがちである。ただし、家計が苦しい場合に「払済保険」に変更して支払いを止める、といった守りの見直しは有効だ。新たに増やすより、今の契約をどう守るか、あるいはどう整理するかに焦点を当てよう。
Q3: 住宅ローンや他の保険の見直しと比べて、学資保険の見直しはどの順番で取り組むのが合理的ですか?
学資保険の見直しは「最後」にしよう。まずは効果の大きい「住宅ローンの借り換え」や「掛け捨て生命保険・医療保険の削減」、「スマホ代の見直し」を優先する。学資保険は貯蓄性があるため、最後まで残しておくべき資産といえる。
Q4: NISAなどの投資商品と学資保険を併用している場合、どちらを優先して増額・減額すべきでしょうか?
教育資金を使う時期が近い(数年以内)なら、元本保証の学資保険を優先して残し、変動リスクのあるNISAを調整する。逆に、子どもがまだ0歳〜3歳で時間があるなら、インフレに弱い学資保険を最低限にし、NISAの積立額を増やして資産増を目指す戦略も有効だ。
Q5: 祖父母から教育資金の援助がある場合、学資保険を減らす・解約する判断はどう考えればよいですか?
援助額によるが、目標額(例:300万円)を援助でカバーできるなら、学資保険を減額・解約して、その浮いた資金を老後資金やレジャーに回すのも賢い選択だ。ただし、援助が確実でない場合は、学資保険を「教育費」ではなく「子どもの結婚資金」などの名目に変えて残しておくことも検討してみてほしい。
Q6: 一時的に収入が減っただけのとき、契約者貸付制度とカードローン・フリーローンのどちらを先に検討するべきですか?
まずは「契約者貸付制度」を検討する余地がある。一般的にカードローンよりも金利が低く設定されていることが多く、審査もスムーズな場合が多いためだ。ただし、金利は商品によるため、念のためカードローンの金利と比較し、ご自身の資産(解約返戻金)の範囲内で借りる際の利息コストを確認してから判断しよう。
Q7: 払済保険に変更した後に「やっぱり元に戻したい」と思ったとき、どこまで選択肢がありますか?
原則として、一度「払済保険」に変更すると、元の契約に戻す(復旧する)ことはできない。特約なども消滅したままとなる。そのため、払済保険への変更は「もう二度と保険料を払うつもりはない」という最終判断として行う必要がある。
Q8: FPや保険ショップに相談しても商品販売に誘導されそうで不安です。中立に近い相談先を選ぶポイントは何ですか?
「商品を売らない」ことを明言している、有料相談専門の独立系FPを探すのがおすすめだ。相談料(1時間5,000円〜1万円程度)はかかるが、保険販売の手数料で稼ぐ必要がないため、解約や乗り換えについてフラットな意見をもらえる可能性が高いだろう。
まとめ
学資保険の見直しは、単に「新しい保険に入る」ことだけではない。
今の契約を最大限活かす方法を探ることが、損をしないための近道だ。
記事の要点
- 安易な乗り換えは、解約返戻金の元本割れや再加入不可のリスクがあるため慎重に行う。
- 保険料が負担なら、解約の前に「減額」「払済保険」「特約外し」を検討する。
- 一時的な資金不足には「契約者貸付」が選択肢になるが、利息負担や失効リスクに注意する。
- 見直しの際は、今の解約返戻金と将来の受取総額を正しくシミュレーションする。
「自分だけで計算するのは不安」「家計全体を見てアドバイスが欲しい」という場合は、信頼できるファイナンシャルプランナーに相談してみることをおすすめする。
大切なお子様の将来のために、まずは今の保険証券を確認するところから始めてみよう。
出典一覧
文部科学省「私立大学等の平成29年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1412031.htm
日本銀行「時系列統計データ検索サイト」 https://www.stat-search.boj.or.jp/
金融庁「NISAとは?」 https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/index.html
生命保険文化センター「教育資金準備のための生命保険」 https://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/objective/education.html