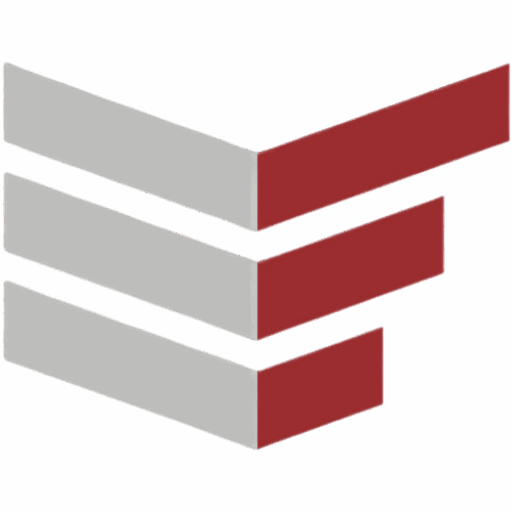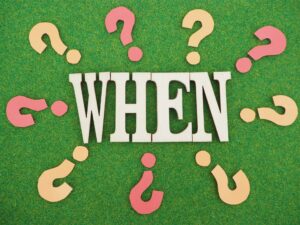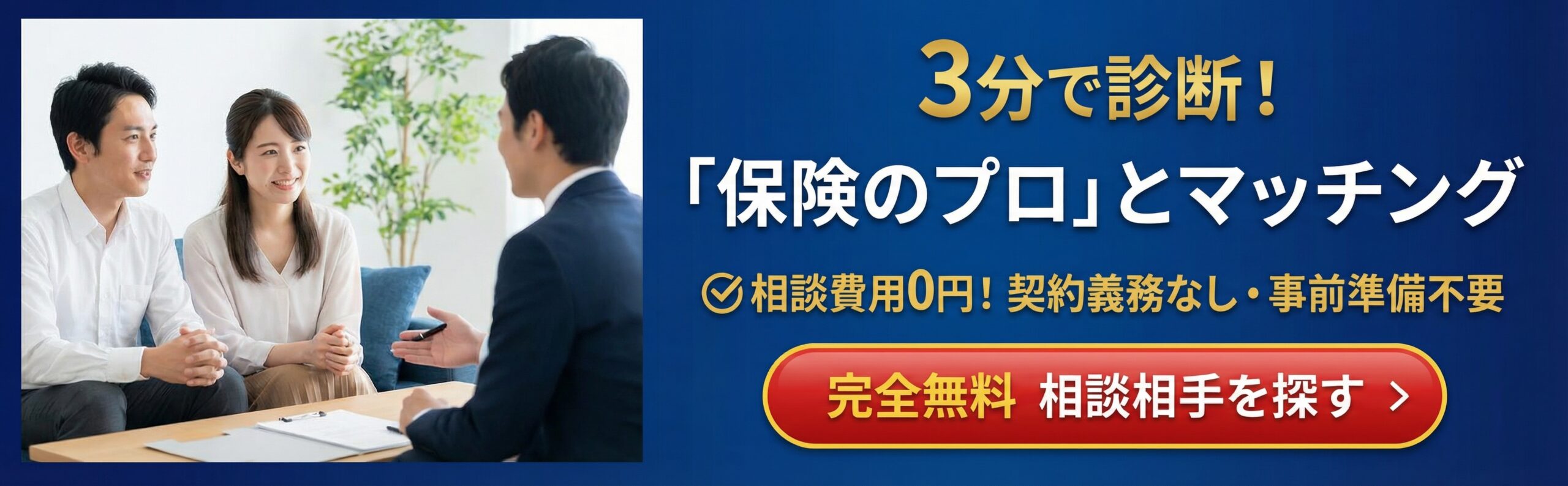・学資保険は満期日までお金を引き出しにくく、途中解約で元本割れのリスクがある貯蓄商品です
・実データから見ると、返戻率の低さ・インフレ対応の難しさ・流動性不足の3点が課題であり、銀行預金や新NISAで対応する家庭が増えています
・家計に合わせた判定基準・弱点分析・代替案の選び方を確認することで、本当に必要かが見えてきます
学資保険は本当に必要か:3つのチェックリスト
学資保険が本当に必要かどうかは、家計の現在地と準備方針によって大きく変わります。すべての家庭に向いているわけではありません。入らない方がいい家庭には、次の3つの特徴があります。
教育資金の貯め方がすでに決まっている
すでに積立投資などを始めている家庭では、学資保険の出番は少ないでしょう。例えば、新NISA枠を活用して月10万円の投資信託積立を実行している家庭では、学資保険は二重の負担になり、管理の複雑さが増すだけです。
毎月の保険料が家計を圧迫しそう
学資保険の保険料は月々5,000円から3万円前後が相場であり、固定費が増えると予期しない支出への対応力が低下します。子育て世帯は想定外の出費が増える時期です。保険料が負担に感じるなら、貯蓄額を減らしてでも預金や投資で進めるべきです。
お金を自由に動かしたい「流動性」重視
学資保険は、契約した満期日までの間、原則として全額を引き出すことができません。子どもが進学先を変えたり、教育費以外で急にお金が必要になったりした場合、現金の自由度を重視する家計運営をしている家庭には相性が悪いと言えます。
学資保険が見直されている理由:気をつけたい3つの弱点
ここ数年、学資保険の評判が下がっている背景には、3つの気をつけたい弱点があります。実際のデータを基に確認していきましょう。
途中解約の元本割れと解約返戻金
学資保険における最大の弱点は、途中で解約した場合に払い込み保険料を下回る返戻金しか受け取れない点にあります。契約から数年以内の解約は、解約返戻金の率が50~80%程度に落ち込みます。例えば月2万円を5年払い込んで120万円を支払ったのに、4年目に解約すると100万円未満で戻ってくるというケースもあります。
保険会社は長期契約を前提に商品を設計しているため、途中で止めると初期コストの回収ができず、返戻金が減ってしまう仕組みです。「保険」という特性上、流動性が著しく損なわれます。
インフレで教育費が増えるリスク
2025年12月時点の消費者物価指数は113.0(2020年=100)に達し、前年同月比で2.1%上昇しています。教育費も例外ではなく、物価上昇に連動して上昇を続けています。
学資保険で契約時に決めた満期額は、将来の物価変動に対応できません。今、お子さんが5歳で18歳での受取を計画し、満期額を300万円と設定した場合、インフレが年2%で推移した場合、13年後に受け取る300万円の実質価値は約250万円相当に目減りする可能性があります。実際の教育費はより多く必要になるという二重の負担が生じる恐れがあります。
必要な時に引き出せない「契約者貸付」の盲点
子どもの進学時期が親の都合で変わったり、予期しない教育費が発生した場合、学資保険から資金を引き出すには、通常は解約か「契約者貸付」を利用します。契約者貸付は、保険の解約返戻金の範囲内でお金を借りる仕組みで、利息は年2~6%程度です。
形式上は「貸付」であるため、返済の義務が生じ、返済しなければ将来の満期受取時に差し引かれます。必要な時に「引き出す」のではなく「借りる」ことになり、後で返す手続きが必要です。教育費のピーク時期に柔軟に対応したいと考える場合、この制度の使い勝手はあまり良くありません。
学資保険が生きる場面:メリットの本質
もちろん、悪いところばかりではありません。学資保険にはメリットがあり、学資保険がぴったりなご家庭もあります。
払込免除で教育資金を守れる
学資保険において最も価値を持つ特約が「払込免除」です。この制度は、契約者(親)が死亡または高度障害状態に陥った場合、以後の保険料の支払いが免除されながらも、満期時には満期金が全額受け取れるというものです。親に万が一があっても、子どもの教育資金は確保される仕組みが基本セットになっていることが多いです。
30代の親が保険期間中に亡くなった場合、月2万5,000円の学資保険に10年契約で加入していれば、300万円の払込予定額のうち150万円しか払い込んでいなくても、それ以降の保険料が免除され、満期時に契約額(たとえば330万円)が全額受け取れます。この保障の役割は、生命保険とは異なる付加価値となります。
生命保険料控除の節税効果は「おまけ」程度に考える
学資保険の加入者は「生命保険料控除」の対象になり、所得から最大40,000円が控除される仕組みです。ただし、この制度の価値を過大評価することは避けるべきでしょう。
控除額が最大40,000円というのは、税率20%の家庭なら節税額は年8,000円程度です。月にすれば約667円のわずかな手助けにとどまります。年100万円の教育費を16年間貯蓄する必要がある場合、税控除による恩恵よりも、その16年間の資金の拘束による機会損失の方が大きいケースが多いのです。
強制貯蓄が合う人もいる
学資保険の本質は「強制貯蓄」です。貯蓄が苦手で、給与が入るとすぐに使ってしまう家庭にとっては、この「強制力」が大きな味方になります。学資保険があれば、お子さんの教育資金だけは確実に積み上がっていくという安心感が得られるでしょう。
ただし、この強制貯蓄の仕組みは、学資保険に限った話ではありません。銀行の定期積立や投資信託の自動積立でも同様の効果が期待できます。さらに、定期積立であれば満期前の解約でも元本割れリスクが低いため、学資保険よりも優れた選択肢になるケースも少なくないのです。
あなたの家計で判定する:教育費ピークの診断プロセス
学資保険の判断は、データと家計診断を組み合わせることで、初めて客観的な答えが見えるようになります。3ステップの診断プロセスで、個別の判断基準を明確にしていきましょう。
わが家のベストを探る!3ステップ診断
学資保険の判断には、下記の順序で考えていくことが有効です。
- 子どもの教育費の総額とピーク時期を把握する
- 家計の月々の固定費と貯蓄余力を点検する
- 親の万一時の保障ニーズを別建てで検討する
教育費の総額とピークをざっくり把握
まず、お子さんの教育費がいくら必要か、いつピークになるかを把握しましょう。文科省の令和5年度調査(2024年度公表)によると、幼稚園から高等学校までの学習費総額は次のようになっています。
| 学校種別 | 年額(子1人) | 定義 |
|---|---|---|
| 公立幼稚園 | 184,646円 | 保護者が支出した学校教育費+学校外活動費 |
| 私立幼稚園 | 347,338円 | 保護者が支出した学校教育費+学校外活動費 |
| 公立小学校 | 366,599円 | 保護者が支出した学校教育費+学校外活動費 |
| 私立小学校 | 1,741,516円 | 保護者が支出した学校教育費+学校外活動費 |
| 公立中学校 | 542,450円 | 保護者が支出した学校教育費+学校外活動費 |
| 私立中学校 | 1,560,359円 | 保護者が支出した学校教育費+学校外活動費 |
| 公立高校 | 596,954円 | 保護者が支出した学校教育費+学校外活動費 |
| 私立高校 | 1,179,261円 | 保護者が支出した学校教育費+学校外活動費 |
仮に公立小学校から公立高校までの12年間を選択した場合、学習費は年間366,599円~596,954円の範囲で推移します。15年間(幼稚園3年~高校3年)の総額を見ると、公立選択で約514万円が必要です。大学進学時には別途、国公立で約82万円、私立で約130万円(文科省「令和6年度学生生活調査」)が目安です。
実際の生活でいえば、高校入学時は制服・教科書・通学定期代で月5~7万円の追加支出が発生し、大学入学時は下宿費も加わって月15~20万円の負担が一気に増えます。この時期に「ピーク」が来たときに対応できるか否かが、家計の分かれ目になります。
家計の固定費と貯蓄余力を点検
教育費の必要額が明確になったら、次は家計の貯蓄余力を確認することが大切です。毎月の収入から、家賃・光熱費・食費・ローン返済といった必須の固定費を差し引いた額が、貯蓄に回せる余力となります。
子育て世帯の家計診断では、固定費の割合に注意を払うことが必要です。一般的には、手取り月収に対して固定費が50%以下であることが目安とされています。例えば、手取り月収が30万円の家庭で、固定費(家賃・ローン・保険料・光熱費等)が16万円なら、残り14万円が変動費と貯蓄に充てられます。学資保険に月2万5,000円を充てると、その他の貯蓄や予備費は月11万5,000円になります。
親の万一リスクは保険で分けて考える
学資保険の「払込免除特約」は、教育資金を守る保障として機能します。しかし、この保障機能が親の万一リスク対策として最適とは限りません。親が亡くなった時に必要な保障は、教育資金だけに限りません。住居費・生活費・医療費といった、遺族全体の生活を支えるお金が必要になります。
親の万一リスク対策は、別建ての収入保障保険や定期生命保険で、必要な保障額を正確に計算したうえで加入することをお勧めします。そうすることで、教育資金と生活費をそれぞれ適切な水準で確保できます。
学資保険なしで準備する:役割分担の組み立て
学資保険が向かないと判断したなら、何をすればいいのか?答えは「貯蓄」「投資」「保障」の3つの役割に分けた組み立てです。教育資金の準備を複数の手段で構成することで、より柔軟で効率的な設計を実現できます。
役割分担の比較表:貯蓄・投資・保障の整理
下記の表は、教育資金準備に利用できる各手段の特性を比較したものです。
| 手段 | 流動性 | 元本保証 | リターン | 適した時期 |
|---|---|---|---|---|
| 銀行定期 | 低 | あり | 低(0.5%程度) | 教育費ピークまで5年以内 |
| 新NISA(つみたて) | 高 | なし | 中~高(年3~5%目安) | 教育費ピークまで10年以上 |
| 個人向け国債 | 中 | あり | 中(年1~2%程度) | 中期(5~10年) |
| 学資保険 | 低 | ×元本割れ | 低(1~2%程度) | 出生直後から長期 |
| 収入保障保険 | N/A | 保障機能 | 保障 | 子ども誕生時 |
預金で元本確保、投資は新NISAで分散
教育費の準備を貯蓄と投資に分けることで、リスク管理と効率化を両立させることができます。
3年以内に教育費が必要な場合は、銀行の定期預金や個人向け国債で元本確保を優先します。金利は0.5~2%程度と低めですが、確実な貯蓄を得ることができます。
一方、教育費ピークまでに10年以上の時間がある場合は、新NISAの活用が有効です。つみたて投資枠は年間120万円まで非課税で運用することができ、長期のつみたてであれば、市場の変動をリスクを分散でき、年3~5%程度のリターンが期待できます。お子さんが0歳で18歳の大学進学時に300万円が必要な場合、月1万5,000円を新NISAで18年間つみたてすれば、合計324万円の積立で300万円以上のリターンが見込める確率が高くなります。
個人向け国債や定期でインフレに備える
インフレ対策として、個人向け国債も有効な手段です。変動10年型であれば、世の中の金利に応じて利息が変わり、インフレ時に実質価値の目減りを緩和できるというメリットを持っています。現在の利回りは年1~2%程度ですが、インフレが加速すれば利回りも上昇する仕組みです。
また、複数の定期預金で分散保管することも検討の価値があります。例えば、3年定期・5年定期・10年定期をそれぞれ組むことで、時間をずらして満期を迎えることができ、その都度金利を確認して追加投資するように柔軟に対応できます。
保障は収入保障保険など別建てにする
親の万一リスクに対しては、学資保険に内包される払込免除特約ではなく、別建ての生命保険で対応することをお勧めします。
収入保障保険は、契約者が亡くなった場合に、遺族が毎月一定額を受け取る保険です。お子さんが独立するまでの20年間、月10万円を保障するといったように、必要な金額と期間を柔軟に設定することができます。定期生命保険であれば、1,000万円の死亡保障を30歳から60歳までの30年間、月2,000円程度で加入することができます。この方が、教育資金に限定される学資保険の払込免除よりも、家族全体の経済保障という観点ではより充実していると言えるでしょう。
学資保険を選ぶなら確認すべき指標:返戻率との付き合い方
それでも学資保険の加入を選択する場合は、商品選びで失敗しないために、チェックすべき指標をしっかり理解しておくことが必要です。見かけ上の数字に惑わされず、実用性を総合的に判断することが大切です。
受取率と返戻率の違いを整理する
学資保険の商品パンフレットを見ると「返戻率115%」といった数字が目立ちます。これは、払い込んだ保険料の総額に対して、受け取る満期金がどの程度の割合になるかを示す指標です。一方、「受取率」という概念も存在します。これは、実際にお子さんが進学する時期に、予定通りお金が受け取れる状況を指します。
返戻率が同じ115%であっても、受取時期が進学の必要な時期と合致していなければ、その保険の実用性は低くなります。高校入学時にお金が必要なのに、受け取れるのが18歳(大学進学時)だけなら、資金繰りに窮する可能性が出てきます。
受取時期と祝金の設計で使い勝手が変わる
学資保険の使い勝手を左右する最重要ポイントは、受取時期と祝金(進学祝金)の有無にあります。
祝金ありのタイプであれば、小学校入学時・中学校入学時・高校入学時に祝金を受け取り、18歳の満期時に満期金を受け取ります。このデザインであれば、実際の教育費の支出時期に現金を受け取ることができるため、家計の足しになりやすいという利点を持ちます。一方、祝金なしで満期時に一括受取するタイプは、返戻率が若干高く設定されていることが多いです。
外貨建て・変額はリスクが増える
学資保険の商品ラインアップには、外貨建てや変額型という選択肢も用意されています。これらはリターンの可能性が高くなっている一方、リスクも大きくなります。
外貨建て学資保険は、米ドルやユーロで運用され、契約時の返戻率が143%といった高水準に設定されていることもあります。しかし、受け取り時の為替レートが契約時と異なれば、想定した日本円額を受け取ることができなくなります。変額学資保険は、保険会社が投資信託などで運用する仕組みであり、市場低迷時は元本割れする可能性も出てきます。教育資金という重要な貯蓄には、このリスクは相応しくないと言えるでしょう。学資保険を選ぶなら、円建て・定額タイプで、返戻率と受取時期が明確な商品を基本としてください。
すでに加入している場合:解約前に検討すべき選択肢
すでに学資保険に加入している家庭は、解約する際に複数の手続き選択肢を検討することで、金銭的な損失を最小化することができます。単に「やめる」のではなく、複数の手続き選択肢と税務上の注意点を理解したうえで判断することが大切です。
解約前の優先順:減額→払済→貸付→解約
学資保険の見直しを判断した際は、いきなり解約するのではなく、下記の優先順で検討することをお勧めします。
- 減額:保険金額を下げて、毎月の保険料を低くする
- 払済:以後の保険料を払わず、その時点での解約返戻金を満期金に充当する
- 契約者貸付:必要な額だけ借りて、返済計画を立てる
- 解約:やむを得ない場合に、全額を返戻金で受け取る
この順序を踏むことで、金銭的な損失と税務上の負担を段階的に調整することができます。
解約の前に減額・払済を確認する
例えば、月2万円の保険料が家計を圧迫していても、全額解約ではなく「減額」という選択肢が存在します。保険金額を300万円から200万円に下げることで、保険料も月1万3,000円程度に低下させられるケースが多いのです。この方法であれば、学資保険としての最小限の機能は保持することができ、その間に新NISAなど別の貯蓄手段に切り替えることができます。
もう一つの選択肢が「払済」です。払済にして以後の保険料の払込を停止しても、その時点での解約返戻金額が、満期時に受け取る金額に反映される仕組みです。10年契約で5年払い込んだ時点で「払済」にした場合、払い込んだ分の解約返戻金(たとえば140万円)が確定します。残りの5年間は保険料を払わずに満期を迎えることができ、元本割れも、その時点の返戻率に限定されるため、完全解約よりも損失が小さくなると言えるでしょう。
契約者貸付は利息と返済計画が鍵
緊急で教育費が必要な場合は、解約ではなく「契約者貸付」の利用を検討してください。契約者貸付は、解約返戻金の範囲内でお金を借りる仕組みで、利息は年2~6%程度です。
例えば、解約返戻金が150万円あり、100万円を貸付で借りた場合、利息が年3%なら月々の利息は2,500円になります。返済計画を立てずに借りたまま放置してしまうと、10年後に利息と元本が膨らみ、予定していた教育費が大幅に減額されることになります。貸付を利用する場合は、返済期限と金額を明確に設定することが不可欠です。
受取時の税金と名義設定の落とし穴(贈与税に注意)
学資保険の満期金受け取り時には、想定外の税負担が生じることがあります。特に注意が必要なのは「一時所得」と「贈与税」の関係です。
契約者が親で受取人も親の場合、満期金は一時所得として扱われます。受け取った金額が払い込んだ保険料を上回る部分(利益部分)の半額が課税対象になります。例えば、払い込み保険料が200万円で、満期金が230万円であれば、利益は30万円です。この場合、(30万円÷2)=15万円が一時所得として、他の所得と合算されて課税されます。
一方、契約者が親で受取人がお子さん(祖父母が契約者の場合も含む)のケースでは、注意が必要です。この場合、受け取った全額が贈与扱いされ、年間110万円の非課税枠を超える部分に対して贈与税(10~50%)が課せられます。学資保険を選ぶ際は、契約者と受取人の関係を慎重に設定し、税務署に事前相談することをお勧めします。
全体のまとめ
学資保険が本当に必要かは、家計と人生設計次第です。返戻率の低さ、インフレ対応の難しさ、流動性の制限といった3つの弱点がある一方、払込免除特約による保障機能や強制貯蓄という仕組みにはメリットがあります。重要なのは、これらの特性を正確に理解したうえで、個別の家計状況に照らし合わせて判断することです。教育費ピークの時期、月々の貯蓄余力、親の万一リスク対策など、複数の視点から総合的に検討することで、本当に必要かが見えてきます。学資保険を選ばない場合であっても、銀行預金・新NISA・個人向け国債という複数の手段を組み合わせることで、むしろより柔軟で効率的な教育資金準備が実現可能です。すでに加入している場合も、安易に解約するのではなく、減額や払済といった段階的な見直しを検討することで、損失を最小化できます。
今すぐ実行できる3つのアクション
判定を先延ばしにせず、今月中に次の3点を実行してください。
- 家計管理アプリやExcelで、お子さんの教育費総額を試算する(幼稚園から大学までの総額と時期)
- 手取り月収と固定費(家賃・ローン・保険・光熱費)を把握し、毎月の貯蓄余力を計算する
- 親の死亡時に必要な保障額を整理し、学資保険の払込免除で足りるか、別途生命保険が必要かを検討する
この3点を具体的な数字で把握することで、あなたの家庭に最適な選択肢が明確になります。
学資保険に入らないと教育費は足りなくなりますか?
入らなくても、計画的な貯蓄と家計管理で対応することは十分可能です。
調査データでは、教育資金の準備方法として「銀行預金54.3%」が最多で、学資保険の38.4%を上回っています。つまり、預金で十分に対応している家庭が多いということを示しています。年間の貯蓄目標は月5~8万円程度あれば、18年間で到達可能な水準です。
学資保険の代わりに新NISAだけで大丈夫ですか?
教育費ピークまでの時間が長ければ、新NISAは有力な選択肢になります。ただし「だけ」では家計判断が必要です。
新NISAは月10万円の積立で18年なら総額2,160万円になります。ただし、市場変動があるため、教育費ピークまで3年以内であれば、定期預金と組み合わせるリスク管理が求められます。
学資保険はいつまでに入るのがいいですか?
お子さんが0~3歳までの加入が、返戻率や保障効果の観点では望ましいです。
学資保険は年齢が低いほど、加入から満期までの期間が長くなり、返戻率が高く設定されます。0歳加入で返戻率105%程度のものが、5歳加入では103%程度に低下する傾向を見せています。
すでに加入している学資保険は解約すべきですか?
解約すべきかは、見直しの優先度と家計負担を天秤にかけて判断することが大切です。
加入から10年以上経ていれば、返戻率が90%以上に回復している可能性が高く、全解約よりも「減額」や「払済」で保険料負担を軽くする方が得策になることが多いです。一方、加入後3年以内の解約なら、返戻率が70~80%程度に落ち込むため、新NISAや定期預金への乗り換えと損得を詳しく試算する必要があります。
学資保険の返戻率はどのくらいが目安ですか?
返戻率103%以上が理想的ですが、受取時期と使い勝手も同等に大切です。
返戻率103~105%は、月額保険料と満期金のバランスが取れた水準です。100%未満は払い込み総額より受け取り額が少なくなるため避けるべきです。返戻率と受取の自由度のバランスを見て、総合的に判断することが大切です。
学資保険と終身保険、教育資金にはどちらがいいですか?
教育資金に限定すれば、学資保険よりも定期生命保険と定期積立の組み合わせが効率的です。
終身保険は生涯の死亡保障を提供しますが、教育費は時間限定の需要です。お子さんが成人したら、その分の保障は不要になります。親の万一対策と教育資金準備を分けて、収入保障保険(親の死後の生活費)と学資保険またはNISA(教育資金)で役割分担させる方が、保険料も総額も適切に抑えられます。