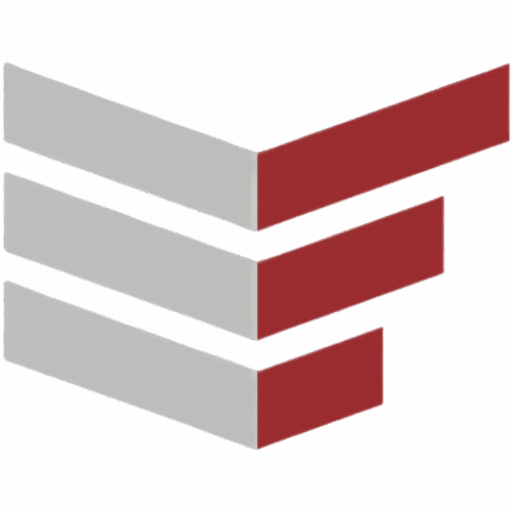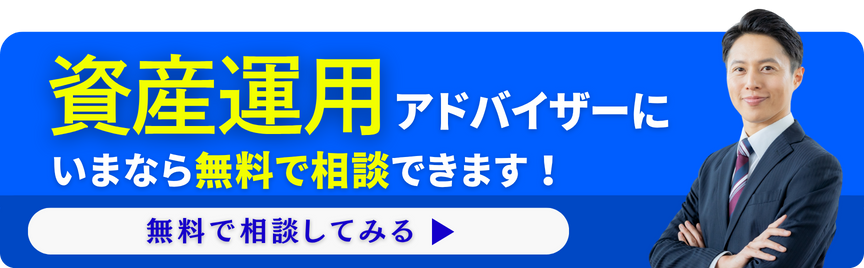50代になって「そろそろ本格的に老後資金を準備しなければ」と焦りを感じていませんか。
「どうやって運用すればいいの?」
「今から始めて間に合うの?」
退職が見えてきた今、このように不安に思う方は少なくありません。
実は、50代から資産運用を始める人は多く、金融庁の調査でも、新NISAなどを積極的に活用しているのは40代から60代の方々が中心であることが分かっています。
50代はご自身の資産状況や将来のライフプランを見通しやすい時期でもあるので、目標に向けた準備は今からでも十分に可能です。
そこで、本記事では、50代の方が無理なく始められる運用方針と、非課税制度の使い方、取り崩しを見据えた設計方法を解説します。
- 本記事で紹介する数値は2025年10月時点の情報です。最新情報は各公式サイトでご確認ください。
50代が資産運用を始める前に考えるべき3つのこと

50代からの資産運用は決して遅くありません。
ただし、20代や30代とは違い、「退職までの時間」「大きな支出」「健康リスク」といった50代特有の事情を考慮する必要があります。
これらを踏まえ、無理のない計画を立てるために、まずは以下の3点を順番に整理しましょう。
- ライフイベント費の把握
- 退職までの年数に基づく目標設定
- 生活防衛資金の確保
それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
教育・介護・相続でいくら必要?ライフイベントの資金を把握する
50代は、大きな支出が重なる時期です。こうした大きな支出が「いつ」「いくら」必要になるのかを事前に把握しておくことが、資産運用の第一歩です。
ライフイベント費用の目安
まず、50代が直面しやすい主なライフイベントと、その費用の目安を確認しましょう。
【代表的なライフイベントと費用の目安】
| 時期 | おおよその金額 | |
|---|---|---|
| 大学費用 | 50〜54歳頃 | 子1人400〜800万円 |
| 住宅修繕 | 50〜60歳頃 | 100〜300万円 |
| 親の介護費用 | 50〜70歳頃 | 月5〜15万円 |
大学費用は、子どもが18歳前後で進学する場合、50代前半から半ばにかけて発生します。国公立大学であれば1人あたり400万円程度、私立文系なら500〜600万円、私立理系や医歯薬系になると800万円以上かかることも珍しくありません。複数のお子さんがいる場合は、その分だけ時期をずらして費用が発生します。
住宅修繕費は、築年数によって大きく変わります。一般的に、築20年を超えると外壁の塗り替えや屋根の補修、給湯器の交換など、まとまった費用が必要になります。規模にもよりますが、100万円から300万円程度は見込んでおいた方が安心です。
親の介護費用は、最も予測が難しい項目です。いつ始まるか、どの程度の介護が必要になるかは人それぞれですが、在宅介護でも月5万円から10万円、施設介護になると月15万円以上かかることもあります。公的な介護保険制度があるとはいえ、自己負担分は決して小さくありません。
自分のライフイベントを整理する
これらの情報を頭に入れたら、次は自分自身の状況を具体的に書き出してみましょう。
イベント名、予定年、見積額を表にまとめると、全体像が見えやすくなります。
【例】
| イベント名 | 予定年 | 見積額 | 確度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 長男大学入学 | 2027年 | 500万円 | 高 | 私立文系想定 |
| 外壁塗装 | 2028年 | 150万円 | 中 | 築5年予定 |
この作業を通じて、「今後5年以内に確実に必要な資金」と「将来的に必要になる可能性がある資金」を区別することができます。前者は現金や元本保証の預金で確保し、後者については長期的な資産運用で備えることも検討できます。
介護・相続制度の確認方法
- 介護保険制度
厚生労働省「介護サービス概算料金の試算」 - 相続税の基礎情報
国税庁「相続税の申告要否判定コーナー」
退職までの年数から目標金額と期限を設定する方法
ライフイベント費用の把握ができたら、次は老後資金の目標を設定します。
50代の資産運用で最も重要なのは、「退職までの時間」という明確な期限があることです。この期限から逆算して、現実的な目標を立てることが成功のカギとなります。
まず、自分が何歳で退職する予定なのかを明確にしましょう。この「残存年数」が、資産運用の戦略を大きく左右します。
残存年数が10年以上あれば、ある程度リスクを取った運用も検討できます。
一方、10年以下の場合は、より保守的な運用を心がける必要があります。市場の暴落から回復するまでの時間が限られているためです。
次に、老後の生活で年金だけでは足りない金額を試算します。
これには、将来もらえる年金額を知ることが不可欠です。日本年金機構の「ねんきんネット」に登録すれば、自分の年金加入履歴や将来の年金見込み額を確認できます。まだ登録していない方は、ぜひこの機会に登録しておきましょう。
年間不足額が分かったら、それに老後の年数を掛けて目標金額を算出します。日本人の平均寿命を考えると、65歳から95歳まで30年間と仮定するのが一般的です。
ただし、インフレや医療費なども考慮し、計算結果に2〜3割の余裕を持たせると安心です。
また、すでに一定の貯蓄がある場合は、その金額を差し引いた「追加で必要な金額」を目標にします。
目標金額と退職までの残存年数が決まれば、毎月いくら積み立てる必要があるかを計算できます。
- 達成係数を用いた概算です。実際の運用成果は市場環境によって変動します。
ただし、これはあくまで概算です。運用成果は市場によって変動するため、楽観的すぎる想定は避け、現実的な計画を立てましょう。
もし計算結果(例:月10万円)が厳しければ、「目標額を下げる」「退職を遅らせる」「生活費を見直す」といった調整が必要です。
生活防衛資金はいくら必要?
これまで資産運用のプランを検討してきました。
いよいよここから資産運用を開始しますが、その大切な第一歩として、まずは「生活防衛資金」をしっかりと確保することから始めましょう。
50代の生活防衛資金の目安
生活防衛資金とは、病気やケガで働けなくなったり、急な失業や収入減少があったりした場合に備えて、生活を守るために確保しておく現金のことです。この資金がないまま資産運用を始めてしまうと、緊急時に投資商品を売却せざるを得なくなり、大きな損失を被る可能性があります。
50代の生活防衛資金の目安は、現在の働き方や収入の安定性によって変わります。
- 自営業・フリーランス:12か月分以上
- 会社員(安定収入):6〜9か月分
- 持病がある・不安定な収入:12か月分以上
例えば、月の生活費が30万円の場合、会社員なら180万円〜270万円、自営業なら360万円以上が目安となります。これに加えて、特別費として50〜100万円程度を上乗せしておくと、冠婚葬祭や家電の故障などの突発的な出費にも対応できるでしょう。
この生活防衛資金は、すぐ現金化できるよう普通預金や定期預金で保管し、株や投資信託で持つのは避けましょう。
50代の資産管理は「備える・守る・増やす」の3つに色分けしよう

50代から資産運用を始める際に、多くの方が迷うのが「どのくらいの金額を、どんな金融商品で運用すればいいのか」という点です。
この問題を解決するため、資産を目的別に3つのグループに分けて管理する方法をおすすめします。
- 備える資金
半年〜1年以内に使うお金 - 守る資産
元本変動を抑えつつ着実に運用 - 増やす資産
長期で積極的にリターンを狙う
このように、お金の「置き場所」と「役割」を明確に分けることで、必要な時にすぐ使えるお金を確保しながら、長期的な資産形成も進められます。
備える資金
備える資金とは、半年から1年以内に使う予定のあるお金のことです。具体的には、毎月の生活費、近々予定している旅行費用、家電の買い替え資金、冠婚葬祭費などが該当します。前章で説明した生活防衛資金も、この「備える資金」に含まれます。
この資金の最大の特徴は、「いつでもすぐに引き出せること」が最優先だということです。金利の高さや運用益よりも、必要な時に確実に現金化できることが重要なのです。そのため、元本割れのリスクがある投資信託や株式は、この区分には適していません。
備える資金に適した金融商品
備える資金に適した置き場所は、以下の通りです。
- 普通預金
ATMやネットですぐに引き出せる、最も流動性が高い置き場所です。ただし金利は低くなります。 - 定期預金
普通預金より金利が高いのがメリットです。ただし、満期前に解約すると金利が下がるため、「確実に使わない期間」が明確な資金に向いています。 - 個人向け国債(固定3年)
元本が保証されて安全性が高いのが特徴です。ただし、発行後1年間は換金できない点と、中途換金時にはペナルティがある点に注意が必要です。
守る資産
守る資産は、1年から10年程度の間に使う可能性のあるお金を指します。例えば、5年後に予定している住宅のリフォーム費用、子どもの結婚資金、退職後すぐに必要になる生活費の補填などが該当します。
この区分の資産は、備える資金ほどすぐに引き出す必要はないものの、10年以内という比較的近い将来に使う予定があるため、大きな元本割れは避けたいお金です。そのため、株式のような価格変動の大きい商品よりも、安定性を重視した運用が求められます。
50代は、20代や30代と異なり、退職までの時間が限られています。全額を株式などのリスク資産に投じてしまうと、退職直前に市場が暴落した場合、回復を待つ時間的余裕がありません。
国債や債券型の投資信託でバランスを取ることで、着実に資産を守りながら育てることができます。「守る」ことと「増やす」ことのバランスを取るのが、この区分の重要な役割なのです。
守る資金に適した金融商品
守る資産に適した金融商品としては、以下のようなものがあります。
- 個人向け国債(変動10年・固定5年)
元本が保証されており、定期預金より金利が高いため、着実に資産を育てられます。 - 国内・外国債券
- 国内債券:値動きが小さく為替リスクもないため、円ベースでの安定性が高いのが特徴です。
- 外国債券:国内より利回りが期待できますが、為替リスク(円高になると損)があります。
- 投資信託のバランス型
株式と債券を組み合わせており、株式100%よりも値動きが穏やかです。リスクを抑えつつ、ある程度のリターンも狙いたい場合に適しています。
増やす資産
増やす資産は、10年以上の長期にわたって運用できるお金を指します。退職後の生活費のうち、当面使う予定のない部分や、将来的な医療費の備え、子どもや孫への贈与資金などが該当します。
この区分の最大の特徴は、「時間を味方にできる」ことです。短期的には価格が上下しても、10年、20年という長い期間で見れば、市場全体は成長する傾向があります。そのため、ある程度の価格変動リスクを受け入れながら、積極的にリターンを狙うことができます。
増やす資金に適した金融商品
増やす資産に適した代表的な商品は、以下のとおりです。
- インデックス投資信託
日経平均やS&P500など市場全体の指数に連動する投資信託です。分散効果が高くコストも低いため、長期投資の王道とされ、特に投資初心者におすすめです。 - REIT(不動産投資信託)
オフィスビルや商業施設など複数の不動産に投資する商品です。株式とは異なる値動きをする傾向があるため、分散投資先として有効です。 - 個別株・ETF(上場投資信託)
ETFはインデックス投信と同様に指数に連動するものが多いですが、株式のように市場でリアルタイムに売買できます。個別株も含め、これらは投資信託より専門知識が必要なため、投資経験がある方向けです。
50代におすすめの「守りながら増やす」運用戦略

ここまで「備える・守る・増やす」という資産の3区分について説明してきましたが、実際に運用を始める際には、具体的な戦略が必要になります。
ここでは、50代の方に特におすすめしたい3つの運用戦略、「コア・サテライト戦略」と「長期・積立・分散」「バケット戦略」を紹介します。
コア・サテライト戦略
コア・サテライト戦略とは、資産を「コア(中核)」と「サテライト(衛星)」の2つに分けて管理する方法です。資産全体の安定性を保ちながら、一部でチャレンジできる点が優れています。
| 区分 | 役割 | 配分目安 | 代表的な商品 |
|---|---|---|---|
| コア | 資産全体の柱。 安定運用を重視 | 70〜90% | 全世界株式インデックス投信 バランス型投信 |
| サテライト | 少額でリターンの 上乗せを狙う | 10〜30% | テーマ型投信 REIT 個別株 |
コアとは、資産全体の柱となる部分で、安定した運用を目指します。全世界株式インデックス投資信託やバランス型投資信託など、堅実な商品を中心に配置し、着実に長期的な成長を重視します。
一方、サテライトは、少額でリターンの上乗せを狙う部分です。テーマ型投資信託、REIT、個別株など、コアよりもやや積極的な商品を配置します。
50代であれば、コアに70〜90%、サテライトに10〜30%程度を配分するのが一般的です。
この配分比率は、退職までの期間やリスク許容度によって調整します。退職まで10年以上ある50代前半であればサテライトをやや多めに、退職まで5年程度の50代後半であればコアを厚くして安定性を重視しましょう。
長期・積立・分散
「長期・積立・分散」は資産運用の基本原則であり、特に時間的制約がある50代こそ、この原則を徹底することが成功の鍵となります。
長期:時間を味方につける
10年、20年という長い時間軸で資産を保有し続けることです。株式市場は短期的には大きく上下しますが、長期的には成長してきた歴史があります。60歳で退職しても、その後30年、40年と続く老後を考えれば、50代でも十分に「長期」の恩恵を受けられます。短期的な値動きに一喜一憂せず、じっくりと構えることが大切です。
積立:タイミングを気にしない
毎月一定額を継続的に投資し続けることで、購入価格が平準化されます(ドルコスト平均法)。市場が高い時には少なく、安い時には多く買えるため、平均購入単価を抑える効果があります。毎月自動的に購入されるため、感情に左右されず、機械的に投資を続けられるのも大きなメリットです。
分散:リスクを抑える
投資先を一つに集中させず、複数に分けることでリスクを抑えます。分散には3つの種類があります。
- 資産の分散:株式、債券、不動産(REIT)など、異なる値動きをする資産を組み合わせる
- 地域の分散:国内、米国、欧州、新興国など、複数の国や地域に投資する
- 時間の分散:積立投資により、購入時期を分散する(高値掴みのリスクを減らす)
バケット戦略|資産を取り崩しながら運用する方法
退職後は、資産を取り崩しながら生活することになります。 この「取り崩し」の段階で役立つのが「バケット戦略」です。
これは、先ほどご説明した「備える・守る・増やす」の考え方を、資産の取り崩しに応用したものと考えると分かりやすいでしょう。
資金を短期・中期・長期の3つのバケット(バケツ)に分けて、使用する時期(=時間軸)に応じて資産配分を変えることで、暴落時でも慌てずに生活費を確保できます。
- 短期バケット
-
- 1〜3年分の生活費を確保するためのもの
- 現金や短期債券で保有
すぐに使う予定のお金なので、値動きのリスクを一切取らず、確実に引き出せる状態にしておきます。
- 中期バケット
-
- 3〜10年分の生活費を確保するためのもの
- 個人向け国債や債券中心のバランス型投資信託で運用
ある程度の期間があるため、多少の値動きは許容しながらも、安定性を重視します。
- 長期バケット
-
- 10年超先の資金
- 株式や全世界株式インデックス投資信託で運用
当面使う予定がないため、積極的にリターンを狙い、長期的な成長を目指します。
運用の仕組みはシンプルです。短期バケットから生活費を取り崩していき、残高が減ったら中期バケットから補充します。中期バケットが減ったら、長期バケットから補充します。年1回、各バケットの残高を確認して調整することで、計画的に資産を取り崩しながら運用を続けることができます。
この方法の優れている点は、短期的な市場の変動に左右されずに生活費を確保できることです。株式市場が暴落しても、短期バケットに3年分の生活費があれば、長期バケットを不利なタイミングで売却する必要がありません。市場が回復するまで待つことができるのです。
 【監修者】平行秀
【監修者】平行秀50代の資産運用は、「守りながら増やす」ことが最優先です。
老後の安心のためにも「長期・積立・分散」の基本原則を守りましょう。
そして、「コア・サテライト戦略」や「バケット戦略」で全体のバランスを取りながら、自分に合ったペースで着実に資産を育てていくことが重要です。
資産運用、誰に相談する?
簡単な質問に回答するだけ!
あなたに合った資産運用アドバイザーを紹介
\ 簡単60秒!相談料はずっと無料 /
【ケース別】50代におすすめの資産運用プラン


ここでは、運用経験やリスク許容度、年齢に応じたポートフォリオの例を紹介します。
ご自身の状況に応じて、適切なポートフォリオを参考にしてください。
運用経験・リスク許容度別のポートフォリオ例
50代の資産運用では、自分のリスク許容度を正しく理解することが重要です。どれだけの値動きなら耐えられるのか、どの程度のリターンを目指すのか。これらは人によって大きく異なります。
ここでは、安定型、バランス型、積極型の3つのタイプに分けて、それぞれに適したポートフォリオを紹介します。
安定型(リスクを極力抑えたい)
安定型は、資産の減少を極力避けたい方に適したポートフォリオです。
- 株式:40%
- 債券・国債:50%
- 現金:10%
債券や国債の比率を高めることで安定性を重視します。想定年間変動幅は±5〜10%程度です。
このポートフォリオが向いているのは、退職が5年以内に迫っている方や、価格変動に不安を感じやすい方です。安定した運用を優先し、大きなリターンよりも着実に資産を守ることを重視します。
退職後の生活が目前に迫っている場合、市場の急落から回復を待つ時間的余裕が限られているため、このような保守的な配分が適しています。
バランス型(安定とリターンどちらもほしい)
標準型は、リスクとリターンのバランスを取りたい方に適したポートフォリオです。
- 株式:50%
- 債券・国債:40%
- 現金:10%
株式と債券をバランスよく組み上げることで、成長性と安定性の両方を追求します。想定年間変動幅は±10〜15%程度です。
このタイプが向いているのは、退職まで5〜10年程度ある方や、運用の基本を理解している方です。ある程度の価格変動は受け入れながらも、極端なリスクは避けたいというバランス重視の考え方です。
50代の多くの方にとって、最も現実的な選択肢と言えるでしょう。
積極型(リターン重視)
積極型は、短期的な値動きに耐えられる方に適したポートフォリオです。
- 株式:60%
- 債券・国債:35%
- 現金:5%
株式の比率を高めることでリターンを追求します。想定年間変動幅は±15〜20%程度です。
このタイプが向いているのは、退職まで10年以上ある方や、運用経験がある方です。市場が下落しても慌てず、長期的な視点で運用を続けられる精神的な余裕が必要です。
ただし、50代という年齢を考えると、若い世代ほど積極的にリスクを取るべきではありません。あくまで「50代の中では積極的」というレベルに留めることが重要です。
年齢別のポートフォリオ例
同じ50代でも、前半と後半では退職までの時間が異なるため、適切なポートフォリオも変わってきます。
50代前半(50〜54歳)
50代前半は、退職まで10年以上あるため、ある程度リスクを取れる時期です。
資産配分の目安は、以下のとおりです。
- 株式:50〜60%
- 債券・国債:30〜40%
- 現金:10%
この時期に重視すべきポイントは、積立投資の継続です。定期的に一定額を投資し続けることで、ドルコスト平均法の効果を得られます。
また、新NISAのつみたて投資枠を最大限活用することで、税制優遇のメリットを享受できます。
さらに、子どもがまだ学生の場合は、教育費の準備と並行して老後資金の準備を進める必要があります。両立が難しい場合は、まず教育費を優先し、それが一段落してから資産運用に本格的に取り組むという選択肢もあります。
50代後半(55〜59歳)
50代後半は、退職が近づいているため、徐々にリスクを下げる時期です。
資産配分の目安は、以下のとおりです。
- 株式:40〜50%
- 債券・国債:40〜50%
- 現金:10%
前半と比べて株式の比率を下げ、債券や国債の比率を高めることで、安定性を重視します。
この時期に重視すべきポイントは、退職金の受取準備です。退職金をどのように運用するかの計画を立て始めましょう。
また、退職後の資産の取り崩し方法についても検討を始める時期です。年金だけでは足りない分をどのように補うのか、どのペースで資産を取り崩すのか、具体的なシミュレーションが必要になります。
債券や国債の比率を引き上げることで、退職直前の市場急落リスクに備えることも重要です。
50代の運用は「見直し・リバランス」が重要


ポートフォリオの管理は、一度決めて終わりではありません。定期的に見直し、必要に応じて調整することで、自分の目標に合った資産配分を維持できます。手間はかかりますが、長期的な資産運用の成功には欠かせない作業です。
ここでは、ポートフォリオの見直しとリバランスという2つの重要な作業について説明します。
ポートフォリオの見直し
ポートフォリオの見直しとは、資産配分そのものを根本から再検討することです。人生の節目やライフステージの変化に応じて、資産配分の目標自体を変更する必要があります。
見直すべきタイミング
住宅ローンを完済した時、子どもが独立した時、退職金を受け取った時、年金受給開始前など、重要なライフイベントのタイミングで資産配分を再検討しましょう。これらの節目では、収入や支出の状況が大きく変わるため、それに合わせてポートフォリオも調整することが求められます。
例えば、住宅ローンを完済すれば、毎月の固定支出が大きく減ります。その分、リスクを取った運用に回せる余裕が生まれるかもしれません。逆に、退職が近づけば、株式の比率を下げて債券や現金の比率を高め、安定性を重視する方向に見直す必要があります。
また、定期的な見直しも重要です。基本的には、年1回(例えば毎年1月)のタイミングでポートフォリオ全体を確認しましょう。ライフイベントがなくても、自分のリスク許容度や運用目標が変わっている可能性があります。
リバランス
リバランスとは、資産配分が目標から大きくずれた場合、元の配分に戻す作業です。ポートフォリオの見直しが「目標自体を変更する」作業であるのに対し、リバランスは「決めた目標を維持する」ための作業です。
時間とともに、株式が値上がりして比率が高くなったり、債券の比率が下がったりすることがあります。この配分のずれを元に戻すことで、意図したリスク水準を維持できます。
リバランスのタイミング
年1回程度が、手間とコストのバランスが取れた頻度と言えます。頻繁にリバランスしすぎると売買コストがかさみますし、逆に放置しすぎると当初の意図した配分から大きく離れてしまいます。
より機械的に実行したい場合は、許容乖離を設定する方法もあります。
例えば、ポートフォリオにおける株式の割合を50%、許容範囲を±10%と設定します。もし株価上昇で株式が60%を超えたら、ルール通りに超過分を売却し、減った資産を買い増す。このように機械的に決めておけば、感情に左右されずに実行できます。
税制優遇をフル活用!50代からの新NISA・iDeCo


資産運用で得た利益には通常約20%の税金がかかりますが、新NISAやiDeCoを活用すれば税負担を大きく減らせます。
- 新NISA:運用益・配当金が非課税
- iDeCo:掛金が全額所得控除+運用益が非課税+受取時も税制優遇
ここでは、NISAやiDeCoの活用方法、そしてどちらを使うべきかなどを解説します。
新NISAの非課税保有限度額はどう使う?つみたて・成長投資枠の使い分け
2024年から始まった新NISA制度は、旧NISA制度から大きく進化しました。最も大きな変更点は、非課税保有期間が無期限になったこと、そして生涯非課税保有限度額が1,800万円に拡大されたことです。この枠をどう使うかが、50代の資産運用を左右します。
新NISAには、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」という2つの枠があります。それぞれに特徴があり、年間の投資上限額も異なります。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間上限 | 120万円 | 240万円 |
| 対象商品 | 金融庁選定の投信 | 上場株式・投信等 |
| 購入方法 | 積立のみ | 積立・一括両方可 |
| 非課税期間 | 無期限 | 無期限 |
つみたて投資枠は、金融庁が選定した低コストで長期投資に適した投資信託に限定されています。年間120万円まで、つまり月額10万円まで積み立てることができます。購入方法は積立のみで、毎月コツコツと投資していくスタイルです。
一方、成長投資枠は、上場株式や投資信託など、より幅広い商品に投資できます。年間240万円まで、つまり月額20万円まで投資可能で、積立だけでなく一括購入もできます。ただし、生涯非課税保有限度額1,800万円のうち、成長投資枠で使えるのは最大1,200万円までという制限があります。
50代の使い分け
50代の方がこの2つの枠をどう使い分けるべきかというと、基本的にはまずつみたて投資枠で低コストインデックス投資信託を積み立てることから始めるのがお勧めです。
具体的には、全世界株式インデックスファンド、米国株式インデックスファンド、あるいはバランス型ファンドなど、分散が効いた商品を積み立てします。
そして、つみたて投資枠だけでは物足りない、あるいは余力がある場合は、成長投資枠で補完するという使い方が効果的です。成長投資枠では、個別株やREIT(不動産投資信託)に投資することもできますし、まとまった資金を一括で投資することも可能です。
ただし、個別株は銘柄選択の知識が必要になるため、投資経験が浅い方は無理に手を出さず、つみたて投資枠だけでも十分に効果があります。
iDeCoの受給は何歳から?年齢制限と税制メリット
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を拠出し運用する私的年金制度です。加入資格は原則20歳以上65歳未満ですが、2025年度の改正で70歳未満まで拡大予定です。
掛金の上限額は加入区分によって異なります。
| 区分 | 月額上限 |
|---|---|
| 自営業・フリーランス | 6.8万円 |
| 会社員(企業年金なし) | 2.3万円 |
| 会社員・公務員(企業年金あり) | 最大2万円 |
| 専業主婦(夫) | 2.3万円 |
- 2024年12月の制度改正による。2025年度にさらなる改正予定
受給は原則60歳から75歳の間で開始できますが、開始年齢は加入期間によって異なります。
50代後半から始める場合は、60歳からすぐに受給開始できない点に注意しましょう。
受給開始年齢
- 加入期間10年以上:60歳から
- 8年以上10年未満:61歳から
- 6年以上8年未満:62歳から
iDeCoの3つの税制優遇
iDeCoには3つのメリットがあります。
- 掛金の全額所得控除
所得税・住民税が軽減 - 運用益が非課税
運用中の利益に税金がかからない - 受取時にも税制優遇
退職所得控除または公的年金等控除
受取方法は一時金、年金、併用から選べます。
ただし、60歳まで原則引き出せないこと、口座管理手数料が年間数千円程度かかることに注意が必要です。
新NISAとiDeCoはどっちを優先?
新NISAとiDeCoは、どちらか一方ではなく、状況に応じて使い分けるか併用することが効果的です。
まず生活防衛資金(生活費6〜12か月分)を確保した上で、近い将来に大きな支出予定がある場合は流動性のある新NISAを優先します。老後資金の準備が主目的で節税効果を最大化したい場合は、iDeCoの併用を検討しましょう。
年収600万円、退職金見込み1,500万円、企業年金:なし
配分例
- 生活防衛資金:200万円(預金)
- 新NISAつみたて投資枠:月8万円(全世界株式インデックス)
- iDeCo:月2万円(バランス型)
- 個人向け国債:300万円(変動10年)
年収500万円、退職金:なし、公的年金のみ
配分例
- 生活防衛資金:300万円(預金)
- 新NISAつみたて投資枠:月5万円(バランス型)
- iDeCo:月3万円(バランス型)
- 個人向け国債:500万円(変動10年+固定5年)
それぞれの制度の特徴を理解し、自分の年齢、収入、退職までの期間、ライフイベントの予定に合わせて柔軟に使い分けることが、50代の賢い資産運用につながります。
50代から始める「資産運用3ステップ」
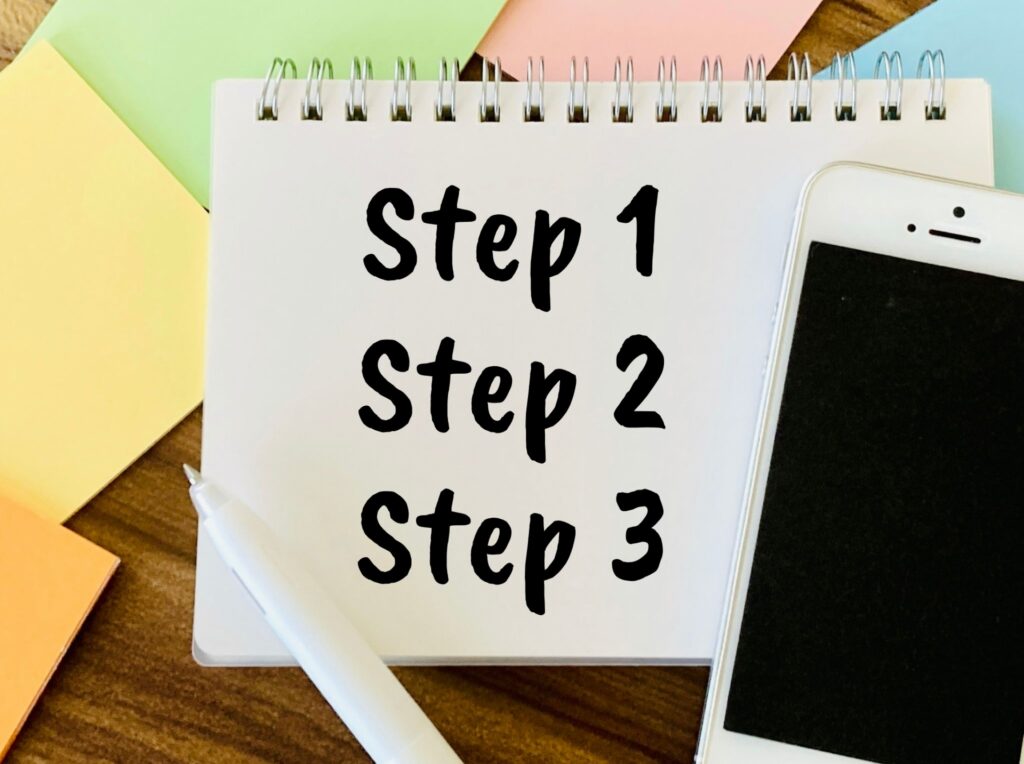
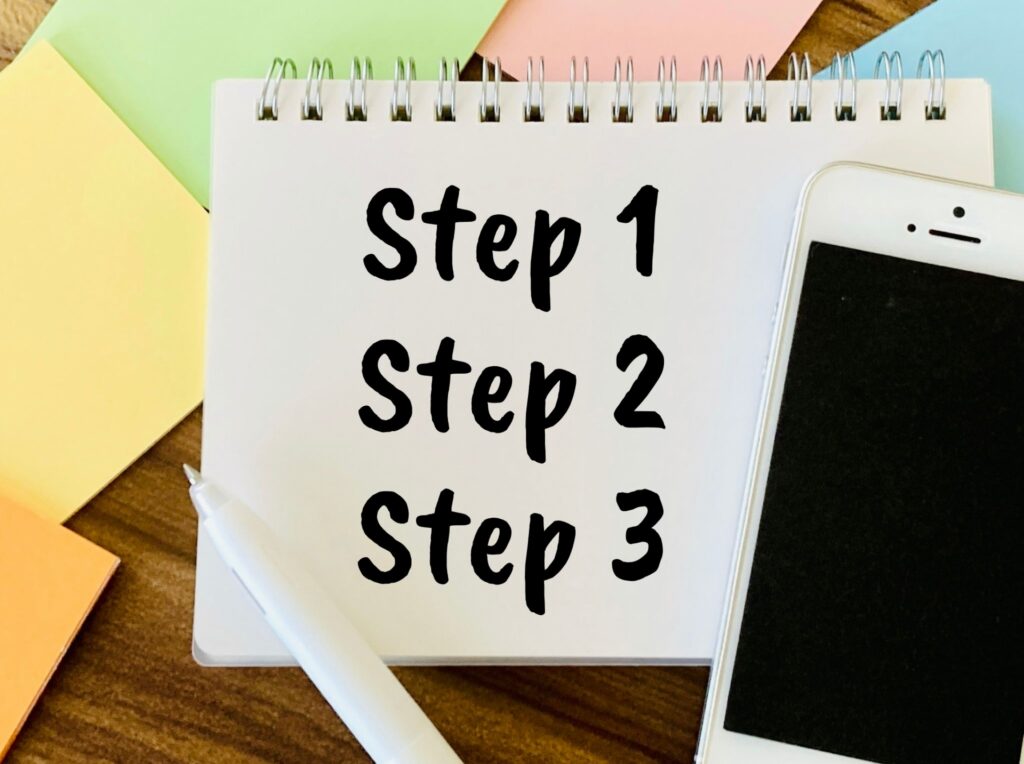
ここまで、50代の資産運用の考え方や戦略について説明してきました。
ここからは、実際に資産運用を始めるための具体的な手順を、3つのステップに分けて解説します。
ステップ1: 証券口座・NISA口座を開設する
資産運用を始める第一歩は、証券口座を開設することです。
銀行や証券会社など、さまざまな金融機関がありますが、50代から始める場合は、手数料が安く、取扱商品が豊富なネット証券がお勧めです。
金融機関を選ぶ5つのポイント
証券会社を選ぶ際には、ご自身の「使いやすさ」や「目的」に合うかを、以下の5つのポイントで確認しましょう。
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 手数料 | 売買手数料、為替手数料、入出金手数料 |
| 取扱商品 | NISA・iDeCo対応、投資信託の本数 |
| アプリ操作性 | スマホでの使いやすさ |
| 積立設定 | クレカ積立の上限や還元率 |
| サポート体制 | 電話・チャット対応の有無 |
証券会社を選ぶ際は、まず「手数料」の安さが重要です。特に投資信託の購入時手数料が無料(ノーロード)のところを選びましょう。
次に、NISAやiDeCoに対応しているか、そして低コストのインデックス投信など「取扱商品」が充実しているかを確認します。
また、アプリやPC画面の「操作性」がご自身にとって分かりやすいかも大切です。あわせて、クレジットカード積立でのポイント還元率なども比較しましょう。
最後に、特に運用が初めての方は、電話やチャットでの「サポート体制」が手厚いと安心です。
- SBI証券
- 楽天証券
- マネックス証券
- 松井証券
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- マイナンバー(個人番号)
- メールアドレス
- 銀行口座情報
NISA口座の開設を忘れずに
証券口座の開設を申し込む際に、同時にNISA口座の開設も申し込みましょう。
NISA口座は、運用で得た利益が非課税になる非常にお得な制度です。証券口座とは別に申し込む必要があり、1人1口座しか持てません。(金融機関の変更は年に1回可能です)
- 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の両方が使えるかを確認しましょう。
- クレジットカードで積立を行う場合は、カード情報の登録など、「クレカ積立」の設定も忘れずに行いましょう。
ステップ2: 手数料・税金のコストを管理する
口座開設が完了したら、いよいよ商品選びです。 その前に、資産運用で成功するために最も重要な「コスト意識」を身につけましょう。
運用で得られるリターン(利益)は不確実ですが、手数料や税金といった「コスト」は確実に発生します。このコストをいかに低く抑えるかが、長期的なリターンを高める鍵となります。
投資信託の手数料を確認する
投資信託を選ぶ際は、目論見書の「費用」の章を必ず読みましょう。特に以下の3つのコストに注目してください。
- 購入時手数料
商品を買う時にかかる手数料です。
現在は「ノーロード」(手数料無料)の商品も多くあります。 - 信託報酬(しんたくほうしゅう)
商品を保有している間、ずっとかかり続ける手数料です。年率(%)で表示されます。
同じような商品でも、信託報酬が年0.1%と年0.5%では、長期で大きな差になります。 - 実質コスト
信託報酬のほかに、売買手数料などを含めた「隠れたコスト」の総称です。
為替スプレッド(為替手数料)も忘れずに
アメリカの株式など、外国の資産に投資する場合は、「円」を「ドル」などの外貨に交換する必要があります。 この交換時に発生するのが為替スプレッド(為替手数料)です。
例えば「1ドルあたり0.25円(25銭)」のスプレッドがある場合、10万円をドルに交換すると約250円のコストがかかります。金額が大きくなれば無視できません。 証券会社によってこのスプレッドも異なるため、比較対象の一つとしましょう。
ステップ3: 資産状況を定期的に確認する
資産運用は「始めたら終わり」ではありません。しかし、「毎日価格をチェックして一喜一憂する」ものでもありません。
適切な距離感を保ち、定期的に資産状況を確認する「メンテナンス」が重要です。
お勧めするのは、「月1回のライト点検」と「年1回のフル点検」を組み合わせる方法です。
- 月1回のライト点検(数分でOK)
資産残高が大きく減っていないか、積立が正常に実行されているかを確認する程度で十分です。 - 年1回のフル点検(年に一度、じっくりと)
1月やご自身の誕生日月など、時期を決めて行いましょう。
以下の点検リストを参考に、ご自身の資産全体を見直します。- 目標:目標金額に対する達成率はどうか?
- リバランス:決めた資産配分(例:株式60%, 債券40%)が崩れていないか?
- 商品:もっと信託報酬の低い(コストが安い)商品が出ていないか?
- 制度:NISAやiDeCoの枠を使いきれているか?
- 生活防衛資金:万が一の備え(現金)は十分か?
50代の資産運用でやりがちな「3つの失敗」とリスク管理法


資産運用を始めると、誰もが大なり小なり失敗を経験します。しかし、初心者が陥りやすい失敗を事前に知っておくことで、多くのリスクを避けることができます。
特に50代は、若い世代と比べて失敗から回復する時間が限られているため、事前の知識がより重要になります。ここでは、50代に特有の3つの失敗例と、その対策を紹介します。
失敗例1: 一つの商品に集中投資してしまう
「○○株が今、話題になっている」「△△のテーマ投資が熱い」といった情報は、SNSや知人との会話でよく耳にします。こうした話題の銘柄に魅力を感じて、資金の大半を一つの商品に投じてしまうケースは、初心者に非常に多い失敗です。
なぜ危険なのか
一つの商品に集中投資すると、その商品が暴落した場合、資産全体が大きく減ってしまいます。例えば、ある個別株に500万円を投資して、その株が半分に下落すれば、250万円の損失です。これが複数の商品に分散されていれば、一つが下落しても他の商品でカバーできる可能性があります。
特に50代では、退職が近いため、損失から回復する時間が限られています。20代や30代であれば、10年、20年かけて回復を待つこともできますが、50代後半でこのような大きな損失を被ると、老後資金の計画が大きく狂ってしまいます。
対策法
先に述べた通り、「資産・時間・地域」の三分散を徹底することが、この失敗を避ける最も確実な方法です。株式だけでなく債券や国債も組み合わせる資産の分散、一括投資ではなく積立や分割投入で購入時期を分散する時間の分散、日本株だけでなく全世界や米国株式にも投資する地域の分散。この3つを実践しましょう。
また、コア・サテライト戦略も有効です。資産の70〜90%を低コストインデックス投資信託や個人向け国債といったコアに配分し、話題の銘柄に投資したい場合は、残りの10〜30%のサテライト部分に限定することで、リスクを抑えながら「攻めの投資」も楽しめます。
失敗例2: 老後の想定外の支出に備えていない
資産運用に熱心になるあまり、手元の現金を減らしすぎて、いざという時に困るケースも少なくありません。
介護費用や住宅の大規模修繕、予期せぬ医療費など、50代以降は突発的な支出が増える傾向にあります。運用に資金を回しすぎると、こうした支出に対応できなくなります。
なぜ危険なのか
手元資金が不足し、補填するために運用資産を途中で売却すると、市場が下落しているタイミングでは大きな損失を被る可能性があります。また、NISA枠を使い切っている場合、売却すると翌年まで枠が復活しないため、機会損失にもつながります。想定外の支出に備えていないと、こうした不利な状況での売却を余儀なくされてしまうのです。
対策
まず、冒頭で説明した通り、運用の前に生活防衛資金(生活費の6〜12か月分+特別費50〜100万円程度)を別枠で確保することが最優先です。この資金は運用に回さず、普通預金や定期預金など、いつでも引き出せる状態にしておきます。
次に、前述のバケット戦略を活用することも有効です。短期・中期・長期の時間軸で資産を分けて管理しておけば、短期的な市場の変動に左右されず、計画的に資産を取り崩せます。
さらに、想定外の支出を事前に試算しておくことも重要です。介護費用、住宅修繕、医療費などについて、予定時期、概算額、準備済み額、不足額を整理しておきましょう。
失敗例3: 相場の下落時に焦って売却してしまう
株価が大きく下落すると、不安になるのは当然のことです。「このまま持ち続けて大丈夫だろうか」「さらに下がる前に売ってしまおう」と考えて、前章で説明した長期投資の原則を忘れ、損失を確定して売却してしまうケースがあります
なぜ危険なのか
失敗例2でも説明したように、長期的に見れば市場は回復する可能性があったのに、売却で損失を確定してしまうと、その後の上昇局面に乗れなくなります。株式市場は短期的には大きく変動しますが、長期的には上昇傾向にあるという歴史があります。焦って売却することで、この長期的な成長の恩恵を受けられなくなってしまうのです。
対策
まず、前述の通り、リバランスのルールを守りましょう。年1回の定期点検を基本とし、許容乖離(目標配分から±5%程度)を超えたときだけリバランスを行うというルールです。相場のニュースに反応して売買することは避けてください。
また、運用を自動化することも有効です。毎月一定額を自動で積み立てる設定にしておけば、相場の状況に関わらず、機械的に投資を続けられます。バランス型投資信託を選べば、自動でリバランスされるため、自分で判断する必要がありません。感情的な判断を避けるために、できるだけ仕組みで対応することをお勧めします。
退職金や相続…「50代の資産運用」はプロへの相談も検討しよう


ここまで読んで、「自分一人で判断するのは不安」と感じた方は、プロのアドバイザーに相談するのも一つの方法です。
プロに相談する3つのメリット
資産運用の専門家に相談することで得られるメリットは、大きく3つあります。
メリット1:現状の見える化と目標の明確化
専門家に相談する最大のメリットは、現在の資産状況や家計を客観的に整理してもらえることです。自分では気づかなかった問題点や、見落としていた資産が見つかることもあります。
また、リスク許容度の診断も重要です。どれだけの値動きまで心理的に耐えられるのか、客観的に判断してもらうことで、自分に合った運用方法が見えてきます。こうした作業を通じて、漠然とした不安が、具体的な数値目標に変わります。目標が明確になれば、そこに向かって計画的に進むことができるのです。
メリット2:具体的な実行プランの提示
目標が決まったら、次はそれを達成するための具体的な計画を提示してくれます。専門家は、退職金をどのように分割投入するか、毎月いくら積み立てればよいかを、シミュレーションを使って示してくれるでしょう。
さらに、どの商品を選べばよいか迷っている方には、推奨商品のリストとコスト比較表を提示してもらえます。信託報酬や実質コストを一覧にして比較できるため、自分で調べる手間が省けます。ただし、推奨される商品については、その理由をしっかり説明してもらい、納得した上で選ぶことが大切です。
メリット3:継続的なフォローアップ
資産運用は、始めたら終わりではありません。市場環境の変化、ライフイベントの発生など、さまざまな要因によって、当初の計画を修正する必要が出てきます。
専門家に継続的に相談することで、年に1回程度のフォローアップを受けられます。運用状況を一緒に確認し、目標配分から大きくずれている場合はリバランスのアドバイスをもらえます。
また、子どもの独立や親の介護開始など、ライフイベントが発生した際に、それに応じた運用計画の見直しも提案してもらえます。
相談が向いている人・向いていない人
ただし、すべての人にプロへの相談が必要なわけではありません。相談が向いている人と向いていない人がいます。
- 退職金の配分に迷う:まとまった金額をどう運用すればいいか分からない
- 制度や操作が不安:口座開設や積立設定の手順が分からない
- 介護や相続が絡み複雑:家族の状況が複雑で、自分だけでは判断しきれない
これらに当てはまる場合は、専門家の力を借りることで、スムーズにスタートできます。
- 短期で大きな利益を狙う:デイトレードや頻繁な売買を望む人
- レバレッジ前提:借金をして投資したい、ハイリスク商品を狙いたい人
長期的な資産形成ではなく、短期的な利益を求める場合は、専門家のアドバイスとミスマッチになる可能性があります。
どこで相談できる?証券会社・FP・IFAの違い
資産運用の相談先としては、主に証券会社、FP、IFAの3つがあります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った相談先を選びましょう。
| 相談先 | サービス範囲 | 費用形態 | 顧客本位 | オンライン可否 |
|---|---|---|---|---|
| 証券会社 | 資産運用の相談 | 商品購入で手数料 | 自社商品を勧める傾向がある | ◯ |
| FP | 家計や保険の相談・見直し | 時間制または定額 | 中立的な立場からアドバイス | ◯ |
| IFA | 金融全般の相談 | 商品購入で手数料 | 中立的な立場からアドバイス | ◯ |
証券会社への相談
証券会社の窓口や担当者に相談する方法です。
最大のメリットは、相談が無料であることと、口座開設から商品選びまで一貫してサポートしてもらえることです。特に初めて資産運用を始める方にとっては、手続きから教えてもらえるのは大きな安心材料です。
ただし、デメリットもあります。証券会社の担当者は、基本的に自社の営業方針に従って商品を勧めます。他に手数料が安い商品があっても、それを紹介してくれるとは限らないので、注意が必要です。
FP(ファイナンシャルプランナー)への相談
FPは、家計全般について相談できる専門家です。資産運用だけでなく、保険の見直し、住宅ローンの相談、教育費の準備、など、幅広いテーマに対応してくれます。
メリットは、中立的な立場からアドバイスをもらえることです。特定の金融機関に所属していない独立系のFPであれば、複数の金融機関の商品を比較して、最も適したものを提案してくれます。また、家計全体を見てもらえるため、資産運用だけでなく、保険の見直しなども含めた総合的なアドバイスが受けられます。
デメリットは、具体的な商品名を挙げた提案ができない場合が多いことです。FPは金融商品の販売資格を持たないことが一般的なため、「この投資信託を購入してください」といった個別具体的な商品の推奨はできません。そのため、FPに方向性を相談した後、自分で商品を選ぶか、別途証券会社やIFAに相談する必要があります。
IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)
IFAは、特定の証券会社に所属せず、複数の証券会社と提携して投資アドバイスを行う専門家です。FPと同様、資産運用だけでなく、保険の見直し、住宅ローンの相談、教育費の準備、相続対策など、幅広いテーマに対応してくれます。
メリットは、複数の証券会社の商品を比較して提案してもらえることです。FPのように方向性の提案だけでなく、具体的な商品選びから購入手続きまで一貫してサポートしてもらえます。商品購入後も、定期的に運用状況を確認し、リバランスのアドバイスをもらえるため、継続的なフォローアップが受けられます。
デメリットは、近年注目されている新しい選択肢ですが、まだ普及段階にあるため、探しにくいことです。自分に合ったIFAを見つけるのに時間がかかる場合があります。
相談料は?勧誘されない?よくある疑問を解消
専門家への相談を検討する際、多くの方が不安に感じるのが、費用面や勧誘についてです。ここでは、よくある疑問にお答えします。
Q1. 相談料の相場は?
相談料は、相談先によって大きく異なります。
- 証券会社:相談無料(商品購入時に手数料)
- FP:1時間5,000円〜1万円程度
- IFA:相談無料(商品購入時に手数料)
初回無料の相談では、現状のヒアリングと大まかな方向性の提示までが行われます。2回目以降で、具体的な商品の提案や詳細なシミュレーションを受ける流れが多いようです。
Q2. 商品を強く勧められたら断れる?
もし特定の商品を強く勧められて違和感を覚えた場合は、はっきりと断って問題ありません。「検討させていただきますが、他の選択肢も比較したいので、一度持ち帰らせてください」と伝えれば大丈夫です。
納得できない場合は契約しなくても問題ありません。
Q3. 個人情報の扱いは?
相談時に提供した個人情報は、プライバシーポリシーに基づいて厳重に管理されます。第三者に無断で提供されることはありませんので、安心して相談できます。
Q4. 相談前に準備する書類は?
以下の書類を準備しておくと、相談がスムーズに進みます。
- 現在の資産状況が分かる資料(通帳、証券口座の残高など)
- 収入・支出の概算
- 目標金額と時期
- ねんきん定期便(年金見込み額)
- 退職金の見込み額(わかる場合)
Q5. オンライン相談は可能?
多くの証券会社やFPは、オンライン相談に対応しています。Zoomやビデオ通話で、自宅から気軽に相談できます。
専門家への相談は、決して敷居の高いものではありません。自分一人で悩むよりも、プロの力を借りることで、より安心して資産運用をスタートできます。まずは初回無料の相談から始めてみてはいかがでしょうか。
まとめ
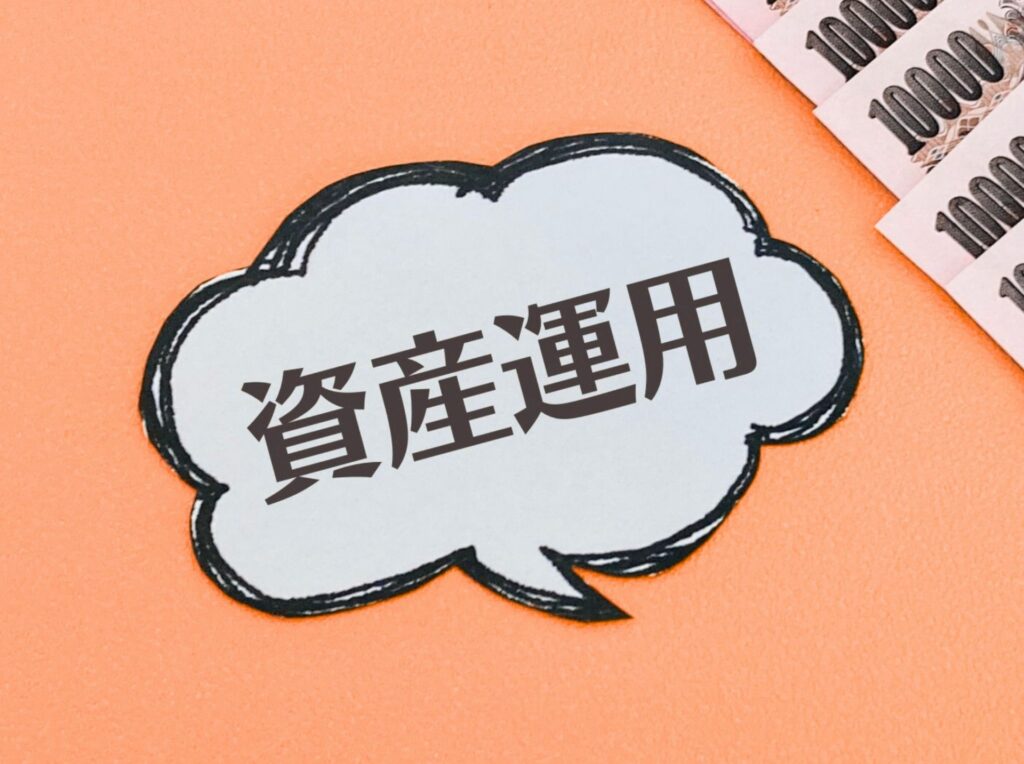
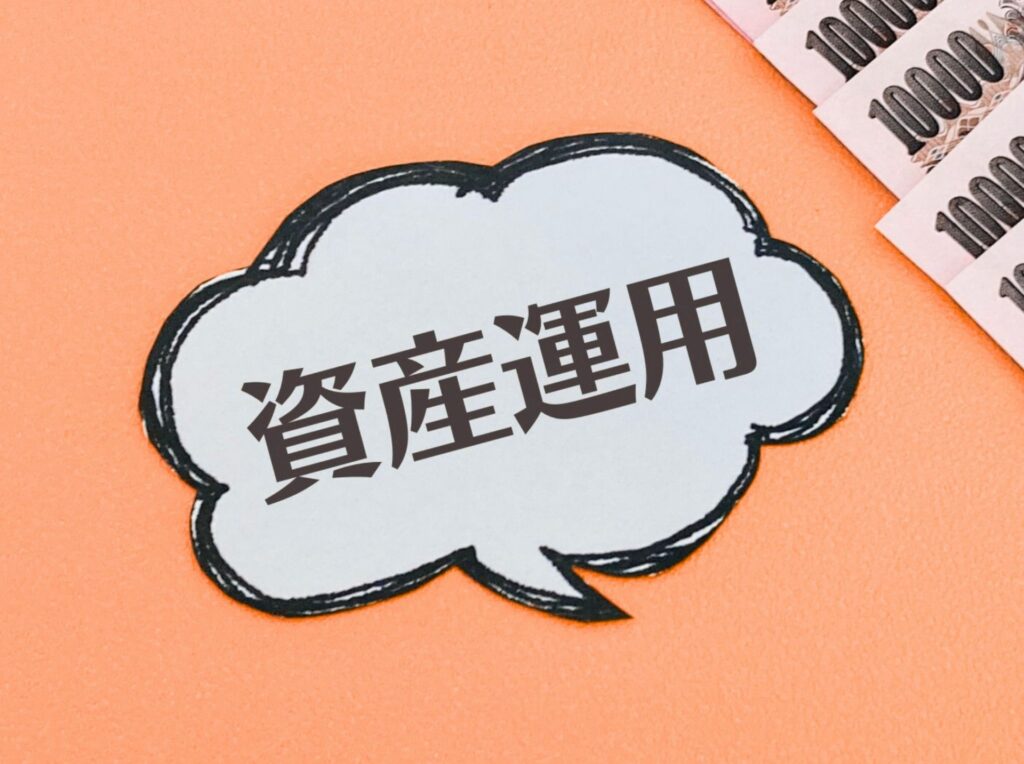
50代からの資産運用は決して遅くありません。まず、ライフイベント費用の把握、退職までの目標設定、生活防衛資金の確保という3つの準備から始めましょう。
資産は「備える・守る・増やす」の3つに分けて管理し、コア・サテライト戦略で全体のバランスを保ちながら、長期・積立・分散という基本原則を徹底することが成功の鍵です。
新NISAとiDeCoを活用することで、税制優遇を受けながら効率的に資産を増やせます。
ただし、50代は退職金の配分や老後資金の準備など、人生で最も重要な資産運用の決断を迫られる時期です。
「自分一人で判断するのは不安」と感じたら、証券会社、FP、IFAなどの専門家に相談してみませんか。
初回相談は無料の場合も多く、客観的なアドバイスを受けることで、より安心してスタートできます。
FAQ


出典一覧
金融庁NISA特設サイト
iDeCo公式サイト
財務省「個人向け国債」案内
日本年金機構「ねんきんネット」
総務省統計局 消費者物価指数
日本銀行 金利(預金・貸出関連)
- 本記事の内容は2025年10月時点の情報に基づいています。最新情報は各公式サイトでご確認ください。
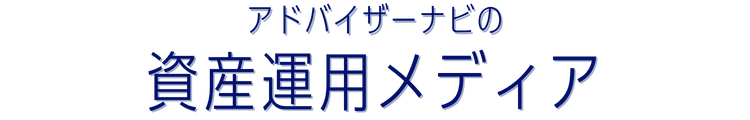
-5.png)