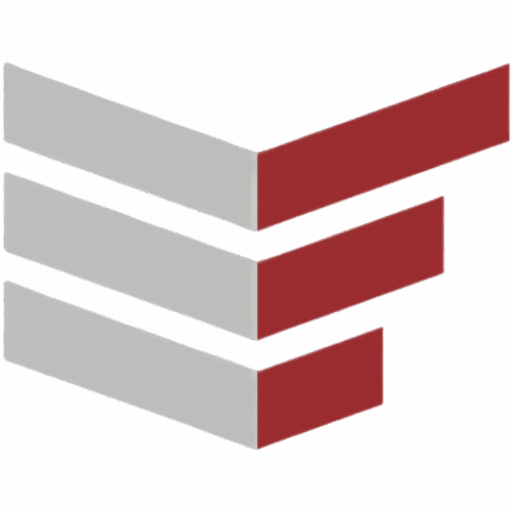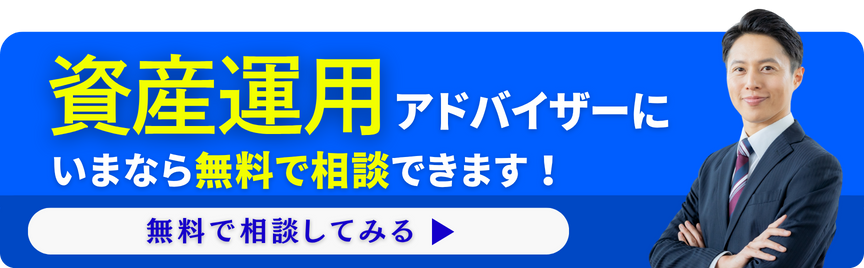- 老後の毎月の不足額をどう見える化すればいいのか分からない
- 60代からNISAを始めても遅くないのか、どう始めれば良いのか迷っている
- 退職金を受け取ったので、安全な運用順序が知りたい
60代に入ると退職金の受け取りや年金生活の準備が現実味を帯び、資産の守り方と増やし方のバランスに悩む方は少なくありません。
現在の物価上昇が続く環境では「ただ預金しているだけ」では実質的にお金の価値が目減りしてしまいます。一方で、リスクを取りすぎて大切な資産を減らすわけにもいきません。
本記事では、インフレ環境でも資産寿命を延ばせる運用の考え方から、現金・債券・株式の役割分担、そして具体的な取り崩し方まで分かりやすく解説します。
60代が資産運用を始める前に考えるべきこと

60代からの資産運用で大切なのは、焦らず、そして市場の動きに一喜一憂しない「ぶれない運用方針」を最初に立てることです。
その土台作りとして、この記事では以下の3つのステップを具体的に解説していきます。
年金・退職金・生活費を把握する
まず取り組みたいのは家計の現状把握です。具体的には、以下の手順で「月次キャッシュフロー表」を作成してみましょう。
手順1:固定費と変動費を分ける
住居費・保険料・通信費など毎月ほぼ一定の「固定費」と、食費・光熱費・交際費など月によって変わる「変動費」を書き出します。家計簿アプリやクレジットカードの明細を見返すと、抜け漏れが減るでしょう。
手順2:生活防衛資金を先取りする
生活費の2〜3年分に加え、今後5年以内に予定している医療費・家のリフォーム・旅行などの特別費を合計し、「生活防衛資金」として確保します。この現金は運用に回さず、すぐ使える預金や個人向け国債などの安全資産に置いておくのが基本です。
手順3:年金見込額を確認する
日本年金機構の「ねんきんネット」や毎年届く「ねんきん定期便」で、将来もらえる年金額の目安を調べましょう。繰下げ受給を検討している場合は、何歳からいくらもらえるのかを試算しておくと、運用計画が立てやすくなります。
- 収入源(年金・給与・その他)の一覧を作成したか
- 税金・社会保険料の負担額を把握したか
- 医療費・介護費の予備費を計上したか
退職金はまとまった金額になりますが、一度に全額を運用に回すのは避けましょう。資金の用途や時期に応じて段階的に投入するルールを設定することで、大きな値動きに翻弄されるリスクを減らせます。
インフレに負けない利回りの目標を決める
物価が上がる環境では、「名目利回り」だけでなく「実質利回り」を意識することが大切です。実質利回りとは、投資で得られる利回りから物価上昇率を引いた値を指します。
実質利回り = 名目利回り − インフレ率
たとえば、2025年8月時点の消費者物価指数は前年同月比で2.7%上昇しています。
この状況で、もし資産運用の名目利回りが年2%だった場合、実質利回りは「2% − 2.7% = −0.7%」となり、実はお金の価値は目減りしている「インフレ負け」の状態です。
そのため、資産の実質的な価値を守るには、インフレ率を上回る利回りを目指す必要があります。
具体的な目標としては、実質利回りで年1%程度を確保できれば、資産価値を維持しながら取り崩しにも対応しやすくなるでしょう。仮にインフレ率が2.5%なら、名目利回りで3.5%程度が目標ラインとなります。
ただし、目標を立てる際には、漠然と「増やす」とだけ考えたり、一年ごとの短期的な値動きで方針をコロコロと変えたりしないことが重要です。
リスク許容度と時間軸を確認する
リスク許容度とは、資産が一時的に値下がりしたときにどこまで耐えられるかの度合いです。60代では、収入状況・使途までの期間・下落耐性の3つの軸で考えると整理しやすくなります。
軸1:収入の有無
就業を続けている、または年金受給前であれば、多少のリスクを取る余裕があります。一方、年金のみで収入が限定的なら、安定性を重視した配分が望ましいでしょう。
軸2:使途までの期間
5年以内に使う予定のお金は、原則としてリスク資産に回さず、現金や個人向け国債など元本が保全される資産で保有します。5年以上先に必要な資金は、適度にリスクを取って運用しても時間的猶予があるといえます。
軸3:下落耐性
「もし資産が20%下落したらどう対応するか」と自問してみてください。慌てて売却してしまいそうなら、株式比率を下げる、あるいは債券やバランス型ファンドの比率を高めるなどの調整が必要です。
自分の下落耐性を把握することが、無理のない運用計画を立てるための第一歩です。
60代の基本戦略は「分散投資」と「コア・サテライト」

60代からの資産運用では、大きな失敗を避けつつ資産を守り育てるための基本戦略として「コア・サテライト」という考え方が非常に有効です。
これは、資産の大部分を占める守りの「コア資産」と、一部で成長を狙う攻めの「サテライト資産」に分けて管理する方法です。
さらに、退職金などのまとまった資金をどう投じるか、「一括投資と積立の使い分け」も重要なポイントになります。
ここでは、コア・サテライト戦略と一括投資と積立の使い分けについて、具体的に解説していきます。
コア資産で安定配分を作る
コア資産の役割は、資産全体の価格変動(ボラティリティ)を抑え、将来の取り崩しに備えるための安定した土台を作ることです。
具体的には、以下のような値動きが比較的穏やかな商品で構成します。
- 個人向け国債(変動10年)
- 国内外の債券インデックスファンド
- バランス型ファンド(株式と債券の比率が固定、または自動調整されるもの)
- 全世界株式のファンドを少し含める(リスク許容度に応じて)
これらの商品を選ぶ際のポイントは、まず信託報酬(手数料)の低いインデックスファンドを優先することです。
そして、分配金は自動で再投資されるタイプを選ぶのが基本です。分配金を受け取るタイプは、運用効率を高める複利の効果が薄れてしまうため、守りを固めるコア資産にはあまり向きません。
コア資産を構築した後のメンテナンスも大切です。半年に一度、または年に一度を目安に、資産配分のバランスを確認しましょう。
もし当初決めた比率から5%以上ズレていたら、機械的に元の配分に戻します。例えば、株式の比率が想定より増えていたら一部を売却し、その資金で債券を買い増す、といった調整です。
サテライト資産で成長を狙う
サテライト資産の役割は、インフレに負けないように資産の価値を守り、さらに成長を目指すことです。
具体的には、以下のような株式を中心とした資産で構成します。
- 全世界株式インデックスファンドまたはETF
- 先進国株式インデックスファンド
- 配当株ファンド(個別株ではなく、低コストの分散ファンドを中心に)
ただし、サテライト資産の比率は、原則として資産全体の30%以内にとどめましょう。
万が一の相場下落に備え、「株式指数が15%下がったら、手元資金の一部を定額で追加投資する」といった自分なりのルールを事前に決めておくと、いざという時も冷静に対応できます。
商品を選ぶ際は、個別株や特定のテーマに集中投資するのではなく、幅広い銘柄に分散されたファンドを選ぶことが大切です。
また、成長を狙うサテライト資産であっても、手数料の意識は重要です。信託報酬が年0.1〜0.2%程度の低コストな商品を選ぶことで、長期的に見れば手元に残る利益に大きな差が生まれます。
一括投資と積立を使い分ける
退職金などのまとまった資金がある場合、一度に全額を投資してしまうと、タイミングによっては高値で買ってしまうリスクがあります。これを避けるため、購入時期をずらす「時間分散」を意識することが非常に重要です。
- 初期30%程度をコア資産に一括投資
- 残りを12〜24カ月かけて積立投資
具体的な方法としては、まず資金全体の30%程度を、値動きの安定したコア資産に一括で投資します。
そして、残りの資金は1年から2年(12〜24ヶ月)ほどの期間をかけて、コツコツと積立投資していくのがおすすめです。この方法により、購入価格が平準化され、リスクを抑えやすくなります。
投資を始める際には、金融機関のキャンペーンなどに心を動かされず、あくまでご自身で決めた資産計画を優先するようにしましょう。
そして何より大切なのは、投資を実行した後でも、手元に生活費の2〜3年分にあたる生活防衛資金がしっかり残っているかを確認することです。
もし残らないようであれば、投資額を減らし、まずは手元の現金を十分に確保することを最優先してください。
60代に適した金融商品と使い方のポイント

ここからは、60代の資産運用で活用しやすい具体的な金融商品を紹介します。
- 個人向け国債
- 投資信託・ETF
- 債券
それぞれの特徴と、運用に組み込む際のポイントを理解し、ご自身の運用方針に合ったものを選びましょう。
個人向け国債
個人向け国債は、国が元本と利子の支払いを保証する、安全性の高い金融商品です。資産の安定的な土台(コア資産)を築く上で中心的な役割を果たします。
60代では、半年ごとに金利が見直され、金利上昇の恩恵を受けやすい「変動10年」を主軸に検討するのがおすすめです。
- 購入単位:1万円以上1万円単位
- 利払い:半年ごと
- 満期:3年/5年/10年
- 中途換金:発行から1年経過後に可能
※ただし、直前2回分の利子相当額が差し引かれます。 - 税制:利子に20.315%が課税
個人向け国債の活用ポイント
預金の一部を個人向け国債に置き換えることで、普通預金より有利な金利収入が期待できます。
例えば、2025年9月募集分の「変動10年」は初回適用利率が年1.06%(税引前)と、メガバンクの定期預金(年0.2%台)を大きく上回っています。金利上昇局面では半年ごとに利率が見直されるため、インフレ環境にも強いのが特徴です。
個人向け国債の注意点
発行から1年間は原則として中途換金できません。また、1年経過後も中途換金する際にはペナルティ(直前2回分の利子相当額×0.79685)が差し引かれます。ただし、この場合でも元本割れの心配はありません。
投資信託・ETF
投資信託・ETFは、少額から手軽に世界中の資産へ分散投資ができる便利な商品です。コア資産とサテライト資産の両方で中心的な役割を果たします。
60代では、特に手数料(信託報酬)が低く、運用実績が安定しているファンドを選ぶことが重要です。
商品を選ぶ際のポイント
| 確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 信託報酬 | 年0.1〜0.2%程度の低コストな商品を優先する |
| 純資産総額 | 数百億円以上あると運用の安定性が高い |
| 運用期間 | 3年以上の実績があるファンドが望ましい |
投資信託・ETFの活用ポイント
投資信託は、コア資産として国内外の債券や株式に分散する「バランス型ファンド」、サテライト資産として長期的な成長が期待できる「全世界株式ファンド」を組み合わせるのが基本戦略です。
バランス型ファンドは自動で資産配分を調整してくれるため、運用の手間を減らしたい方に向いています。
投資信託・ETFの注意点
投資信託やETFは、市場の動向によって基準価額は日々変動し、購入時よりも値下がりして元本割れする可能性がある点には注意が必要です。また、保有中は信託報酬などのコストが継続的にかかるため、長期的なリターンに影響します。分配金の高さや一時的な人気テーマだけで安易に選ばず、長期的な資産形成の土台となるかを判断することが大切です。
債券
債券投資には、円建ての「国内債券」と、米ドルやユーロなどの「外国債券」があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の資金計画やリスク許容度に合わせて使い分けることが大切です。
国内債券と外国債券の比較
| 国内債券 | 外国債券 | |
|---|---|---|
| 為替リスク | なし | あり |
| 利回り | 低め | 高め |
| 安定性 | 高い(円ベース) | 為替変動の影響を受ける |
債券の活用ポイント
「3年後に家のリフォーム資金が必要」「5年後に使う予定の資金」といったように、お金を使う時期が明確で、為替変動のリスクを避けたい場合は「国内債券」が適しています。円建てのため、受け取る金額が確定しており、計画的に資産を準備できます。
一方、より高い利回りを求め、為替変動リスクを許容できる場合は「外国債券」も選択肢になります。ただし、円高になると受け取る円の金額が減ってしまうため、よく理解した上で投資する必要があります。
債券の注意点
外国債券には為替変動リスクがあり、債券自体の価値が変わらなくても、円高・円安によって円換算の評価額が大きく変動します。また、国内債券・外国債券ともに、発行体が倒産してしまう「信用リスク」があります。信頼性の高い発行体の債券を選ぶことが重要です。
資産運用、誰に相談する?
簡単な質問に回答するだけ!
あなたに合った資産運用アドバイザーを紹介
\ 簡単60秒!相談料はずっと無料 /
60代の運用におすすめしない金融商品

一方で、60代からの資産運用では、リスクやコストの観点から慎重な判断が求められる商品もあります。ここでは代表的な2つのケースについて、その注意点を解説します。
株式(特に個別株への集中投資)
「高配当株投資」という言葉を聞いたことがある方もいるでしょう。配当金を受け取りながら資産の成長を狙えるのが魅力ですが、60代からの投資では個別銘柄への集中投資はリスクが高まります。
注意すべき理由
「高配当」という響きだけで特定の銘柄に集中投資するのは危険です。企業の業績が悪化すれば、株価の下落だけでなく、配当金が減額・廃止される「減配リスク」があります。また、個別株は情報収集の手間や売買手数料といったコストもかかります。
もし投資するなら
もし株式に投資をするのであれば、個別株ではなく、様々な企業に分散された「投資信託」を選びましょう。その場合でも、資産全体に占める株式の比率はご自身のリスク許容度の範囲内に収め、資産全体の10%以内など上限ルールを設けることが賢明です。
外貨建て保険
退職金を受け取った際などに金融機関から勧められることが多い商品ですが、その仕組みをよく理解しないまま契約するのは避けるべきです。
注意すべき理由
為替手数料や早期解約時のペナルティ(解約控除)など、コストが非常に複雑で高い傾向にあります。また、保険であるため途中で現金化しにくく(流動性が低く)、急にお金が必要になった際に困る可能性があります。国民生活センターからも、為替リスクや手数料の説明が不十分なケースについて注意喚起がされており、契約前の慎重な確認が不可欠です。
もし利用するなら
利用を検討するのは、以下のすべての条件を満たす場合に限定すべきです。
- 10年以上先の将来、その外貨(米ドルなど)で使う具体的な目的(海外移住、孫の留学費用など)が決まっている。
- 預けるお金が、途中で絶対に引き出す必要のない余裕資金である。
- 為替手数料や解約時のペナルティなど、すべてのコストを完全に理解し、投資信託など他の金融商品と比較しても有利だと判断できる。
退職金専用定期預金
こちらも退職金の運用先としてよく提案される商品ですが、魅力的に見える金利には注意が必要です。
注意すべき理由
「当初3ヶ月だけ」といったように、ごく短期間のみ高い金利が適用されるキャンペーン商品がほとんどです。魅力的な金利に惹かれて預けても、満期後は通常の低い金利に戻ってしまいます。その後の運用先を明確に決めていないと、結局は資金を効率的に活かせないまま遊ばせてしまうことになりかねません。キャンペーン金利だけに惑わされず、ご自身の長期的な資産計画を優先することが重要です。
もし利用するなら
本格的な運用プランが決まるまでの、ごく短期間の「資金の一時的な置き場所」として割り切って利用すると良いです。その際は、以下の点を必ず守りましょう。
- 預け入れる前に、キャンペーン期間が終了した後の資金の移動先を具体的に決めておく。
- 満期日をカレンダーに登録するなどして、解約や資金移動の手続きを絶対に忘れないようにする。
長寿リスクに備える取り崩し設計のポイント
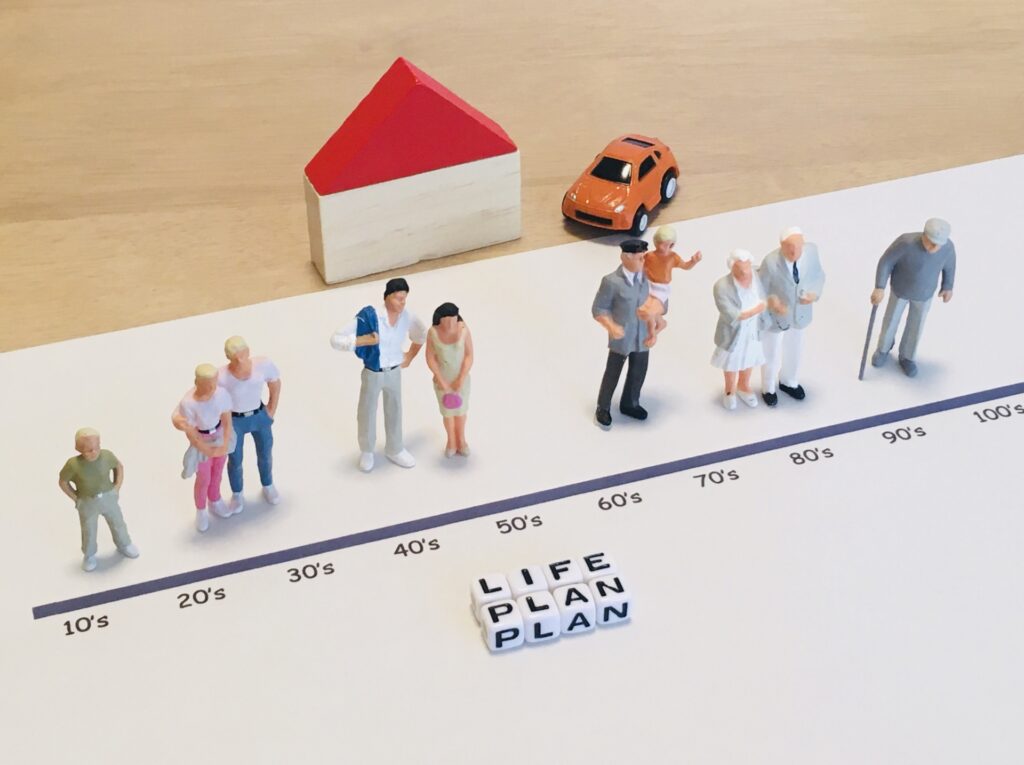
資産を運用しながら計画的に取り崩していくためには、「基本となるルール」と「市場が下落した時の備え」をあらかじめ決めておくことが非常に重要です。
この2つの柱を最初にしっかり立てておくことで、感情的な判断に流されることなく、安心して資産と付き合っていくことができます。
ここでは、その具体的な方法について解説していきます。
運用しながら取り崩す考え方
まず、資産を取り崩していく上での基本的な考え方と、年に一度行うべきメンテナンス作業についてルール化しましょう。
1. 取り崩しの方式を決める
取り崩し方には、主に以下の3つの方式があります。ご自身の家計に合わせて、柔軟に調整できる方法を選ぶのがおすすめです。
| 内容 | メリット/デメリット | |
|---|---|---|
| ① 定率法 | 毎年、資産残高の一定割合を取り崩す (例:4%) | 資産寿命を延ばしやすいが、 受け取る金額が毎年変動する |
| ② 定額法 | 毎年、一定の金額を取り崩す (例:40万円) | 計画は立てやすいが、 相場下落時に資産を大きく減らす可能性がある |
| ③ ハイブリッド法 | ①と②を組み合わせ、上限・下限を設ける (例:年4%が基本。ただし30〜50万円の範囲) | 安定性と持続性のバランスが取れる |
基本的には、「①定率法」(上限は年4%が目安)としつつ、物価の上昇が激しい年には翌年の取り崩し率を少し抑えるなど、状況に応じて調整するのが最もバランスの取れた方法です。
また、現金化の際はリバランスを兼ねて、目標配分より比率が高くなった資産から取り崩します。たとえば、株式の比率が想定より高くなっていれば、株式ファンドを一部売却して現金化し、債券の比率を元に戻すイメージです。
2. 現金化の順番を決める(リバランス)
生活費として現金を取り崩す際は、年に一度の資産配分の見直し(リバランス)と同時に行うのが効率的です。
- 年に一度、資産全体のバランスを確認する。
- 当初決めた目標配分よりも比率が増えすぎている資産(例:値上がりした株式ファインドなど)を一部売却し、現金化する。
- その現金を生活費にあて、同時に資産全体のバランスを元の比率に戻す。
この方法なら、利益が出ている資産から計画的に現金化しつつ、資産配分を健全に保つことができます。
3. 将来の見通しを立てておく
ご自身の資産が将来どのように推移していくか、いくつかのシナリオを想定しておくと、精神的な安心感が大きく変わります。
シミュレーション例
初期資産1,000万円から、毎年40万円ずつ取り崩した場合の25年後の資産残高
| シナリオ | 想定リターン(年率) | 25年後の資産残高(概算) |
|---|---|---|
| 保守的 | 1% | 約550万円 |
| 標準的 | 3% | 約900万円 |
| 楽観的 | 5% | 約1,400万円 |
- 税金・手数料を考慮しない概算値
このように複数の見通しを持っておくことで、市場が変動しても過度に不安になるのを防げます。
市場が大きく下落した時のためのルール
相場が大きく下落した時に、恐怖心から資産を売却してしまうと、大きな損失を確定させてしまいます。そうならないために、冷静なうちに「暴落時のマニュアル」を作っておきましょう。
事前に決めておくべき行動ルール
- 下落幅に応じた行動を決める
- 例:「資産全体が15%下落したら、翌年の取り崩し額を10%減らす」
- 例:「20%下落したら、取り崩しを一時停止し、生活防-衛資金(バッファ現金)から生活費を補填する」
- 生活予備資金を使う順番を決める
- 例:①普通預金 → ②個人向け国債の中途換金、といった順番を明確にしておく。
- 買い増しの条件を決める
- 例:「株式指数が20%下落したら、手元資金の10%を追加投資する」など、パニックにならず機械的に行動できるルールを作る。
恐怖や楽観といったその場の感情に基づいて場当たり的に売買することは避け、事前に決めたルールに沿って機械的に対応することが、長期的に資産を守る上で最も重要です。
また、万が一ご自身で判断が難しくなった場合に備え、資産状況や運用ルールを家族と共有したり、信頼できる専門家への連絡先を整理したりしておくと、より安心です。
[
プロファイル別のポートフォリオ例を紹介

次に、収入の有無や一括資金の有無によって、具体的な資産配分の例を3つ紹介します。
あくまで一例ですので、ご自身の状況に合わせて調整してください。
在職中・年金受給前(60〜65歳)のポートフォリオ
ここでは、60歳で定年を迎えた後も、65歳まで再雇用などで働き続ける方をモデルケースとして見ていきましょう。給与収入で日々の生活費はまかなえており、受け取った退職金の一部を運用に回す、という状況を想定します。
このケースでは、まだ安定した給与収入があるため、年金生活に完全に移行した方よりは比較的リスクを取る余力があります。そのため、資産の配分も安定性を重視しつつ、ある程度の成長を狙うバランスが考えられます。
資産配分の目安
- コア資産(守りの資産):60%
債券ファンドやバランス型ファンドが中心 - サテライト資産(攻めの資産):40%
全世界株式ファンドなどで成長を狙う - 生活防衛資金:生活費の2年分 + 近い将来の特別費
投資には回さず、預金などで確保
この資産配分は、新NISAの2つの枠をうまく活用することで効率的に構築できます。
例えば、「つみたて投資枠」では国内外の債券ファンドやバランス型ファンドを毎月コツコツ積み立ててコア資産の土台を作り、「成長投資枠」で全世界株式のETFなどを購入してサテライト資産を育てるといった使い分けが考えられます。
【重要】近い将来に使うお金の置き場所
ただし、一つ重要な注意点があります。もし5年以内に使う予定が決まっているお金(例えば、住宅のリフォーム資金やお孫さんへの贈与など)がある場合は、その分をサテライト資産の株式ファンドなどには含めず、コア資産の中でも特に安全性の高い個人向け国債などで確保しておくのが鉄則です。
定年後・年金受給開始後(65歳〜)のポートフォリオ
次に、65歳から年金の受け取りが始まり、本格的なリタイア生活に入った方のケースを考えてみましょう。年金だけでは毎月の生活費が5万円〜10万円ほど不足し、その分を資産運用からの取り崩しで補う、という状況を想定します。
現役時代の給与収入がなくなるため、資産配分はより安定性を重視した「守り」の姿勢が基本となります。
資産配分の目安
- コア資産(守りの資産):80%
資産の大部分を、値動きの穏やかな債券ファンドなどで固める - サテライト資産(攻めの資産):20%
資産の一部で株式ファンドなどを持ち、インフレに負けない成長を目指す - 生活防衛資金:生活費の2〜3年分
急な出費や相場下落に備え、必ず確保しておく
資産の配分が決まったら、次に最も重要なのが「生活費をどう引き出すか」のルールを決めておくことです。ルールがあれば、相場の状況に惑わされず計画的に資産を使うことができます。
ルールは、以下のようにシンプルに決めると分かりやすいでしょう。
「毎年、資産残高の4%」と「年間の生活費の不足額」を比べ、大きい方の金額を引き出す。
例えば、資産が800万円なら4%は32万円ですが、年間の不足額が50万円なら、生活を優先して50万円を引き出します。
これにより、資産をなるべく長持ちさせつつ、最低限の生活もしっかり守ることができます。
こうしたルールを決めた上で、実際の運用では以下の点を意識すると、手間を減らしながら資産を上手に管理できます。
- 投資信託の分配金は、生活費として受け取る設定にはせず、自動で再投資されるコースを選び、資産が育ち続ける仕組みを維持します。
- 生活費の取り崩しは、その都度行うのではなく、年に1回(または半年に1回)、計画的に行います。
- この取り崩しは、年に一度の資産配分の見直し(リバランス)と同時に行いましょう。値上がりして比率が増えすぎた資産(例えば株式ファンド)を一部売却して現金化することで、効率的に生活費を確保しつつ、資産全体のバランスを健全に保つことができます。
一括投資中心(退職金活用)のポートフォリオ
最後に、退職金として2,000万円を受け取った方をモデルケースに、まとまった資金をどう運用していくかを考えてみましょう。
まず大前提として、受け取った退職金の全額をすぐに投資に回すのは危険です。最初に生活費の3年分(この例では約900万円)を「生活防衛資金」として必ず確保し、残りの1,100万円を運用に回す、という計画を立てます。
高値掴みを避ける「段階投入」のルール
まとまった資金を一度に投資すると、タイミングによっては高値で買ってしまうリスクがあります。これを避けるため、購入時期をずらす「段階投入」という方法を取ります。
- ステップ1:初期投資
まず、運用資金(1,100万円)の約30%(330万円)を、値動きの安定したコア資産に一括で投資します。 - ステップ2:積立投資
残りの770万円は、2年間(24ヶ月)かけて毎月約32万円ずつコツコツと積立投資していきます。
段階的な投資と並行して、資産の安定性をさらに高めるために、安全資産の置き方と為替リスクへの備えも意識しましょう。
まず、生活防衛資金の一部は、個人向け国債や定期預金に預ける際に、満期が来る時期をずらして複数に分けておくと、より効率的です。
例えば、1年後に満期を迎えるもの、2年後に満期を迎えるもの、3年後に満期を迎えるもの、というように意図的に時期を分散させます。こうすることで、毎年まとまった資金が使える状態になり、もしその時の金利が上昇していれば、満期を迎えた資金をより有利な商品へ再投資できる機会が生まれます。
また、海外の資産を持つ際は為替リスクを考慮し、資産全体に占める外貨建て資産の割合は10%以内など上限を決めておくと安心です。その際には、手数料が不透明な外貨建て保険は避け、コストが明確な外貨建て債券や投資信託を選ぶのが望ましいでしょう。
60代の資産運用でやってはいけないこと

ここからは、60代の資産運用で特に避けるべき行動を3つに絞って解説します。これらのポイントを押さえることで、無駄なコストやリスクを減らし、安定した運用を続けやすくなります。
「集中投資」と「高コスト商品」
退職金などのまとまった資金を、特定のテーマや単一の商品に集中させてしまうのは、非常にリスクの高い行動です。また、手数料が高い商品は、気づかないうちに大切な資産を削り取ってしまいます。
- 単一のテーマ(AI関連株だけ、など)に資産を集中させる
- 手数料が不透明な商品を購入する
- 販売手数料が3%以上かかるような、高コスト投資信託を選ぶ
まず基本として、低コストで幅広く分散された投資信託やETFを選び、個人向け国債などで安全資産を確保することから始めましょう。
商品を選ぶ際には、必ずコストを比較検討する習慣をつけてください。例えば、以下のように手数料を一覧にしてみると、どの商品が低コストか一目で分かります。
| 商品 | 信託報酬(年率) | 販売手数料 | 為替手数料 |
|---|---|---|---|
| 全世界株ファンドA | 0.12% | なし | – |
| バランス型ファンドB | 0.18% | なし | – |
| 外貨建て保険C | 不明 | 3% | 片道2% |
流行や短期的な値動きに合わせた「過度な売買」
市場の動きを見ていると、つい売り買いしたくなる気持ちが湧くかもしれませんが、60代からの資産運用では「頻繁に売買しない」ことが鉄則です。
その理由は、売買を繰り返すたびに手数料や税金がかさみ、結果的に手元に残る利益を減らしてしまうからです。また、タイミングを狙った売買はプロでも難しく、感情的な判断で高値で買って安値で売ってしまう失敗にも繋がりがちです。
基本的には、半年に一度、または年に一度の定期的なメンテナンス(リバランス)以外は、原則として”触らない”というルールを徹底しましょう。
そして、メンテナンスを行った際には「2025年10月1日、株式の比率が目標より増えたため、一部を売却して債券に振り替えた」といったように、日時や理由を記録に残しておくと、後から冷静に振り返ることができます。
特に、「直近1年で最も成績が良かったファンドに乗り換える」といった行動は禁物です。過去の成績は将来を保証するものではなく、むしろ話題になっている時はすでに価格が高騰しており、高値掴みになってしまうリスクが高いと心得ましょう。
税制・手数料・為替の見落とし
税金や手数料、為替コストは、一つ一つは小さく見えても、長期的に見ると運用成績に大きな影響を与える「見えないコスト」です。これらを正しく理解し、対策することが大切です。
NISA
非課税制度を最大限に活用するNISA口座では、運用で得た利益(配当金や売却益)が非課税になります。60代からでも年齢制限なく利用できる、非常に有利な制度です。まずはNISAの非課税枠を使い切ることを最優先に考えましょう。
- 非課税保有限度額
生涯で1,800万円まで - 年間投資枠
つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円
課税口座のルールを理解する
NISA枠を使い切った後に利用する課税口座では、利益に対して**20.315%**の税金がかかります。ただし、同じ年の中であれば利益と損失を相殺(損益通算)して税金の負担を軽くすることができます。
為替手数料に注意する
海外の資産に投資する際には、円と外貨を交換するための「為替手数料」がかかります。この手数料は金融商品によって大きく異なります。
- 外貨預金:1ドルあたり1円前後
- 外貨建てETF:1ドルあたり0.25円前後
- 外貨建て保険:1ドルあたり2〜3円かかることも
例えば、100万円を米ドルに換えて1年後に円に戻す場合、外貨預金なら往復で約2万円の手数料がかかるのに対し、外貨建てETFなら約5,000円に抑えられることもあります。コストが明確な商品を選ぶことが重要です。
60代の資産運用はプロへ相談がおすすめ

ここまで自分で運用方針を決める方法を解説してきましたが、「やはり不安」「家族への説明が難しい」と感じる方もいるでしょう。
そうした場合は、資産運用の専門家に相談することで、第三者の視点から「あなたの場合」に合わせた数値化されたプランを作成してもらえます。
ここでは、プロに相談するメリット、向いている人・向いていない人、相談先の比較、そしてよくある不安とその解消法について説明します。
プロに相談するメリット
専門家への相談は、単にアドバイスをもらうだけでなく、ご自身の考えを整理し、具体的な計画に落とし込む上で大きな助けとなります。
- 家計と資産を一体で最適化できる
現在の収入・支出・資産状況をすべて洗い出し、家計全体のバランスを見ながら、無理のない資産配分を提案してもらえます。 - 具体的な計画を「見える化」してくれる
「保守的・標準的・楽観的」といった複数の将来シミュレーションや、商品ごとのコスト比較表など、判断の助けとなる具体的な資料を作成してもらえます。 - 「いつ・何を・どうするか」という行動ルールを明文化できる
「どの資産をいつ、どれくらい取り崩すか」「市場が下落したらどうするか」といった、いざという時に迷わないための具体的な行動ルールを一緒に作り、文書化してくれます。 - 家族への説明や合意形成をサポートしてもらえる
ご自身だけで説明するのが難しい場合も、専門家が作成した客観的な資料を使ったり、相談に同席してもらったりすることで、配偶者やお子様の理解を得やすくなります。
相談が向いている人・向いていない人
ご自身の状況によって、専門家への相談が有効なケースと、ご自身で進める方が向いているケースがあります。
- 退職金などまとまった資金をどう配分すればよいか、客観的な意見が欲しい方
- 一人で判断することに不安があり、専門家のサポートを受けながら進めたい方
- 資産状況について、家族(配偶者やお子様)の理解や合意を得る必要がある方
- 短期的な売買で利益を狙うなど、長期運用とは異なる目的をお持ちの方
- ご自身で情報収集し、自分の判断と責任で投資を進めたいと考えている方
相談先の比較(証券会社・FP・IFA)
では、実際に資産運用は誰に相談すればよいのでしょうか。
相談先には主に「証券会社」「FP」「IFA」があり、それぞれに特徴があります。以下の比較表を参考に、ご自身に合った相談先を検討しましょう。
| 証券会社(対面) | FP(ファイナンシャルプランナー) | IFA(独立系金融アドバイザー) | |
|---|---|---|---|
| 報酬形態 | 主に販売手数料 | 相談料またはフィー | 主に販売手数料またはフィー |
| 取扱商品 | 自社商品中心 | 保険・ローン・税務など幅広い | 複数の金融機関の商品 |
| 利益相反 | 自社商品優先になる可能性 | 保険販売に偏る場合あり | 中立的な立場 |
| 伴走支援 | 担当者の異動あり | 長期的な関係が築きやすい | 長期的な関係が築きやすい |
証券会社は窓口が身近で相談しやすい反面、提案が自社商品に偏る可能性があります。
FPは家計全体からアドバイスをくれるのが強みですが、保険販売が収益源の場合、提案が保険中心になることもあります。
IFAは金融機関から独立した立場で、幅広い商品から比較提案してくれるのが特徴です。
どの相談先を選ぶ場合でも、「なぜその商品を勧めるのか(推奨根拠)」と「どこで費用が発生するのか(収益構造)」の2点を必ず質問し、納得できる説明が得られるかどうかを見極めることが最も重要です。
よくある不安とその解消法
専門家への相談をためらう理由としてよく挙げられるのが、「費用」「勧誘」「個人情報」への不安です。事前にポイントを知っておくことで、安心して相談に臨めます。
まず費用については、無料相談と有料相談の違いを理解しましょう。無料相談は、商品販売による手数料が相談先の収益源となっていることがほとんどです。
有料相談の場合、初回1時間5,000円〜1万円程度が相場ですが、事前に見積もりを確認し、納得してから申し込むのが基本です。
次に勧誘への不安ですが、その場で契約を迫るような相手は避けましょう。提案内容を持ち帰って検討する時間を与えてくれるかどうかが、信頼できる相談先を見極めるポイントになります。
最後に個人情報については、相談前に必ず情報の利用目的や保管期間を書面で確認しましょう。
相談前に準備しておくと良いもの
相談をよりスムーズで有意義なものにするために、事前に以下の資料を準備しておくと良いでしょう。
- 家計の収支が分かるもの
(家計簿など) - 保有資産の一覧
(預金、投資信-託、保険などの残高が分かるもの) - 年金の見込額が分かる資料
(ねんきん定期便など) - 退職金の金額が分かるもの
(源泉徴収票や見込み額の通知など)
まとめ

60代の資産運用では、まず家計の現状を把握し、インフレに負けない実質利回りを目標に設定し、リスク許容度と時間軸を確認することが大切です。
コア資産で安定を確保しながら、サテライト資産で成長を取り込むバランスが、長寿時代の資産寿命を延ばすカギとなります。
運用しながら計画的に取り崩すためには、取り崩し率・金額・リバランスのルールを明文化し、市場下落時の対応も事前に決めておきましょう。
自分で判断するのが難しい場合は、資産運用アドバイザーへの相談してみるのもおすすめです。
FAQ

出典一覧
統計局ホームページ/消費者物価指数(CPI) 全国(最新の月次結果の概要)
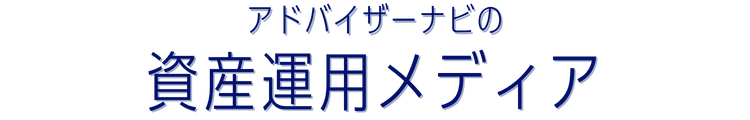
-4.png)