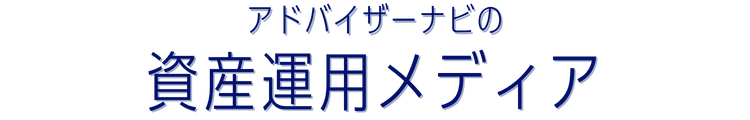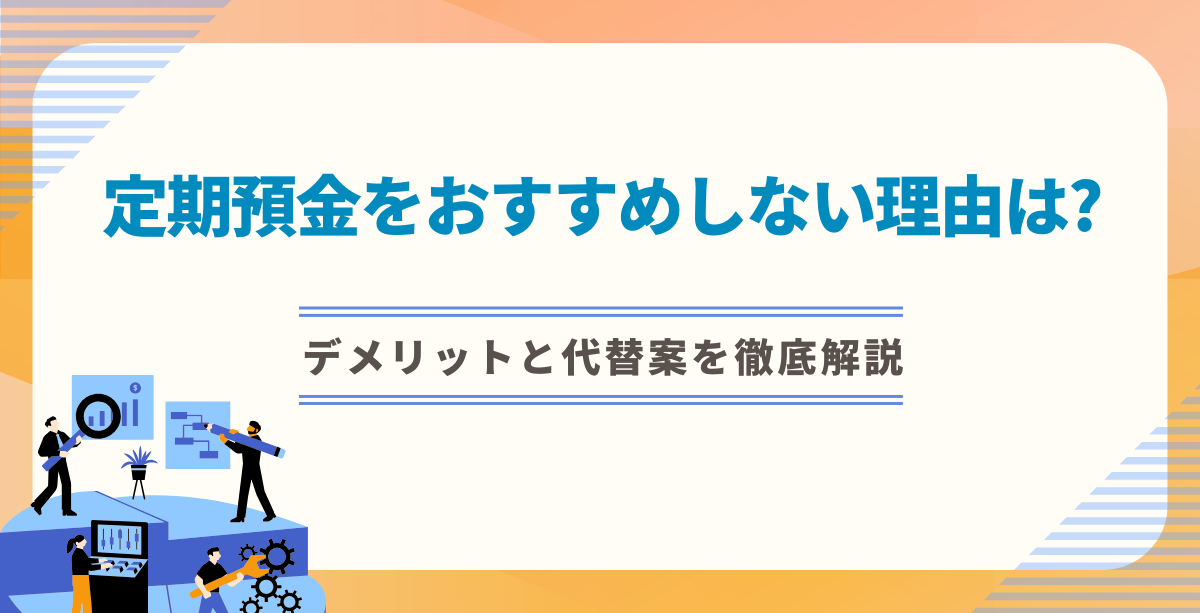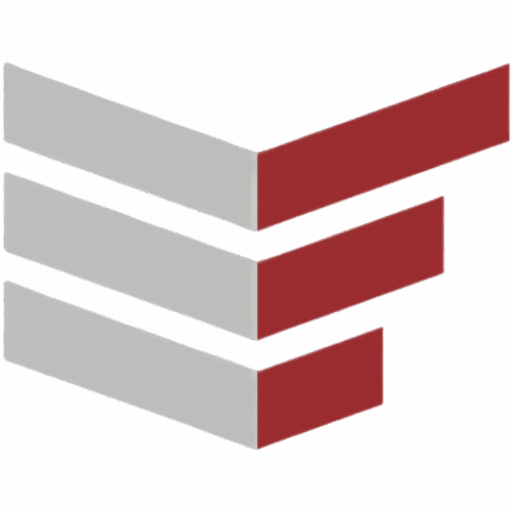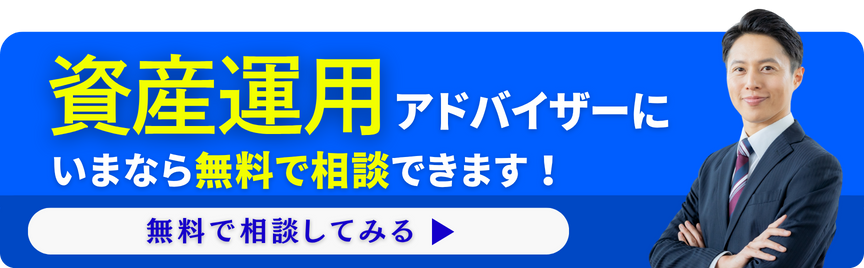- インフレでお金の価値が減らないか心配している
- 定期預金と他の運用方法で迷っている
- 元本を守りながら少しでも増やしたい
「定期預金は安全だから」という理由だけで選んでいませんか。
たしかに定期預金は元本が保証されますが、実はインフレや低金利の影響で、預けたお金の価値が実質的に目減りしている可能性があります。さらに、満期前に引き出せない・金利上昇局面で固定される・預金保険には上限があるといったデメリットも見逃せません。
本記事では、定期預金の基本的な仕組みから、資産形成に不向きな理由、使い勝手の悪さ、安全性の限界まで、わかりやすく解説します。さらに、個人向け国債やつみたてNISA、短期定期を組み合わせる方法など、代替案も紹介するので、あなたに合った方法を見つけてください。
定期預金とは?基本の仕組みを理解する

まずは、定期預金の基本的な仕組みを理解しましょう。
ここでは、定期預金の基本と普通預金との違い、そして満期・自動継続・中途解約という3つの重要なルールを解説します。
仕組みと普通預金との違い
定期預金とは、あらかじめ決めた一定期間、お金を預ける代わりに、普通預金よりも高い金利を受け取れる預金です。
銀行は、預けられた資金が一定期間引き出されないことを見込んで安定的に運用できるため、その対価として普通預金よりも高い金利を設定しているのです。
普通預金との大きな違いは次の通りです。
| 普通預金 | 定期預金 | |
|---|---|---|
| 流動性 | いつでも引き出し可能 | 満期まで原則引き出し不可 |
| 金利※ | 年0.182% | 年0.253%(1年もの、1000万円以上) |
| 解約条件 | 制約なし | 中途解約時は金利が下がる |
| 目的適合 | 生活費・緊急資金向け | 使う時期が決まった資金向け |
- 2025年4月時点の平均
- 流動性
普通預金はいつでも自由に引き出せますが、定期預金は原則として満期まで引き出せません - 金利
定期預金の方が高く設定されています - 解約条件
定期預金を満期前に解約すると、金利が大幅に下がります
以上より、定期預金は「いつ使うかがはっきりしている資金」に向いていることがわかります。
一方で、いつ必要になるかわからない生活防衛資金は、普通預金のまま置いておく方が安心です。
満期・自動継続・中途解約のルール
定期預金を利用するうえで、満期・自動継続・中途解約という3つのルールは必ず理解しておきましょう。
これらを知らないと、思わぬタイミングで不利な金利が適用されたり、資金が引き出せなくなったりする可能性があります。
満期とは
満期日とは、預入期間が終了する日のことです。たとえば1年定期なら、預け入れた日から1年後が満期日になります。満期日を迎えると、元本と利息を合わせた金額が指定口座に戻ります。
満期後の資金の扱いは、契約時の設定によって変わります。たとえば、「満期後は普通預金に戻す」と設定していれば、自動的に普通預金口座に入金されます。
一方で、何も設定していないと、次に説明する自動継続が適用されることがあります。
自動継続とは
自動継続とは、満期を迎えた定期預金が自動的に同じ期間・同じ条件で更新される仕組みです。多くの銀行では、契約時に「元金継続」か「元利継続」のどちらかを選びます。
- 元金継続
満期時の元金だけを再び定期預金にして、利息は普通預金に入金される - 元利継続
満期時の元金と利息を合わせた金額を再び定期預金にする
一見すると、元利継続の方が複利効果で有利に見えるでしょう。しかし、ここに落とし穴があります。
それは、自動継続時の金利は「継続時点の店頭表示金利」が適用されることです。つまり、もし金利が下がっていれば、当初よりも不利な条件で再スタートすることになります。
自動継続を止めたい場合は、満期前に銀行窓口やネットバンキングで手続きを行う必要があります。満期の1週間前までには確認しておくと安心でしょう。
中途解約とは
中途解約とは、満期を待たずに定期預金を解約することです。急な出費が必要になった場合には便利ですが、大きなデメリットがあります。それは、中途解約時の利率が大幅に下がることです。
多くの銀行では、中途解約すると普通預金と同じ金利、もしくは銀行が定める「所定の低利率」が適用されます。たとえば、年0.3%の1年定期に預けていても、半年で解約すると年0.001%程度の金利しか受け取れないケースがあるのです。
つまり、せっかく定期預金に預けても、途中で引き出せば普通預金とほとんど変わらない利息しかもらえません。これは意外と見落としがちなポイントといえるでしょう。
中途解約に必要な手続きは、通帳・届出印・本人確認書類を持って銀行窓口に行くのが一般的です。手続きの方法は、申し込み前に確認しておくと安心でしょう。
申込前に確認すべきチェックリスト
定期預金を申し込む前に、次の4点を必ず確認しましょう。
- 継続方式は元金継続か元利継続か
- 満期の通知方法はメールか郵送か
- 満期資金はどの口座に受け取るか
- 中途解約時の利率はどこで確認できるか(銀行の公式サイトに記載されています)
これらを事前に確認しておけば、後で「思っていた金利がもらえなかった」「いつの間にか自動継続されていた」という失敗を防げます。
特に中途解約利率については、各銀行の公式サイトで確認しておくことをおすすめします。
定期預金が資産形成に不向きな3つの理由

資産形成の視点で定期預金を見ると、利回りの低さ・インフレによる実質目減り・金利上昇局面での固定化リスクという3つの問題があります。
これらを理解すると、定期預金を使うべきかどうかの判断がぐっと早くなります。
利回りの低さと複利効果の弱さ
定期預金の最大の課題は、金利の低さです。
2025年4月時点で、定期預金(1年もの、1000万円以上)の平均金利は年0.253%です。100万円を1年間預けても、税引き前で2530円、税引き後では約2016円しか増えません。
この金利水準を、他の金融商品と比較してみましょう。
金利・利回りの比較(2025年9月時点の参考値)
| 商品 | 金利・利回り(年率) | 特徴 |
|---|---|---|
| 普通預金 | 0.182% | いつでも引き出し可能 |
| 定期預金(1年) | 0.253% | 満期まで原則引き出し不可 |
| 個人向け国債(変動10年) | 1.06% | 半年ごとに金利見直し、中途換金可能 |
この表を見ると、個人向け国債の方が定期預金の約4倍の利回りであることがわかります。もちろん個人向け国債にも「発行から1年間は解約できない」などの制約はありますが、金利水準の差は明らかです。
次に、100万円を1年・3年・5年の定期預金(年0.253%)に預けた場合の受取利息を計算してみます。
100万円を預けた場合の受取利息(定期預金、年0.253%)
| 預入期間 | 税引き前の利息 | 税引き後の利息 |
|---|---|---|
| 1年 | 2,530円 | 2,016円 |
| 3年 | 7,590円 | 6,048円 |
| 5年 | 12,650円 | 10,080円 |
- 税率は利子所得に対する20.315%(所得税および復興特別所得税15.315% + 住民税5%)を適用しています。
以上より、5年間預けても1万円程度しか増えないことがわかります。さらに、後述するインフレ率を考慮すると、実質的にはお金の価値が目減りしている可能性が高いのです。
また、定期預金は単利計算が基本なので、複利効果もほとんど期待できません。複利効果とは、利息に対して再び利息がつくことで、資産が雪だるま式に増えていく効果のことです。
投資信託などでは複利効果が大きな武器になりますが、定期預金では微々たるものです。
インフレによる実質的な目減り
定期預金の金利が0.2〜0.3%だとしても、物価が上がっていればお金の価値は実質的に目減りします。
この「実質的な目減り」を理解するために、インフレ率と実質金利という考え方を押さえましょう。
2025年3月時点の消費者物価指数(生鮮食品を除く総合、コアCPI)は、前年比で3.2%上昇しています。つまり、去年100円で買えたものが今年は103円かかる計算です。一方で、定期預金の金利は年0.253%です。
この状況で100万円を1年間定期預金に預けると、1年後には約100万2530円になります(税引き前)。しかし、物価が3.2%上がっているため、100万円の購買力は約96万9000円相当に下がっています。
このギャップを示すのが「実質金利」です。実質金利は次の式で近似的に計算できます。
実質金利 ≒ 名目金利 − インフレ率
2025年の状況に当てはめると、
実質金利 ≒ 0.253% − 3.2% = −2.947%
つまり、定期預金に預けていても、実質的には年率約3%のペースで資産価値が目減りしていることになります。
「定期預金に預けておけば減らない」というのは、額面上の話にすぎません。実際には、物価上昇に追いつかないペースでしか増えないため、買えるものが少しずつ減っていくのです。
実際、日本銀行(日銀)は2%のインフレ目標を掲げており、今後もある程度の物価上昇が続く可能性があります。そうした局面では、定期預金だけで資産を守るのは難しいといえるでしょう。
金利上昇時の固定化リスク
定期預金のもう一つの問題は、「固定金利の長期定期に預けると、途中で金利が上がっても恩恵を受けられない」ことです。これを固定化リスクと呼びます。
たとえば、年0.3%の5年定期に100万円を預けたとします。翌年、日本銀行の金融政策の変更などで市場金利が上昇し、定期預金の金利が年0.8%になったとしましょう。
この場合、新規で預ける人は年0.8%の金利を受け取れますが、すでに5年定期に預けているあなたは年0.3%のままです。中途解約して預け直せば新しい金利を受けられますが、中途解約時の利率は大幅に下がるため、結果的に損をします。
実際、2024年以降は日本銀行の金融政策が転換し、預金金利が緩やかに上昇しています。2025年1月には政策金利が0.5%程度まで引き上げられ、メガバンクの普通預金金利も0.2%に上昇しました。こうした金利上昇局面では、短期で回す方が有利になります。
下の表で、長期固定と短期で回す場合の利息差を比較してみましょう。
金利上昇局面でのシミュレーション(100万円、5年間)
| 預け方 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 合計利息 (税引き前) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年定期 (年0.3%固定) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 15,000円 |
| 1年定期で毎年乗り換え | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 32,000円 |
- 2年目以降は金利が0.5%、3年目以降は0.8%に上昇すると仮定
このシミュレーションはあくまで一例ですが、短期で回す方が金利上昇の恩恵を受けやすいことがわかります。
もちろん、金利が下がる局面では長期固定の方が有利になるため、一概にどちらが良いとは言えません。
ただし、現在の日本は長らく続いた低金利から脱却しつつあります。こうした局面では、長期の固定金利に縛られるリスクをよく考える必要があります。
定期預金の使い勝手が悪い3つの理由

定期預金は運用面での手間や制約も多くあります。
ここでは、満期前に引き出せない制約・預入単位や期間の制限・自動継続による管理の煩雑さという3つのポイントを解説します。
満期前に引き出せない・中途解約は不利
定期預金の最大の不便さは、満期前に自由に引き出せないことです。もし急に現金が必要になった場合、中途解約しなければなりません。しかし、中途解約すると金利が大幅に下がります。
多くの銀行では、中途解約時には普通預金と同じ金利や、銀行が定める「所定の低利率」が適用されます。たとえば、年0.3%の1年定期に預けていても、半年後に解約すると年0.001%程度の金利しか受け取れないこともあります。
下の表で、主要銀行の中途解約時の取り扱いを比較しました。
主要銀行の中途解約時利率の考え方(参考)
| 銀行 | 中途解約時の利率 |
|---|---|
| A銀行 | 普通預金金利を適用 |
| B銀行 | 所定の低利率を適用(詳細は各銀行サイト参照) |
| C銀行 | 預入期間に応じた段階的な利率を適用 |
- 具体的な数値は各銀行の公式サイトで必ず確認してください
このように、中途解約時の利率は銀行によって異なります。定期預金を申し込む前には、必ず各銀行の「中途解約時利率」のページを確認しておきましょう。
では、どうすれば中途解約のリスクを減らせるでしょうか。答えは、生活防衛資金は定期預金に入れないことです。
生活防衛資金とは、病気や失業などの緊急時に備えて確保しておく資金のことです。この資金は流動性の高い普通預金や決済用預金に置いておき、すぐに引き出せる状態にしておくことが大切です。
定期預金に預けるのは、「1年後の結婚式の費用」「3年後の車の買い替え資金」など、使う時期がはっきりしている資金だけにしましょう。
資産運用、誰に相談する?
簡単な質問に回答するだけ!
あなたに合った資産運用アドバイザーを紹介
\ 簡単60秒!相談料はずっと無料 /
預入単位・期間の制約
定期預金には、最低預入金額や期間選択の制約があります。これが原因で、自分の目的とのミスマッチが起きやすくなります。
多くの銀行では、定期預金の最低預入金額は1万円や10万円に設定されています。また、期間は1か月・3か月・6か月・1年・3年・5年といったように、あらかじめ決められた選択肢の中から選ばなければなりません。
たとえば、「8か月後に使う予定の資金」があったとしても、6か月か1年のどちらかを選ぶしかありません。6か月を選べば少し早く満期を迎えてしまいますし、1年を選べば4か月も余計に資金が拘束されます。
こうしたミスマッチを避けるために、期間分散という考え方があります。期間分散とは、満期日をずらして複数の定期預金に分けて預けることです。
たとえば、300万円を一度に1年定期に預けるのではなく、3か月ごとに100万円ずつ預けていきます。こうすると、3か月ごとに満期を迎えるため、必要なタイミングで引き出しやすくなります。
期間分散の例(300万円を3か月ごとに分散)
| 預入時期 | 金額 | 満期時期 |
|---|---|---|
| 1月 | 100万円 | 翌年1月 |
| 4月 | 100万円 | 翌年4月 |
| 7月 | 100万円 | 翌年7月 |
このように分散することで、流動性を保ちながら定期預金のメリットを活かせます。
もう一つのポイントは、ボーナス時に一括で預けるのではなく、月次や四半期で分散して預けることです。これにより、金利が変動した際にも柔軟に対応できるようになります。
自動継続と休眠化のリスク
定期預金の管理で見落としがちなのが、自動継続と休眠化のリスクです。
自動継続とは、満期を迎えた定期預金が自動的に同じ期間で更新される仕組みです。便利な反面、次のような問題があります。
- 満期時点の金利が低ければ、不利な条件で再スタートする
- 満期の通知を見落とすと、いつの間にか何度も更新されている
- 長期間放置すると、休眠口座になる恐れがある
休眠化とは、長期間取引のない口座が「休眠預金」として扱われることです。2018年の法改正により、10年以上取引のない預金は休眠預金等活用法に基づいて公益活動に活用される仕組みが始まりました。
もちろん、後から請求すれば引き出せますが、手続きが煩雑になります。
こうしたリスクを避けるために、次の対策を取りましょう。
【自動継続を止め忘れないための対策】
- ネットバンキングの満期通知設定をオンにする
- スマホやパソコンのカレンダーに満期日を登録する
- 満期の1か月前に銀行に確認する習慣をつける
- 店頭で申し込む際に、自動継続オフの手続きを明示的に依頼する
特にネットバンキングの通知機能は便利です。多くの銀行では、満期日の数週間前にメールやアプリで通知してくれます。必ず設定しておきましょう。
また、満期日を管理するための簡単なシートを作っておくのもおすすめです。エクセルや手帳に、次のような項目を記録しておきましょう。
満期管理シートの例
| 銀行名 | 預入日 | 満期日 | 金額 | 金利 | 自動継続の有無 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A銀行 | 2025/1/10 | 2026/1/10 | 100万円 | 0.3% | オフ | 教育費用 |
| B銀行 | 2025/4/1 | 2026/4/1 | 50万円 | 0.25% | オフ | 旅行資金 |
このように記録しておけば、うっかり忘れてしまうリスクを大幅に減らせます。
資産運用、誰に相談する?
簡単な質問に回答するだけ!
あなたに合った資産運用アドバイザーを紹介
\ 簡単60秒!相談料はずっと無料 /
定期預金の安全性にも限界がある理由

定期預金は安全と言われますが、「安全=無制限」ではありません。
ここでは預金保険制度の保護範囲と、同一銀行内での合算ルール(名寄せ)について解説します。
預金保険の上限は1,000万円+利息
定期預金や普通預金などの一般預金等は、預金保険制度によって保護されています。しかし、保護されるのは「1金融機関ごと・預金者1人あたり・元本1,000万円までと破綻日までの利息」です。
つまり、1つの銀行に1,000万円を超える預金がある場合、超えた分は保護されません。
もし銀行が破綻した場合、1,000万円を超える部分は破綻した銀行の残余財産から配当される形になるため、全額戻ってこない可能性があります。
一方で、決済用預金は全額保護されます。決済用預金とは、次の3つの要件を満たす預金のことです。
- 無利息であること
- 要求払いであること(いつでも払い戻しができること)
- 決済サービスを提供できること
無利息の普通預金や当座預金などが決済用預金に該当します。こちらは金額の上限なく、全額が保護されます。
一般預金等と決済用預金の比較
| 種類 | 保護範囲 | 該当する預金 |
|---|---|---|
| 一般預金等 | 元本1,000万円 + 破綻日までの利息 | 定期預金、利息のつく普通預金など |
| 決済用預金 | 全額保護 | 無利息の普通預金、当座預金など |
この仕組みを理解しておけば、もし1,000万円を超える資金がある場合には、複数の銀行に分散する、または一部を決済用預金にするといった対策が取れます。
同一金融機関で合算される仕組み
預金保険制度には、もう一つ重要なルールがあります。それは、同一金融機関内で複数の口座を持っていても、すべて合算されるということです。
たとえば、A銀行に普通預金で800万円、定期預金で600万円の合計1,400万円を預けているとします。
この場合、銀行が破綻すると、保護されるのは1,000万円と破綻日までの利息のみです。残りの400万円は、銀行の残余財産から配当されるため、全額戻ってくる保証はありません。
この合算のことを「名寄せ」と呼びます。名寄せとは、同一銀行内のすべての口座を預金者ごとに集計し、保護対象金額を確定する作業のことです。
ただし、持株会社の傘下であっても、「銀行ごと」に判定される点には注意が必要です。
たとえば、同じグループ内でもA銀行とB銀行は別の銀行として扱われるため、それぞれ1,000万円ずつ保護されます。
合算の例(A銀行に複数口座がある場合)
| 口座 | 預金額 | 保護される金額 |
|---|---|---|
| 普通預金 | 800万円 | 合算で1,000万円 + 利息のみ保護 |
| 定期預金 | 600万円 | 合算で1,000万円 + 利息のみ保護 |
| 合計 | 1,400万円 | 1,000万円 + 利息(残り400万円は保証なし) |
このルールを踏まえると、1,000万円を超える資金を預ける場合の対策は次の2つです。
- 複数の金融機関に分散する
A銀行に1,000万円、B銀行に400万円というように分けて預ける - 一部を国債などに振り替える
預金保険の対象外である国債や投資信託に一部を移し、リスクを分散する
定期預金が向いている人・向いていない人とは

ここまでの内容を踏まえて、定期預金が向いている人と向いていない人の特徴を整理します。自分がどちらに当てはまるか確認してみましょう。
向いていない人の特徴
次のような人は、定期預金を避けるか、利用する比率を低めにした方が良いでしょう。
- インフレ率が金利を上回る状況を受け入れられない人
実質的にお金の価値が目減りすることに抵抗がある場合、定期預金は不向きです - 満期前に使う可能性が高い人
急な出費が予想される場合、中途解約のペナルティがあるため、普通預金や流動性の高い商品の方が適しています - 1,000万円を超える資金を単一の銀行に置きがちな人
預金保険の上限を超える部分は保護されないため、複数の銀行に分散するか、他の商品と組み合わせる必要があります - 金利上昇局面で機会損失を避けたい人
長期の固定金利に縛られると、金利が上がっても恩恵を受けられません。短期で回すか、変動金利の商品を検討しましょう - 運用の目的や期限が明確な人
資産を増やす目的であれば、個人向け国債やつみたてNISAなど、より高い利回りが期待できる商品の方が適しています
特に、つみたてNISAなどの非課税制度の利用を迷っている方は、定期預金の比率を低めにすることをおすすめします。
資産形成を目的とするなら、インフレに負けない成長が見込める商品を中心に据えた方が良いでしょう。
向いている人の特徴
一方で、次のような人には定期預金が適しています。
- 生活防衛資金の一部を安全に置きたい人
ただし、すべてを定期預金にするのではなく、流動性の高い普通預金と組み合わせることが大切です - 使途と期限が近い資金を管理したい人
たとえば、1年後の教育費や3年後の納税資金など、使う時期がはっきりしている資金は定期預金に向いています - 価格変動のある商品に心理的抵抗が強い人
投資信託や株式は価格が上下するため、それが不安な場合は元本保証の定期預金が安心です - 家計合議で元本確保が最優先の人
家族と話し合った結果、「絶対に元本を減らしたくない」という結論になった場合、定期預金は有力な選択肢です
定期預金を使うなら守りたい条件
ただし、定期預金を使う場合でも、次の条件を満たすことが重要です。
- 短期(1年以内)で預ける
- 満期をずらして複数に分散する(ラダー)
- 1つの銀行に1,000万円を超えて預けない
- 自動継続はオフにして、満期ごとに見直す
これらを守れば、定期預金のデメリットを最小限に抑えながら、メリットを活かせます。
定期預金の代わりに検討したい3つの選択肢

定期預金以外にも、安全性や流動性、実質的な利回りを重視した選択肢があります。
ここでは、個人向け国債・つみたてNISA(投資信託)・普通預金と短期定期の組み合わせという3つの代替案を紹介します。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 個人向け国債 (変動10年) | 半年ごとに金利見直し、元本保証、中途換金可能(一定コスト) | 発行から1年間は解約不可 |
| NISA・投資信託 | 長期での成長が期待できる、非課税 | 価格変動リスクあり |
| 普通預金 + 短期定期 | 流動性と金利のバランスが取れる | 単体では利回りが低い |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
個人向け国債(変動10年)
個人向け国債は、国が発行する債券で、元本割れがなく、満期まで保有することで元本が全額返金されます。
中でも「変動10年」は、半年ごとに金利が見直されるため、金利上昇局面でも恩恵を受けやすい商品です。
個人向け国債(変動10年)の特徴
2025年9月募集分の変動10年の初回適用利率は年1.06%(税引き前)です。これは定期預金の約4倍の水準です。
金利は半年ごとに見直され、実勢金利の動きに応じて変動します。もし今後金利が上昇すれば、それに合わせて受け取れる利息も増えます。一方、金利が下がっても、最低金利(年0.05%)が保証されているため、大幅に下がる心配はありません。
中途換金も可能ですが、発行から1年間は解約できません。また、解約時には直前2回分の利息相当額×0.79685が差し引かれます。ただし、定期預金のように「普通預金金利まで下がる」といった大きなペナルティはありません。
財務省の公式サイトでは、毎月の利率やシミュレーションツールが用意されているので、申し込み前に確認しましょう。
たとえば、100万円を変動10年に投資した場合、半年後に受け取る利息は次のように計算できます。
100万円 × 1.06% × 1/2(半年間)
= 5,300円(税引き前) 税引き後:約4,223円
定期預金(年0.253%)と比べると、半年で約2,000円も多く利息を受け取れます。
向いている人
個人向け国債の変動10年は、次のような人に向いています。
- 中期的に使う予定がある資金(3〜10年後)
- インフレに対する耐性を高めたい人
- 元本保証を重視しつつ、定期預金よりも高い利回りを求める人
個人向け国債は額面での買い取りなので、市場での売買による価格変動リスクはありません。この点は初心者にも安心です。
NISAで積立投資
つみたてNISAは、長期の資産形成を目的とした非課税制度です。投資信託を積み立てることで、株式や債券などに分散投資でき、長期的には実質的な成長が期待できます。
NISAの特徴
2024年から制度が恒久化され、年間投資枠も拡大しました。 通常、投資で得た利益(配当金や売却益)には通常20.315%の税金がかかりますが、NISA口座なら非課税です。
ただし、NISAで保有する商品には価格変動リスクがあります。株式市場が下落すれば、一時的に元本を下回ることもあります。そのため、長期(10年以上)で運用し、時間をかけてリスクを分散することが大切です。
向いている人
つみたてNISAは、次のような人に向いています。
- 10年以上の長期で資産を増やしたい人
- インフレに負けない実質的な成長を求める人
- 価格変動を受け入れられる人
重要なのは、生活防衛資金は別枠で確保しておくことです。NISAでの積立投資に回すのは、「当面使う予定のない余裕資金」に限定しましょう。
普通預金と短期定期の組み合わせ
もう一つの選択肢は、普通預金と短期定期を組み合わせる方法です。
これは、流動性と金利のバランスを取りたい人に向いています。
具体的な手順
- 必要な月数を算定する
生活費の3〜6か月分を生活防衛資金として確保します - 生活防衛資金は普通預金へ
いつでも引き出せるよう、普通預金や決済用預金に置きます - 目的資金は短期定期へ
使う時期が決まっている資金は、1〜3か月の短期定期に預けます - 満期を分散する
たとえば、300万円を3か月ごとに100万円ずつ預けることで、満期のタイミングを分散します - 自動継続はオフにする
満期ごとに金利を見直し、必要なら乗り換えます
この方法のメリットは、短期で回すため金利の変動に柔軟に対応できることです。もし金利が上がれば、次の満期で新しい金利を適用できます。
向いている人
この方法は、次のような人に向いています。
- 生活防衛資金と目的資金を明確に分けたい人
- 金利の変動に応じて柔軟に乗り換えたい人
- 定期預金のデメリットを最小限に抑えたい人
ここまで、定期預金に代わる3つの方法を紹介しましたが、実際には、この3つの選択肢を組み合わせることも可能です。
たとえば、生活防衛資金は普通預金、目的資金は短期定期、余裕資金はNISAでの積立投資、といった具合です。
自分の状況に合わせて、最適な組み合わせを見つけましょう。
定期預金の選択に迷ったら専門家への相談がおすすめ

ここまで読んで「自分一人では判断しきれない」と感じた方もいるでしょう。
そんな時は、資産運用アドバイザーへの相談を検討してみてください。
相談で得られるメリット
専門家に相談すると、次のような具体的なアドバイスが得られます。
- あなた専用の資産配分(生活防衛資金・目的資金・運用資金)の提案
家計の状況や今後のライフイベントを踏まえて、資金をどう分けるべきか具体的に提示してもらえます - 期待リターンのシミュレーション
現在の金利環境や将来の見通しを踏まえた上で、どの程度の利回りが期待できるか試算してもらえます - 保有商品の見直し
すでに保有している金融商品がある場合、その手数料や運用コストを一覧にして確認できます
アドバイザーに相談することで、「何となく不安」という状態から、「やるべきことが明確」な状態に変わるのが大きなメリットでしょう。
相談が向いている人・向いていない人
- どの資金をどこに置くべきか、判断軸が定まらない人
- 家族と話し合いながら決めたい人
(配偶者と一緒に相談できる場合もあります) - 預金額が大きく、選択ミスのリスクが高い人
- 短期間で高利回りを期待している人
(専門家は現実的な提案をするため、期待に沿えない場合があります) - 投機的な判断を求める人
(資産運用アドバイザーは長期的な視点での提案が基本です)
なお、相談時には中立性や手数料の透明性を確認することが大切です。
特に、販売手数料が発生する商品を勧められる場合は、利益相反がないかをよく確認しましょう。
相談先の候補と選び方
相談先には、証券会社・銀行・FP・IFAなどがあります。それぞれの特徴を比較しましょう。
| 相談料 | 報酬体系 | 取扱商品 | 中立性 | オンライン対応 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 証券会社 | 無料 | 販売手数料 | 自社商品中心 | 会社方針に影響されがち | 多くが対応 |
| 銀行 | 無料 | 販売手数料 | 自社商品中心 | 会社方針に影響されがち | 一部対応 |
| FP | 有料 | 相談料 | 取扱なし | 中立性が高い | 対応可能 |
| IFA | 無料 | 販売手数料 | 幅広い選択肢 | 中立性が高い | 対応可能 |
FPやIFAは、特定の金融機関に属さないため、幅広い選択肢から中立的な提案を受けられる点が特徴です。
また、FPは具体的な商品の提案ができないことが多いが、IFAであれば商品選定までサポートすることができる。
【相談先を選ぶ際のチェックポイント】
- 報酬体系は明確か(無料なのか有料なのか、手数料はどこで発生するのか)
- どの商品を取り扱っているか
- 利益相反管理の方針が公開されているか
- オンラインで相談できるか
- アフターサポートの内容はどうか
これらを確認したうえで、自分に合った相談先を選びましょう。
まとめ

定期預金の「元本保証」は大きな魅力ですが、インフレが進む現在、その安心感だけでは大切なお金の価値を守り切れないかもしれません。「インフレ負け」のリスクを理解し、一歩進んだ対策を始めることが重要です。
この記事でお伝えした、資産を守り育てるための具体的な3つのステップを振り返りましょう。
- 資金を「目的別」に3分割する
まずは全資産を「生活防衛資金」「目的資金」「運用資金」に分類。それぞれの役割に合った置き場所を考えるのが基本です。 - 定期預金の「満期をずらす」
もし定期預金を活用するなら、満期を分散させる「ラダー戦略」で。急な出費にも対応できる流動性を確保できます。 - 「インフレに強い」選択肢を知る
個人向け国債(変動10年)やNISAなど、インフレ下でも価値が下がりにくい金融商品を組み合わせる視点を持ちましょう。
資産形成のプランは人それぞれです。もし具体的な方法に迷ったら、一度FPやIFAのような専門家に相談してみるのもおすすめです。
客観的なアドバイスが、あなたの次の一歩を後押ししてくれるでしょう。
FAQ
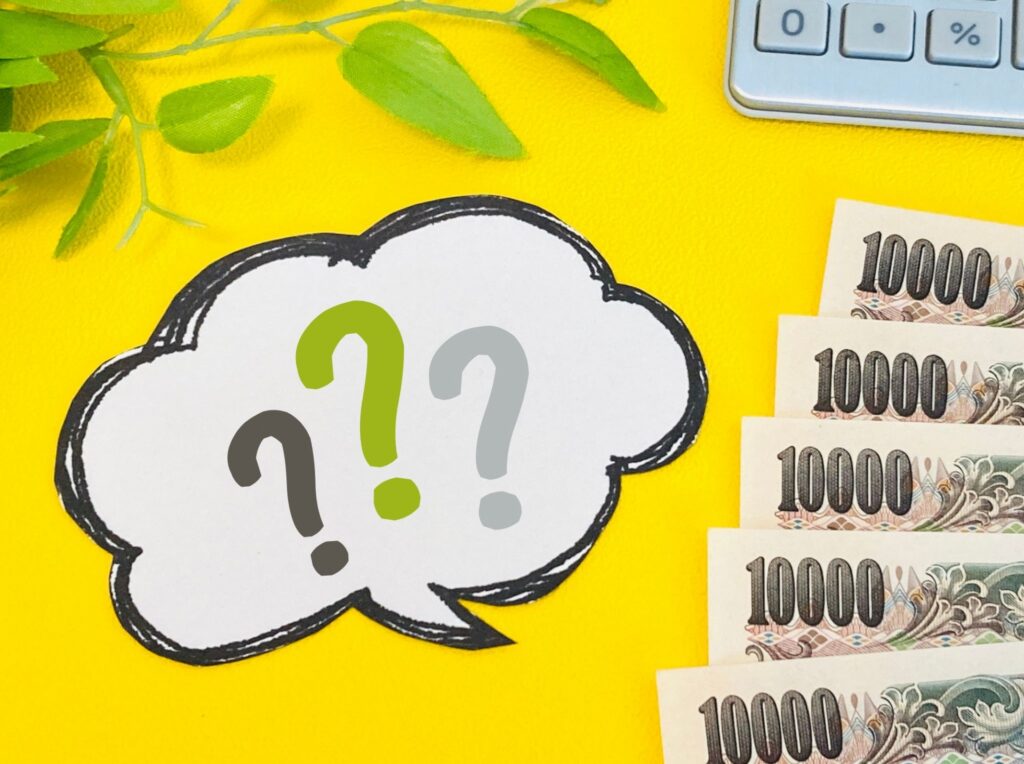
出典一覧
預金種類別店頭表示金利の平均年利率等:日本銀行 Bank of Japan
3メガバンク、普通預金金利0.2%に 日銀利上げ受け:日本経済新聞