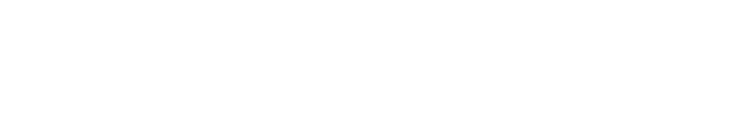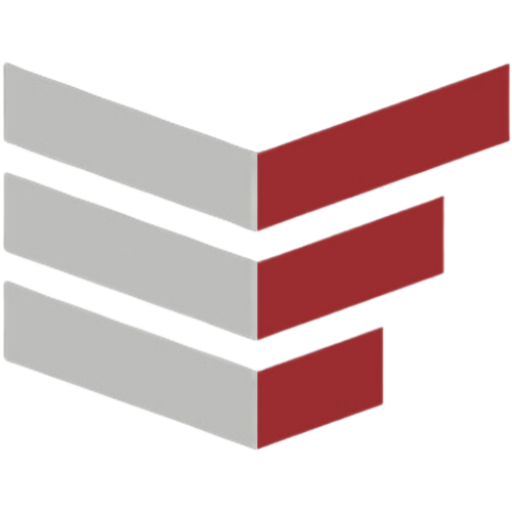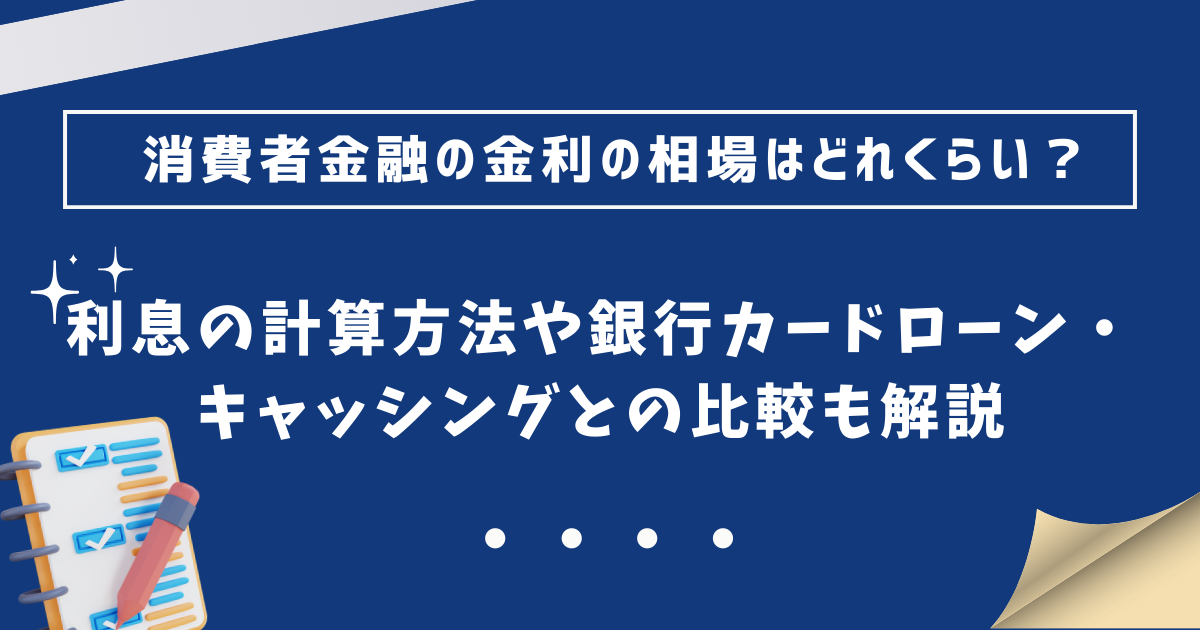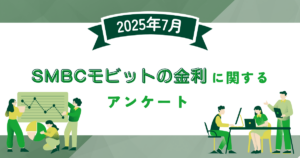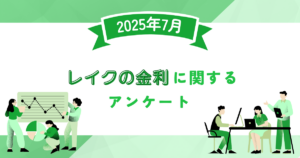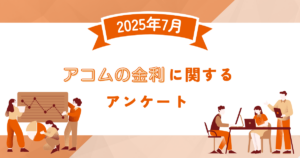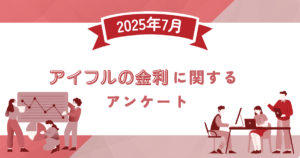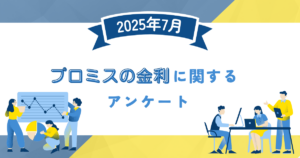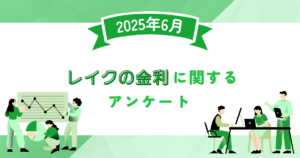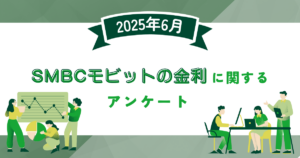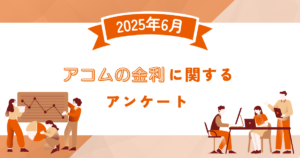消費者金融を利用する際に気になるのが金利ではないだろうか。数%の違いでも借入額が大きかったり返済期間が長引いたりすれば負担は大きく変わってしまう。
そのため、自分が借入を検討している消費者金融の金利が相場に対して高めなのか低めなのかは気になるはずだ。
そこで、本記事では金利の相場について解説する。また、利息の計算方法や銀行カードローン、キャッシングとの比較もあわせて説明する。消費者金融を選ぶ際の参考にしてほしい。
※当サイトには広告が含まれます。※当サイトは広告収入を得て運営しております。
消費者金融の金利相場は3%〜18%前後

消費者金融の金利相場は、日本貸金業協会が公表している統計によると平均で約15.32%だ。参考までに他の金利との比較も表で整理した。
| 平均約定金利 | |
|---|---|
| 消費者向け無担保貸付 | 15.32% |
| 消費者向け有担保貸付 | 4.25% |
| 消費者向け住宅向貸付 | 2.08% |
| 事業者向け無担保貸付 | 13.63% |
| 事業者向け有担保貸付 | 3.76% |
消費者金融のカードローンは担保や保証人不要で借入できる「消費者向け無担保貸付」に該当する。
上記からもわかるように、その金利は消費者向け貸付の中でも特に高めであることが分かる。
借りたお金の用途が自由で担保もいらないため利便性が高い分、金利も高めになると考えれば分かりやすいだろう。
次に実際の消費者金融の金利を確認してみよう。大手から中小の消費者金融を以下にまとめてみた。
| 金利 | ||
|---|---|---|
| プロミス(大手) | 4.5%〜17.8% | |
| レイク(大手) | 4.5%〜18.0% | |
| SMBCモビット(大手) | 3.0%〜18.0% | |
| アコム(大手) | 3.0%〜18.0% | |
| アイフル(大手) | 3.0%〜18.0% | |
| フクホー(中小) | 7.3%〜20.0%(5〜10万円借入の場合。10万円以上なら上限18.0%) | |
| ライフティ(中小) | 8.0%〜20.0% |
大手だけでみると、金利の相場は3.0%〜18.0%といったところだろう。中小まで含める上限20.0%まで設定しているところもある。
※当サイトには広告が含まれます。※当サイトは広告収入を得て運営しております。
消費者金融と銀行カードローン・クレジットカードのキャッシングとの金利比較

担保や保証人なしで借入ができる銀行カードローンとクレジットカードキャッシングとも比較してみよう。
一概には言えないところもあるが、傾向として以下のようになる。
| 金利 | 借入限度額 | |
|---|---|---|
| 消費者金融 | 高め | 中〜高 |
| 銀行カードローン | 低め | 高 |
| クレジットカードキャッシング | 高め | 低 |
具体例として、それぞれ代表的な商品を2つずつ挙げて以下に整理した。
| 金利 | 借入限度額 | ||
|---|---|---|---|
| アイフル(消費者金融) | 3.0%〜18.0% | 800万円 | |
| プロミス(消費者金融) | 4.5%〜17.8% | 500万円 | |
| 三井住友銀行カードローン | 1.5%〜14.5% | 800万円 | |
| 横浜銀行カードローン | 1.5%〜14.6% | 1,000万円 | |
| 楽天カード(キャッシング) | 18.0% | 90万円 | |
| イオンカード(キャッシング) | 7.8%〜18.0% | 300万円 |
銀行カードローンは金利が低く借入限度額も高い傾向にある。条件面だけでみると銀行カードローンは、消費者金融とキャッシングに比べて有利だ。
ただし、審査が厳しく借入できるまでの期間も余裕をもっておく必要がある。
クレジットカードのキャッシングに関しては、実質的に多くの人が適用される上限金利は消費者金融と同程度だ。
ただし、借入限度額に関しては上限が消費者金融や銀行カードローンに比べると低めに設定されている。
既にキャッシング枠のあるクレジットカードを持っていて少額だけ借りたいという場合は、とても便利に使える。
消費者金融はキャッシングに比べて借入限度額が大きく、借入額や取引実績次第では金利を下げやすいという特徴がある。
銀行カードローンと比べると、金利は高めだがその分、消費者金融の方が即日融資を受けやすかったり審査に通りやすかったりする別のメリットがある。
金利や借入限度額を比較しつつ、他のメリット・デメリットを踏まえて自分にあった商品を選ぶとよい。
※当サイトには広告が含まれます。※当サイトは広告収入を得て運営しております。
消費者金融の金利の決まり方

消費者金融の金利は各社で自由に決められるが、一定の制約がある。消費者金融の金利を比較してみると
20%以上に設定されているところを見かけないはずだ。万一、20%以上の業者を見かけたら違法業者の疑いがあるので注意してほしい。
- 利息制限法
- 利用限度額
消費者金融は、この2つで設定できる金利が制限されている。消費者金融の金利を理解する上で知っておくべきポイントでもあるので解説する。
利息制限法
日本ではお金を借りる人を保護するために利息制限法という法律が定められている。
| 借入額 | 上限金利 |
|---|---|
| 10万円未満 | 20% |
| 10万円〜100万円未満 | 18% |
| 100万円以上 | 15% |
全ての消費者金融が利息制限法の制約の中で、金利を決めている。
そのため、全国の消費者金融の金利を調べても、25%や30%などに設定している業者は見つからないはずだ。
消費者金融各社の金利がどこも多少の差はあれども似たり寄ったりに感じたとすれば、この制限があるためだ。
利用限度額
利息制限法に関連する話になるが、利用限度額も上限金利を決める要素になる。
消費者金融のカードローンは、実際に借入する額ではなく利用限度額によって上限金利が決まる。
利用限度額とは、ここでは審査に応じて各利用者がそれぞれ借入できる上限額のことだ。
借入限度額が10万円未満なら上限金利20%、10万円〜100万円未満なら18%、100万円以上なら15%となる。
利息制限法の借入額の部分を利用限度額に置き換えて考えればよい。
この利息制限法と利用限度額の関係があるため、金利が下がる節目のところまで上限額を引き上げることができれば、法律で定められた上限以上の金利だった場合は金利引き下げが期待できる。
例えば、利用限度額が80万円で金利が18.0%だった場合、20万円の引き上げに成功すれば、利用限度額100万円となり金利が15.0%に抑えられることになる。
この考え方は消費者金融各社の利用で共通して使えるため参考にしてほしい。
※当サイトには広告が含まれます。※当サイトは広告収入を得て運営しております。
カードローンの利息の求め方
消費者金融を利用する際に気になるのは、借りた額とは別にいくら支払わなければいけないかではないだろうか。
この借りた額とは別に支払う対価が利息だ。利息をお金のレンタル料と考えれば分かりやすい。
利息は金利によって左右される。
カードローンの利用では、具体的な利息の求め方を知っておくことで計画的な利用をしやすくなる。
- 計算式
- 返済シミュレーションの例
- シミュレーションするメリット
利息について理解するために、以上の3つを確認してみよう。
計算式
計算式は以下の通り。
この式に具体的な数字を代入すれば利息が計算できる。例えば、3万円を30日間、実質年率20%で借りた
場合を計算してみよう。式に代入すると以下のようになる。
この場合は3万円を借りると利息は493円となる。3万円を借りた場合のレンタル料が493円と理解してもよいだろう。金利を2%下げて18.0%にした場合も計算してみよう。
金利を2%下げただけでも利息が50円も変わる。金利がいかに利息に影響するのかも感じ取れる例ではないだろうか。では、次は利用日数を倍の60日にして計算してみよう。
日数を倍にすると利息も約2倍になった。同じ額を借りるにしても金利や利用日数次第で随分、利息が変わることがお分かりいただけたのではないだろうか。
金利は低めに、返済は早くが利息を下げる原則だ。
返済シミュレーションの例
- 自分でいちいち細かく計算をしたくない
- 利息以外にも毎月、返済する額や具体的な返済期間なども知りたい
- 利息が変わった場合、返済期間を短くした場合どうなるかを知りたい
このように感じた人も多いだろう。消費者金融各社はそれぞれ返済シミュレーションを用意している。
実際には返済シミュレーションを活用して返済計画を立てるのがおすすめだ。アイフルで50万円を借入した場合を想定していくつかシミュレーションをしてみよう。
ケース1:50万円を年率18.0%で借入した場合
| 返済回数 | 返済予定日 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 2024/11/18 | 500,000円 | |||
| 1 | 2024/12/18 | 13,000円 | 5,624円 | 7,376円 | 494,376円 |
| 2 | 2025/1/18 | 13,000円 | 5,452円 | 7,548円 | 488,924円 |
| 3 | 2025/2/18 | 13,000円 | 5,526円 | 7,474円 | 483,398円 |
| 4 | 2025/3/18 | 13,000円 | 6,326円 | 6,674円 | 477,072円 |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 58 | 2029/9/18 | 9651円 | 9,506円 | 145円 | 0円 |
| 累計 | 750,651円 | 250,651円 |
アイフルで毎月、決められた日に最低限決められた額だけ返済した場合のシミュレーションが「ケース1」だ。
この場合、返済に58ヶ月かかり利息は最終的に250,651円になることが分かる。
金利を低くしたケース2と返済期間を短くしたケース3も、シミュレーションで確認してみよう。
ケース2:50万円を年率15.0%で借入した場合(金利が低い)
| 返済回数 | 返済予定日 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 2024/11/18 | 500,000円 | |||
| 1 | 2024/12/18 | 13,000円 | 6,853円 | 6,147円 | 493,147円 |
| 2 | 2025/1/18 | 13,000円 | 6,726円 | 6,274円 | 486,421円 |
| 3 | 2025/2/18 | 13,000円 | 6,804円 | 6,196円 | 479,617円 |
| 4 | 2025/3/18 | 13,000円 | 7,482円 | 5,518円 | 472,135円 |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 53 | 2029/04/18 | 9,583円 | 9,463円 | 120円 | 0円 |
| 累計 | 685,583円 | 185,583円 |
ケース3:50万円を年率18.0%で借入した場合(返済期間が短い)
| 返済回数 | 返済予定日 | 返済金額 | 元金充当 | 利息充当 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 借入日 | 2024/11/18 | 500,000円 | |||
| 1 | 2024/12/18 | 21,000円 | 13,624円 | 7,376円 | 486,376円 |
| 2 | 2025/1/18 | 21,000円 | 13,574円 | 7,426円 | 472,802円 |
| 3 | 2025/2/18 | 21,000円 | 13,772円 | 7,228円 | 459,030円 |
| 4 | 2025/3/18 | 21,000円 | 14,662円 | 6,338円 | 444,368円 |
| ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 30 | 2027/5/18 | 13,932円 | 13,729円 | 203円 | 0円 |
| 累計 | 622,932円 | 122,932円 |
金利を18.0%から15.0%に下げた場合は、利息が250,651円から185,583円にまで下がった。
しかし、金利は据え置きの18.0%で返済期間を短くした場合は、毎月の返済額は13,000円から21,000円まで増えるものの利息は250,651円から122,932円まで下がっていることが分かる。
このようにシミュレーションを実際してみることで返済計画の見通しを立てやすくなるだろう。
返済シミュレーションを使うメリット
返済シミュレーションを使うことで以下のようなメリットがある。
- 利息が分かる
- 具体的に返済する額や期間が分かる
- 金利や返済期間を変えた場合の違いを比較できる
- 煩雑な計算をせずにすむ
特に実際の消費者金融では残高に応じて元金と金利を合わせて返済する複雑な計算で、毎月の返済額が決まるケースが多い。
シミュレーションを使えば、煩雑な計算をしなくても返済計画を立てる際に必要な情報が一目で分かる。そのため、積極的に活用していこう。
※当サイトには広告が含まれます。※当サイトは広告収入を得て運営しております。
カードローンの利息を抑える3つの方法

特に消費者金融のカードローンは利息が高くなりがちだ。カードローンの利息で実際に支払う額はなるべく抑えたいところだろう。
利息を抑えるためにすぐにできる以下の3つの方法を紹介する。
- 低金利のカードローンを選ぶ
- 繰上げ返済をする
- 無利息期間やキャンペーンを有効活用する
それぞれ確認してみよう。
低金利のカードローンを選ぶ
金利を下げることで利息は下げられる。そのため、利息を下げるなら少しでも低金利のカードローンを選ぼう。
もし、金利だけを重視するなら無担保、用途自由な借入の中では銀行カードローンがおすすめだ。
ただし、金利が低い分、審査にかかる期間が長くなったり厳しくなったりするデメリットもある。
審査や借入にかかる期間なども考えつつ、なるべく低金利なものを選ぶようにしよう。
先に紹介したシミュレーションでも、低金利になれば、以下のような差が出ることを確認できる。
| 50万円の借入(アイフルで毎月決められ額を返済した場合) | 利息 |
|---|---|
| 金利18.0% | 250,651円 |
| 金利15.0% | 185,583円 ※約65,000円利息を抑えた |
実際のところ大手消費者金融の金利はほぼ横並びだ。しかし、取引実績の積み重ねで借入限度額を引き上げることができれば、金利を低くできる可能性がある。
繰上げ返済をする
同じ額を同じ金利で借りても返済期間を短くすれば、利息は減らせる。返済期間を短くするには、繰上げ返済を積極的にしていくことがおすすめだ。
消費者金融は毎月、決められた額を決められた日までに返済するのが基本だ。
しかし、毎月の返済と別に多めに返済して借入残高を減らすことができる。この決められた返済とは別に返済することを繰上げ返済という。
先のシミュレーションでも、繰上げ返済で返済期間を短くすると以下のような差ができることが確認できる。
| 50万円の借入(アイフルで金利18.0%の場合) | 利息 |
|---|---|
| 58回で返済 | 250,651円 |
| 30回で返済(繰上げ返済を利用した場合) | 122,932円※約127,000円の利息を抑えた |
繰上げ返済で毎月の返済額は増えるが利息は減らせる。余裕のあるときに積極的に繰上げ返済をすることで利息を抑えるとよいだろう。
無利息期間やキャンペーンを有効活用する
消費者金融の中には初回契約者向けのお得なキャンペーンを実施していることがある。代表的なのが無利息期間だ。
大手消費者金融の中ではアイフル、アコム、プロミス、レイクの4社が実施している。
アイフルとアコムは契約日の翌日から30日間無利息、プロミスは初回借入から30日間の無利息期間を初回利用者に提供している。
特に大手の中ではレイクは無利息期間が充実している。Web申込なら契約から60日間無利息、またはご契約額が50万円以上なら365日間無利息を選べる。
利息を節約するためにも有効活用しよう。
※当サイトには広告が含まれます。※当サイトは広告収入を得て運営しております。
カードローンの借入先で迷ったら

カードローンが多すぎてどこで借りるか迷ってしまうという人もいるだろう。もし、迷ったら以下の3つの観点から選んでほしい。
- 融資スピード
- 借入額
- 金利
この中から特に何を重視するのかを明確にしておくと、迷いづらくなるはずだ。
融資スピード
今日すぐにでも借りたい、遅くとも明日には借入できていないと困るという人は融資スピードを重視しよう。
融資スピードを見分けるポイントは「即日融資」に対応しているかどうかだ。特に消費者金融大手各社は、融資スピードの点で強みがある。
| 融資スピード | ||
|---|---|---|
| プロミス | 即日融資可:最短3分※1 | |
| レイク | 即日融資可:最短25分 | |
| SMBCモビット | 即日融資可:最短15分 | |
| アコム | 即日融資可:最短20分※2 | |
| アイフル | 即日融資可:最短18分 | |
| 三菱UFJ銀行バンクイック | 即日に審査結果の回答可能。ただし即日融資は難しい。 | |
| 三井住友銀行カードローン | 即日に審査結果の回答可能。ただし即日融資は難しい。 |
- お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
- お申込時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
- 参考:プロミス レイク SMBCモビット アコム アイフル 三菱UFJ銀行 三井住友銀行
借入額
たくさん借りたい人は、カードローンが設定している限度額が高いところを選ぼう。ただし、実際に借入できる額は審査によって決まる点に注意してほしい。
また、借入額の上限を重視するならクレジットカードのキャッシングより、消費者金融または銀行のカードローンのどちらかを選ぶことをおすすめする。
金利
利息を抑えたい人は金利を重視しよう。金利の低さを重視するなら銀行カードローンを選ぶとよい。
大手消費者金融の上限金利が18.0%前後、中小だと20%のところもある。しかし、銀行カードローンなら金利の上限が14%〜15%前後ですむ。
ただし審査はその分長引いたり厳しくなったりする点を許容する必要はあるだろう。
※当サイトには広告が含まれます。※当サイトは広告収入を得て運営しております。
消費者金融の金利の相場を理解して計画的に利用しよう!

消費者金融の金利の相場について解説した。相場は大手と中小を広く確認してみると約3%〜上限20%の範囲におさまる。
ただし、法的な規制もあるため特に上限金利に関しては概ねどこも似たり寄ったりで大きな差はないのが実情だ。
しかし、金利が1%や2%でも違えば借入額が増えたり、返済期間が長引いたりすれば無視できない利息の差になってしまうので、消費者金融を選ぶ際には重視してほしい。
また、本記事で紹介したように消費者金融以外の選択肢もある。
特に金利の低さを重視する場合は銀行カードローンも、審査が厳しくなったり長引いたりすることを許容できれば考えてもよいだろう。
そして計画的な返済をする際には、金利と利息の関係を理解しシミュレーションを積極的に活用することもおすすめする。
金利を理解し、相場を意識して計画的に消費者金融を利用できるようにしよう。
※当サイトには広告が含まれます。※当サイトは広告収入を得て運営しております。