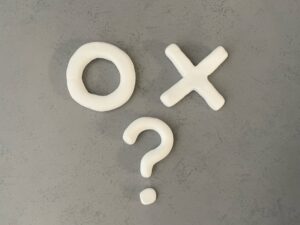- 10歳からでも学資保険に加入すべきか迷っている
- 学資保険のメリットとデメリットを知りたい
- 10歳から教育資金を貯蓄するおすすめの方法が知りたい
子どもの教育や進学の費用を貯蓄する方法として、学資保険を考えている方も多いだろう。
しかし、子供が10歳になってから学資保険に入る意味はあるのだろうか。
結論から言ってしまうと、基本的に10歳から学資保険に入ることはおすすめできない。
そこで本記事は、その理由について解説していく。
また、学資保険の概要と10歳から教育資金を貯蓄する際におすすめの方法について説明する。
子どもの教育資金の貯蓄方法に悩んでいるという方は、参考にしてほしい。
10歳からでも必要?学資保険とは何か

教育資金の準備を検討していると「学資保険」という選択肢が視野に入ってくる。
しかし「実際にどういった商品か分からない」「メリットとデメリットを知りたい」という方も多いのではないだろうか。
ここでは、まず学資保険の特徴やメリット・デメリット、選ぶ際の注意点などを解説していく。
学資保険の特徴
学資保険とは、子どもの教育資金を準備することを目的とした保険商品のことだ。
貯蓄型の保険となっており、支払った保険料を積み立てながら将来の教育資金を準備する仕組みになっている。
学資保険は、子どもが成長していく過程で必要となる進学費用などを備えるケースが多い。
契約時に定めたタイミングで進学祝金・満期保険金などが支給され、まとまった費用がかかる教育費の一部として充当できる。
また、親や保護者などの契約者が万が一死亡した場合、以降の保険料払込は免除となる。
祝金・満期保険金は予定通り支給されるため、万が一の際にもしっかりと教育資金を子どもに残せる点が大きな特徴だ。
万が一の「保障」と積立による「貯蓄」を両立できる点が魅力の商品となっている。
「自分の子どもが希望する進学先を叶えてあげたい」とお考えの方は、学資保険を活用して教育資金を準備しておくと良いだろう。
学資保険に加入するメリット・デメリット
学資保険の加入にあたってはメリットとデメリットがあるため、それぞれ把握しておくことが大切だ。
主なメリットとして以下の2点が挙げられる。
- 貯蓄と保障を両立できる
- 保険料が所得控除の対象となる
前述の通り、学資保険は貯蓄と保障を両立したタイプの商品だ。貯蓄や投資でも教育資金は準備できるが、万が一死亡してしまうと教育資金が足りなくなるリスクがある。
万が一のリスクに備えつつ、教育資金も準備できる点は大きな魅力と言えるだろう。
また、学資保険で支払った保険料は「一般生命保険料控除」として所得控除の対象となる。
一定額が課税所得から差し引ける仕組みとなっており、所得税・住民税の負担を軽減できる点も学資保険のメリットだ。
一方、学資保険のデメリットは以下の2点である。
- 中途解約による元本割れのリスクがある
- インフレに弱い
原則として、学資保険は満期まで保険料を引き出すことができない。
途中解約によって解約返戻金を受け取ることはできるが、支払った保険料を下回る可能性があるため注意が必要だ。
特に早期解約の場合は元本割れのリスクが高いため、保険料の支払いを継続できるか検討した上で加入しよう。
また、学資保険はインフレが起きて物価が上昇する局面では弱いというデメリットがある。
将来的に物価が上昇し、必要な教育資金が増えたときに対応できない可能性がある点は視野に入れておこう。
学資保険を選ぶ際の注意点
学資保険の具体的な商品選びをする際、以下の点に注意が必要だ。
- 返戻率を確かめる
- 払込期間をチェックする
- 保険料の予算を決めておく
学資保険選びの重要なポイントとして返戻率の確認が挙げられる。
返戻率とは、支払ったトータルの保険料に対してどの程度の保険金を受け取れるかという割合を示したものだ。
同じ保障内容の商品であれば返戻率が高い方が良い保険と言えるため、必ず返戻率を確かめておこう。
また、保険料の払込期間をチェックすることも大切だ。
「子どもが18歳になるまで」「10歳まで」などを選べるため、自身のライフプランに合わせて払込期間を選択しよう。
基本的には払込期間が短い方が返戻率が高くなりやすいものの、毎月の保険料も高くなるためバランスを見極めることが重要だ。
そして「保険料をどの程度まで支払えるか」という予算も決めておこう。
前述の通り、途中で解約すると元本割れの可能性が高いため、無理なく支払える範囲を把握しておく必要がある。
加入前に家計を見直し、どの程度の保険料までなら負担できるか確かめておこう。
これらのポイントをしっかりと押さえた上で、自分に合った最適な保険商品を選択しよう。
10歳から学資保険に加入する意味はあるのか

子どもが10歳になり、将来の進学などが現実味を帯びてくると、学資保険などで教育資金を準備した方が良いと考え始める方も多いだろう。
一般的に小学校入学前までに加入するケースが多い学資保険だが、10歳から加入する意味はあるのだろうか。
ここでは、10歳からの学資保険加入可否と加入のメリット・デメリットなどを解説していく。
10歳から学資保険に加入できるのか
基本的には「0歳〜満3歳まで」「満6歳まで」などと年齢の上限を定められていることが多い学資保険だが、10歳でも加入できる商品はある。
「子どもが10歳になってしまったから加入できる商品はない」とあきらめてしまわず、加入できる商品を探してみよう。
例えばかんぽ生命の「はじめのかんぽ」では、大学の入学・在学費用を準備するコースの対象年齢を「0〜12歳」と定めている。
また、三井住友海上あいおい生命の「&LIFEこども保険」も「0〜11歳」までの契約年齢が設定可能だ。
このように10歳からでも加入できる学資保険は存在しているため、自分に合った商品を探してみると良いだろう。
しかし商品の選択肢は少なく、希望する保障内容や返戻率の商品が見つからない可能性もあるため、やはり早めに加入しておくことが大切だ。
10歳から学資保険に加入するメリット・デメリット
10歳から学資保険に加入するメリットとしては、以下の2点が挙げられる。
- 保障と貯蓄が両立できる
- 税負担を軽減できる
前述したメリットと重なる部分が多いが、保障と貯蓄を両立できる点、そして税負担を軽減できる点は大きな魅力と言える。
10歳からの加入は比較的遅い方であるが「万が一のことがあっても確実に教育費を残したい」「所得税・住民税の負担軽減に魅力を感じる」という場合は、10歳からでも学資保険に加入すると良いだろう。
一方、10歳から学資保険に加入する場合は以下のようなデメリットがある。
- 月々の保険料負担が大きい
- 返戻率が低い
10歳での学資保険加入は、0〜6歳までに加入するケースに比べて保険料払込期間が短くなってしまう。
短期間でまとまった資金を準備できるだけの保険料を支払う必要があるため、月々の負担が大きくなる点に注意が必要だ。
また、運用期間が短い分だけ返戻率も低くなってしまう。
通常の場合と比べて受け取れる祝金・保険金が少なくなる可能性が高い。場合によっては元本割れのリスクもあるため注意しておこう。
こうしたメリット・デメリットを踏まえ、本当に10歳から学資保険に加入するべきかどうかを判断することが大切だ。
10歳から学資保険を利用するのはおすすめできない
ここまで10歳からの学資保険加入についてご紹介してきたが、基本的には10歳からの加入はおすすめしない。
なぜなら返戻率が低くなり、月々の保険料負担も大きくなってしまうためだ。
前述の通り10歳からの加入は一般的に比較的遅く、運用期間が短いため、返戻率が低くなってしまう。
月々の保険料が高いにも関わらず元本割れを起こすリスクも想定され、「普通に貯金した方が多くお金を準備できる」という事態に陥る可能性もある。
もちろん、万が一死亡した際に以降の保険料払込が免除され、教育資金も準備できるという点は大きな魅力だ。
しかしわざわざ不利な契約となる学資保険を使わなくても、死亡保険などに加入していれば死亡保険金を教育資金に回すことができる。
学資保険はあくまでも教育資金を準備する目的のひとつであるため、ほかの選択肢で十分に準備できる可能性がある。
「返戻率が低い」「月々の保険料が高い」という不利な状況での学資保険加入にこだわらず、柔軟にほかの選択肢の活用を視野に入れておくと良いだろう。
このように、「いつ学資保険に加入するか」によって保険の適性や活用法は変化し、子どもが10歳の場合には学資保険へ加入するメリットは限定的である。
以下の記事では年代別のおすすめの学資保険についてもまとめているので、比較してみるとより理解を深めることができるはずだ。
学資保険以外で10歳から教育資金を貯蓄するおすすめの方法とは

10歳から教育資金を準備する場合、学資保険以外の選択肢も視野に入れておく必要がある。
さまざまな方法が考えられるが、特に以下の3つの方法による準備がおすすめだ。
- NISA
- 外貨建て保険
- 低解約返戻金終身保険
それぞれの特徴を正しく理解し、自分に合った方法で教育資金の準備を進めていこう。
NISA
NISA(少額投資非課税制度)による運用がおすすめの準備方法のひとつとして挙げられる。本来投資で得た利益に対してかかる約20%の税金が非課税となる制度であるため、効率的に利益を得られる点が大きな特徴だ。
2024年からNISAにはあらたに「成長投資枠」「つみたて投資枠」の2つの非課税枠が設けられ、非課税投資枠や期間が拡大した。中でも「つみたて投資枠」が教育資金の準備に活用しやすい特徴を持っている。
つみたて投資枠は18歳以上が対象となっている制度で、年間120万円までの投資枠から得た利益が恒久的に非課税となる仕組みだ。例えば子どもが生まれたタイミングで運用を始め、大学に進学するまでの期間非課税で運用することで、効率的に資金を準備可能だ。
なお、投資であるため元本割れのリスクがある点には注意が必要だ。
外貨建て保険
外貨建て保険も学資保険以外の選択肢としておすすめだ。外貨建て保険とは、支払った保険料を米ドルや豪ドルなどの外貨で運用する保険商品のことである。
日本に比べて高い金利の通貨を活用し、運用による高いリターンを狙いに行ける点が大きな特徴となっている。
また、外貨建て保険は為替変動による影響を受ける点も特徴のひとつだ。
為替相場が円安になると受け取れる保険金額が増え、円高になると保険金額が減ってしまう。
為替相場の動きによって大きなリターンを得られたり、反対に元本割れをしたりするリスクがある点を頭に入れておくと良いだろう。
そして、外貨で運用するメリットとして「留学費用などに活用できる」という点も挙げられる。
外貨建て保険の保険金・解約返戻金は外貨で受け取れるため、米ドルを受け取って「子どものアメリカ留学の費用に充てる」などといった使い方もできる。
為替変動によるリスクはあるものの、高いリターンが期待できたり、留学費用準備としての使い道があったりなど魅力は多い。
教育資金準備の手段として外貨建て保険も視野に入れておくと良いだろう。
低解約返戻型終身保険
教育資金準備の方法として終身保険もおすすめだ。
特に低解約返戻型の商品であれば、保険料を抑えながら死亡保障を準備し、教育資金の貯蓄もできる。
終身保険は、万が一死亡したときの保障が一生涯にわたって継続する保険商品のことだ。
そして低解約返戻型は、その名の通り途中で解約した場合の返戻金が少ないタイプのことである。
途中解約による返戻金が少ない分、月々の保険料負担は安く抑えられる。
手頃な保険料で一生涯の手厚い死亡保障が得られ、万が一死亡してしまったときでも死亡保険金を子どもの教育費として残すことが可能だ。
また、保険料払込期間後の据置期間を設けると返戻率が上がるという特徴もある。
短期間で保険料を抑えながら払込を終え、返戻率が上がる時期と教育費が必要になるタイミングを合わせることで効率良く資金を準備できる。
ただし途中解約の際には返戻金が少ないため、無理なく契約を継続できるかを確認した上で加入手続きを進めよう。
10歳からは学資保険以外の貯蓄方法を検討しよう

本記事では、「10歳から学資保険に加入する意味があるのか」という疑問について、学資保険の概要やメリット・デメリットと合わせて解説した。
また、10歳から教育資金を貯蓄する際におすすめの方法についても解説した。
学資保険は、早めに加入した方が返戻率が高くなる特徴がある。
そのため、10歳から加入しても満期保険金が保険料を下回る可能性が高く、基本的に加入はおすすめできない。
教育資金を貯蓄する代わりの方法としてはNISAや外貨建て保険、低解約返戻型終身保険などが挙げられるが、その適性は各家庭の事情や目標とする貯蓄額によっても異なるだろう。
もしこれらの比較や自身にとって適切な保険の選択にまよったら、保険のプロに相談することも検討してみよう。
一人一人に合ったアドバイスをもらうことで、お子様に必要な保険を的確に判断することができるはずだ。
また、全国の保険のプロから自分に合った担当者を探す際には「生命保険ナビ」の活用をおすすめする。
「生命保険ナビ」は、自身の条件に合った保険のプロを簡単に見つけることができるマッチングサービスである。
気になった担当者とは無料相談もできるので、ぜひ活用してほしい。