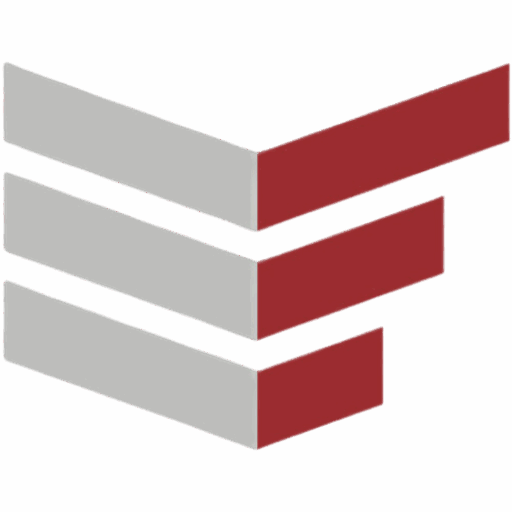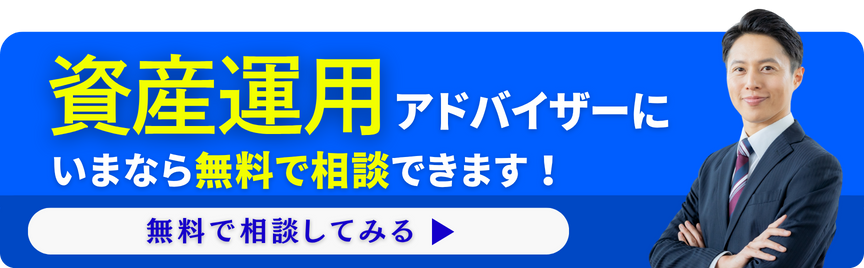- 資産管理会社を設立するべきか迷っている
- いくら資産があれば作るべきなのか知りたい
- 資産管理会社を作りたいが、何から始めればいいかわからない
資産管理会社とは、個人が保有する不動産や金融資産を法人名義で管理・運用する目的で設立される会社である。
かつては富裕層や事業オーナーに限られる印象があったが、相続対策や税制優遇などの多彩なメリットが注目されるにつれ、個人投資家にも選択肢として浸透しつつある。
もっとも、資産規模や投資スタイルによっては、法人化によるコスト負担や手間がかえって大きくなる場合もあるため、事前の十分な検討が欠かせない。
そこで本記事では、資産管理会社の検討に必要な情報を整理し、丁寧に解説した。
読み進める中で、資産管理会社を作るメリット・デメリット、設立に必要な資金や手続きなどの理解を深めていただける。
記事の情報が、資産管理会社の設立や活用を、より具体的に検討する一助となれば非常に嬉しい。

証券アナリスト
監修者: 平 行秀
新卒で野村證券に入社し、富裕層1,000人以上の資産運用コンサルを担当する。 その後、2019年にアドバイザーナビ株式会社を創業し、代表取締役へ。 投資家とアドバイザーをつなぐマッチングプラットフォームを運営している。
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)。
資産管理会社とは?いくらから必要?

ここでは資産管理会社の定義と、他の法人形態との違い、そして実際にどの程度の資産額から設立を検討すべきかを解説する。
資産管理会社の定義
資産管理会社とは、不動産や株式などの資産を所有・管理する目的で設立される法人の総称である。
資産を法人に移管し、その法人が保有・管理しながら投資や運用を行うため、個人名義のまま保有する場合と比べて税制面・相続面などで多様なメリットが生じるとされる。
 証券アナリスト 平行秀
証券アナリスト 平行秀資産管理会社は次世代への計画的な資産移転の実現にも直結します。
加えて、長期的な資産形成を進めるための基盤としても活用価値が高い制度です。
会社法で、資産管理会社として一般的に利用される法人形態には、「株式会社」と「合同会社(LLC)」の2つがある。
税務上の観点からは、保有している特定資産の割合や、収益源に着目して区分することもある。
不動産や株式などの保有割合が総資産の大半を占めれば「資産保有型会社」、運用による収益(賃貸収入・配当など)が総収入の大半を占めれば「資産運用型会社」とされる。
資産管理会社と他の法人形態との違い
資産管理会社と他の法人形態では、その目的や性格に違いがある。
資産管理会社は、あくまで「個人の資産を移して管理・運用するための法人」だ。
通常の事業会社のように、商品やサービスを販売して収益を得ることが主目的ではない。
また、医療法人や宗教法人などの特殊法人とも異なり、純粋に私的資産の管理・投資を行う性格が強い。
具体的には、以下のような特徴を備えている。
- 資産の管理が主目的である
- 主たる収入は運用益であり、商品販売やサービス提供による事業収益はほぼない
- 法人税・所得税のメリットを得るために設立されることが多い
ただし、法人としての実態(本店所在地、代表者、取締役など)を整え、法人税や消費税などの申告を行う義務がある点は、他の法人形態と共通している。
資産管理会社を立てる資産額の目安
一般的には、年収700万円を超えるあたりから設立を検討し始めるのが、一つの目安とされている。
資産管理会社を設立する主な目的の一つは、個人にかかる累進課税(所得税や住民税)を抑制することだ。



毎年安定的に高額な収益が見込まれる方や、複数の不動産・金融資産を保有している方にとっては、法人化により明確な節税効果があります。
また、帳簿管理や資金移動の透明性も高まり、資産管理の効率性と実務的メリットの双方を確実に享受できます。
ただしこれは、設立コストや維持コストを上回るだけの節税効果を得られることが大前提となる。
たとえば、定款の作成・登録免許税・公証人手数料・司法書士への依頼費など、設立時だけでも数十万円程度の費用が発生する。
また、会計事務所への顧問料や法人住民税の均等割(赤字でも年間7万円程度)など、維持費も継続的にかかる点に注意が必要だ。
「年収700万円程度」という水準は、こうしたコストとメリットを総合的に勘案したときの、メリットが上回る可能性が高い「理論上の水準」にすぎない。
あくまで一般論であり、実際には個々の状況や資産内容、将来的な収入見込みなどを踏まえて、総合的に判断する必要がある。
資産管理会社を設立するメリット


ここからは、資産管理会社を設立した場合に具体的にどのような利点があるのかを解説していく。
トータルの税負担を抑制しやすい
資産管理会社を活用すると、個人の高い累進課税率を回避し、比較的低い範囲の法人税率に収められる可能性がある。



年間の利益が一定以上で安定している方にとっては、税率の上昇を抑えながら利益を社内に蓄積することは有効な資産形成戦略となります。
さらに、法人内に残した資金を再投資に回すことで、複利的な資産拡大も実現しやすくなります。
たとえば、個人の年収(課税所得)が900万円を超えると所得税率は33%(住民税を合わせると約43%)に達し、1,800万円を超えると所得税率が40%(住民税を合わせると約50%)程度に上昇してしまう。
一方、資本金1,000万円以下の中小法人の場合、年800万円以下の所得にかかる法人税率は15%前後となる(800万円を超える部分には23.2%が適用される)。
法人税、法人住民税、法人事業税などを含めた実効税率でも、30%程度に収まることが多い。
以下に、課税所得1,000万円の場合について、個人と法人の税負担を単純化した例で比較する。
①個人が課税所得1,000万円を得る場合
国税庁の「所得税の税率」によると、課税される所得金額1,000万円に対する税率は33%である。住民税10%を考慮すると、合わせて約43%の負担率となる。
所得税・住民税簡易計算機を用いた試算では、所得税・復興特別所得税の合計が約180万円、住民税が約100万円ほどかかり、トータルで約280万円程度の税負担となる。
② 中小法人で課税所得1,000万円を得る場合
法人税は累進課税ではなく、定められた税率が適用される。そのため、利益(課税所得)が大きくなっても、個人ほど急激に税率が上がらない。
企業規模や所在地などによっても差はあるが、実効税率は30%前後だ。
個人の累進課税率に比べると低めであるため、結果的に税負担を抑えられ、より多くの資金を法人内部に残すことが期待できる。
このように、一定以上の所得が見込まれる場合は、法人化することで、トータルの税負担を抑制しやすい点は大きなメリットだ。
相続時のトラブルを回避できる
資産管理会社を通じて不動産や株式などの投資資産を法人名義にしておけば、相続時には法人株式を相続する形となる。
株式は、不動産とは異なり相続割合や所有割合をきめ細かく調整しやすい。不動産を兄弟で分割相続する場合などに比べると、遺産分割での争いを回避しやすい。
また、後継者に経営権や株式を生前贈与しておくことで、相続が発生する前の段階から円滑に資産を承継できる点もメリットと言える。



資産を法人化しておくことで、相続の際に分割や評価の調整がしやすくなり、感情的な対立や手続きの煩雑化を未然に防げます。
特に不動産のように物理的分割が難しい資産の場合でも、株式を通じて柔軟な承継が可能となります。
繰越控除が10年間認められる
個人で投資を行う場合、株式や投資信託の損失繰越は「最長3年まで」である。
しかし、法人として決算を行う場合は、中小法人が青色申告を行っていることを前提に、欠損金の繰越控除が「最長10年間」にわたって認められる。
このため、相場下落などで一時的に損失が発生しても、将来の利益と相殺できる期間が長る分大きなリスクヘッジとなり得る。
さらに、長期的視点で運用戦略を立てやすくなる点も、資産管理会社化のメリットである。
経費や損益通算の対象が広くなる
法人を通じて投資や資産運用を行うと、経費として認められる範囲が拡大することが多い。
たとえば、セミナー参加費や書籍代、出張費用などは、事業遂行上必要であり合理的と判断される範囲内であれば法人経費に計上できる。
また、法人化すれば事業全体の損益をまとめて計上しやすい点もメリットだ。
個人投資家の場合、投資の損益通算は種類別に限定されることが多く、たとえば株式の譲渡損失を不動産所得と直接通算することはできない。
しかし、法人化すれば一括で扱えるため、赤字部門と黒字部門の損益を内部で通算しやすい。
社会保険に加入できる
法人を設立し、代表取締役や役員が報酬を受け取る形をとることで、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できる点も大きなメリットである。
個人事業主の場合は国民健康保険や国民年金への加入となるが、法人の役員であれば厚生年金を利用し、将来受け取れる年金額のベースを高めることも可能になる。
ただし、法人が負担する社会保険料が増える点には注意が必要だ。
社会保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛け合わせて算出され、事業主(法人)と従業員の双方が折半する仕組みになっている。
そのため、役員報酬を高く設定すればするほど、会社側の社会保険料負担も相応に大きくなるのだ。
資産管理会社を設立するデメリット


メリットがある一方で、資産管理会社にはデメリットやリスクも存在する。ここではデメリットと考えられる代表的なものを紹介する。
設立手続きが煩雑で費用がかかる
資産管理会社を新たに設立する場合、法人としての実体を整えるために多くの手続きが必要になる。



節税や資産保全の効果がコストを上回るかどうかを、事前に数字ベースで比較・判断することが重要。複数年にわたる収益見込みや支出の推移も踏まえた、長期的なシミュレーションが有効です。
具体的には、定款の作成、公証人役場での認証、法務局への登記などが挙げられ、いずれも法律や規定に則って正しく行わなければならない。
自力で進めようとすると、相応の手間と時間が必要になる。
加えて、設立登記には登録免許税、公証人認証には手数料がかかるなど、初期費用だけでも数十万円単位の出費となる可能性が高い。
設立後も、税務署や都道府県・市区町村への届出、社会保険・労働保険への加入手続きなどが順次必要となる。
これらを専門家(司法書士や税理士など)に依頼するケースも多いが、当然その分の報酬が別途必要になる。
資産移転時に課税される
個人名義の資産を新しく設立した法人に移転する行為は、税務上は「資産売却」とみなされる。
そのため、譲渡所得税(いわゆるキャピタルゲイン課税)などが発生する場合がある。



多額の譲渡益が発生すると、短期的には税負担が急増することも。
特に不動産や有価証券などは移転時期や評価方法によって納税額が大きく異なるので、慎重に進める必要があります。
特に、不動産のように評価額が大きい資産の移転で、譲渡益が大きくなる場合は、個人側でまとまった所得税・住民税を負担しなければならないケースも多い。
また、不動産を法人に移す際は、登録免許税や不動産取得税など、各種税金・手数料が追加でかかる点にも注意が必要だ。
実態としては個人と法人が同一だとしても、法律上は別人格として扱われるため、移転に伴う税負担は避けられない。
解散手続きは複雑で費用もかかる
単に「会社を畳む」だけでも手間とコストがかかる点も、デメリットと言える。
法人を解散する際には、定款の定めや会社法上の手続きに則って進めなければならない。
一般的には、まず株主総会などで解散決議を行って法務局に解散登記を申請し、残余財産の清算を行って清算結了登記を完了させる流れで行われる。
これらの手続きには、解散登記や清算結了登記にかかる登録免許税が発生し、専門家(司法書士・税理士など)への報酬も必要となる。
また、清算結了までの期間にも、法人税や消費税などの申告義務が継続する場合がある。
資金引き出しが自由に行えない
会社が保有する資金は、個人の都合で自由に引き出すことができない。これは、資産管理会社は法人であり、個人とは別の法的主体であるからだ。
会社資金を引き出す場合は「役員報酬」や「配当」として処理し、税務上のルールに則って源泉徴収や申告を行わなければならない。
適切な手続きを踏まないと「役員貸付」や「不正な利益供与」とみなされるおそれがある。
資産管理会社はどのような場合に作るべきなのか


ここまで紹介したメリット・デメリットを踏まえ、資産管理会社の設立が有効なケースを具体的に見ていく。
不動産投資の規模が大きく、今後も拡大する計画がある場合
複数の不動産を所有し、家賃収入や物件売却益などが大きくなると、個人にかかる所得税や住民税が高額になる可能性がある。
そこで、資産管理会社を設立して不動産を法人名義に移管し、法人として運営すれば、相続税対策や高額所得に対する節税効果を期待できる。
不動産評価の観点からも、相続時の負担を軽減しやすい点でメリットがある。
継続的に高額な所得が見込まれる場合
配当所得やキャピタルゲインが大きく、毎年の所得税・住民税の負担が重い場合、個人よりも法人税の適用を受けるほうが、トータルの税負担を抑えられる可能性が高い。



金融資産の利益が安定して見込めるなら、課税を一定水準に抑えつつ、再投資の余力も高めるという、戦略的かつ持続的な運用が可能に。
加えて、利益管理や資金移動の自由度が高まる点も見逃せない利点です。
ただし、継続的に安定した収益が見込めなければ、設立費用や維持コストばかりがかさんで結果的に損失となることもある。
十分にシミュレーションして、慎重に判断する必要がある。
将来の相続トラブルを避けたい場合
複数の不動産や金融資産を所有しており、相続時の遺産分割が複雑になる恐れがある場合、法人設立は選択肢のひとつとなる。
資産管理会社に資産を集約し、株式を分割する形にしておけば、不動産などを複数の相続人で物理的に分けるよりスムーズに調整できる。
また、後継者への株式譲渡や生前贈与を行いやすい点もメリットである。
家族で運用して所得分散したい場合
家族みんなで不動産や株式などを運用し、報酬や配当を分散させて家計を支えたいと考えている場合、資産管理会社が役に立つ。
家族を役員や従業員として雇用し、報酬や配当金を複数人に分配すれば、所得税の累進課税を抑えやすいからだ。
さらに、将来にわたって家族内で株式を承継しやすくなり、教育資金や生活費などを法人から適切に支払うことも可能になる。
ただし、実態のない雇用契約は認められず、業務内容との整合性が求められる点には注意が必要だ。
資産管理会社を設立するには?手順を解説


ここからは、資産管理会社設立の大まかな流れを紹介する。専門家に依頼する場合でも、手順の大きな流れは押さえておく方が良い。
1. 事業目的・設立形態を検討する
まずは、どのような資産を管理・運用する会社にするのかを明確にし、定款に記載する事業目的を決める必要がある。
たとえば、「不動産賃貸」「有価証券投資」などを決め、具体的な収益源や運用方針を事前に整理しておくと、後の手続きがスムーズになる。



設立後の税務戦略や資産配分にも関わるため、この初期設計を丁寧に行うことは、将来的な節税効果や資産承継のしやすさにも影響を及ぼします。結果として、安定的かつ効率的な法人運営と中長期的な資産形成を支える重要な土台となります。
あわせて、設立形態を株式会社にするか、合同会社(LLC)にするかも検討する。
一般的に、株式会社は社会的信用度が高く、金融機関からの融資を受けやすいとされる。
一方、合同会社は設立コストや維持コストが比較的安価で、内部の意思決定も柔軟に行える。
自社のビジネス規模や今後の運営方針、コスト面などを踏まえて判断すると良い。
2. 定款を作成し、認証する
設立形態が決まったら、定款を作成し、公証人役場で認証を受ける。
定款には会社名(商号)、事業目的、本店所在地、発起人(出資者)、資本金などを記載する。
定款認証にあたっては、手数料(資本金の額や定款の形式によって異なる)に加え、収入印紙代が必要になることもある。
3. 資本金を払い込む
定款認証を終えたら、発起人(出資者)が定款に定めた資本金を払い込む。
発起人名義の銀行口座に資本金を振り込み、その後、振込明細書や預金残高証明書などを発行してもらうのが一般的だ。
なお、1円からでも会社設立は可能だが、資産管理会社の場合は資産規模や金融機関との取引を考慮し、ある程度まとまった資本金を用意するケースが多い。
出資者が複数いる場合は、出資額の割合や役員構成についても事前に十分協議しておくことが望ましい。
4. 法務局で設立登記する
資本金の払い込みが完了したら、本店所在地を管轄する法務局で設立登記を行う。
登記申請には、登記申請書や定款の写し、資本金の払込証明書など、必要書類を揃えて提出する必要がある。
登録免許税は「資本金の0.7%」が基本で、最低額が株式会社なら15万円、合同会社なら6万円と定められている。
提出した申請書類に問題がなければ、申請からおよそ1〜2週間ほどで登記が完了し、登記完了日が会社の設立日となる。
5. 税務署や自治体に届出する
設立登記が完了したら、管轄の税務署や都道府県・市区町村へ「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」などの各種書類を提出する。
さらに、従業員を雇用する、または役員報酬を支払う場合には「給与支払事務所等の開設届出書」も必要となる。
あわせて、社会保険(健康保険・厚生年金)や、労働保険(雇用保険・労災保険)への加入手続きも進めなければならない。
資産管理会社の場合、事業規模や運営方法によって手続きが異なることもあるが、これらを怠ると罰則や追加費用発生の可能性がある点は共通している。
できるだけ早めに対応を始めることが重要だ。
6. 資産移転や口座開設を行う
設立登記や各種届出が終わったら、実際に個人が所有している不動産や金融資産を法人名義へ移す手続きを進める。
不動産の場合は、所有権移転登記が必要であり、譲渡所得税や登録免許税などが発生し得るため、専門家に相談・依頼するのが一般的だ。



この段階での正確な資産評価や税務処理は、法人化後の運用効率や税務リスクの回避に直結するため、信頼できる専門家の助言を得ることが不可欠です。特に評価が難しい不動産や有価証券を扱う場合、税務上のトラブルを避けるためにも事前の確認が重要です。
また、会社設立後の投資や運用資金は、原則として法人口座を用いて管理する。
必要に応じて銀行や証券会社に新しく口座を開設し、資金の流れを法人として一元管理できるよう体制を整えておくと良い。
資産管理会社で運用するなら「資産運用ナビ」で専門家に相談しよう


資産管理会社を活用して資産運用するには、設立手続きや税務処理、投資戦略など、幅広い専門知識が必要となる。
これらすべてをひとりで行うのは、時間・労力・知識の面から難しいと言わざるを得ない。
資産管理会社の設立判断は難しい
まず、資産管理会社を作るべきかという判断自体が難しい。
単に「税負担を下げたい」という理由だけで設立するのは、非常にリスクが高い。法人化による恩恵より、デメリットのほうが大きくなる可能性もあるからだ。
したがって、投資収益の見通しや家族全体のメリット、将来の相続・事業承継における利点など、さまざまな角度から総合的に検討する必要がある。
その際には、専門家によるシミュレーションやアドバイスが大いに役立つだろう。
法人化メリットを享受するには専門家の力が必要
また、法人化した場合は、個人とは別の難しさに直面する。
以下に挙げるような難点をクリアできなければ、せっかくの法人化によるメリットを十分に活かせない恐れがある。
- 法人の税制・会計処理は複雑で難しい
- 個人と法人では適用される税率や処理方法が異なるため、節税を狙うには専門的知識が欠かせない。
- 適切な投資対象選定は、より一層難しくなる
- 法人口座で扱える商品や運用方法は幅広く、適切なリスク管理や商品選定には専門家のアドバイスが不可欠である。
- 相続・事業承継には、長期視点が必要
- 法人化が真価を発揮するのは、相続や事業承継などの長期的課題を見据えた場合であり、事前の計画が重要となる。
資産管理会社の設立目的を「資金効率を上げる」「リスク管理を向上させる」とするなら、専門外の作業は任せて、安全かつ確実に進めるのが賢明だ。
適切な専門家に任せることで、自分は資産運用という本来業務に集中できるようになる。
良い相談相手は「資産運用ナビ」で探せる
とはいえ、資産管理会社の設立に関する業務は、手続き面や税務面など多岐にわたり、誰に相談すれば良いのかわからない方も多いだろう。
そこで活用をおすすめしたいのが、投資家と専門家をつなぐマッチングプラットフォーム「資産運用ナビ」である。
「資産運用ナビ」には、資産管理会社の設立アドバイスをはじめ、税理士や会計士、司法書士との連携を含めたサポートができる専門家も多数登録している。
サイト上でいくつかの質問に答えるだけで登録が完了し、条件に合ったプロを無料で紹介してもらえる。
「まずは可能性だけでも聞いてみたい」という段階でも利用が可能だ。迷っている方は、気軽にアクセスしてみると良いだろう。
資産管理会社とは「資産を拡大する仕組み」〜検討するなら専門家に相談しよう
資産管理会社とは、個人所有の資産を法人名義で運用し、効果的に拡大していくための「仕組み」とも言える。
税負担の軽減だけでなく、相続税対策や所得の分散効果を狙えるため、資産形成・資産保全に有効な選択肢となり得る。



一定以上の金融資産や不動産を保有している方にとって、資産管理会社は税務効率や承継設計の観点から資産の一元管理を行う有力な手段。
資産全体の可視化と管理のしやすさも大きな利点です。
しかし、法人の設立や維持には手間や費用がかかり、各分野にわたる専門知識を要するため、一筋縄ではいかない局面も多い。
よって、資産管理会社を検討する場合は、専門家に相談することが望ましい。
それぞれの状況に合わせたアドバイスを受けることで、法人化によるメリットを最大限に引き出すことが期待できる。
もし「自分に資産管理会社は必要だろうか」と迷っているなら、まずは「資産運用ナビ」を通じて専門家に相談すると良い。
プロの視点を得ることで、自身に合った最適解に一歩近づくことができるはずだ。