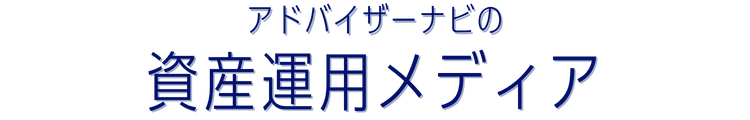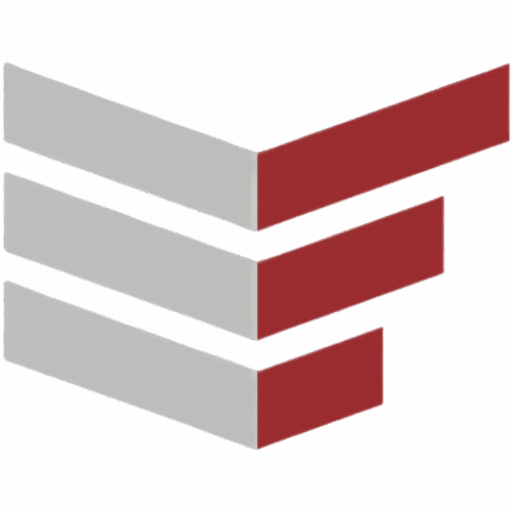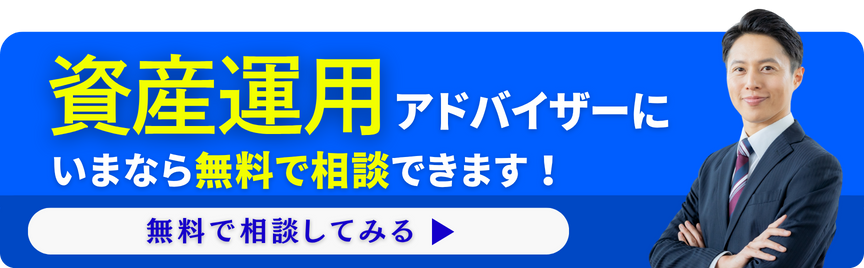老後資金については、多くの人が不安を抱えています。
“老後2000万円問題”って、本当に誰でも2000万円必要なの?
夫婦で月にいくら必要なの?持ち家と賃貸で、準備する金額は変わる?
また、老後資金をめぐる話は、平均値だけが一人歩きしがちです。しかし実際には、持ち家か賃貸か、夫婦か独身か、働き続けるかどうかで必要な金額は大きく変わります。「みんなと同じ金額を準備すればいい」という単純な話ではないのです。
この記事では、あなた自身の状況に合わせた老後資金を計算できる方法をお伝えします。実際に手を動かして「自分の場合はいくら必要か」を導き出してみましょう。
老後資金を考える上で知っておきたい2つの前提

老後資金がいくら必要なのかを理解するために、まず2つの前提を確認しましょう。
ひとつは「生活水準の前提」です。最低限の生活を送るのか、旅行や趣味にもお金を使いたいのかで、必要な金額は大きく変わります。
もうひとつは「期間の前提」です。65歳で退職して何歳まで生きるかで、準備すべき総額が決まります。
まずはこれらを考え、「自分はいくら必要なのか」を把握するところから始めましょう。
ゆとりある老後とは?最低限の生活費との差額
老後の生活費を考えるとき、「最低限の生活」と「ゆとりある生活」は明確に区別しておきたいところです。
最低限の生活とは、食費・住居費・光熱費・医療費といった必須支出を賄える水準を指します。一方、ゆとりある生活には、外食や旅行、趣味の習い事、孫へのお小遣いといった嗜好的な支出が含まれます。
生命保険文化センターの調査では、夫婦2人の「最低日常生活費」は月額23.2万円、「ゆとりある老後生活費」は月額37.9万円とされています。
このように、目指す老後の生活によって、必要な支出が大きく変わります。老後資金を考える際は、大きく3つに分けて考えると、自分に合った支出バランスが見えやすくなります。
| 主な支出項目 | 特徴 | |
|---|---|---|
| 必須層 | 食費(自炊中心)、住居費、光熱・通信費、医療費、税・社会保険料 | 生活の基本。削減は難しい |
| 準必須層 | 衣類・家電の買い替え、冠婚葬祭費、交通費 | ある程度調整可能 |
| 嗜好層 | 外食、旅行、趣味、交際費、孫へのお小遣い | 生活の質を左右する支出 |
たとえば「旅行を年1回」「外食を月数回」といった希望を持つなら、その分を嗜好層として上乗せして考えましょう。
この“上乗せ部分”こそが、最低限の生活とゆとりある生活の差を生む要素です。
老後の生活期間は「95歳まで」を想定しよう
老後資金を計画するとき、「老後は何年間続くのか?」を想定することは非常に重要です。この期間が長いほど、必要なお金も多くなります。
最近は日本人の寿命が延びており、65歳の方がその後20年以上生きることは珍しくありません。
ただし、「平均寿命」はあくまで平均です。平均より長く生きる可能性(長生きリスク)に備えて、資金計画には余裕を持たせるのが賢明です。
そこで、ここでは「95歳まで生きる」ことを前提に、老後の期間を考えてみましょう。
例えば、65歳で退職するなら、95歳までの【30年間】が老後期間となります。
また、老後期間を考える際、特に注意したい点が2つあります。
1. ご夫婦の場合は「長く生きる方」に合わせる
夫婦の場合、どちらか一方が先に亡くなっても、残された方の生活は続きます。二人世帯から単身世帯になった後の生活費もしっかり見込んで、「長く生きる方」を基準に計算しましょう。
2. 「働く期間」を延ばす選択肢も
もし資金が不足しそうな場合、「働く期間を延ばす」ことも有効な対策です。
例えば、65歳以降もパートや嘱託で働き、月10万円の収入を得たとします。すると、年間120万円分、貯蓄を取り崩すペースを遅らせることができます。長く働くほど、準備すべき老後資金の総額は少なくて済みます。
「95歳まで」という設定は、少し保守的(長め)に感じるかもしれません。しかし、医療の進歩などを考えれば、決して大げさな数字ではありません。
「老後資金が足りなくなるかも…」と不安を抱えながら過ごすよりも、「余裕を持って計画できた」という安心感がある方が、精神的にもずっと楽に過ごせるはずです。
【データで見る】老後に必要な生活費の平均額
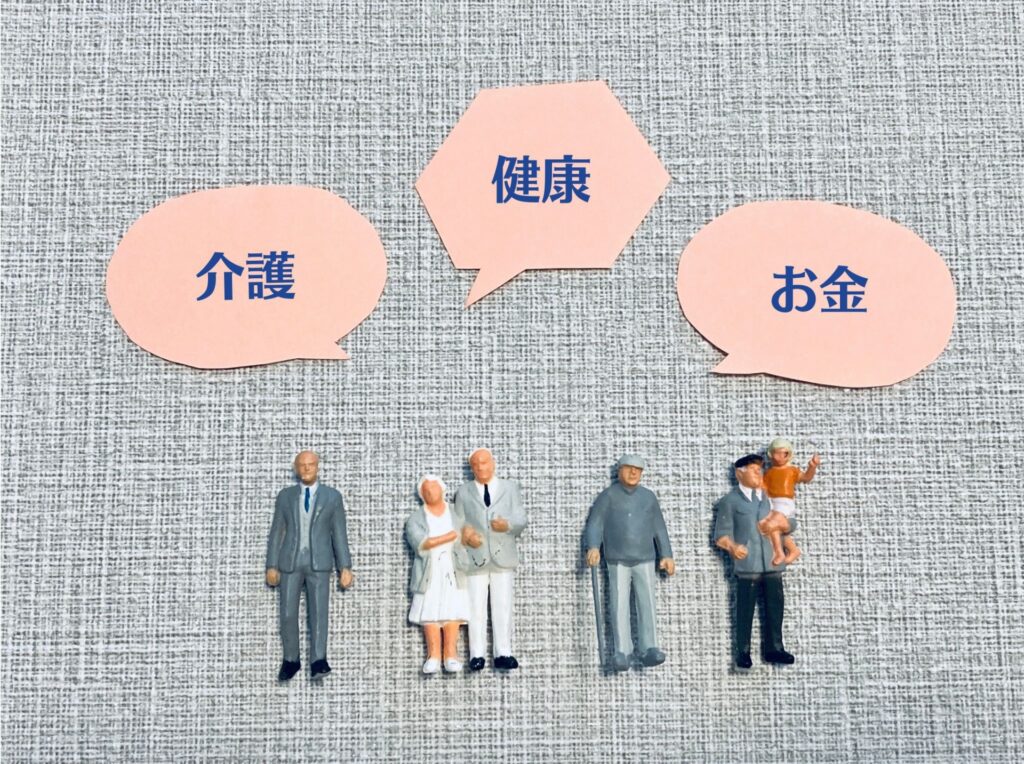
ここからは、公的な統計データをもとに、実際の高齢者世帯がどれくらいの生活費で暮らしているかを確認します。
この数値を参考にしていただき、あなた自身の状況に合わせて調整してください。
夫婦世帯・おひとりさま世帯の平均的な支出額
総務省の家計調査によると、2024年の65歳以上無職世帯の月次支出は以下のとおりです。
【65歳以上・無職世帯の月次支出】
| 夫婦世帯 | 単身世帯 | |
|---|---|---|
| 収入(年金など) | 約25.3万円 | 約13.4万円 |
| 支出(合計) | 約28.7万円 | 約16.2万円 |
| (内訳) 生活費 (消費支出) | 約25.7万円 | 約14.9万円 |
| (内訳) 税・社会保険料 (非消費支出) | 約3.0万円 | 約1.3万円 |
| 不足額 (収入-支出) | 約3.4万円 | 約2.8万円 |
これを年額に換算すると、平均で以下の金額が不足する計算になります。
夫婦世帯(65歳以上・無職)
年間 約41万円の不足
単身世帯(65歳以上・無職)
年間 約34万円の不足
この「平均額」を見る際には、注意点が2つあります。
1. 「平均値」は高めに出る傾向がある
これらの数字は「平均値」です。平均値は、一部の高所得者や高支出世帯の影響を受けて、全体の金額が引き上げられる傾向があります。
2. 「住居費」は低めに見積もられている
高齢者世帯は「持ち家」の割合が高いため、家計調査上の「住居費」は比較的低めに出ています。
もしあなたが賃貸住宅にお住まいの場合、ご自身の「年間の家賃」を不足額に上乗せして考える必要があります。
老後の収入は「年金」が中心となります。 この「年間の不足分」を、貯蓄や就労収入などでどのように補っていくかを具体的に計画することが、老後資金準備の鍵となります。
ゆとりある生活費「月37.9万円」の内訳と根拠
生命保険文化センターの調査(2022年度)によると、夫婦2人で「ゆとりある老後生活」を送るための目安は月37.9万円です。
ゆとり分のの使い道としては、回答者の6割が「旅行やレジャー」を挙げており、次いで「日常生活費の充実」「趣味や教養」が続きます。
以下は、調査結果や実態をもとにした費目別の目安です。
| 費目 | 月額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 食費 | 7〜9万円 | 外食や嗜好品を含む |
| 住居費 | 1〜10万円 | 持ち家なら低め、賃貸なら高め |
| 光熱・水道 | 2〜3万円 | 季節変動あり |
| 保健医療 | 1.5〜2万円 | 通院・薬代など |
| 交通・通信 | 2〜3万円 | 車の維持費を含む場合は増 |
| 教養娯楽 | 3〜5万円 | 旅行費を別途積み立てる場合は減 |
| 交際費 | 2〜3万円 | 冠婚葬祭・贈答品など |
| 被服・家事用品 | 1〜2万円 | 季節ごとの買い替え |
| その他 | 3〜5万円 | 予備費・特別支出 |
例えば、「旅行を年に1回入れたい」なら年間20〜30万円程度の上乗せ、「月に数回は外食したい」なら月2〜3万円の追加といった具合に、自分の希望に合わせて調整できます。
持ち家と賃貸、車の保有有無、扶養家族の有無によっても金額は変わります。たとえば賃貸の場合は家賃分として月5〜10万円を上乗せする必要がありますし、車を持ち続けるなら維持費や買い替え費用も見込んでおきましょう。
また、物価上昇を踏まえると、2025年時点では38〜40万円程度に上昇している可能性があります。
老後資金を試算する際は、将来の物価上昇を見込み、やや多めに見積もるのが安心です。
老後資金の不足額は約2000万円って本当?
「老後資金2000万円問題」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。これは2019年に金融審議会が公表した報告書が事の発端です。
当時の家計調査を前提に、夫婦2人・無職世帯で以下の状況を30年間続けると、約2,000万円の取り崩しが必要——という試算でした。
- 年金収入:約21万円/月
- 支出:約26万円/月
- 不足額:約5〜5.5万円/月
5〜5.5万円 × 12ヶ月 × 30年
=1,800〜1,980万円
ただし、これは当時の前提に基づく平均的な試算です。前提が変われば、必要額も変わります。
| 不足額が増える要因 | 不足額が減る要因 |
|---|---|
| 賃貸住まい 車の維持費 医療費の増加 旅行・趣味などの上乗せ支出 物価上昇(インフレ) | 持ち家で住居費が低い 年金額が多い/企業年金・退職金がある 就労収入がある 生活費の見直しができている |
結論として、「誰にでも2,000万円が必要」ではありません。
大切なのは、あなたの条件で収入(年金・就労・年金以外の年金や配当等)と支出を見積もり、その差から必要な貯蓄額を逆算することです。
次章では、年金・退職金などの「もらえるお金」を整理し、あなたの場合の不足額を計算していきます。
老後にもらえるお金はいくら?収入の種類と金額を確認
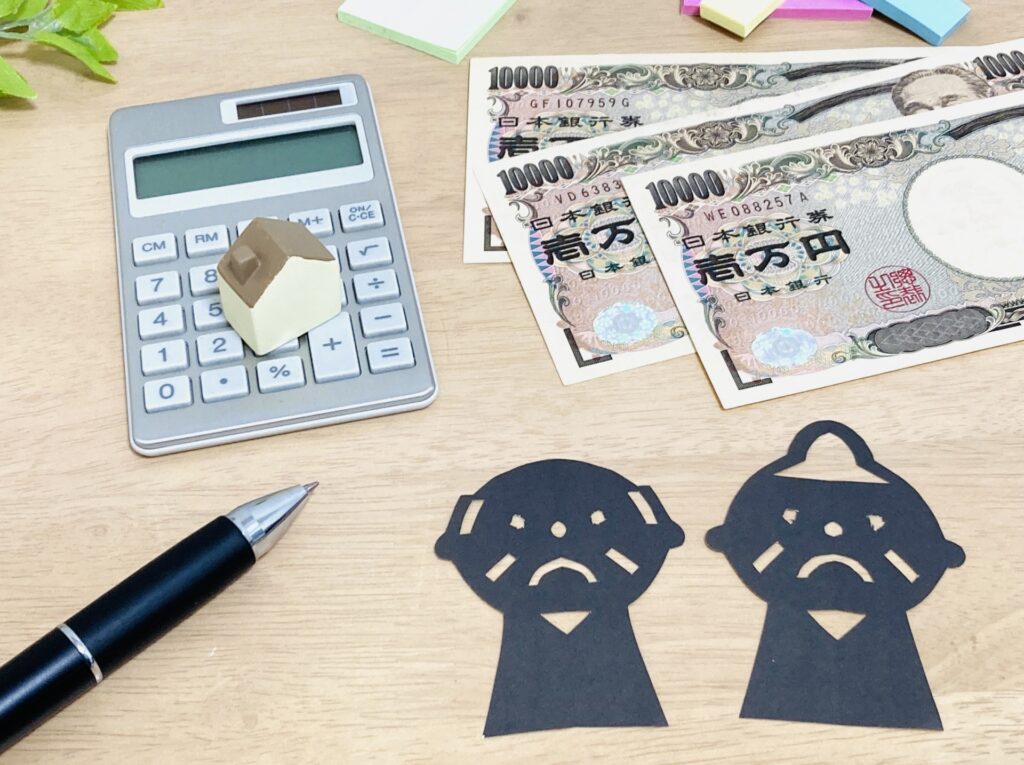
老後の不足額を計算するには、まず「もらえるお金」を洗い出す必要があります。
老後の収入源は大きく分けて以下の6種類です。
- 公的年金(国民年金・厚生年金)
- 退職金
- 企業年金(確定給付・確定拠出)
- 個人年金保険
- 就労収入(パート・嘱託など)
- 金融資産からの配当・利子
これらを合計した金額が「老後の収入」となり、生活費との差額が不足額です。ひとつずつ確認していきましょう。
公的年金(国民年金・厚生年金)の平均受給額
公的年金は老後収入の柱です。国民年金と厚生年金の2種類があり、加入期間と収入によって受給額が決まります。
国民年金(老齢基礎年金)
20歳から60歳までの40年間(480か月)、全期間保険料を納めた場合、2025年度の満額は以下の通りです。
- 月額:6万9,308円
- 年額:83万1,700円
未納期間がある場合は、その分だけ減額されます。たとえば30年間(360か月)しか納めていなければ、満額の4分の3である月額約5万2,000円となります。
厚生年金(老齢厚生年金)
会社員や公務員が加入する厚生年金は、国民年金に上乗せされます。受給額は「加入期間」と「平均収入」で決まるため、人によって大きく異なります。
2024年度のデータでは、厚生年金受給者の平均月額は約14.4万円(国民年金分を含む)です。男性は平均約16.6万円、女性は平均約10.7万円と、男女差があります。
モデル世帯の受給額
夫が平均標準報酬月額45.5万円で40年間働き、妻が専業主婦(国民年金のみ)の場合、2025年度のモデル世帯の受給額は月額約23万2,784円です。
正確な見込額を知るためには、ねんきんネットにログインして試算してみましょう。
退職金・企業年金・個人年金
公的年金以外にも、老後の収入源はいくつかあります。これらを合算することで、不足額を減らすことができます。
退職金
会社員の場合、退職時に一時金として受け取るか、年金形式で受け取るかを選べる場合があります。
- 一時金受取
退職所得控除が適用され、税負担が軽減される - 年金受取
毎年一定額を受け取るため、生活費の補填に使いやすい
大学・大学院卒の平均退職金は約1,900万円程度(2022年調査)とされていますが、企業規模や勤続年数によって大きく異なります。
企業年金
企業年金には大きく2種類あります。
- 確定給付企業年金
給付額があらかじめ約束されている制度。会社が運用リスクを負う。 - 確定拠出年金(企業型DC)
会社が掛金を拠出し、加入者が運用する制度。運用成績によって給付額が変わる。
企業年金の受取額は、企業の制度設計によって異なります。自分の会社の制度を確認し、受取時期や金額を把握しておきましょう。
個人年金保険
生命保険会社の個人年金保険に加入している場合、65歳以降に年金形式で受け取れます。
個人年金保険料控除の対象となるため、現役時代の税負担を軽減できるメリットがあります。ただし、受取時には雑所得として課税されるため、公的年金等控除の範囲内に収まるよう調整が必要です。
【税・控除のポイント】
| 受取タイミング | 税・控除のポイント | 注意点 | |
|---|---|---|---|
| 退職金 (一時金) | 退職時に一括 | 退職所得控除で大幅に減税 | 受け取った後に運用方法を考える必要がある |
| 退職金 (年金) | 退職後、分割で (5年、10年など) | 雑所得として課税 | 毎年もらう公的年金と合算して税金計算されるため、税額が上がりやすい。 |
| 企業年金 | 60〜65歳以降 | 雑所得または退職所得 (制度によって異なる) | 自分の会社の制度をしっかり確認する必要がある。 |
| 個人年金 | 契約で決めた年齢から | 雑所得として課税 | 公的年金と合算して税金計算されるため、控除の枠に注意。 |
ここで一度、自分の想定受取額を整理しておきましょう。
- 退職金(一時金):______ 万円
- 企業年金(年額):______ 万円
- 個人年金(年額):______ 万円
- その他(配当・利子など):______ 万円
これらを合計し、公的年金と足し合わせることで、老後の年間収入総額が見えてきます。
資産運用、誰に相談する?
簡単な質問に回答するだけ!
あなたに合った資産運用アドバイザーを紹介
\ 簡単60秒!相談料はずっと無料 /
年金の繰下げ受給で受給額が増やせる!損益分岐点は?
公的年金は原則65歳から受け取れますが、受給開始を遅らせることで月額を増やせる「繰下げ受給」という制度があります。受給開始を1か月遅らせるごとに年金額が0.7%ずつ増え、最大で75歳(120か月)まで繰り下げると、増額率は84%にも達します。
簡易計算式
繰下げ受給の計算は以下の通りです。
例えば、65歳時点の年金月額が15万円の人が70歳まで(60か月)繰り下げた場合、増額率は42%(0.7%×60か月)となり、受給額は毎月21.3万円(15万円×1.42)に増えます。
- 増額率 = 0.7% × 60 = 42%
- 増額後の年金月額 = 10万円 × 1.42 = 14.2万円
損益分岐点は「81歳」
繰下げ受給は増額率が魅力的ですが、受け取りを遅らせる分、65歳から受給し始めた場合と比べて総受給額が追いつくまでに時間がかかります。
この「損益分岐点」は、70歳受給と65歳受給を比較した場合、一般的に81歳前後とされています。つまり、81歳より長生きすれば繰下げした方が生涯の総受給額は多くなり、それより早く亡くなれば65歳から受給した方が得だった、という計算になります。
夫婦の場合は、どちらか一方だけを繰り下げる選択肢もあります。一般的に平均余命が長い側(例えば妻)の年金を70歳まで繰り下げ、もう一方(夫)は65歳から受給開始するといった戦略が考えられます。
繰下げ待機中の注意点
繰下げ受給を検討する際は、税金や社会保険料についても考慮が必要です。
まず、繰下げ期間中も働いて厚生年金保険料を納め続ける場合、保険料の負担は増えますが、その分が将来の年金額にさらに上乗せされます。
一方で、繰下げによって年金額そのものが増えると、所得税や住民税、国民健康保険料や介護保険料などの負担も増加します。手取りベースで計算すると、増額率ほどには手元に残らない可能性がある点にも注意が必要です。
繰下げ受給は、ご自身の健康状態や家計状況、働き続ける意思などを総合的に考えて判断することが大切です。制度の詳細や最新の増額率は、日本年金機構のウェブサイトで確認することをおすすめします。
資産運用、誰に相談する?
簡単な質問に回答するだけ!
あなたに合った資産運用アドバイザーを紹介
\ 簡単60秒!相談料はずっと無料 /
老後にかかるお金はいくら?支出の種類と金額を確認

収入の次は、老後にかかる「支出」を見ていきます。
老後の支出は、大きく「毎月の生活費」と、臨時に発生する「特別な支出」の2つに大別されます。これらを漏れなく把握することで、現実的に必要なお金(不足額)が見えてきます。
この章では、支出の全体像を把握するために、それぞれの内訳を詳しく確認していきましょう。
1.毎月の生活費(固定費・変動費)
老後の生活費は、固定費と変動費に分けて考えると管理しやすくなります。
- 固定費
毎月一定額出ていく支出。金額が大きいため、優先的に見直すことで節約効果が長続きします。
(例)住居費(家賃、固定資産税)、通信費、保険料など。 - 変動費
月によって変動する支出。日々の工夫次第で削減の余地があります。
(例)食費、交際費、娯楽費、医療費など。
では、具体的にどの項目にどれくらいの削減余地があるのでしょうか。
以下に、主な項目の相場と見直しのポイントを優先度別にまとめましたので、ご自身の状況と照らし合わせて参考にしてください。
【見直しポイント】
| 項目 | 相場レンジ | 削減余地 | 優先度 |
|---|---|---|---|
| 通信費 | 0.5〜1.5万円 | 格安プランへの変更で半減可能 | 高 |
| 保険料 | 0.5〜3万円 | 保障内容の見直しで過不足を調整 | 高 |
| 食費 | 5〜8万円 | 外食を減らす、まとめ買いで節約 | 中 |
| 娯楽費 | 1〜5万円 | 優先順位をつけて取捨選択 | 中 |
| 光熱費 | 2〜3万円 | 電力プラン変更で1割削減 | 低 |
2.特別支出(臨時の大きな出費)
特別支出は、毎月の生活費とは別に、数年ごと、あるいは突発的に発生する大きな出費です。これらを見落とすと、想定外の貯蓄の取り崩しが必要になります。
①医療費
高齢になると入院や手術のリスクが高まります。公的医療保険で自己負担は1〜3割に抑えられますが、それでもまとまった出費になることがあります。
- 目安
-
入院費用(平均約20万円)
手術費用(数万〜数十万円)
- 備え方
-
医療保険やがん保険で備えるか、現金で50〜100万円程度の予備費を確保する。
②介護費用
介護が必要になった場合にかかる費用。在宅か施設かで費用が大きく異なります。
- 目安
-
訪問介護・デイサービス(月5〜10万円)
特別養護老人ホーム(月10〜15万円)
有料老人ホーム(月15〜30万円)
- 備え方
-
公的介護保険の範囲を確認し、不足分は貯蓄で備える。事前に家族とも相談しておく。
③住宅の修繕・リフォーム
持ち家の場合、10〜20年ごとに外壁塗装や水回りのメンテナンスが必要です。
- 目安
-
外壁塗装(100〜200万円)
水回りリフォーム(50〜150万円)
屋根の葺き替え(100〜200万円) など
- 備え方
-
毎月1〜2万円を修繕積立金として確保しておく。
④耐久消費財の買い替え
冷蔵庫・洗濯機・エアコンといった家電は10〜15年で寿命を迎えます。車も10年前後で買い替えが必要です。
- 目安
-
家電一式の買い替え(50〜100万円)
車の買い替え(100〜300万円)
- 備え方
-
毎年10〜20万円を積み立て、または一時金から充当
- 60代
退職、住宅ローン完済、車の買い替え - 70代
家電の買い替え、外壁塗装、医療費増加 - 80代
介護開始の可能性、施設入居、配偶者の相続 - 90代
在宅介護の継続、医療費のさらなる増加
これらの特別支出は、老後30年間で数百万円規模になる可能性があります。毎月の生活費とは別に、年間20〜50万円程度の特別支出枠を確保しておくと安心です。
3.見落としがちなリスク(インフレ・税金・社会保険料)
老後資金を考える際は、物価の上昇や公的な負担の影響も見逃せません。
インフレの影響
インフレとは、モノやサービスの価格が継続的に上昇することです。現在日本では2024〜2025年にかけて年率2〜3%程度の上昇が続いています。
たとえば、年率2%のインフレが続くと、現在月25万円で暮らせる生活が、20年後には月37万円必要になる可能性があります。
税金・社会保険料の影響
年金収入にも税金(所得税・住民税)や社会保険料(国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料)がかかります。
「公的年金等控除」があるため全額に課税されるわけではありませんが、年金額が多いほど負担も増えます。例えば、年金月額が20万円の場合、税・社会保険料を差し引いた手取り額は約17〜18万円程度になるのが一般的です。
生活費の計画は、額面の年金額ではなく「手取り額」をベースに立てないと、資金不足に陥る可能性があるため注意しましょう。
【世帯別】あなたの老後資金はいくら必要か計算しよう

ここからは、あなたご自身の状況に合わせて、老後に必要な貯蓄額を計算していきます。
まずは世帯別のケーススタディで、働き方や住まいの状況によって必要額がどう変わるのか、大まかなイメージを掴みましょう。
夫婦世帯のケース(共働き/片働き/自営業)
夫婦世帯は、共働きか片働きか、また会社員か自営業かによって年金額が大きく変わるのが特徴です。(老後期間は30年として計算)
ケース1:共働き(夫婦ともに厚生年金)
夫(会社員40年)、妻(会社員35年)、持ち家(ローン完済)
- 収入:年金 月26万円(夫16万+妻10万)
- 支出:生活費 月28万円 + 特別支出 年30万円
- 年間の不足額:54万円
((支出28万 − 収入26万)× 12ヶ月 + 特別支出30万) - 30年間の不足額:54万円 × 30年
= 1,620万円
退職金(夫1,500万+妻800万=2,300万)で十分カバーできる見込み。
ケース2:片働き(夫・会社員、妻・専業主婦)
夫(会社員40年)、妻(国民年金40年)、持ち家(ローン完済)
- 収入:年金 月23.9万円(夫17万+妻6.9万)
- 支出:生活費 月26万円 + 特別支出 年25万円
- 年間の不足額:50.2万円
((支出26万 − 収入23.9万)× 12ヶ月 + 特別支出25万) - 30年間の不足額:50.2万円 × 30年
= 1,506万円
夫の退職金(2,000万円)でカバーできる見込み。ただし、旅行などのゆとり費用のために追加の準備が望ましい。
ケース3:自営業(夫婦ともに国民年金のみ)
夫・妻ともに国民年金(40年満額)、持ち家(ローン完済)
- 収入:年金 月13.8万円(夫6.9万+妻6.9万)
- 支出:生活費 月25万円 + 特別支出 年30万円
- 年間の不足額:164.4万円
((支出25万 − 収入13.8万)× 12ヶ月 + 特別支出30万) - 30年間の不足額:164.4万円 × 30年
= 4,932万円
会社員と異なり退職金がないため、約5,000万円の準備が必要。iDeCoや小規模企業共済などでの自助努力が不可欠。
おひとりさま世帯のケース
単身世帯は生活費を抑えやすい一方、年金額も少なくなりがちです。特に賃貸の場合は住居費の負担が大きくなります。(老後期間は30年として計算)
ケース1:男性・会社員・持ち家
会社員40年、持ち家(ローン完済)
- 収入:年金 月16万円
- 支出:生活費 月17万円 + 特別支出 年20万円
- 年間の不足額:32万円
((支出17万 − 収入16万)× 12ヶ月 + 特別支出20万) - 30年間の不足額:32万円 × 30年
= 960万円
退職金(1,500万円)で十分カバーできる見込み。
ケース2:女性・会社員・賃貸
会社員35年、賃貸(家賃7万円)
- 収入:年金 月12万円
- 支出:生活費 月22万円(家賃7万含む) + 特別支出 年15万円
- 年間の不足額:135万円
((支出22万 − 収入12万)× 12ヶ月 + 特別支出15万) - 30年間の不足額:135万円 × 30年
= 4,050万円
退職金(800万円)を差し引いても約3,250万円の準備が必要。家賃負担が大きいため、早期からの貯蓄・運用が重要。
ケース3:自営業・持ち家
国民年金(40年満額)、持ち家(ローン完済)
- 収入:年金 月6.9万円
- 支出:生活費 月16万円 + 特別支出 年25万円
- 年間の不足額:134.2万円
((支出16万 − 収入6.9万)× 12ヶ月 + 特別支出25万) - 30年間の不足額:134.2万円 × 30年
= 4,026万円
退職金がないため、約4,000万円の準備が必要。国民年金基金やiDeCoの活用が必須。
老後資金の不足額を計算する簡単なシミュレーション方法
ケーススタディで大枠を掴んだら、いよいよご自身の数字で計算してみましょう。以下のステップに従って、必要な情報を当てはめてください。
ステップ1:老後の「収入」を把握する
まずは老後(65歳以降)の主な収入源を確認します。
A. 年金見込額(月額):___ 万円
日本年金機構の「ねんきんネット」で試算できます。
B. 老後の就労収入(月額):___ 万円
65歳以降も働く場合の(手取り)見込み額。
C. 退職金・企業年金(一時金):___ 万円
勤務先の規程を確認しましょう。
D. 老後期間:___ 年間
(例)65歳から95歳まで生きる場合「30年間」
ステップ2:老後の「支出」を見積もる
次に、老後の支出を「毎月の生活費」と「年間の特別支出」に分けて計算します。
E. 毎月の生活費(月額):___ 万円
現在の家計簿を参考に、以下の表で試算してみましょう。
| 費目 | 自分の金額(万円) |
|---|---|
| 食費 | 万円 |
| 住居費 (家賃・固定資産税など) | 万円 |
| 光熱・水道 | 万円 |
| 通信費 | 万円 |
| 医療費 | 万円 |
| 交通費 | 万円 |
| 娯楽費 | 万円 |
| 交際費 | 万円 |
| 保険料 | 万円 |
| その他 | 万円 |
| 合計(E) | 万円 |
F. 年間の特別支出(年額):___ 万円
医療・介護費、住宅リフォーム、家電・車の買い替え、旅行費用など。
(例)年間30万円
ステップ3:「年間の不足額」を計算する
ステップ1と2の数字を使って、1年あたりいくら不足するかを計算します。
年間の不足額 =
( ( E + F/12 ) − ( A + B ) )× 12ヶ月
または、
年間支出合計 − 年間収入合計
( E × 12 + F )−( ( A + B ) × 12 )
= ___ 万円
ステップ4:「最終的に必要な貯蓄額」を計算する
年間の不足額に老後期間を掛け、そこから退職金を引いた額が、「今から準備すべき貯蓄額」です。
最終的な必要貯蓄額 =
( 年間の不足額 × D ) − C
( __ 万円 × __ 年間 ) − __ 万円
= __ 万円
シミュレーションのチェックリスト
計算が完了したら、以下の点を見落としていないか確認しましょう。
- 年金見込額は「手取り」に近いか?
(額面から税・社会保険料を引いて考えると、より現実的です) - 賃貸の場合、家賃の更新料や高齢者向け住宅への住み替え費用を考慮したか?
- 介護費用を「特別支出」に含めたか?
(少なくとも数百万単位で見積もっておくと安心です) - 物価上昇(インフレ)の影響を考慮したか?
(例:物価が年1〜2%上昇すると仮定すると、30年後の必要額は現在の1.3〜1.8倍程度になる可能性があります。計算結果には余裕を持たせましょう)
これらを確認できたら、「あなたの場合」の不足額が明確になります。
次章では、この不足額をどう準備していくかを解説します。
老後資金の不足額を準備する3つの方法

老後に必要な資金額(不足額)が見えたら、次は「どう準備するか」という具体的な行動に移ります。やみくもに貯蓄を増やすのではなく、効率的かつ安全に資産を形成することが重要です。
ここでは、老後資金を準備するための3つの柱を紹介します。
- 税制優遇制度(新NISA・iDeCo)の活用
- 長期・積立・分散投資の実践
- 安全資産(保険・国債・現金)での手堅い備え
どれか一つに偏るのではなく、ご自身の年齢やリスク許容度に合わせて、これらをバランス良く組み合わせることが成功の鍵となります。
方法1:新NISA・iDeCoの税制優遇を最大限活用する
老後資金準備の核となるのが、税制優遇制度の活用です。運用で得た利益が非課税になったり(新NISA)、掛金そのものが所得から控除されたり(iDeCo)するため、通常の貯蓄や投資よりも効率的に資産を増やすことができます。
新NISA(少額投資非課税制度)
2024年から始まった新NISAは、投資枠が大幅に拡大され、非課税期間も無期限になりました。
- 2つの投資枠:
- つみたて投資枠:年間120万円(長期の積立・分散投資向き)
- 成長投資枠:年間240万円(株式や多様な投資信託が対象)
- 生涯投資枠:1,800万円(非課税で保有できる元本の上限)
- メリット:運用益や配当金がすべて非課税になります。いつでも引き出し可能です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは、より老後資金に特化した制度です。
- 拠出限度額:職業によって異なる(月1.2万〜6.8万円)
- 3つの税制メリット:
- 掛金が全額「所得控除」の対象となり、毎年の所得税・住民税が安くなる。
- 運用益が非課税になる。
- 受取時も「退職所得控除」または「公的年金等控除」が使え、税負担が軽減される。
- デメリット:原則60歳まで引き出すことができません。
NISAとiDeCo、どちらを選ぶべき?
基本的には両方の活用を推奨しますが、ご自身の状況に合わせて優先順位をつけましょう。
iDeCoが向いている人
- 節税メリット(所得控除)を最大限に受けたい人
- 「老後まで絶対に使わない資金」として強制的に貯めたい人
新NISAが向いている人
- 60歳より前に引き出す可能性(教育資金、住宅購入など)がある人
- iDeCoの限度額以上に投資したい人
- 所得控除の必要がない専業主婦(夫)の方
投資信託を選ぶ際のポイント
NISAやiDeCoで投資信託を選ぶ際は、まず「コスト(購入手数料・信託報酬)」に注目しましょう。信託報酬とは、投資信託を保有している間、継続的にかかる運用管理費用のことです。長期投資ではこのわずかな差が大きなリターン(または損失)の差につながるため、年0.1〜0.3%程度の低コストなインデックスファンドを選ぶのが基本です。
その上で、ご自身の運用方針に合わせ、「全世界株式(世界中に分散)」、「国内債券(安全性重視)」、「バランス型(株式と債券を自動で配分)」などから選びましょう。
方法2:長期・積立・分散投資で着実に資産を増やす
老後資金の準備には、時間を味方につけた投資が有効です。長期・積立・分散投資の3つの原則を守ることで、リスクを抑えながら資産を増やせます。
- 1. 長期投資(時間を味方につける)
-
投資は短期間で見ると価格が大きく変動し、損をすることもあります。しかし、10年、20年という長い期間で保有し続けることで、一時的な市場の下落を乗り越え、世界経済の成長とともに資産価値が上昇していくことが期待できます。また、運用で得た利益が次の利益を生む「複利効果」も、期間が長いほど大きくなります。
- 2. 積立投資(買うタイミングをずらす)
-
「ドルコスト平均法」とも呼ばれます。毎月1万円など、決まった金額を定期的に買い続ける方法です。この方法なら、価格が高い時には少なく買い、価格が安い時には多く買うことになり、自動的に平均購入単価を平準化できます。一度にまとめて購入する「高値掴み」のリスクを避け、短期的な値動きに一喜一憂せずに淡々と続けることができます。
- 3. 分散投資(投資先を分ける)
-
卵を一つのカゴに盛らない(Don’t put all your eggs in one basket.)という格言の通り、投資先を一つに集中させると、その価値が暴落した際に大きな損失を被ります。「株式」と「債券」、「国内」と「海外(先進国や新興国)」のように、異なる値動きをする複数の資産や地域に分けて投資することで、全体としてのリスク(値動きの振れ幅)を抑えることができます。
積立投資のシミュレーション(将来値の計算)
例えば、毎月3万円を積み立てた場合、将来いくらになるでしょうか。
以下の表は、積立期間と想定利回りごとに、将来の試算額がいくらになるかを示したものです。
| 積立期間 (元本) | 年利2% | 年利4% | 年利6% |
|---|---|---|---|
| 10年 (360万円) | 396万円 | 441万円 | 489万円 |
| 20年 (720万円) | 885万円 | 1101万円 | 1386万円 |
| 30年 (1080万円) | 1476万円 | 2085万円 | 3012万円 |
表の通り、毎月3万円を20年間、年利4%で積み立てた場合、試算額は1,101万円となります。(元本720万円に対し、381万円が運用益)
- これはあくまでシミュレーションであり、税金や手数料は考慮していません。また、将来の成果を保証するものではなく、元本割れのリスクもあります。
方法3:保険や個人向け国債などで手堅く備える
投資で「増やす」ことばかり考えると、足元が不安定になります。「守る」資産もしっかりと確保しましょう。
1. 医療・介護リスクへの保険
老後の大きな支出要因である医療費や介護費には、保険で備えるのも一つの手です。ただし、日本には公的保険(健康保険・介護保険)があるため、民間の保険は「公的保険で足りない部分を補う」という意識で過不足を点検しましょう。
- 医療保険
入院日額5,000〜1万円程度が目安。 - がん保険
治療が長期化しやすいため、診断一時金(100〜300万円)があると安心です。 - 介護保険
公的介護サービスで不足する分や、施設入居費用に備えます。
すでに加入中の保険があれば、保障内容が重複していないか、老後の生活に見合っているかを確認しましょう。
2. 個人向け国債を活用
「元本割れのリスクは一切取りたくない」という資金の置き場所として、国が元本と利息を保証する個人向け国債があります。「変動10年」(金利が半年ごとに見直される)タイプなどが人気で、最低金利も年0.05%が保証されており、銀行の普通預金より有利な場合があります。
3. 生活防衛資金を確保
投資や保険とは別に、すぐに使える「現金(普通預金)」を確保しておくことは非常に重要です。病気や失業、市場の暴落時にも、投資資産を取り崩さずに生活を維持できます。
- 現金クッションの目安
- 生活費の6ヶ月〜24ヶ月分
(例)最低6ヶ月分、標準12ヶ月分、介護などに備えるなら24ヶ月分など。
- 生活費の6ヶ月〜24ヶ月分
現金を持ちすぎるとインフレで価値が目減りしますが、少なすぎると緊急時に対応できません。ご自身の安心できる額を決めましょう。
| 商品 | 目的・役割 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|---|
| 医療・介護保険 | 大きな出費への備え | 万が一の際にまとまったお金を得られる | 保険料負担が長期化する |
| 個人向け国債 | 安全な運用 | 元本保証、銀行預金より高利回り | 途中解約にペナルティあり |
| 現金・普通預金 | 流動性・緊急時の備え | いつでも引き出せる | インフレに弱く、利息はほぼゼロ |
老後資金の準備は、「増やす(NISA・iDeCo)」「守る(国債・保険)」「すぐに使える(現金)」という3つの資産をバランスよく準備することが大切です。
ご自身の年齢や目標額に応じて、これらの配分を決め、着実に準備を進めていきましょう。
老後資金がいくら必要か専門家へ相談してみよう

ここまで老後資金の計算方法や準備方法を解説してきましたが、「自分の場合はどう計算すればいいか分からない」「家族と方針を合わせたい」など、一人で判断するのが難しいと感じることもあるでしょう。
そのような場合は、無理に一人で抱え込まず、専門家への相談を選択肢に入れることをおすすめします。相談することで何が明確になり、どのような点に注意すべきかを解説します。
老後資金について専門家に相談するメリット
専門家に相談する最大のメリットは、「あなた専用の具体的な実行プラン」が手に入ることです。
初回相談では、一般的に以下のようなことが明確になります。
- 現状の可視化
現在の家計、資産、保険、手数料(コスト)の一覧 - 目標額の設定
リスク許容度(どれくらいのリスクを受け入れられるか)の診断 - 不足額の確定
現状のまま進んだ場合の、老後資金の具体的な不足額 - 対策プランの提示:
- 不足額を埋めるための毎月の積立額
- NISAやiDeCoの最適な活用法
- 必要な保障額(医療・介護保険)の見直し
相談の基本的な流れ
- 現状ヒアリング
収入、支出、資産、負債、家族構成、将来の希望などを伝えます。 - 目標設定
いつまでに、いくら準備したいかを具体化します。 - 分析・試算
現状と目標のギャップ(不足額)を分析します。 - 対策案の提示
積立額、運用方針、保険見直しなどのプランが示されます。 - 実行計画
次に何をすべきかが明確になります。
初回相談は無料で受けられる窓口も多いため、まずは試してみるのも良いでしょう。
相談時に持参するとスムーズなもの
- ねんきん定期便
(または「ねんきんネット」の試算結果) - 家計簿
(または月々の支出が分かるメモ) - 資産一覧
(預金、株式、投資信託、保険証券、不動産など) - 退職金の見込額がわかる書類
(あれば)
専門家への相談が向いている人・向いていない人の特徴
専門家への相談は万能ではありません。ご自身の状況によって向き・不向きがあります。
- 前提が複雑な人
自営業、不動産収入がある、親の介護費用も見込む必要がある、など。 - 時間が取れない人
仕事や家庭が忙しく、自分で調べる時間的余裕がない。 - 家族の合意形成をしたい人
夫婦で方針を統一したい、子どもに説明する資料が欲しい。 - 客観的な意見が欲しい人
既に準備を始めているが、自分のやり方が適切か確認したい(セカンドオピニオン)。
- 短期で確実なリターンを求める人
「絶対に儲かる」といった保証を期待している(投資のリスクを理解していない)。 - 自分で調べるのが好きな人
ウェブや書籍で十分な情報を集め、自分で判断・実行できる。 - 既に明確な計画がある人
相談しなくても、自分で計画を実行に移せる。
主な相談先3つ(銀行・証券会社/FP/IFA)の特徴を比較
老後資金の相談先は、大きく「銀行・証券会社」「FP(ファイナンシャルプランナー)」「IFA(独立系金融アドバイザー)」の3種類に分かれます。
| 料金 | 顧客本位 | 得意分野 | オンライン対応 | |
|---|---|---|---|---|
| 銀行・証券会社 | 無料 | 会社方針に左右される可能性が高い | 資産運用 | 一部対応 |
| FP (ファイナンシャルプランナー) | 有料が多い (1時間5,000〜2万円) | 中立的 | 家計全般の見直し、ライフプラン作成 | 対応 |
| IFA (独立系金融アドバイザー) | 無料 | 中立的 | 資産運用、ライフプラン、相続など金融全般 | 対応 |
一つの窓口だけで判断せず、複数の相談先で話を聞き、提案内容を比較する「セカンドオピニオン」の活用も非常に有効です。
また、相談内容は(許可を得て)録音したり、詳細なメモを取ったりして、後で家族と共有できるようにしておくと、「こんなはずじゃなかった」という事態を防げます。
相談前のよくある不安(費用・勧誘など)を解消
専門家への相談をためらう理由として、以下のような不安があります。ひとつずつ解消していきましょう。
- Q1:費用はいくらかかる?
-
初回相談は無料の場合が多いです。継続的なサポートを受ける場合は、購入時手数料や相談料が必要になることあります。事前に料金体系を確認しましょう。
- Q2:しつこい勧誘はない?
-
金融商品取引法や保険業法により、強引な勧誘は禁止されています。もし不快な勧誘があった場合は、金融庁や各業界団体の苦情窓口に相談できます。
- Q3:個人情報は大丈夫?
-
金融機関やFPは個人情報保護法に基づき、情報を適切に管理する義務があります。契約前にプライバシーポリシーを確認しましょう。
- Q4:商品の押売りはない?
-
相談先が商品販売を目的としている場合、特定の商品を強く勧められることがあります。提案理由を明確に聞き、納得できない場合は断りましょう。
まとめ

老後資金の不安を解く第一歩は、「平均」ではなく自分の前提で試算することです。
まずは将来の受給見込額を確認し、生活費を差し引いて不足額を把握しましょう。足りない分は、新NISAやiDeCoを活用した長期・積立投資で早めに準備を始めてください。
もし、老後資金について何か不安があれば、ファイナンシャルプランナーなど専門家への相談がおすすめです。
老後資金に関するよくある質問(FAQ)

出典一覧
総務省統計局「家計調査報告(家計収支編)2024年平均結果の概要」
公益財団法人 生命保険文化センター「老後の生活費はどれくらい?」
日本年金機構「ねんきんネット」
厚生労働省「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
金融庁「NISA特設ウェブサイト」
- 本記事は2025年10月21日時点の情報に基づいて作成しています。制度や数値は今後変更される可能性があるため、最新情報は各公的機関のウェブサイトでご確認ください。
- 本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の資産運用や年金受給に関するアドバイスではありません。具体的な判断が必要な場合は、専門家への相談をおすすめします。