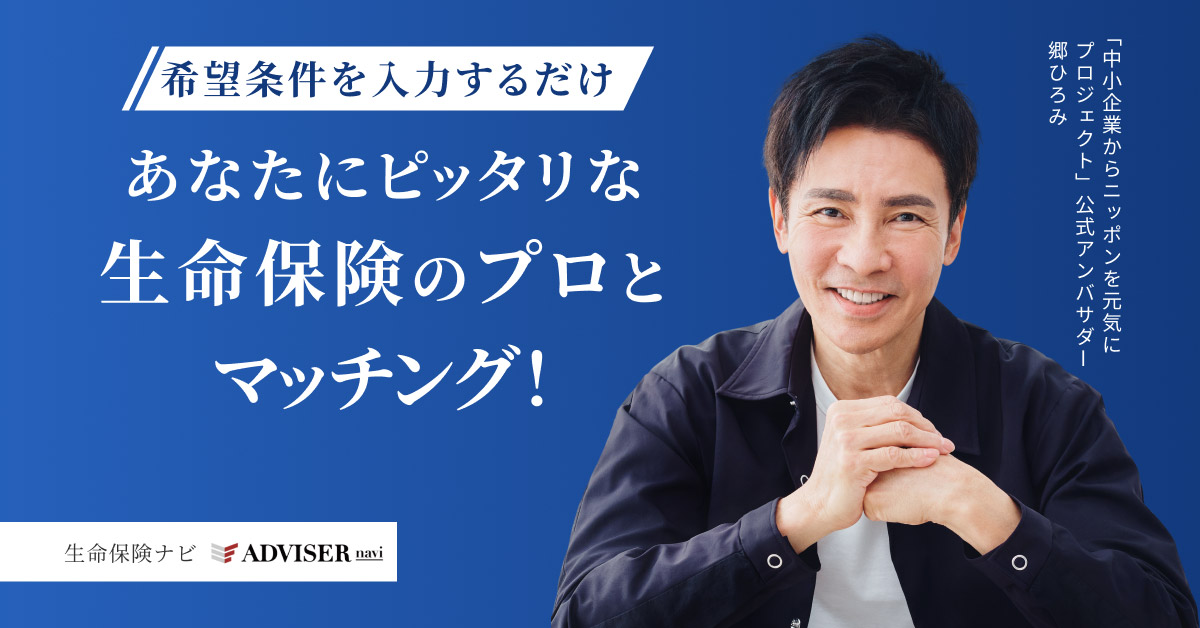- かんぽ生命の養老保険に加入しているが、満期保険金がいくらになるのか知りたい
- 満期保険金を受け取る際にかかる税金の仕組みについて知りたい
- 満期保険金の活用法がわからない
かんぽ生命は、保険料の払込期間や受け取る保険金の金額などの目的別に、さまざまな養老保険を販売している。
養老保険は万一の際の保障と資産形成の役割を兼ね備えた保険であるため、選ぶ際に「満期保険金がいくらになるのか」が気になる方も多いだろう。
そこで本記事では、かんぽ生命が販売する養老保険の特徴やメリットを踏まえ、満期保険金について詳しく解説していく。
また、保険に加入する際の注意点についても述べるので、養老保険への理解を深め、より効果的に活用するための一助としてほしい。
満期保険金はいくら?かんぽ生命の養老保険を詳しく解説

かんぽ生命は、養老保険・終身保険などに医療特約を付加する、小口の保障額(1件あたり平均保険金額266万円)の商品を中心に展開する保険会社である。全国の郵便局の窓口や支店を通じて契約が可能だ。
まずはかんぽ生命の養老保険の満期保険金や、かんぽ生命の養老保険の種類について解説する。
満期保険金と養老保険とは
満期保険金とは、保険契約が満期を迎えたときに受け取れる保険金の一種である。
保険期間中に被保険者が死亡(または高度障害状態)になったときに受け取れる死亡保険金(高度障害保険金)と、ある意味で対となる保険だ。
保険契約を途中で解約したときに受け取れる解約返戻金とも、異なる性質を持つ。
満期保険金が受け取れる保険としては、生存給付金付定期保険、学資保険、養老保険といった満期がある貯蓄型の商品が挙げられる。
そして養老保険とは、保険期間中に被保険者が亡くなったときには死亡保険金、満期まで生存したときの満期保険金が受け取れる二重の保険だ。
性質上、死亡保険金と満期保険金はどちらかしか受け取れない。
老後資金や教育資金などを準備しながら、万が一のときに備えられるのが養老保険のメリットである。
しかし貯蓄性が高い分、月々の保険料は高めに設定されているデメリットがある。
かんぽ生命の養老保険・満期保険金の特徴
かんぽ生命の養老保険なら、契約者の目的によって柔軟に保険期間を選ぶことができる。
例えば「養老保険 新フリープラン」なら、10~60年の間で保険期間を設定が可能だ(加入年齢により一定の制限あり)。
かんぽ生命の満期保険金は、100〜1,000万円の間で設定できる。設定金額によって月々の払込保険料が変わるので、無理のない金額を設定しよう。
死亡保険金の設定は、プランによって満期保険金の同額・2倍・5倍・10倍に設定できる。
さらにかんぽ生命の養老保険は、特約を付与することで不慮の事故や感染症などへの保障も受けられる。
具体的には総合医療特約(R04)を付けることで、病気やケガで入院したときも入院一時金・入院保険金・手術保険金・放射線治療保険金が受け取れる。
他にも、無配当先進医療特約や無配当傷害医療特約(R04)などの特約を、任意で付けることが可能だ。
契約者の目的に応じた資産形成と、死亡・病気・ケガへの備えを1つの保険でまかなえるのが、かんぽ保険の養老保険の特徴だと言えるだろう。
かんぽ生命の養老保険の種類・特徴
2023年11月時点での、かんぽ生命の養老保険の種類と特徴を紹介する。
- 新フリープラン
- 新フリープラン(短期払込型)
- 新フリープラン(2倍保障型)
- 新フリープラン(5倍保障型)
- 新フリープラン(10倍保障型)
- かんぽにおまかせ(満期タイプ)
新フリープランとは、かんぽ生命の養老保険の中でもオーソドックスなタイプである。
満期保険金は100万〜1,000万円の範囲で設定が可能だ。死亡保険金は、満期保険金と同額となる。
また、契約日を含めた1年6か月以内に「不慮の事故によるケガで180日以内に死亡したとき」、または「所定の感染症で死亡したとき」に支払われる倍額保障が付いている。
なお満6歳未満の被保険者が死亡したときは、受け取れる死亡保険金が80%または50%になるので注意しよう。
| 新フリープラン | 概要 |
|---|---|
| 保険期間 | 10~60年 |
| 死亡保障 | 満期保険金と同額 |
| 加入年齢 | 0~80歳 |
| 満期年齢 | 10~90歳 |
| 死亡保険金額 | 100万~1,000万円 |
新フリープラン(短期払込型)は、原則として保険料払込期間10年・保険期間15年と、短い期間が設定されているタイプの養老保険である。
貯蓄や収入に余裕があり、保障を受けつつ早めに満期保険金を受け取りたいときは、短期払込型にするとよい。
| 新フリープラン(短期払込型) | 概要 |
|---|---|
| 保険期間 | 15年 |
| 死亡保障 | 満期保険金と同額 |
| 加入年齢 | 0~75歳 |
| 満期年齢 | 15~90歳 |
| 死亡保険金額 | 100万~1,000万円 |
新フリープランの2倍・5倍・10倍保障型は、受け取れる死亡保険金の金額が満期保険金の倍数で受け取れる商品だ。
通常の新フリープランよりも手厚い死亡保険金を求めるときは、こちらの商品を選ぶのがよい。
| 新フリープラン(~倍保障型) | 概要 |
|---|---|
| 保険期間 | 10~60年 |
| 死亡保障 | 満期保険金の2倍・5倍・10倍 |
| 加入年齢 | ・2倍保障型は15~70歳 ・5倍10倍保障型は15~65歳 |
| 満期年齢 | 25~75歳または80歳 |
| 死亡保険金額 | 100万~1,000万円 |
かんぽにおまかせ(満期タイプ)は、「3か月以内に医師から入院や手術などを勧められたことがない」「過去2年間で入院や手術をしたことがない」「過去3年以内にがん・肝硬変・認知症の診察・検査などを受けたことがない」に該当すれば、持病があっても加入できる引受基準緩和型の養老保険である。
特約は、引受基準緩和型無配当総合医療特約(R04)を付与可能だ。
これまでに持病や入院歴がある人でも、かんぽにおまかせなら養老保険として運用ができる。
| 新フリープラン(~倍保障型) | 概要 |
|---|---|
| 保険期間 | 10~35年 |
| 死亡保障 | 満期保険金と同額(支払削減期間中を除く) |
| 加入年齢 | 40~80歳 |
| 満期年齢 | 50~90歳 |
| 死亡保険金額 | 100万~1,000万円 |
かんぽ生命の養老保険で付けられる特約一覧
かんぽ生命の養老保険に付けられる特約についても、一部紹介する。
医療保障をより充実させたい方は、特約を利用しよう。
| かんぽ生命の養老保険に 付けられる特約 | 概要 |
|---|---|
| 無配当総合医療特約(R04) | 病気や不慮の事故でのケガにより3年以内に入院、手術、放射線治療となったときに、入院一時金や手術保険金などを受け取れる特約 |
| 無配当先進医療特約 | 先進医療に該当する療養を受けたときに、先進医療保険金を受け取れる特約 |
| 無配当傷害医療特約(R04) | 無配当総合医療特約と同じく、入院や手術への備えができる特約 |
| 無配当災害特約 | 特約の保険期間中に不慮の事故・ケガで死亡または所定の身体障害になったときに特約保険金を受け取れる特約 |
| 引受基準緩和型無配当総合医療特約(R04) | かんぽにおまかせ(満期型)といった、引受基準緩和型保険に付けられる特約 |
なお上記の特約は、養老保険以外のかんぽ生命の医療保険にも適用可能だ。
満期保険金と税金の関係

身体の疾病や傷害などによって受け取れる生命保険の保険給付全般は、原則として非課税である。
一方で満期保険金は保険契約による保険金ではあるものの、疾病や傷害が起因となって受け取れるものではないので、金額に応じて税金がかかる。満期保険金と税金の関係を見ていこう。
満期保険金にかかる税金
満期保険金にかかる税金は、「保険料を誰が負担していたのか」「満期保険金を誰が受け取るのか」によって、発生する税金の種類が変わる。対応表を以下で見ていこう。
| 保険料を支払っている人 | 満期保険金の受取人 | かかる税金の種類 |
|---|---|---|
| A | A | 所得税 |
| A | B | 贈与税 |
保険料を支払っている人と満期保険金の受取人が同じ場合は、受取人の収入として所得税が課せられる。
かんぽ生命の満期保険金は一時金として受け取ることから、所得税の一時所得として受け取る。
一時所得は給与所得などと異なり、払込保険料分の差し引きや特別控除などが適用されるのが特徴だ。
具体的な一時所得の計算式は、「(満期保険金-払込保険料-特別控除50万円)×1/2」である。
一時所得を算出した後は、給与所得といった所得と合算し税額を計算する。
一方で、保険料を支払っている人と満期保険金の受取人が異なる場合(親が支払って子どもが受け取るなど)は、受取人へお金を渡すという流れになる。
そのため、かかる税金は所得税ではなく贈与税だ。
同じ金額の満期保険金を受け取る場合、贈与税は所得税より高くなるので注意しよう。
なお、かんぽ生命以外の保険会社の養老保険だと、満期保険金の受け取り方を年金形式(年金のように分割して少しずつ受け取る方法)にできる場合がある。
年金形式だと、一時金として受け取るときと税金のかかり方が異なるので注意しよう。
解約返戻金や死亡保険金にかかる税金
養老保険で受け取れる可能性がある保険金には、満期保険金以外にも解約返戻金(保険を途中解約したら返ってくるお金)と死亡保険金がある。
解約返戻金の税金のかかり方は、満期保険金と同じだ。もし受け取る解約返戻金より払込保険料総額の差が50万円を超える場合は、税金が発生しない。
とはいえ、解約返戻金は満期保険金よりも返戻率が低くなるので注意したい。
死亡保険金にかかる税金は、保険料を支払っている人と受取人が異なると種類が変わる。
死亡保険金の場合は相続も絡んでくるので、満期保険金の税金関係より複雑になる。課税関係の表は次の通りだ。
| 被保険者 | 保険料を支払っている人 | 死亡保険金の受取人 | かかる税金の種類 |
|---|---|---|---|
| A | B | B | 所得税 |
| A | A | B | 相続税 |
| A | B | C | 贈与税 |
死亡保険金に相続税がかかる受け取り方をしたときは、死亡保険の非課税枠を利用できる。
適用できるのは、「500万円×法定相続人の数」である。
例えば死亡保険金が1,000万円だと、配偶者と子1人が相続人なら1,000万円の非課税枠が適用され、死亡保険金には税金がかからない。
満期を迎えたときに気を付けるべきポイント
かんぽ生命の養老保険で満期を迎えるときには、「満期保険金の受取人が本当にそのままでよいのか見直す」「満期になったときに更新するかどうかを検討する」などの点を、あらためて確認しておこう。
また、満期保険金を受け取る年度は満期保険金の分だけ所得税が高くなる可能性がある。
養老保険にかかった保険料分の生命保険料控除の申請などを忘れないようにしよう。

満期保険金の活用法とは?

ここからは、満期保険金の活用方法の例について解説する。
かんぽ保険の満期保険金を何に活用すべきか検討している方は、ぜひ参考にしてほしい。
満期保険金の活用方法の例
かんぽ生命の満期保険金は、100万〜1,000万円と高額になる。
そのため、受け取った後はさまざまな活用方法が考えられる。
満期保険金の活用方法について、いくつか例を見ていこう。
- 子どもの大学入学金や生活費などの教育資金
- 老後の生活費用や介護費用
- マイホーム購入時の頭金や住宅ローン返済、リフォームなどのマイホーム用の資金
- 家族旅行や車の買い替え、趣味などのプライベート費用
- 株式や投資信託などの保険以外の資産運用の元本
- 独立・起業用の開業資金
上記はあくまで一例であり、他にも多くの使い道があるだろう。
満期保険金の使い方に制限はないので、あなたが本当に必要なことに活用することをおすすめする。
満期保険金の活用方法を見極める方法
満期保険金の活用方法を見極めるには、あなた自身のニーズやライフプランを明確にすることが大切だ。
以下の方法で、満期保険金を何に使うべきなのか洗い出してみよう。
- 将来を見越したライフプランを設計し、養老保険の満期になった時点でどのようなライフイベントや支出が発生するのか見ておく
- 養老保険が満期になった時点での生活環境、経済状況、健康状態、貯蓄状況の予測を立て、満期保険金をいくら使えるのかを確認しておく
- 保険のプロや資産運用のプロへ相談し、活用を検討してみる
数百万円レベルを受け取れるので、なんとなくで使うよりもしっかりと検討した上で使い道を決めることをおすすめする。
まとめ

本記事では、かんぽ生命が販売する養老保険の特徴やメリットを踏まえ、満期保険金について詳しく解説した。
かんぽ生命は目的別に現在6タイプの養老保険を販売している。それぞれの保険金設定や保険金にかかる税金の仕組みについて把握し、貯蓄型保険としての養老保険を賢く活用してほしい。
数多くのプランの中から、自分が求める保障内容を備えた保険を選ぶのは簡単なことではない。
また、保険金の活用先にも多様な選択肢がある。何より重要なことは、それぞれ保険の特徴を理解し、また自分自身の生活環境や経済状況、健康状態を考慮して保険を選ぶことだ。
そのため、自分が加入するべき保険について、少しでも疑問や不安があれば保険のプロに相談することも積極的に検討しよう。
1人ひとりに合ったアドバイスをもらうことで、あなたに合った保険を見つけることができるはずだ。
しかし保険のプロは数多く存在し、その中から自分にとって最適な担当を見つけるのは困難になる。
そのようなときはマッチングサイト「生命保険ナビ」の活用がおすすめだ。
無料で利用できるので、ぜひ活用してほしい。