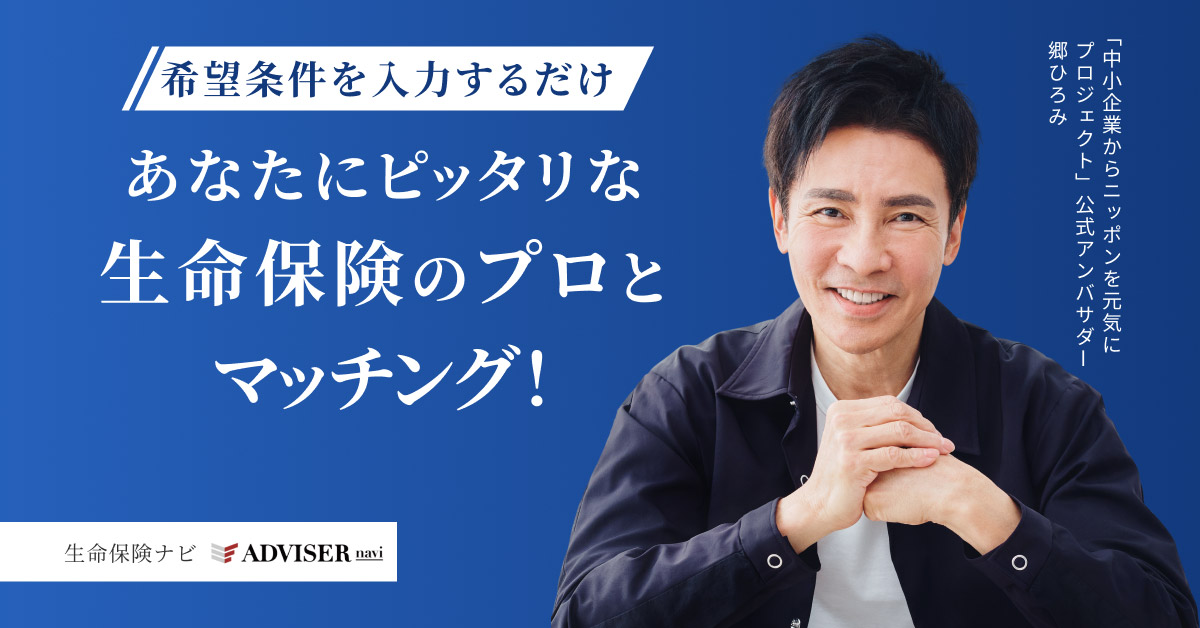- かんぽ生命の学資保険の返戻率がよく分からない
- かんぽ生命の学資保険の基本的情報が知りたい
- 他社の学資保険と比較した時の選択基準が知りたい
かんぽ生命の学資保険には、保険金の受け取り時期に合わせて3つのタイプが用意されている。
また、今年の3月には保険をリニューアルし、返戻率が改善された。
そこで本記事では、かんぽ生命の学資保険の特徴やメリット、返戻率について詳しく解説していく。
また、保険に加入する際の注意点についても述べるので、学資保険への理解を深め、より効果的に活用するための一助としてほしい。
かんぽ生命の学資保険「はじめのかんぽ」を徹底解説

子どもの将来をサポートする学資保険だが、「どの学資保険を選べばいいのだろう?」と悩んでしまう人も多いだろう。
ここでは、学資保険についての知識や、おすすめの学資保険「はじめのかんぽ」について紹介していくので、ぜひ今後の参考にしてみてはいかがだろうか。
子どもの未来をサポートする「学資保険」
子どもが進学するタイミングで保険金を受け取れる「学資保険」は、妊娠中から加入でき、子どもの将来をサポートする手段として加入している人が多い傾向にある。
割合で言うと、49%の人が学資保険で子どもの将来のために備えており、そのうち34%の人が保険金(総額)200万円に設定している割合が高い。
全体の約半分の人が学資保険に加入しているとしても、「本当に学資保険に加入すべき?」と悩んでしまう人も少なくないだろう。
実際に、「高等学校等就学支援金制度(通称:高校無償化制度)」という制度で国が学びをサポートしている。
高等学校等就学支援金制度は、条件を満たしている者は実質無料で高校に通える制度のことだ。
このような制度を利用すれば、「高校進学時にお金はかからない」と感じてしまうが、入学金・教科書代・通学定期代・制服などの衣類代は対象外になる。
他にも、学校納付金・遠足や修学旅行の積立金・教科外活動費などの費用が必要になるため、学資保険に加入しておくと安心できるだろう。
高校入学時に必要な費用(目安)を下記の表で紹介するので、実際にどれくらいの費用がかかるのか確認していこう。
高校入学時の費用(目安)
| 費用名 | 金額 |
|---|---|
| 入学金(公立) | 5,550円/5,650円※都道府県によって異なる |
| 入学金(私立) | 平均約160万円 |
| 教材 | 平均約4万1千円 |
| 通学関連費※定期代・制服やバッグなど | 平均約8万円 |
公立・私立で入学金は異なるが、入学金を除いても約12万円もの費用がかかるのだ。
兄弟などの進学タイミングと重なれば、大きな金額が必要になるため、経済的負担を減らすためにも学資保険に加入しておくのが理想的だ。
次に、大学入学時(目安)の費用を下記で紹介していく。
国立大学・私立大学、進学する学科によって金額の差はあるが、1つの基準として参考にしてほしい。
大学入学時の費用(目安)
| 入学先 | 初年度費用 |
|---|---|
| 国立大学 | 約80万円~100万円 |
| 私立大学(文系) | 平均約120万円 |
| 私立大学(理系) | 平均約160万円 |
| 私立大学(医歯系) | 平均約490万円 |
参考:マネープラザ ONLINE「大学の学費はどのくらいかかる? 金額の目安や資金を確保する方法」
以上のように、大学へ進学するとなると高校進学よりも多額のお金が必要になる。
将来、子どもが進みたい道を選べるために備えたい人は、学資保険への加入を検討するといいだろう。
学資保険「はじめのかんぽ」について解説
かんぽ生命の「はじめのかんぽ」は、日本で最初に作られた学資保険で、現在260万人以上の人が加入している学資保険だ。
さまざまな学資保険がある中、多くの人が契約しており、「はじめのかんぽ」の保有契約数が第1位である。
2023年4月にリニューアルし、返戻率が旧タイプよりもよくなった。
そのため、子どもの将来をサポートしたいと考える人に人気がある保険だ。
支払った保険料に対して、どれだけの保険金を受け取れるか表したパーセンテージのこと
はじめのかんぽは、コースが3種類用意されているので、保険に加入する目的や保険料などに合わせて選べる。
下記では、基本情報を紹介していくので確認していこう。
「はじめのかんぽ」の基本情報
| 小・中・高+大学入学時コース | 大学入学時+在学中コース | 大学入学時コース | |
|---|---|---|---|
| 被保険者加入年齢 ※子ども | 0~3歳 | 0~12歳 | |
| 契約者加入年齢 ※親・祖父母 | 男性:18~65歳 女性:16~65歳 | ||
| 満期年齢 | 17歳・18歳 | 21歳 | 17歳・18歳 |
| 保険料払込期間 | 12歳満期まで | 12歳・18歳 | 12歳満期まで |
| 受給タイミング | 小学校・中学校高校・大学 | 大学入学時大学2~4年生 | 入学時 |
| 医療特約 | 可能 | ||
| 保険料払込免除特約 | 可能 | ||
| 出生前加入 | 可能 (予定日より140日前から) | ||
以上のように、保険金を受け取りたいタイミングに合わせてコースを選べるため、ライフプランなどに合わせながら選んでいこう。
中には、「子どもにお金がかからないうちに保険料の支払いを終わらせたい」と考える人も多いだろう。
そのような人は、10歳までに払込みが終えられるプランを選べるため、計画的に保険に加入可能だ。
また、病気やケガをした際に保障を受けられる「医療特約」を付帯させられることや、契約者(親など)が亡くなった(高度障害状態)場合、保険料の払込を免除される「保険料払込免除特約」を受けられる。
そのため、子どもの将来をサポートするための教育資金準備だけではない魅力が詰まった保険だと言えるだろう。
「はじめのかんぽ」の口コミ
実際に「はじめのかんぽ」に加入した契約者のリアルな口コミを紹介していくので、ぜひ今後の参考にしてほしい。
- ポジティブな口コミ
30代/女性
郵便局の担当者の方がとてもわかりやすく丁寧に説明してくれて、利用しやすいと思いました。
30代/女性
掛け金が負担なく出来るプランがある点が良かった。本荘郵便局の人柄がとてもいい。
40代/男性
万が一の時のために加入しているのと、将来のために加入しているので、安心感がある。
40代/女性
子供の進学に伴う出費など、計画的に貯められて将来に役立つ。
参照:オリコン顧客満足度ランキング 「かんぽ生命 学資保険の評判・口コミ」
- ネガティブな口コミ
30代/女性
手続きにやや時間を要した。乳児を見ながらだともう少し短縮できるとありがたい。
30代/男性
窓口の郵便局が閉鎖してから、ほとんど何も連絡がなくなった。
50代/男性
手続きに、時間と手間がかかります。ネットでいつでも、契約できるようになってほしい。
参照:オリコン顧客満足度ランキング 「かんぽ生命 学資保険の評判・口コミ」
以上のように、窓口があるからこそ丁寧な説明を受けられ、「利用しやすい」と感じる人が多い傾向にある。
だが、その反面、契約自体に時間がかかるなどのネガティブな口コミが目立った。
そのため、はじめのかんぽの説明を聞きに行きたいときや、保険の契約を行いたい場合は、時間を確保してから窓口に行くといい。
「はじめのかんぽ」の返戻率はどれくらい?

支払った保険料に対して、どれだけの保険金を受け取れるか表したパーセンテージが「返戻率」だが、はじめのかんぽの返戻率はどれくらいあるのだろうか。
ここでは、はじめのかんぽの返戻率と他社の学資保険の返戻率を比べながら、メリットなどを解説していく。
「はじめのかんぽ」の返戻率は?
「はじめのかんぽ」の返戻率を参考として下記に紹介していくので、参考にしてほしい。
また、返戻率は、コース・契約者(親など)・被保険者(子ども)などによって異なるので注意してほしい。
| 契約条件 | |
|---|---|
| 種類 | 18歳満期学資保険 |
| 受取学資金 | 200万円 |
| 被保険者(子ども) | 0歳 |
| 契約者(親など) | 30歳男性 |
| 保険料払込期間 | 10年 |
| 支払方法 | 口座振込み月払い |
| 返戻率 | 101.2% |
参照:かんぽ生命「かんぽの「学資保険」がリニューアル!」
はじめのかんぽでは、返戻率は101.2%となっている。そのため、支払った保険料よりも多い保険料を受け取れる。
しかし、101.2%という数字を見ても「他社に比べたらどうなんだろう?」と感じてしまう人も多いだろう。
下記では、他社の学資保険の返戻率を紹介するので、はじめのかんぽは他社に比べてどうなのか確認していこう。
契約条件(被保険者・契約者・保険料払込期間・18歳満期)は、上記「契約条件」と同じに設定しているので、ぜひ参考にしてほしい。
| 保険会社 | 学資保険 | 返戻率 |
|---|---|---|
| かんぽ生命 | はじめのかんぽ | 101.2% |
| 明治安田生命 | つみたて学資 | 104.70% |
| こくみん共済 | こども保障満期金付タイプ | 101.75% |
| JAこども共済 | 学資応援隊 | 101.10% |
| アフラック | 夢みるこどもの学資保険 | 98.10% |
| SOMPOひまわり生命 | こども保険 | 91.09% |
| 太陽生命 | わくわくポッケ | 85.81% |
以上のように、「はじめのかんぽ」よりも返戻率が高い学資保険はあるが、保険料などが異なるため返戻率の項目以外もしっかりと比較しなければならない。
また、返戻率が100%を下回る保険もあるため、学資保険への加入を考えている人は返戻率をしっかりと確認しよう。
「はじめのかんぽ」に加入するメリット
「はじめのかんぽ」に加入するメリットはどのようなものがあるのだろうか。
ここでは、加入するメリットを紹介するので、ぜひ参考にしてみてはいかがだろうか。
- 学資保険に加入する目的に合わせてコースを選べる
- 出産前でも学資保険に加入できる
- 契約者貸付制度を活用できる
- 18歳満期だけではなく、17歳満期も選べる
- 契約者(親など)が万が一死亡しても、保障される
学資保険に加入する目的に合わせてコースを選べる
「小・中・高+大学入学時コース」「大学入学時+在学中コース」「大学入学時コース」のコースがあるため、保険に加入する目的によってコースを選べる。
保険料や望んでいる条件などに合わせて選べるため、計画的に教育資金を準備したい人は多くのコースから選べる「はじめのかんぽ」はおすすめだ。
出産前でも学資保険に加入可能
出産予定日から140日前から保険に加入できるため、子どもが生まれ忙しくなる前に学資保険に加入しておくと安心だ。
出産前に加入しておくと、毎月の保険料を安く抑えられるメリットもあるため、早めの加入がおすすめである。
契約者貸付制度の利用ができる
万が一、まとまったお金が必要になった場合、「はじめのかんぽ」であれば契約者貸付制度の利用ができる。
カードローンなどでお金を用意するよりも利息を抑えられるため、もしものときに利用できるのはメリットだと言える。
18歳満期だけではなく、17歳満期も選べる
多くの学資保険では18歳満期が多い傾向にあるが、「はじめのかんぽ」では17歳満期の選択ができる。
子どもが早生まれの場合、17歳満期がおすすめである。
早生まれの場合、18歳満期で契約すると、高校卒業~大学入学直前のタイミングで保険金を受け取る可能性が高いからだ。
入学金・教材・引越し費用などに充てたいと考えていても、理想のタイミングで保険金の振込みが間に合わないケースがある。
そのため、17歳満期に設定しておくと安心できるだろう。
契約者(親など)が万が一死亡しても、保障される
上記「学資保険「はじめのかんぽ」について解説」でも紹介した「保険料払込免除特約」は、契約者(親など)に万が一のことがあった場合に適用されるため、非常に大きなメリットだ。
自分にもしものことがあっても保障は継続されるため、子どもが進学を諦めることを回避できる。
「はじめのかんぽ」への加入が向いている人
「はじめのかんぽ」への加入が向いている人は、下記のような人である。
1つの判断基準として、考えてみてはいかがだろうか。
- 目的に合わせてコースを選びたい
- 出産前からの学資保険への加入を考えている
- 推薦入試などの一般入試以外にも備えたい
- 病気やケガに備えて医療保障を受けたい
- もしものときのために「契約者貸付制度」を利用できる学資保険がいい
学資保険選びのポイント

「子どものためにベストな保険を選びたい」と考える人は多いだろう。
しかし、学資保険は多くの種類があるため、ベストな保険を選ぶのは難しい。
ここでは、学資保険選びのポイントを3つ解説していくので、ぜひ参考にしながらベストな学資保険を選んでほしい。
「どうして学資保険に加入するか」を考える
学資保険に加入する目的をハッキリさせなければ、ベストな保険を見つけるのは難しい。
そのため、「どうして学資保険に加入するか」をしっかりと考えた上で、複数の学資保険を比較するのがおすすめである。
例えば、「計画的に教育資金を準備したい」「出産前から備えて保険料を抑えたい」「自分にもしものことがあっても、保険金を受け取れるようにしておきたい」など、目的はさまざまだ。
家族と学資保険に加入する目的を話し合い、ベストな保険を選ぶための軸として活用していこう。
だが、学資保険への加入目的を明確にしても「どの保険を選べばいいかわからない…」と感じる人もいるだろう。そのような人におすすめな方法は、保険の専門家に相談するということだ。
「生命保険ナビ」であれば、保険の専門家と無料でマッチングできるため、より理想に近い学資保険を選びたいと考えている人はぜひ利用してほしい。
保険金を受け取るタイミングはいつがいいか
保険金を受け取るタイミングは、人によって望むタイミングは違う。
例えば、「大学に進学するときに保険金を受け取りたい」「進学するタイミングで毎回保険金を受け取りたい」などだ。
上記で考えた「保険に加入する目的」を基準に、受け取るタイミングを考えると、複数の学資保険から選びやすくなるだろう。
保険料を毎月支払い続けられるか考える
「子どものために保険金は多くしたい」「病気やケガにも備えておきたい」など、学資保険に対して多くのことを求めたくなる人も多い。
しかし、理想をすべて詰め込むと保険料が高くなるため、注意が必要である。
また、「この金額なら保険料を毎月支払える」と現時点で感じていても、第二子を授かる・転職・引越し・病気やケガが原因で入院するなどが発生すると、保険料を支払えない可能性が0ではない。
そのため、「これからも毎月支払える保険料かな?」と考えることが、学資保険を選ぶ際に重要なポイントである。
まとめ

本記事では、かんぽ生命の学資保険の特徴やメリット、返戻率について詳しく解説した。
学資保険は子供の未来を保障する大切な経済的支えだ。
また、「返戻率」とは、保険契約者が支払った保険料に対する、受け取る保険金額の割合を指し、特に貯蓄型保険の一種である学資保険を選ぶ際には重要な指標となる。
しかし返戻率だけで加入する保険を決めることはお勧めできない。
一口に学資保険と言っても数多くのプランが存在し、その中で自分に必要な保障内容を備えた保険に入ることが求められるのだ。
今回紹介した保険選びのポイントを参考に、あなたに合った学資保険を見つけるようにしてほしい。
このように、何より重要なことは、保険の特徴を理解し、また自分自身の生活環境や経済状況、健康状態を考慮して選ぶことだ。
そのため、自分が加入するべき保険について、少しでも疑問や不安があれば保険のプロに相談することも積極的に検討してほしい。
一人一人に合ったアドバイスをもらうことで、あなたに合った保険を見つけることができるはずだ。
また、保険のプロは数多く存在し、その中から自分にとって最適な担当を見つけるのは難しいだろう。
そんな時はマッチングサイト「生命保険ナビ」を使えば、自身の条件に合った保険のプロを簡単に見つけることができる。
無料で利用できるので、ぜひ活用してほしい。