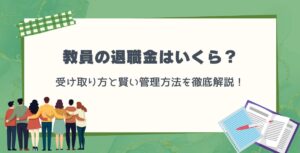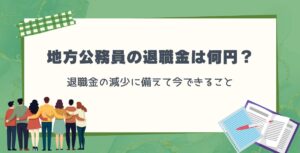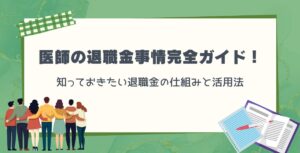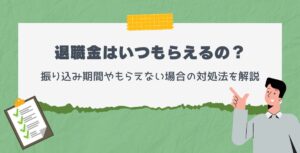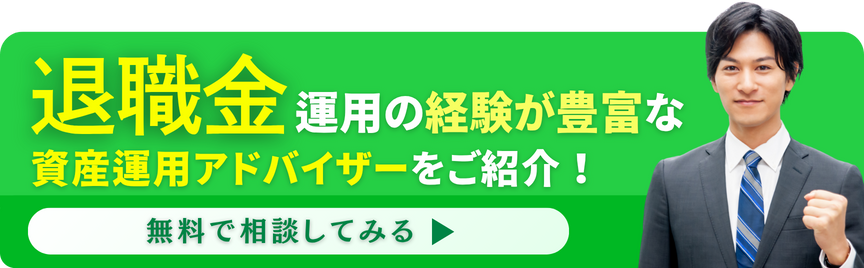少し前までは「国家公務員は残業も少なく、福利厚生も充実している。さらに給与待遇も良い」というイメージがあったかと思うが、ここ数十年の間で実態は大きく変わっている。
特に退職金は総務省の人事院が定期的に「減額勧告」をするため、国家公務員の退職金は年々減少傾向にある。
その他にも共済年金の制度が見直され、厚生年金に統合されたことで保険料率の引き上げも行われている。
このように、安定のイメージがあった国家公務員も実態が変わりつつあるので、今後を見据えて今からでも老後の準備をしておくことを推奨する。
そこで、この記事では国家公務員の退職金を紹介しつつ、国家公務員の方はどのようにして老後に向けて資産を作るべきかご紹介する。
資産形成は早い段階から始めることでメリットが大きくなる。ぜひ最後までご覧いただき、参考にしていただければと思う。

退職金ナビ
- 60秒で簡単検索!
- 自分に合ったアドバイザーが見つかる!
- 相談料は完全無料!
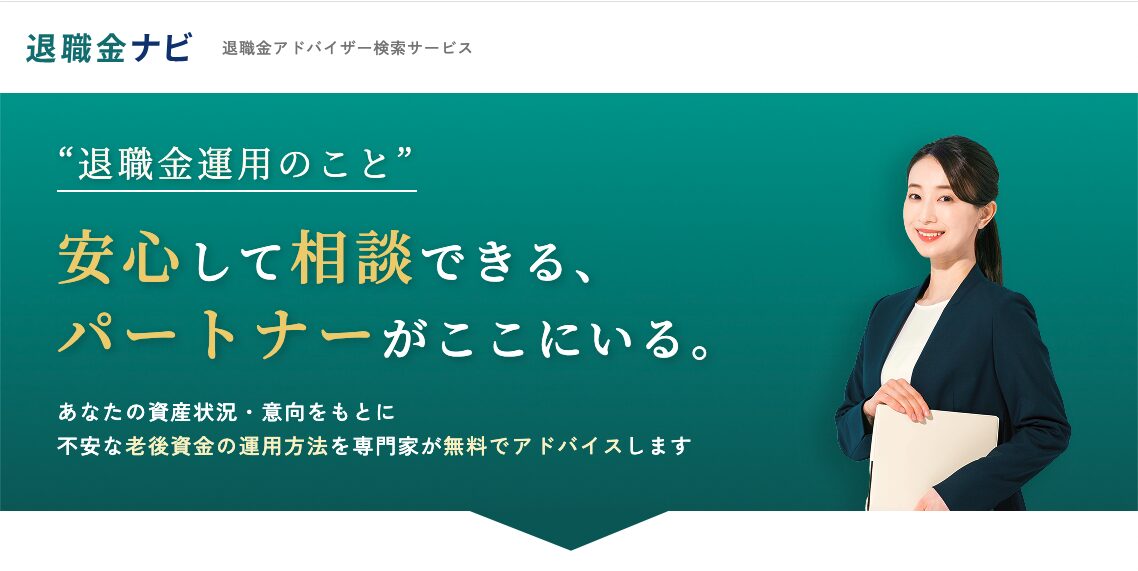
\あなたに合う相談相手がすぐに分かる/
国家公務員の退職金はいくら?

実際に国家公務員の方がもらえる退職金の金額をご存知だろうか。
民間企業の退職金は法律で定められておらず、各企業が独自のルールで算出する。
企業によっては退職金がない会社もある。
一方で、国家公務員の方は「国家公務員退職手当法」という法律に基づいて退職金が計算される。
では、具体的な金額相場と計算方法を確認していこう。
国家公務員の退職金相場
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 定年退職のみの 平均退職金額 | 約2,142万円 |
| 自己都合を含んだ 平均退職金額 | 約1,023万円 |
毎年、総務省の内閣人事局が公表している「国家公務員退職手当実態調査(令和2年度)」によると、常勤職員として定年を迎えた国家公務員の方は約2,142万円だ。
自己都合による退職を含めた平均額は1,023万円だ。
当然といえば当然だが、国家公務員として長く勤めた方ほど退職金の金額が多い傾向がある。
また、職員別で見た場合、都道府県職員で約2,164万円、政令指定都市職員で約2,097万円、市職員で約2,101万円、町村職員で約1,981万円、特別区職員で約2,097万円だ。
ここからさらに職種別でみていくと、教育公務員の場合は退職金平均が約2,262万円、警察官の場合は約2,229万円だ。
国家公務員の退職金の計算方法
国家公務員の退職金は「国家公務員退職手当法」に定められており、「基本額(退職日の俸給月額×退職理由別・勤続期間別支給率)+調整額」で計算されている。
例えば、在職38年、退職日の俸給月額が40万円、定年で退職した場合は、基本額は40万円×47.709(勤続38年の支給割合)となり、調整額は54,150円×60ヶ月となるので、これらを合算した2,233万2,600円が退職金として支給される。
国家公務員の退職金は今後減額される?

国家公務員の退職金は定期的に総務省の人事院から国家公務員給与改定の勧告を受けている。
これは国家公務員などの公務員と民間人の格差を埋めるのが目的で、従業員50人以上の企業から抽出した1万2千事業所を対象に民間の給付状況を調査している。
その調査結果次第では、国家公務員の退職金が減額される場合があり、実際に2013年1月〜2014年7月までで約15%(約400万円)が減額され、2017年にも国家公務員と民間の退職金を比較し、国家公務員の退職金減額が勧告されている。
直近では、長引く新型ウイルス感染症の影響で落ち込んだ民間企業の給与水準に合わせるため、2年連続でボーナスや退職金の引き下げを勧告している。
さらに、今後人口が減少し、経済成長が鈍化してしまうと民間の企業も給与が下がり、それに連動する形で国家公務員の退職金も減少することも考えられる。
民間との格差が是正されても、今後も民間よりも給与待遇が良すぎる場合は、引き続き減額圧力がかかることが予想される。
退職金のこと、誰に相談する?
簡単な質問に回答するだけで、
あなたの条件に合う資産運用アドバイザーを紹介します
\ 簡単60秒!相談料は完全無料 /
退職金を元手に老後に向けた資産形成を始めよう

このように急に給与が増えたり、様々な要因で退職金が減少することが予想される国家公務員こそ老後に向けた準備を早期に行うことが重要だ。
幸いにも、2017年1月からiDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)の加入対象者に公務員も含まれるようになっている。
ゆとりある老後を送るためにも、退職金を始めとする資金を上手く活用して資産形成を進めていこう。
以下で紹介する2つの方法は、投資が初めての方でも比較的実施しやすい資産運用だ。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
これまで国家公務員は対象外でしたが、2017年から公務員もiDeCoに加入できるようになった。
iDeCoとは個人型確定拠出年金の略称で、優遇された税制で投資をしつつ将来の老後資金として活用できる制度だ。
国家公務員の場合は毎月の掛け金上限が12,000円と少額にはなるが、早い段階で取り組むことで長期投資の恩恵を受けることができおすすめだ。
新NISA制度
NISAとは、英国のISA(Individual Savings Account)に倣って創設された「毎年一定金額の範囲内で購入した株式や投資信託などの金融商品から得られる利益が非課税になる」という制度だ。
資産運用では配当課税や譲渡益課税のように利益に対して約20%の税金がかかるが、新NISAであれば、非課税で運用できるため節税効果も高い。
NISA制度は、2024年1月より「一般NISA」および「つみたてNISA」は新制度に変更になり、より使いやすい制度に生まれ変わった。
新NISAでは、年間の非課税投資枠が最大360万円に拡大され、成長投資枠とつみたて投資枠が同時に利用できるようになった。生涯で非課税保有できる総額は1,800万円まで、非課税期間は無期限化された。
つみたて投資枠は、年間120万円まで投資でき、金融庁の基準をクリアした投資信託で、長期・積立・分散投資を実現できる。投資が初めての方でも続けやすい「投資初心者の方向け」と言える。
成長投資枠は年間240万円まで投資でき、個別株式や投資信託を購入できる。つみたて投資、一括投資のどちらでも利用できるので、資産運用に慣れてきたらチャレンジするという使い方も可能だ。
セカンドライフに向けた国家公務員の退職金運用は早めに始めよう
様々な要因で退職金が減少することが予想される国家公務員こそ老後に向けた準備を早期に行うことが重要だ。
ただ、投資には勉強せずに投資を始めてしまうと、大きな損をしてしまう可能性もある。
自分のリスク許容度に応じた投資を始められるように、退職金受け取りが近づいているのであれば、老後の生活に関して考えておくと良いだろう。
とはいえ、自分だけでは不安、時間がない、調べてみても分からないという方もいると思う。
そんな時は、「退職金ナビ」を活用して、資産運用アドバイザーに相談をしてはいかがだろうか。
プロの視点から資産運用の疑問を解決し、納得した上で資産運用を行おう。
退職金や資産運用に関して、少しでも不安やお悩みがある方は、無料相談を申し込んでみてはいかがだろうか。