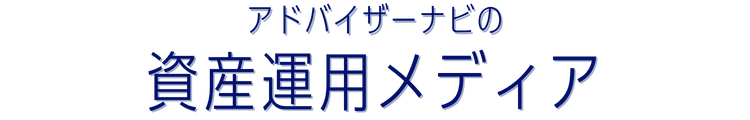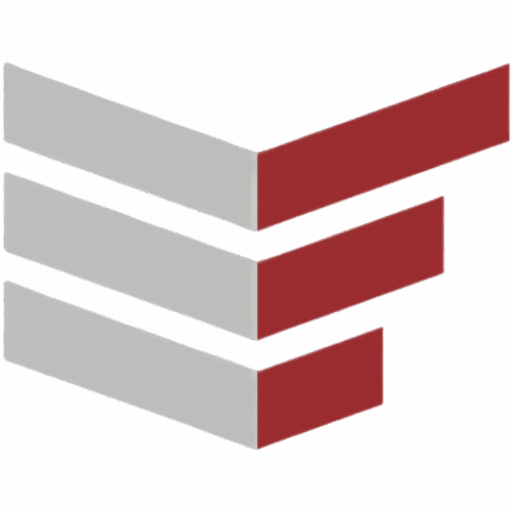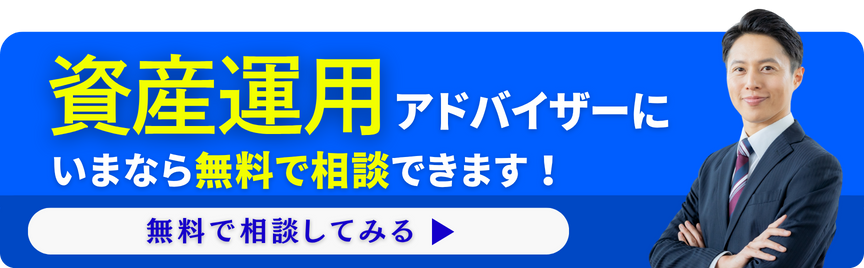- 資産運用をプロに任せたい
- 資産運用をプロに任せる時の注意点が知りたい
- プロに資産運用してもらうメリットが知りたい
新NISAの開始や老後資金への不安などから、資産運用に興味を持つ方が増えた。
しかし資産運用の経験がない方は、どのように始めたらいいかわからないため、プロにお任せしたいと考える人も多いのではないだろうか。
この記事では、資産運用をプロに任せるメリットやデメリット、具体的な運用手法について解説している。
最後には、信頼できるプロに出会う方法も紹介しているので、資産運用を始めたい、プロに任せてみたいと考えている方は参考にしてほしい。
なぜ資産運用をプロに相談するのか
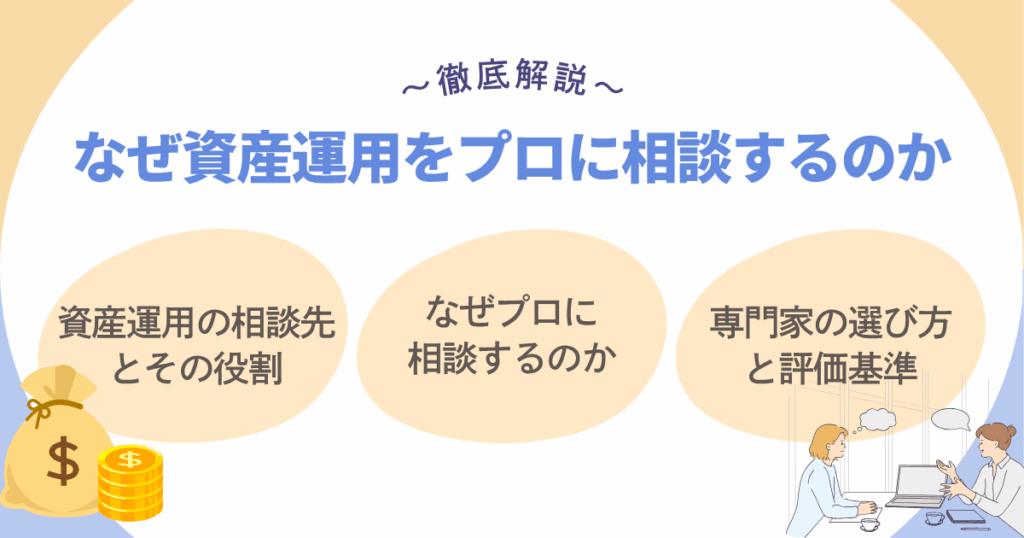
投資運用を専門家に相談する目的は、より良い知識やプランを得るためだ。
ここでは、相談先の種類や相談するメリット、選び方について解説する。
資産運用をプロに任せる方法とは?
運用の相談先には、次のようなものがある。
銀行
店舗数が多く身近な存在であるため、相談しやすい体制が整っている。
扱う商品は、投資信託や債券、保険が中心だ。株式の取り扱いはなく、投資商品の選択の幅は狭い。
証券会社
投資を専門としているため、資産運用の相談を積極的に受け付けている。
大手は支店があり足を運びやすい。一方で、ネット証券は手数料が安く設定されている。
幅広く運用商品を扱うが、ラインナップの偏りや自社商品を推奨している場合もある。
IFA
金融機関と業務提携を結んだ独立系ファイナンシャルアドバイザーを指す。
証券会社との仲介役として、独立した立場から提案やアドバイスを行っている。金融機関で経験を積んだエキスパートが多く、運用の知識をもちながら公正なアドバイスができる。
しかし知名度が低いため、相談するきっかけがない、信頼できるIFAを探すのが難しいという問題がある。
 証券アナリスト 平行秀
証券アナリスト 平行秀IFAは特定の金融機関に属さない中立的な立場で相談に乗ってくれます。
将来設計やライフプランに合わせた柔軟な提案が可能で、真に最適な資産運用プランを一緒に考えることができます。
なぜプロに相談するのか
資産運用を専門家に相談すると、次のメリットがある。
効率的に最適な運用を選べる
投資で成果を上げるためには、まず十分な知識を身につけ、その上で地道に経験を積み重ねていくことが不可欠だ。
しかし、熟練者と同じレベルで資産運用を行えるようになるまでには、長い時間と多くの資金が必要となるのが現実だ。
そこで、プロフェッショナルの力を借りれば、最適な運用方法をより効率的に実現することが可能となる。
情報を精査できる
ネットや書籍を開けば、投資に関するさまざまな情報やテクニックが溢れている。運用について学び始めると、情報が足りないというよりも、むしろ情報が多すぎて混乱してしまうことが少なくない。
その中から自分にとって最適な方法を選び出すのは、時に非常に難しく感じるものだ。
こうしたとき、専門家の助言を得ることで、情報を冷静に整理し、自分に合った選択がしやすくなるだろう。
安心感を得られる
自己流で投資を続けていると、「本当にこの方法で正しいのだろうか」と迷いが生じることも少なくない。
しかし、プロの経験や知見に基づく客観的な分析を得ることで、自分の選択に納得感を持つことができ、お金に対する不安から解放される。
安心感が得られれば、感情に流されて売買してしまうリスクも減り、冷静な判断ができるようになる。こうした環境は、運用を継続するモチベーションにもつながるだろう。
長期的な視点を持てる
個人で資産運用計画を立てる場合、どうしても目先の利益を優先してしまいがちだ。
しかし、運用のプロは人生設計(ライフプラン)と密接に結びつけて資産形成を進めていく。
プロの視点では、単なる一時的な利益の追求ではなく、「人生をより豊かに生きるための資産づくり」に重きを置き、長期的かつ持続的な資産の拡大を目指せるのだ。
資産運用のプロを選ぶときの3つのポイント
資産運用の専門家を選ぶ際、押さえておきたいポイントは次の通りだ。
幅広い商品を扱っているか
商品ラインナップが豊富であれば、自分の投資目的やリスク許容度に合わせた運用プランを立てやすくなり、商品同士の比較検討もしやすくなる。



複数の選択肢から中立的に提案してくれるアドバイザーは、信頼に値します。
顧客の人生設計に寄り添いながら、無理のない最適な運用方針を一緒に描いてくれる心強い存在となるでしょう。
また、提携している金融機関が2社以上あると選択肢が広がり、より自分に合ったサービスを選ぶことができる。
さらに、異なる資産クラス(例:株式、債券、不動産など)を複数取り扱っていれば、分散投資によるリスク低減が図れるため、より幅広い資産運用が可能となる。特に、3種類以上の資産クラスを扱っていると、運用の自由度が高まり、安定した資産形成につながる。
中立的な立場か
金融機関によっては、営業担当者に数値目標やノルマが課されていることもある。その達成を優先するあまり、顧客本位ではなく、担当者が売りたい商品を勧めるケースが依然として見受けられる。
特に、自社グループの商品がラインナップの中心になっている場合、企業側の都合が優先され、顧客にとって最適な投資プランから逸脱するリスクもある。
そのため、提案される商品の構成をよく確認し、自社商品が他社商品に比べて極端に多くなっていないかをチェックすることが重要だ。
商品ラインナップの偏りがないかを見極めることで、企業都合ではなく、本当に自分に合った選択ができるかどうか判断する材料となる。
相談しやすいか
面談方法には、対面・オンライン・店頭・自宅訪問などさまざまな選択肢があり、ご自身が相談しやすいスタイルを選べるかどうかが重要だ。
また、担当者がどのような体制でサポートしてくれるのかも、安心して相談を続ける上で大切なポイントだ。担当者の異動や交代が頻繁に行われていないか、その有無や頻度についても事前に確認しておくとよいだろう。
さらに、担当者が抱える顧客数が多すぎる場合、きめ細やかなフォローが難しくなることもある。
担当者が十分に時間を割ける体制か、柔軟に対応できる人数で運営されているかを把握できると、より安心して相談できるはずだ。
資産運用をプロに任せるメリット
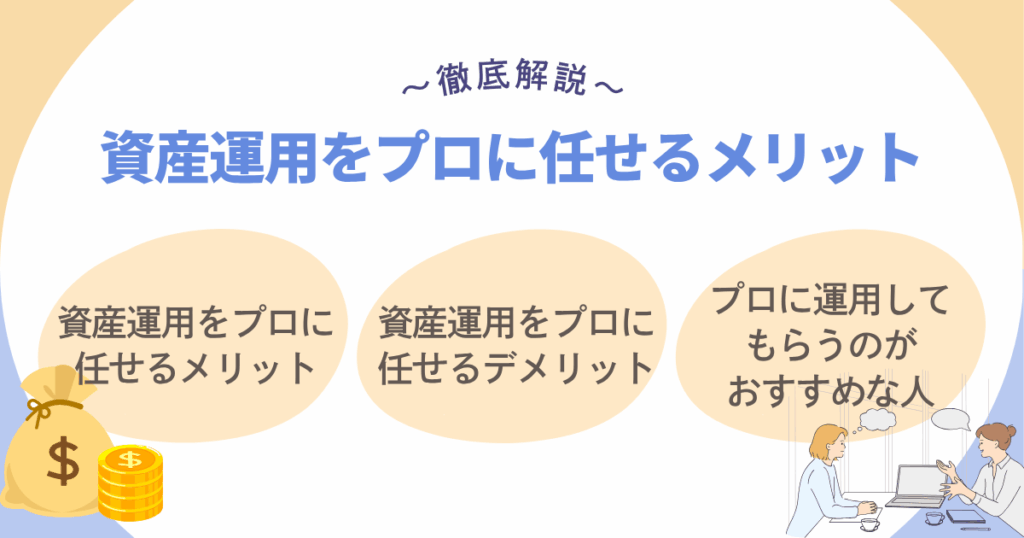
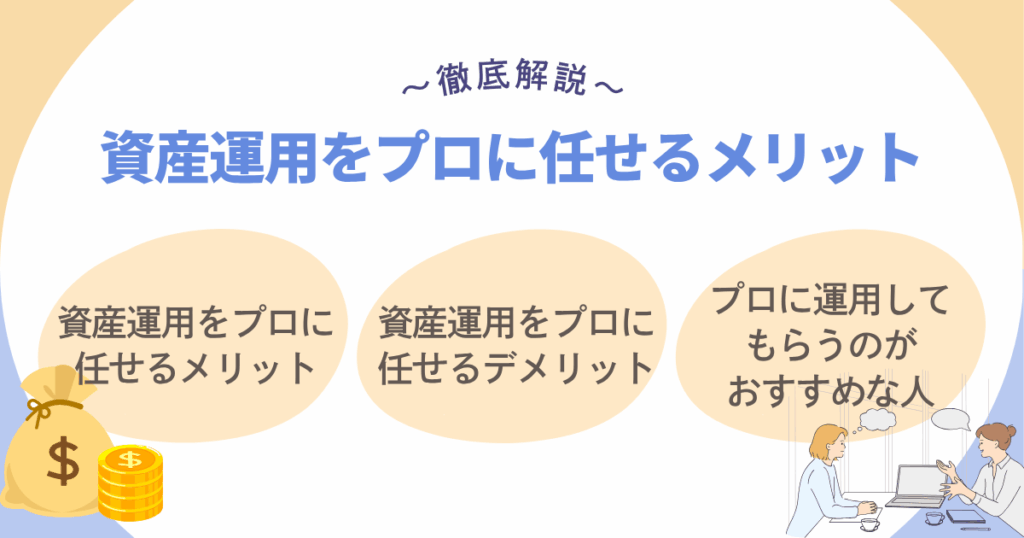
資産運用をプロに任せるメリットとデメリット、プロに運用を任せるのがおすすめな人の3つについて解説する。
- 資産運用をプロに任せるメリット
- 資産運用をプロに任せるデメリット
- プロに運用してもらうのがおすすめな人
資産運用をプロに任せるメリット
資産運用をプロに任せるメリットは以下の3つだ。
- 資産運用の手間や時間を削減できる
- 投資できる商品の幅が広がる
- 手軽にプロのノウハウを活用できる
資産運用の手間や時間を削減できる
本来、資産運用で成果を出すには、世界経済の動向チェックや個別企業の分析など、専門的な情報収集と分析が欠かせない。
しかし、仕事や日々の生活で忙しい方が、これらすべてを自分で行うのは現実的ではないだろう。
そこで、資産運用をプロに任せることで、こうした日々の情報収集や分析にかかる時間を最小限に抑え、本業やプライベートな時間に集中できるようになる。
さらに、資産運用では「ポートフォリオのメンテナンス」が重要だ。一度最適なポートフォリオを組んでも、市場の変動で資産のバランスは崩れるし、ご自身のライフステージの変化によっても最適な構成は変わる。
プロはこうした状況を常に管理し、あなたに代わって定期的なリバランス(資産配分の調整)やポートフォリオの見直しを提案してくれる。複雑で手間のかかるメンテナンス作業を代行してくれるのも、プロに任せる大きなメリットだ。
投資できる商品の幅が広がる
プロに資産運用を任せる大きなメリットの一つが、個人では投資しにくい専門的な投資商品へのアクセスが可能になる点だ。
具体的には、ヘッジファンドや未公開株(プライベートエクイティ)、オフィスビルなどの高級不動産といった、一般には情報が少なく、まとまった資金が必要な資産クラスが挙げられる。
プロを活用することで、こうした専門領域への投資が可能となり、自分だけでは得られない多様な投資チャンスを捉えることはできるようになる。



こうした商品への投資はリスクとリターンのバランスが重要で、専門家の助言を得ながら進めることで判断の精度が高まります。
特に市場環境が不安定な時期には、的確な助言が大きな損失回避につながることがあります。
また、投資先の選択肢が広がることは、「分散投資によるリスク管理」という観点からも非常に重要だ。
株式や債券といった伝統的な資産だけではなく、さまざまな値動きをする専門的な資産をポートフォリオに組み込むことによって、特定の市場や資産に依存するリスクを低減し、より安定したリターンを目指すことが可能になる。
このように、プロを活用することは、投資先の広がりと分散投資の効果という2つの大きなメリットにつながるのだ。
手軽にプロのノウハウを活用できる
資産運用を独学で進めようとすると、膨大な知識を身につける必要がある。さらに、その膨大な情報の中から何が重要かを見極めたり、市場の短期的な変動に惑わされず冷静な判断を保ったりするのは至難の業だ。
そこで、プロに資産運用を任せることで、実際の運用手法や判断基準を間近で観察することができ、彼らの長年の経験に基づいたノウハウを学ぶことが可能となる。
なぜその資産配分なのか、どのような経済指標に注目しているのかなど、具体的な判断基準を直接聞くことで、資産運用のスキルが身につき、自身の投資判断能力を高めることができるのだ。
このように、プロの運用を「見て学び、真似る」ことは、初心者が資産運用の基礎から応用までを身につける近道となるのだ。
資産運用をプロに任せるデメリット
資産運用をプロに任せるデメリットは以下の3つだ。
- コストが高くなりやすい
- 短期運用で成果を出すことは難しい
- 相性の良いプロを見つけるのが難しい
コストが高くなりやすい
資産運用をプロに頼ると、自分で運用するよりもコストが高くなりやすい。
SBI証券や楽天証券では国内株式の取引手数料は無料化されており、保有コストもかからない。
一方で投資信託やファンドラップ、ロボアドバイザーなど資産運用を任せられるサービスは、商品購入時に手数料が生じるケースは珍しくない。
また運用手数料はおよそ0.1%〜3%かかるのが一般的だ。さらに商品によっては、解約時の手数料も発生する。
コストは資産運用のリターンを押し下げる原因となる。
プロに運用を依頼するときは、手数料以上の成果を上げられるのかは十分にチェックする必要がある。
短期運用は難しい
一般的にプロの資産運用は、長期運用が前提となっている。
つまり短期運用でリターンを得たい方は、プロに資産運用を依頼しても望み通りの成果を得られない可能性が高い。
短期運用はギャンブル性が高くなりやすく、プロであっても安定的にリターンを出すことは難しい。
プロに運用を任せる場合は、長期的な視点でリターンが出れば良いという気持ちで依頼しよう。
相性の良いプロを見つけるのが難しい
資産運用のプロといっても、経歴や得意分野ごとにさまざまな専門家がいる。
その中から自分の投資目的やリスク許容度に合ったプロを見つけることは非常に難しい。



信頼できるアドバイザーを見極めるには、資格の有無だけでなく、提案内容の中立性やヒアリング力、継続的なフォロー体制まで確認することが重要です。口コミや実際の相談事例なども判断材料になります。
また資産運用のプロをうたっていても、何の専門知識やスキルも持たない人もいる。
そのような方は無資格であることが多く、素性を十分に調査しないと、詐欺に巻き込まれてしまうリスクがある。
資産運用のプロに依頼する場合、代表者の経歴や実績、素性を必ず確認し、自分と相性が良いのかを必ずチェックしよう。
プロに運用してもらうのがおすすめな人
プロに運用してもらうのがおすすめの人は、日常生活や仕事が忙しい方、または投資初心者だ。
日常生活や仕事が忙しい人
先述したように資産運用の成功のためには、日頃から情報収集や勉強が欠かせない。
また投資手法によっては日々の値動きを確認しなければならず、仕事や家事に追われている人にとって現実的ではない。
プロに運用を依頼すると、上記のような面倒なことはすべて任せられる。
そのため、プロに任せることで日々忙しい方であっても、資産運用に取り組める。
投資初心者
資産運用で成功するためには、多くの知識や経験が必要だ。
しかし、初心者はどちらも持っていないため、利益を出すことが難しい。
そこで、プロの力を借りることにより、初心者でも専門的なノウハウを生かした投資ができる。
また銘柄選びや売買タイミングなどの投資判断も、プロがサポートしてくれるため安心だ。
プロにおまかせ!おすすめの資産運用法を紹介


ここまで、資産運用を任せられるプロとはどんな人たちなのかを解説してきた。
ここでは、プロに運用を任せられるおすすめ商品3つを紹介する。
- 投資信託
- ファンドラップ
- ロボアドバイザー
投資信託
投資信託(ファンド)とは、多くの投資家から集めた資金を一つにまとめ、運用の専門家であるファンドマネージャーが株式や債券などに投資・運用する金融商品だ。
個人では難しい多数の銘柄への分散投資や、専門的な知識が必要な投資判断を専門家が代行してくれるのが最大の特長で、「運用のプロが作ったパッケージ商品」とイメージすると分かりやすい。
中でも、初心者の方に得におすすめなのが、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」だ。
このファンドは、日本を含む全世界の株式およそ3,000銘柄に投資をしている。つまり、このファンドを購入すれば、世界の成長の恩恵を受けることができるのだ。



低コストでグローバルに分散されたインデックスファンドは、初心者が最初に取り組む運用手段として非常に有効です。特に長期投資との相性が良く、定期積立と組み合わせることで安定した資産形成が目指せます。
また、基本的に購入時の手数料は無料で、信託報酬は年率0.05775%と業界最低水準である。
さらに、過去5年のリターンは19.60%※と、驚異的な成績を残している。
どこの国に投資すればいいかわからない、あまり多くの商品を持ちたくないという方におすすめだ。
- 将来の成果を保証するものではありません。
ファンドラップ
ファンドラップとは、投資家一人ひとりの考え方や目的に合わせて、専門家が資産の管理・運用をまとめて代行する「お任せサービス」だ。
金融機関との対話を通じてリスク許容度などを診断した上で、複数の投資信託を組み合わせた最適なポートフォリオを専門家が構築。その後の運用や定期的な資産配分の見直し(リバランス)まで一任できるため、投資に関するほとんどの手間を省けるのが大きな魅力だ。
代表的なサービスの一つが、三井住友信託銀行の「ラップ口座」だ。
日経新聞の調査(2022年3月末時点)によると、運用損益がプラスの顧客の割合が98%と、調査対象の大手金融機関の中で最も高い実績を誇る。
三井住友銀行のラップ口座には2つの種類があり、最低投資金額が異なる。
| 最低投資金額 | |
|---|---|
| ファンドラップ | 500万円以上 |
| ファンドラップ・ プレミアム | 1億円以上 |
それぞれのサービス内では、5つの運用コースが用意されており、自分の目的に合った運用スタイルを選択することができる。
- 保守的
- やや保守的
- 重要
- やや積極的
- 積極的
ただし、このサービスは手数料が高めに設定されており、固定報酬(最大で年率1.760%)と成功報酬(運用成果の16.5%)を支払う必要がある。
利用する際は、高い手数料に見合うだけの価値があるかを慎重に検討することが重要だ。
ロボアドバイザー
ロボアドバイザーは、オンライン上でいくつかの簡単な質問に答えるだけで、AI(人工知能)がその人に合った資産運用プランを提案・実行してくれるサービスだ。
最適な資産の組み合わせ(ポートフォリオ)を自動で構築し、その後のリバランスまで含めて全てお任せできるのが特長だ。
ロボアドバイザーの代表格が、預かり資産・運用者数で国内NO.1の「ウェルスナビ(WealthNavi)」だ。(預かり資産1.3兆円、運用者数40.8万人 ※2024年7月4時点 )



ロボアドバイザーは資産運用の入り口として非常に優れた選択肢です。
自動でリスク許容度に応じた資産配分を行い、定期的なリバランス機能もあるため、投資に不慣れな方でも安心して運用を継続できます。
ウェルスナビは「長期・積立・分散」の考え方を徹底し、リスクを抑えながら中長期的に安定した資産成長を目指している。
運用にかかる面倒な作業はすべて自動化されており、手数料は預かり資産に対して年率1.1%(税込)※と、コスト体系が分かりやすいのも初心者にとって大きな魅力だ。
公式サイトでは多くの利用者の運用実績が公開されており、投資の知識や時間がない方でも、安心して資産運用を始められるサービスと言えるだろう。
※3,000万円を超える部分は年率0.55%
資産運用、誰に相談する?
簡単な質問に回答するだけ!
あなたに合った資産運用アドバイザーを紹介
\ 簡単60秒!相談料はずっと無料 /
プロに資産運用を任せるときの注意点
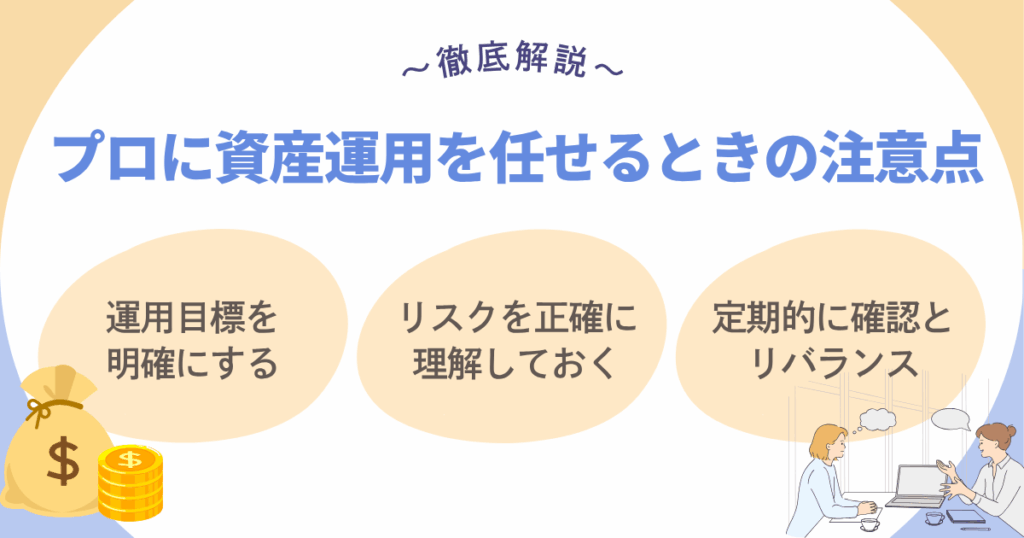
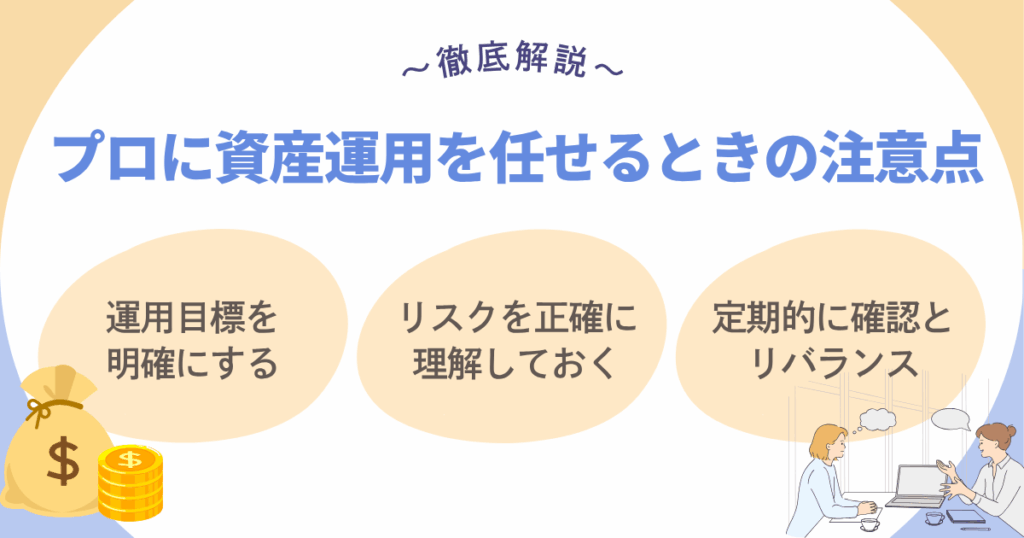
プロに運用を任せるときの注意点について以下3つを解説する。
- 自分の余剰資金額やリスク許容度、運用目標を明確にする
- 各運用手法や金融商品のリスクを正確に理解しておく
- 運用成績を定期的に確認し、必要に応じてリバランスする
自分の余剰資金額やリスク許容度、運用目標を明確にする
まずは自分の余剰資金額を確認しよう。お金は3つに区分できる。
1つ目は生活防衛資金だ。病気やけがなどで働けなくなったときに備えるためのお金で、生活費の3か月から6か月分が目安である。
2つ目は使い道の決まっているお金だ。たとえば5年後に必要になるマイホームの頭金、3年後の結婚式の費用などが該当する。
3つ目が余剰資金だ。余剰資金は上記2つに該当しないお金である。
余剰資金だけで資産運用を行っていれば、仮に含み損をかかえても、生活やライフイベントに支障が出ない。



余剰資金での運用は、長期的な視点で資産を育てるうえで基本中の基本です。焦らず冷静に判断できる状況を整えることで、途中で投資をやめずに継続できる可能性が高まります。
次に自分のリスク許容度を把握しよう。リスク許容度とは、投資家ごとに耐えられる損失額を示す指標だ。
リスク許容度が高いと多額の損失にも動じない人といえる。一方でリスク許容度の低い人は、少額の損失にも耐えられない。
リスク許容度は投資手法を選ぶうえで、非常に重要な指標だ。
心地よく資産運用を継続するためには、リスク許容度に合った投資手法を選択しよう。
適切な投資手法を選ぶためには、運用目標を明確にすることも重要だ。
運用目標とは「お金が必要な時期、金額、用途」を明確にすることである。
たとえば「30年後までに3,000万円を老後資金として準備したい」といったものが目標だ。
運用目標を明確にすることで、必要な投資金額、リターンがわかる。
それらを把握できると、投資すべき商品を絞れるため、投資手法の選択が楽になる。
各運用手法や金融商品のリスクを正確に理解しておく
各運用手法や金融商品のリスクはそれぞれ異なる。そもそも資産運用には下記のリスクがある。
| リスクの種類 | 概要 |
|---|---|
| 信用リスク | 投資先の企業や債券の発行体が破産し、投資資金を回収できなくなること |
| 流動性リスク | 現金化できなくなること |
| 金利変動リスク | 金利が変動し、金融商品の価値に影響が出ること |
| 価格変動リスク | 価格が変動し、元本割れするリスクのこと |
| 為替変動リスク | 為替が変動し、円建ての資産価値に影響が出ること |
株式は価格変動リスクが大きい。一方で、流動性リスクは低く、現金化できなくなるというケースはほとんど考えられない。
不動産は株式よりも価格変動リスクは小さい。一方で価格が高く売却相手を見つけにくいため、流動性リスクは高い。つまり現金が欲しいときにすぐに売却できないリスクを伴う。
また同じ株式であっても国内株式に為替変動リスクはないが、海外株式にはある。
このように選択する運用手法や金融商品ごとにリスクは異なる。
そのため投資先を検討する場合は、どのようなリスクを抱えているのかを確実にチェックし、想定外のトラブルが起きないようにしよう。



リスクを正しく理解しないまま投資を始めると、価格下落や為替変動時に不安を感じて継続できなくなることがあります。
あなたが許容できるリスクを把握し、それに合った商品を選ぶことが投資成功の鍵です。
運用成績を定期的に確認し、必要に応じてリバランスする
基本的に、資産運用を開始する前にポートフォリオを決める。
ポートフォリオとは資産配分のことで「株式50%+債券50%」のように表現する。
運用を始めた当初は、ポートフォリオと資産の保有比率が同じであったとしても、運用成績によってはそこにズレが生じる。
たとえば上記のポートフォリオで運用しており、株式のリターンが好調であれば「株式70%+債券30%」のように株式の比率が高まり、債券の比率が低下する。
このズレをポートフォリオ通りに戻すことをリバランスという。
リバランスは次の2つの方法によって行う。
- 保有比率が高まった資産を売却する
- 保有比率が低下した資産を購入する
リバランスを行わないと過大なリスクを取ってしまったり、想定通りのリターンが得られなくなったりする。
そのような事態を避けるためにも、年に1・2回はリバランスを行おう。
資産運用の相談は誰にすべき?
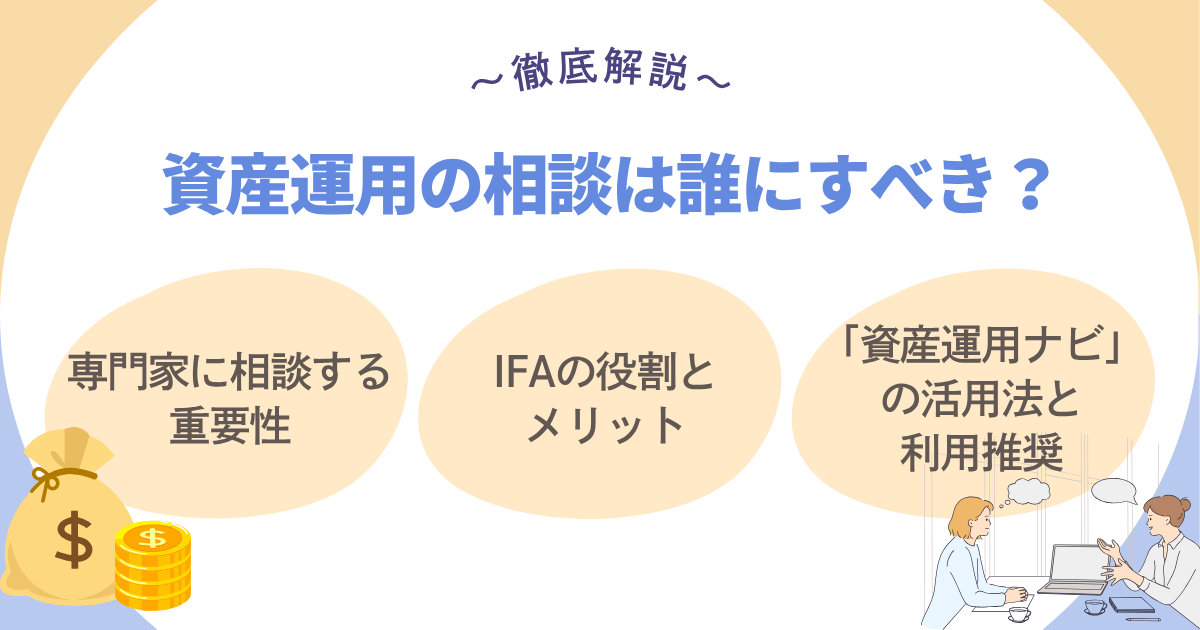
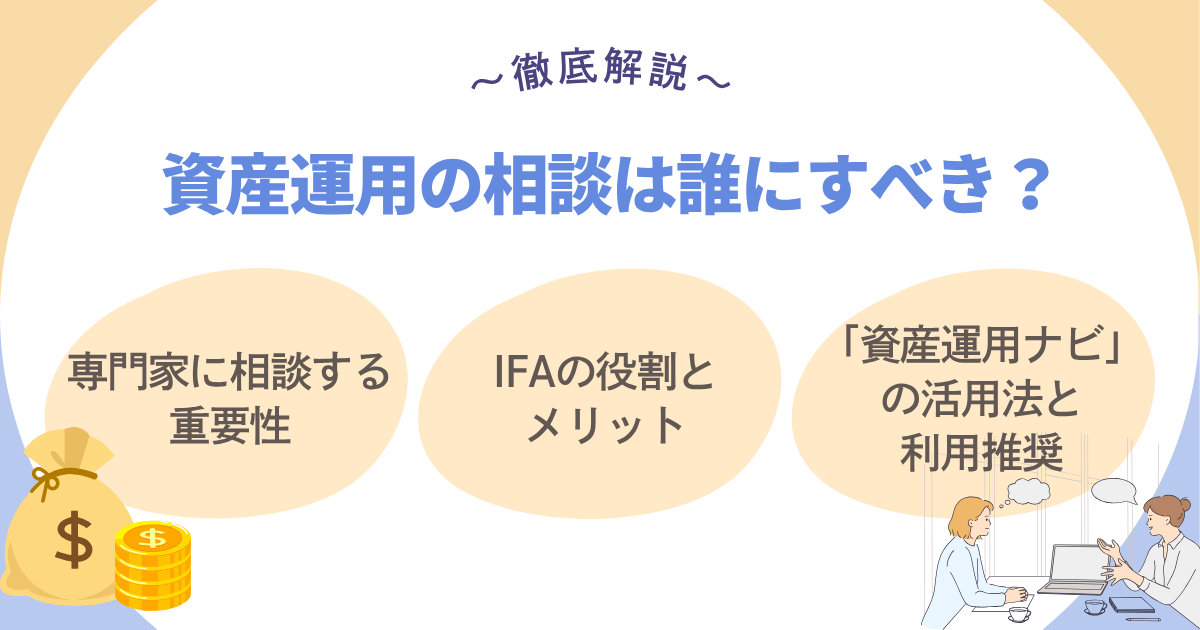
ここまではプロに資産運用を任せる手法やメリット・デメリットについて紹介してきた。
ただしプロに任せられるといっても、希望や不安が出てくることもあるだろう。
そのようなときは専門家に相談する選択肢も考えられる。
ここでは資産運用の相談は誰にすべきかについて以下の3つを解説する。
- 資産運用を専門家に相談することの重要性
- IFAの役割とメリット
- IFA検索サービス「資産運用ナビ」の活用法と利用推奨
資産運用を専門家に相談することの重要性
資産運用を成功させるためには、多くのプロセスを経なければならない。
リスク許容度や余剰資金額の把握、運用目標の設定などを投資家ごとに行う必要がある。
これらを正しく行う際に専門家の力が必要になる。
専門家は豊富な知識や相談実績をもとにして、投資家ごとに最適な運用戦略やポートフォリオなどをアドバイスしてくれる。
また信頼できる専門家がいれば、相場が不安定なときにもすぐにアドバイスを求められるため、資産運用を継続しやすくなる。
長期的に資産運用を継続したい方は、専門家の力を借りるべきだ。
IFAの役割とメリット
資産運用の相談先としておすすめしているのは、証券会社や銀行をはじめとした金融機関から独立したIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)だ。
金融機関に所属していると、ノルマを優先するケースがあり、顧客に適さない提案が行われることもある。
しかし、IFAは特定の金融機関に所属していないため、組織のしがらみはなく、中立的な立場からアドバイスを提供してくれる。
また定期的な転勤がないため、長期にわたって関係性を構築しやすい。資産運用は長期で行うのが前提だ。
信頼できるアドバイザーがいれば、ライフイベントの変化があっても、すぐに対応できる。
どのような専門家にアドバイスを求めたら良いかわからない方には、IFAをおすすめする。
IFA検索サービス「資産運用ナビ」の活用法と利用推奨
「IFAがおすすめ」といっても、探し方がわからないという方もいるだろう。
おすすめの方法は、IFA検索サービス「資産運用ナビ」の活用だ。
年収や金融資産、運用目的など簡単な情報を入力するだけで、あなたと相性の良いIFAを紹介してくれる。
紹介されたIFAの経歴や実績、得意分野は事前にチェックできるため、ミスマッチが起こりにくい。
また現在「資産運用ナビ」では、無料相談を実施している。
IFAに話を聞いてみたい方は、下記のリンクから「資産運用ナビ」に登録してほしい。
資産運用をプロに任せたいならIFAに相談しよう
この記事では、プロに資産運用を任せるメリット・デメリットやおすすめの運用方法、任せる際の注意点について解説した。
記事中では、具体的なおすすめ商品も紹介しているが、あくまでも一例だ。
最適解は投資家ごとに異なるため、商品を通じてプロに運用を任せたい方は投資を始める前に、専門家からアドバイスを受けよう。
特にIFAは中立的な立場から長期にわたって、有益なアドバイスを提供してくれる。
自分と相性の良いIFAを見つけたい方は、IFA検索サービス「資産運用ナビ」を活用するのがおすすめだ。



IFAは特定の金融機関に縛られず幅広い商品から提案が可能で、顧客一人ひとりの目標やライフプランに沿った運用設計がしやすいのが特長です。継続的な伴走が期待できる点でも初心者には特に心強い存在です。