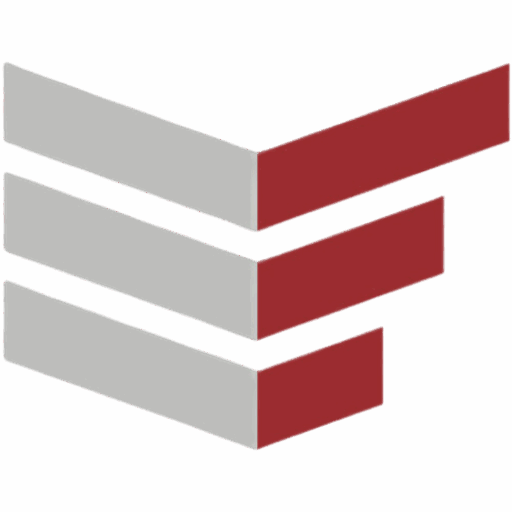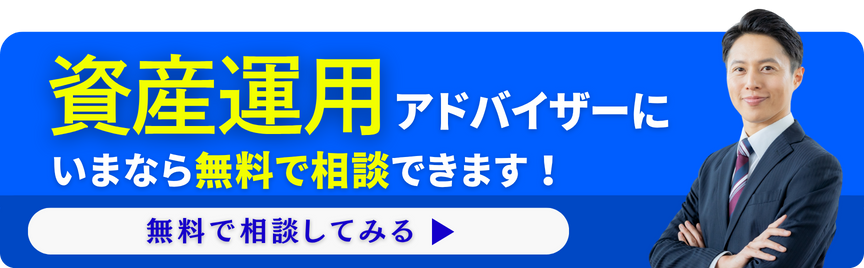- 20代におすすめの投資法が知りたい
- 20代からの資産運用を成功させたい
- 初心者でも取り組める運用法や投資のコツが知りたい
ネット証券の台頭によって若年層にも投資が広がりを見せており、20代から資産運用を始めるケースが増えてきた。
20代の方のなかには「おすすめの資産運用を知りたい」「資産運用を成功させるポイントを知りたい」と考えている方も多いだろう。
本記事では、20代におすすめの資産運用の方法や投資のコツ、おすすめの運用ポートフォリオを紹介していく。
相談先を探せるサービス「資産運用ナビ」の特徴も紹介するのでぜひ本記事を参考にしてほしい。

証券アナリスト/代表取締役
アドバイザーナビ株式会社
監修者: 平 行秀
新卒で野村證券に入社し、富裕層1000人以上の資産運用コンサルを担当。2019年に弊社創業し、投資家とアドバイザーをつなぐマッチングプラットフォームを運営。公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)。
20代には投資信託がおすすめ

20代で資産運用を始めるのであれば、投資信託の活用がおすすめだ。
投資信託とは、投資家から集めた資金をもとに運用の専門家が株式・債券などで投資を行い、運用成果を投資家に分配する仕組みの金融商品である。
ここでは、20代に投資信託を推奨する理由やおすすめの銘柄、投資信託による運用のコツを紹介していく。
20代に投資信託がおすすめの理由
20代の資産運用に投資信託がおすすめである理由は以下の2点だ。
- 少額で分散投資ができる
- 投資の手間や時間がかからない
投資信託は、投資家から集めた資金をもとに複数の株式・債券等で運用されている。
そのため、投資信託を購入することで間接的にさまざまな投資先に資金を投じることになる。
投資信託は100円から買えるケースもあり、少額から投資しやすいことが特徴の金融商品だ。
少ない自己資金でもさまざまな投資先に分散投資できる点が投資信託のメリットである。
また、投資信託は資金を預けて運用を任せる仕組みであるため、手間や時間をかけずに投資を行える。
自分で投資先を選定したり、売買するタイミングを見極めたりする必要がないため、投資経験が少ない20代でも安心して投資を始められるだろう。
 証券アナリスト 平行秀
証券アナリスト 平行秀「投資は難しそう・・・」と感じる方こそ、プロに運用を任せられる投資信託を検討すべきです。
20代のうちから少額から積立投資を始めておけば、複利の力で将来の資産は大きく育ちます。
長期的な視点で、焦らずコツコツと積み立てることが成功の鍵です。
少額から投資を始めやすく、運用に手間や時間をかけずに済む点が投資信託の大きなメリットだ。
「投資にまとまった資金を回す余裕がない」「仕事が忙しくて投資に時間や労力を費やせない」という20代の方は、投資信託を活用して資産運用を始めてみよう。
おすすめの銘柄
20代が投資信託で運用したいのであれば、以下の3つの銘柄がおすすめだ。
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)
それぞれの銘柄の特徴を紹介していく。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は、日本を含む先進国および新興国の株式市場に連動する投資成果を目指す投資信託である。
全世界の株式に広く分散投資を行うことが特徴の商品だ。
本ファンドは運用期間中のコストが極めて低く、信託報酬は年率0.05775%となっている。
長期的に運用してもコストを低く抑えられるため、運用期間が長くなりやすい20代に適した商品だ。
投資対象も比較的安定した成長が見込まれる先進国だけでなく、大きな成長性を秘めた新興国も含まれている。
中長期的な新興国の経済成長の恩恵を得られる点も本ファンドの魅力である。
「コストを抑えて運用したい」「新興国の経済成長に期待している」という方は、本ファンドへの投資を検討してみよう。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は、米国の株価指数「S&P500(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指す投資信託である。
S&P500は、米国を代表する大企業で構成されている指数であるため、米国の有名企業に分散投資できることが特徴の商品だ。
本ファンドの信託報酬は年率0.09372%となっており、ランニングコストを抑えて運用できる。
長期的に運用を継続してもコストの負担は小さく、高いコストパフォーマンスを期待できる商品だ。
また、世界経済をリードする米国のなかでも代表的な企業に投資できるため、中長期でのリターンも見込める。
成長性が高い米国企業に分散投資を行える点は本ファンドの強みである。
「コストを抑えたい」「米国企業に投資をしたい」という方は、本ファンドへの投資がおすすめだ。
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)は、テクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資を行う投資信託である。
1999年に設定されてから25年以上にわたって運用されており、信頼できる実績を有する商品だ。
本ファンドの信託報酬は年率2.09%となっており、ここまで紹介した商品に比べてコストが高い。
ファンドマネージャーと呼ばれる専門家が銘柄を分析・選定するため手数料が高いものの、その分だけ高いリターンも期待できる。
銘柄選定は、テクノロジーの活用によってコスト構造や収益性、競争優位性の改善や維持が期待できる企業というポイントに注目している。
今後も継続的な収益拡大が期待される企業に投資を行えるため、中長期で大きなリターンを見込めるだろう。
「積極的にリターンを追求したい」「米国のテクノロジー企業に投資をしたい」という方は、本ファンドへの投資を検討してみよう。
投資信託を運用するコツ
投資信託で運用を行う場合、以下の2つのポイントを押さえておくと良い。
- 時間を味方につける
- リスク許容度に合った商品を選ぶ
まず、時間を味方につけて運用を行うことが大切だ。投資で運用期間を長く設定すると、利益が新たな利益を生み出す「複利効果」の恩恵を受けられる。
複利効果とは、投資で得られる利益を再投資して元本に加えることで、雪だるま式に資産が増えていく仕組みのことだ。
複利効果は運用期間が長くなるほど威力を発揮していく。20代という若さのメリットを最大限に活かし、効率的に資産を運用していこう。



複利効果を最大限活かすには、「毎月一定額をコツコツ積み立てる」積立投資が有効です。
相場が高いときは少なく、安いときは多く買える「ドルコスト平均法」により、価格変動リスクを抑えながら長期で資産形成ができます。
また、自分のリスク許容度を踏まえて商品を選ぶことも重要である。リスク許容度とは、投資のリターンがマイナスに振れたときに「どの程度のマイナスまで許容できるか」という度合いのことを指す。
20代は多少損失を抱えても取り返す時間が十分にあるため、年代的にはリスク許容度が高い。
しかし同じ20代でも資産状況や性格は異なっており、堅実に運用したい人もいれば、リスクを負ってでも資産を増やしたい人もいる。
自分のリスク許容度に合った商品を見極めることが大切だ。
リスク許容度に合った投資信託を選び、時間を味方につけた長期運用で資産を増やしていこう。
20代が投資信託以外で運用するなら


20代には投資信託がおすすめであると解説したが、ほかの運用方法を視野に入れておくことも重要だ。
自分の投資目的に合わせ、適切な運用方法を選択していこう。
ここでは、投資ニーズ別のおすすめの運用法について紹介していく。
さらなる資産成長を目指すなら株式投資
より大きく資産を成長させたいのであれば、株式投資がおすすめだ。
株式投資とは、企業が資金調達のために発行する株式を取引して利益を狙う投資手法である。
通常、株式は証券取引所で売買し、株価の値上がり益や企業から支払われる配当金を狙うことが一般的だ。
なかには株式を保有する株主に対して、自社商品やサービス特典を贈呈する「株主優待」を設けている企業もある。
株主優待を目的に株式を購入する投資家も少なくない。
株式は比較的値動きが大きい傾向にあるため、上手くいけば短期的に大きなリターンを得られることが特徴だ。
一方で失敗すると短期間で大きく資産を減らしてしまう危険性もあり、ハイリスク・ハイリターンな投資先と言える。
20代の場合、運用期間が長く取れることから短期的な価格変動の影響を抑えやすい。
ある程度のリスクを許容できるのであれば、中長期的に株式を保有して大きなリターンを狙うという戦略を検討してみても良いだろう。
安定運用を目指すなら債券投資
安定的な運用を心掛けたいのであれば、債券投資がおすすめだ。
債券投資とは、企業や国、地方公共団体が資金調達のために発行する債券を取引して利益を狙う投資手法である。
投資家は債券の購入によって発行体に資金を貸し付けたことになり、あらかじめ約束した利率で定期的に利子を受け取れる。
満期を迎えると元本も返済されるため、比較的安全性が高いことが債券の特徴だ。
また、債券は市場で売買することもでき、購入時よりも高い価格で売却して利益を得ることもできる。
反対に市場で額面金額より安く購入し、満期まで保有して額面金額を受け取って利益を得るという方法もある。
比較的安全性が高い債券だが、金利変動に伴って価格が変動するリスクや発行体の債務不履行によって利子・元本が償還されないリスクには注意が必要だ。
それでも株式に比べるとリスクは小さい傾向にあるため、安全性を重視したいのであれば債券投資を検討してみると良いだろう。
定期収入を狙うなら不動産投資
投資で定期的な収入源を確保したいのであれば、不動産投資がおすすめだ。
不動産投資とは、土地や建物などの不動産物件を購入し、第三者に貸し出して賃料収入を得る投資手法である。
20代で高額な不動産を自己資金のみで購入することは難しいが、金融機関から融資を受けることで数百万円〜数千万円の物件も購入できる。
賃料収入から融資の返済を行うことで、少額の自己資金からでも大規模な運用を始めることが可能だ。そして入居者から定期的な賃料収入を得られる点は大きなメリットである。
ローンを組むことに抵抗がある場合、REIT(不動産投資信託)への投資が選択肢に入る。
REITとは、投資家から集めた資金をもとに不動産投資のプロが運用を行い、利益を投資家に分配する仕組みの金融商品だ。
REITは数万円程度から購入でき、定期的に分配金が支払われるため定期収入も確保できる。
融資を活用して大規模な運用をしたい人は現物の不動産投資、ローンを利用せずに定期収入を得たい人はREITで運用を行うと良いだろう。
老後資金を準備するならiDeCo
老後の資金を早いうちから準備したいのであれば、iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用がおすすめだ。
iDeCoとは、自分で掛金の拠出・運用を行って老後の年金を準備する私的年金制度である。
少子高齢化により、国民年金や厚生年金などの公的年金制度は維持が難しくなっており、保険料の値上がりや年金額の減少などが問題視されている。
支払った保険料に対して受け取れる年金額は少なく、老後資金は公的年金だけでは不足するという意見が多い。



老後に必要とされる生活費のうち、公的年金だけでは不足する「年金ギャップ」をどう埋めるかが重要な課題です。
iDeCoはこのギャップを埋めるための有効な選択肢のひとつです。
iDeCoは公的年金に上乗せする形で老後資金を準備する制度だ。
「掛金が全額所得控除」「運用益が非課税で再投資」「一時金・年金での受け取り時に控除適用」といった税制面でのメリットもあり、税負担を軽減しながら老後資金を準備できる。
また、拠出した掛金の運用方法も自分で選択でき、元本が保証された定期預金型やリスクが伴う投資信託型などの商品が設けられている。
自分のリスク許容度や老後までの運用目標に応じて商品を選べる点もiDeCoの魅力だ。
「20代からコツコツ老後資金を準備したい」という方は、iDeCoを活用して税制優遇を受けながら老後資金を積み立てていこう。
20代における資産運用の失敗例とそこから得るべき学び
資産運用の経験が浅い20代の方の失敗例としては、以下の2つが挙げられる。
・情報収集を十分に行わず、他人にすすめられるがままに投資をする
・一つの金融商品に偏った投資をする
まず、十分に情報収集せずに他人にすすめられるがままに投資を始めると、失敗してしまうケースが少なくない。なぜなら、すすめられた金融商品が本当に投資するに値するものであるかを判断できないからだ。



金融商品は人によって「適切さ」が異なるため、自身のライフプランやリスク許容度を考慮したうえでの判断が不可欠です。
万人に最適な商品はないので、自分の判断軸を持つことが大切です。
また、一つの金融商品に偏った投資をしてしまうのも失敗例として挙げられる。仮にその金融商品の価値が大きく下がってしまうと、自身の資産価値も大きくマイナスとなってしまう。
これらの失敗をしないためにも、資産運用で気をつけるべき点は以下の2つだ。
- 自身で調べた上で投資の判断をする
- 分散投資をする
資産運用に関する知識や経験が豊富な方からのすすめであれば、自身で調べる必要はないと考えてしまうかもしれない。しかし、自身でしっかりと調べた上で投資するか否かを判断することが重要だ。
加えて、投資は「分散投資が基本」である点は覚えておいてほしい。分散投資とは、一つの金融商品のみではなく、特徴の異なる複数の金融商品に投資することをいう。
具体的には、1社の株だけを買うのではなく複数社の株を買ったり、株式投資だけでなく債券や投資信託、REITなどさまざまな運用商品に投資したりすることだ。これにより、どれか一つの価値が下がってしまったとしても、資産全体のマイナス幅を抑えることが可能となる。



分散投資はリスク軽減の基本原則です。運用は資産の「バランス」を意識しましょう。
収益性・安全性・流動性のバランスをとることで、長期的な資産形成に耐えうるポートフォリオを作ることが可能になります。
20代が知っておくべき投資のコツ


20代で資産運用を始めるのであれば、以下の3つのポイントを押さえておくべきである。
- 長期的な視点に立つ
- アクティブ運用とパッシブ運用を併用する
- 積立投資でリスクをコントロールする
それぞれのポイントを押さえ、効果的に資産運用を実践していこう。
長期的な視点に立つ
まず、資産運用を行う際には長期的な視点に立って戦略を構築することが大切だ。
20代は長い人生で見るとまだまだ序盤であるため、将来の見通しをしっかりと立てて長期的に運用を継続する意識を持っておこう。
長期的に運用を行うメリットは以下の3点だ。
- 複利効果を活かせる
- リスクを軽減できる
- 投資計画を修正しやすい
先ほども解説した通り、運用期間が長くなると利益が新たな利益を生み出す「複利効果」の恩恵を受けられる。
雪だるま式に資産の増加速度が上がっていき、効率的に資産を増やしていける点が長期運用のメリットだ。
また、株式や投資信託などの金融商品は日々価格が変動しており、短期的には暴落などで大きな損失を抱える危険性がある。
しかし運用期間が長くなるほど価格変動のブレが収束していき、安定したリターンを得やすくなっていく。
短期的な価格変動のリスクを軽減するためにも、長期目線で運用を継続することが大切だ。
そして、長期目線で運用計画を立てておくと、もし途中で計画に狂いが生じてもカバーしやすい。
投資は予測不可能なことが多く、当初に立てた投資計画の通りに運用できることは少ない。
あとから投資計画を修正できるように、余裕を持って投資計画を立てておくと良いだろう。
上記のメリットを活かすためにも、長期的な視点に立って資産運用を始めよう。
アクティブ運用とパッシブ運用を併用する
アクティブ運用とパッシブ運用を併用するという戦略もおすすめだ。
いわゆる「コア・サテライト戦略」と呼ばれる運用方法であり、安定したリターンを確保しながら積極的にリスクを取りに行く戦略である。
パッシブ運用は日経平均株価やS&P500などの市場指数との連動を目指す運用手法であり、運用戦略の「コア部分」となる。
市場の平均リターンを確保できるため、運用戦略の基盤となる部分だ。
アクティブ運用は市場指数を上回るリターンを目指す運用手法であり、運用戦略の「サテライト部分」となる。
積極的にリスクを取り、市場の平均リターン以上のパフォーマンスを目指す部分だ。
コア部分のパッシブ運用で安定したリターンを確保しているため、サテライト部分のアクティブ運用では大きなリターンを狙いに行ける。
特徴が異なる運用手法を組み合わせているため分散効果も高く、ある程度リスクを抑えられることも利点だ。
最初は安定したリターンを期待できるパッシブ運用のみでも良いが、慣れてきたらアクティブ運用を組み合わせた投資戦略も検討してみると良いだろう。



投資経験の浅い方はまずパッシブ運用で投資に慣れ、生活資金に支障が出ないよう管理することが大切です。
その上で、余裕資金を使ったアクティブ運用を段階的に導入するのが理想的です。
積立投資でリスクをコントロールする
資産運用におけるリスクを軽減する方法として、一定の頻度で一定額の投資を行う「積立投資」という運用手法が挙げられる。
積立投資でリスクをコントロールしつつ、安定的なリターンを狙いに行くことが大切だ。
金融商品を毎月・毎週のような一定のタイミングで一定額ずつ買い付けることで、商品を買い付ける時期を分散できる。
価格変動によるリスクを軽減でき、安定した利益を目指せることが特徴だ。
また、積立投資では、価格が安いときには購入数量が多くなり、価格が高いときには相対的に購入数量が少なくなる。
購入単価が平準化され、価格変動のリスクを抑えられる点がメリットだ。
期間が長くなるほどリスク軽減効果は高いため、長期投資との相性も良い。
20代から資産運用を始めるのであれば、長期的な積立投資でじっくり資産を増やしていこう。
20代の運用ポートフォリオとは?


資産運用を始める際、自分に合った運用ポートフォリオを構築することが重要だ。
資産運用におけるポートフォリオは「どの投資先にどういった比率で投資を行うか」という資産配分のことを指す。
ここでは、ポートフォリオを構築する重要性や組み立て方を紹介していく。
20代におすすめの運用ポートフォリオも紹介するので、ぜひ参考にして自分に合ったポートフォリオを作成しよう。
ポートフォリオを構築する重要性
ポートフォリオを構築するメリットとして以下の2点が挙げられる。
- 自分に合ったリスク水準に調整できる
- リバランス(資産の再配分)がしやすい
ポートフォリオを構築することで、自分に合ったリスク水準に調整しやすくなる。
リスク許容度や運用目標に合わせた資産配分で投資を始められ、効率的に資産運用を行える点がメリットだ。
例えば「積極的にリターンを狙いたいから株式を多めにする」「リスクを抑えたいから債券中心のポートフォリオを組む」といった形でリスク水準を調整できる。
自分のリスク許容度や運用目的に最適化された資産配分で運用を始めるためにも、ポートフォリオを構築することが大切だ。



20代は時間的な余裕があるため、リスクをある程度取って資産を成長させる選択肢も有効です。
ご自身の収入や生活防衛資金の確保状況も踏まえて、どの程度のリスクを取るかを慎重に検討することをおすすめします。
また、資産運用はスタートしたら終わりではなく、定期的に見直しを行う必要がある。
値上がりしている資産を一部売却して利益を確定させたり、値下がりしている資産を安く買い足したりといった形で見直しを行うことが重要となる。
あらかじめポートフォリオを組んでおけば、見直しの際にはもとの配分比率に戻すだけで良い。
リバランス(資産の再配分)がしやすくなる点も、ポートフォリオを構築するメリットだ。
ポートフォリオの組み立て方
ポートフォリオを組む場合、以下のステップで資産配分を決定していこう。
- 予定しているライフイベントを羅列する
- ライフイベントに必要な金額を算出する
- 投資額・積立額を踏まえて目標利回りを決める
- 目標利回りに合わせて資産の配分比率を決める
まずは、今後のライフイベントを明確にするところから始める。
20代の時点では先の見通しが立てにくいかもしれないが、「5年後にマイホームを購入する」「15年後に子どもが大学に進学する」などの大まかなライフプランを作成しよう。
次に、ライフイベントに必要な金額を算出する。自身の投資額・積立額から逆算し、どの程度の目標利回りであれば必要な金額を達成できるのかを計算しよう。



ライフプランの明確化は、無理のない運用計画を立てるうえで非常に重要です。
保険や住宅ローンなどの固定費も含めたキャッシュフロー表を作成することで、投資可能額や目標の現実性を見極めることを推奨しています。
最後に目標利回りに合わせて資産の配分比率を決めていく。
目標利回りが3%程度であれば債券などの低リスク資産を中心に構成し、目標利回りが5%以上であれば株式などの比率を増やしていくと良い。
自分のライフイベントや投資額をもとにポートフォリオを構築しよう。
20代におすすめの運用ポートフォリオ
20代の方におすすめの運用ポートフォリオを3つ紹介していく。自分のリスク許容度や投資目的に合ったポートフォリオを参考に、最適な資産配分を検討しよう。
リターンを追求するポートフォリオ
積極的にリターンを追求したいのであれば、以下のようなポートフォリオがおすすめだ。
- 投資信託:60%
- 株式:40%
資産の半分以上を投資信託で運用しつつ、40%ほどを株式に投資する資産配分である。
投資信託も株式で運用される商品を選び、積極的にリターンを追求していくと良いだろう。
比較的安定したリターンを狙える投資信託が中心となっているため、株式の運用はある程度リスクを取ってリターンを狙いに行って良い。
今後の成長性が期待できる中小型の銘柄に投資をしたり、米国の成長企業に投資をしたりなど、高いリターンを目指していこう。
ただし特定の株式に集中投資をするのはリスクが高過ぎるため、さまざまな銘柄に分散させることが重要だ。
また、年齢を重ねると上記のポートフォリオはリスク許容度に合わなくなる可能性があるため、次第に株式の割合を減らして投資信託や債券に切り替えていく必要があるだろう。
堅実に運用するポートフォリオ
堅実に運用していきたいのであれば、以下のようなポートフォリオがおすすめだ。
- 投資信託:50%
- 債券:30%
- 株式:20%
資産の約半分を投資信託で運用しつつ、残り半分を債券と株式に投資を行う資産配分である。
投資信託については、とにかくリスクを抑えたいのであれば債券で運用される商品、多少リスクを取る余裕がある場合は株式で運用される商品に投資を行うと良い。
債券は比較的値動きが小さく、債務不履行にならない限りは満期まで保有することで元本が返済される。
安定したリターンを期待できるため、およそ30%の割合で保有しておくと良いだろう。
また、債券と株式は異なる値動きの特徴があり、負の相関関係にあると言われている。
どちらか一方の価格が下落している局面ではもう一方の価格が上昇する傾向にあり、片方の損失をもう一方がカバーできる可能性が高い組み合わせだ。
あえて少しリスクが大きい株式を組み込むことでポートフォリオ全体のリスクを抑えている。
なるべくリスクを回避したい人は、上記のポートフォリオを活用して堅実に運用していこう。
定期収入を獲得するポートフォリオ
定期的な収入源を確保したいのであれば、以下のようなポートフォリオがおすすめだ。
- REIT:40%
- 債券:30%
- 株式:30%
REIT・債券・株式にバランス良く投資を行う資産配分である。REITの分配金や債券の利子、株式の配当金を定期的に受け取れることが特徴のポートフォリオだ。



収入源がまだ安定しない20代にとって、定期的なインカムゲインを得られるポートフォリオは心理的な安心感にもつながります。
ただし、REITや高配当株に偏りすぎると市場変動の影響を受けやすくなるため、リスク分散の視点は忘れないようにしましょう。
REITは、利益の90%以上を分配することで法人税が免除される仕組みとなっているため、高い利回りで分配金が支払われる。
定期収入を確保したい投資家に最適な投資先だ。
債券と株式についても利回りが高い銘柄を中心に選定すると良い。
極端に利回りが高い銘柄はリスクが大きいが、3%程度の利回りであれば比較的リスクを抑えて運用することも可能となる。
ポートフォリオ全体で3〜4%程度の目標利回りを設定し、長期にわたって安定した定期収入を確保しながら運用していこう。
20代の資産運用を成功させるなら「資産運用ナビ」で専門家に相談しよう
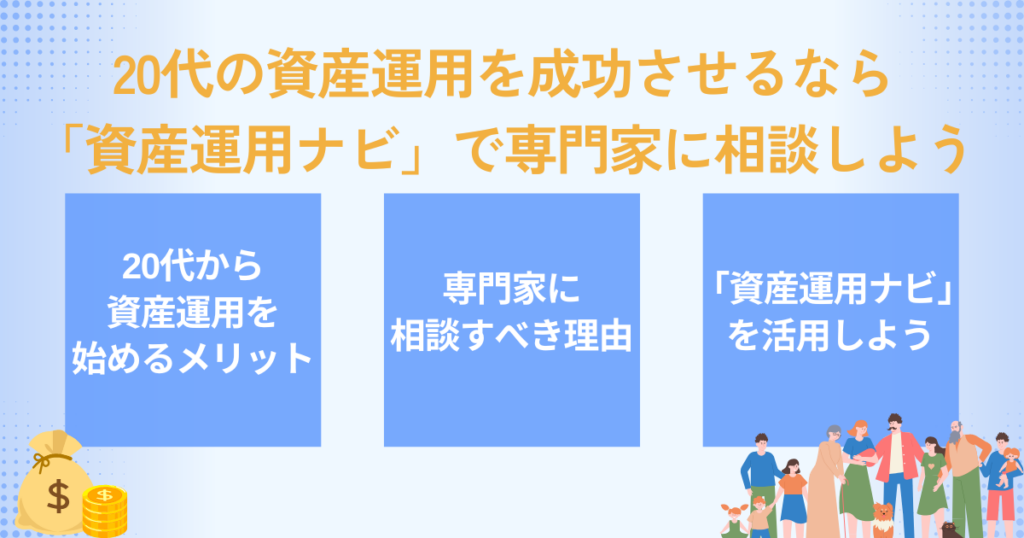
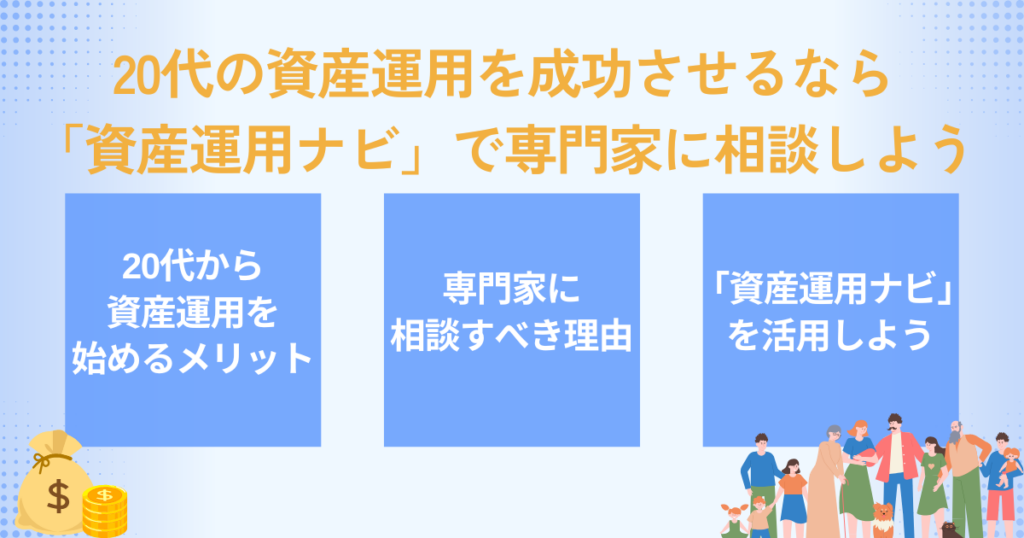
20代で資産運用を成功させたいのであれば、資産運用アドバイザーを探せるサービス「資産運用ナビ」の利用がおすすめだ。
投資助言を行う専門家を「資産運用ナビ」で探し、資産運用の悩みや不安を解消しよう。
ここでは、20代から資産運用を始めるメリットや専門家に相談すべき理由、「資産運用ナビ」の特徴や利用方法を解説していく。
20代から資産運用を始めるメリット
20代から資産運用を始めるメリットとして以下の2点が挙げられる。
- 少額の投資でも目標額に到達できる可能性がある
- 投資経験を積める
繰り返しとなるが、20代から投資を始める場合は長期的に運用できるため、複利効果の恩恵を受けやすいことがメリットだ。
利益が新たな利益を生み出す分、自分で投資する金額が少なくても目標額に到達できる可能性がある。
目標額を無理なく達成するためにも、早くから資産運用を始めることが大切だ。
また、投資を始めると経済の動向や企業の決算情報、投資している分野に関連するニュースに興味を持つようになる。
さらには若いうちに投資を始めて損失を経験しておくことで、その後の投資判断のスキルも身に付く。
投資経験を早い段階から積める点も20代で資産運用を始めるメリットだ。
専門家に相談すべき理由
20代から資産運用を始めるメリットが多くある一方、自分だけで資産運用を始めることは容易ではない。
投資助言を行う専門家に相談した上で資産運用を始めることをおすすめする。
専門家に相談すべき理由として以下のような点が挙げられる。
- 万人におすすめの運用法が存在しないため
- 常に最新の情報をチェックする必要があるため
- 運用開始後も適切なアフターフォローが必要であるため
資産運用の方法は個人の資産状況やリスク許容度、運用目的によって最適解が異なる。
万人におすすめの運用法は存在しないため、自分の状況に合ったものを選択しなければならない。専門家から助言をもらい、自分に合った運用方法を見極める必要があるだろう。
また、資産運用を行う際は常に変化するマーケットの動向をチェックしつつ、経済や国際情勢についての最新情報も入手しておく必要がある。
しかし本業で忙しい人にとって情報を入手・分析することは容易ではない。専門家から情報を提供してもらうほうが効率が良く、スムーズに投資判断を行える。
そして、運用を始めてからも状況に応じて運用方法を切り替えていく必要がある。適切なアフターフォローを受けるという意味でも専門家の存在は欠かせない。
20代から資産運用を始めたいのであれば、投資助言を行う専門家に相談してみよう。
「資産運用ナビ」を活用しよう
信頼できる相談先をお探しの方は「資産運用ナビ」を利用しよう。
「資産運用ナビ」は、あなたにぴったりの資産運用アドバイザーを無料で紹介するサービスである。
「資産運用ナビ」でアドバイザーとマッチする流れは以下の通りだ。
- 専用フォームに希望条件を入力する
- 条件に合ったアドバイザーが自動診断される
- プロフィールをチェックして相談先を選ぶ
- 初回面談の日程を調整する
- アドバイザーと面談を行う
「資産運用ナビ」ではアドバイザーの詳細なプロフィールを公開しており、事前に経歴や保有資格、得意分野などをチェックした上で相談先を選べる。
アドバイザーの紹介料や相談費用は無料となっており、何度面談を行っても費用がかからないことが特徴だ。
アドバイザーの紹介は全国47都道府県どこでも対応しており、オンラインでの面談も可能である。
面談の時間を捻出することが難しい方でも、自宅で気軽に相談を行える。
ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を活用し、信頼できるアドバイザーに資産運用の相談をしてみてはいかがだろうか。
自分に合った方法で20代から資産運用を始めよう
20代から資産運用を始めるのであれば、まずは投資信託の活用がおすすめだ。
リスク許容度に合った商品を選び、時間を味方につけた長期運用で効率的に資産を増やしていこう。
投資信託以外の運用法を検討したい方は、株式や債券、不動産などの投資先がおすすめだ。
投資目的やリスク許容度に合わせて投資先を選び、最適な運用ポートフォリオを構築していこう。
資産運用について悩みや不安な点がある場合、投資助言を行う専門家への相談をおすすめする。
最適化された投資戦略を提案してもらえるため、効率的に資産運用を始められる点が魅力だ。
「資産運用ナビ」では、あなたにぴったりの資産運用アドバイザーを無料で紹介するサービスを提供している。
ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を活用し、信頼できるアドバイザーを探してみてはいかがだろうか。



20代は将来のライフイベント(結婚・住宅購入・教育資金など)を見据えた資産形成のスタートに最適な時期です。
分散投資や積立型の運用を基本とし、ライフプランに基づいた資産配分を検討することで、無理なく着実な運用が可能になります。