- 投資の種類が多く、どれを選べば良いかわからない
- それぞれのメリット・デメリットを比較したい
- 初心者におすすめの投資法が知りたい
本記事では、株式や債券、不動産などの代表的な投資の種類について、それぞれの特徴やメリット・デメリットをわかりやすく解説する。
さらに、リスクとリターンの基本知識、初心者におすすめの投資法や、NISAやiDeCoのような資産形成を後押しする制度についても紹介する。
投資の基礎を理解することは、資産形成を目指すうえでの強力な支えとなるはずだ。
「余裕資金をどう増やすべきか迷っている」「どの投資方法が自分に合っているかわからない」という人は、ぜひ最後まで読み進め、参考にしていただきたい。
投資の基本知識
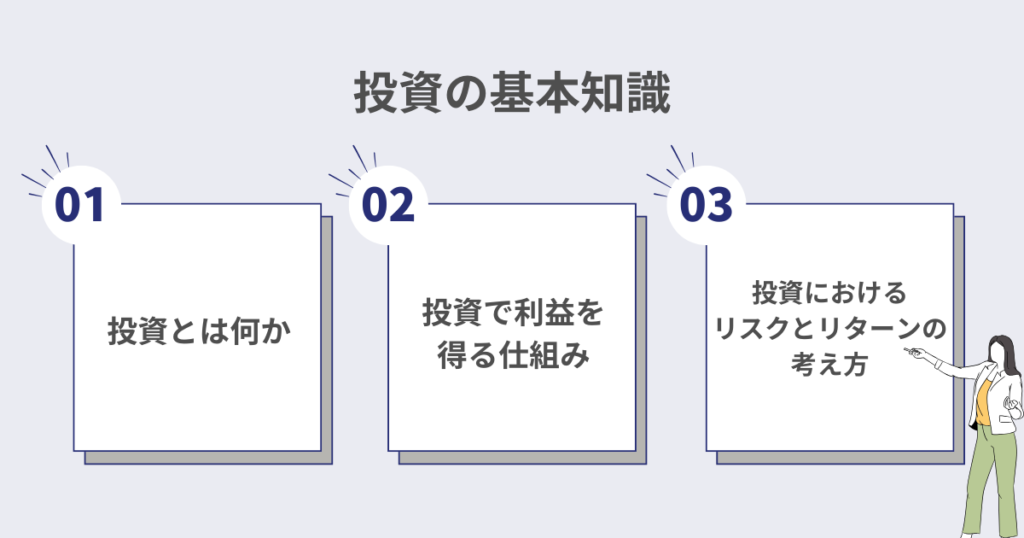
まずは、投資とはどのようなものかを確認していこう。
投資とは何か
投資とは、「将来的に資産を増やし、利益を得ることを目的に、資金をさまざまな対象へ投入する行為」のことだ。
投資対象には、株式や債券、不動産、コモディティなど多様な選択肢があり、それぞれ異なるリスクとリターンを持つ。
投資で利益を得る仕組み
投資によって得られる利益には、「キャピタルゲイン」と「インカムゲイン」の2種類がある。
- キャピタルゲイン(値上がり益)
- 株式や債券、不動産などの価値が上昇した際、売却によって得られる差益のこと。例えば1株1,000円で買った株式が1,200円に値上がりした場合、その差額がキャピタルゲインにあたる。
- インカムゲイン(配当・利息・家賃収入など)
- 保有しているだけで定期的に受け取れる利益を指す。株式の配当金、債券の利子、不動産投資の家賃収入などが代表例だ。
投資におけるリスクとリターンの考え方
投資で大切なのは、「どのくらいのリスクを取って、どのくらいのリターン(利益)を期待するか」をバランスさせることだ。
値動きが大きい商品ほど大きな利益を狙えるが、同時に損失リスクも高くなる。
例えば貯金は、金融機関にお金を預けるため元本が保証され、リスクは非常に低い。しかし、資産が大きく増える可能性も低い。
一方、投資には元本保証がなく、市況が悪化すれば投資額を下回る恐れがあるが、投資先が成長すれば大きなリターンを得られる可能性がある。
リスクとリターンのバランスは人それぞれだ。
ライフステージや運用期間、精神的な許容度を踏まえ、どの程度のリスクを負い、その対価としてどれだけのリターンを求めるかを投資家自身が見極めることが重要だ。
主な投資の種類と特徴
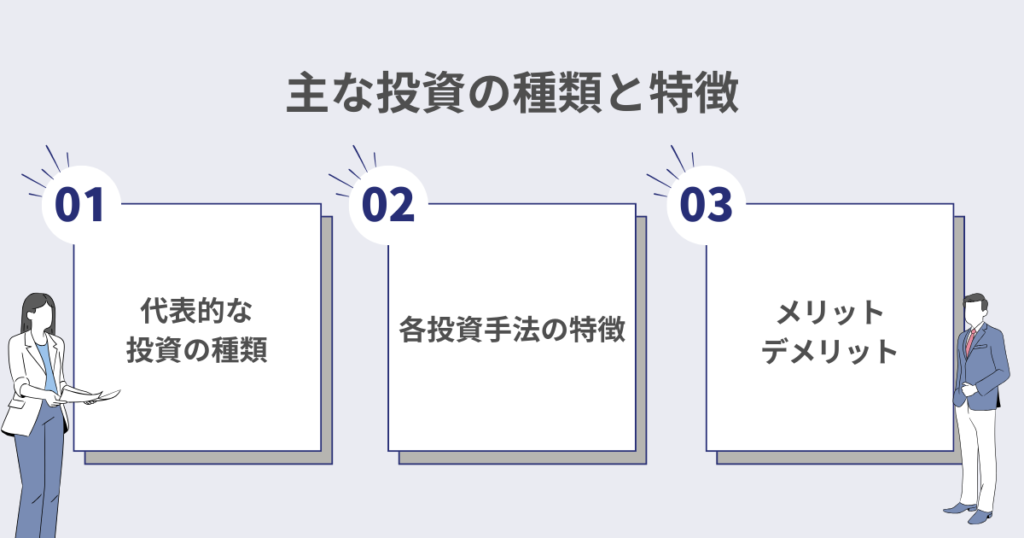
ここからは、代表的な投資の種類について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説していく。
債券投資
債券投資とは、国や企業などの発行体に資金を貸し付け、定期的な利息収入と満期時に元本返済を受け取る投資手法である。
利息収入が定期的に得られ、満期時には原則として元本が返済されるため、「リスクが低い投資」とみなされることが多い。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 安定した収益源になる 株式と異なる値動きをするため、ポートフォリオのリスク分散に貢献する 発行体が破綻した場合でも、優先的に弁済を受ける権利がある | 株式投資と比較してリターンが低い傾向 発行体の信用状況が悪化すると、利息の支払い停止や元本返済の遅延・不履行もある 市場金利の上昇により、既存の債券価格が下落することがある |
債券には、「国債」「地方債」「社債」などさまざまな種類が存在する。この中で個人投資家に身近なのは、「個人向け国債」だろう。
個人向け国債は1万円から購入することが可能だ。証券会社や銀行のほか、郵便局でも取り扱っているため、誰でも購入しやすい。
投資信託
投資信託とは、複数の投資家から集めた資金を運用のプロ(ファンドマネージャー)が株式や債券などに分散投資し、その成果を投資家に還元する仕組みの商品だ。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 少額から分散投資ができる プロに運用を任せられる 種類が豊富で目的に合わせて選べる | 信託報酬などの保有コストがかかる 元本保証はない リスクやコストが高い商品もある 選択肢が多く、選ぶ手間がかかる |
投資信託は、株式や債券といった資産を幅広くカバーするうえ、運用の手間を抑えられる点が大きな特徴である。
初心者や、運用に割く時間が限られている投資家にとって有効な手法と言える。
低コストのインデックス型投資信託は、特に長期的な資産形成に力を発揮する商品で、初心者から上級者までにおすすめできる。
株式投資
株式投資とは、企業が発行する株式を購入し、その企業の成長や業績向上による株価上昇や配当金などの利益を得る投資手法だ。
リスクが高い分、高いリターンを狙える可能性があり、ポートフォリオ全体の成長を牽引する役割を果たす。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 値上がり益を期待できる 配当金や優待のある銘柄を保有すれば、継続的なリターンも期待できる 国内外の幅広い銘柄に投資できる | 値動きが大きく、短期間で大きな損失を被る可能性がある 企業分析が大変 倒産や破綻などの場合は、投資額が大幅に減少するリスクがある |
株式投資は、長期的な企業の成長を取り込める反面、短期的な値動きも大きい。
初心者は、まずリスク許容度を確認し、安定性の高い銘柄や配当のある銘柄から始めるのが望ましい。
- 過去の業績や財務状況が安定している大型企業や、業界内で高いシェアを持つ優良企業を中心に検討する
- 配当金や株主優待がある銘柄は継続保有するメリットが大きい
- 馴染みの業界や会社を選ぶと、企業分析や事業内容の把握が容易になり、投資判断しやすい
ETF(上場投資信託)
ETF(Exchange Traded Fund)とは、証券取引所に上場している投資信託の一種だ。株式と同じように取引所でリアルタイムに売買できる点が特徴である。
投資信託の分散効果と株式の売買のしやすさを兼ね備えており、時間分散(コツコツ買い増し)とリアルタイム売買を両立させたい投資家に向いている。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| リアルタイムで売買できる 指数連動型が多く、運用状況がわかりやすい 取引コスト(信託報酬)が比較的低い 多様なETFがあり、目的に合わせた投資がしやすい | 再投資したいなら、自分で注文する必要がある 証券会社によっては、取引(売買)手数料がかかる |
投資信託とETFは、株式や債券など複数の資産を一つにパッケージ化している点で共通しているが以下のような違いもある。
- 投資信託は1日1回決定される基準価額で売買するが、ETFはリアルタイムの市場価格で売買できる
- 投資信託では分配金の受取方法(再投資か現金受取)を選択できるが、ETFは分配金が必ず投資家に支払われる。再投資を行う場合は、自分で注文を出す必要がある
- 投資信託は金額指定で購入できる商品が多いが、ETFは株式同様に取引単位(例えば1株)で売買する。そのため、銘柄によっては初期投資額が大きくなることもある
REIT(不動産投資信託)
REIT(Real Estate Investment Trust)は、不動産を主な投資対象とする投資信託だ。
複数の投資家が共同で不動産を保有し、その賃貸収入や物件の売却益などの運用成果を投資家に分配する仕組みになっている。
証券取引所に上場しているREITであれば、株式と同様にリアルタイムでの売買が可能である。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 少額で複数の不動産に分散投資できる 安定的な分配金を期待できる 維持や管理の手間がかからない 上場REITなら流動性が高く、売買が容易 | 市況変動に左右されやすい 物件価値が下落すると、配当も減少し得る 金利上昇局面では下落リスクが高まる傾向 |
REITは、景気や金利、不動産市況といった外部要因から受ける影響が大きい投資商品である。
- 好景気ではオフィス需要や商業施設利用が増え、賃貸収入が伸びやすい。しかし、不況期にはテナントの撤退や賃料引き下げが発生し、収益悪化につながりやすい。
- 不動産取得には借入金が利用されることが多く、低金利下では借入コストが低く抑えられるため分配金を高水準に維持しやすい。金利上昇局面ではコスト増により収益が圧迫される
- 金利が上昇すると、安全資産である債券などの利回りが魅力的になるため、REITから資金が流出(価格下落)しやすい
外貨預金
外貨預金とは、円資金を米ドルやユーロなどの外国通貨に交換し、外国通貨建ての預金口座に預ける金融商品だ。
日本円よりも金利が高い通貨を選ぶ場合、利息による収益を期待できるが為替変動によるリスクを伴う。
そのため、「リスクをある程度許容しながら、円預金より高い利息を得たい」と考える投資家に向いている。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 高金利通貨を選べば、高い利息が得られる 為替相場が有利に動いたら、円換算額が増える 銀行の窓口やネットバンキングで手続きでき、仕組みがわかりやすい | 為替リスクを負う 売買時のスプレッドなどの手数料がかかる 為替レートが不利に動くと、利息以上の損失になることがある 預金保険制度の対象外である |
金(ゴールド)投資
金(ゴールド)投資とは、「金」という希少金属に資産を振り向ける投資手法である。
株式や債券などのペーパー資産とは異なり、実物資産としての「希少価値に基づく需要」が価格に反映される。
古くからインフレヘッジや通貨不安への備えとして活用されており、現物購入のほか、ETF(上場投資信託)や純金積立など、多様な投資手段が存在する。
インフレや金融危機への備えとして、資産保全を重視する投資家や、ポートフォリオの一部を金で保有したい人に向いている。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| インフレや通貨不安に強い ETFや投資信託、純金積立など、投資スタイルに合わせた選択が可能 株式や債券との相関が低くポートフォリオ分散に役立つ | 利息や配当がないため、キャピタルゲインのみを狙う形になる 短期的に大きな値動きをすることがある(現物の場合) 保管コストがかかる |
実物不動産投資
実物不動産投資とは、マンションやアパート、戸建て住宅、オフィスビルなどの不動産を直接購入し、賃貸収入(家賃)や売却益(キャピタルゲイン)を得る投資手法である。
ローンを活用すれば、投資規模を拡大し投資効率を高められる。一方で、物件の管理や運営に手間がかかるため、一定の知識や資金的余裕が求められる。
長期的に安定したキャッシュフローを狙いたい人で、株式などの金融資産とは異なる値動きをポートフォリオに加えたい投資家に向いている。
管理や修繕などの手間、初期費用の大きさを厭わない人であればなお良い。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 安定的な賃貸収入が期待できる 不動産価格が上がれば売却益も期待できる ローンを活用すれば少ない自己資金で大きな投資が可能 インフレに強い傾向がある | 初期費用や維持管理コストが高い 空室や家賃下落のリスクがある 流動性が低く、物件売却に時間を要する場合がある 物件選びを誤ると大きな損失につながる可能性がある |
FX(外国為替証拠金取引)
FXとは、証拠金(担保)を預けて通貨の売買を行い、為替レートの変動による差益を狙う取引のことだ。
通貨同士の交換レートに焦点を当てており、主に短期から中期の売買が中心である。
短期的なトレードやレバレッジ取引に慣れている人で、ハイリスクを許容してでも短期的に大きなリターンを狙いたい人に向いている。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| レバレッジを利用して大きな利益を狙える 平日は24時間取引が可能 流動性が高く、取引が成立しやすい 上昇相場・下落相場いずれでも利益を狙える | ハイリスク・ハイリターンの取引になりがち 為替レートが急変した場合、損失拡大の恐れがある 証拠金の追加(追証)が発生するケースもある |
暗号資産(仮想通貨)
暗号資産(仮想通貨)とは、ブロックチェーン技術を基盤に発行・運用されるデジタル資産の総称である。
中央銀行などの特定の管理者を必要としない、分散型の仕組みを特徴とする。
価格変動が非常に大きい、ハイリスク・ハイリターンの投資対象だ。実際に投資を検討する際は、最新の情報収集と慎重な判断が不可欠である。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 短期間で大きなリターンを狙える可能性がある グローバルに利用される通貨としての将来性が期待できる 24時間365日取引が可能 ポートフォリオの分散効果を高める潜在力がある | 価格変動が非常に激しい 法規制や国際的な動向に左右されやすい 保管・セキュリティ面のリスクがある |
投資種類のリスク・リターン比較表
以下の表は、リスク水準と期待リターンを5段階(低・やや低・中・やや高・高)に区分したものだ。
あくまで一般的な傾向であり、商品や運用方法によって大きく変化し得るため、目安としての利用にとどめて欲しい。
| 投資種類 | リスク | リターン | 特徴と例 |
|---|---|---|---|
| 預金 | 低 | 低 | 元本保証。資産はほぼ増えないが、生活防衛資金には最適。 |
| 国内債券 | やや低 | やや低 | 為替リスクがなく、比較的安定した利息収入が期待できる。 |
| 先進国債券 | 中 | 中 | 為替リスクあり。国内債券より利回りがやや高い。 |
| 国内株式(インデックス型) | やや高 | やや高 | 東証株価指数(TOPIX)等に連動し、中長期の成長が期待できる。 |
| 先進国株式(インデックス型) | やや高 | 高 | 為替リスクあり。世界経済成長の恩恵を受けやすい。 |
| 新興国株式(インデックス型) | 高 | 高 | 政治・経済リスクは大きいが、高成長によるリターン期待も大きい。 |
| REIT(不動産投資信託) | 中〜やや高 | 中〜やや高 | 国内外の不動産に分散投資可能。家賃収入からの配当が魅力。 |
| コモディティ(金など) | 中〜やや高 | 中〜やや高 | インフレや政治リスクに強いが、値動きは荒い。 |
| 暗号資産(仮想通貨) | 非常に高 | 非常に高 | 値動きが極端に大きく、短期で大きな利益も損失もあり得る。 |
上表のとおり、暗号資産(仮想通貨)や新興国株式などは値動きの幅が大きい。
政治情勢や為替の変動、投機的な思惑などで市場が急変する場面もあり、短期的に損失が拡大しやすい。
レバレッジを大きく効かせるFXや先物取引などは、少ない証拠金で大きな金額を動かせるが、相場が逆に振れると想定以上の損失を被る恐れがある。
市場そのものや資金管理に慣れていない初心者は、これらの手法に安易に手を出さない方が賢明だ。
相場に慣れてきて挑戦したくなったとしても、あくまで「趣味」として、すべてを失っても良いと思える額を投じるようにして欲しい。
投資を始める前に知っておくべきこと
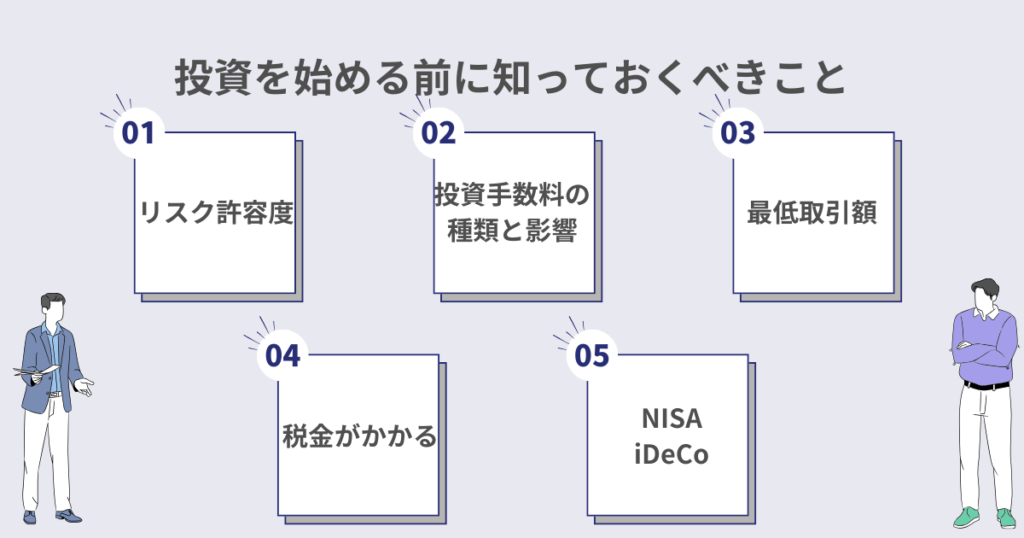
ここでは、投資をスタートする前に、最低限押さえておきたいポイントを紹介する。これらを理解しておくことで、無理のない運用計画を立てやすくなるはずだ。
自分のリスク許容度
投資を始める前には、自分の「リスク許容度」の把握が不可欠だ。
リスク許容度とは、投資先の価値が下落しても精神的・経済的に耐えられる範囲のことである。
年齢や家族構成、収入状況、さらには投資に対する考え方などによっても異なる。
Webの無料診断を利用し、「安全型」「バランス型」「積極型」などのどれに該当するのかを確認する方法は、簡易的でありおすすめだ。
これに加えて、自分で損失シナリオを考えてみるのも有用である。
例えば、収入や支出、貯蓄額を整理し、「投資額が20%下落しても耐えられるか」「どの程度の下落なら生活に支障が出るか」などを具体的に考えておくと良い。
一般的なリスク許容度の考え方も参考にして欲しい。
- 投資期間が長いなら、一時的な価格下落があっても回復を待てるため高いリスクにも耐えられる
- 収入源が少なく生活がギリギリなら、大きな損失に耐えられない。リスクの低い投資から始めるべき
- 急な出費の予定があるなら、現金化ニーズが高いためリスクを許容できる範囲は狭まる
投資判断をする際は、常にリスク許容度と合致しているかを確認することを習慣づけよう。これが無理なく資産を増やしていくための基本となる。
投資手数料の種類と影響
手数料の仕組みについての理解も、投資において非常に重要だ。
手数料負担が大きいと、投資成績が好調であっても最終的なリターンを低く抑えられる可能性があるためだ。
投資にかかる手数料には、主に以下のようなものがある。
売買にかかる手数料
買付時に一度だけ支払う「購入(申込)手数料」や、売却時に必要な「売却(解約)手数料」、FX取引で発生する「スプレッド(売買価格の差)」などが該当する。
投資信託では、追加で「信託財産留保額」が設定される場合がある。
この費用は、解約時に投資家が負担するもので、解約によって生じるファンド内コストを、残存投資家が被らないようにする目的で導入されることが多い。
証券会社や商品によっては無料の場合もあれば、一定の料率が設定されている場合もある。
これらは取引ごとに生じるコストであるため、売買頻度が高いほど負担が増す点に注意したい。
保有にかかる手数料
投資信託やファンドラップ、ロボアドバイザーなどでは、保有期間中に継続して発生するコストがある。
これらは「信託報酬」や「管理費用」などの名称で呼ばれ、年間の料率(例えば年0.1%など)が設定されている。
中でも信託報酬は、毎日の運用過程でファンド資産から差し引かれる、投資家にとっての「見えづらいコスト」だ。
しかし、長期投資を行う上でこのコストが積み重なっていく影響は想像以上に大きい。
例えば、信託報酬の差が1%程度でも、20年後の資産額が数十万円以上変わるケースは珍しくない。
長期の資産形成を考えるなら、手数料水準をしっかり比較し、自分の運用方針に合った商品を選ぶことが大切だ。
投資には「最低取引額」があること
投資対象によっては、取引を開始するための「最低取引額」や「最低購入単位」の設定がある。
近年では、少額で取引できる仕組みを備えた証券会社も多い。
例えば楽天証券やSBI証券では、投資信託や株式の積立投資は「100円から」、個別株式の売買は「1株単位から」できる。
一方で、投資対象によっては高額資金や一定の預かり資産が求められることがある。
例えば、特定の投資ファンドや不動産投資案件では、数百万円以上からでなければ参加できない場合がある。
こうした高額商品では、最低取引額を満たせないと、そもそも投資そのものが成立しない。
投資には税金がかかること
日本では、課税口座(一般口座や特定口座など)で行った取引による利益には税金が課される。
上場株式や投資信託の譲渡益、配当(分配金)、そして預金利息に対しては、20.315%の税率(所得税・住民税・復興特別所得税を含む)が適用される。
一方、暗号資産(仮想通貨)やFX取引では、所得の区分が異なるため、課税ルールも変わる。
暗号資産は雑所得として総合課税の対象となることが多く、FXは先物取引にかかる申告分離課税として扱われる場合が一般的だ。
投資対象によって適用される税制は変わるため、事前に商品ごとのルールを確認しておくようにしよう。
投資を有利に進められる制度があること(NISAとiDeCo)
NISAやiDeCoを活用すれば、運用益に対する税負担を大幅に軽減できる。
- NISA(少額投資非課税制度)
- 投資による利益が非課税となる
- 新NISAでは1,800万円まで、非課税で投資できる
- 年間投資上限は360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 毎月拠出する掛金は、所得控除の対象となる
- 投資による利益が非課税となる
- 引き出し時には退職所得控除や公的年金等控除が適用される可能性がある
これらの制度をうまく活用できるかどうかが、長期的なリターンに大きく影響する。自分の投資目的や資金状況に合わせて、積極的に検討すると良い。
投資初心者におすすめの組み合わせと実践方法
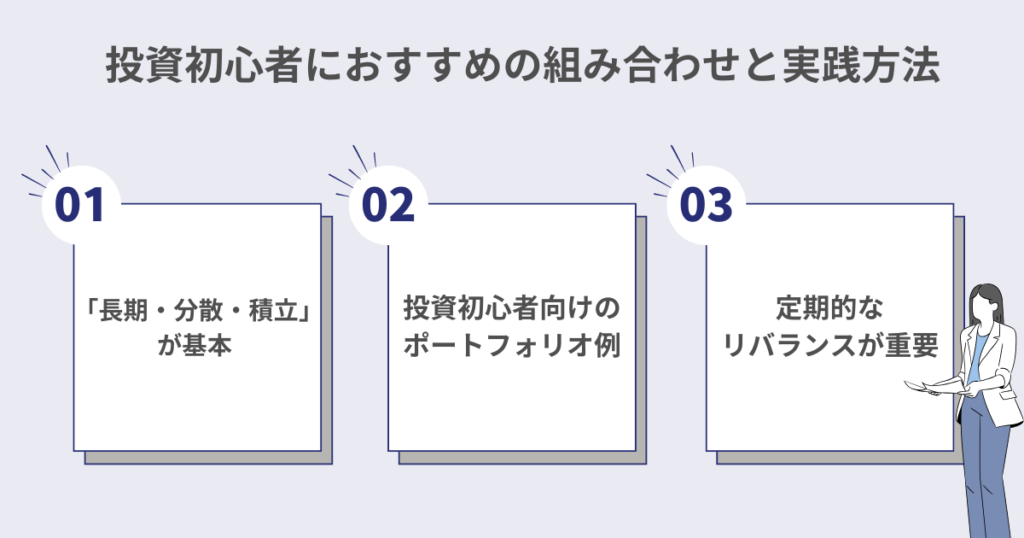
ここでは、投資初心者が無理なく始められる「長期・分散・積立」を軸とした実践方法と、具体的なポートフォリオ例を紹介する。
あわせて、運用を続けるうえで重要となるリバランスの考え方も解説する。
「長期・分散・積立投資」が基本
投資初心者が資産形成を安定して進めるには、「長期・分散・積立」の3つの要素を組み合わせることが重要となる。
長期投資とは、短期的な相場の上下に左右されず、時間を味方につけて複利効果を最大限に取り込む投資手法である。
分散投資は、複数の投資対象を組み合わせてリスクを分散させる方法だ。
例えば、株式や債券など異なる「資産クラス」や投資地域を分けて組み入れることで、一つの市場が急変した際の影響を抑える。
積立投資(ドルコスト平均法)は、投資タイミングを分散するやり方である。毎月(または定期的)に一定額を投資することで取得価格の平準化を図る。
価格が上がっているときには少なく、下がっているときには多く買い付ける仕組みのため、長期的には取得単価を引き下げる効果が期待できる。
投資初心者向けのポートフォリオ例
初心者が投資を始める際には、複数の資産を組み合わせた「バランス型」のポートフォリオを組むと良い。以下に、いくつかの例を挙げる。
リスク控えめタイプ
リスクを極力抑えたいなら、債券を中心に据えて安定性を高めると良い。具体的には、債券70%、株式30%といった配分が考えられる。
複数の商品を組み合わせてポートフォリオを組む方法もあるが、管理が煩雑になるため、かえってリスクが高まるケースもある。
よって投資商品も極力絞り込むのがおすすめだ。バランス型投資信託を1本選び、積立投資していくのが安心である。
証券会社の検索機能で「バランス型」「債券中心」「安定型」などの条件を指定し、純資産額が大きく、信託報酬が低い商品を探すと良い。
こうしたバランス型商品なら、1本でリスクを抑えつつ、一定のリターンを狙える設計になっているため、初心者でも取り組みやすい。
バランス重視タイプ
リスクを抑えながらもリターンをしっかり狙いたいなら、「バランス重視」の配分がおすすめだ。
例えば、株式50%、債券50%のように均等配分を基本とし、自身のリスク許容度に合わせて調整を加えると良い。
資産均等型のバランス型投資信託を購入すれば、管理の手間を軽減しながら分散を図りやすい。
人気の「オルカン」や「S&P500連動」の株式型ファンドに興味があるなら、それらを利用しても良いだろう。
例えば、債券型ファンドを組み合わせれば均等配分を実現できる。
リスクの程度は国内資産と海外資産の割合によってもコントロール可能だ。国内中心にすれば為替リスクを低減できるため、全体のリスクは相対的に低くなる。
一方で海外資産を多めにすれば、より高いリターンを狙いやすくなる。
リスク許容度高めタイプ
積極的にリターンを追求したいなら、株式の比率を大きめに組むことで成長性を狙うと良い。
例えば、株式80%、債券20%といった配分であれば、相場が好調なときに大きな利益を期待できる。
初心者には、株式型とバランス型を積立投資し、理想の配分を目指す方法がおすすめである。
慣れてきたら個別株やETFのリアルタイム取引に挑戦してみるのも面白い。
リスク許容度が高いポートフォリオでは、相場急変時の下落幅も大きくなりがちな点には注意が必要だ。
取り組む前には、短期的に大きな下落(例えばマイナス30%程度)を被っても耐えられるか、しっかり考えるべきである。
加えて、定期的なモニタリングを欠かさず行い、株式の比率が想定以上に膨らんでいないかを確認することが重要になる。
定期的なリバランスが重要
安全な運用を続けるためには、モニタリング(監視)とリバランスが欠かせない。
リバランスとは、運用を続けるうちにズレてしまった資産配分を、当初の計画に近づけるために売買調整を行う手法である。
運用中は時価の変動によって、株式が極端に値上がり(または値下がり)し、ポートフォリオ内の株式比率が想定以上に高まる(あるいは低まる)可能性がある。
そのまま放置すると、リスクが偏りすぎたり、期待していたリターンを得にくくなったりするため、定期的に資産を売却・買い増しして配分を戻すのである。
半年から1年に1回程度を目安に、ポートフォリオを点検し、必要に応じて売却や追加投資を行うのが一般的だ。
ただし、頻繁に行いすぎると、取引手数料や税負担が増大してしまうため、過度な調整は避けるようにすべきだ。
投資を成功させるためのポイントと注意点
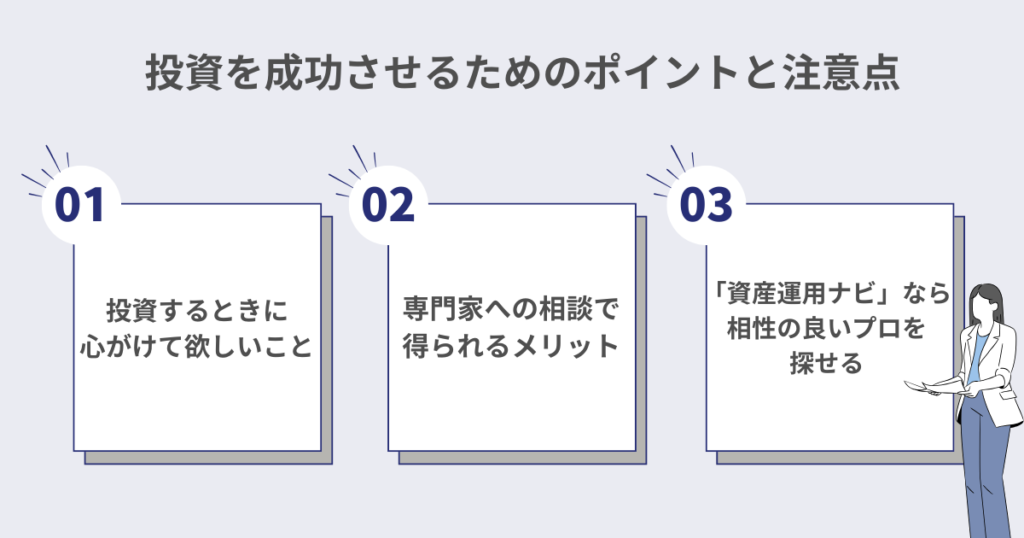
最後に、投資を成功させるためのポイントについて整理する。
投資するときに心がけて欲しいこと
以下は、着実に資産形成を進めるために、心がけていただきたいポイントだ。
- 生活防衛資金には手をつけず、余剰資金の範囲で投資する
- 長期目線を持ち、短期的な値動きに振り回されない
- コスト意識を高め、手数料が低い商品を選ぶ
- リスク許容度を把握し、それを踏まえて投資する
投資初心者がすべてを独力で判断するのは、難しいこともある。
プロのアドバイスを受けることは、投資における失敗を上手に回避し、効率的に資産形成を進めるための近道となる。
専門家への相談で得られるメリット
投資を始める段階で専門家に相談するのは、「何もわからない状態で話をしていいのだろうか」「投資資金が少ないから相手にされないのでは」といった不安を抱く方もいるかもしれない。
しかし、投資初心者こそ得られるメリットは大きいのだ。
- プロの視点からの具体的な提案を受けられる
- 難しい専門用語なども、わかるまで丁寧に説明してもらえる
- リスク許容度に合わせたポートフォリオを提案してくれる
- 感情的な売買の判断ミスを防ぎやすい
一人ですべてを抱え込まず、プロの意見を取り入れることで、投資家としての成長が促され、安心感も高まるはずだ。
「資産運用ナビ」なら相性の良いプロを探せる
投資初心者に向けたアドバイスを得意とする専門家は多いが、信頼できる相手を見つけるのは容易ではない。
そこで役立つのが、検索機能が充実したマッチングプラットフォーム「資産運用ナビ」である。
「資産運用ナビ」のレコメンドシステムを使えば、たった3つの質問に答えるだけで、ニーズに合う専門家が紹介してもらえる。
気になる専門家が見つかったら、そのまま面談に進める仕組みとなっている。
登録・利用・相談は、すべて無料だ。複数の候補者と話してみて、気の合う専門家を選ぶことも可能だ。
初心者の段階から専門家に相談すれば、不要な失敗を避け、資産形成をスムーズに進めやすくなる。
自力で学びながら、プロの力を賢く借りることで、大きな成長や納得感を得られるだろう。
投資の種類を理解して「自分なりの組み合わせ」を見出すことが成功への第一歩!
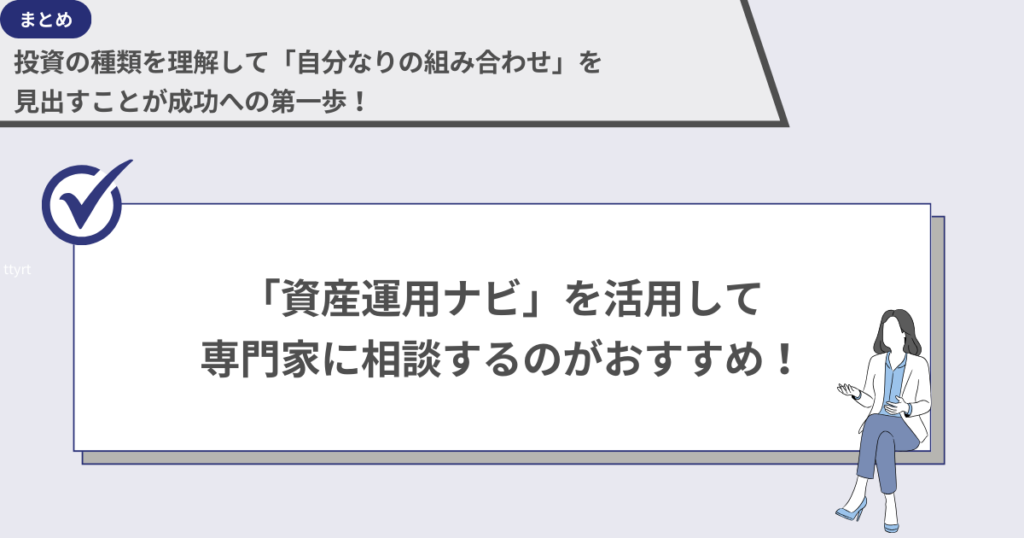
投資にはさまざまな種類があり、それぞれが異なる特徴とリスク特性を持つ。
自分のリスク許容度や投資期間を踏まえたうえで、「これなら続けられる」と感じる投資方法を選び、組み合わせることが大切だ。
とはいえ、最適な組み合わせは人によって異なるため、初心者が独力で判断するのは難しい。
こうしたときは「資産運用ナビ」を活用し、専門家に相談するのがおすすめだ。
客観的なアドバイスを得ることで、リスク管理や投資先の選定をスムーズに行い、失敗を回避しやすくなる。
まずは無料相談で、気になる専門家と話してみて欲しい。相性の良いプロを見つければ、目指す資産形成の目標に、また一歩近づくはずだ。


