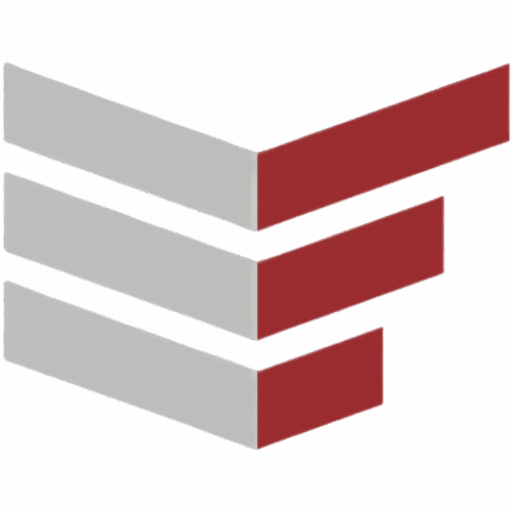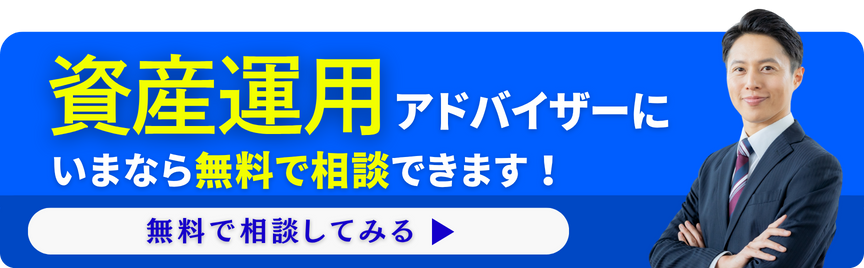- 手元の1,000万円を、ただ預金しておくのはもったいないと感じる
- でも、投資で大損するのは絶対に避けたい
- 自分に合った、失敗しない資産運用の方法が知りたい
- 何から始めれば良いのか、具体的な手順を知りたい
退職金や貯蓄などで得た1,000万円。
「賢く増やしたいけれど、損はしたくない」と考える人は多いでしょう。
日銀は2024年7月31日、8月1日付で政策金利を 0.25%程度に引き上げ、プラス金利政策へ復帰したが、2025年8月現在も日本の金利は高いとは言い難い。銀行預金だけでは将来が不安な一方、投資にはリスクがつきものだ。
この記事では、あなたの目標に合った資産運用の始め方を、具体的なモデルプランを交えて解説する。
この記事は将来の不安を「安心」に変える、その一歩をサポートするための解説書だ。
1,000万円の運用で失敗しないための基本
1,000万円の運用で最も多い失敗パターンは、「全額を一気に投資して暴落で慌てて売却する」ことです。
この「感情的な売却」を防ぐ最もシンプルな方法が、お金を目的別に「3つの財布」に分けて管理することです。
| 資金性格 | 役割・目的 | 配分の目安 |
|---|---|---|
| ① 守る資金 | 生活防衛資金+直近3年以内の支出 絶対に減らしてはいけないお金 | 生活費3〜12ヶ月分 (100〜300万円程度) |
| ③ 使う資金 | 3〜10年後の支出に備える (教育費・住宅・取り崩しなど) | 残りの20〜50% (200〜400万円程度) |
| ② 育てる資金 | 10年以上使わない長期運用枠 | 残りの50〜80% (400〜600万円程度) |
では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
① 守るお金
守るお金とは、絶対に減らしてはいけないお金のことです。
具体的には、以下の2つが該当します。
- ケガ・病気・失業など不測の事態に備える「生活防衛資金」
- 直近3年以内に確実に使う予定があるお金
この資金は投資に回さず、すぐに引き出せる普通預金や個人向け国債で保管しましょう。
【生活防衛資金の目安】
| 働き方 | 確保すべき金額 | 月25万円の生活費なら |
|---|---|---|
| 会社員 | 生活費の3〜6ヶ月分 | 75〜150万円 |
| 自営業・ フリーランス | 生活費の6〜12ヶ月分 | 150〜300万円 |
守るお金を確保せずに全額を投資に回すと、急な出費が必要になったとき、運用中の資産を売却せざるを得なくなります。
市場が下落しているタイミングなら、損失を確定させることになってしまうのです。
② 使うお金:教育費や住宅購入など中期の支出用
備えるお金は、3〜10年後に使う予定があるお金です。教育費、住宅購入の頭金、老後の生活費などが該当します。
この資金の運用は、「守る」ほど安全である必要はありませんが、「増やす」ほどリスクを取るべきではないでしょう。ちょうど中間のバランスが求められます。
【備えるお金に適した運用先】
- 債券ファンド
値動きが穏やかで安定性が高い - 高配当株ファンド
定期的な配当収入が期待できる - バランスファンド
株式と債券を自動で配分してくれる
使う時期が近づいてきたら、徐々に安全資産(債券や預金)の比率を高めていくことで、「いざ使おうとしたら資産が大きく減っていた」というリスクを軽減できます。
③ 増やすお金
増やすお金は、10年以上使う予定のない「純粋な余裕資金」です。
この資金こそ、株式や投資信託で積極的にリターンを狙う対象となります。
長期運用の最大の武器は「複利効果」です。運用で得た利益を再投資することで、時間とともに資産が雪だるま式に増えていきます。
【1,000万円を年5%で運用した場合(複利)】
| 運用期間 | 将来の資産額 (目安) | 増えた金額 (目安) |
|---|---|---|
| 10年後 | 約1,630万円 | 約+630万円 |
| 20年後 | 約2,650万円 | 約+1,650万円 |
| 30年後 | 約4,320万円 | 約+3,320万円 |
また、長期投資には「時間によるリスク軽減効果」もあります。
株式市場は短期的には大きく上下しますが、10年、20年という長期で見ると右肩上がりの傾向にあります。
過去のデータでは、全世界株式に15年以上投資した場合、元本割れの確率は極めて低いことが示されています。
 証券アナリスト 平行秀
証券アナリスト 平行秀1,000万円規模の資産があれば、複数の資産クラスに分散投資できる十分な余力があります。目的別に資金を色分けすることで、感情的な判断を避け、長期的な運用を継続しやすくなります。
特に投資初心者の方は、この「目的別管理」を徹底することで、暴落時のパニック売りを防ぐことができます。
【ケース別】1,000万円におすすめのポートフォリオ
「3つの財布」の理論はシンプルですが、いざ実践しようとすると「自分ならどう分けるべきか」で迷ってしまうものです。
最適な資産配分は、年齢や家族構成、そして将来のライフプランによって一人ひとり異なります。ここでは、多くの方に当てはまりやすい2つの代表的なモデルケースをご紹介します。
自分に近いケースを参考に、配分のイメージをつかんでください。
ケース1:40代・共働き夫婦
【状況】
- 世帯年収900万円
- 子ども2人(10歳・7歳)
- 住宅ローン残債あり
- 貯蓄から1,000万円を運用に回したい。
40代世帯は、直近の「教育費」という大きな支出に備えつつ、遠い将来の「老後資金」も同時に作らなければならない、資産運用のもっとも難しい時期にあります。
このケースでは、手元の1,000万円を「いつ、いくら必要になるか」という予定に沿って、以下の通りバランスよく配分してみました。
【ポートフォリオ例】
| 主な目的 | 金額 (比率) | 具体的な預け先 | |
| 守る 資金 | 生活防衛・ 急な出費 | 150万円 (15%) | ・普通預金 ・個人向け国債 |
|---|---|---|---|
| 使う 資金 | 子どもの 大学進学費 | 300万円 (30%) | ・定期預金 ・債券ファンド |
| 育てる 資金 | 夫婦の 老後資金 | 550万円 (55%) | ・全世界株式 (NISA活用) |
この配分のポイント
- 「使う時期」から逆算した商品選び
-
大学進学まで10年を切っている教育費(使う資金)は、暴落のリスクを避けるためにあえて株式を避け、「安定重視」の債券や定期預金に割り当てています。
これにより、いざという時に「株価が下がっていて学費が足りない」という事態を防ぎます。
- 「20年」という時間を味方につける
-
一方で、老後資金(育てる資金)は使うまで20年以上の猶予があります。
この550万円は、一時的な変動を恐れず「全世界株式」などで積極的に運用し、複利効果を最大化させることで、将来の大きな資産形成を狙います。
- NISA制度の段階的活用
-
一度に投資するのではなく、NISAの年間投資枠を活用し、2〜3年かけて「育てる資金」を特定口座からNISA口座へと移していくことで、非課税メリットを最大限に享受する戦略が有効です。
-11.png)
-11.png)
ケース2:50代・退職前
【状況】
- 年収750万円
- 子どもは独立済み
- 住宅ローン残債500万円(完済まであと5年)
- 退職金は約1,500万円の見込み
50代は、資産運用において「増やす」から「守りながら増やす」へと舵を切る、もっとも戦略的な判断が求められる時期です。
このケースでは、手元の1,000万円を、10〜15年後の定年退職と、親の介護という「不確実なイベント」の両方に備えるため、以下の3つの役割に振り分けてみました。
| 主な目的 | 金額 (比率) | 具体的な預け先 | |
| 守る 資金 | もしもの備え | 250万円 (25%) | ・普通預金 ・個人向け国債 |
|---|---|---|---|
| 使う 資金 | 住宅ローンや 退職直後の生活費 | 300万円 (30%) | ・定期預金 ・債券ファンド |
| 育てる 資金 | 夫婦の 老後資金 | 450万円 (45%) | ・バランスファンド (NISA活用) |
この配分のポイント
- 「バランス運用」へのシフトで大負けを防ぐ
-
40代なら株式中心でも暴落から回復する時間がありますが、50代で大きな暴落に遭うと、退職までに資産が戻りきらないリスクがあります。
「育てるお金」も株式100%ではなく、債券などを組み合わせた「バランスファンド」を活用し、着実な成長を目指すのが賢明です。
- 介護やリフォームなど「不確実な支出」を想定する
-
50代は、親の介護や自身の病気、自宅の修繕など、タイミングが読みにくい大型支出が重なりやすい時期です。
「守る」と「備える」を合わせて資産の半分以上(550万円)確保しておくことで、想定外の出費にも慌てず対応できます。
- 退職後の生活に向けた「出口戦略」の準備
-
住宅ローンの完済(このケースでは5年後)が見えてきたら、それまで返済に充てていた資金をそのまま投資に回すなど、ラストスパートが可能です。
また、退職金の受け取り方やiDeCoの出口戦略など、「どう受け取るか」のシミュレーションを始めるのもこの時期の重要なタスクです。
ケース3:60代・退職金受取後
【状況】
- 退職金2,000万円を受け取り、うち1,000万円を運用に回したい。
- 年金と合わせて生活費を賄いつつ、資産寿命を延ばしたい。
- 子ども独立済み
- 住宅ローン完済済み
60代は、これまでの「積み立てる時期」から、資産を「計画的に使う時期」へと移り変わる人生の大きな転換期です。
このケースでは、退職金のうち1,000万円を、セカンドライフを安心して楽しむために、「いつ、どのようにお金が必要か」という視点から、以下の3つの役割に振り分けてみました。
【ポートフォリオ例】
| 主な目的 | 金額 (比率) | 具体的な預け先 | |
| 守る 資金 | 医療費・ 介護費用など | 300万円 (30%) | ・普通預金 ・個人向け国債 |
|---|---|---|---|
| 使う 資金 | 日々の生活費 の補填 | 400万円 (40%) | ・高配当株ファンド ・債券ファンド |
| 育てる 資金 | 夫婦の 老後資金 | 300万円 (30%) | ・バランスファンド |
この配分のポイント
- 「守るお金」を厚くして精神的なゆとりを
-
現役時代よりも収入が限られるため、急な入院や自宅の修繕に備える「守るお金」を全体の30%と多めに設定しています。
いつでも引き出せる現金が手元にあることで、心穏やかに毎日を過ごすことができます。
- 「使うお金」は資産の寿命を延ばす工夫を
-
年金だけでは足りない生活費を補うための資金は、大きな変動を避けるのが鉄則です。
債券や安定型のファンドをメインに据えることで、資産を急激に減らすことなく、少しずつ切り崩していく「資産の延命」を図ります。
- 「育てるお金」でインフレに備える
-
「もう60代だから投資は不要」と思われがちですが、人生100年時代ではまだ30年以上あります。
物価の上昇(インフレ)でお金の価値が下がるのを防ぐため、一部は「全世界株式」などで運用を続け、将来の購買力を守ります。
【補足】退職後の資産取り崩し方法は3つ
退職後の資産取り崩しには、主に3つの方法があります。
それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選びましょう。
| 方法 | 特徴・メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| 定額取り崩し | 毎月一定額を引き出します(例:毎月10万円)。 生活費の計画が立てやすいです。 | 市場下落時に多く売却してしまい、資産寿命が読みにくくなります。 |
| 定率取り崩し | 資産残高の一定割合を引き出します(例:毎年4%)。 資産寿命を延ばしやすいです。 | 引き出し額が変動します。市場下落時は収入も減ります。 |
| バケット戦略 | 短期・中期・長期の3つに分けて管理します。 用途別に運用方法を最適化できます。 | 管理がやや複雑で、定期的なリバランスが必要です。 |
1,000万円は一括投資すべき?分割すべき?判断基準を解説
1,000万円を運用する際、最も悩むのが「一括で投資するか、分割して投資するか」という問題だ。
この問いに対する答えは、実は「どちらが正解」というものではない。
理論上は「一括投資」が有利だが・・・
統計的に見ると、一括投資の方が期待リターンは高い。
なぜなら、市場は長期的には右肩上がりの傾向があり、早く市場に資金を投入するほど、複利効果を長く享受できるからだ。
バンガード社の研究によると、過去のデータでは一括投資が分割投資(ドルコスト平均法)を上回るケースが約3分の2を占めていた。つまり、「できるだけ早く投資した方が有利」というのが理論上の結論だ。
しかし、これはあくまで「途中で売却しなければ」という前提の話である。
1,000万円を一括投資した直後に20%の暴落が来たら、200万円の含み損を抱えることになる。多くの人は「このまま持ち続けて大丈夫か」と不安になり、損切りしてしまうのだ。
【一括投資が向く人・分割投資が向く人】
| 一括投資が向く人 |
|---|
| 投資経験があり、暴落時も売却しない自信がある この1,000万円以外にも十分な資産がある 10年以上の長期投資を確実に継続できる 市場タイミングを計ることに興味がない 相場の上げ下げに一喜一憂しない性格 |
| 分割投資が向く人 |
|---|
| 投資初心者、または大きな損失に耐えられない この1,000万円が資産の大部分を占める 数年後に使う可能性のあるお金が含まれる 心理的な安心感を重視したい 投資のニュースを見ると不安になりやすい |
迷ったら「12〜24ヶ月で分けて投資」がおすすめ
迷う人には、1,000万円を12〜24ヶ月に分けて投入する方法をおすすめする。
毎月40〜80万円程度を定期的に投資することで、高値で買いすぎるリスクを軽減できる。
これは「時間分散」と呼ばれる手法で、一括投資のリターン効率と、分割投資の心理的安心感のバランスを取ったアプローチだ。
【具体例】1,000万円を18ヶ月で分割投入する場合
- 毎月約55万円を投資信託の積立設定(証券口座で自動設定可能)
- 投資先:全世界株式インデックス(NISA枠を優先活用)
- 残りの資金は普通預金で待機(または個人向け国債)
- 18ヶ月後、すべての資金が投資完了
この方法なら、「投入完了前に市場が上がりすぎる」リスクと、「投入直後に暴落する」リスクの両方をある程度軽減できる。
暴落時にやってはいけない5つのNG行動
分割投入の途中、あるいは投資開始後に市場が急落した場合、以下の行動は絶対に避けるべきだ。
- 積立を止める
暴落時こそ「安く買える」タイミング。感情に流されず、積立は継続すべきだ。 - 慌てて売却する
売却した瞬間に損失が確定する。長期投資なら回復を待つのが基本。 - 待機資金を一気に投入する
「今が底だ」と思っても、さらに下がる可能性はある。ルール通りの積立を継続しよう。 - SNSやニュースに振り回される
暴落時は悲観的な情報が溢れる。感情的な判断は禁物だ。 - 投資先を頻繁に変える
「この商品はダメだ」と乗り換えを繰り返すと、手数料がかさみ、タイミングも悪化する。



一括投資と分割投資の優劣は、理論と心理の両面から考える必要があります。統計的には一括投資が有利ですが、暴落時に売却してしまえば意味がありません。
「自分が継続できる方法」を選ぶことが、最終的なリターンを最大化する秘訣です。
迷ったら、12〜24ヶ月の分割投入から始めてみてください。
1,000万円の運用先を選ぶ3つのポイント
投資信託だけでも数千本以上あり、すべてを比較するのは現実的ではない。
だからこそ、「どの視点で絞り込むか」という判断軸を持つことが重要だ。
押さえるべきポイントは3つだけ。①手数料、②分散の度合い、③リバランスのしやすさだ。この3つを基準にすれば、自分に合った商品を効率よく選べるようになる。
ポイント①:手数料(信託報酬)は年0.3%以下を目安に
1,000万円を運用する場合、手数料の差は無視できない。
年0.1%の差でも、10年間で約10万円、30年間で約30万円以上の差が生まれる。しかも複利効果により、運用期間が長くなるほど差は広がっていく。
投資信託にかかる主な手数料は以下の3つだ。
| 手数料の種類 | 目安 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 信託報酬 (年率) | インデックス型:0.1〜0.3%以下 アクティブ型:1.0〜1.5%程度 | 長期運用なら低コストのインデックス型が有利 |
| 購入時手数料 | 0%(ノーロード)が基本 | ネット証券なら無料が主流。銀行窓口は要確認 |
| 信託財産留保額 | 0〜0.3%程度 | 解約時にかかる費用。長期保有なら影響は小さい |
特に重要なのは「信託報酬」だ。これは保有している間ずっとかかり続ける費用で、運用成績に直接影響する。
商品を選ぶ際は、信託報酬が年0.3%以下かどうかをまずチェックしよう。
最近は年0.1%を切る超低コスト商品も登場しており、0.1〜0.2%台であれば十分に優良と言える。逆に1%を超える商品は、よほどの理由がない限り避けた方が無難だ。
ポイント②:地域・資産・通貨を分散させる
「卵は一つのカゴに盛るな」という投資格言の通り、分散投資はリスク管理の基本だ。
分散には3つの軸がある。
- 【地域の分散】
-
日本だけでなく、米国・欧州・新興国など世界中に投資する。
特定の国の経済が低迷しても、他の国がカバーしてくれる可能性がある。
- 【資産の分散】
-
株式・債券・不動産(REIT)・金など、異なる値動きをする資産を組み合わせる。
株式が下落しても債券が上昇するなど、全体の値動きを安定させる効果が期待できる。
- 【通貨の分散】
-
円建てだけでなく、ドル建て資産も保有する。
円安になれば外貨資産の価値が上がり、円高になれば円資産の価値が相対的に上がる。どちらに転んでも対応できる体制を作れる。
全世界株式インデックスファンドなら、世界約50カ国、数千銘柄への分散投資が自動的に行われる。
「何を買えばいいかわからない」という初心者には、まずこの1本から始めることをおすすめする。
ポイント③:定期的な見直し(リバランス)がしやすいか
長期運用では、定期的に資産配分を元に戻す「リバランス」が必要だ。
例えば、株式50%・債券50%の配分でスタートしても、株価が上昇すると株式の比率が60%、70%と高くなっていく。これを放置すると、当初想定よりもリスクの高いポートフォリオになってしまう。
リバランスのしやすさを考えると、以下の点が重要になる。
- 売買手数料が安い(または無料)こと
- 少額から売買できること(100円単位など)
- 保有商品の値動きが把握しやすいこと
- リバランスの頻度は年1回程度で十分
バランスファンド(株式と債券が自動でリバランスされる商品)を活用すれば、自分でリバランスする手間も省ける。
「8資産均等型」や「株式50%・債券50%」などのバランスファンドは、手間をかけたくない人に適している。
1,000万円のおすすめ運用先を目的別に紹介
商品選びの3つのポイントを押さえたところで、次は具体的な運用先を見ていこう。
「守る・増やす・備える」の目的ごとに、適した商品タイプを整理した。
【守る資産】元本重視の運用先
「守る資金」には、元本割れリスクを極力避けた安全性の高い商品を選ぼう。
| 商品 | 特徴 | 期待利回り |
|---|---|---|
| 普通預金 | いつでも引き出せる流動性が最大のメリット ペイオフで1,000万円まで保護される | 年0.001〜0.1% |
| 個人向け国債 (変動10年) | 国が発行、最低金利0.05%保証 1年経過後は中途換金可能 金利上昇局面で有利 | 年0.05〜0.5% |
| 定期預金 | 一定期間預け入れで普通預金より高金利 中途解約でペナルティあり | 年0.02〜0.3% |
個人向け国債は財務省が発行しており、国が破綻しない限り元本が保証される。
特に「変動10年」は金利上昇局面で有利で、最低金利0.05%も保証されているため、銀行の普通預金より有利な場合が多い。1万円から購入でき、発行から1年経過すれば中途換金も可能だ。
【使う資産】安定収入重視の運用先
「使う資金」には、値動きが穏やかで、定期的な収入も期待できる商品を選ぶ。
| 商品 | 特徴 | 期待利回り |
|---|---|---|
| 債券ファンド | 国内外の債券に分散投資 株式より値動きが穏やか 金利上昇局面では価格が下落するリスクあり | 年1〜3% |
| 高配当株 ファンド | 配当利回りの高い株式に投資 定期的な配当収入 株式なので値動きは債券より大きい | 年3〜5% |
| REIT (不動産投信) | 不動産に間接投資 株式・債券と異なる値動きで分散効果 金利上昇や景気後退で下落リスクあり | 年3〜5% |
| バランス ファンド | 株式・債券を自動配分 リバランス不要で手間なし 「8資産均等」「株式50債券50」など多様 | 年2〜5% |
数年後に使う予定のあるお金は、株式100%では変動リスクが高すぎる。
債券ファンドやバランスファンドを活用して、安定性と成長性のバランスを取ろう。使う時期が近づいてきたら、徐々に債券や預金の比率を高めていくのがセオリーだ。
【育てる資産】成長重視の運用先
「育てる資金」には、長期的な成長が期待できる株式中心の商品を選ぼう。
| 商品 | 特徴 | 期待利回り |
|---|---|---|
| 全世界株式 インデックス | 世界中の株式に分散投資 長期の資産形成の王道 1本で数千銘柄に投資できる手軽さが魅力 | 年5〜7% (長期平均) |
| 米国株式 インデックス | 世界最大の経済大国・米国に集中投資 成長性は高いが、米国一国への集中リスクも | 年6〜8% (長期平均) |
| 個別株式 | 個別企業の成長に投資 配当や株主優待も魅力 銘柄選定に知識・時間が必要 | 銘柄による |
「育てる資金」の中心は、低コストのインデックスファンドだ。信託報酬0.1%前後の商品を選び、NISAを活用して非課税で運用しよう。
初心者は「全世界株式」1本から始め、慣れてきたら米国株式や新興国株式を加えるのも良い。
【上級者向け】外貨建て債券・実物不動産の注意点
外貨建て債券は高い金利が魅力だが、為替リスクを常に伴う。
例えば、米ドル建て債券で年5%の利息を受け取っても、円高が10%進めば、円換算では損失になってしまう。購入時より円高が進むと、高い利息を受け取っても、元本割れする可能性があるのだ。
実物不動産投資は、うまくいけば高い利回りが期待できるが、物件選定・管理・修繕・空室対策など、専門的な知識と手間が必要だ。
「不動産投資で年利10%」といった情報を見かけることもあるが、これは空室リスクや修繕費用、管理費用などを考慮しない「表面利回り」であることが多い。実質利回りはもっと低くなるケースがほとんどだ。
これらの商品は、投資経験を積み、リスクを十分に理解した上で検討することをおすすめする。
1,000万円を運用するならNISA・iDeCoを最大活用しよう
「NISAとiDeCo、どっちを優先すべき?」「両方やるべき?」——これは資産運用を始める人が必ずぶつかる疑問だ。
結論から言えば、1,000万円を運用するなら両方の活用を検討すべきである。
ただし、それぞれ特徴が異なるため、自分に合った使い分けが重要になる。
新NISAの仕組み
2024年から始まった新NISAでは、年間最大360万円、生涯で1,800万円までの投資枠が非課税となる。
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 年間投資上限 | 120万円 | 240万円 |
| 対象商品 | 積立向け投資信託 | 株式・投資信託・ETF等 |
| 非課税保有 限度額 | 1,800万円 (うち成長投資枠1,200万円) | |
| 非課税期間 | 無期限 | 無期限 |
活用のポイント
1,000万円を運用する場合、約3〜5年でNISA枠を使い切るペースで投資するのが効率的。
つみたて投資枠と成長投資枠を両方活用し、年間360万円のフル活用を目指そう。
iDeCoの仕組み
iDeCoは、掛金が全額所得控除になる点が最大のメリットだ。
ただし、原則60歳まで引き出せないため、老後資金として割り切れる金額のみを拠出しよう。
| 加入者区分 | 現行上限(月額) | 2026年12月〜(予定) |
|---|---|---|
| 会社員 (企業年金なし) | 2.3万円 | 6.2万円 |
| 会社員 (企業年金あり) | 1.2〜2万円 | 企業型との合算で6.2万円 |
| 公務員 | 1.2万円 | 6.2万円 |
| 自営業・ フリーランス | 6.8万円 | 7.5万円 |
| 専業主婦(夫) | 2.3万円 | 6.2万円 |
2026年12月の制度改正で、多くの加入者区分で上限が引き上げられる予定だ。
改正後は、NISAとiDeCoを合わせて年間500万円以上の非課税投資も可能になる。
NISAとiDeCoはどちらを優先すべき?
結論から言えば、多くの人には「NISA優先」をおすすめする。理由は以下の通りだ。
- 流動性
-
NISAはいつでも引き出せるが、iDeCoは原則60歳まで引き出せない
- 非課税枠
-
NISAは年間360万円、iDeCoは年間27.6万円(会社員の場合)と、NISAの方が大きい
- 商品選択
-
NISAは幅広い商品から選べるが、iDeCoは金融機関ごとに商品が限定される
ただし、所得税率が高い人(年収800万円以上など)は、iDeCoの所得控除メリットが大きいため、両方の活用を検討しよう。
「60歳まで絶対に使わない」と割り切れる金額をiDeCoに、それ以外をNISAに振り分けるのが基本戦略だ。
30代〜60代の年代別おすすめ活用法
- 【30〜40代】資産最大化期
-
NISAを優先的にフル活用(年間360万円)し、余力があればiDeCoも上限まで。
運用は株式中心で積極的にリターンを狙う。時間を最大の味方につける時期だ。
- 【50代】リタイア準備期
-
iDeCoの所得控除メリットを最大限活用。
NISAでは株式と債券のバランスを取り、徐々に安定運用へシフト。
退職金の受け取り方(一時金 or 年金)も考慮してiDeCoの出口戦略を検討。
- 【60代以降】取り崩し期
-
iDeCoは受取開始(一時金または年金)。
NISAは「増やす」から「取り崩しながら運用する」フェーズへ。
高配当株ファンドや債券ファンドで安定収入を非課税で受け取る。



特に1,000万円規模の資産がある場合、非課税制度を活用することで複利効果を最大限に引き出せます。
NISAは引き出し自由、iDeCoは60歳まで拘束という違いを理解し、ライフプランに合わせて使い分けることが重要です。
1,000万円を投資すると資産はどのくらい増える?運用シミュレーション
1,000万円を運用すると、実際にどのくらい資産が増えるのか。
利回り別にシミュレーションを見てみよう。
| 利回り | 10年後 | 20年後 | 30年後 |
|---|---|---|---|
| 年3% (安定型) | 約1,344万円 | 約1,806万円 | 約2,427万円 |
| 年5% (バランス型) | 約1,629万円 | 約2,653万円 | 約4,322万円 |
| 年7% (積極型) | 約1,967万円 | 約3,870万円 | 約7,612万円 |
- 出典:三菱UFJアセットマネジメント「一括投資シミュレーション」を参考に算出
年7%で30年運用すれば、1,000万円が約7,600万円になる計算だ。
これが「複利の力」である。ただし、この数字を鵜呑みにしてはいけない。
シミュレーションを見る際のチェックポイント
- 手数料は考慮されているか
信託報酬を差し引いた「実質リターン」で考える - 税金は考慮されているか
NISA外の運用では、利益に約20%の税金がかかる - 為替変動は考慮されているか
外国資産への投資では、円高で目減りする可能性 - 過去の実績は将来を保証しない
年7%は過去の平均であり、今後も同じとは限らない
弊社調査※によると、運用時に目標にしている利回りは「2〜4%未満」が44.0%で最多であった。
まずは年3%程度の安定運用を目指し、経験を積んでから徐々にリスクを取っていくのが現実的だ。
- 対象:資産1,000万円以上を運用する投資家100名、2024年実施)
1,000万円の運用で効率的に資産を増やすなら「資産運用ナビ」で専門家に相談しよう
ここまで、1,000万円での運用方法や運用の際の注意点などを解説してきたが、「自分に適した金融商品がどんなものが判断できない」「ポートフォリオの見直しを定期的に行う自信がない」など、不安に感じている方も少なくないだろう。
結論から言うと、1,000万円での資産運用を始める場合は、資産運用の専門家に相談しながら進めていくのがおすすめだ。
ここでは、資産運用を専門家に相談すべき理由や、相談先の見つけ方について紹介する。
資産運用についてプロに相談した方がいい人の特徴
資産運用の専門家への相談は、全員に必要なわけではない。
以下のチェックリストで、あなたが相談すべきかどうかを判断してみよう。
【専門家に相談した方がいい5つのパターン】
- 退職金や相続で、まとまったお金が入ったばかり
- 投資経験がほとんどなく、何から始めればいいかわからない
- 自分に合った資産配分(ポートフォリオ)がわからない
- NISA・iDeCoをどう使い分ければいいか迷っている
- 市場の急変時や、ライフプランの変更時に、どうすればいいか判断できない
これらに1つでも当てはまる場合、専門家のアドバイスを受けることで、感情的な判断や情報不足による失敗を避けやすくなる。
資産運用の相談先4選
資産運用の相談先としては、銀行、証券会社、FP(ファイナンシャルプランナー)、IFA(独立系金融アドバイザー)など、さまざまな選択肢がある。
それぞれ特徴が異なるため、自分に合った相談先を選ぶことが重要だ。
| 相談先 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 銀行 | 身近で相談しやすい。 預金や保険も一緒に相談可能 | 既存の取引がある人 総合的な相談をしたい人 |
| 証券会社 | 株式・投資信託の品揃えが豊富。 情報提供も充実 | 株式投資を中心に考えている人 |
| FP | ライフプラン全体の設計が得意。 保険見直しも相談可能 | 家計全体を見直したい人 |
| IFA | 特定の金融機関に属さない中立的な立場。 転勤がなく長期サポート | 中立的なアドバイスを求める人 長期的な関係を築きたい人 |
「資産運用ナビ」であなたにぴったりの相談先を探してみよう
「銀行、証券会社、FP、IFA……結局どこに相談すればいいの?」
それぞれ得意分野や報酬体系が異なるため、自分に最適な相談先を見極めるのは簡単ではない。そこで活用したいのが、無料で相談先を診断・検索できる「資産運用ナビ」だ。
使い方はシンプル。年齢、金融資産、相談したい内容などを入力するだけで、あなたの希望にマッチするアドバイザーが一覧で表示される。
【資産運用ナビで事前に確認できること】
- 得意分野(株式・投資信託・不動産・保険・相続対策など)
- 経歴・保有資格(FP・証券アナリスト・CFPなど)
- 相談実績・利用者の声
- 対面・オンラインの対応可否
- 報酬体系(相談料・仲介手数料など)
面談を申し込む前にプロフィールをじっくり確認できるため、「相談してみたら合わなかった」というミスマッチを防げる。
診断・検索から面談申し込みまで、利用料はすべて無料。
まずは気軽に、自分に合った相談先を探してみよう。
1,000万円の運用はプロに相談して計画的に行おう
1,000万円の運用を成功させるポイントを振り返ろう。
- 「3つの財布」で目的別に分ける
守る・育てる・使う、それぞれに最適な運用を行うことで、感情的な判断を避けられる - 一括か分割かは「自分が続けられる方」を選ぶ
理論より継続性を重視。迷ったら12〜24ヶ月の分割投入から - 商品は「手数料・分散・リバランス」の3軸で選ぶ
銘柄名より判断基準を持つことが重要 - NISA・iDeCoを最大限活用する
非課税の恩恵は長期で数百万円の差になる - 迷ったら専門家に相談する
感情的な判断を避け、長期的な運用を継続するための最大のサポート
資産運用は「始める前の設計」で9割が決まると言っても過言ではない。逆に言えば、最初にしっかりと計画を立てれば、その後は「計画通りに継続する」だけで良いのだ。
この記事を参考に、あなたに合った運用計画を立て、着実に資産を育てていこう。
迷ったときは、「資産運用ナビ」であなたに合った専門家を探し、一歩を踏み出してほしい。



1,000万円規模の資産があれば、目標や期間に応じて複数の戦略を組み合わせる分散運用が可能です。
計画的な配分設計と継続的な見直しを行うことで、安定した資産形成が実現しやすくなります。早めの準備が成功の鍵です。
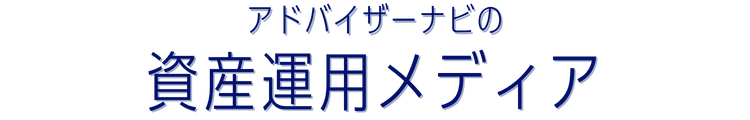
-1-4.png)