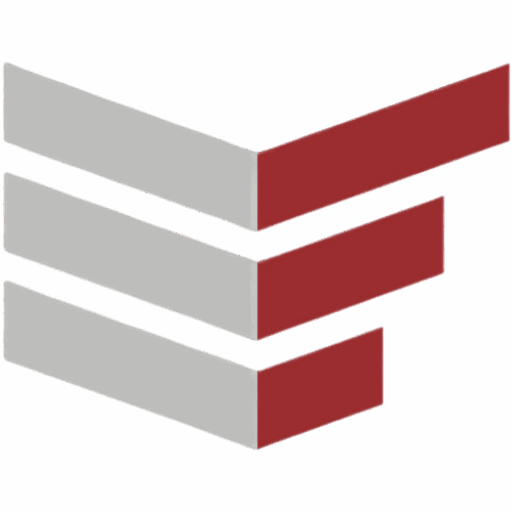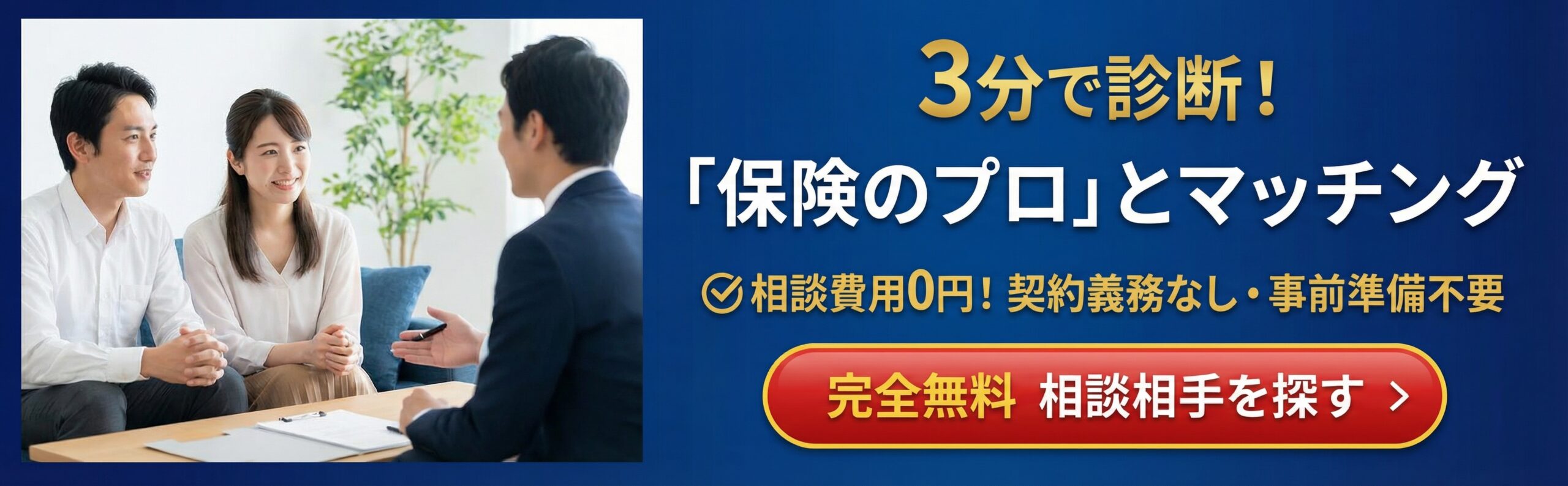- 60代の医療保険は商品名ではなく「判断軸」で候補を絞るのが近道である。
- 公的保障の上限(標準報酬月額28〜50万円なら月80,100円+α)や対象外費用を把握すれば、必要な保障額を逆算できる。
- 以下で費用・比較軸・逆算・持病対応・見直し手順を整理する。
60代で医療保険を見直そうとすると、「結局どの商品がいいのか」で手が止まる。
商品名を並べたランキングでは自分に合うかどうかが判断できない。
カギを握るのは、判断軸を先に固定することだ。公的保障の自己負担上限は所得区分によって異なり、たとえば標準報酬月額28〜50万円なら月80,100円+αが目安となる。
以下では、費用の実態から比較軸、公的保障の逆算、持病対応、見直し手順まで順を追って整理していく。
60代の医療保険おすすめの結論
60代の医療保険選びで最初に決めるべきは、「終身か定期か」という保障期間の軸である。商品名を比較する前に、自分がどのタイプに当てはまるかを先に整理すると、候補がぐっと絞りやすくなる。
おすすめの基本形は終身が多い
60代から医療保険を検討する場合、終身型が選ばれやすい傾向にある。理由はシンプルで、定期型(更新型)だと更新のたびに保険料が上がり、70代・80代で負担が読みにくくなるからだ。終身型であれば、契約時の保険料が生涯変わらない設計が多く、年金生活に入っても固定費として管理しやすい。
60代の目的別おすすめ3パターン
「おすすめ」は一律ではない。貯蓄の余力、家族への負担の考え方、治療への不安の度合いによって、厚くすべき保障と削ってよい保障が変わる。大きく分けると次の3パターンで整理できる。
| タイプ | 優先する保障 | 削る候補 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 貯蓄少なめ型 | 入院日額・一時金 | 先進医療特約(検討) | 公的保障の上限を先に確認 |
| 貯蓄多め型 | 最低限の入院保障 | 日額上乗せ・特約全般 | 保険より貯蓄で賄う範囲を明確に |
| 家族負担が不安型 | 一時金・請求しやすさ | 長期入院向け保障 | 請求導線を家族と共有 |
どのタイプかを判定するには、「入院したとき貯蓄で数十万円を出せるか」「家族が請求手続きできる状態か」を自問してみるとわかりやすい。
医療保険・医療特約は民保加入世帯ベースで世帯加入率95.1%、世帯主90.0%という高い水準にある。すでに何らかの保障を持っている前提で点検を始めるのが現実的だ。重複があれば削り、不足があれば補う——この順番で進めるとスムーズだ。
おすすめできない契約例
逆に、後悔しやすい契約パターンも押さえておきたい。典型的なのは次の3つである。
- 特約を盛りすぎて月々の保険料が家計を圧迫している
- 既存の保険と保障内容が重複しているのに気づいていない
- 更新型で契約し、70代以降の保険料上昇を想定していない
加入率が高いということは、すでに持っている保障との重複が起きやすいということでもある。新しく入る前に、まず手元の証券を確認し、主契約と特約を一覧化するステップを挟むと失敗を減らせる。
では、具体的にどんな費用に備えればいいのか——次章で見ていく。
60代の医療保険で不足しがちな費用
医療保険で備えるべき費用は、公的保障でカバーされない部分である。高額療養費制度があるため医療費そのものには上限がある。問題は、その上限に含まれない出費だ。
入院で増える自己負担と雑費
入院すると、医療費以外の支出が積み上がる。生命保険文化センターの調査(2025年度速報)によると、入院時の自己負担費用は1日当たり平均24,300円とされている。この数字には医療費だけでなく、食費や日用品、家族の交通費なども含まれる。
平均在院日数は一般病床で15.5日だが、療養病床になると117.4日と長期化する可能性がある(令和6年統計)。入院が長引けば、日額ベースの負担はさらに膨らむ。
特に見落としやすいのが、食費と差額ベッド代だ。入院の食費は自己負担になり、一般の標準負担額は1食510円(令和7年4月〜)である。1日3食で1,530円、30日入院すれば約4万5,000円になる計算だ。
差額ベッド代は保険外で、1人室の平均徴収額(推計)は1日8,625円(令和6年8月1日現在)。2人室でも3,149円かかる。希望しなくても病室の空き状況で個室になるケースもあり、事前の確認が欠かせない。
通院・在宅医療の費用
退院後も費用は続く。通院や薬代は「継続費」として家計に残り続ける。家計調査では、65歳以上の無職世帯で保健医療費が月平均18,383円(夫婦)・8,640円(単身)と示されている(2024年統計)。これは入院していない平時の数字であり、治療中であればさらに増える可能性がある。
先進医療・自由診療の扱い
先進医療は、保険診療と併用できる一方で技術料は全額自己負担になる。厚生労働省の実績報告によると、先進医療の患者数は211,153人、総金額は約1,084億円で、そのうち先進医療等(技術料等)の総額は約127億円、割合は11.7%となっている(令和6年7月〜令和7年6月)。
先進医療特約の世帯加入率は54.0%(民保加入世帯ベース)とされ、半数以上が付帯している状況だ。ただし、先進医療と自由診療は別物である。先進医療特約は厚生労働省が定めた技術が対象であり、自由診療すべてをカバーするわけではない。約款で「対象範囲」と「付け外しの可否」を確認してから判断したい。
介護費用は医療保険外が多い
入院から介護へ移行するケースも60代以降は想定しておきたい。ただし、介護費用は医療保険の守備範囲外であることが多い。生命保険文化センターの調査によると、介護の自己負担は一時費用平均47.2万円、月々費用平均9.0万円で、在宅5.3万円、施設13.8万円と水準が分かれる(2024年度調査)。
不足しがちな費用は把握できた。では、どの保険を選ぶか——比較のポイントを見ていこう。
医療保険(60代)の比較ポイント5つ
医療保険を比較するときは、同じ条件で横並びにできる「比較軸」を先に固定する。商品ごとに用語の定義が異なり、軸を揃えないと比較事故が起きるからだ。
入院日額と支払限度日数
入院日額は、公的保障でカバーされない費用を埋める役割として位置づける。高額療養費制度があるため医療費そのものには上限があるが、食費や差額ベッド代は対象外だ。これらを日額で補填する発想である。
支払限度日数は、長期入院リスクに対応するパラメータだ。60日型、120日型、無制限などの設定があり、入院が長引いた場合に給付が打ち切られるタイミングが変わる。平均在院日数は一般病床で15.5日だが、これはあくまで平均であり、疾患によっては長期化する。限度日数は「平均」ではなく「自分が許容できるリスク」で選ぶ。
手術給付金の対象と倍率
手術給付金は、対象となる手術の定義が商品によって異なる。公的保険の診療報酬点数に連動するタイプと、保険会社独自の分類で対象を定めるタイプがあり、同じ手術でもA社では給付対象、B社では対象外というケースがあり得る。
高額療養費制度があるため、手術費用そのものの自己負担には上限がある。70歳未満で標準報酬月額28〜50万円の区分なら、月の上限は80,100円+(医療費-267,000円)×1%だ。手術給付金だけで「元を取る」という発想より、食費や差額ベッド代など対象外費用の穴埋めとして位置づけるほうが現実的である。
通院保障と一時金の有無
通院保障は、支払条件の狭さを先に確認してから要否を判断する。「入院後の通院のみ対象」「退院後180日以内」「30日限度」など、条件が細かく設定されていることが多い。条件に合わなければ給付されない。自分の想定する治療パターンに当てはまるか、先に確認しておきたい。
一時金は、入院や診断時にまとまった金額が支払われる仕組みだ。初期費用の穴埋めとして使い勝手がよく、日額と組み合わせて設計するケースもある。請求もシンプルなため、家族が手続きする場面を想定すると負担が軽い選択肢といえる。
先進医療特約と上限額
先進医療特約を付けるかどうかは、付帯率も参考にしつつ最終的には自分のリスク許容度で決める。先進医療特約の世帯加入率は54.0%で、半数以上が付帯している状況だ。先進医療の実績としては、患者数211,153人、先進医療等の総額約127億円という規模感である。
比較する際は、上限額の条件を揃える必要がある。「通算2,000万円」と「1回の治療につき○万円」では意味が違う。対象となる技術は厚生労働省の告示で変わるため、約款で「告示に準じる」旨が明記されているかも見ておくとよい。
保険料と払込期間・更新
60代は退職前後の収入変化が大きい時期だ。保険料は「今払えるか」だけでなく「年金生活でも払い続けられるか」で判断したい。世帯の年間払込保険料は平均35.3万円とされ、医療保険単体ではないものの、保険全体の固定費として無視できない水準だ(2024年度調査)。
比較軸は固まった。次のステップは、公的保障から逆算して「いくら必要か」を出すことだ。
60代の医療保険は公的保障から逆算
医療保険の必要保障額は、公的保障の上限を確認してから逆算するのが基本である。高額療養費制度を知らずに保険を設計すると、過剰な保障に保険料を払い続けることになりかねない。
高額療養費制度を先に確認
高額療養費制度は、1カ月の医療費自己負担に上限を設ける仕組みだ。70歳未満の場合、所得区分によって上限が5段階に分かれる。
| 所得区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額(月) |
|---|---|---|
| 区分ア | 83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 区分イ | 53〜79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 区分ウ | 28〜50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 区分エ | 26万円以下 | 57,600円 |
| 区分オ | 住民税非課税 | 35,400円 |
自分の所得区分がどこに当たるかは、健康保険証や給与明細で標準報酬月額を確認すればわかる。退職後に国民健康保険に切り替わると区分が変わる可能性があるため、加入している健康保険の窓口で確認しておくと確実だ。
70歳以上になると仕組みが変わる。一般区分では外来の上限が18,000円(年間上限144,000円)、外来+入院の上限が57,600円(多数回44,400円)となる。60代後半で契約を検討する場合は、70歳到達後の変化も視野に入れておきたい。
自己負担の目安を出す手順
高額療養費の上限はあくまで「医療費」の上限であり、対象外の費用は別に積み上がる。逆算の手順は次のとおりだ。
- 自分の所得区分で高額療養費の上限を確認する
- 食費(1食510円×3食×日数)を加算する
- 差額ベッド代(1人室なら1日8,625円が平均)を加算する
- 日用品・家族の交通費など雑費を見積もる
- 合計から貯蓄で賄う分を引き、残りを保険で備える
入院時の自己負担費用は1日当たり平均24,300円という調査結果があるが、これはあくまで平均だ。個室を希望するか、入院日数がどれくらいになるかで大きく変わる。平均値をそのまま当てはめるのではなく、自分の条件で計算し直す必要がある。
貯蓄がある人の医療保険設計
貯蓄に余裕がある場合、保険で備える範囲を絞り込める。たとえば「入院しても100万円までは貯蓄で出せる」と決めれば、その範囲を超えるリスク——長期入院や先進医療——に限定して保険を設計できる。
貯蓄が少なければ、日額や一時金を厚くして初期費用に備える設計となる。どちらが正解ということではなく、「貯蓄で賄う範囲」と「保険で備える範囲」の境界線を自分で引くことが設計のポイントになる。
医療保険・医療特約の加入率は高く、すでに何らかの保障を持っている人が多い。新規で入る前に、既契約の棚卸しをして重複と空白を同時に確認するステップを挟むと、無駄な保険料を払わずに済む。
ここからは持病がある場合の選び分けを扱う。
持病がある60代の医療保険の選び分け
通常型→緩和型の申し込み順
持病がある場合でも、まずは通常型(標準型)の医療保険に申し込むのが原則だ。理由は、通常型のほうが保険料が安く、保障内容も充実しているケースが多いからだ。告知内容によっては通常型で引き受けられることもあるため、最初から緩和型を選ぶと機会損失になり得る。
通常型で引き受け不可となった場合に、次の選択肢として引受基準緩和型を検討する。緩和型は告知項目が少なく加入しやすいが、保険料が割高だったり、契約から一定期間は給付が削減されたりする条件がつくことが多い。
告知・健康診断で見られやすい点
告知は事実ベースで記入するのが鉄則。推測や記憶で書くとミスが起きやすい。お薬手帳、健康診断の結果、診療明細など、手元の資料を見ながら正確に記入する。
見られやすいポイントは、過去5年以内の入院・手術歴、現在の投薬状況、健康診断での指摘事項など。不明点があれば医療機関に確認し、推測で書かない。告知内容に誤りがあると、いざ給付を請求する段階で問題になる可能性がある。
引受基準緩和型の注意点
緩和型は加入しやすい反面、条件をよく確認してから選ぶ必要がある。チェックすべき項目は次のとおりだ。
- 契約から○カ月間は給付金が削減される条件があるか
- 特定の疾病や部位が免責(対象外)になっていないか
- 保険料は通常型と比べてどれくらい割高か
- 更新や払込期間の条件はどうなっているか
緩和型であっても、公的保障で足りる部分まで盛り込む必要はない。高額療養費制度で医療費には上限があることを踏まえ、対象外費用の補完に徹する設計でよい。
無選択型は最終手段
無選択型は告知なしで加入できるが、保険料が最も高く、保障内容も限定的になりがちだ。通常型も緩和型も難しい場合の最終手段として位置づけるのが妥当である。
加入できたとしても、不足分が埋まるかを逆算で確認しておきたい。保険料に対して給付が見合わないと感じるなら、保険ではなく貯蓄で備える選択肢も検討に値する。
持病がある場合の選択肢は以上。続いて、保険料を抑えるコツを見ていく。
60代の医療保険の保険料を抑えるコツ
保険料を抑えるには、削る順番を間違えないこと。必要な保障まで削ると本末転倒になる。公的保障で足りる部分から順に削っていく。
保険料を下げる削る順番
削る順番は「使わない特約→重複している保障→過大な保障」の順が安全だ。まず、付帯しているが使う見込みが低い特約を外す。次に、既契約と重複している保障を整理する。最後に、公的保障でカバーされる部分を削って日額や限度を調整する。
高額療養費制度があるため、医療費そのものには上限がある。たとえば標準報酬月額28〜50万円なら月80,100円+αが目安だ。この上限を超える部分に備えれば十分であり、上限内の費用まで保険でカバーする必要はない。
払込満了を60代で迎える工夫
払込満了のタイミングは、家計の見通しとセットで決める。60歳や65歳で払込満了にすれば、年金生活に入ってから保険料の負担がなくなる。一方、終身払いにすれば月々の負担は抑えられるが、生涯払い続けることになる。
家計調査では、65歳以上の無職世帯で保健医療費が月平均18,383円(夫婦)・8,640円(単身)とされている。医療費の継続支出がある中で保険料も払い続けるのか、払込満了で固定費を減らすのか——収入と支出のバランスで決める。
掛け捨てと貯蓄型の考え方
医療保険は「備え」が主目的であり、貯蓄目的とは分けて考えたい。貯蓄型の医療保険は解約返戻金や満期金があるが、その分保険料が高くなる。医療リスクへの備えと資産形成は別の手段で行うほうが、目的がぶれにくい。
保険料の考え方はここまで。最後に、見直しの具体的な手順を押さえておこう。
医療保険を60代で見直す手順
現契約の保障を棚卸しする
まず、手元の保険証券を引っ張り出し、主契約と特約を一覧化する。確認すべき項目は、入院日額、支払限度日数、手術給付金の対象、通院保障の有無、先進医療特約の有無、保険料、払込期間、更新の有無。
医療保険・医療特約の加入率は世帯ベースで95.1%と高い。「すでに何か入っている」前提で点検を始め、重複があれば削り、不足があれば補う方針を立てる。棚卸しの段階で不安を煽る必要はなく、事実を可視化することが目的だ。
乗り換えは新契約成立が先
乗り換えを検討する場合、旧契約の解約は新契約の承諾後に行う。これが鉄則だ。新契約に申し込んでも、告知内容や審査結果によっては引き受けられないことがある。旧契約を先に解約してしまうと、新契約が不成立になった場合に無保険状態になる。
二重払いの期間が発生することを恐れて解約を先にしたくなる気持ちはわかる。しかし、数カ月の二重払いと保障の空白期間を天秤にかければ、二重払いのほうがはるかにリスクが低い。
告知ミスを防ぐ準備
新契約の申込み時には、告知を正確に行うための準備が必要だ。用意しておくと安心な資料は次のとおりだ。
- お薬手帳(現在の投薬状況)
- 健康診断の結果(直近のもの)
- 診療明細・領収書(過去の入院・手術歴)
不明点があれば、かかりつけ医や医療機関に確認する。推測で記入すると、後から「告知義務違反」を問われるリスクがある。告知ミスは給付に影響し得る。手間を惜しまず正確に記入しておきたい。
家族に共有する請求の導線
入院や手術をした際に給付金を請求するのは、本人ではなく家族になるケースも多い。請求導線を家族と共有しておくと、請求漏れを防げる。
共有すべき情報は、保険会社の連絡先、証券番号、証券の保管場所、請求に必要な書類の概要だ。すべてを詳細に伝える必要はなく、「ここを見ればわかる」という場所を示しておくだけでも十分。プライバシーに配慮しつつ、最低限の情報を共有しておくと安心だ。
60代の医療保険おすすめFAQ
最後に、よくある疑問をまとめて解消しておこう。
60代は何歳まで加入できる?
加入可能年齢の上限は商品によって異なる。65歳まで、70歳まで、80歳までなど幅がある。候補を比較する際は、「加入可能年齢」を列に加えておく。年齢だけでなく健康状態による条件もあるため、商品ごとに確認が必要だ。
入院日額はいくらが目安?
日額の「正解」は一律には決められない。目安の出し方は、高額療養費の上限+対象外費用(食費・差額ベッド代など)-貯蓄で賄う分=保険で備える分、という逆算だ。
入院時の自己負担費用は1日当たり平均24,300円という調査結果があるが、差額ベッド代の有無や入院日数で大きく変わる。平均をそのまま日額に設定するのではなく、自分の条件で計算し直す必要がある。
先進医療特約は付けるべき?
先進医療特約の要否は、リスク許容度で判断する。先進医療の患者数は211,153人、先進医療等の総額は約127億円という実績がある。世帯加入率は54.0%で、半数以上が付帯している。
ただし、先進医療特約は厚生労働省が定めた先進医療が対象であり、自由診療すべてをカバーするわけではない。「付けておけば安心」ではなく、対象範囲を理解したうえで判断したい。
持病があると入れない?
持病があっても医療保険に入れる可能性はある。通常型で難しい場合は引受基準緩和型、それでも難しい場合は無選択型という順番で選択肢が残っている。まずは通常型で可否を確認し、順番に検討していくのがよい。
医療保険とがん保険は両方必要?
医療保険とがん保険は守備範囲が異なる。医療保険は入院・手術全般をカバーし、がん保険はがんに特化して通院や診断一時金を手厚くしている。両方入ると重複する保障が出てくるため、どの部分が重複しているかを確認し、不要な部分は削るとよい。
加入率が高い以上、すでに何らかの保障を持っている可能性が高い。新しく入る前に既契約を棚卸しし、重複を点検することが先決である。
共済と医療保険はどう違う?
共済と民間の医療保険は、運営主体や仕組みが異なるが、比較軸を揃えれば横並びで検討できる。掛金(保険料)、保障期間、更新の有無、加入条件、割戻金の有無などを列に並べて比較する。
共済は掛金が安い傾向がある一方、保障内容がシンプルで特約の選択肢が少ないことが多い。どちらが優れているということではなく、自分の求める保障に合っているかで判断することになる。
見直しで損しないコツは?
見直しで損しないためのポイントは、保障の空白期間を作らないこと、告知を正確に行うこと、既契約の棚卸しを先にすることの3つだ。旧契約の解約は新契約の承諾後に行い、告知は資料を見ながら正確に記入する。この手順を守れば、大きな失敗は避けられる。
まとめ
60代の医療保険選びは、商品名のランキングではなく「判断軸」を先に固定することで候補が絞りやすくなる。高額療養費制度により医療費には上限があるため、備えるべきは対象外の費用——食費、差額ベッド代、通院の継続費——である。
比較では入院日額、支払限度日数、手術給付金の対象、通院保障、先進医療特約、保険料・払込期間の5軸を揃え、同条件で横並びにする。持病がある場合も通常型→緩和型→無選択型の順で選択肢が残っている。
出典一覧
- 厚生労働省「高額療養費制度について(参考資料)」
- 厚生労働省「入院時の食費・光熱水費について」
- 厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況について」
- 厚生労働省「令和6年 医療施設(動態)調査・病院報告の概況」
- 厚生労働省「令和5年度 国民医療費の概況」
- 厚生労働省「先進医療の実績報告について」
- 生命保険文化センター「生活保障に関する調査(2025年度速報)」
- 生命保険文化センター「介護にかかる費用」
- 生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査(2024年度速報)」
- 生命保険文化センター「世帯年間払込保険料」
- 総務省統計局「家計調査報告(2024年平均結果の概要)」