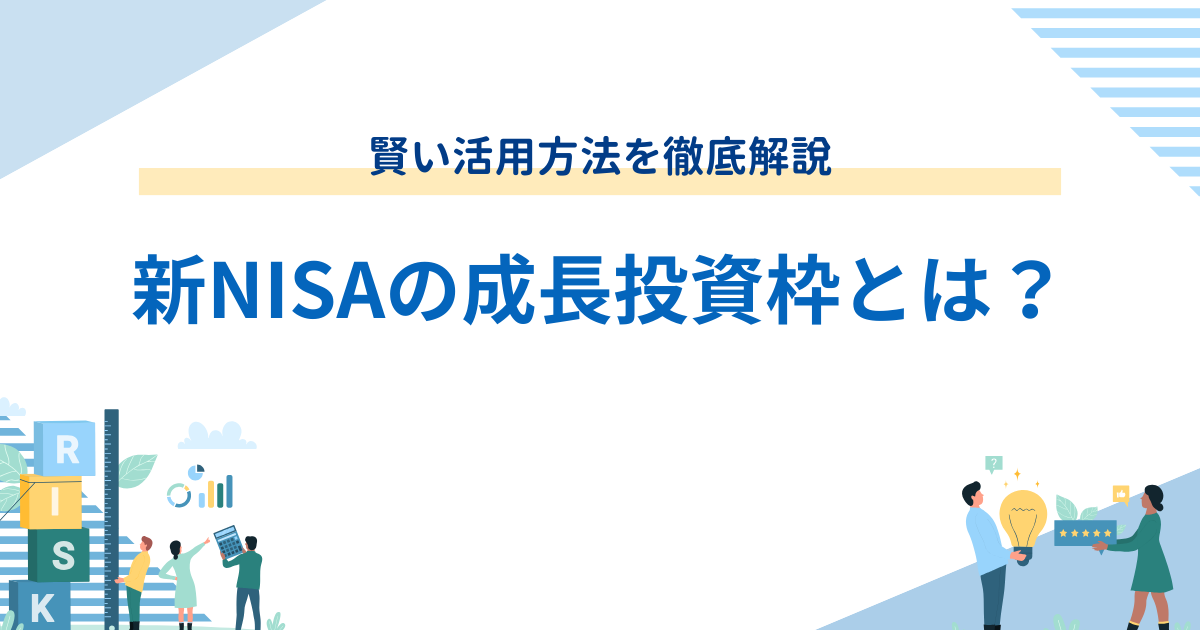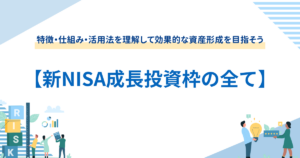「つみたて投資枠」は理解しつつも、「成長投資枠」はよくわからない、と後回しにしていないだろうか。
しかし、その活用こそが、より柔軟で効果的な資産形成の鍵となる。
本記事では、成長投資枠の基本から、あなたに合った賢い使い方、おすすめの金融機関まで詳しく解説する。
新NISA「成長投資枠」とは?
まず、新NISAの「成長投資枠」がどのような制度なのか、その基本を正確に把握することから始めよう。
「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の決定的な違い
新NISAには「成長投資枠」と「つみたて投資枠」という2つの非課税投資枠が用意されており、これらは併用が可能である。
両者の最も大きな違いは、「年間の投資上限額」と「投資できる商品の範囲」にある。
一言でその役割を表現するなら、コツコツ堅実に資産を育てる『守りのつみたて投資枠』と、より積極的で自由な投資を目指す『攻めの成長投資枠』とイメージすると分かりやすいだろう。
両者の主な違いを以下の表で確認してほしい。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間投資 上限額 | 240万円 | 120万円 |
| 非課税保有 限度額 | 生涯で1,800万円 (うち、成長投資枠のみの利用は1,200万円まで) | |
| 投資対象商品 | 上場株式、投資信託、ETF、REITなど (一部除外あり) | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託・ETF (金融庁の基準を満たしたもの) |
| 投資方法 | ⚫︎一括投資 ⚫︎積立投資 | 積立投資のみ |
このように、成長投資枠は年間で最大240万円まで投資でき、投資対象も個別株や幅広い投資信託から選べるなど、自由度が格段に高いのが特徴である。
意外と広い!成長投資枠で買える金融商品の種類
成長投資枠の最大の魅力は、投資対象の広さだ。
つみたて投資枠が金融庁の厳格な基準をクリアした投資信託・ETFに限定されているのに対し、成長投資枠では以下のような多様な金融商品に非課税で投資できる。
- 個別株式(国内・海外)
トヨタ自動車やソニーグループといった日本の有名企業から、AppleやGoogleといった米国のグロース株まで、国内外の企業の株式を直接購入できる。 - 投資信託
つみたて投資枠の対象商品に加え、より積極的なリターンを狙うアクティブファンドや、特定のテーマ(AI、環境など)に投資するファンドなど、多彩な選択肢から選べる。 - ETF(上場投資信託)
日経平均株価や米国のS&P500といった株価指数に連動する銘柄が多く、株式と同様にリアルタイムで売買できる。 - REIT(不動産投資信託)
オフィスビルや商業施設など、複数の不動産に分散投資する商品。家賃収入や売却益などを原資とした分配金が期待できる。
ただし、整理・監理銘柄や信託期間20年未満、高レバレッジ型、毎月分配型の投資信託など、長期の資産形成に不向きとされる一部の商品は対象外となる。
とはいえ、個人投資家が選択する商品のほとんどをカバーしていると考えてよいだろう。
 証券アナリスト 平行秀
証券アナリスト 平行秀成長投資枠では、比較的リスクの高い資産を自分の判断で選びます。幅広い商品から自由に選べる反面、迷いやすくもあるので、まずは投資信託やETFから、無理のない運用を目指しましょう。
知っておくべき成長投資枠のメリット・デメリット
自由度の高さが魅力の成長投資枠だが、利用を検討する上ではメリットとデメリットの両方を正しく理解しておくことが不可欠である。
- 年間240万円という大きな非課税枠
つみたて投資枠の2倍の金額を非課税で投資できるため、まとまった資金を効率的に運用したい場合に有利である。 - 個別株など幅広い商品を選べる
自分の信念や分析に基づいて応援したい企業や成長が期待できる企業に直接投資したり、投資信託では得られない大きなリターンを狙ったりすることが可能になる。 - 一括投資も可能
株価が下がったタイミングを狙ってまとまった資金を投じる「スポット購入」ができるため、積立投資に加えて柔軟な投資戦略を組むことができる。
- 商品によってはリスクが高くなる
自由度が高い分、値動きの激しい個別株やアクティブファンドなど、つみたて投資枠の対象商品に比べてハイリスク・ハイリターンな商品も含まれる。 - 商品選定に一定の知識が必要
選択肢が膨大であるため、自分に合った商品を見つけ出すためには、ある程度の金融知識や情報収集が求められる。 - 非課税枠の再利用ルールがやや複雑
売却すれば非課税枠は翌年に復活するが、短期的な売買を繰り返すと枠の管理が煩雑になる可能性がある。
これらのデメリットは、正しい知識を身につけ、適切な戦略を立てることで十分コントロール可能だ。次の章で、具体的な使い方を見ていこう。
新NISA成長投資枠は「いくらから」始めるべきか?
結論から言えば、「いくらから」という決まった正解はない。
しかし、一つ確かなのは、多くの人が想像するよりずっと少額から始められるということだ。
ここでは、投資の経験や目的別に、金額の目安を解説する。
投資が初めての方・まずは試してみたい方
まずは月々5,000円~10,000円といった、家計に負担のない範囲で始めてみるのがおすすめだ。
最初の目的は、大きな利益を得ることではなく、「値動きに慣れる」「投資を続ける習慣をつける」ことにある。
ネット証券なら100円からでも投資信託を購入できるため、まずは「お試し」感覚で一歩を踏み出し、数ヶ月続けてみて、慣れてきたら徐々に金額を増やしていくのが賢明な方法である。
目標金額・時期が決まっている方
「30年後に老後資金として2,000万円」のように、具体的な目標がある場合は、そこから逆算して毎月の投資額を決めるのが良い。
金融庁の「資産運用シミュレーション」などを使えば、目標達成に必要な積立額は簡単に試算できる。
例えば、年利3%で運用できると仮定した場合、上記の目標達成には毎月約35,000円の積立が必要だ。
まずは自分のライフプランを考え、将来に必要な資産額を考えることから始めよう。
【結論】大切なのは「最初の一歩」
重要なのは、金額の大小ではない。
大切なのは、無理のない範囲で「最初の一歩を踏み出す」こと、そして「投資に慣れていくこと」である。
上記の例を参考に、自身の状況に合った金額で始めるべきだ。
新NISA成長投資枠の賢い使い方【ケーススタディ】
新NISAの基本を理解したところで、次は「具体的にどう使えばいいのか?」を解説する。
最適な使い方は、あなたの投資経験や目標、リスク許容度によって異なる。ここでは、3つのタイプ別の活用法を提案する。
【初心者向け】「つみたて投資枠」の補助として使う
「個別株の売買はまだ怖い」「商品選びに自信がない」という投資初心者には、成長投資枠を「つみたて投資枠の延長・補助」として活用する方法がおすすめだ。
具体的には、つみたて投資枠で投資しているのと同じ、あるいは類似の低コストなインデックスファンド(例:全世界株式やS&P500に連動するファンド)を、成長投資枠でも買い増していく戦略である。
これにより、実質的に年間120万円というつみたて投資枠の上限を超えて、同じ方針で非課税投資を継続できる。
商品選びに新たに悩む必要がなく、リスクを抑えながら新NISAの非課税メリットを最大限に享受できる、最もシンプルで堅実な使い方だ。
【ポートフォリオ例】
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 投資商品 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |
| 投資額/月 | 10万円 | 10万円 |
| 投資額/年 | 120万円 | 120万円 |
【中級者向け】つみたて投資枠とは別のアクティブファンドを選ぶ
ある程度のリスクは受け入れ、より積極的なリターンを目指したい中級者には「コア・サテライト戦略」が適している。
これは、資産全体を「守り」のコア部分と「攻め」のサテライト部分に分けて運用する考え方だ。
- コア(核)資産
資産の70〜90%を占める中心部分。全世界株式や先進国株式のインデックスファンドなど、長期で安定的な成長が見込める低リスクな商品を「つみたて投資枠」でコツコツ積み立てる。 - サテライト(衛星)資産
資産の10〜30%を占める周辺部分。これを「成長投資枠」で運用する。特定のテーマを持つアクティブファンドや、成長が期待できる個別株など、コア資産よりも高いリターンを狙う。
この戦略により、資産全体の安定性を保ちつつ、一部で積極的にリターンを追求するという、バランスの取れたポートフォリオを構築できる。
【ポートフォリオ例】
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 投資商品 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(Bコース) |
| 投資額/月 | 10万円 | 3万円 |
| 投資額/年 | 120万円 | 36万円 |
【上級者向け】国内株・外国株に投資する
「応援したい企業がある」「自分の分析で銘柄を選びたい」「配当金で定期的な収入を得たい」など、より積極的に投資を行いたい上級者には、成長投資枠での株式投資がおすすめだ。
例えば、将来大きな値上がりが期待できる「グロース株」と、安定した配当収入(インカムゲイン)が見込める「高配当株」をバランス良くポートフォリオに組み入れる、といった方法が考えられる。
NISA口座なら配当金も非課税になるため、メリットは大きい。
これらの投資には、企業業績や財務状況を分析する知識が不可欠となる。
しかし、つみたて投資枠で安定的なコア資産を築きつつ、成長投資枠では、自分の投資哲学に基づいて個別株を組み合わせることでより効果的な運用が期待できる。
【ポートフォリオ例】
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | ||
|---|---|---|---|
| 投資商品 | eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | Amazon.com | NTT |
| 投資額/月 | 10万円 | – | – |
| 投資額/年 | 120万円 | 100万円 | 100万円 |



個別株投資は成長性が高い分リスクも伴うため、1社に偏るのではなく、業種や地域を分けて分散することが重要です。例えば、IT・医薬・インフラなど異なる景気サイクルの業種を組み合わせると、価格変動リスクを軽減できます。
新NISA成長投資枠の始め方・買い方を5ステップで解説
ここまでの解説で、成長投資枠で投資を始める気持ちが高まってきたのではないだろうか。
この章では、口座開設から商品購入までの具体的な流れを、初心者でも迷わないよう5つのステップで丁寧に解説する。
NISAを始めるには、まず銀行や証券会社でNISA専用の口座を開設する必要がある。どこで開設するかは非常に重要であり、最初の大きな選択となる。金融機関選びの比較軸は主に「手数料」「取扱商品数」「使いやすさ」の3つだ。
結論として、これからNISAを始めるなら、対面での相談に強いこだわりがない限り、手数料が安く、取扱商品が豊富なネット証券を強くおすすめする。店舗運営コストがかからない分、各種手数料が格段に安く、長期的な資産形成においてその差は無視できないものとなる。


口座開設が完了したら、次はいよいよ投資する商品を選ぶ。おそらく、ここが最も悩むポイントだろう。
選び方の基本は、前章で解説した「使い方戦略モデル」に立ち返ることだ。
- 初心者タイプ
つみたて投資枠と同じインデックスファンドを選ぶ。 - 中級者タイプ
サテライト部分として興味のあるテーマのアクティブファンドや、よく知っている有名企業の株を探してみる。 - 上級者タイプ
自分の分析に基づいて銘柄をリストアップする。
最初から完璧な商品を選ぶ必要はない。まずは低コストのインデックスファンドから始め、知識が深まるにつれて個別株などに挑戦していくのが王道だ。
▶︎新NISA「成長投資枠」におすすめの商品はこちらの記事をチェック


商品が決まったら、購入代金となる資金を証券口座に入金する。
主な入金方法は以下の通りだ。
- 銀行振込
ご自身の銀行口座から、証券会社が指定する口座へ振り込む。 - 自動引落設定
毎月決まった日に、指定した銀行口座から自動で引き落とされる設定。入金の手間が省け、積立投資に便利。 - 即時入金サービス
提携しているネットバンクなどから、手数料無料でリアルタイムに入金できるサービス。非常に便利で多くのネット証券が対応している。
手数料を抑え、スムーズに取引するためにも、即時入金サービスの利用がおすすめだ。
入金が完了したら、いよいよ注文を出す。投資信託の購入画面では「金額指定」や「口数指定」を選び、個別株の場合は「成行(なりゆき)注文」か「指値(さしね)注文」かを選択する。
- 成行注文
価格を指定せず、その時の市場価格で即座に売買を成立させる注文。 - 指値注文
「1株1,000円で買いたい」のように、希望する価格を指定する注文。
投資信託を購入する際は、必ず「目論見書(もくろみしょ)」に目を通す習慣をつけよう。手数料(信託報酬)や投資方針、リスクなど、そのファンドに関する重要な情報がすべて記載されている。すべてを熟読する必要はないが、コストと投資対象は最低限確認すべきポイントだ。
投資は「買ったら終わり」ではない。一度ポートフォリオを組んだら、少なくとも年に一度は内容を見直す習慣をつけることが、長期的な成功の鍵となる。
時間の経過とともに各資産の価格は変動し、当初決めた資産配分(アセットアロケーション)のバランスは崩れていく。例えば、株式の割合が増えすぎて、意図せずハイリスクな状態になっている場合がある。このズレを修正するために、値上がりした資産の一部を売却し、値下がりした資産を買い増す「リバランス」を行うのだ。
ただし、NISA口座で商品を売却した場合、その非課税枠が復活するのは翌年以降である点には注意が必要だ。頻繁な売買は推奨されないため、あくまで長期的な視点での見直しを心掛けるべきである。
新NISA「成長投資枠」の運用に悩んだら、プロに相談しよう
ここまで、新NISA成長投資枠の仕組みから具体的な商品の選び方まで解説してきた。
しかし、情報が多ければ多いほど、「自分にとっての正解はどれなのか」と、かえって決断できなくなる人もいるだろう。
特に、投資は自己責任の世界。大切な資産を投じるからには、絶対に失敗したくないと考えるのは当然だ。
もし、あなたが一人で決断することに少しでも不安を感じるなら、資産運用のプロに相談してみよう。
なぜ今、プロへの相談が有効なのか?
新NISAは自由度が高い分、投資家一人ひとりの判断がより重要になる制度だ。
インターネット上には有益な情報も多いが、その情報が本当に自分のライフプランやリスク許容度に合っているかを見極めるのは容易ではない。
専門家は、あなたの収入や家族構成、将来の夢といった個人的な状況を深くヒアリングした上で、客観的かつ中立的な視点から、あなただけの投資プランを設計してくれる。
それは、情報過多の時代において、時間と手間を節約し、最適な答えにたどり着くための賢明な近道といえるだろう。
資産運用のプロに相談するメリット・デメリット
プロへの相談を検討する際は、メリットとデメリットの両方を把握しておこう。
- 最適なポートフォリオを提案してくれる
あなたの目標やリスク許容度に合わせ、具体的な金融商品の組み合わせを提案してくれる。 - 金融商品を中立的な立場で比較検討できる
特定の金融機関に所属しないアドバイザー(IFAなど)であれば、幅広い選択肢の中から公平なアドバイスが期待できる。 - 時間と労力を大幅に節約できる
自分で膨大な情報を収集・分析する手間が省ける。 - 相場急変時の精神的な支えになる
市場が大きく変動した際に、冷静なアドバイスをくれる専門家がいることは、大きな安心材料となる。
- 相談料などのコストがかかる場合がある
相談が有料の場合や、金融商品購入時に手数料が発生する場合がある。事前に料金体系を確認することが必須だ。 - アドバイザーによって力量や相性が異なる
担当者との相性も重要。一人の意見を鵜呑みにせず、複数の専門家に話を聞いてみるのも有効な手段である。
プロ探しならマッチングサービス「資産運用ナビ」が便利
「プロに相談するメリットはわかったけれど、どうやって信頼できる人を探せばいいのかわからない」という方には、資産運用アドバイザーのマッチングサービス「資産運用ナビ」の利用がおすすめだ。
「資産運用ナビ」は相談内容(NISA、ポートフォリオ、投資信託など)や地域を指定するだけで、全国の登録アドバイザーから自分に合った人を探し出すことができる。
このサービスの大きな特徴は、何度でも無料で相談できる点だ。
さらに、紹介されるアドバイザーは、金融庁の登録を受けた、経験豊富で実績のある専門家のみ。
無理な勧誘や提案の心配もなく、安心して相談できる。
投資を何から始めればいいかわからない初心者から、すでにある資産の最適化を目指す経験者まで、一人ひとりの状況に合った信頼できるパートナーが見つかるだろう。
失敗しないための新NISA成長投資枠の注意点
最後に、成長投資枠で投資を始める前に必ず知っておくべき注意点を解説する。
事前にリスクや疑問点を解消しておくことで、安心して資産形成を続けることができるだろう。
注意点1:損益通算・繰越控除はできない
NISAの最大のメリットは利益が非課税になることだが、裏返しとして損失も税務上ないものとして扱われる。
通常の課税口座(特定口座など)であれば、ある取引で出た利益と、別の取引で出た損失を相殺する「損益通算」や、その年に相殺しきれなかった損失を翌年以降3年間繰り越せる「繰越控除」が可能だ。しかし、NISA口座ではこれらの制度は利用できない。
例えば、NISA口座で10万円の損失、特定口座で20万円の利益が出た場合、特定口座の20万円の利益にそのまま課税される。
この点は、課税口座と併用する際には必ず覚えておくべきルールである。
注意点2:非課税枠の再利用ルールを正しく理解しよう
NISA口座で保有している商品を売却した場合、その商品を取得した時の金額(簿価)分の非課税枠が、翌年以降に復活し、再利用できる。
例えば、100万円で買った株が120万円に値上がりした時点で売却した場合、翌年に復活するのは購入時の簿価である100万円分の枠だ。
このルールにより、ライフイベントなどで資金が必要になった際にも柔軟に対応できる。
ただし、枠が復活するのはあくまで翌年以降であり、同一年内での短期的な売買には向かない設計となっている点に注意が必要だ。
注意点3:高値掴みと狼狽売りを避ける
投資で失敗する最も典型的なパターンが、感情的な取引だ。
市場が盛り上がっている時に焦って高値で買ってしまう「高値掴み」や、市場が下落した時に恐怖に駆られて底値で売ってしまう「狼狽(ろうばい)売り」である。
特に、値動きの大きい個別株などを扱う成長投資枠では、この罠に陥りやすい。
対策は、投資の基本原則である「長期・積立・分散」に立ち返ることだ。
市場の短期的な変動に一喜一憂せず、長期的な視点で資産を育てていくという強い意志を持つことが、成功への何よりの近道となる。
まとめ
本記事では、成長投資枠の基本知識や活用戦略を解説してきた。
新NISAの成長投資枠は個別株への投資を実践したり、非課税枠の再利用を有効活用したりすることで効果的に活用できる。
本記事で紹介したおすすめの運用例や資産形成のポイントを参考に、自分に合った運用戦略を立てていこう。



成長投資枠は投資対象が幅広く自由度が高い反面、迷いやすいという難点もあります。だからこそ、自分の目的やリスク許容度に応じた投資計画と継続的な見直しが、成功への第一歩です。
また、新NISAについての不安や疑問がある場合、専門家からアドバイスを受けることをおすすめする。
ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を活用し、自分に合ったパートナーを探してみよう。