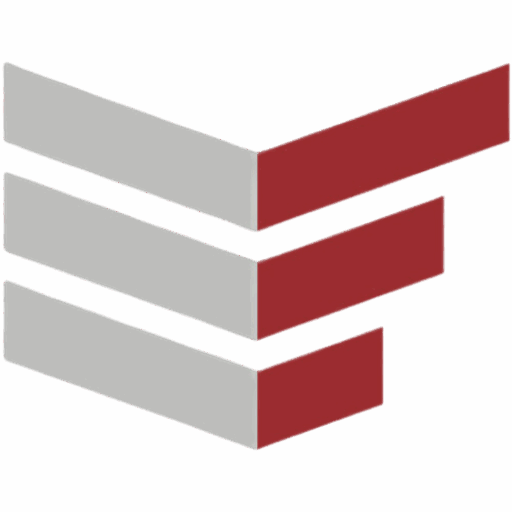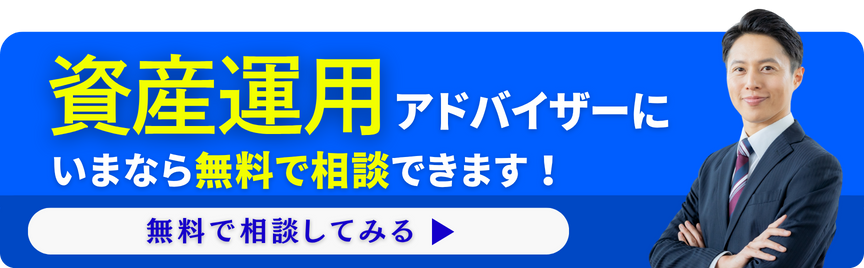- 100万円の運用におすすめの方法が知りたい
- 100万円を投資で効率的に増やしたい
- 初心者でも取り組める運用法や投資のコツが知りたい
手元の100万円を投資に回す際、どういった方法で運用すべきか悩むケースは少なくない。
自分に合った投資法を見つけ出し、効率的に資産を増やしていくことが大切だ。
本記事では、100万円でできるおすすめの運用法や運用時に押さえておきたい6つのポイントを解説していく。
100万円を投資する場合の運用シミュレーションや非課税制度の特徴、相談先の専門家を探せるサービスも紹介するので、ぜひ本記事を参考に100万円の投資を始めよう。

証券アナリスト
監修者: 平 行秀
新卒で野村證券に入社し、富裕層1,000人以上の資産運用コンサルを担当する。 その後、2019年にアドバイザーナビ株式会社を創業し、代表取締役へ。 投資家とアドバイザーをつなぐマッチングプラットフォームを運営している。
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)。
100万円を運用すれば効率的に資産を増やせる

資産運用と聞くと「まとまった金額を投資して資産を増やしていく」というイメージを抱く方も多いだろう。
一般的な資産運用のイメージからすると100万円の投資は少額に感じられるかもしれないが、少ないと思われる金額であっても投資を行うことで効率的に資産を増やせる。
 証券アナリスト 平行秀
証券アナリスト 平行秀100万円はリスクとリターンのバランスを意識しながら、実践的に資産運用を学ぶのに適した金額です。
分散投資や制度の活用などを体験することで、将来に向けた投資判断力が養われ、長期的な資産形成の土台を築くことができます。
少額からでも投資を行うメリットとして以下の2点が挙げられる。
- 複利効果を活かせる
- 投資経験が身に付く
複利効果とは、投資で得られる利益を再び元本に加えて投資に回すことで、利益が新たな利益を生み出す効果のことを指す。
運用当初は少額であっても、利益が利益を生んで資産が雪だるま式に増えていく仕組みだ。
例えば100万円を利回り5%で運用した場合、1年目の利益は「100万円×5%=50,000円」となる。
その5万円の利益を元本に加えた場合、2年目の利益は「105万円×5%=52,500円」となる。
さらに運用を続けていけば得られる利益はどんどん増えていき、資産も加速度的に増えていく。
少額投資であっても時間を味方につければ効率的に増えていくため、なるべく早く投資を始めることが大切だ。
また、投資経験が身に付く点も少額投資のメリットである。
少額からでも投資をしていれば、金融商品の価格変動を実際に体感したり、マーケットの動向に興味を抱いてニュースをチェックするようになったりと、投資に関する経験値が蓄積されていく。



投資経験は“お金のリテラシー”を高める第一歩です。
重要なのは金額の大小ではなく、関心を持って実際に行動すること。日々の積み重ねが将来の資産形成に直結し、自分に合った投資スタイルを見つける力にもつながっていきます。
将来的に投資額が増えたときに経験が活かされ、資産を効率良く増やせる可能性がある。
上記のような点を踏まえると、100万円は投資に回して運用すべきと言えるだろう。
100万円でできる運用法5選


実際に100万円を投資に回すのであれば、以下の5つの運用法がおすすめだ。
- 株式
- 債券
- 投資信託
- ETF
- REIT
それぞれの運用法について解説していくので、ぜひ参考にしてほしい。
株式
株式とは、企業が資金調達のために発行する有価証券のことを指す。
投資家は株式を購入することで企業に投資を行い、企業の成長に伴ってリターンを得るというのが「株式投資」の基本的な仕組みだ。
株式は一般的に証券取引所で売買されており、投資家からの需要・供給のバランスで株価が変動している。
購入時よりも高い株価で売却して利益を得たり、企業が株主に対して支払う配当金を受け取ったりという形で利益を得る。
また、企業のサービス・商品やギフトカタログなどが贈呈される「株主優待」を目的に株式を購入する投資家も少なくない。
株式は比較的値動きが大きい金融商品であるため、上手く運用できれば短期的に資産を大きく増やすチャンスがある。
一方で急激に株価が下落し、一気に資産が減ってしまう危険性も伴う投資先だ。
特定の銘柄ばかりに資金を集中させてしまうとリスクが大きいため、複数の銘柄に分散投資を行うことが重要である。
100万円の資金であれば数十銘柄に分散することは難しいが、異なる業種の数銘柄での分散投資を推奨する。



まずは、いつまでに、いくら増やしたいのかといった具体的な目標を設定しましょう。
そして、投資期間や生活資金とのバランスを踏まえて無理のない計画のもとで投資判断を行うことがポイントです。
債券
債券とは、企業や国、地方公共団体が資金調達のために発行する有価証券のことを指す。
投資家は債券の購入によって資金を発行体に貸し出したことになり、満期まで利子を受け取りながら運用できる。
債券はあらかじめ決められた利率で利子が支払われ、満期には元本が償還される。
収益の見通しを立てやすく、比較的安定した運用を行えることが債券の特徴だ。
債券は市場で売買されており、満期を迎える前に売却したり、市場で流通している債券を購入して満期まで保有したりすることもできる。
購入時よりも高い価格で売却して利益を得たり、額面金額よりも安く購入して満期を迎えたときに差額を得たりといった運用も可能だ。
通常、企業が発行する「社債」などは10万円単位・100万円単位で購入できる。
100万円を運用したいのであれば、10万円単位の債券を複数保有すると良いだろう。
投資信託
投資信託とは、投資家から集めた資金をもとに専門家が株式・債券等で運用を行う金融商品である。
運用成果が投資家に分配される仕組みとなっており、専門家に投資を一任できることが特徴だ。
投資信託では、複数の株式・債券で運用が行われているため、1つの商品を購入するだけで間接的に複数の投資先に分散できる。
個別の株式を購入するよりもリスクが小さく、投資初心者にもおすすめの投資先だ。
また、投資先銘柄の選定や売買のタイミングを見極める必要もなく、一度投資信託を購入したら放置していても問題ない。
本業で忙しい人や投資経験が少ない人でも投資しやすい金融商品である。
運用を任せる分だけ手数料が発生するものの、市場指数との連動を目指して運用される「インデックスファンド」はコストも低い。
運用コストを抑えて市場の平均リターンを狙いたい人は、インデックスファンドに100万円を投資してみると良いだろう。
ETF
ETFとは、金融商品取引所に上場する投資信託のことだ。「上場投資信託」とも呼ばれており、株式と投資信託の性質を併せ持つ金融商品である。
ETFは市場指数との連動を目指す「インデックスファンド」が大半であり、低コストで市場の平均リターンを得られることが特徴だ。
手軽に分散効果を得られる点は投資信託と共通している。
一方、金融商品取引所で売買されることからリアルタイムで価格が変動している。
株式のように値動きを見ながら投資判断を行い、売買するタイミングを見極めてリターンを狙うことが可能だ。
一般的な投資信託に比べて運用の自由度が高い点がETFの特徴である。より自由に運用したい人は、100万円をETFに投資してみると良いだろう。
REIT
REITとは、不動産で運用される上場投資信託のことだ。
金融商品取引所に上場しており、投資家から集めた資金で専門家が不動産投資を行う仕組みとなっている。
通常、不動産に投資するためには数百万円〜数千万円の資金が必要となるため、100万円の投資先には向かない。
ローンを活用する方法もあるが、投資経験が少ないタイミングでローンを組むことに抵抗がある方も多いだろう。
REITは数万円程度の自己資金で不動産に投資を行える。複数の不動産物件で運用されており、少額で分散投資を行える点が大きな魅力だ。
また、REITは利益の90%以上を分配することで実質的に法人税がかからない仕組みとなっている。
利益のほとんどが分配されるため、高い分配金利回りで運用できることも特徴だ。
「不動産に資金を投じたい」「定期的な分配金を受け取りたい」という方は、REITへの投資を検討してみよう。
【投資目的・期間別】100万円のおすすめの運用法


次に、投資目的別と運用期間別の100万円のおすすめ運用法を紹介していく。
自分の投資目的・運用期間に合った方法で100万円を投資し、計画的に資産を増やしていこう。
投資目的別の運用法
まず、投資目的に応じたおすすめの運用法を紹介していく。ここでは、以下の3つの目的について適切な運用法を紹介する。
- 子どもの教育資金の準備
- 老後に向けた資産形成
- 定期的なインカムゲインの獲得
それぞれのパターンについておすすめの運用法を紹介する。
子どもの教育資金の準備
教育資金の準備は子どもの年齢にもよるが、なるべくリスクを抑えた運用が推奨される。
大学の進学費用などは時期をずらすことができず、進学時に「費用が足りない」という事態を避けなければならないためだ。



使途と時期が明確な資金には、価格変動の少ない金融商品を選ぶことが重要です。
元本割れのリスクを極力抑え、確実に必要なタイミングで資金を確保できるように設計することが、堅実な資産運用の基本です。
例えば「5年後に海外旅行に行くためのお金を準備したい」という目的の場合、5年後に資産価値が下落して目標額に到達できなくても旅行を延期すれば対応できる。
しかし子どもの大学進学は金銭的な都合で先延ばしにはできないため、なるべく減らさないように運用する必要がある。
リスクを抑えて運用したいのであれば、債券への投資がおすすめだ。
満期を迎えると額面金額で償還されるため安全性が高く、収益の見通しも立てやすい。目標の時期が決まっている教育資金の準備に適しているだろう。
また、債券で運用を行う投資信託を活用しても良い。比較的リスクが小さい債券に分散投資を行うことで、より堅実に運用できる。
安定的なリターンを目指し、なるべく資産を減らさないように堅実に運用していこう。
老後に向けた資産形成
老後に向けた資産形成は年齢にもよるが、ある程度のリスクを取った運用がおすすめだ。
老後を迎えるまでの期間が長いほどリスク許容度も高くなり、リターンを狙って積極的な運用を行える。
例えば、20代〜30代であれば老後を迎えるまでに30年前後の年数があるため、途中で資産が減少しても取り返す時間的な余裕がある。
100万円を株式や株式型投資信託などで運用し、資産の成長を目指していくと良いだろう。
定期的なインカムゲインの獲得
定期的なインカムゲインを獲得したいのであれば、配当金や分配金、利子などを得られる投資先に分散投資を行うと良い。
複数の投資先に分散しておくことで安定した利回りを維持でき、中長期的にインカムゲインを獲得していける。
具体的な投資先としてはREITや債券、株式、ETFなどが挙げられる。
ただし、株式やETFについては配当金・分配金が支払われない銘柄もあるため、事前のチェックが必要だ。
利回りが高い「高配当株」「高配当ETF」と呼ばれる商品で運用すると良いだろう。
また、債券のなかには利子の支払いがない「ゼロクーポン債」と呼ばれる商品もある。
利子がない代わりに額面から一定率を割り引いた価格で発行され、満期日に額面金額が償還される仕組みだ。
ゼロクーポン債はインカムゲイン目的の投資には向かないため注意しておこう。
運用期間別の運用法
次に、運用期間別のおすすめ運用法を紹介していく。短期・中期・長期に分けて適切な運用法を紹介する。
短期投資におすすめの運用法
短期間で利益を狙う投資スタイルの場合、株式による運用がおすすめだ。
株式は比較的値動きが大きいため、短期的な価格変動を利用して売買差益を狙いやすい。
特に、時価総額が小さい中小型株の方が値動きが大きい傾向にあり、短期間で狙えるリターンの幅も大きい。
目安として、時価総額3,000万円以下の銘柄で投資を行うと良いだろう。
ただし短期投資でハイリターンを狙うスタイルはリスクも大きいため、投資初心者には推奨しない。
ある程度投資経験を積み、リスクをしっかり管理できるだけのスキルが身に付いてから始めると良いだろう。
中期投資におすすめの運用法
ある程度の運用期間でリターンを狙う投資スタイルの場合、債券やETFによる運用がおすすめだ。
安全性を重視したい人は債券、リターンを狙いたい人はETFを活用すると良いだろう。
債券の場合、満期が事前に決まっているため中期投資を実践しやすい。自分の運用期間に合った債券を選び、じっくり資産を運用していける点が魅力だ。
ETFの場合、株式に比べると値動きが落ち着いているため、短期投資には向かない。
しかしリアルタイムで値動きを見て売買できるため、相場が急激に上昇したタイミングを狙いやすい商品だ。
割安なタイミングでETFを購入しておき、相場の急騰を狙って売却する戦略を検討してみると良いだろう。
長期投資におすすめの運用法
数年〜数十年にわたる運用期間で資産を増やす投資スタイルの場合、投資信託やREITによる運用がおすすめだ。
いずれも長期運用に適した金融商品であり、じっくり資産を成長させていける投資先である。



長期投資では、短期的な価格変動に一喜一憂せず、積立投資や分散投資を組み合わせて“時間を味方につける”姿勢が大切です。
焦らずコツコツと資産を積み上げていくことで、複利効果が最大化され、成功につながる可能性が高まります。
投資信託で長期運用をする場合、株式に投資する商品を選ぶと良いだろう。
運用期間を長く取れる分、一時的な相場の下落があっても株価が回復するのを待つ余裕がある。
中長期的な資産成長を目指し、株式型の投資信託で運用していこう。
REITは定期的な分配収入を得られるだけでなく、インフレリスクに強いというメリットもある。
インフレによって物価が上昇した場合、不動産の価格や賃料収入も増加するため、REITの収益性も高くなる。
分配金を定期的に受け取りつつ、中長期でのインフレリスクにも備えておくと良いだろう。
100万円を投資すると資産はどのくらい増える?運用シミュレーション
次に、100万円を運用した場合の資産成長をシミュレーションで紹介していく。
以下の表は、運用利回り3%・5%・7%で投資をした場合の期間別の運用成果をまとめたものだ。
| 1年後 | 10年後 | 30年後 | |
|---|---|---|---|
| 利回り3% | 1,030,000円 | 1,343,916円 | 2,427,262円 |
| 利回り5% | 1,050,000円 | 1,628,895円 | 4,321,942円 |
| 利回り7% | 1,070,000円 | 1,967,151円 | 7,612,255円 |
上記の表を見て分かる通り、運用期間が長くなるほど得られるリターンは大きくなっていく。



運用の成果は「投資額×利回り×時間」で決まります。
たとえ少額でも、長期的に継続すれば複利効果が働き、資産は雪だるま式に増加していきます。
時間を味方につけることが、無理なく大きな資産形成を実現する最大のポイントです。
時間を味方につけることで100万円を大きく増やすことも可能であるため、なるべく早く投資を始めよう。
利回り3%は債券中心の運用、利回り5%は債券と株式をバランス良く保有する運用、利回り7%は株式中心の運用で実現できる可能性が高い。
自分のリスク許容度に合わせた資産配分を構築し、上記のシミュレーションを参考に投資計画を立てていこう。
100万円を運用するなら非課税制度も活用するべき


100万円を運用するのであれば、NISAやiDeCoなどの非課税制度の活用がおすすめだ。
それぞれの制度の特徴や投資法を紹介していく。
NISAの概要と投資法
NISAとは、投資で得られる利益が非課税となる制度のことだ。
年間360万円・生涯1,800万円の非課税投資枠が与えられ、枠内で購入した株式や投資信託の利益に税金がかからない仕組みとなっている。
通常、株式や投資信託の売却益や配当金・分配金には20.315%の税金がかかる。
仮に10万円の利益が得られたとしても、およそ2万円が税金で引かれて手元に残るのは8万円になってしまう。
しかしNISA口座内で投資をしていれば、10万円の利益をそのまま受け取ることが可能だ。
100万円でNISAを活用するのであれば「つみたて投資枠」の利用を推奨する。
つみたて投資枠とは、年間120万円までの積立投資を対象とした非課税投資枠だ。
金融庁の基準を満たした投資信託のみが対象となっており、長期の資産形成に適した銘柄が厳選されている。
具体的には「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」や「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」などの銘柄がおすすめだ。
いずれも分散効果が高い株式型の商品であり、中長期での資産成長を期待できる投資先である。
まずはつみたて投資枠を使って100万円を分割しながら投資をしていき、着実に資産を増やしていこう。
iDeCoの概要と投資法
iDeCoとは、自分で掛金の拠出・運用を行って老後資金を準備する私的年金制度のことだ。
以下の3つの税制優遇を受けられることが特徴となっている。
- 掛金が全額所得控除になる
- 運用益が非課税で再投資される
- 年金・一時金で受け取るときにも控除が適用される
掛金の全額所得控除により、所得税・住民税の負担を軽減できる。税負担を抑えて手取り収入を増やしつつ、老後に向けた資産準備も行える点がiDeCoの大きなメリットだ。
また、運用益の非課税再投資や受け取り時の控除適用による税負担の軽減も魅力として挙げられる。
ただしiDeCoで積み立てた資産は原則60歳まで引き出せないため、老後を迎える前の資産準備には向かない。
iDeCoは老後資金の準備に特化して活用し、マイホームの購入資金や子どもの教育資金などの準備はNISAで行うと良いだろう。
100万円を運用する時の6つのポイント


100万円を運用する際、以下の6つのポイントを押さえておこう。
- 運用の目的や期間を設定する
- 余剰資金で投資を行う
- 市場動向や商品の特徴・リスクを理解する
- 分散投資を実践する
- 長期目線で運用する
- ポートフォリオを定期的に見直す
それぞれのポイントを押さえ、効率的に運用していこう。
運用の目的や期間を設定する
まず、運用の目的や期間を設定することが重要となる。
目的・期間が定まらないまま運用を始めてしまうと、ライフイベントを迎えたときに資産が不足したり、過剰にリスクを取り過ぎることになったりする可能性があるためだ。



目的と期間が明確であれば、投資のゴールが可視化されます。
リスクの取り方や商品の選び方にも一貫性が生まれ、ブレない判断が可能になります。
結果として、運用の途中で迷いが生じにくくなり、計画的に資産を積み上げていくことができます。
運用の目的には以下のようなものがある。
- 子どもの教育費を準備したい
- マイホーム購入の頭金を貯めたい
- 老後資金を準備したい
運用目的・期間が定まると「いつまでにどのくらいの資産が必要か」が明確となる。適切なリスク水準で運用するためにも、目的と期間を設定しよう。
余剰資金で投資を行う
投資は価格が変動するリスクがあり、損失を抱える危険性が伴う。投資を行う際には余剰資金で行うことが鉄則だ。
生活費や緊急用の資金を投資に回してしまうと、相場が暴落して損失を抱えたときに生活に支障をきたす恐れがある。
生活費・緊急用の資金は預貯金等の安全資産で管理しつつ、残った余剰資金でリスクを取った運用を行おう。
一般的には「生活費の3ヶ月〜半年分」は預貯金で確保すべきと言われている。当面の生活費を確保し、残った資金で投資を活用して資産を増やしていこう。
市場動向や商品の特徴・リスクを理解する
投資を行う際には、市場の動向や商品の特徴を正しく理解しておくことが大切だ。
よく分からないまま投資を始めてしまうと、想定外の失敗で大きく資産を減らす可能性があるため注意しておこう。
例えば、株式に投資をする場合は経済や金利の動向などを把握しておく必要がある。
加えて個別企業の決算情報などを分析し、投資対象としてふさわしいことを確認しなければならない。
また、プロに運用を任せられる投資信託であっても、商品の特徴やリスクについては理解しておく必要がある。
「どういった投資対象で運用を行っているのか」「どういったリスク要因があるのか」という点を把握した上で資金を投じることが大切だ。
大切な資産を投じる以上、投資先の特徴やリスクをしっかり理解しておこう。
分散投資を実践する
資産運用の基本として「分散投資」が挙げられる。複数の資産クラスや地域、銘柄に分散して投資を行うことが大切だ。
特定の投資先ばかりに資金を集中させると、その投資先が暴落したときに資産が一気に減ってしまう。
1つの投資先のリスク要因に資産全体が左右されてしまうため、安定した運用を行うことが難しい。
投資先を分散させておけば、そのうちのひとつが暴落しても資産全体で受けるダメージは小さい。
ほかの投資先で利益が出ていれば、暴落による損失をカバーすることも可能だ。
株式や債券を組み合わせたり、国内外の資産に投資をしたりなど、分散投資で安定的な運用を目指そう。
長期目線で運用する
大きなリスクを回避するポイントとして「長期投資」も挙げられる。運用期間を長く設定し、じっくり資産を増やしていく戦略がおすすめだ。
すぐに成果を出そうとすると、値動きが激しいハイリスクな投資手法に手を出すことになる。
上手くいけば短期的に大きなリターンを得られるかもしれないが、一気に資産を減らす危険性もある。
冷静な判断も難しくなってしまい、不適切なタイミングで売買して損失を抱える可能性も高い。
長期的な視点で運用していれば、安定した値動きの投資手法でじっくりリターンを狙える。
短期的な価格変動の影響を抑えつつ、利益が利益を生み出す「複利効果」の恩恵も受けられる。
途中で運用が上手く行かなくても、運用期間に余裕があれば投資計画を修正しやすい。
長期的な目線を持ってじっくり運用することを心掛けよう。
ポートフォリオを定期的に見直す
投資は「金融商品を買ったら終わり」ではない。運用を始めてからも定期的に資産状況を見直し、必要に応じて資産配分を調整し直すことが大切だ。



ポートフォリオの定期的な点検は、いわば投資の健康診断です。
市場環境の変化やライフステージの節目に応じて資産配分を見直すことで、過度なリスクを回避しながら、自分に合った適正なバランスを保つことが可能になります。
例えば「株式50%・債券50%」のバランスで運用を始め、株価の上昇によって「株式60%・債券40%」という比率になった場合、運用当初よりもリスクが高い資産配分になっている。
自身のリスク許容度と乖離してしまい、想定以上の損失を抱える可能性が出てくる。
この場合は株式を一部売却したり、債券を追加購入したりすると運用当初の資産配分に調整可能だ。
定期的に資産状況の見直しを行い、必要に応じて資産の売却や購入をしながら適切なバランスに調整していこう。
100万円の運用で効率的に資産を増やすなら「資産運用ナビ」で専門家に相談しよう


100万円の運用で効率的に資産を増やしたい方は「資産運用ナビ」で専門家を探すと良い。
自分に合った専門家に資産運用の相談を行い、自分自身の投資を成功に近づけよう。
ここでは資産運用を始めるステップや専門家に相談すべき理由、「資産運用ナビ」の特徴・利用方法について解説していく。
資産運用を始めるステップ
資産運用を始める場合、以下のステップで準備を進めることになる。
- 投資目的・運用期間を明確化する
- 目的・期間に合ったポートフォリオを構築する
- 具体的な銘柄を選定する
まず、自分の投資目的や運用期間を明確にするところから始める。
頭に描いているライフプランを具現化した上で「いつまでにどのくらい資産を準備すべきか」という点を明確にしよう。
そして、目的・期間に合った運用ポートフォリオを構築していく。運用期間と投資額から利回りを算出し、目標利回りを達成できる資産配分を考えよう。
運用ポートフォリオが決まったら、具体的な銘柄の選定に進む。
リスク水準や運用コスト、利回りなどの要素を総合的に判断し、銘柄を選定していく。
資産運用を専門家に相談すべき理由
上記のステップを自分ひとりで実践するのが難しいと感じる方も多いだろう。
投資を自分だけで行うことに不安を感じる方は、投資助言を行う専門家に相談すると良い。
専門家に相談すべき理由として主に以下の3点が挙げられる。
- 最適な運用法はそれぞれ異なるため
- 常に最新の情報を取り入れる必要があるため
- 運用開始後も適切なアフターフォローが必要であるため
資産運用の方法については、運用目的や投資期間、リスク許容度などによって最適解が異なる。
万人におすすめの運用方法は残念ながら存在しないため、自分の状況に合ったものを選ばなければならない。
豊富な知識・経験を有する専門家に相談し、自分に合った運用方法を提案してもらうべきだろう。
また、資産運用を行う際には常に変化し続けるマーケットの動向を把握しつつ、経済・国際情勢などに関する最新情報もチェックしておく必要がある。
しかし投資経験が少ない人や本業で忙しい人は投資情報を的確にキャッチし、分析することは容易ではない。
専門家から情報を提供してもらい、投資判断を行う方がスムーズだ。
そして、運用開始後も資産状況に応じて投資戦略を練り直していく必要がある。
適切なアフターフォローを提供してもらうためにも、専門家に相談すべきと言える。
100万円を投資に回して資産運用を始めたい方は、投資助言を行う専門家への相談を検討してみよう。
「資産運用ナビ」を活用しよう
相談先の専門家を探したい方は「資産運用ナビ」の活用をおすすめする。
「資産運用ナビ」とは、相談先を探す投資家にぴったりの資産運用アドバイザーを無料で紹介するサービスのことだ。
「資産運用ナビ」では、以下のステップでアドバイザーとマッチングできる。
- 専用フォームに希望する条件を入力する
- 条件に合ったアドバイザーが自動診断される
- アドバイザーのプロフィールをチェックして相談先を選ぶ
- 初回面談の日程を調整する
- アドバイザーと面談を行う
たった60秒、あなたの希望条件を入力するだけで条件にぴったりのアドバイザーがランキング形式で紹介される。
「資産運用ナビ」では、アドバイザーの詳細なプロフィールを公開しており、事前に経歴や得意分野をチェックした上で申し込むことが可能だ。
アドバイザーの紹介料や相談費用は無料となっており、何回相談しても費用はかからない。紹介は全国47都道府県どこでも対応しており、オンラインでの面談も可能だ。
ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を活用し、自分に合ったアドバイザーに投資の悩みを相談してみてはいかがだろうか。
100万円を効果的に投資しよう
100万円は一般的な資産運用のイメージだと少額に感じるかもしれないが、投資に回すことで複利効果を活かせる点や投資経験が身に付く点などのメリットがある。
手元に余剰資金として100万円があるなら資産運用を始めるべきだ。
本記事では、100万円でできる運用法や投資目的別・期間別のおすすめ運用法を紹介した。
ぜひ参考にして自分に合った運用方法を見つけ出し、100万円を効果的に投資していこう。
また、100万円を運用する際は「運用の目的や期間を設定する」「市場動向や商品の特徴・リスクを理解する」といったポイントが重要となる。
自分だけで投資を行うことに不安がある方は、投資助言を行う専門家に相談すると良いだろう。
「資産運用ナビ」では、あなたにぴったりの資産運用アドバイザーを無料で紹介するサービスを提供している。
ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を活用し、信頼できるアドバイザーに運用の悩みを相談してみよう。



100万円は“試して学ぶ”のに適した金額です。
リスクを抑えながら分散投資や資産配分を実践することで、将来に活かせる運用スキルと判断力を身につけることができます。
経験を積むことが長期的な資産形成の基盤になります。