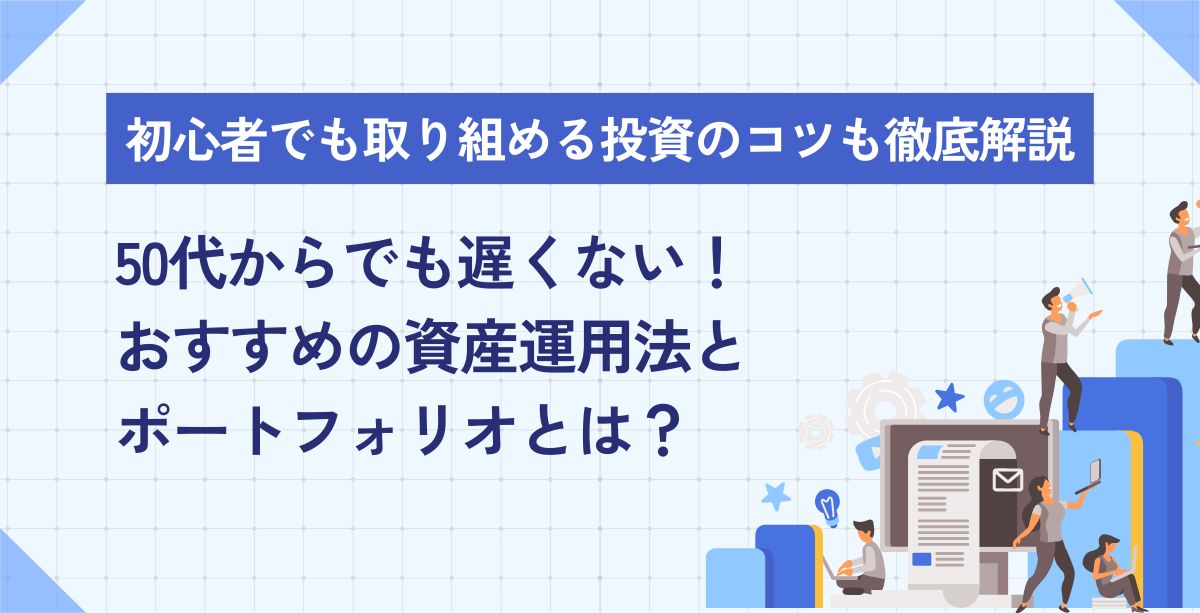- 投資は50代からでも遅くない
- 50代は「コア・サテライト運用」で効率的にお金を増やすのがおすすめ
- 50代におすすめの投資信託はバランス型・インデックス型
- 効率的な投資戦略を立てるなら「資産運用ナビ」でアドバイザーに相談がおすすめ
50代は定年後の豊かな生活のために、将来への備えを視野に入れ始める時期だ。
収入の増加や子供の独立、親からの資産継承、相続等により手元資金に余裕が生まれやすくなり、資産運用を始める人も多く、効率的に運用できれば今からでもお金を増やすこともできる可能性は十分にある。
だが、資産運用をいつから始めるか、またどのような目的で行うかによって、投資家ごとにおすすめの運用法は異なる。また、正直今からどの程度の資金を投資に回すべきなのか、その割合も気になるところではないだろうか。
そこでこの記事では、50代から資産運用を始めようと考えている方に向けて、50代が理解しておきたい資産運用の基本と注意点、そしておすすめの運用ポートフォリオについて解説する。
最後には資産運用のおすすめの相談先についても解説するので、あわせてぜひ参考にしてほしい。
資産運用は50代からでも決して遅くない
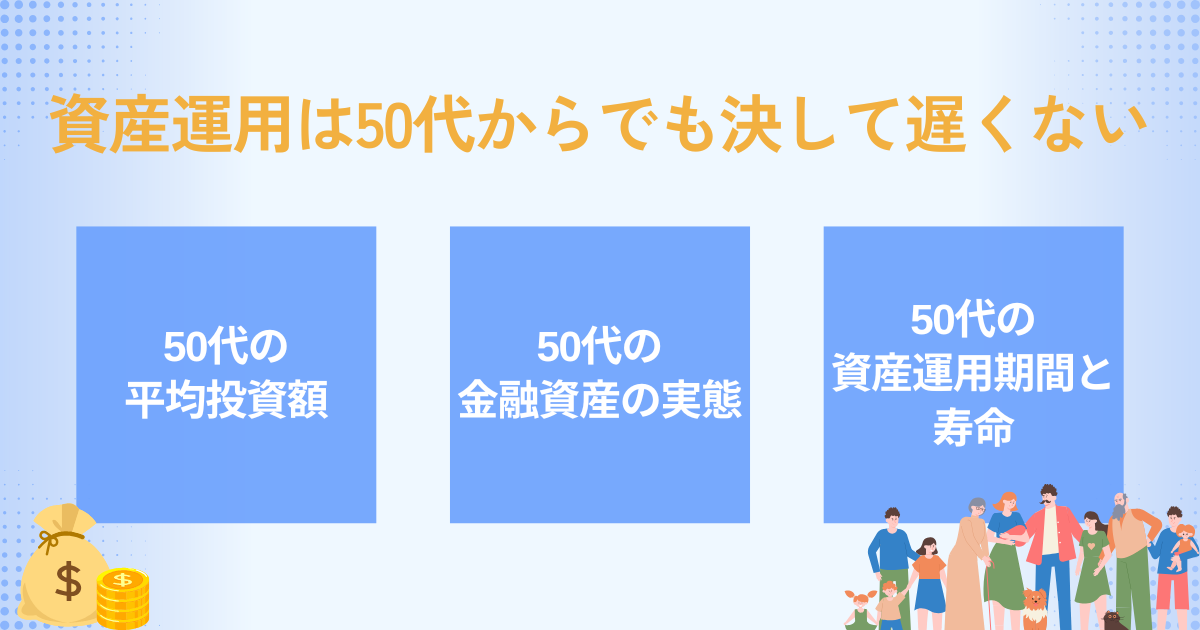
50代から資産運用を始めるのは遅すぎると感じている人もいるかもしれない。
これまで、預貯金や保険だけで過ごしてきた50代も決して少なくないだろう。そんな50代でも資産運用を始めることをおすすめしたい。
デフレの時代は預貯金で持っていることが堅実だった。しかし米やガソリンの価格が高騰し日常生活でもインフレを感じる機会は増えたのではないだろうか。
預貯金だけで資産を守ることは難しい。しかし、資産運用をすれば資産の目減りを防ぎ老後資金を蓄えることができる。
 証券アナリスト 平行秀
証券アナリスト 平行秀50代はまだまだ資産形成に有効な期間です。
特に収入の安定している方であれば、計画的に投資を行うことで老後資金の準備に大きく貢献できます。
重要なのは、リスクを理解した上で無理のない範囲で運用を始めることです。
まず、資産運用を本格的に始めることを検討している50代が知っておくべき以下の3つのポイントを解説する。
- 50代の平均投資額
- 50代の金融資産の実態
- 50代の資産運用期間と寿命
50代が資産運用の必要性を理解して、はじめるきっかけになれば幸いだ。
50代の平均投資額
50代の投資と貯金に関する統計を紹介する。ご自身の資産運用を考える際の一つの参考にしてほしい。
まずは平均投資額について確認してみよう。
| 50代の平均投資額(単身) | 株式 | 債券 | 投資信託 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 220万円 | 75万円 | 138万円 |
| 金融資産保有世帯 | 376万円 | 128万円 | 236万円 |
※全体は金融資産を保有していない世帯を含んだ統計
| 50代の平均投資額(二人世帯以上) | 株式 | 債券 | 投資信託 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 187万円 | 37万円 | 142万円 |
| 金融資産保有世帯 | 268万円 | 52万円 | 204万円 |
※全体は金融資産を保有していない世帯を含んだ統計
こんなに投資しているのかと感じる人もいれば、意外と少ないなと感じた人もいるのではないだろうか。
平均だけをみると単身世帯は株式の投資額が高く、二人世帯以上は投資信託が高めな点が興味深い。
続いて50代が手取りのうちどの程度の割合を株式や債券、投資信託に回しているのかの統計も参考になるので紹介する。
| 金融資産保有世帯のみ | 0% | 5%未満 | 5〜10%未満 | 10〜15%未満 | 15%〜20%未満 | 20%〜25%未満 | 25%〜30%未満 | 30〜35%未満 | 35%以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50代単身 | 36.7% | 7.6% | 13.9% | 10.1% | 2.5% | 7.6% | 2.5% | 3.8% | 15.2% |
| 50代 二人世帯以上 | 37.7% | 13.9% | 15.7% | 13.6% | 6.0% | 5.7% | 3.0% | 2.1% | 2.4% |
単身、二人世帯以上共に最も高いのが0%で約4割近くが株式や債券、投資信託などに手取りを回していない。
資産運用の必要性が強くさけばれるようになったが、株式、債券、投資信託を買っていない層の割合も依然として高いことが分かる。
一方、単身世帯は株式や債券、投資信託に手取りの35%以上を回している人が15.2%と高い。
逆に二人世帯以上は手取りの5%〜15%未満に集中している。同じ50代でも単身世帯と二人以上世帯で資産運用の取り組み方の差を確認できる統計だ。
資産運用をする際に同世代に比べてどの程度、投資をするかの参考にしてみてほしい。
50代の金融資産の実態
続いて50代の金融資産の実態も統計から確認してみよう。単身世帯、二人以上世帯それぞれの金融資産の平均値と中央値、そして目標残高の統計を以下にまとめた。
| 50代の金融資産額(単身世帯) | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 全体 | 1,087万円 | 30万円 |
| 金融資産保有世帯 | 1,859万円 | 600万円 |
| 目標残高 | 2,841万円 | 1,000万円 |
| 50代の金融資産額(二人以上世帯) | 平均値 | 中央値 |
|---|---|---|
| 全体 | 1168万円 | 250万円 |
| 金融資産保有世帯 | 1677万円 | 700万円 |
| 目標残高 | 2,891万円 | 2,000万円 |
50代が目標とする目標残高と金融資産額を比べてみると平均値、中央値ともに全く届いていないことが分かる。
単身世帯、二人以上世帯共に平均値と中央値の差が大きいことも気になる。これは平均値が一部の金融資産保有額が大きい層によって引き上げられるためだ。
より実態に近い中央値に注目すると50代の厳しい現実に気づくことができるだろう。
特に単身世帯50代全体の中央値が30万円というのは衝撃の数字だ。50代と言っても置かれている状況によって格差も大きいようだ。
平均や中央値などの統計で資産運用の方針は決まらないが、ご自身の置かれている状況を客観視するための参考にしてほしい。
ただ、一つ確かなことは50代の金融資産額が目標額との差に大きな開きがあることだ。
多くの50代が目標と現実を埋めるための対策を考える必要があるのではないだろうか。



目標額とのギャップが明確になった場合には、支出の見直しや保険の最適化、資産運用の再設計といった総合的な家計診断が重要です。
現状を正確に把握し、具体的かつ実行可能な対策を講じることが求められます。
50代の資産運用期間と寿命
50代の資産運用期間を以下の2つに分けて考えると分かりやすい。
- 現役期(一般的に65歳まで)
- 約15年前後
- 退職後(一般的に65歳以降)
- 約20年(平均寿命男性81.09歳、女性87.14歳)
- 参考:令和5年簡易生命表
20代〜40代に比べれば資産運用の期間は当然、短くなる。しかし50歳ならば現役期だけでも約15年前後は資産運用をする期間がある。
現役期だけでも15年と考えると決して短くない。
退職後も資産運用は続く。50代の中にはまとまった退職金を受け取る予定の人も多いだろう。
年金と退職金を含む預貯金を取り崩すだけでは資産が一方的に減り続けることになりかねない。
特に政治や経済の変遷次第では、現在の常識や前提条件では考えられないようなことも起こりうる。
資産寿命を延ばし続けることが長寿社会では生活を守るために欠かせない。
日本人の平均寿命は男性で81.09歳、女性で87.14歳だ。長生きする可能性も考えると65歳以降も約20年は資産運用が必要になるだろう。
現役期と退職後あわせて約35年は資産運用期間があると考えて良いだろう。
50代の代表的な投資目的
50代で投資を始める人の主な目的としては、以下のようなものが挙げられる。
- 老後の生活費
- 医療費
- 親の介護費
- 子供の教育費
50代は、会社で役職や責任が増すにつれて収入面ではピークを迎えやすい一方、定年退職が近づき始めることで、徐々に老後の生活を意識し始めるタイミングだ。
老後資金が足りるのか不安になり、50代になってはじめて投資を経験するという方も少なくない。
また、自分の健康面での不安が増してくる世代でもあり、今後の医療費の増加も気になるポイントだ。
50代におすすめの4つの投資法


50代で資産運用を始めた人に代表的なつの投資法を紹介する。
結論から述べると長期・積立・分散投資と運用益を非課税にできる制度の活用が資産運用の基本だ。
投資と聞くと何に投資をすれば良いかを気にする人も多いだろう。
もちろん投資対象の選定や組み合わせも大切だが土台となる考え方から押さえてほしい。
- 長期投資
- 積立投資
- 分散投資
- NISAやiDeCoの活用
リターンを安定させ複利の恩恵を受ける長期投資
資産運用の基本は長期投資だ。長期投資のメリットは大きく分けて以下の3つだ。
- 忙しい人でも取り組みやすい
- 運用成績が安定する
- 複利の効果が得られる
日計りのような短期間で売買を完結させて利益を積み重ねていく取引は働く50代が取り組むには時間も手間も精神的な負担も大きすぎる。
日々の値動きに振り回されながら生活することになるため、働き盛りの一般的な50代が手を出すべきではない。
一方、長期投資ならばせいぜい投資先を必要なときに入れ替えたりするだけで日々の値動きに振り回されずにすむ。
何をいつ買ったり売ったりするのかの判断が少ないため忙しい50代の現役世代におすすめだ。
長期投資の良いところは運用成績が安定するところにもある。
保有期間が短すぎると大きく上がるタイミングに当たることもあれば、下がるタイミングに当たることもある。
しかし、保有期間を長くすることでリターンが平準化していく。
次によく言われるのが複利効果だ。運用益を再投資していくことで効率良く資産形成ができる。長期投資をすると複利効果の恩恵を受けやすくなる。
特に分配金を出さず利益を再投資していくタイプの投資信託で長期投資をすれば効率よく資産形成ができるだろう。



長期投資は、リスク分散だけでなく、ライフプランに合わせた資金準備にも適しています。
特に50代からの資産運用では、目的と金額を明確にしたうえで、老後資金を効率的に準備する手段として有効です。
高値づかみを防ぎ心理的な不安を和らげる積立投資
積立投資の良さは以下の2つだ。
- 高値づかみを防げる
- 心理的な不安を和らげる
値動きのある投資対象は日々、高くなったり安くなったりする。当然、安いときに買える方が良いが売買のタイミングを判断するのは簡単なことではない。
運が悪いと高値づかみをしてしまうこともあるだろう。しかし、買うタイミングを分散させることで取得単価が平均化される。
また実際に投資をしてみると元本割れが怖くなったり、買い遅れたりどうしようと不安になったりすることもあるかもしれない。
特に自分で売買のタイミングを見極めようとすると心理的に厳しいことも出てくるだろう。
しかし、機械的に積立を続けるだけなら心理的な負担を和らげることができる。
50代からはじめても資産運用は長く続けることになる。だからこそ心理的に負担の小さい積立投資がおすすめだ。



毎月一定額を積み立てる仕組みは、収支管理をしながら無理なく資産形成を進めるうえでも重要です。
支出とのバランスを考慮しながら、無理のない金額で設定することが50代からの投資では大切です。
リスクを抑えるなら分散投資
売買のタイミングだけでなく投資対象も分散させた方がよい。
分散投資のメリットは以下の通りだ。
- 特定の投資対象が倒産、デフォルトなどに陥っても損失を限定できる
- 値動きの特性が異なる投資先を組み合わせることで資産の増減が緩やかになる
特に個別株投資は複数の銘柄に分散投資をするのが基本だ。
例えば、手堅そうに感じる銘柄、儲かりそうだと信じた銘柄に一点集中投資をしてしまうと何か不測の事態が起きたときに資産を大きく失うことになりかねない。
例えば東日本大震災(2011年3月11日)に東京電力の株価が暴落したことは50代なら記憶に残っている人も多いのではないだろうか。
1日で2124円から466円と約78%も下げた。安心安全のディフェンシブ銘柄とされるような銘柄でもこのような想定外のことが起きる。
個別株投資の場合、何百銘柄にも分散させる必要はないが5〜20銘柄程度に分散させておくとリスクを抑えられるだろう。
また値動きの傾向が異なる投資対象を組み合わせて買うと投資した資金の増減が緩やかになる。
値動きの増減が平均化されるためだ。資産運用で日々、資産が大きく上がったり下がったりしては落ち着かないだろう。
日々の値動きが緩やかで右肩あがりで上昇していく方が安心して保有できるだろう。



分散投資は「投資の基本」であり、資産形成を長期視点で考える上でも非常に重要です。
リスク許容度に応じたポートフォリオを構築することで、精神的なストレスを軽減し、投資継続力を高めることにもつながります。
非課税の恩恵を受ける NISAやiDeCoを活用した運用
非課税の恩恵を受けられるNISAやiDeCoも積極的に使っていこう。
概要は以下の通り。
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |
| 非課税保有期間 | 無期限 | 無期限 |
| 非課税保有限度額 | 合計1,800万円ただし成長投資枠の上限は1,200万円まで | |
| 投資対象 | 上場株式、投資信託など※一部のリスクの高い銘柄などは除く | 長期・積立・分散投資に適した金融庁の基準を満たした投資信託 |
| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 |
特にNISAは原則60歳になるまで引き出せないiDeCoに比べて利用しやすいだろう。
年間投資できる額や非課税で保有できる限度額、投資できる商品の制限などの縛りはあるが長期・積立・分散投資と相性が良い。
また50代でもiDeCoを始めるのに遅すぎることはない。50代でも加入でき、最長で75歳まで運用できる。
iDeCoは私的年金で将来の備えができる制度。受け取るときは税金がかかるものの運用益は非課税なので効率良く資産形成ができる。
拠出した掛金も全額控除の対象になるため節税にもつながる。
ただし、iDeCoの一時金を60歳で受け取ってから5年あけて退職金を受け取ることで、どちらにも退職所得控除を適用できていた従来の制度(5年ルール)が2026年以降、10年あけなければ適用されなくなった。
つまり70歳で退職金を受け取らない限り従来ほどの節税効果がなくなってしまった。
このような制度変更のリスクに関しては日々のニュースを追っていく必要があるだろう。



NISAとiDeCoは、目的やメリットが異なります。ライフプランや退職後の資金ニーズを踏まえ、どちらを優先すべきか検討することが重要です。たとえば、教育資金や住宅購入など中期的な資金ニーズがある方には、流動性の高いNISAが適しているケースもあります。
50代が知っておくべき投資のコツ


50代が知っておくべき投資のコツを紹介する。証券口座を開くとすぐに何かに投資したくなってしまうかもしれない。
しかし何も考えずに闇雲に投資を始めてしまうと資産運用の目標を十分に達成できないばかりか大切な資産を失うことになりかねない。
50代が知っておくべき投資のコツを以下の5つにまとめた。
- 退職後の収入と支出の見通しを立てる
- 資産運用のシミュレーションをしてみる
- コア・サテライト戦略で安定収益と積極投資
- リスク管理のルールを決める
- 冷静な投資判断と損切りを心がける
投資を始める前に参考にしてほしい。
退職後の収入と支出の見通しを立てる
50代の資産運用は老後資金を十分に用意できるかどうかが大切だ。
老後資金がいくら必要かには諸説があり2,000万円は必要だという意見もあれば足りないという意見もある。
実際のところ退職後にいくら必要になるかは退職後の収入と支出で決まる。
受け取る年金や退職後の仕事の収入でいくら入ってきそうか見通しを立ててほしい。
支出に関しても現在の家計の状況を見直して月にどの程度、必要になりそうか計算してみよう。
また、参考に退職後の平均的な収入と支出を紹介する。
将来の政治経済の動向などで現在の50代が退職する頃にはこのような数値も変わっていくが定期的に収入と支出がどうなるか自分なりに見通しを立てることに意義がある。
| 単身世帯 | 二人以上世帯 | |
|---|---|---|
| 退職後の平均可処分所得 | 114,663円 | 213,042円 |
| 退職後の平均支出 | 145,430円 | 250,909円 |
| 平均可処分所得―平均支出 | -30,768円 | -37,916円 |
ご自身の実態に合わせて収入と支出の見落としを立てて資産運用でどの程度、補う必要があるかの見通しを立てよう。



老後の生活費に加え、医療・介護費や住居修繕費などの一時的支出も見込んだシミュレーションが重要です。
公的・私的年金や退職金の受取時期も確認し、専門家の助言を得ると安心です。
資産運用のシミュレーションをしてみる
- 毎月いくら積み立てるか
- 老後にいくら取り崩せるか
この2つを明確にできれば資産寿命の見通しを立てやすくなる。
資産運用に関するシミュレーションを実際にしてみると、具体的な資産運用の積立額や取り崩せる額の目安が分かるだろう。
シミュレーターには金融庁が提供している以下のようなものがある。
金融庁の公式サイトで利用可能
- つみたてシミュレーター
- ライフプランシミュレーター
他にも民間の金融機関が各種シミュレーターを公式サイトなどで提供している。ご自身が使いやすいと感じたシステムで運用シミュレーションをしてみよう。
コア・サテライト運用で安定投資と積極投資
50代におすすめの運用法の一つとして紹介したいのがコア・サテライト運用だ。
- 例
- バランスファンド
- 80%〜90%
- 例
- 個別株や成長性の高い投資信託など
- 目安10%〜20%
堅実な運用と高いリターンを狙う運用を組み合わせた運用法だ。例えば分散投資の効いたバランスファンドをメインに投資しつつ、高いリターンが狙える個別株を少額だけ投資する。この運用法ならば堅実な運用をしつつ、
成長性の高い銘柄で高いリターンを狙うチャンスも出てくる。50代以降は若い世代に比べて一般的にリスクを抑えた運用をするべきだ。
しかし50代の人の中には、せっかく資産運用をするのだから高いリターンが見込める株や応援したい企業の株に投資したいという人もいるだろう。
コア・サテライトで運用すれば資産を堅実に増やす投資も積極的な投資も両立できる。
リスク管理のルールを決める
資産運用は預貯金と違って元本割れすることもある。基本的にリターンはリスクの対価だ。
リスクとうまく折り合いをつけることが資産運用では欠かせない。リスクを抑えるには損を抑える運用ルールを最初から組み込んでおけば良い。
例えば分散投資をする場合はリスクの高い資産の比率を一定以下に抑える、特定の国や業種に偏りすぎないようにするなどが考えられる。
また、個別株投資を組み入れる場合は一定の額を下回ったら損切りをするなど機械的な売買ルールを設けておくと迷いなく運用が続けやすくなるだろう。
ただしリスク管理とルールづくりは絶対的な正解がないので難しいかもしれない。
具体的なルールづくりに関しては専門書や証券会社のセミナーなどで勉強するのもよい。資産運用のプロに相談してみるのもおすすめだ。
冷静な投資判断と損切りを心がける
50代は資産運用の期間が若年層に比べると限られている。そのため資産運用で大きな失敗や取り返しのつかない損失を被らないように対応することが求められる。
特に日々の値動きを気にしすぎて冷静な判断ができなくなってしまわないように気をつけたい。
予め決めたルールを一貫して守って運用を行うと冷静な投資判断をしやすいだろう。
また、当初の投資をはじめた根拠がなくなった場合に思い切って損切りをする必要も出てくる。
例えば個別株投資で期待していた業績の伸びを維持できなくなった等の理由で投資先に魅力がなくなったら思い切って損切りをして、新しい投資先への資金に充てた方が良いこともある。
50代におすすめの運用ポートフォリオとは?


50代におすすめの運用ポートフォリオについて解説する。資産運用の世界ではポートフォリオをどのように組むかで運用成績が左右される。
そのため投資を始める前に十分、理解しておきたい。
- ポートフォリオの基本
- 50代のポートフォリオの決め方
- 50代におすすめのポートフォリオ
以上3つのポイントを解説するので参考にしてほしい。
ポートフォリオの基本
国内株式や国内債券、外国株式、外国債券、不動産、コモディティなど様々な資産を配分することをアセット・アロケーションと呼ぶ。
そしてアセット・アロケーションによって構成された各種資産の組み合わせのことを資産運用の世界ではポートフォリオと呼ぶ。
ポートフォリオの組み合わせは無限に考えられる。同じ資産の組み合わせでも比率を変えるだけでリスク・リターンも大きく変わってしまう。
例えば同じ株式と債券に投資したポートフォリオでも株式80%債券20%と株式50%債券50%では値動きはかなり変わってしまう。
ポートフォリオを選ぶということは「投資先とその比率を選ぶこと」だと考えれば分かりやすいだろう。
50代のポートフォリオの決め方
50代以降と若年層〜中年層の特性を比較した。
| 所得 | 貯蓄 | 投資期間 | リスク許容度 | |
|---|---|---|---|---|
| 50代以降 | 高 | 大 | 短い | 小 |
| 30〜40代 | 中 | 中 | やや長い | 中 |
| 20代 | 低 | 小 | 長い | 大 |
50代は所得や貯蓄などの余裕資金はあるが、働ける期間は短めだ。そのため資産をなるべく減らさない堅実な運用でリスク許容度を抑えた運用がおすすめだ。
ポートフォリオを構成する資産クラスについて簡単に確認しよう。一概には言えないところもあるが、主な資産クラスのリスク・リターンを比較した。
| 資産クラス | リスク・リターンの比較 | 特性 |
|---|---|---|
| 先進国株式 | 中 | 日本株や米国株など それぞれの先進国の経済成長によるリターン獲得、インフレ対策など。 |
| 新興国株式 | 高 | 中国やASEAN諸国などの新興国株 新興国の経済成長の恩恵を受けてリターン獲得、インフレ対策など |
| 先進国債券 | 低 | 米国債、日本国債、企業の社債など 株に比べて安定した資産。リスクを抑えるならポートフォリオに入れたい |
| 新興国債券・ハイイールド債 | 中 | ブラジル国債、中国国債、信用格付けの低い債券など 先進国の債券に比べて金利が高く高めのリターンが狙える |
| 不動産 | 低〜高 | REITなど インフレ対策や株、債券との分散効果 |
| コモディティ | 低〜高 | 金、原油、天然ガスなど インフレ対策や株、債券との分散効果 |
50代でリスクを抑えた運用をする場合、リスクが相対的に低い債券をポートフォリオに組み込む必要があるだろう。
その上で目標リターンに応じて株式などをどの程度、組み込むかを決めてほしい。



50代の資産運用では、「いつ使うお金か」を明確に分けて考えることが重要です。
近い将来使う予定がある資金は、元本割れリスクの低い運用(個人向け国債や定期預金など)に、10年以上先に使う資金は成長性のある資産(株式など)に配分するといった“目的別の運用”を意識しましょう。
50代におすすめのポートフォリオ
リスク許容度に応じて50代におすすめのポートフォリオを3つ紹介する。
それぞれ参考にしてほしい。
伝統的なアセットアローケーション
| 資産配分 | 株式60% 債券40% |
|---|
伝統的な資産クラスである株式と債券のみで構成されたポートフォリオだ。
60:40は伝統的な資産配分の比率として知られている。リスク許容度を抑えた運用をする場合、債券の比率をどこまで高めるかが基本になる。
まずはこの伝統的な比率をもとにリターン重視なら株式70%債券30%、安定重視なら株式50%債券50%など比率を変えて調整してみると良いだろう。
有名ファンドマネージャー考案
| 資産配分 | 株式(S&P500)30% 長期米国債 40% 中期米国債 15% 金 7.5% コモディティ 7.5% |
|---|
米国の著名なファンドマネージャーのレイダリオが考案したポートフォリオだ。
資産クラスとしてはリスクが高めの米国株式を30%に抑えて、債券の比率が55%と高い。
残りの15%を近年、インフレもあり上昇している金を含めたコモディティにも広く分散している。
近年、年金の運用でも知られるGPIFも株式と債券だけでなく金や暗号資産をはじめとしたオルタナティブ資産への分散投資に対する情報提供を求める動きがあった。
運用の多様化の流れをご自身の資産運用に組み込む場合、コモディティをポートフォリオに入れることを検討しても良いだろう。
売れ筋のバランスファンドのポートフォリオ
| 資産配分 | 国内株式12.5% 先進国株式12.5% 新興国株式12.5% 国内債券12.5% 先進国債券12.5% 新興国債券12.5% 国内不動産12.5% 先進国不動産12.5% |
|---|
50代以降の投資家にはインデックスファンドよりも、複数の資産クラスに分散投資してリスクを抑えられるバランスファンドがおすすめだ。
このポートフォリオは大手ネット証券のバランスファンドの中でも売れ筋の投資信託「eMAXIS Slim8資産均等型」の構成だ。投資信託を買うだけで簡単に再現できる。
人気の「eMAXIS Slim全世界株式」通称オルカンも有名だが、国や業種は広く分散されている。しかし、資産クラスは株式100%だ。
そのため50代以降の投資家のポートフォリオとしてはややリスクが高い。
全ての資産クラスが株式では、リスクが高いと不安を感じている投資家ならばeMAXIS Slim8資産均等型も選択肢に入るだろう。



50代は「守りの資産形成」にシフトするタイミングです。
バランスファンドのように自動で資産配分が調整される商品は、運用経験が少ない方にも有効です。ただし、定期的にポートフォリオを見直しましょう。
ニーズ別|50代主婦・50代独身者におすすめの運用戦略


ここからは、主婦と独身者のケース別に、最適な運用戦略や具体的な運用法について解説していく。
50代主婦におすすめの運用戦略
50代主婦が資産運用を始める場合、適切なポートフォリオを構築した上で、正しくリスク管理を行うことが重要だ。
安定的な資産運用を行うための具体的な投資方法について解説していく。
年代に合ったリスク管理の重要性
どれだけリスクを許容できるか、というリスク許容度は、年代によって異なるのが一般的だ。
20代や30代であれば、多少ハイリスクな金融商品を購入して損失が発生したとしても、その後長い時間をかけて損失が回復する可能性が高い。
しかし、50代は老後までそれほど時間が残されていないため、大きく損失が発生するようなハイリスク商品は避ける方が良いだろう。
ただし、人によっては金融資産が潤沢にある場合など、50代であっても問題なくリスクを取れるケースもある。
年代に合わせた一般的なリスク許容度を知りつつ、自分が許容できるリスクについて考えるのが重要だ。



リスク許容度の判断には、資産額だけでなく支出予定や年金見込み、介護リスクなどを含むライフプラン全体の視点が重要です。
単に年齢だけで判断せず、包括的な将来設計の中で総合的に判断しましょう。
安定的な資産運用のためのポートフォリオの構築
安定的に資産を増やしていくことを考えるのであれば、「なんとなく良さそう」と思った金融商品を購入していくのではなく、しっかりとポートフォリオを構築するのが重要だ。
ポートフォリオとは、資金をどんな金融商品にいくら投じるかという資産の組み合わせのことを指す。
「国内債券は○%、国内株式は○%」といったように、あらかじめ配分比率を決めておくことで、計画的に資産運用を行いやすくなるだろう。
ポートフォリオは一度組んだらそれで終わりではなく、定期的に見直すことも重要だ。
相場の変動に合わせて組み入れ比率を調整したり、投資ニーズの変化に応じてポートフォリオの配分を変更したりすることで、より効果的な資産運用を行える。
専業主婦でも実践可能な投資法の具体例
専業主婦が初めて資産運用を行う場合、新NISAのつみたて投資枠を活用して積立投資を行うのがおすすめだ。
まずは、少額の余剰資金から積立投資を始めてみよう。
NISAのつみたて投資枠で運用できる金融商品は、金融庁の基準を満たす一定の投資信託に限られているため、初心者でも選びやすいというメリットがある。
まずは、運用コストが比較的低いバランス型の投資信託を選んでみよう。
世界中の資産にバランスよく分散投資することで、リスクを減らしながら安定したリターンを期待しやすくなる。
投資に慣れてきた場合や、ある程度自分で運用したいという場合は、いくつかの投資信託を組み合わせてポートフォリオを組むのも良いだろう。
50代独身におすすめの運用戦略
次に、50代独身の方におすすめの運用プランを紹介していく。資産状況やリスク許容度に応じたプランを3つ紹介していくので、自分に合ったものを選んで資産運用に活かそう。
おすすめプラン①
1つ目は、日本の年金を管理・運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)と同一のポートフォリオで運用するプランだ。具体的には「国内株式25%・外国株式25%・国内債券25%・外国債券25%」という資産配分で運用を行い、安定した資産成長を目指す。
株式と債券は相関性が低い資産となっており、どちらか一方が下落する局面ではもう一方が上昇しやすいという特徴がある。それぞれの資産をバランス良く保有することで、分散効果を高めて安定したリターンを狙える。
また、国内外の資産を組み合わせることで投資対象地域を分散できるという点も、このポートフォリオの強みだ。幅広い資産に分散投資を行い、リスクを抑え込みながら安定した収益を目指すことができる。
投資信託のなかには国内外の株式・債券にバランス良く投資するファンドもあるため、個別の銘柄を選定する必要もない。GPIFの運用ポートフォリオを参考に、資産運用を始めてみると良いだろう。
おすすめプラン②
2つ目は、配当や分配金による定期収入を狙った運用プランだ。具体的には高配当株式・ETFやREIT(不動産投資信託)といった投資商品を活用し、定期的なインカムゲインを目指す。
前述の通り、高齢者の単身世帯では生活費として毎月およそ3万円が不足する計算となっている。50代のうちから定期収入を得られるポートフォリオを構築しておくことで、退職後の不足分をカバーできる可能性が高くなる。
例えば、1,200万円を利回り3%で運用することで年間36万円(毎月3万円)の定期収入を得ることが可能だ。退職するまでは配当金や分配金を使わずに再投資することで、より多くのインカムゲインを得られるようになっていく。
ただし、ある程度まとまった資産がないと十分な定期収入にはならない。50代時点で1,000万円ほどの資産がない場合は、インカムゲイン狙いのプランよりも資産を増加させるための戦略をおすすめする。



定期収入を目的とした資産運用は年金補完に有効ですが、配当等は課税対象である点にも注意が必要です。
医療・介護費も見据え、手取り収入を考慮した収支シミュレーションを行うことが重要です。
おすすめプラン③
3つ目は、現物の不動産を購入して賃貸に出し、入居者から受け取る家賃収入で資産を増やすという運用プランだ。不動産物件は比較的高額であるためハードルは高いものの、まとまった定期収入を得られる点が大きな魅力である。
50代前半であれば年齢的にもローンを組むことができ、自己資金だけで物件を購入する必要はない。一般的に50代は高年収で社会的信用力も高いため、比較的有利な条件で融資を受けられる可能性がある。利回りが高い物件を選べれば家賃収入からローンを返済でき、ローンが完済したらそのまま家賃収入を得ることが可能だ。
50代後半になるとローンを組める可能性は低くなるため、自己資金を準備する必要がある。ある程度まとまった資金を準備できているのであれば、資産の一部を活用して不動産物件を購入してみても良いだろう。
2つ目のプラン同様、退職後も継続的な定期収入を得られる点が不動産投資の魅力だ。ローンや自己資金を活用し、不動産投資を実践してみても良いだろう。
50代の資産運用を成功させるなら「資産運用ナビ」で専門家に相談しよう


50代の資産運用を成功させるために実践してほしいのが「ゴールベースアプローチ」だ。
資産運用の先進国であるアメリカでは広く普及している考え方だ。資産運用や投資はあくまでも人生を豊かにするための手段だ。
そのため明確なゴールを決めて、それを実現できるように進めていくのがおすすめだ。
そこで、ゴールベースアプローチを実践するための50代が資産運用を始める流れを紹介する。
また資産運用をするなら専門家に相談するべき理由と具体的な探し方についても解説する。
50代が資産運用を始める流れ
50代が資産運用を始める流れは以下の通りだ。
- 資産運用のゴールを決める
- 実現シナリオの設定
- 投資手段の選択と実行
- 見直し(レビュー)
この1〜4を繰り返していく。それぞれの内容を解説する。
①資産運用のゴールを決める
まずは資産運用の目標を明確にしよう。目標を決めないまま投資を始めても方向性が定まらずうまくいかないだろう。
投資を始める前に自分自身や家族と向き合って目標を決めてほしい。
例えば老後に不安のない生活をしたい、子どもや配偶者に資産を残したい、海外に移住してセミリタイアしたいなど実現したいゴールをリストアップしてみよう。
②実現シナリオの設定
目標が決まったら優先順位と達成可能性を総合的に勘案して実現できそうなシナリオを設定する。
現在の収入や資産を踏まえて、実現するためにはどの程度の投資期間やリスクをとる必要があるのか考えてみてほしい。
③投資手段の選択と実行
シナリオを実現するために必要な投資手段の選定をする。
ここでリスク許容度と目標リターンに応じたポートフォリオをはじめとした具体的な方針を決める。そして投資を始めよう。
④見直し(レビュー)
定期的に目標や資産運用の結果などを見直す機会を設けよう。
資産運用を続けているとゴールや生活や投資を取り巻く市況などが変わってしまうこともあるだろう。
ポートフォリオのリバランスなども必要になるはずだ。資産運用は一度、決めれば終わりではない。定期的な見直しを続けることが大切だ。
資産運用を専門家に相談するべき理由
資産運用のゴールベースアプローチを一人で実践するのは難しいと感じた人も多いのではないだろうか。
目標を決めても実現できそうなシナリオの設定、リスク許容度に応じた投資手段の選定、ポートフォリオを組む際に迷ったり戸惑ったりする人も多いだろう。
知識と経験がなければ、なかなかうまくいかないはずだ。
そこで専門家に相談してほしい。一人では紹介したゴールベースアプローチを実践した資産運用は難しい。
しかし、専門家と相談すれば客観的なアドバイスをもとに資産運用に必要な流れを進められる。
また、資産運用を続けていくには継続的な見直しが欠かせない。そのため、生涯にわたって長く相談できる専門家を探してほしい。
専門家に相談するなら「資産運用ナビ」
資産運用のことを相談できる専門家が身近にいないという人も多いだろう。そこで活用してほしいのが「資産運用ナビ」だ。
専門家を探せる検索サービスで全国どこからでも無料で利用できる。
専用のフォームに相談したい内容などを入力して送信すれば、あなたのニーズにあった資産運用の専門家のプロフィールを閲覧できる。
「資産運用ナビ」に登録している専門家は、相談者の収入や支出、家族構成、将来のライフプランなどを踏まえて、個別の事情に最適化した資産設計や運用計画を立ててくれる。インターネットや書籍の一般的な情報では対応しきれない、きめ細やかなアドバイスが受けられるのが大きな強みだ。
また、専門家のサポートを受けることで、情報過多や自己判断による迷いを避け、冷静かつ効率的に資産運用を進められる。プロの経験や知見に基づく客観的な分析を得られるため、安心感も大きく、不安や感情に流されずに長期的な運用を継続しやすくなるのも大きなメリットだ。
「資産運用ナビ」ならプロフィールを事前に確認して相談してみたい専門家がいれば無料で相談できる。
50代の資産運用についても具体的なアドバイスをしてもらえるはずだ。相談してみて信頼できそうな専門家なら資産運用のパートナーとして指名もできる。
担当者選びが運任せになってしまう金融機関よりも、あなたにあった専門家がきっと見つかるはずだ。
50代でも資産運用は遅くない!資産運用ナビで相談しよう!
50代の資産運用について解説した。若年層〜中年層に比べると50代が資産運用できる期間は短いかもしれない。
しかし50代以降の人生も長い。特に日本人の平均寿命を考えると50歳から投資を始めるなら余裕をもって35年程度は資産運用をする期間があると考えても良いだろう。
老後資金を守るには資産寿命を延ばすことが必要だ。
資産寿命を延ばすには老後の生活の収支のバランスをとることはもちろん、資産運用をするのがおすすめだ。
特にインフレで物価が高騰し先行きも不安な時代だからこそ資産寿命を延ばせる運用のメリットが大きい。
この記事では50代の資産運用の基本となる長期・積立・分散投資やポートフォリオの考え方を紹介した。
基本的にはリスク許容度を抑えた堅実な運用をおすすめする。
そして、資産運用を本当に成功させるためには50代一人ひとりの目標や状況にあった資産運用が必要だ。
特にゴールベースアプローチを通した資産運用を実践するなら、専門家の客観的なアドバイスや専門的な知見が欠かせない。
資産運用の専門家に相談すればきっとあなたのための具体的なアドバイスが期待できる。
「資産運用ナビ」を活用してあなたの資産運用のパートナーを探してほしい。



老後資金の見積もりや生活設計を踏まえたうえでの資産運用は極めて重要と考えます。
収支シミュレーションやライフプランを明確にすることで、どの程度のリスクを取れるか、どの運用スタイルが適しているかを具体的に判断しやすくなります。