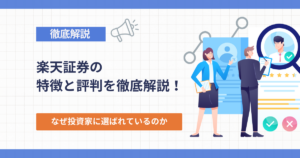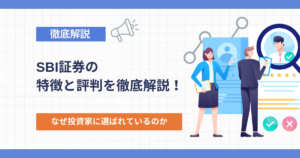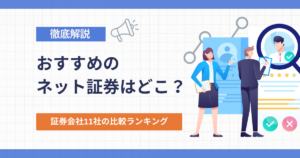※本ページはアフィリエイトリンク(広告)を含みます
- 三菱UFJ eスマート証券の特徴とメリットを知りたい
- 三菱UFJ eスマート証券がおすすめな人を知りたい
- 三菱UFJ eスマート証券にはどのようなデメリットがあるか知りたい
三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)は、2025年1月、三菱UFJ銀行の100%子会社となり、2月「三菱UFJ eスマート証券」へ社名変更した。
MUFGとKDDI株式会社の業務提携契約に基づき、今後もau経済圏におけるネット証券の役割を担い続け、従来と同じサービス・機能を提供している。今後もauカブコム証券の強みを活かしつつ、サービスレベルの向上を図っているのだ。
そんな三菱UFJ eスマート証券は、Pontaポイントを貯めて投資信託を購入できるなど、特にauユーザーへおすすめの証券会社だ。
今回は三菱UFJ eスマート証券について、特徴やメリット、デメリットを紹介していく。
三菱UFJ eスマート証券の利用を検討している方はぜひご覧いただきたい。

三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)の特徴とメリット

三菱UFJ eスマート証券の特徴は主に以下の4つである。
- Pontaポイントが貯められる
- 手数料割引サービスが豊富
- じぶん銀行の円普通預金金利100倍
- 1株から取引可能
1つずつ紹介していく。
Pontaポイントが貯められる
三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)では取引する度にPontaポイントを貯められる。
特にauPayカードを使って投資信託を積み立てるだけで、投資金額1%がPontaポイントとして還元される。
au回線やUQモバイル利用者ならさらに4%上乗せされて最大5%まで還元可能だ。
獲得したPontaポイントは、1ポイント1円で投資信託を購入できる。
その他にも日々の買い物でポイントを使うのも良いだろう。
様々な用途に使いやすいPontaポイントがもらえるのは、三菱UFJ eスマート証券のメリットといえる。
手数料割引サービスが豊富
三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)には、様々な方を対象とした豊富な割引サービスが用意されている。
三菱UFJ eスマート証券自体の基本的な手数料コースは、大きく2種類ある。
- 1日の取引金額に応じて手数料が決定する「1日定額手数料コース」
- 1回の取引金額に応じて手数料が決定する「ワンショット手数料コース」
これら2種類のコースの手数料から、以下の割引サービス対象者は自動的に割り引かれる。
| 割引サービス名 | 対象者 | 割引率 | 適用コース |
|---|---|---|---|
| シニア割引 | 満50歳以上 | 60歳以上:4% 50歳以上60歳未満:2% | ワンショット手数料 1日定額手数料 |
| NISA割 | NISA口座開設者 | 開設年数ごとに1%加算(最大5%) | ワンショット手数料 1日定額手数料 |
| 株主推進割引 | 対象銘柄購入者 | 最大10% | ワンショット手数料 |
| auで株式割 | au ID登録者 | 1% | ワンショット手数料 1日定額手数料 |
| au割 + | KDDI(9433)株式保有者 | 最大15% | ワンショット手数料 1日定額手数料 |
1日定額手数料コースにおける割引は、国内現物株式と国内信用取引の手数料が対象だ。
ワンショット手数料コースでは、投資信託や特定銘柄の国内現物株式が対象となっている。
ちなみに割引サービスは併用可能だ。
じぶん銀行の円普通預金金利が100倍
三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)とauじぶん銀行を連携する「auマネーコネクト(auじぶん銀行自動引落)」を行えば、じぶん銀行の円普通預金金利が0.10%へアップする。
通常金利は0.001%なので、およそ100倍も金利を上げられるのだ。
三菱UFJ eスマート証券へ入金せずとも、じぶん銀行から自動的に引き落とされるので入金の手間がかからない。
また三菱UFJ eスマート証券で取引に使われていない資金は自動的にじぶん銀行へ手数料0円で出金される。
金利を上げられて、入出金もスムーズになる便利なサービスといえるだろう。
1株から取引可能
三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)では「プチ株(単元未満株)」という1株から購入できるサービスがある。
直近では米国株も1株から購入できるようになり、より幅広い選択肢を提供できるようになった。
もちろん保有株数に応じて配当金も受け取れる。
NISA対応で取り扱い銘柄数も多いため、NISA制度の利用や少額投資を検討している方にもおすすめだ。
三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)のデメリット

三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)のデメリットは大きく以下の3つが挙げられる。
- 手数料が割高
- クレカ積立の毎日設定は不可
- リアルタイム入金対応銀行は少なめ
それぞれ解説していく。
手数料が割高
三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)で100万円以上取引する場合、他社よりも手数料が割高となる。
以下は1回あたりの取引金額で決定する「ワンショット手数料コース」の手数料を比較した表である。
| 取引金額 | 三菱UFJ eスマート証券(現物) | SBI証券(現物) |
|---|---|---|
| 100万円~150万円 | 約定金額×0.099%+99円(上限4059円) | 640円 |
例えば、現物株式を1回150万円取引する手数料はSBI証券の方が割安となる。
- 三菱UFJ eスマート証券
- 1,584円
- SBI証券
- 640円
100万円以下であれば手数料に違いはないものの、高額取引を検討している方には少々不利となる点に注意していただきたい。
クレカ積立の毎日設定は不可
三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)では、クレジットカードを使って毎月100円から積立投資できる。
しかし、購入タイミングは1ヵ月に1度のみと決められており、毎日購入する投資方法は選べない。
毎月第1営業日に一括して購入されるため、積立日を指定できず自由度に欠けるというデメリットもある。
なおクレカ積立は他社でも基本的に日時指定できないものがほとんどだ。
給料日に合わせて設定するなど細かくカスタマイズしたい場合、クレカ積立以外の投資方法を選ぶことになる。
リアルタイム入金対応銀行は少なめ
三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)へリアルタイム入金できるサービスに対応している銀行は少なめだ。
対象銀行は以下の4つである。
- 三菱UFJ銀行
- 三井住友銀行
- auじぶん銀行
- みずほ銀行
普段使っている銀行が上記の4つの中にあれば、問題ないだろう。
しかし対象銀行以外の場合、銀行振込となるので入金から反映まで少々時間を要する可能性がある。
三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)がおすすめな人

メリットとデメリットを踏まえ、三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)の利用がおすすめな人は以下の通りだ。
- 信頼できる運営元の証券会社を使いたい人
- 割引サービス対象の人
- auユーザー、UQモバイル利用者
三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)は2025年1月に三菱UFJ銀行の100%子会社となり社名変更した証券会社だ。
そのため、「よく知らない企業のサービスを使いたくない」という方でも安心して利用しやすい。
また自分自身が手数料割引サービスの対象者なら、よりお得に取引可能だ。
他にもau PayやUQモバイルなどを使えば受けられる特典も多くなるため、auユーザー向けの証券会社といえるだろう。
自分に合った証券会社を選ぼう
今回は三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)の特徴とメリットデメリットについて紹介してきた。
三菱UFJ eスマート証券のリアルタイム入金に対応している銀行口座を保有していれば、スムーズに投資が始められる。
投資信託やプチ株(単元未満株)を購入しながら、Pontaポイントをお得に貯められるauユーザーの強みを活かせる証券会社といえるだろう。
また一方で、資産運用をやってみたいが、どの様にして運用して良いか悩んでいる人も多いのではないだろうか。
最近、「よく分からないまま資産運用をして何百万円も損をした」という話をよく聞く。
そんな時は、「資産運用ナビ」に相談をしてはいかがだろうか。
プロの視点から資産運用の疑問を解決し、納得した上で資産運用を行おう。
現在、下記ボタンから申し込むと無料で資産運用の相談にのってくれる。