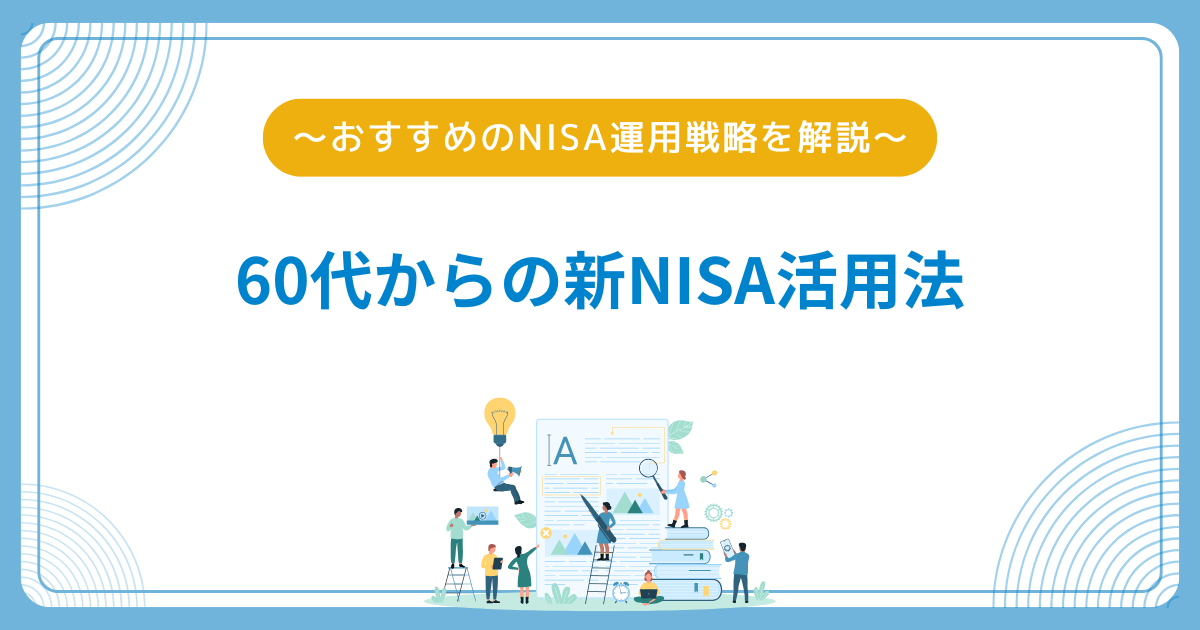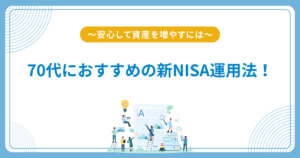※本ページはアフィリエイトリンク(広告)を含みます

新NISAがスタートし、ますます資産運用を始める人が増えている。
一方で「60代から始めても良いのだろうか」と悩み、新NISAを始めるきっかけを見失っている人もいるだろう。
本記事では、新NISAが60代からでも利用すべき理由やおすすめの投資戦略、適切な積立投資額を解説していく。
新NISAを活用した資産運用においておすすめの相談先も紹介するので、ぜひ本記事を参考に新NISAを始めてみてはいかがだろうか。
おすすめの新NISA相談先はこちら
新NISAが60代からでも遅くない理由

「新NISAは60代から始めても意味がない」などと考えている方も多いのではないだろうか。
特にこれまで投資をしてこなかった人は「いまさら投資を始めても遅い」と考えるケースが少なくない。
しかし、60代であっても新NISAを利用した投資は始めるべきである。
ここでは、新NISA制度の概要を解説し、60代で新NISAを活用するメリットについて紹介していく。
新NISAの概要
NISAは、国民の資産形成を推進するために2014年に導入された「少額投資非課税制度」である。
2024年には制度の改正が行われ、より資産運用に活用しやすい「新NISA」として生まれ変わった。
新NISAでは、一定の非課税投資枠内で購入した株式や投資信託の利益に対し、税金がかからない仕組みとなっている。
本来であれば株式・投資信託で得られる売却益や配当金などの利益には20.315%の税金が発生するが、NISA口座内で購入していた場合は非課税となる。
例えば100万円の利益が生じた場合、本来は約20万円が課税されて手元に残るのは80万円になってしまう。
しかしNISAであれば利益の100万円を丸ごと受け取れるため、効率的に資産運用を行えることが特徴だ。
2つの非課税投資枠
新NISAでは「つみたて投資枠」「成長投資枠」という2つの非課税投資枠が設けられている。
いずれも非課税で投資できることに変わりないが、投資限度額や対象商品が異なるため注意しておこう。
つみたて投資枠は、年間120万円までの積立投資で得られる利益が非課税となる投資枠だ。
対象商品は金融庁が設けた基準を満たす投資信託のみとなっており、投資方法も積立投資に限定される。
株式を購入したり、自由なタイミングで商品を買い付けたりすることはできない。
成長投資枠は、年間240万円までの投資で得られる利益が非課税となる投資枠だ。
上場株式・投資信託が対象となっており、投資方法も積立投資・一括投資の両方に対応している。
つみたて投資枠よりも自由度が高い運用を行えることが成長投資枠の特徴だ。
2つの非課税投資枠を合計し、年間360万円・生涯1,800万円までの非課税投資枠が与えられる。
それぞれの非課税投資枠の特徴を理解し、効果的に活用していこう。
新NISAでの変更点
2024年から始まった新NISAは、旧NISAと比べて以下のような点が変更されている。
| 旧NISA | 新NISA | |||
|---|---|---|---|---|
| 投資枠の 名称 | つみたてNISA | 一般NISA | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
| 口座開設 期間 | 2042年まで (新規買付は2023年まで) | 2023年まで | 無期限 | |
| 年間投資枠 | 40万円 | 120万円 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税期間 | 最大20年 | 最大5年 | 無期限 | |
| 非課税保有 限度額 | 800万円 | 600万円 | 1,800万円 (成長投資枠は1,200万円) | |
| 非課税 投資枠の 併用 | 不可 | 可能 | ||
従来は期間が定められていたNISA制度だが、新NISAからは制度の期間が恒久化されて非課税期間も無期限となっている。
非課税で投資できる枠も拡大された上に2つの投資枠を併用できるようになっているため、より自由度の高い資産運用を行えるようになったことが新NISAの特徴だ。
60代が新NISAを活用するメリット
60代の方が新NISAを活用するメリットとして以下の2点が挙げられる。
- 資産運用に資金を投じる余裕がある
- 十分に運用期間を取れる
60代になると多くの場合、子どもが独立したり、住宅ローンを払い終えたりして支出が減少する。
その分だけ資産運用に資金を投じる余裕が生じ、新NISAを有効に活用できる。
非課税のメリットをより活かしやすい点が60代からでも新NISAを始めるべき理由のひとつだ。
また、近年の日本は「人生100年時代」と言われており、60代からでもまだまだ長生きする人が多い。
新NISAは年齢制限がなく、非課税期間も無期限化されているため、60代でも十分に非課税のメリットを受けられる。
生涯にわたって非課税の恩恵を受けるためにも、新NISA制度を始めてみよう。
60代の新NISAはつみたて投資枠から始めるのがおすすめ

先ほど新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類があると解説したが、60代から新NISAを利用するのであれば、つみたて投資枠から始めることをおすすめする。
ここでは、つみたて投資枠の利用を推奨する理由や投資すべき商品の特徴、おすすめのネット証券を紹介していく。
つみたて投資枠を推奨する理由
60代からの新NISAでつみたて投資枠の利用を推奨する理由として、主に以下の2点が挙げられる。
- 商品がすでに絞り込まれている
- 運用リスクを抑えやすい
前述の通り、つみたて投資枠で購入できる商品は金融庁が設けた基準を満たす投資信託のみとなっている。
厳選された銘柄のなかから選べるため、投資先を探しやすい点がつみたて投資枠のメリットだ。
成長投資枠の場合、投資信託だけでも数千本の選択肢があり、そこに上場株式が加わることを考えると投資先を選ぶことは容易ではない。
投資経験が少なく、これから新NISAを始めたいのであれば商品が絞り込まれたつみたて投資枠を活用すると良いだろう。
また、運用リスクが抑えやすい点もつみたて投資枠のメリットだ。
金融庁がつみたて投資枠の商品を選定する基準は「長期・積立・分散に適した銘柄」となっており、基本的には低リスクで運用できる商品である。
さらに投資方法は積立投資のみであるため、購入タイミングを分散してリスクを抑えることができる。
上記の2点を踏まえると、60代から新NISAを始める際にはつみたて投資枠から始めるべきと言えるだろう。
投資すべき商品の特徴
つみたて投資枠で投資すべき商品の特徴として以下の3点を押さえておこう。
- 長期的なリターンを期待できる
- 地域が広く分散されている
- 分配金が再投資される
新NISA制度は非課税期間が無期限となっており、長期投資を行うことで大きな効果を発揮する制度だ。
投資先を選ぶ際も長期的に安定したリターンを期待できそうな銘柄を選定しよう。
過去の運用パフォーマンスをチェックし、値動きが安定している銘柄を選ぶことを推奨する。
また、投資対象の地域が広く分散されている銘柄もおすすめだ。地域が分散されることで特定の地域の要因に左右されにくくなり、リスクを軽減できる。
できるだけ世界中の国や地域に分散された銘柄を選択しよう。そして、分配金が再投資されるタイプの銘柄を選ぶことも重要だ。
投資信託では得られた収益を投資家に分配する仕組みとなっているが、分配金は受け取るよりも再投資に回した方が投資効率が高まる。
資産が雪だるま式に増えていくため、分配金が再投資される銘柄を選ぶと良いだろう。
上記3つのポイントを押さえ、自分に合った銘柄でつみたて投資枠での運用を始めてみよう。
おすすめのネット証券
つみたて投資枠を活用して資産運用を始める場合、金融機関に口座を開設しなければならない。
おすすめのネット証券として以下の2つを紹介する。
- SBI証券
- 楽天証券
それぞれの特徴について解説していく。
SBI証券
SBI証券はSBIグループ傘下の大手ネット証券だ。
SBIグループの証券口座開設数は国内で初めて1,300万口座を突破し、2025年オリコン顧客満足度調査ではネット証券第1位に選ばれた。
多くの個人投資家から人気を集めている証券会社だ。
SBI証券は投資信託の売買手数料が無料となっており、つみたて投資枠の取扱商品は250本(2025年1月時点)と非常に多い。
取引コストを抑えやすく、豊富な商品ラインナップから投資先を選べることが特徴だ。60代からのつみたて投資枠の活用に向いていると言えるだろう。
また、三井住友カードおよびOliveでのクレジットカード積立を利用すると、積立額の最大3%が還元されるサービスも提供している。
資産運用におけるリターンに加え、ポイント還元を受けられる点も大きな魅力である。
貯めたポイントはショッピングだけでなく、株式や投資信託の購入にも活用可能だ。
そして、SBI証券は国内株式の手数料が無料となっている点も強みである。
つみたて投資枠での運用に慣れ、成長投資枠で株式の運用を始めるときに大きなメリットとなるだろう。
「取引にかかるコストを抑えたい」「ポイントを効率良く貯めたい」という方は、SBI証券でつみたて投資枠の運用を始めてみてはいかがだろうか。
\ 累計口座数1,000万突破!手数料無料で取引するなら /
楽天証券
楽天証券は、SBI証券と並んで個人投資家から高い人気を集める大手ネット証券だ。
総合口座数は1,100万口座(2024年4月時点)を超えており、口座開設時のアンケート(2024年1月〜6月)では投資未経験者の割合が83.4%だった。
投資経験が少ない初心者から支持を集めている証券会社だ。
楽天証券ではNISAの取引手数料が無料となっており、投資信託や国内株式、米国株式、海外ETFの取引手数料が一切かからない。
日本円と米ドルのリアルタイム為替手数料も無料となっており、極めて低いコスト水準で運用を行えることが特徴だ。
つみたて投資枠の対象商品も241銘柄を取り扱っており、充実した商品ラインナップを提供している。
また、楽天証券では楽天カード・楽天キャッシュを利用した投信積立で1年間で最大27,000ポイントが貯まる。
貯めた楽天ポイントは楽天グループのサービスやショッピングでの利用に加え、株式や投資信託の購入代金に充てることも可能だ。
普段から楽天ポイントを貯めている人にとっては非常にメリットが大きい。
さらに楽天証券の総合口座を持っている場合、おすすめのマネー本やマネー雑誌を無料で閲覧できる。
日経テレコン(楽天証券版)も無料で利用可能となっており、投資に関する情報収集をしやすい環境が整っている。
知識を身に付けながら、投資を実践できる点も大きな魅力だ。
「普段から楽天グループのサービスを利用している」「投資に関する知識を身に付けたい」という方は、楽天証券にNISA口座を開設してみてはいかがだろうか。
60代は新NISAで毎月いくら積み立てるべき?将来いくらになる?

60代で新NISAのつみたて投資枠を利用する場合、毎月の積立額はいくらに設定すべきなのだろうか。
また、積立投資を継続した場合、将来いくらになるのだろうか。
ここでは、適切な積立額と運用シミュレーションを紹介していく。ベストな積立投資額を見極めつつ、シミュレーション結果をモチベーションにしよう。
余剰資金での運用が鉄則
積立投資額については「〇〇円にすべき」という具体的な金額はない。自分にとっての余剰資金の範囲内で運用を行うことが大切だ。
積立投資は比較的リスクを抑えやすいものの、投資である以上はリスクを抱える可能性が十分にある。
直近で使う予定がある生活費や緊急用の資金まで投資に回してしまうと、損失を抱えたときに生活に支障をきたしてしまう。
必ず「多少損失を抱えても問題ない」という資金を投資に回すように心掛けよう。
余剰資金の算出方法は一般的に「生活費の半年〜1年分を除いた額」と言われるが、60代の方はもう少し余裕を持っておきたい。
生活費の2年〜3年分を確保し、残った金額を投資に回すと安心だ。
総務省統計局の「家計調査」によると、世帯主が60歳以上の世帯における1ヶ月の平均消費支出は226,966円となっている。
単純計算で約540万円〜810万円が2年〜3年分の生活費となる。540万円〜810万円ほどを預貯金で確保し、残りを新NISAに回すと良いだろう。
そして金融広報中央委員会の「(参考)家計の金融行動に関する世論調査[総世帯](令和5年)」によると、60歳代の金融資産保有額は平均1,862万円である。
預貯金で確保する分を差し引くと1,000万円〜1,300万円となり、10年かけて積み立てる場合は月8〜10万円、20年で積み立てる場合は月4〜5万円となる。
上記の計算はあくまでも平均的な生活費・貯蓄額をもとに計算したものだ。自分の生活費や資産状況に合わせ、無理のない範囲で積立額を設定しよう。
少額からでも始めることが重要
余剰資金があまり多くないと「少額で投資をしても意味がない」と感じてしまう方もいる。
しかし、まずは少額でも良いので資産運用を始めることが重要だ。
少額から投資を始めるべき理由として以下の2点が挙げられる。
- 非課税期間をできる限り長く活用するため
- 複利効果を利用するため
少額の投資であっても、新NISAを利用していれば非課税の恩恵を受けられる。
少しでも早く運用を始め、できる限り非課税期間を長く活用することが大切だ。
また、複利効果を活用するという意味でも少額投資から始めることが重要となる。
複利効果とは、投資で得た利益を再び投資に回すことで利益が新たな利益を生む仕組みのことだ。
少額投資の場合は得られる利益が多くないものの、その利益を元本に加えていくと少しずつ得られる利益が増える。
最初は少額からの投資であっても、時間を味方につけることで資産が雪だるま式に増えていく。
複利効果を最大限に活かすには運用期間を長く設定する必要があるため、少額からでも早めに投資を始めることが大切だ。
積立投資シミュレーション
実際に積立投資を行った場合、運用成果はどれくらいになるのだろうか。ここでは以下の条件に基づいて積立投資シミュレーションを行う。
- 月1万円・10万円・30万円の3つの積立額を設定
- 運用期間は5年・10年・20年に設定
- 年間の利率は3%で固定
上記の条件でシミュレーションを行ったときの積立元本と運用利益の合計額は以下の表の通りだ。
| 5年 | 10年 | 20年 | |
|---|---|---|---|
| 月1万円 | 647,402円 (積立元本:60万円) | 1,397,919円 (積立元本:120万円) | 3,276,606円 (積立元本:240万円) |
| 月10万円 | 6,474,024円 (積立元本:600万円) | 13,979,191円 (積立元本:1,200万円) | 32,766,056円 (積立元本:2,400万円) |
| 月30万円 | 19,422,071円 (積立元本:1,800万円) | 41,937,574円 (積立元本:3,600万円) | 98,298,167円 (積立元本:7,200万円) |
いずれのパターンでも運用期間が長くなるほど資産が増加していることが分かる。
月1万円の積立でも時間を味方につけることでしっかりと資産が増えていくため、少額から投資すべきか迷っている人はぜひ始めてみよう。
なお、新NISAの非課税投資枠は合計で1,800万円であることに注意が必要だ。
上記の表のなかには積立元本が1,800万円を超えているものがあるが、1,800万円以上の部分については課税されることを頭に入れておこう。
NISAのこと、
誰に相談する?
簡単な質問に回答するだけ!
あなたに合う資産運用アドバイザーを紹介
\ 簡単60秒!相談料はずっと無料 /
成長投資枠との併用は必要?60代が新NISAが上手に活用するコツ

先ほど「60代からの新NISAはつみたて投資枠から始めるべき」と解説したが、成長投資枠は使うべきなのだろうか。
ここでは、成長投資枠と併用すべきケースや成長投資枠に適した商品の特徴、効果的な活用法を紹介していく。
成長投資枠と併用すべきケース
すでにつみたて投資枠で運用を行っている人が成長投資枠も併用すべきケースは以下の通りだ。
- 余剰資金がある
- 家族のために資産を増やしておきたい
- 個別株式に興味がある
つみたて投資枠は年間120万円(月10万円)の積立投資が上限となっている。
しかし、なかには月10万円を積立投資に回しても余剰資金が残っているというケースがあるだろう。
つみたて投資枠を利用した上で余剰資金がある場合、成長投資枠との併用を検討してみると良い。
そして、余剰資金がある前提の上で「家族のために資産を増やしたい」という方は、成長投資枠との併用がおすすめだ。
60代を過ぎると資産の相続について考える人が増え始め、少しでも家族に残しておきたいと考える方は多い。
預貯金のみで運用するよりも、成長投資枠を活用して資産の増加を目指していくと良いだろう。
また、個別株式に投資をしてみたいという方も成長投資枠との併用を検討すべきだ。
つみたて投資枠では個別の株式は売買できず、投資信託の積立のみに限られてしまう。
「成長企業を応援したい」「配当金を受け取りながら投資を楽しみたい」という方は、成長投資枠の併用がおすすめだ。
ただし、あくまでも余剰資金の範囲内で行うことを徹底し、投資先を分散させながらリスクを抑えた運用を行うことが重要である。
成長投資枠に適した商品の特徴
60代の方が成長投資枠を利用して運用する場合、選ぶべき商品の特徴は以下の通りだ。
- 地域が分散されている
- 値動きが落ち着いている
- 運用コストが低い
まず、投資対象地域が分散されている商品を選択することが大切だ。
複数の地域に分散されていると特定の地域のリスク要因に左右されにくく、安定した収益を期待できるためである。
また、値動きの安定性が高い商品を選ぶことも重要である。
60代の方はなるべくリスクを抑えた運用が推奨されるため、短期的な価格変動が大きい商品は避けよう。
そして、商品の運用コストも比較しておきたい。比較的自由な売買ができる成長投資枠だが、基本的には長期投資が推奨される。
運用期間が長くなると運用コストの差も開いていくため、できるだけコストが低い商品を選択することが大切だ。
上記の特徴を踏まえた上でのおすすめ商品を2つ紹介する。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は、全世界の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す投資信託だ。
投資対象地域が日本を含む全世界に分散されており、比較的安定した値動きとなる点が魅力の商品である。
信託報酬(運用コスト)は年率0.05775%と極めて低い水準になっており、長期運用に適した銘柄だ。
投資対象が株式である分、ややリスクが大きいため、リスク許容度が高い人におすすめの商品である。
〈購入・換金手数料なし〉ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
〈購入・換金手数料なし〉ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)は、国内外の株式・債券に分散投資を行う投資信託だ。
国内株式・先進国株式・国内債券・先進国債券に25%ずつ投資を行い、安定的なリターンを目指している。
信託報酬(運用コスト)は年率0.154%と低水準であり、長期的に運用を継続しても負担は大きくならない。
複数の投資対象に分散し、安定したリターンを目指したい人におすすめの商品だ。
NISAを効果的に活用する方法
成長投資枠を含めたNISA制度を上手く活用するポイントとして、以下の3点を押さえておこう。
- 減らさない運用を意識する
- NISA以外の運用方法も組み合わせて分散投資する
- 専門家に相談する
60代は主な収入源が年金のみとなるケースが多く、大きな損失を抱えてしまうと老後生活に支障をきたす恐れがある。
リスクを取って積極的に増やそうとするのではなく、堅実に減らさないような運用を心掛けることが大切だ。
また、NISA制度では株式や投資信託、ETFにしか投資することはできない。
より分散効果を高めるためにも、NISA以外の投資方法を組み合わせてリスクを抑えていくことが大切だ。
具体的には個人向け国債や不動産投資などが選択肢に挙げられる。
そして、専門家への相談も検討しておきたい。資産運用の助言を行う専門家に相談し、自分にとって最適なNISAの活用法を提案してもらうと良いだろう。
60代が新NISAを始めるなら「資産運用ナビ」で専門家に相談しよう

60代から新NISAを始めるのであれば、資産運用の助言を行う専門家に相談すると良い。
相談先を探せるサービス「資産運用ナビ」を活用し、信頼できる専門家に新NISAについて相談してみよう。
ここでは、新NISAを専門家に相談すべき理由や「資産運用ナビ」の特徴・利用方法について解説していく。
ぜひ参考にしてベストな相談先を見つけ出そう。
60代から始める新NISAの難しさ
60代からの新NISAでは以下のような点でハードルを感じる方が多い。
- 商品を選ぶことが難しい
- 適正な投資額を見極めることが難しい
- いつ売却すべきか分からない
新NISAは、成長投資枠で数千の選択肢があり、商品が厳選されているつみたて投資枠であっても数百銘柄から選ばなければならない。
数ある商品のなかから自分に合ったものを選ぶことは簡単ではなく、挫折してしまう人も多い。
また、毎月の積立投資額の適正額を見極めることが難しい点も新NISAのハードルのひとつだ。
現状の資産状況や生活費、運用目標などの複数の要素を考慮しなければならず、自分に合った投資額を決定できないケースが多い。
そして、運用の出口戦略も新NISAの難しいポイントだ。
「いつから資産の取り崩しを始めるべきか」「どの程度の割合で取り崩していくべきか」など、運用資産の売却について悩んでしまうパターンも多い。
上記のような点で新NISAが難しいと感じる方は、資産運用の助言を提供する専門家に相談すると良いだろう。
専門家に相談すべき理由
新NISAでの運用について専門家に相談すべき理由として「最適化された投資戦略を提案してもらえる」という点だ。
あなたの状況にマッチした戦略を助言してくれるため、効率的に資産運用をスタートできる。
近年はインターネットやSNS等で投資情報にアクセスできるようになっており、専門家の助言は必要ないと考えている方も多いだろう。
しかしインターネット等の投資情報はあくまでも「一般向けにおすすめの情報」であり、あなたの状況を考慮したものではない。
個々の資産状況や家族構成、年齢、運用目標、リスク許容度などによって適切な投資戦略は異なるため、一般向けにおすすめされている情報が自分に合っているとは限らない。
資産運用の助言を行う専門家は、あなたの資産状況や運用目標、リスク許容度などを丁寧にヒアリングしながら投資戦略を構築していく。
あなたに向けてカスタマイズした投資戦略を提案してくれるため、安心して資産運用を始めることが可能だ。
自分に合った投資戦略で効率的に資産運用を始めるためにも、専門家に相談することを検討しよう。
「資産運用ナビ」を活用しよう
自分に合った相談先をお探しの方は「資産運用ナビ」の利用がおすすめだ。
「資産運用ナビ」は、あなたに合った資産運用の専門家を自動で診断し、マッチングさせるサービスである。
「資産運用ナビ」を利用する手順は以下の通りだ。
- 専用フォームに希望条件を入力する
- 希望条件に基づいたアドバイザーが自動で抽出される
- 紹介されたなかで気になるアドバイザーを選ぶ
- 初回面談の日程を調整する
- アドバイザーと初回面談を行う
フォームに希望条件を入力したら、あとは紹介されたなかから気になるアドバイザーを選ぶだけで良い。
アドバイザーのプロフィールが公開されているため、事前に経歴や得意分野、保有資格などをチェックした上で申し込むことが可能だ。
もちろんアドバイザーの紹介は全国47都道府県で行っており、オンラインでの面談にも対応している。
アドバイザーの紹介料や相談費用は無料となっているため、気軽にプロとマッチングできることが特徴だ。
ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を利用し、信頼できるアドバイザーを探してみてはいかがだろうか。
60代から新NISAを効果的に活用しよう
60代であっても運用期間は十分に確保可能であり、非課税メリットも享受できるため、新NISAの活用は有力な選択肢である。
運用を開始するにあたっては、まず値動きの幅が比較的小さな「つみたて投資枠」から着手し、時間を味方につけた複利効果による資産形成を目指すのが賢明だ。さらに、つみたて投資枠を活用しても資金に余裕が残るならば、成長投資枠の併用も検討すべきである。ただしその際は、投資対象地域を広く分散させ、価格変動が比較的落ち着いた商品を選定し、元本を極力減らさない運用姿勢を徹底しよう。
もし銘柄選定や運用方針に不安が残る場合は、資産運用の専門家に相談することをおすすめする。専門家に相談することで、個々の状況に応じて最適なアドバイスを受けることができ、それによって効率的に運用を行うことができるだろう。
「資産運用ナビ」では条件に合うアドバイザーを無料で紹介している。この機会にこうしたサービスを活用し、自分に合った担当者と新NISAを軸にした投資戦略を相談してみよう。