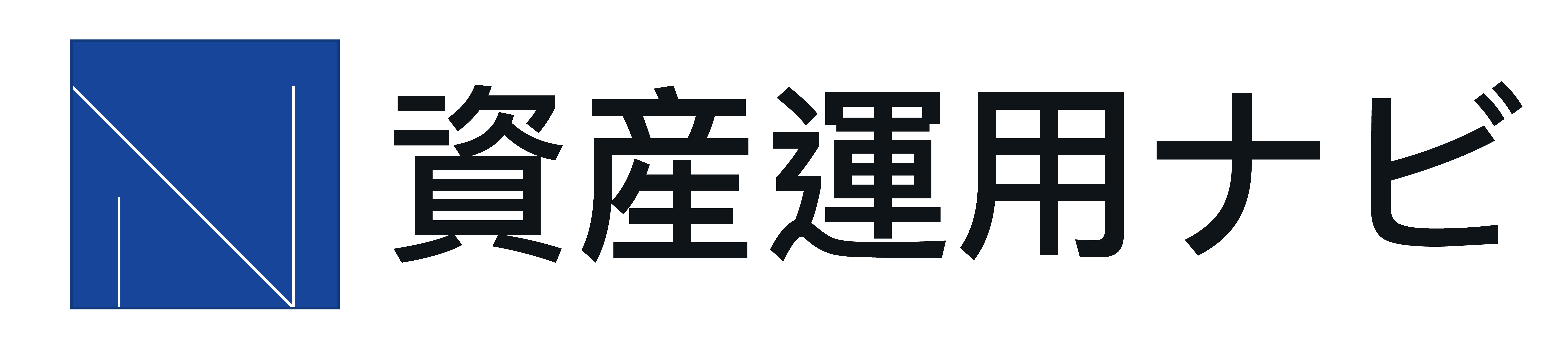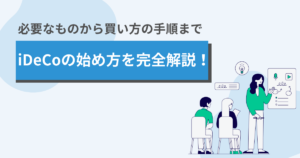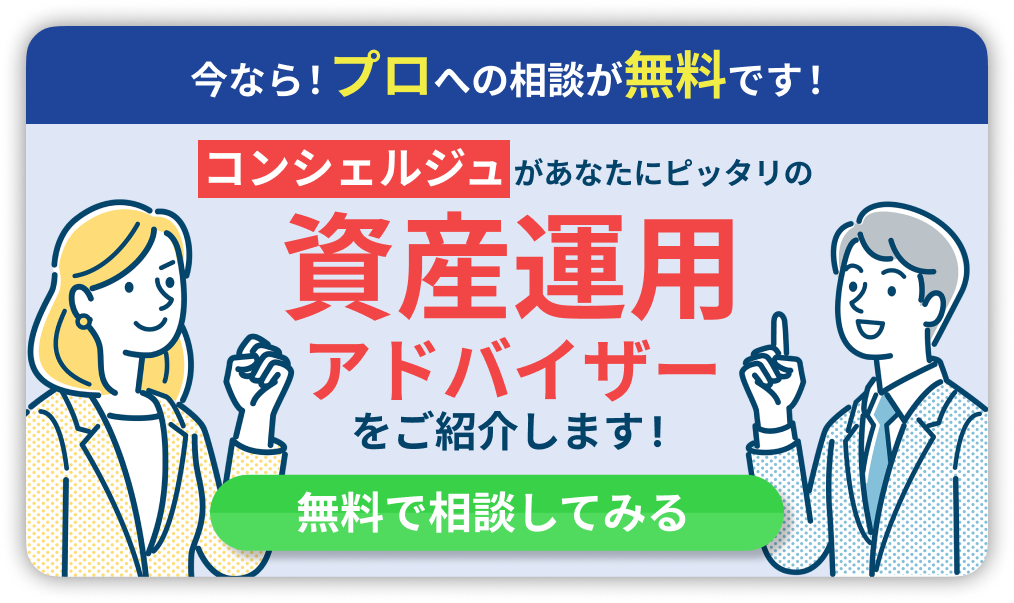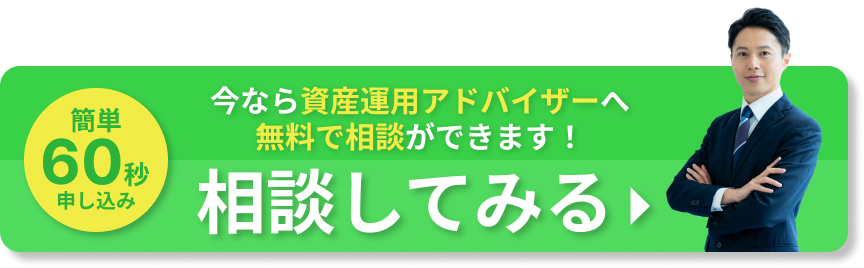- 各年代に適したiDeCoの運用法が知りたい
- 年代別におすすめのiDeCoの商品が知りたい
- 自分に合った方法でiDeCoを活用したい
iDeCoの運用では、引き出し可能年齢(原則60歳)までの残り時間に合わせた適切な商品選定が重要だ。
年齢によってリスク許容度や投資目標が変わるため、20代、30代の若年層から50代、60代のシニア層まで、それぞれの年代に適した運用戦略を立てる必要がある。
本記事では、iDeCoでの効果的な運用方法と年代別におすすめの商品選びについて詳しく解説する。
これからiDeCoでの運用を始めようという方から見直しを検討している方まで、幅広く活用できる内容となっている。
長期的な資産形成の実現に向けたポイントを、運用例や商品例を交えて紹介しているので、ぜひ参考にしていただきたい。
【年代別】若年層におすすめのiDeCo戦略

ここからは、20代から30代の若手におすすめのiDeCoでの資産運用について解説していく。
年齢とリスク許容度の関係などの基本的事項についても説明しているので、30代以降の方にも目を通していただきたい。
20代・30代の商品選びのポイント
まずは、20代や30代がiDeCo運用の商品を選ぶ際の考え方について整理していこう。
若い投資家は、長い時間軸と高いリスク許容度を活かして、積極的な運用戦略を検討することが効果的である。
年齢とリスク許容度の関係
投資商品は、自分のリスク許容度に合ったものを選ぶべきだ。
これは、個人の財務状況や心理的な耐性に応じた適切なリスクレベルの投資が、長期的に安定した資産形成を可能にするからである。
リスク許容度とは、投資による損失をどれだけ受け入れられるかを示す指標で、一般的に年齢とともに低下する。
- 時間分散効果
- 若いほど投資期間が長く、市場の短期的変動を吸収しやすい
- 回復までの時間的余裕
- 損失が生じても、若いうちは回復を待つ時間が十分にある
- 将来の稼得能力
- 若い世代は今後の収入増加が期待でき、現在の資産へのリスクを取りやすい
- ライフステージの柔軟性
- 若いうちは、結婚、子育て、住宅購入などのライフイベントに柔軟に対応できる
リスクとリターンのバランスを取る
20代や30代からiDeCo投資を始める人は、年齢だけを考慮すれば、比較的高めのリスクを取ることができる。
一般的に、リスクとリターンは比例関係にある。たとえば、株式はリスクが高い分リターンも高く、債券はリスクもリターンも比較的低い。
投資では、これらの資産クラスを組み合わせて個人のリスク許容度に合わせた資産配分を行う。
そのため、「高めのリスクを取れる若い人」は、株式比率を高めに設定して高いリターンを狙えるのだ。
それでは、20代や30代の適切な株式配分はどの程度だろうか。年齢に基づく資産配分の一般的な指針として「100 – 年齢」がある。
ただし、平均寿命が伸びた現在では、「110 – 年齢」や「120 – 年齢」の方が適切だと言われることもある。
これを適用すると、20〜30代なら「株式比率80〜90%、債券比率10〜20%」が目安となる。
20代〜30代ににおすすめの運用例
さて、「株式比率80〜90%、債券比率10〜20%」というザックリとした資産配分を商品選定に落とし込むため、ここでは「ターゲットデート・ファンド」の配分を参考にしてポートフォリオを組むことを試みる。
ターゲットデート・ファンドとは、特定の将来の目標年(一般的には退職時期)を基準に設計された投資信託だ。40年ほど先に目標年を置き、5年刻みで商品が設計されることが多い。
iDeCo運用なら、受給開始年を目標年に設定するのが適切だろう。20代や30代なら2055年、2060年、2065年が目標年となる。
そこでここでは、現時点から約35年後の2060年をターゲットと定めた商品を確認していく。
以下は、「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)」と、「マイターゲット2060(確定拠出年金向け、野村アセット)」の資産配分だ。フィデリティは成長を狙う配分で、野村はより安定的な配分となっている。
| フィデリティ2060 (2024年4月30日現在) | 野村マイターゲット2060 (2023年6月28日現在) |
|---|---|
| 株式:97.6% 日本 14.9% 先進国 67.4% 新興国 15.3% | 株式:71.1% 日本 45.9% 外国 25.2% |
| 債券:1.8% グローバルETF 1.0% 米国債券ETF 0.7% | 債券:28.8% 国内債券 19.0% 外国債券 9.8% |
フィデリティ2060は野村と比べると、株式比率が大幅に高い商品だ。
新興国に15%以上を配分しているため、成長市場からの利益を享受しやすく、長期的にはより高いリターンが見込まれる。
一方、野村は、資産を守ることに目的を置いており、国内資産への配分も債券比率も高い。
日本市場の好調時には有利に働く可能性があるが、世界的な成長からの恩恵は限定的になる。
どちらも設計意図は明確で、資産配分は合理的である。大きなリターンを狙うならフィデリティ、安定を求めるなら野村の配分を参考にするのが良い。
中間を取るなら株式比率を80%程度にすると良いだろう。
各ファンドを参考に調整する際は、以下の点に注意して欲しい。
フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド2060
- 株式比率が非常に高いため、放置すると後々高いリスクを負担することになりかねない。定期的に見直しを行い、資産配分を調整する必要がある
- 短期的な市場変動に対して脆弱な面があるため、これに耐性が必要になる
- ポートフォリオの安定性を高めるために、国内資産または債券部分の比率を増やす調整を加えると良い
(野村)マイターゲット2060
- 安定的な配分のため、運用状況の確認にあまり時間がかけられない方や、リスクを取りたくない人にはおすすめである
- ただし、国内資産および債券の比率が高いため、リターンは限定的になる可能性がある
- 株式では、国内資産への配分を減らし、グローバル分散投資の商品を組み込むことで、リスクを抑えつつリターンを狙うことができる
20〜30代におすすめの運用商品
資産配分ができたら、これに合わせて商品を選択していこう。
参考にした資産配分を実現するための商品選択の方法と、投資家ごとにアレンジを加える方法を紹介する。
資産配分に基づき商品を選ぶ
まず、参考とするファンドの資産配分を、性質の似た商品で実現する方法を試してみよう。
iDeCoの運用は、運営管理機関(金融機関)を複数持つことはできない。一つの機関で、すべての商品を選択して運用する。
たとえばSBI証券で運用するなら、同社のiDeCoセレクトプランの運用商品(2024年6月現在37商品)から選択しなければならない。
SBI証券の取り扱い商品でフィデリティ2060を再現するなら、以下のような組み合わせが考えられる。
株式比率が高いバランス型投資信託を選ぶ
1つの商品で運用したい場合は、株式比率が高めのバランス型投資信託を選択する方法がある。
また、金融機関にターゲットデート・ファンドの扱いがあれば、これも一つの選択肢となる。
ただし、株式比率の高いバランス型の提供がない場合、リターンが限定的になる可能性が高い。
また、ターゲットデート・ファンドは信託報酬等の手数料が高く設定されている商品が多いため、その分リターンが減少することは認識しておいて欲しい。
自分のポートフォリオに追加したい商品を入れる
iDeCo以外でも資産を運用している方は、全体の資産配分をバランスさせるか、不足している資産を補うために商品を選ぶこともできる。
SBI証券のセレクトプランなら、以下のような商品を組み入れてみるのも面白い。
- レオス-ひふみワールド年金
- 中長期的視点で資産の形成が期待できる
- アクティブ運用のグローバル株式ファンドである
- 運用者の判断による銘柄選択の付加価値を期待できる面白さがある
- SBI – SBI – PIMCO 世界債券アクティブファンド(DC)
- 資産の多様性を増やしたいが、リターンも求める投資家に適している
- 先進国債券と新興国債券を組み合わせることで、安定と成長が期待できる
【年代別】中高年層におすすめのiDeCo戦略

ここからは、40代と50代向けに、iDeCoで運用する商品選びのポイントを解説する。
この年代の投資家は、積極的な投資が可能な30代までとは異なり、リスク許容度が徐々に低下し、より保守的なアプローチが必要になる。
収入がピークに達し、蓄積された資産の保全も重要になってくるからだ。
40代・50代の商品選びのポイント
40代と50代では、投資商品選びの注意点に明確な違いがある。
40代はまだある程度積極的な運用ができるが、50代はより慎重な運用が求められる。
40代と50代はリスク許容度が大きく違う
40代は多くの場合、子育てや教育費の負担が大きいが、キャリアの絶頂期にあり、収入が最も高い時期だ。
まだ15-25年程度の就業期間が残っているため、ある程度高いリスクを取ることができる。
一方、50代は子育てなどの出費が一段落し、自身の老後資金に注力できる時期に入る。
キャリアの後半で収入は安定しているものの、今後の大幅な増加は見込みにくい。そのため、リスク許容度が低下し、より保守的な運用が求められる。
これらの違いを踏まえ、それぞれの年代での注意点は以下のようになる。
40代が商品を選ぶ場合の注意点
- 成長性を維持しつつ、リスクを管理したバランスの取れたポートフォリオ構築を構築する
- まだ20年以上の投資期間があるため、短期的な予測ではなく長期的視点で商品を選定する
- 自身のキャリアや収入の将来性を考慮し、それに応じたリスク設定を行い商品選定に反映させる
- ライフステージの変化やに合わせて、資産配分を調整する
50代が商品を選ぶ場合の注意点
- 退職が近づくにつれ、ポートフォリオのリスクを徐々に低下させる必要がある。具体的には、株式の比率を下げ、債券や安定的な資産の比率を上げていく
- 配当や利子収入など、安定的なインカムを得られる商品を検討する
- 退職後の生活に備え、高い流動性のある商品を選択する
- 完全にリスクを避けるのではなく、インフレに負けない程度のリターンを目指すよう心がける
- 退職後の収入計画を意識し、iDeCoからの受け取り方法(一時金か年金か)を考慮した商品選択を行う
40代におすすめの商品と運用例
ここでは、20〜30代投資家のセクションで行ったように、ターゲットデートファンドの資産配分を参考に、具体的な商品を使ったポートフォリオ例を紹介する。
40歳が60歳で引き出しを開始する場合、目標年は2045年となる。
45歳なら2040年だ。「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド (ベーシック)」はアグレッシブな設計なので、65歳での引き出しを想定する場合でも、2040か2045を参考にすることをおすすめしたい。
| フィデリティ2040 (2024年4月30日現在) | フィデリティ2045 (2024年4月30日現在) |
|---|---|
| 2024から約15年運用 | 2024から約20年運用 |
| 株式:64.5% 日本 9.8% 先進国 45.4% 新興国 9.3% | 株式:73.7% 日本 10.8% 先進国 51.5% 新興国 11.4% |
| 債券:36.3% グローバルETF 19.9% 米国債券ETF 16.4% | 債券:25.8% グローバルETF 14.4% 米国債券ETF 11.5% |
資産配分を再現してみる
フィデリティ2045の資産配分を、楽天証券iDeCoセレクション(2024年6月現在36商品)の商品で作ったポートフォリオは、以下のとおりだ。
いずれの商品も低コストで、それぞれの資産クラスのパフォーマンスを効率的に捉えることができるインデックスファンドを中心に選択した。
このポートフォリオをよりアグレッシブにしたいなら、「ラッセル・インベストメント外国株式ファンド(DC向け)」は、検討に値する。
同商品は、複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行っているアクティブファンドで、市場平均を上回るリターン獲得が期待できる。
バランスファンド1本で運用する
1本で運用したいなら、「セゾン・グローバルバランスファンド」は魅力的な選択肢となろう。
低コストのインデックス運用で定評のある米バンガードのファンドを採用しており、運用にかかるコストを抑えつつ幅広い分散投資を実現している。
50代におすすめの商品と運用例
50代なら、5年から10年の運用期間を想定するのが妥当だろう。
受給開始可能年齢まで「10年しかない」と考えるか「10年もある」と考えるかは人による。
一般的には元本確保型商品に多くを振り向けるべきだと言われるが、50代に入って資金に余裕が出てきたという方は、無理に株式の比率を下げる必要はない。
| フィデリティ2030 (2024年4月30日現在) | フィデリティ2035 (2024年4月30日現在) |
|---|---|
| 2024から約5年運用 | 2024から約10年運用 |
| 株式:37.1% 日本 5.1% 先進国 26.8% 新興国 5.2% | 株式: 51.3% 日本 7.9% 先進国 35.5% 新興国 7.9% |
| 債券:66.1% グローバルETF 36.5% 米国債券ETF 29.7% | 債券:49.9% グローバルETF 27.5% 米国債券ETF 22.4% |
資産配分を再現する
楽天証券iDeCoセレクションでフィデリティ2035を再現する場合でも、おすすめ商品の基本は40代と同じだ。
リスク許容度が低い場合は、日本債券型を組み入れたいところだが、楽天におすすめできる商品がない。この場合、バランス型かターゲットイヤー型の組み入れを検討すると良いだろう。
ポートフォリオに高めのインカム収入要素を加えるなら、先進国と債券の比率を下げて「みずほUSハイイールドファンド<DC年金>」を組み入れるのも面白い。
また、日本を除く先進国のREITに幅広く投資できる「三井住友・DC外国リートインデックスファンド」を加えれば、分散とともにインフレヘッジとしての機能も期待できる。
1本で運用する場合の選択肢
バランス型なら、おすすめはやはり「セゾン・グローバルバランスファンド」である。パフォーマンスが安定しており、信託報酬も低く設定されている。
資金に余裕があって、iDeCoでは株式のみでよいという方には、「楽天・全米株式インデックス・ファンド」は魅力的な選択肢となる。
大型株から小型株まで約4,000銘柄をカバーしており、単一の商品で十分な分散が図れるうえ、管理費用(信託報酬)が0.162%と非常に低いため長期投資に適している。
【年代別】シニア世代におすすめのiDeCo戦略

ここでは、60代以上のiDeCo活用戦略を解説する。
すでに受給可能年齢を迎えたからといって、運用による資産拡大を諦める必要はない。
60代がiDeCoで商品選びをする際のポイント
60代のiDeCo加入者が商品を選ぶ際には、以下のポイントを考慮することが重要になる。
- 積立期間が最長でも5年と短いため、リスクの高い商品は避け、安定的な運用を心がける
- 受給開始を遅らせる場合で、他に資産がある場合などは、ある程度のリスクを取ることも検討できる。あくまでも自身の状況で商品を選ぶこと
- 家計収支や資産全体を確認し、自身がいまどのような状況にあるかを確認する。退職後の生活に不安が残る場合は、退職時期を遅らせることや、運用期間を伸ばすことも検討し、それを商品選定に反映させる
- iDeCo以外の資産状況も考慮し、全体的なポートフォリオのバランスを取る。
iDeCoでの運用資産がある60代の場合
ここでは、60歳時点にiDeCoでの運用資産が300万円ある投資家を想定し、松井証券のiDeCo取扱商品(2024年6月現在40商品)でポートフォリオを組み立てている。
65歳で一時金として受給する場合
一時金で受け取る場合、まず優先すべきは元本保全である。
一部を株式やREITなどのインフレヘッジ商品に投資して長期的な購買力を維持しつつ、流動性の高い資産に配分した。
- 債券(安定的な収入源)
- 70%
- 株式(インフレヘッジ)
- 20%
- REIT(インフレヘッジ)
- 10%
- 流動性資産
- 20%
上記の資産配分は、以下のようにバランス型に債券型を加える商品構成で実現した。
債券型や流動性資産の比率を増やすことで、簡単にリスクを下げられるメリットがある。
65歳から年金形式で受給する場合
iDeCo運用資産が300万円ある投資家で、65歳から毎月3万円を10年間年金形式で受け取りたい方向けのポートフォリオである。日本株式へのエクスポージャーを増やした。
60歳から運用を開始する場合
一方、60歳からiDeCoで運用を開始し、70歳から受給開始するケースは、これまでと少し異なる考え方をする。
この場合も元本保全は重要な課題となるが、資産の保全を優先しつつも、インフレに対抗するためのリターンを追求する必要があるからだ。
年3%〜5%のリターンを目標とすることで、リスクを抑えつつも資産の実質価値を維持することができる。
リターン目標を4%に設定するなら、資産クラスの平均リターンから鑑みて、以下のような資産配分が適当となる。
- 株式
- 40%
- 債券
- 45%
- REIT
- 10%
- 現金・短期金融資産
- 5%
この場合のおすすめの商品は、以下のとおりである。投資効率を最大限に上げる必要があるため、低コストの「eMAXIS Slimシリーズ」でまとめている。
年代別におすすめのiDeCo戦略が知りたいなら誰に相談するべき?

ここまでの説明で、「iDeCoの運用には、年代に応じた戦略が重要だ」ということを十分ご理解いただけたと思う。
しかし、iDeCoでの運用成功には、商品選びだけでなく、自分に適した金融機関を選ぶことも不可欠となる。
このとき、頼りにしていただきたいのが、独立系フィナンシャルアドバイザー「IFA」だ。
IFAは金融機関の選定から商品選定まで、運用成功に向けた包括的なサポートを提供するからだ。
iDeCoでは金融機関選びが非常に重要
iDeCoを取り扱う金融機関(運営管理機関)は、証券会社や銀行だけでなく、生命保険会社や損害保険会社など、さまざまな業態がある。
各社はiDeCo運用商品を35ほどに絞り込んで提供しているが、そのセレクトは各社独自の特色が出る。
基本的に幅広い資産クラスをカバーしているが、自社系列の運用会社の商品を中心に提供する傾向がある。
IFAなら、特定の金融機関や運用会社に縛られない独立した立場にあるため、投資家の利益を第一に考えた提案ができる。
この中立性こそが、iDeCoにおいて最適な金融機関と商品を選択する上で、非常に重要な要素となる。
IFAなら最適な選択をサポートできる
IFAは、単なる商品選びにとどまらない、以下のようなサービスを提供する。
- 金融機関の枠組みを超えた広い視野に立った、顧客に最適な提案
- 投資家の年齢、リスク許容度、財務状況、長期的な目標を総合的に考慮した意思決定サポート
- 特定の金融機関や商品に偏らない中立的なアドバイスの提供
- 市場環境や個人の状況変化に応じた、定期的な見直しと調整
iDeCoを通じて効果的な資産運用を行いたい方にとって、IFAのアドバイスは非常に有益なものとなるだろう。
「資産運用ナビ」なら簡単にプロが探せる
そうはいっても、金融機関に属していないアドバイザーをどう探すべきか、迷ってしまう方も多いだろう。
そんなときは、「資産運用ナビ」にアクセスしてほしい。
「資産運用ナビ」は、投資家と優秀なアドバイザーをつなぐ、IFAの検索サービスである。
サービス利用の最大のメリットは、自動診断を利用して素早くIFAを見つけられる点にある。
地域や専門領域、資産規模などでフィルターをかけることもできる。実際に話をしてから契約できるので、相性の確認ができる点でも安心だ。
「資産運用はこれから」という方から「すでに相当の資産を持っている」という方まで、すべての投資家におすすめしたいサービスである。
iDeCoでの運用戦略は年代別に組み立てるべき!

本記事では、iDeCoでの運用法やおすすめ商品を年代別に整理し、解説した。
iDeCoは「60歳以降の引き出し」というゴールが設定された制度であり、運用戦略や商品選択は残り時間に大きく影響される。
そのため、年代や状況に応じて適切に見直していくことが重要になる。
しかし、運用戦略の立案や見直しを一人で行うのは難しい場合もあるだろう。
そんなときは、IFAへの相談を強くおすすめする。IFAなら、加入資格の判定から節税効果の試算、商品選択まで丁寧にアドバイスできる。
個人投資家に寄り添い、一緒に考えて答えを探してくれる頼れる存在なのだ。
まずは「資産運用ナビ」にアクセスして、自分に合った専門家を見つけ、相談してみてはいかがだろうか。
専門家のサポートを受けることで、より効果的かつ安心な iDeCo 運用を実現できるだろう。
iDeCoの年代別運用に関するQ&A