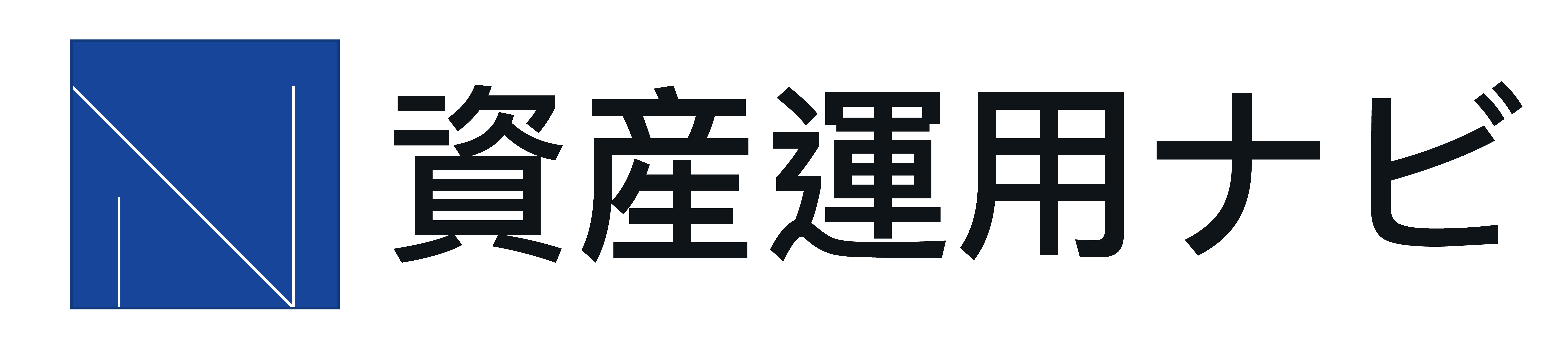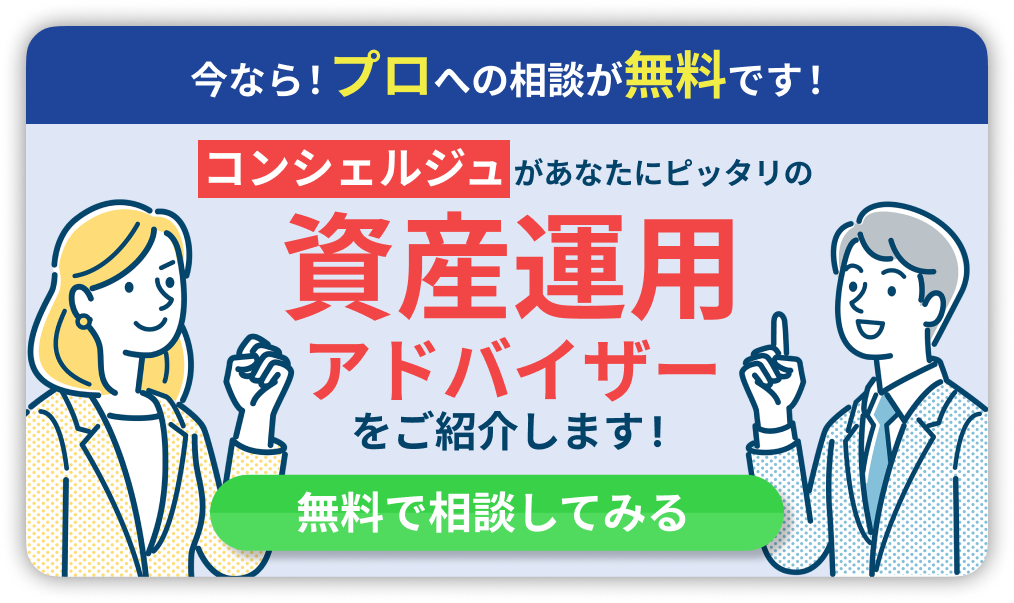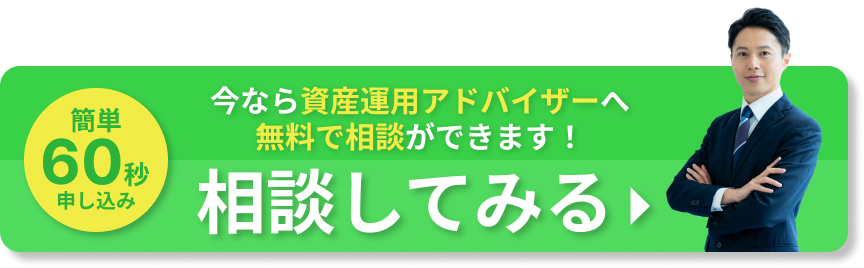- 無職でも始められる資産運用の方法が知りたい
- 少額から始める投資のコツを学びたい
- 安全な投資戦略とリスク管理のポイントを理解したい
仕事をしていなくても、賢く資産を増やすことは可能である。
本記事では、改めて資産運用の基本を整理した上で、リスクを最小限に抑えながら安定した収益を目指す実践的な方法を解説する。
初心者であっても安心して運用をスタートできるような具体的な戦略と役立つヒントを提供するので、ぜひ参考にしてほしい。
職業別の資産運用について、より詳しく知りたい人は下記の記事を参考にするといいだろう。
職業別の資産運用について、分かりやすく解説されている。

無職でも資産運用はするべきか

2023年の総務省の調査によると非労働力人口は4,031万人も存在する。
この中には学生や専業主婦、定年退職した高齢者なども含まれているが、かなりの数の人が広い意味で「無職」と言えるかもしれない。
収入を伴う仕事をしていない人を無職と考えてみると決して少なくない数の人が該当する。
無職と言っても年齢や性別、立場、資産の有無など様々だ。
年金や生活保護などで一定の収入が入ってくる人も中にはいるかもしれないが、共通しているのは「働くことで得られる安定した収入がない」ことだ。
無職が資産運用をするべきかどうかは個別具体的に考えるべきだ。
しかし年金などを除くと、お金を得るには労働市場に身を投じて働いて稼ぐか、金融市場に資産を投じて増やすかの2択に分けられる。
働いて稼ぐという手段が、様々な事情で取れない人でも資産運用で増やせる可能性はある。
そんな資産運用の選択肢を無職だからという理由で完全に捨てるべきではないだろう。
- 長期的な収入源を確保する必要性
- 低リスクで始める資産形成の重要性
- 資産運用を始める前に確認するべきポイント
以上3つの観点から、無職で資産運用を考えている方が事前に押さえておきたいことを解説する。
長期的な収入源を確保する必要性
人は生きているだけでもお金がかかる。食費や光熱費、通信費、交際費、税金など日々の支払いにあてるためのお金が必要だ。
貯蓄があっても一方的に減っていくだけの状況では、いつまで取り崩せるのか不安になったり、ストレスを感じたりするだろう。
そのため長期的な収入源の確保が生きていく上で必要なのは当然のことだ。
総務省が公表している家計調査報告では、単身世帯の消費支出は1か月平均161,753円、2人以上の世帯ならば1か月平均244,231円という結果が公表されている。
月々にかかる生活費は節約などで減らせるとはいえ、1ヶ月に20万円前後の長期的な収入源を確保できなければ貯蓄は減っていく一方になってしまうだろう。
かなり、まとまった資産があったとしても一方的に減り続ける預金残高を確認するのは精神的に苦しいのではないだろうか。
低リスクで始める資産形成の重要性
無職は働くことによる稼ぎがないため、安定した収入源がない。
安定した収入がないからこそ資産をなるべく減らさない低リスクの資産形成を考える必要がある。
会社員や公務員のように安定した収入があれば資産運用でもリスクを取りやすい。
万一、資産運用に失敗しても月々の収入があれば生活費は賄えるためだ。
一方、無職の場合、収入がないため資産を減らしてしまうと、減らした資産の中から生活費を捻出することになってしまう。
日々の生活を守るためにも再就職の予定があれば、無職期間中の生活費は現金にしておいた方が安全だ。
まとまった資産がある人でも働くことによる稼ぎがなければ、高リスクな運用は避けるか、失っても生活に支障のない程度の余剰資金の範囲内でのみ運用するべきだ。
資産運用を始める前に確認するべきポイント
無職と一口に言っても再就職を前提としているのか、定年退職していて働く予定がないのか、専業主婦で家事に専念するのかなど置かれている状況は様々だ。
運用できる資産も学生と退職金を受け取った高齢者ではかなり事情は違うはずだ。
資産運用を始める前に確認しておきたいのが運用の目的だ。
例えば再就職後のことも考えた長期的な資産形成を目指すのか、再就職せずに資産運用のみで暮らしていきたいのか、専業主婦で多少の家計の足しになれば良いのかなど無職と言っても目指すゴールは異なる。
今後の人生設計をもとにゴールを設定した上で、それぞれの資産運用のあり方を考えたい。
リスク許容度に関しては無職だからこそ慎重になる必要がある。
働くことで得られる収入がないと、万一、運用に失敗したときに運用だけで損失を取り返すのは簡単ではない。
例えば、話題になっている成長株(株価1,000円)を買って半値の50%になったとする。
500円になった株価が買値に戻るには50%の上昇では750円にしかならない。
半値になった銘柄は100%上昇しないと元値に戻らない。
資産運用の損を資産運用だけで取り返すのは難しいため、働くことで得られる収入がないからこそリスクは取り過ぎない方が安全だ。
余剰資金も資産運用を始める際には重要なポイントだ。
投資は基本的に、なくなっても生活に支障のない範囲で行うべきだ。
再就職の予定がある、資産形成途中の働き盛りの人ならば投資よりも、再就職までの生活費を減らさないことを意識するべきだろう。
資産運用のみで生計を立てたい高齢者ならば本当に余剰資金だけで生活費を賄えるだけの運用ができるのかどうかをシミュレーションしてみることをおすすめする。
余剰資金次第でできること、できないこと、優先するべきことは変わってくる。
運用の目的を決めたら余剰資金を確認し、目的達成が現実的かどうかはしっかりと確認しよう。
無職の方が知っておきたい資産運用におけるリスク管理方法

資産運用は、さまざまなリスクに晒されながら行う必要がある。
しかしリスクに晒されるからこそ、投資家はリターンを得られる。
資産運用ではリスクがあることを前提にうまくつきあっていくことが重要だ。
資産運用におけるリスクの種類や存在を知り、どのようにすればリスクとリターンの丁度良いバランスを取ることで、持続可能で無理のない運用を続けられるのか。
特に無職の場合、働いて得られる収入がない以上、会社員以上にリスク管理に関しては慎重になるべきだ。
- 資産運用におけるリスクの種類とその回避方法
- 無職期間中の資金計画と運用のバランス
- 長期的な視点で考える資産運用
無職で資産運用をする前に確認しておきたいリスク管理のポイントについて解説する。
資産運用におけるリスクの種類とその回避方法
リスクは細かいものを上げていくと多すぎるため、特に注意したい以下の4つを紹介する。
- 価格変動リスク
- 流動性リスク
- 信用リスク
- 市場リスク
価格変動リスクは、投資した資産の価値が変動することだ。
変動が激しいことをボラティリティが高い等と表現することもある。
値動きの振れ幅が激しければ短期売買をするトレーダーにとっては、利益を狙える売買の機会が増えるため歓迎されることもある。
しかし、中長期で運用する場合は日々の資産が不安定に大きく増減するのは気持ちが休まらないだろう。
中長期での運用をする場合、値動きの相関関係がない資産クラスや銘柄に分散投資をすることで日々の価格変動リスクを緩やかにすることで抑えられる。
流動性リスクは、現金が必要になったときにすぐに現金化できないリスクのことだ。
例えば、不動産投資のような実物資産は売却するまでに時間がかかるため、流動性リスクは一般的に株式や債券のようにすぐに市場で売買できる資産クラスよりも高いといえる。
株式でも新興国で上場廃止されたり、地政学的な理由で取引ができなくなったりすることもある。
流動性が低い投資先かどうかも事前に確認することをおすすめする。
信用リスクは、株式や債券を発行している発行体が経営破綻や財政破綻などをしてしまい元本を回収できなかったり、債務不履行に陥ったりするリスクだ。
債券は元本と利子の支払いが約束されているため、安全資産と位置付けられているが、発行体が破綻してしまい約束が守れないこともある。
本当に投資した資金が戻ってくるのかどうかという視点も資産運用では重要だ。
市場リスクは、金利や為替、株式などの様々な市場の変動によって損失を被るリスクのことだ。
例えば、米国や日本の中央銀行が想定外に金利を上げる政策を行えば、株式は下がりやすくなることで知られている。
外国株投資でも為替レートが変動しドル建てでは利益が出ても、円建てで考えると損をしてしまうことも珍しくない。
金利や為替など市況に影響する指標をニュースなどでこまめに確認することが、リスク回避では大切だ。
無職期間中の資金計画と運用のバランス
働くことで得られる安定収入がない以上、無職期間中の資金計画と運用では少し保守的な方が大きな失敗をしなくてすむ。
資産形成層で再就職を考えている無職の方でも、定年退職をしてまとまった資産があっても今後、働く予定がない無職の方も、働くことで得られる安定収入がなければ運用で大切な資産を不用意に失うことは避けたい。
資産家でもなく、運用に回せる資金がなければ無理に投資をせずに再就職先やアルバイト・パートなどを探すことに力を入れてみる方が現実的だろう。
定年退職やFIREなどでまとまった資産があり、働く予定がない無職の場合も一般的には長期・分散投資でリスクを抑えつつ長期的な目線で運用できるポートフォリオを組むのがおすすめだ。
また、無職で日々の生活費を運用で賄う必要がある場合、株式ならば配当金、投資信託なら分配金、不動産投資ならば家賃収入、債券ならば利息と手元にお金が入ってくる運用方法の方が日々の支払いにあてられるお金も手元に入ってくる。
これらの資産を保有することで得られる収入をインカムゲインとよぶ。
資産を売却して利益を狙うキャピタルゲインのみにしか期待できない運用の場合、資金を拘束されてしまい、取り崩そうにも不本意な価格で売却しなければいけないこともある。
無職で資産運用をする場合は手元にどのように使えるお金を用意するかも、合わせて考えたい。
長期的な視点で考える資産運用
短期間に売買を繰り返すトレーディングをしない限り、資産を育てるには長期的な視点が必要だ。
例えば先進国、新興国の大型株・中型株で構成されるMSCI ACWIや米国を代表する銘柄で構成されたS&P500などの指数は歴史的にITバブル崩壊や新興国バブル崩壊、リーマンショック、コロナショックなど様々な危機で下げる期間もあったが右肩上がりで成長を続けてきた。
時代によって調子の良い個別銘柄や業界は入れかわってきたが、その時々によって時代に即した銘柄構成に入れ替わるMSCI ACWIやS&P500は高値を更新し続けている。
この上昇の恩恵を受けるには、簡単に資産運用をやめずに長期で運用することが必要だった。
長期的な視点で運用を続けることの大切さが分かるだろう。
無職でも安全に始められる資産運用の方法

無職でも資産をこれから形成する方、働き盛りの世代で転職活動中の方と既に資産を築いた定年退職者やFIREを達成した方とでは運用法は違ってくる。
ここでは将来的に働くことも考えており、これから資産形成をしていこうと考えている無職の方向けの安全に始められる運用法を紹介する。
- 少額投資が可能な運用商品の紹介
- 定期的な収益を目指す分散投資戦略
- リスクを抑えた資産運用のポイント
この3点を押さえて無理のない安全に始められる運用に挑戦してみると良いだろう。
少額投資が可能な運用商品の紹介
まず前提として資産運用する際に大手ネット証券の口座開設をおすすめする。
取引手数料が安く投資できる資産クラスも銘柄も豊富なためだ。
例えばSBI証券、楽天証券、マネックス証券などが挙げられるが、基本的には自分が使いやすいと感じたところで良い。
そして長期分散投資を簡単にできる投資信託を積立投資で買い続けるのがおすすめだ。
代表的な長期分散投資ができる投資信託の例を挙げると以下の通りだ。
| 名称 | ベンチマーク | 信託報酬 |
|---|---|---|
| e MAXIS Slim 米国株式(S&P500) | S&P500指数 | 0.09372% |
| e MAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | MSCI ACWI | 0.05775% |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | S&P500指数 | 0.0938% |
| SBI・V・全世界株式・インデックス・ファンド | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | 0.1338% |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | CRSP US トータルマーケットインデックス | 0.162% |
| 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | 0.192% |
小口で100円からでも購入可能。今、話題のNISA口座でも投資対象となっている。
米国や世界各国の株式に簡単に分散投資できる。無理のない範囲でつみたて投資をしてみると良いだろう。
定期的な収益を目指す分散投資戦略
定期的な収益を得られる方が安心だと感じる方は、高配当銘柄に分散投資できる投資信託への積み立ても考えられる。
2024年現在、注目されている投資信託は以下のとおりだ。
| 名称 | ベンチマーク | 信託報酬 |
|---|---|---|
| SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型) | 日本の高配当銘柄に分散投資 | 0.099% |
| SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | SPYD:S&P500の中でも配当金の高い企業に分散投資 | 0.1338% |
| SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型) | VYM:バンガード・米国高配当株式ETF、時価総額が大きく平均以上の配当利回りの銘柄分散投資 | 0.1238% |
日本最大手のネット証券のSBI証券から、高配当で年に4回分配を行うことを目指す投資信託が発表され話題となっている。
SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)は2023年12月12日に設定された投資信託だが2024年1月17日の時点で300億円の資金が流入し人気度の高さが伺える。
米国高配当株ETF(SPYD&VYM)に投資信託を通じて投資ができる「SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」と「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド(年4回決算型)」は2024年1月30日から運用が開始されるが、こちらも配当を重視する個人投資家からの注目度が高い。
- 参考:SBIホールディングス
リスクを抑えた資産運用のポイント
無職で資産運用を無理なく始める場合、働くことで得られる安定収入を期待できない。
そのため現金の比率は高めにしておく方が安全だ。
そして、退職金を受け取った高齢者やFIREを達成し余剰資金が十分にある方でもない限り長期・分散投資を軸にしながら働くことをおすすめする。
いくら高配当銘柄に投資しても投資できる元本が少ないと生活費を賄えるほどのリターンを期待できないためだ。
働いて安定収入を確保し余剰資金を少しずつ運用に回していくのが、これから資産形成をする方にはおすすめだ。
無職の方は資産運用の相談をどこにするべき?

無職でもまとまった退職金などを受け取り資産がある高齢者の方、若くして大きな資産を手にして働いていない方は資産運用の専門家に相談することをおすすめする。
特にこれから働く予定がなく運用のみで生活をしていこうとする場合、資産を増やすだけではなく守る視点も必要なためだ。
また、働かないで資産運用のみで生活をする方が、働きながら安定収入が得られる会社員などに比べて運用も難しくなる。
そこで、おすすめなのが資産運用の専門家IFAへの相談だ。
- 資産運用を専門家に相談することの重要性
- IFA(独立系金融アドバイザー)の役割・メリット
- IFA検索サービス「資産運用ナビ」の活用方法
あなたと相性の良いIFAを探す際のポイントを3つ紹介する。
資産運用を専門家に相談することの重要性
無職で資産運用のみで生活する場合、働くことで得られる収入に頼れない分、資産を上手く活用する必要がある。
資産運用のみで生計を立てるのは専門的な知識と経験がなければ難しい。
誰にも頼らず資産運用をしてしまうと、とるべきリスクの許容度なども見誤ってしまうかもしれない。
また専門家に相談すれば一般論ではなく、個別具体的なアドバイスを受けられる。
インデックスファンドへの長期分散投資や高配当銘柄への投資は人気のある運用法だが、必ずしも個々の状況に人生の目標達成のために有効とは限らない。
IFA(独立系金融アドバイザー)の役割・メリット
IFAとは独立系金融アドバイザーのことで、特定の金融機関に所属していない立場にある。
証券会社や銀行の担当者にも資産運用の相談はできる。
しかし、証券会社や銀行の担当者は立場上、営業成績を上げるために顧客と利益相反の提案をせざるを得ない人もいる。
また担当者を指名できない、よい担当者がついても全国転勤などで変わってしまうこともある。
一方、IFAは特定の金融機関から独立した立場で資産運用の提案がしやすい。
特定の金融機関で顧客ファーストの提案ができないことを理由に銀行や証券会社から独立したIFAも少なくない。
そのため信頼できるIFAを見つけやすいだろう。
また大切な資産を預ける際に信頼できそうなIFAを自分で選べるのもメリットだ。
IFA検索サービス「資産運用ナビ」の活用方法
「資産運用ナビ」はIFA検索サービスだ。
信頼できるIFAを見つける際に活用できる。
使い方は簡単で、年齢や職業、相談内容などをフォームに入力すれば、おすすめのIFAのプロフィールが提案される。
そして、気になったIFAにオンラインで面談をして、双方が合意すれば契約が成立する。
IFAを選ぶ際にはキャリアや資格、得意分野、担当している顧客層の保有金融資産などを参考にできる。
オンラインの面談は何回でも無料でできるため、妥協せずに信頼できるIFAを探せる。
信頼できる資産運用のパートナーを見つける際に活用してみてほしい。
無職で資産運用を始めるならIFAを活用しよう

無職でも安心して始められる資産運用の要点を解説した。
まずは現在の資産状況と将来の予測を立てることが重要だ。
少額からでも効果的な投資を行うには、長期・分散投資の実践と適切なリスク管理がポイントとなる。
将来に向けた安定した資産形成への一歩として、資産運用を始めよう。
資産運用に関する疑問や不安があれば、専門家からアドバイスを受けることを推奨する。
特にIFAは、中立的な立場からあなたに最適なアドバイスを長期にわたって提供してくれる。
IFA検索サービス「資産運用ナビ」を活用し、あなたに合ったIFAをみつけよう。
無職の資産運用に関するQ&A