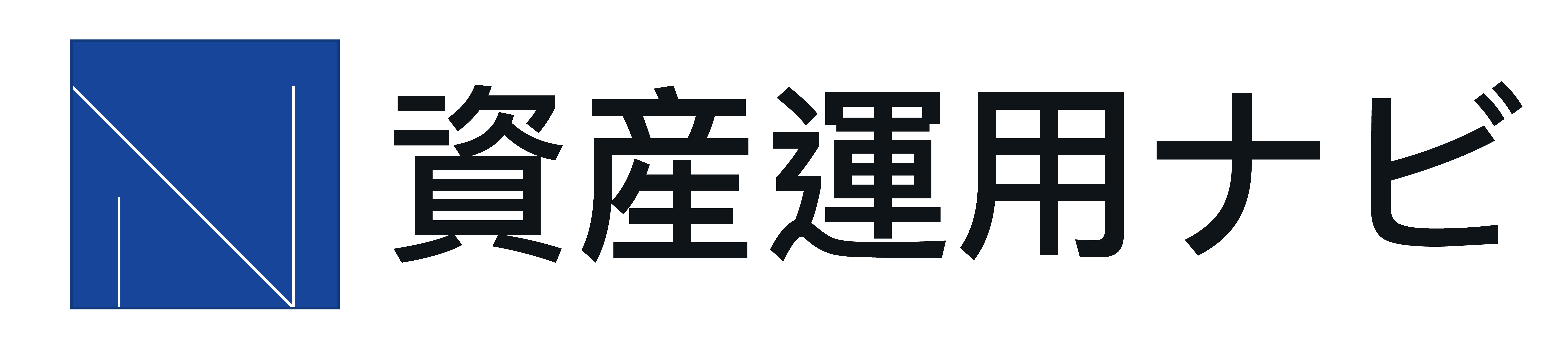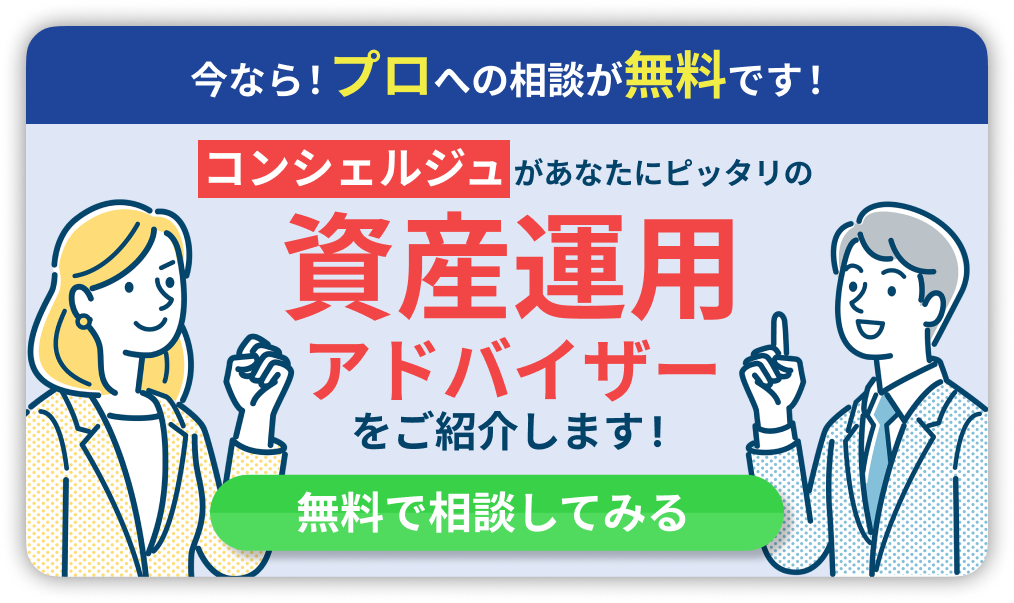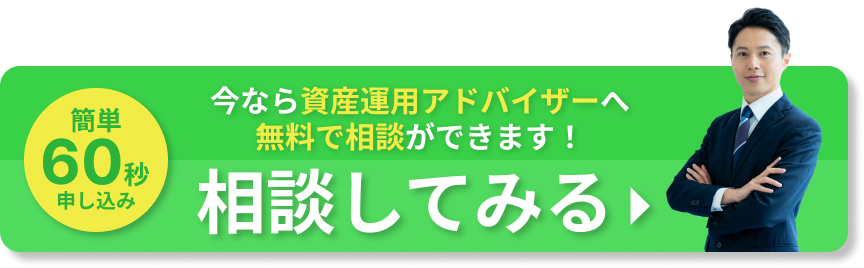投資信託は、証券会社や銀行などの金融機関を通じて購入するが、どの金融機関を利用するかによって商品ラインナップや手数料に違いがある。
そのため、証券口座を開設する際は、複数の証券会社を比較して選ぶことが大切だ。
本記事では、証券会社による投資信託の違いや、ファンドによる違いについて解説していく。
証券会社による投資信託の違い

投資信託での運用は、利用する証券会社によって次のような違いがある。
- ファンドのラインナップ
- 購入手数料
- 最低投資金額
- クレカ積立の有無
それぞれくわしく解説していこう。
違い①ファンドのラインナップ
現在、日本国内には約6,000本もの公募投信があり、その中でどのようなファンドを取り扱っているかは証券会社によって異なる。
たとえば、主要ネット証券のラインナップは次の通りだ。
大型ファンドはどこも取り扱っていることが多いため、証券会社によって不便を感じることは少ないかもしれない。
しかし、より取り扱いファンド数の多い方が選択肢の多さにもつながる。
「マイナーファンドにも投資したい」という投資意向の変化に対応するためにも、証券会社の取り扱い商品は必ず比較しておこう。
違い②購入手数料
投資信託の購入手数料も証券会社によって異なるポイントだ。
投資信託の購入手数料は運用会社によって最大料率を定められているものの、実際に適用される購入手数料は証券会社によって異なる。
たとえば、運用会社が購入手数料を最大3.3%と定めている場合、証券会社Aでは2.2%、証券会社Bでは3.3%など、同じファンドを購入するケースでも利用する証券会社によってコストに違いがある。
購入手数料は運用パフォーマンスに直結する点でもあるため、購入時にどれくらいのコストが差し引かれるかよく確認しておこう。
なお、大手ネット証券については、購入時の手数料を一律無料としているところも多い。
違い③最低投資金額
最低投資金額も証券会社によって異なるポイントだ。
まとまった金額の投資を予定している人にとってはあまり影響のない点だが、少額投資から始めようと考えている人にとっては、投資を始めるハードルの高さにも直結する。
「まずは気軽に始めてみたい」という人は、より最低投資金額が小さい証券会社の方がよいだろう。
また最低投資金額は、一括投資か積立投資かによっても異なる。
基本的に、一括投資の方が最低投資金額が大きく設定されていることが多いため、この点も事前に確認しておこう。
違い④クレカ積立の有無
積立投資の利用を検討している際は、クレカ積立の有無についても比較しておきたい。
クレカ積立とは、積立投資の投資資金をクレジットカードで決済するサービスだ。
クレカ積立は、資産運用をしながらクレジットカードのポイントが貯められるメリットがある。
現金で積み立てる場合はポイントが付与されないが、クレジットカードを通じて決済することで決済額に応じてポイントが付与される。
証券会社によっては「特定のクレジットカードの利用で還元率が上がる」といった特典もあるため、ぜひ複数社のクレカ積立サービスを比較してみよう。
ファンドによる投資信託の違い

投資信託は、ファンドによっても次のような違いがある。
- 投資対象
- 運用コスト
- 為替ヘッジの有無
ひとつずつくわしく確認していこう。
投資対象
投資信託は、ファンドによって投資対象が異なる。主な投資対象は次の通りだ。
- 国内株式
- 海外株式
- 国内債券
- 海外債券
- 国内REIT
- 海外REIT
また、上記の金融商品を組み合わせて運用する「バランスファンド」もある。
どのような金融商品に投資するかで得られるリターンや、抱えるリスクが異なるため、自分の投資意向に合ったファンドを選ぶことが大切だ。
運用コスト
運用コストもファンドによって異なるポイントである。
投資信託は運用中に「信託報酬」というコストが差し引かれ、解約するまで投資家が負担する必要がある。
この信託報酬はファンドによって異なるため、同じ種類に分類されるファンドでも投資家が負担するコストに違いがある。
より効率よく運用するためには、複数のファンドを比較して、どれくらいのコストがかかるか理解したうえで購入するようにしよう。
為替ヘッジの有無
海外の資産に投資するファンドでは、為替ヘッジの有無にも違いがある。為替ヘッジとは、為替変動の影響を受けないようにするための機能だ。
海外の資産に投資するファンドは、実質外貨建てで資産を保有することとなるため、為替が円安に動けば基準価額が上昇し、円高に動けば下落する要因になる。
「為替ヘッジあり」のファンドでは、こうした為替変動による影響を受けなくなり、純粋に投資対象の価格の上下で基準価額が変動するようになる。
つまり、「為替ヘッジありコース」では為替リスクが除かれる代わりに、円安の恩恵を受けることはできない。
一方、「為替ヘッジなしコース」では、為替リスクがあるものの円安によって利益を得られる可能性がある。
どちらがよいかは投資意向によって異なるため、リスクとリターンどちらを優先するかよく考えることが大切だ。
なお、「為替ヘッジあり」の場合はヘッジコストがかかるため、コースを選択する際はコストについても考慮するようにしよう。
証券会社選びはIFAへ相談を

投資信託で運用をする際は、どの証券会社を利用するかによって手数料や最低投資金額に違いがある。
「証券会社が多すぎて、どこを利用すればいいのか分からない」というときは、金融のプロであるIFAへ相談することがおすすめだ。
ここからは、IFAの概要や、利用するメリットについて解説していこう。
IFAとは?
IFAとは、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」と呼ばれる金融アドバイザーの一種だ。
証券会社や銀行など特定の金融機関に所属していないことが特徴で、資産運用のアドバイスやマネープラン作成のサポート、保険の見直しなど幅広いことを相談できる存在だ。
「金融機関に所属していない金融アドバイザー」というと、ファイナンシャルプランナーが思い浮かぶかもしれないが、FPと大きく異なるのが「証券会社の仲介や具体的な商品提案を受けられる」という点だ。
FPは一般的なアドバイスは受けられるものの、証券会社での手続きを仲介してくれたり、具体的な商品提案を受けることはできない。
一方、IFAは証券会社と提携していることから、口座開設や売買の手続きを仲介してくれたり、具体的な商品を提案してもらえるメリットがある。
中には、複数の証券会社と提携しているIFAもいるため、いくつかの証券会社を比較したうえで利用先を決めることも可能だ。
IFAへ相談するメリット
IFAへ相談することの大きなメリットは、「プロの意見をフラットな立場で聞ける」ということだ。
IFAは金融機関に所属していないため、営業ノルマを抱えていない。企業利益を優先する必要がないので、真に相談者の立場に立ってアドバイスをくれるメリットがある。
初めて投資信託で運用を始めるとなると、「証券会社の選び方が分からない」「このファンドで良いのか不安」など、いくつもの疑問点を感じるだろう。
IFAへの相談では、こうしたひとつひとつの疑問点を解消しながら資産運用に取り組める。
プロの意見を聞きながら資産運用に取り組めることは、きっと大きな安心感につながるはずだ。
自分の意向に合った証券会社を見つけよう

投資信託は証券会社によって、購入手数料や商品ラインナップなどに違いがある。
どの証券会社を利用するかで運用パフォーマンスも変わってくるため、利用先は慎重に選定したい。
また、より自分に合った証券会社を見つけるためには、金融のプロであるIFAへ相談することもおすすめだ。
IFAは証券会社選びだけでなく、具体的な商品提案やマネープラン作成のサポートも行ってくれるため、適切な資産運用に取り組むためのアドバイスがもらえるメリットがある。
中には、オンライン面談に対応しているIFAもいるため、ぜひ気軽に相談してみよう。