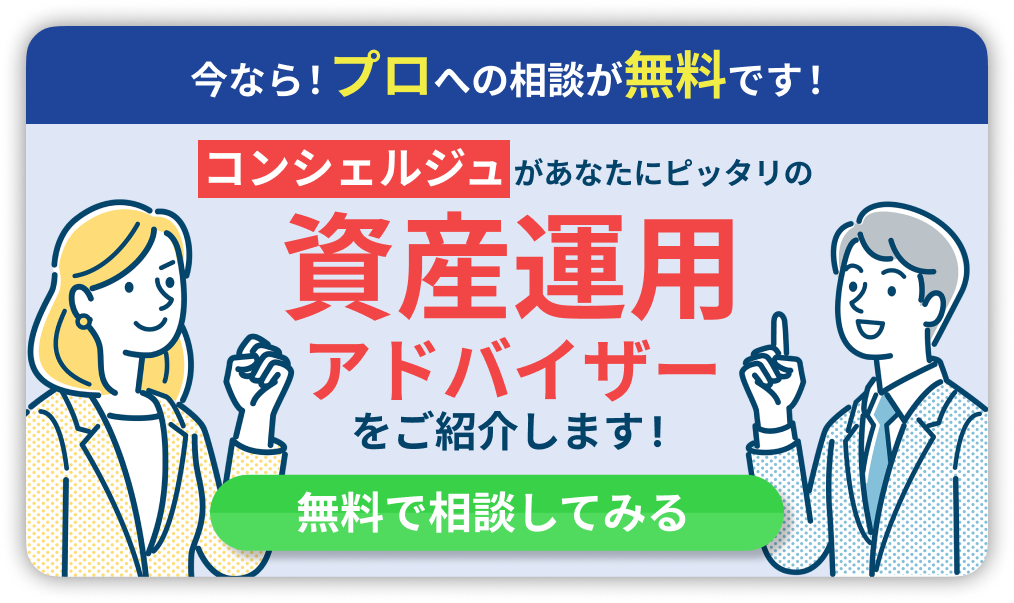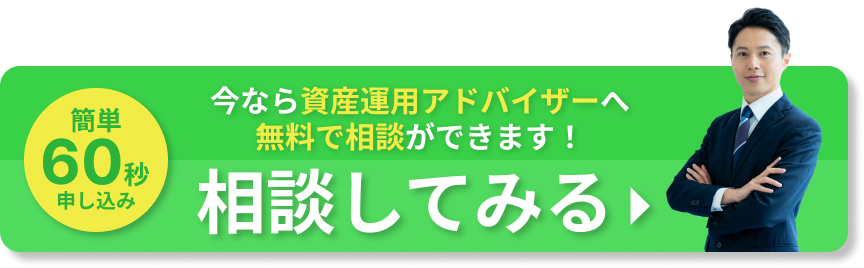2月22日の東京株式市場において、日経平均株価はバブル期の1989年12月29日の取引時間中に記録した3万8957円44銭を終値で上回り、3万9098円68銭まで上昇しました。
ようやくバブル崩壊以降、低迷を続けていた日本の株式市場が新たな歴史の扉を開けたのです。
しかし、年明けから好調すぎる日本の株式市場に一抹の不安を抱える個人投資家も少なくありません。死角がないのかを確認していきます。
バブル崩壊ではないがスピード調整はある

日経平均株価は年始から2か月も経たないうちに上昇率が17%を超えました。
この上昇スピードは異様に速いものであり、たしかにある程度の投資キャリアがある個人投資家からすると、かえって不安になるものです。
2月13日は特に大きなイベントがあったわけでもないのに、日経平均株価は1日で1,000円以上も値上がりしました。
よく言われることですが、株価というものはジワジワと上がり、ガツンと下がるものです。つまり、これだけの上昇速度を実現したということは、近いうちに何日も株価が下落する局面は来るでしょうし、時にはその値幅が1,000円を超えることもあるでしょう。
しかし、これはあくまで上昇し続けた反動であり、いわゆる「スピード調整」というものであり、決してバブル崩壊と騒ぐ必要のないものと考えます。
PER(株価収益率)やBPS(1株当たりの純資産)などを見れば、割安感は消えて、いいとろこまで上昇してきたようには見えるものの、決して実態のないバブルと呼べるほどの株価水準ではないからです。
半導体ブームの落ち着き

日経平均株価が史上最高値を記録した前夜、米国では半導体大手エヌビディアの決算がありました。
予想を上回る四半期決算が好感されたことで同社の株価が時間外取引で急騰し、それに伴いスーパー・マイクロ・コンピューターやアドバンスト・マイクロ・デバイシズなどの関連銘柄も値を上げました。
年始からの日本の株式市場も半導体関連銘柄が牽引しています。アドバンテスト、東京エレクトロン、レーザーテックをはじめ、英半導体設計大手のアームを傘下に抱えるソフトバンクなどが相場全体を押し上げています。
昨今の生成AIブームを受けて、半導体の需要は今後も増えていくことを期待する投資家が多いのです。
しかし、いつまでも投資家の期待を上回り続ける決算を出し続けることは難しく、どこかのタイミングで半導体需要も一服をすることでしょう。そのタイミングで他に相場を牽引できる業種が表れなければ、株価指数も調整局面を迎えることになります。
日本経済は脆弱なまま

日本の株式市場は絶好調ですが、日本の経済はそれほど強くはありません。厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査によれば、実質賃金は21カ月連続でマイナス。
総務省が発表した家計調査によれば1世帯当たりの消費支出は10カ月連続で減少しています。
内閣府が発表した2023年10~12月期の国内総生産(GDP)の内訳を見てみると、日本のGDPの半分以上を占める個人消費は前期比0.2%減と3四半期連続のマイナスとなっており、民間の設備投資も3四半期連続のマイナス。住宅投資は2四半期連続のマイナスで、日本経済のメインである内需は脆弱な状態です。
株価が好調でも生活実感は全く改善されていないと感じている方も多いかと思いますが、その理由はここにあります。
株価とは企業業績の将来に対する期待が反映されているのであって、国民の生活実感を反映するものではありません。
株価ではなく、経済指標を見てみれば、日本に対する印象は変わるのです。
このまま日本経済が脆弱なままであれば、いずれ株価にも悪影響を与えるでしょう。
金融政策の転換に注意

脆弱な日本の経済を更に下押しさせる懸念の1つに金融政策の転換があります。
8日に日銀の内田副総裁は「仮にマイナス金利を解除しても、その後にどんどん利上げをしていくようなパスは考えにくく、緩和的な金融環境を維持していくことになる」と述べ、マイナス金利の解除を匂わせました。
また、22日に植田総裁は衆議院予算委員会に出席し、日本経済について、「デフレではなくインフレの状態にある」と述べました。
前述のように経済状態が万全ではないなかで金融緩和を縮小していけば、日本経済が下押しされるリスクは高まりますし、市場で予想されている通り夏頃から米国が利下げに転じるのであれば、日米の金利差が縮小することで為替が円高方向に転換する可能性もあります。
そうなれば、円安を背景に拡大していた日本企業の業績にも陰りが出てくることでしょう。企業業績という裏付けが剥がれてしまうと、一気に株価に割高感が生じることになります。
現在の株高をバブルであると認識する必要は全くありませんが、全く死角がないわけではないという認識は頭の片隅にはおいておきたいものです。