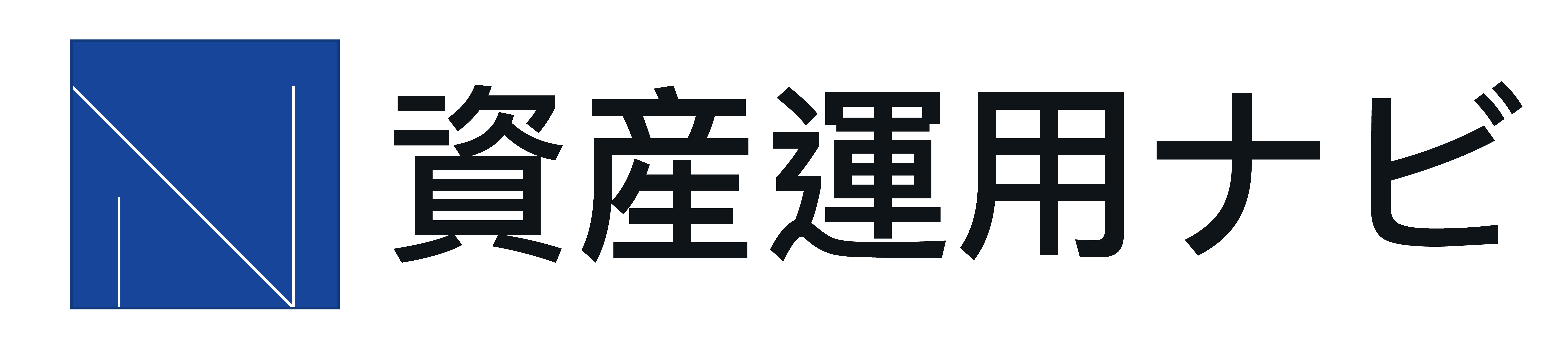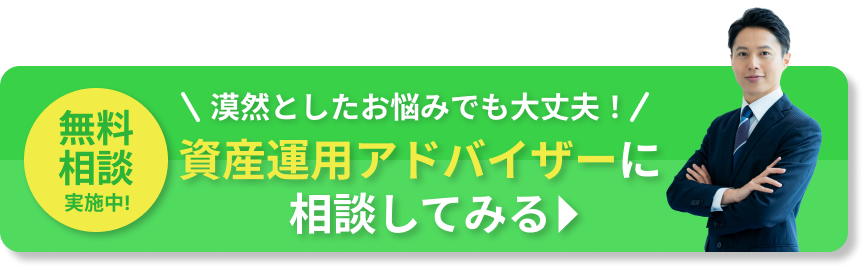- 新NISAのつみたて投資枠での最適な初期投資額が知りたい
- 少額から始める投資のポイントを理解したい
- 少額投資の効果とリスク管理の方法が知りたい
2024年からスタートした新NISAのつみたて投資枠は、年間120万円の非課税枠で投資できる制度である。
長期的な資産形成を目指す方にとって、非常に魅力的な制度と言えるだろう。
しかし、「いくらから始めればいいのかわからない」「リスクが怖い」という方も多いのではないか。
この記事では、つみたて投資枠を少額から始める方法、リスクを抑える投資戦略、そして新NISAを活用した資産形成術について解説する。
少額投資から始められる方法や、リスクを抑えながら収益最大化を目指す方法を紹介しているので、投資初心者の方にもぜひお読みいただきたい。
新NISAつみたて投資枠はいくらから始めるべき?最適な初期投資額の決め方

新NISAのつみたて投資枠は、「いくらから始めればいいのかわからない」という方も多いかもしれない。
ここでは、無理なく続けられる投資額を見つけるためのポイントを解説する。
新NISA制度の基本と投資枠の概要
新NISAとは、従来のNISA制度を大幅に拡充した少額投資非課税制度のことである。
株式投資や投資信託などの運用を行った利益に対する税金が非課税になるという点が、新NISAの一番の特徴である。
新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つがあり、名前からもわかるとおり、定期的な積立投資に適しているのがつみたて投資枠、高成長を期待した投資に適しているのが成長投資枠である。
新NISAとして一年間に投資できる枠は合計360万円までだが、つみたて投資枠120万円と、成長投資枠240万円に分割して利用できる。
また、新NISAでのトータルの投資金額(非課税保有限度額)としては、1,800万円までが非課税となる。
非課税となる期間が無期限とされている点も、非常にメリットが大きいところだ。
つみたて投資枠における初期投資金額の選定基準
投資初心者が、新NISAを使って投資を始める際はやはり積立投資がおすすめだ。
ただし、いきなり投資を始めてはいけない。
投資することで、お金が増える可能性もあれば、減ることもありうる。元本保証はないのだ。
最低でも、6か月程度の生活費を貯めたうえで、余裕資金を投資に回すようにしよう。
たとえば、毎月の生活費が30万円であれば、180万円を預貯金などで確保しておき、毎月の収入から生活費を差し引いた残りの余裕資金を投資に回すことを考えるとよいだろう。
つみたて投資枠は、年間120万円まで投資できるので、月あたり10万円となる。
だが、10万円投資しなくてはいけない、ということではなく、あくまで上限金額であって、その範囲内ならいくらでもいいのだ。
月100円から積立投資できる証券会社もあるくらいだ。
投資は長期戦でもあるので、無理のない金額から始めて、慣れて余裕が出てきたら徐々に投資額を上げていけばいいだろう。
なお、つみたて投資枠の活用法についてはこちらの記事で詳しくまとめているので、より具体的に知りたいという方はぜひ参考にしてほしい。

つみたて投資枠は少ない額からでも問題ない
いくらまでを少額投資というのかは人それぞれ捉え方が違うだろうが、一般に毎月1,000円から1万円程度の投資であれば、少額投資といえるのではないだろうか。
数十万円〜数百万円とまとまったお金でなくとも、少ない資金から始められるのが、少額投資の最大のメリットといえるだろう。
仮に資金があったとしても、リスクが怖くて、いきなり大金をつぎ込みたくない、という人もいるはずだ。
少額から始めて、投資体験を通して、知識を身につけながら、徐々にステップアップするというのもいいだろう。
少額投資のメリットをまとめると以下の3点となる。
- 少ない資金から始められる
- リスクが軽減できて精神的な負担が少ない
- 投資の勉強をしながら進められる
とはいえ、少額投資だと、たとえ儲かっても利益が少ないため、まとまった資産となるのに時間がかかるということはあるだろう。
逆に少額だから、投資が雑になって、ハイリスクハイリターンなことをやってしまったり、無計画に売買したりする人もいるかもしれない。
まとめると、以下が少額投資のデメリットである。
- 資産形成に時間がかかる
- 大きな利益を期待できない
- 投資が雑になる
少額だとしても貴重な自分のお金なのだから、大切にコツコツと投資を進める人に向いているといえるだろう。
いくらからでも大丈夫!新NISAつみたて投資枠を少額から始める際のポイント

つみたて投資枠は、少額から始められるのが魅力だ。
月々1万円からでも、長期的に積み立て続けることで、大きな資産形成を目指すことができる。
ここでは、少額投資で成功するためのポイントを紹介しよう。
つみたて投資枠の少額投資に適した資産クラス
少額投資に向いている投資には、単元未満株、投資信託、ETFなどがある。
通常の株取引では、単元株が決まっており100株単位での取引となることが多いが、単元未満株は、取引単位に満たない1株から売買できるサービスだ。
サービスを提供している証券会社が限られるうえ、リアルタイムに取引できないところも多い。
それよりも、投資信託やETFのほうが、少額で毎月一定額を購入する積立投資にも向いているだろう。
新NISAのつみたて投資枠でも、投資信託やETFの取引が可能であり、少額投資に適しているといえる。
以下の資産クラスを組み込んだ投資信託がおすすめだ。
- 国内株式
- 日本企業の成長や株価上昇に期待できる
- 外国株式
- 世界経済の成長や株価上昇に期待できる
- 債券
- 国内外の公社債にリスクを抑えて投資できる
とくに、つみたて投資枠の対象商品のうち、インデックスファンドやバランスファンドが、少額投資に向いているだろう。
- インデックス型投資信託(インデックスファンド)
- 日経平均株価や米国S&P500など、株式指数に連動する投資信託。
- バランス型投資信託(バランスファンド)
- 国内外の株式や債券に分散投資する投資信託。リスクを抑えながら、安定的なリターンを目指す。
つみたて投資枠の少額投資における時間分散の重要性
少額での積立投資は、継続的に一定額を投資する手法であり、値動きや市場のタイミングを計る必要がない。
市場は常に変動するため、一括投資よりも少額の積立投資で定期的に購入することで、価格変動リスクを抑えることにつながる。
毎月や毎週、あるいは毎日少しずつ積み立てていくため、時間分散によるリスク軽減が期待できるといえるだろう。
つみたて投資枠の少額投資におけるリスク分散の重要性
投資信託への少額投資を行う場合は、一つの資産クラスや国、地域に集中して投資するのではなく、複数の資産クラスや国に分散投資することになり、必然的にリスクを抑えた手法となる。
たとえば、全世界株式のインデックスファンドだとすると、資産クラスは株式一つになるが、日本を含む世界中のさまざまな国へ分散投資を行うことになる。
バランスファンドであれば、株式、債券、不動産などの複数の資産クラスへの分散投資であり、いずれにしてもリスク分散につながる。
いくらから始めるにも欠かせない!新NISAつみたて投資枠で押さえるべき投資戦略

新NISAで長期的な資産形成を目指すには、リスク管理と収益最大化の両立が重要となる。
以下では、それぞれのポイントを詳しく解説しよう。
長期投資の利点とリスク軽減の方法
長期投資は、短期的な市場変動の影響を受けにくく、リスクを抑えることができる。
これは、時間の経過とともに市場が右肩上がりの上昇傾向にあることが前提だ。
一方、投資期間が長くても、以下のようなリスクが発生する可能性は常にある。
- 経済情勢や政治情勢の変化による市場の急落
- 金利上昇による債券価格の下落
- インフレによる購買力の低下
これらのリスクを軽減するためには、以下の方法が有効となるだろう。
- 分散投資
- 複数の資産クラスに投資することで、特定の資産クラスへの集中リスクを軽減
- 定期的な積立投資
- 市場タイミングを図らず、定期的に一定額を投資することで、平均購入単価を下げ、価格変動リスクを抑制
- ポートフォリオの見直し
- 定期的にポートフォリオを見直し、必要に応じて資産配分を調整
マーケット変動への対応策
市場が下落しても、慌てて売却しないことが重要だ。
長期的な視点に立ち、冷静に判断する必要がある。
将来のことはわからないが、過去の相場では、下落は一時的な現象であることが多く、長期的に見ると市場は上昇し続けている。
下落局面で売却してしまうと、損失を確定させてしまうことにつながる。
具体的な対応策として、以下の3点を実行するようにしよう。
- 積立額を増やす
- 市場が下落しているときは、積立額を増やすことで、低い価格でより多くの投資信託を購入することになる
- 一時金で買い増す
- 余裕資金があれば、一括で買い増すことで、平均購入単価を下げることができる
- リバランス
- 保有資産の配分が崩れていないか確認し、必要に応じて調整する
ポートフォリオ管理と定期的な見直し
ポートフォリオとは、保有する複数の金融商品の組み合わせのことだ。
時間が経つと金融市場の変化や投資する側のリスク許容度によって、適切なポートフォリオ構成ではなくなってくることがある。
定期的にポートフォリオの状況や成績を見直し、自分が許容できるリスクと照らし合わせて、ポートフォリオの調整(リバランス)を行う必要がある。
ポートフォリオの調整とは、当初定めた資産ごとの構成比率に戻す投資手法である。
1年に一度程度、ポートフォリオの構成比率やパフォーマンスを確認し、構成比率が目標から乖離していれば、適宜、売買を行ってポートフォリオの比率を再び当初の比率に近づけるといい。
長期の資産管理においては、このような見直しを行うことは、リスク管理のためにも不可欠なプロセスといえるだろう。
新NISAつみたて投資枠をいくらから始めるべきか迷ったら誰に相談するべき?

新NISAで資産形成を続けるには、専門家に相談することも有効となる。
専門家は、豊富な知識と経験に基づき、あなたの状況に最適な資産運用のための戦略作りをサポートしてくれるはずだ。
新NISAの活用における専門家の重要性
新NISAは、長期的な資産形成を目指すすべての投資家にとって有効な制度だが、いかに低リスクで活用するかについては専門知識が必要となる。
自分で調べて取り組むことも重要だが、専門家に相談することで自身の時間と手間を省くこともできるはずだ。
専門家は、とくに以下の点について、重要な役割を果たすだろう。
新NISAに関する知識
専門家は、新NISA制度に関する深い知識を持っているため、投資家にとって最適な投資方法をアドバイスすることができる。
リスク管理のアドバイス
専門家は、投資リスクを理解し、リスクを軽減するための方法を助言できる。
時間と手間の削減
専門家は、投資家にとって必要な情報収集や分析を日々行っており、効率的に提供してくれるので、あなたにとっては時間と手間の削減につながるはずだ。
専門家とは、証券会社のコンサルタントや銀行員、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)などのことをいう。
証券会社や銀行では、投資信託や債券などの金融商品を販売しているため、その商品に関する情報を得ることができる。
また、IFAは、金融商品以外にも資産運用やポートフォリオ管理に関する全般的なアドバイスを受けることができるだろう。
IFAの役割と利用するメリット
新NISAの活用に関する相談は、IFAに任せることをおすすめしたい。
IFAは特定の金融機関に属していないため、顧客の立場に立った客観的なアドバイスを提供することができる。
IFAに相談する具体的なメリットは、以下の通りだ。
客観的なアドバイス
IFAは、金融機関の方針や利益に縛られることなく、顧客目線でかつ客観的なアドバイスを受けられる。
幅広い商品
IFAは、老後の資産形成に限らず、幅広い金融商品のなかから、あなたに合った商品を提案してくれる。
長期的な視点
IFAは、あなたの長期的な目標に沿った資産形成プランを提案してくれる。
IFA検索サービス「資産運用ナビ」の活用法とその効果
自分に最適なIFAを見つけるために、「資産運用ナビ」という資産運用相談サービスを利用することができる。
「資産運用ナビ」公式ウェブサイトから、希望条件を入力すると、全国のIFAの中から、あなたにぴったりな資産運用アドバイザーを見つけ出してくれる。
このサービスは、日本全国にいるIFAを対象としていて、料金はかからず何度でも相談することができる。
上手に「資産運用ナビ」を活用して、自分に最適なIFAを見つけ出し、新NISAの活用を効果的に進めてほしい。
新NISAつみたて投資枠をいくらから始めるべきかは専門家と決めよう

本記事では、積立投資における初期投資額の考え方や設定方法について紹介した。
また、つみたて投資枠で始める少額投資のポイントや効果的な投資戦略、リスク管理の方法についても詳しく解説した。
なお、新NISAを活用した資産運用に関する疑問や不安があれば、専門家からアドバイスを受けることも考えてみてほしい。
とくにIFAは、中立的な立場からあなたに最適なアドバイスを長期にわたって提供してくれるはずだ。
IFA検索サービス「資産運用ナビ」を徹底活用し、あなたに合ったIFAをみつけよう。
新NISA、つみたて投資枠、いくらからに関するQ&A