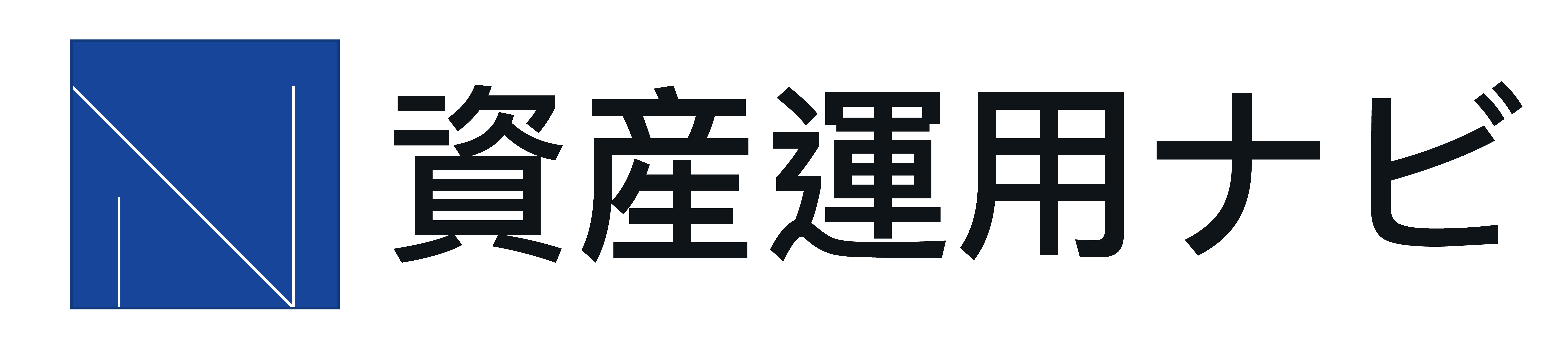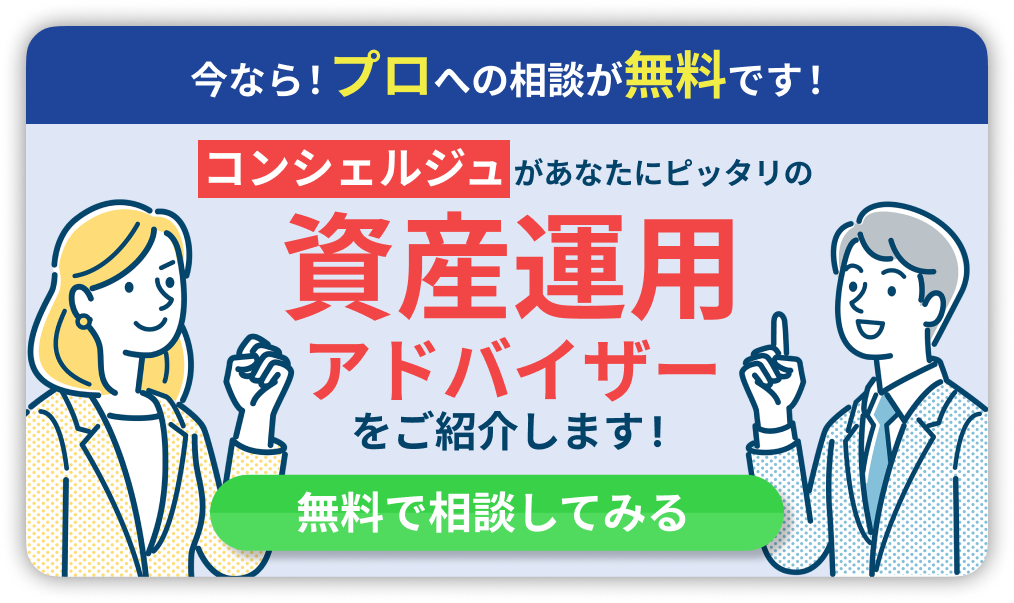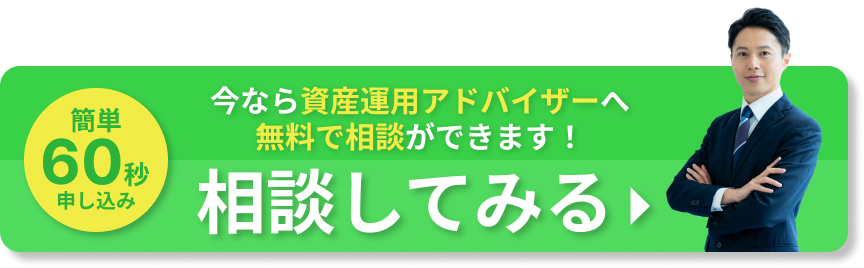- 新NISAのつみたて投資枠の基本的な仕組みを理解したい
- つみたて投資枠で投資を始める手順やポイントが知りたい
- 投資先の選び方やリスク管理の方法が知りたい
2024年から改定された「新NISA」は、リターンを非課税にできる制度で、将来のために資産準備を気軽に行える。
今回の記事では、新NISAの基礎知識からNISA口座の開設方法・積立投資の効果などを紹介していくので、今後のために役立ててほしい。
始め方の前に知っておきたい新NISAつみたて投資枠の基本

まずは2024年から改定された「新NISA」と「つみたて投資枠」について解説していくので、制度について理解を深めていこう。
新NISA制度の概要
「新NISA」とは、2024年に改定された「少額投資非課税制度」のことを指し、資産運用で得たリターン(利益)を非課税にする制度である。
通常、資産運用で得た所得には税金が発生するが、新NISAを活用すれば以下の金額までは税金がかからない。
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 18歳以上 | |
| 非課税保有期 | 無期限 | |
| 非課税保有限度額 ※総枠 | 1,800万(枠の再利用可能) つみたて投資枠と成長投資枠の併用可能 ※成長投資枠は1,200万円まで | |
| 年間投資枠 | 120万/年 | 240万/年 |
| 対象金融商品 | 投資信託(長期積立・分散投資) | 上場株式・投資信託など |
2023年末までの旧NISAではつみたて投資枠と成長投資枠の併用はできなかったが、新NISAでは併用ができるようになったので、将来のために資産運用を行える環境が整えられた。
新NISA専用の口座を金融機関で開設し、NISA口座でNISA対象の金融商品を運用すると非課税の対象になる。
旧NISAと新NISAの違いを以下で解説していくので、どのような改定があったのか学んでいこう。
- 一般NISAとつみたてNISAの併用不可
- 非課税枠(合計)
- 一般NISA 600万円、つみたてNISA 800万円
- 非課税枠(年間)
- 一般NISA 120万円、つみたてNISA 40万円
- 非課税期間
- 一般NISA 5年間、つみたてNISA 20年間
- つみたて投資枠と成長投資枠の併用可
- 旧NISAと新NISAの併用可(旧NISAは運用のみ)
- 非課税枠(合計)
- 1,800万円(成長投資枠1,200万円)
- 非課税枠(年間)
- 成長投資枠 240万円、つみたて投資枠 120万円
- 非課税期間
- 恒久化
- 成長投資枠とつみたて投資枠
- 併用不可→併用可
- 非課税枠(合計)
- 600万円/800万円→1,800万円(成長投資枠1,200万円)
- 非課税枠(年間)
- 120万円/40万円→240万円/120万円
- 非課税期間
- 最大5年/20年→恒久化
以上のように非課税枠を含めたさまざまな部分が大きく改定され、より資産運用を行いやすくなった。
昨今のインフレ(物価が上昇すること)が原因で現金の価値は将来的に目減りする可能性が高い。
つみたて投資枠を活用した運用の始め時がいつなのかわからない、という方も資産を守るためにはできるだけ早くから長い時間をかけて資産運用を行い、効率的に資金準備を進めるのがおすすめだ。

つみたて投資枠の特徴
続けて新NISAの「つみたて投資枠」についてさらに詳しく解説していく。いったいどのような資産運用が可能なのだろうか。
つみたて投資枠で運用できる金融商品は決められており、長期積立・分散投資で行う投資信託がその対象になる。
しかし、すべての投資信託が対象になる訳ではなく、金融庁が定めた条件に当てはまる商品のみが適用される。
1年間につみたて投資枠を活用できる上限枠は「120万円」と決まっており、毎月10万円まで投資可能だ。
つみたて投資枠で活用できる投資信託は、金融機関によっては毎月100円からでも運用ができる。
ある程度お金が貯まらないと・・と始めることを諦めていたり、「どのくらいの資金があればつみたて投資枠での運用ができるのか」などどお悩みの方でもチャレンジしやすい投資法なのだ。
また、クレジットカード支払いが可能な証券会社を選べば、自動で積立投資を行えるので、ポイントを貯められるなど、お得感がある。
仕事や家事で忙しい方でも資産運用を行え、手数料が安価な金融商品も多いため、気軽かつ着実に資産形成を維持できる。

つみたて投資枠の投資対象となる商品の種類
つみたて投資枠で投資対象になる金融商品は「投資信託」で、少額からでも資産運用が可能なので、早い段階から将来のための準備をはじめられる。
投資信託の積立は、資産運用のリスクを軽減させる【分散投資】【積立投資】【長期投資】で運用できるため、比較的安心して運用を継続できるのだ。
また、運用自体は資産運用の専門家が投資家の代わりに行うため、最低限の資産運用の知識があればチャレンジしやすい運用手段である。
では、分散投資と積立投資がどのようにリスクを分散させられるのか学んでいこう。
分散投資
分散投資がなぜリスクを軽減できるのかについて、以下の表を使って解説していくので、ぜひ参考にしてほしい。
| 保有資産 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Aさん | 現金 | 株式 | ||
| Bさん | 現金 | 株式 | 債券 | 不動産 |
AさんとBさんの所有資産が以上の内容の場合、株価が下落するとAさんは総資産の1/2にダメージを負ってしまう。
しかし、Bさんのケースではダメージを1/4に軽減できるため、分散投資の大切さがわかるだろう。
上記では、資産クラスが異なるもので紹介したが、株式などでも複数の銘柄を保有しているとリスクを軽減できる。
| 保有資産 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 株式 | 国内株式A社 | 先進国株式B社 | 先進国株式C社 | 新興国株式D社 |
このように、複数の銘柄を保有していると、A社の株価が下落しても他の金融商品でダメージをカバーできることが分かるだろう。
他にも国内・先進国・新興国というように投資先(国)を分けて運用すれば、投資先(国)の社会情勢や政治などで株価に影響があってもリスク回避できる。
だが、独自で分散投資を行うとなれば膨大な資産と時間が必要になるため、分散投資を実現化させるのは難しい。
通常、日本株式は100株単位で購入でき、1株あたりの株価が3,000円の場合は1社の株式を購入するのに30万円かかってしまう。
また、資産を組み合わせるためには深い専門知識が必要になり、時間をかけて複数の企業について調べるなど、資産運用初心者には難しい。
しかし、新NISAのつみたて投資枠で運用できる「投資信託」は、投資家から集めた資金で分散投資を行っているため、投資信託購入をするだけで分散投資が可能になる。
運用目的や運用期間などの条件に合わせて、保有する投資信託を調整すればリスクとリターンのバランスを整えられるので、理想的な結果を導きやすい。
そのため、最大1,800万円からの利益を非課税にできる新NISAを活用すれば、将来のために低コストで資産形成を行えるのだ。
積立投資
一括投資の方がリターン(利益)を得られるケースもあるが、積立投資を活用することで「ドルコスト平均法」の効果を得られる。
長期投資
数年・十数年と長期的な運用計画で資産運用を行うと、毎日の値動きに感情が左右されずに済むのだ。
投資信託の基準価額は毎日変化するが、長期的な目で見ると日々の基準価額の変動はわずかなものになる。
そのため、資産運用に充てる時間を確保できない方などに長期投資が向いていると言えるだろう。
また、運用期間が長期になるほど「複利効果」を発揮させられ、より効率的に資産を増やせる。
新NISAつみたて投資枠の始め方〜口座開設から投資開始までのポイント

新NISAの積立投資で投資をはじめるには、どのような流れで進めていけばいいのだろうか。
1つ1つ解説していくので、資産運用をスタートさせる際に役立ててほしい。
NISA口座開設から投資開始までのステップ
NISA口座は1人につき1口座までと決まっており、複数のNISA口座を保有できないため、複数の金融機関を見比べてから決めるといいだろう。(年単位であれば変更可能)
金融機関によって取り扱いのある商品や手数料は異なるため、細かい部分も確認しておくと安心だ。
NISA口座開設の流れ
- NISA口座を開設したい金融機関に合わせた方法で、新NISA口座の申込を行う
- 必要書類(本人確認書類)を金融機関に提出
- 金融機関が書類を受け取り、税務署が審査を行う(二重口座ではないかの確認)
- 税務署の審査が終わり次第、NISA口座の開設が完了する
以上の流れで資産運用をスタートさせることができ、書類を提出してからネット証券で最短1〜2日間・金融機関によっては2週間〜3週間程度で開設可能だ。
以下では、必要書類の参考例を紹介していくので、どのような書類が必要になるか事前に確認しておこう。
- マイナンバーカード(顔写真付きのカード)
- 通知カード+運転免許証
- 通知カード+パスポート
- マイナンバーが記載された住民票(写し)+運転免許証
- マイナンバーが記載された住民票(写し)+運転経歴証明書 など
開設時に不明点などが出てきた場合は、証券会社に問い合わせをして解決してほしい。
無事にNISA口座を開設した後は、証券会社のやり方に合わせて運用したい金融商品の積立設定を行えば資産運用をスタートさせられる。
基本的に、資産運用をスタートしたい金融商品を選べば「積立設定」を行えるが、証券会社によってやり方は異なるため、証券会社のサイトなどを確認しながら作業を進めてほしい。
- 参照:ダイヤモンドZAi「新NISAを始める前に今すぐやらなきゃいけない手続きをケース別に紹介! 新NISAで金融機関を変更したい人は旧NISA口座での積立設定を解除するのを忘れずに」
- 参照:野村證券「NISA口座を開設するには何が必要ですか?」
つみたて投資枠における投資目標と投資計画の設定
「新NISAに注目が集まっていて気になる」「友達が新NISAをはじめたから」など、さまざまな理由から新NISAをはじめたいと考えている方も多いだろう。
しかし、具体的な運用目的がなければ、よい結果を得られる可能性が下がってしまうため、「どうして資産運用をはじめたいのか」を明確にしていくといい。
なぜなら、リスク許容度・運用期間・運用目的・貯蓄額などが個人によって異なるため、SNSなどでおすすめされている金融商品がすべての方に合う商品とは限らないためだ。
老後の生活費を準備するために資産運用を行う場合、20代と40代では運用期間も異なるため、毎月の投資額に差が出てくることが予測できる。
計画を立てた上で資産運用をはじめなければ、「得られるはずのリターン(利益)が見込めない」「リスク許容度をオーバーしている」などの問題が発生する。
理想的な運用結果を手にするためにも、運用目的をはっきりとさせ、運用期間や毎月の投資額の把握などを1つ1つ行っていけば自分に合った運用方法を見つけられる。
しかし、「資産運用の知識がないから金融商品を決めるのが不安…」と悩んでいる方も少なくないだろう。
新NISAに関して相談する場合、資産運用の専門家の「IFA」に相談することをおすすめする。
下記「新NISAで始める投資の相談はどこにするべき?」にて詳細を解説しているので、気になる方はぜひ確認してほしい。
つみたて投資枠に効果的な手法とその始め方
上記「投資対象となる商品の種類」で解説した通り、積立投資を行うと「ドルコスト平均法」の効果を発揮できる。
だが、積立投資のメリットはドルコスト平均法だけではなく、手軽に資産運用可能、購入するタイミングに迷わないというポイントがあるのだ。
手軽に資産運用可能
毎月コツコツと資産を積み立てていくので、毎月100円の投資額からはじめられるのだ。
そのため、投資に抵抗がある方はお試し感覚ではじめる選択もでき、金銭的な余裕がない方でも資産形成を行える。
積立投資であれば投資額を調整できるので、長期的に資産運用を行いやすく、上記「投資対象となる商品の種類」で紹介した複利効果も得られるため、大きなメリットだと言える。
購入するタイミングに迷わない
投資と聞くと、「安いタイミングで買うべきでは?」と感じる方も多いだろう。
だが、積立投資であれば、一定額を定期的に購入していく方法のため、「今購入すべきかな…?」と悩む必要がなくなるのだ。
積立設定をしておけば、自動で指定した金融商品の買付けを行うため、手間をかけることなく資産運用を行えるのも魅力的だと言える。
新NISAつみたて投資枠の始め方〜投資先選びのポイント

つみたて投資枠の特徴や口座開設の手順について一通り理解できたところで、「実際にどんな銘柄に投資したらいいのだろう」と考え始めた人も多いだろう。
そこでここでは、つみたて投資枠での自分に合った投資先を選ぶ方法や、リスク管理のポイントを解説していく。
つみたて投資枠の初心者向け:投資信託の選び方
投資を行ったことがない方は特に、「どの商品を選べばいいかわからない…」と悩んでしまう方も多いだろう。
ここでは、初心者向けに投資信託の選び方を解説していくので、自分に合った商品を見つけてほしい。
- どのような金融商品(国)が組み込まれているか確認する
- 運用方法はなにか
- 費用はどれくらい必要か(手数料など)
- 純資産残高はいくらか
どのような金融商品が組み込まれているか確認する
損をするリスクとリターン(利益)は比例しているため、「望んでいるリターンを得られるか」「自分が抱えられるリスク許容度か」を確認しなければならない。
確認する方法の1つとして、投資信託に組み込まれている金融商品を確認することだ。
例えば、「Aファンド:米国株式のみを組み込んでいる投資信託」「Bファンド:国内・先進国・新興国の株式を組み込んでいる投資信託」「C:株式・債券・REIT(不動産投資信託)」があるとする。
Aファンドは長期運用をするとリターンを期待でき、Bファンドは国内以外にも投資を行っているためリスク分散が可能、Cファンドは株式以外の商品も組み合わされているためリスク分散が可能だ。
このように、同じ「投資信託」というジャンルでもどれくらいのリターンを得られ、リスクを背負うことになるかは異なる。
そのため、運用目的や運用目標に合わせて、組み込まれている金融商品を考えるといいだろう。
運用方法はなにか
投資信託の運用方法には「パッシブ運用」「アクティブ運用」があり、どちらの運用方法の投資信託かを把握しておく必要がある。
では、パッシブ運用とアクティブ運用の違いを解説していくので、最初に「ベンチマーク」の意味を理解していこう。
ベンチマークとは投資信託を運用する際に運用の目標にする指数を指し、代表的なベンチマークは以下の通りである。
- 国内
- 日経平均株価
- 国内
- 東証株価指数(TOPIX)
- 米国
- NYダウ
- 米国
- S&P500
パッシブ運用
ベンチマークに連動した運用結果を目指す方法
- 信託報酬はアクティブ運用よりも安い
- ベンチマークよりも大きなリターンを得られる可能性が低い
- 世界経済に影響を受けるため、損をする可能性がある
- 長期運用で資産を増やせる
アクティブ運用
ベンチマーク以上のリターンを目指す運用方法
- ベンチマークよりも大きなリターンを得られる可能性がある
- パッシブ運用に比べると信託報酬が高い
- 世界経済が悪化していても、リターンを得られる可能性がある
- 費用はどれくらい必要か(手数料など)
投資信託は、以下のタイミングで手数料が発生する。
- 購入
- 購入時手数料
- 換金
- 信託財産保留額
- 保有期間
- 信託報酬
新NISAのつみたて投資枠で購入できる投資信託は、購入時手数料が無料になっており、信託報酬も低い傾向にあるが、しっかりと確認しておこう。
純資産残高はいくらか
投資信託の純資産残高が多いほど、投資家からの支持がある「規模が大きい投資信託」だと考えられる。
純資産残高が少なすぎると、早期にに償還される可能性があるので、確認すべきポイントだ。
しかし、「純資産残高が多い投資信託=いい投資信託」とは言えないため、他のポイントを含めて考える必要があるので注意しよう。
つみたて投資枠の投資先選びにおけるリスクとリターンのバランスの重要性
上記「初心者向け:投資信託の選び方」でも解説している通り、リスクとリターンは比例する。
そのため、運用目的に合った投資信託を選ぶことが重要だ。
例えば、20代の方が「長期運用で老後の資金を準備したい」と考えている場合、米国株式の投資信託が理想的である。
株式のみの投資信託は、株式・債券・不動産などのさまざまな金融商品を組み合わせた投資信託よりもリスクが高い。
しかし、長期運用が前提と考えると、リスクを分散させながら大きなリターンを得られる可能性が高いと考えられるのだ。
このように、個人に合ったリスクとリターンのバランスを見つけ、最適な投資信託を見つけるとよい結果を手に入れられる。
金融商品のリスクとリターン・選ぶ際の参考基準について、以下で紹介していくのでぜひ参考にしてほしい。
つみたて投資枠のポートフォリオの多様化と分散投資の重要性
上記「リスクとリターンのバランスの重要性」でも紹介している通り、金融商品によってリスクとリターンは異なる。
運用目的に合わせ、「自分に合ったポートフォリオ」を完成させることが資産運用で成功するための秘訣だ。
上記「投資対象となる商品の種類」でも紹介している通り、複数の資産を保有することでリスクを分散できる。
例えば、50代の方が「資産を守りながら増やしていきたい」と考えている場合、効率的に資産を増やせる米国株式がおすすめではあるがリスクの高さが気になるだろう。
そのような場合、「米国株式の投資信託」と「バランス型の投資信託(株式・債券などを組み合わせたもの)」を保有すると、資産を守りながら増やしていけるのだ。
このように、分散投資が可能な投資信託を選び、個人に合った投資信託を保有することでリスクを軽減させていくことが資産運用において重要なポイントである。
新NISAつみたて投資枠の始め方はどこに相談するべき?

「資産運用の知識がなくて、自分で決めるのは不安だな…」と悩んでしまう方も少なくはない。
ここでは、新NISAについて相談できる専門家について解説していくので、悩んでいる方はぜひ活用してほしい。
新NISAの活用における専門家の重要性
資産運用をしていると「どの金融商品を選べばいいかわからない」「基準価額が下がってしまった…」など、さまざまなタイミングで悩みが発生するだろう。
資産運用は聞きなれない単語が多く、個人に合った金融商品や対処法は違うため、最適な答えをなかなか見つけられないケースもある。
そのような場合、資産運用の専門家「IFA」に相談することをおすすめする。
IFAは資産運用に関する深い専門知識を持ち合わせているため、相談者にとって最適な金融商品や方法を提案してくれるのだ。
大切な資産を守るためにも、資産運用の専門家「IFA」に相談できる環境を整えておくことが大切だと言える。
IFAの役割と利用するメリット
資産運用の専門家「IFA」は「独立系ファイナンシャルアドバイザー」と言われており、金融機関から独立した立場の専門家だ。
資産運用について相談するとなると、証券会社などの金融機関が思い浮かぶだろう。
しかし、証券会社などで資産運用の相談をすると、証券会社に取り扱いのある金融機関の中からの紹介となり、ノルマに反映される商品の提案になるケースも少なくない。
だが、「IFA」は金融機関から独立した立場にいるため、ノルマなど関係なく相談者にとって最適な金融商品やサポートを提供できるのだ。
また、転勤制度などがないため1人のIFAに長期間相談できるメリットもあり、贈与・相続・不動産などの相談も可能である。
「本当に自分に合った金融商品を選びたい」「自分だけのサービスを受けたい」「お金の相談ができるサポーターがほしい」と考える場合、ぜひIFAに相談してほしい。
IFA検索サービス「資産運用ナビ」の活用法とその効果
通常、相談者に合ったIFA探しは時間が必要になるケースも多く、簡単に見つけられない傾向だ。
なぜなら、IFAを探す際に重視すべきポイントは、「専門知識の深さ」「豊富な経験」「サポート範囲」「手数料」だけではないためだ。
「資産運用などに関する考え方」「相談者の意見に寄り添ってくれるか」など、性格の相性も非常に重要になるため、IFAを慎重に選ぶ必要がある。
しかし、IFA検索サービス「資産運用ナビ」を活用すれば、最短60秒で条件に合ったIFAを見つけられるので、仕事などで忙しい方でもスキマ時間を活用するだけで見つけられるのだ。
また、「資産運用ナビ」での相談は原則無料になっており、しつこい営業など不快に感じる対応をされることはない。
「資産運用でよりよい結果を出したい」と考えている方は、ぜひ「資産運用ナビ」を活用し、最短ルートで条件に合ったIFAを見つけてみてはいかがだろうか。
あなたに合った新NISAつみたて投資枠の始め方を見つけよう

新NISAのつみたて投資枠は、最大1,800万円から得たリターンが非課税になり、年間120万円まで投資可能だ。
運用目的に合った計画を立て、将来よりよい結果を手にするために金融商品を選んでいくといいだろう。
つみたて投資枠で活用できる投資信託はドルコスト平均法の効果を得られるので購入単価が安くなり、少額から資産運用が可能だ。
他にも、投資信託は複数の金融商品を組み合わせているのでリスクを軽減でき、長期運用を行えばリターンを得られる可能性が高くなる。
各金融商品のリスクとリターンを理解し、自分が望むリスクとリターンに合った金融商品を選ぶことが、正しくリスクと向き合いながら資産を増やすためのポイントだ。
新NISAを活用した資産運用に関する疑問や不安があれば、資産運用の専門家「IFA」からアドバイスを受けることがおすすめだ。
IFAは金融機関から独立した立場にあるので、相談者にとって最適な金融機関の提案やサポートを行える。
IFA検索サービス「資産運用ナビ」を使えば、最短60秒で条件に合ったIFAを見つけられるので、活用してみてはいかがだろうか。
新NISA、つみたて投資枠、始め方に関するQ&A