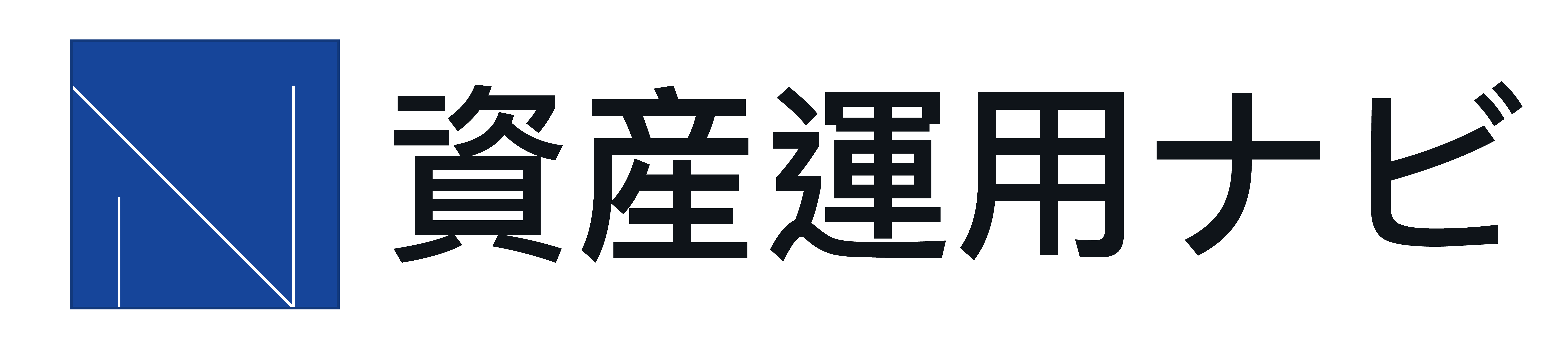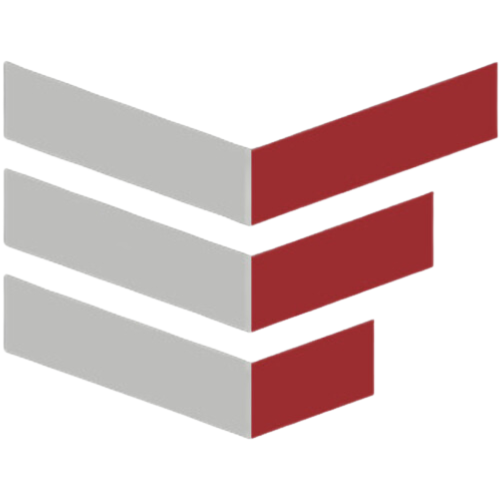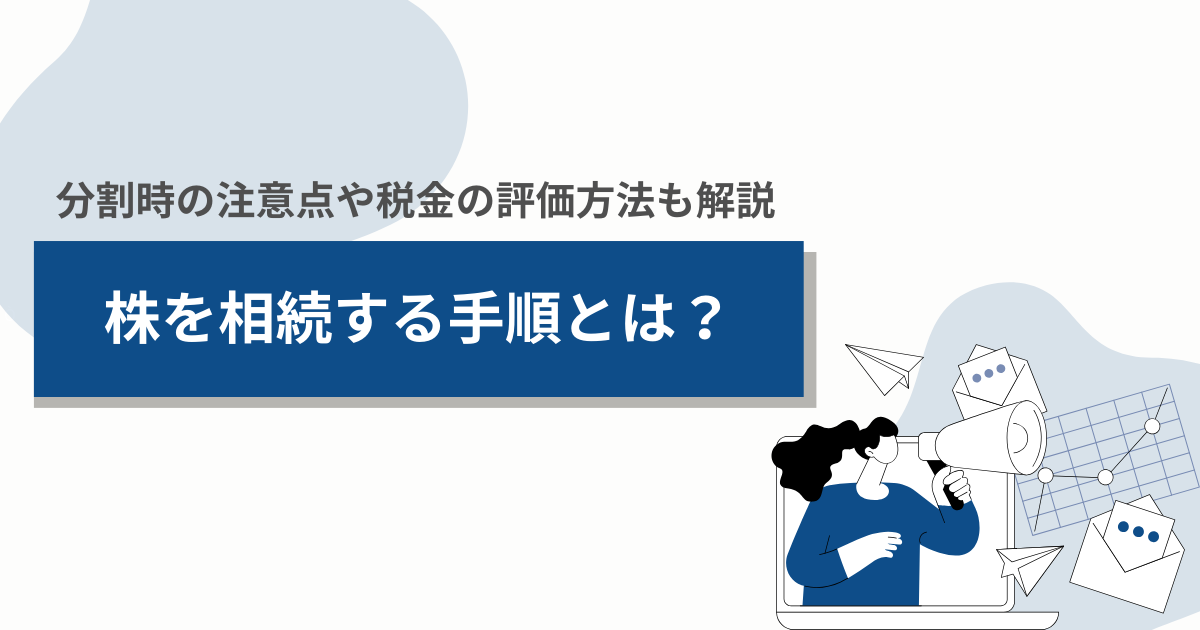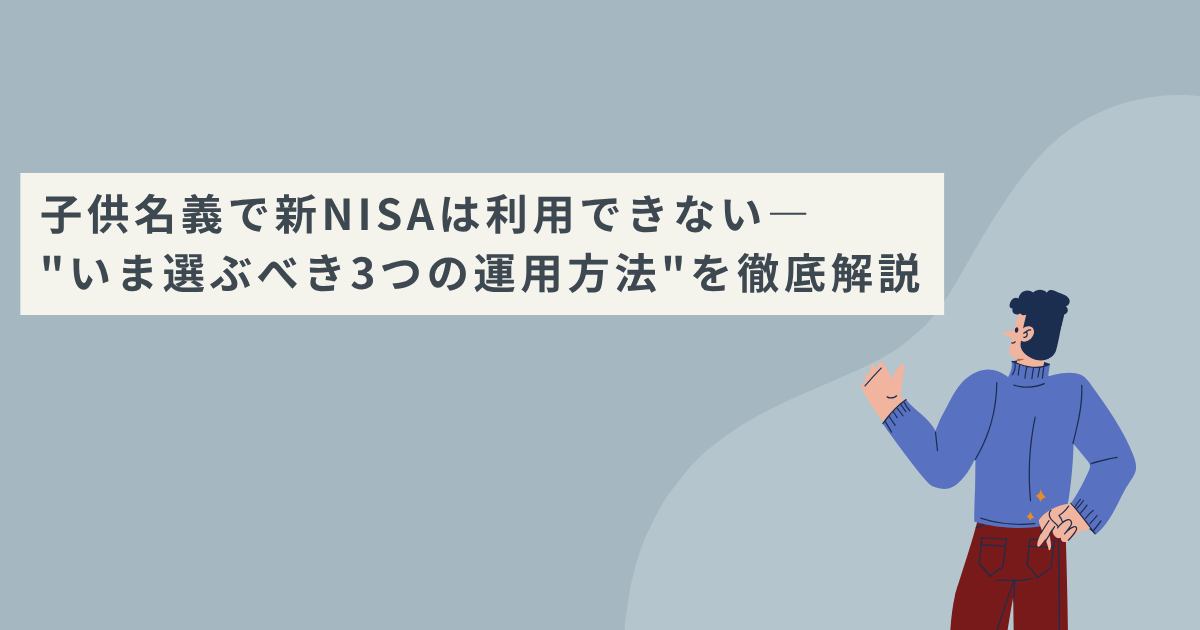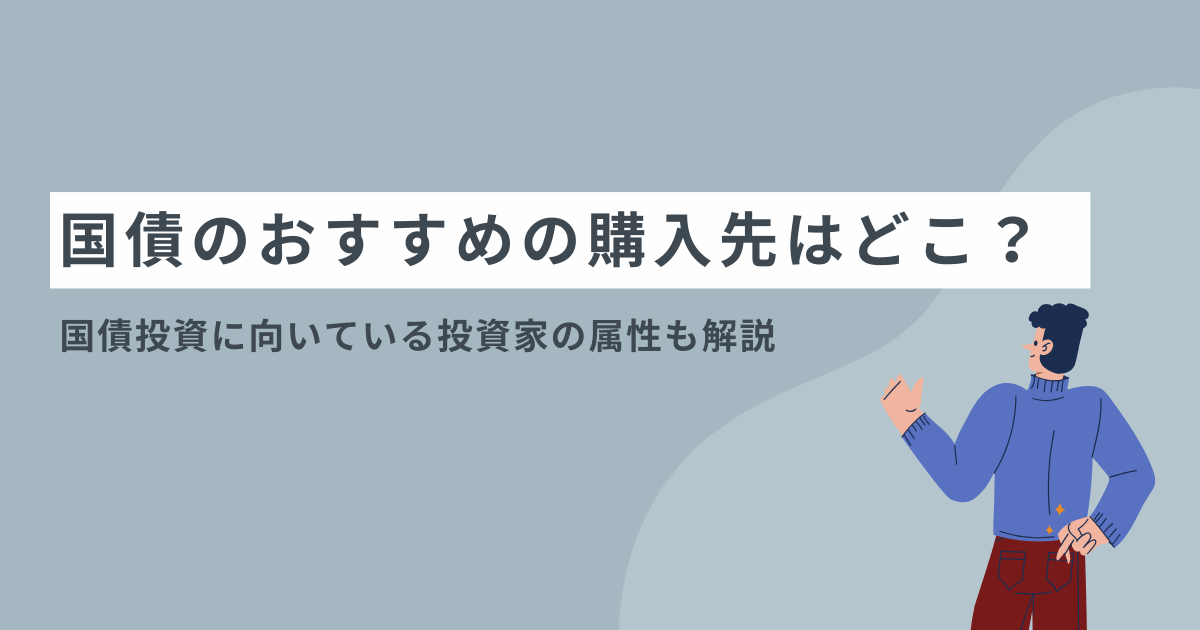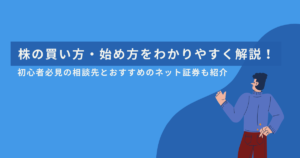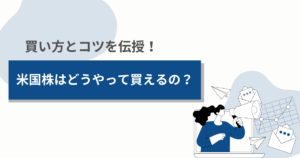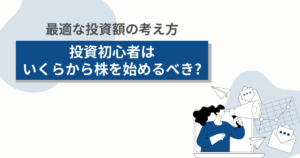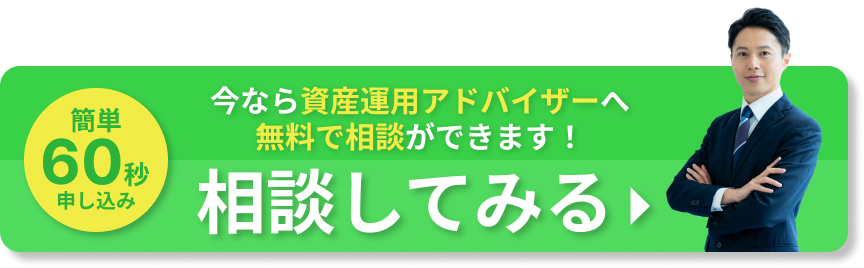- 株を相続する正確な手順が知りたい
- 相続人が複数いる場合の株の分け方が知りたい
- 株を相続する際の注意点が知りたい
「相続財産に株が含まれているかどうしたら良いかわからない」「複数の相続人で株をどのようにわければ良いかわからない」と悩む人は少なくない。
本記事では、株の相続方法や具体的な名義変更手順、株を相続後に売却する際の注意点などを詳しく解説する。
株を相続する人や、今後相続の可能性がある人は、ぜひ参考にしてみていただきたい。
なお、基本的な株のやり方が知りたい人はこちらの記事を見てほしい。

株を相続する手順とは
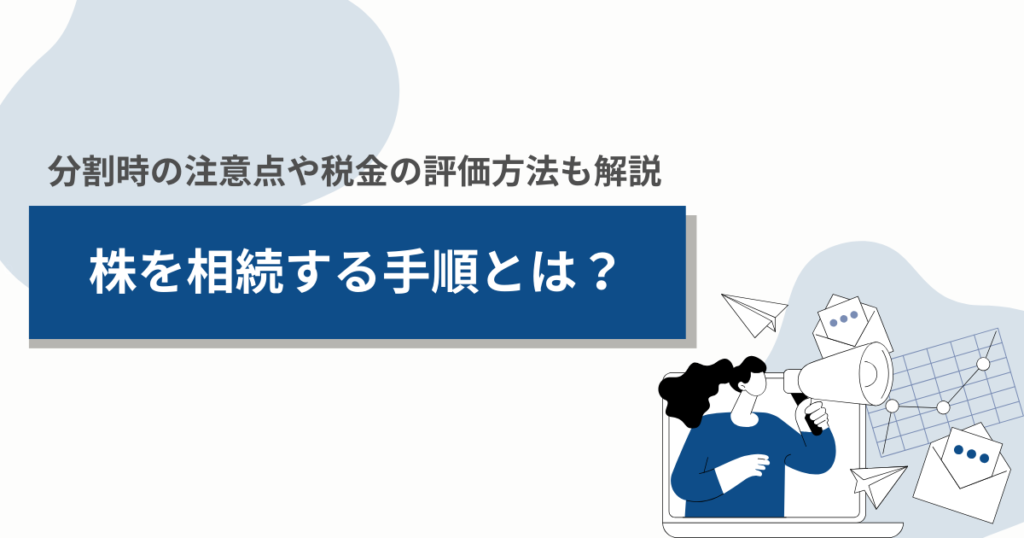
相続が発生すると、さまざまな資産について適切な手続きを行う必要がある。
相続税の申告と納税は、相続が発生してから10ヶ月以内に行う必要があるため、なるべくスムーズに手続きを行わないといけない。
まずは、株を相続する際の基本的な流れを確認しよう。
相続人や相続財産の調査
相続の手続きを始めるにあたって、まずは相続人や相続財産の調査を行う。
被相続人の戸籍謄本を取り寄せ、相続人が誰かを確定させよう。
戸籍謄本を取り寄せると、それまで知らなかった養子や血縁関係にある親族などが判明するケースもある。
また、相続財産についても洗い出し、遺言書があるかどうかもチェックする。
被相続人が株取引を行っていた証券会社に亡くなったことを伝えると、保有していた株式の残高証明書や相続に必要な書類が郵送される。
どの証券会社で口座を保有していたかが不明な場合は、取引残高報告書や残高証明書などの郵送物で確認できる。
郵送物を受け取っていない場合などは、証券保管振替機構に問い合わせることで、被相続人が取引していた証券会社を調べることが可能だ。
ただし、亡くなった人の情報を調べるためには、開示請求書による手続きが必要となる。
上場株式の場合は証券会社で取引することとなるが、投資信託の場合は銀行や信託銀行経由で購入していることもあるため注意しよう。
遺産の分割協議
遺言書があった場合は、遺言書の内容に基づいて遺産の分割を行う。
遺言書がない場合は、遺産分割協議によって被相続人の財産をどう分けるかを決める必要がある。
協議のもとで遺産の分割方法が決まったら、遺産分割協議書を作成する。
株式を複数人で分割して相続する方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種類がある。
遺産分割協議の際の株価の評価方法は分割時となり、分割時に最も近接したタイミングでの終値を用いて評価する。
相続税を申告する際の株式の評価額とは考え方が異なる点に注意しよう。
なお。遺産分割協議が成立するまでは、被相続人が投資していた株は相続人全員の共有財産となるため、勝手に売却したりすることはできない。
相続人の間で遺産分割協議が成立しなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる。
それでも成立しない場合は、審判によって誰が株式を相続するかを決めることとなる。
株式の名義変更の手続き
協議の結果、誰がどれだけ株式を相続するかが決まったら、証券会社で株の名義を変更する。
名義変更に必要な書類は証券会社から案内されるが、一般的に以下のような書類が必要となる。
- 証券会社所定の名義変更依頼書
- 被相続人および相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書または遺言書の写し
- 相続人全員分の印鑑証明書
株の名義を変更する際は、被相続人が取引していた証券会社の口座を相続人も開設する必要がある。
相続人が当該証券会社の口座を持っていない場合は、新たに口座開設の手続きも必要となる点に注意しよう。
なお、上場株式ではなく非上場株式を保有している場合は、発行会社に直接問い合わせを行って名義変更の手続きを行う。
株を相続する方が知っておくべき知識
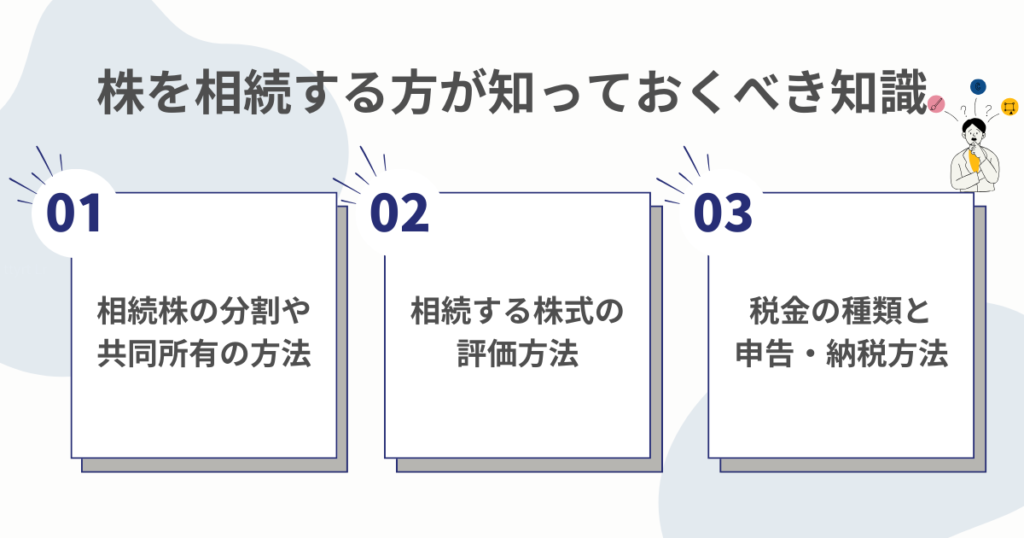
株式の相続を行う際に、必要な基礎知識を確認する。
相続株の分割や共同所有の方法
株式を複数人に分けて相続する場合、以下の3つの方法がある。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
それぞれの仕組みや注意点を確認しておこう。
現物分割
「現物分割」は、株式を売却せずにそのまま株式のまま相続する方法だ。
1,000株を1人がそのまま相続する場合や、1,000株を500株ずつ2人で分ける場合のどちらも現物分割となる。
株式の評価額は日々変動するため、遺産分割協議を終えてから名義を書き換えるまでに株式の評価額が大きく変わることも珍しくない。
また、株式を現金化する際は、証券会社に支払う手数料や売却益に対する譲渡益税などが必要となる。
そのため、相続が発生した後すぐに現金化したとしても相続評価額より手取り金額が減ってしまう可能性がある点に注意しよう。
代償分割
「代償分割」は、株式の現物を1人の相続人がまとめて取得し、それ以外の相続人に対してはその分の現金を支払う方法だ。
株式を取得する相続人は、現金化するために手数料や税金などのコストがかかったり、名義変更などの手間が発生したりするというデメリットがある。
そのため、代償分割を行う際は、その手間やコストを加味して資産配分を調整する場合もある。
換価分割
「換価分割」は、相続手続きの流れの中で保有株を売却し、その売却代金を相続人の中で分割する方法のことだ。
まず、相続人の中の代表者が証券会社に口座を開設して、名義を変える手続きを行った後に株式の売却手続きを行う。
続いて、売却したあと手元に残った現金を相続人の間で協議に基づいて分割する。
分割する時点で証券会社に支払う手数料や譲渡益税などは差し引かれて計算できるため、相続資産を公平に分割しやすいというメリットがある。
相続する株式の評価方法
相続財産がどれくらいかを評価するためには、株式の評価額を決定する作業が必要だ。
株式の時価は日々変動するため、どの時点の価格をもとに計算すべきかが定められている。
上場株式の場合は、以下の4つの価格のうち最も低い価格を評価額として計算する。
- 被相続人が死亡した日の終値
- 被相続人が死亡した月の終値の平均額
- 被相続人が死亡した前月の終値の平均額
- 被相続人が死亡した前々月の終値の平均額
相場の急変などで一気に株価が上がってしまった場合などを考慮して、このような算出方法が定められている。
なお、非上場株式の場合は、上場株式とは異なる算出方法で評価額を決定する。
複雑な算定方法が必要となるため、税理士などに相談するのをおすすめする。
株を相続する時にかかる税金の種類と申告・納税方法
株式にかかわらず、資産を相続する際は相続税が必要となる。
相続税の算出手順は以下のとおりだ。
- 株式の評価額を算出する
- 株式の評価額をその他の財産と合算して、遺産総額を算出する
- 遺産総額から負債や基礎控除などを差し引いて、課税遺産総額を算出する
- 課税遺産総額から、相続税の速算表を用いて、相続税額を算出する
相続税は、取得金額に応じて税率が上がる累進課税方式であり、最大55%の税金がかかる。
詳細や速算表については、国税庁のホームページからも確認できる。
さらに、相続した株を売却した場合は、売却益に対して所得税および住民税が必要となる。
株式の売却益に対してかかる所得税・住民税は一律で20.315%だ。
売却益は、売却代金から売却手数料および被相続人が取得した金額を差し引いた金額となる。
なお、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合は、売却した株式に対して発生した相続税の金額を取得費に加算できる特例がある。
被相続人が取得した金額が不明な場合は、売却代金の5%を取得費として売却益を計算するため、非常に高額な税金がかかる。
被相続人が源泉徴収ありの特定口座を使用していて、相続人も源泉徴収ありの特定口座に移管して売却した場合であれば、証券会社が譲渡益税の計算と源泉徴収を行ってくれるため、確定申告の必要はない。
ただし、被相続人が一般口座を利用している場合や譲渡損が生じている場合は、確定申告が必要となるため注意しよう。
\ あなたに合うアドバイザーを診断 /
相続した株を売却する手順とは
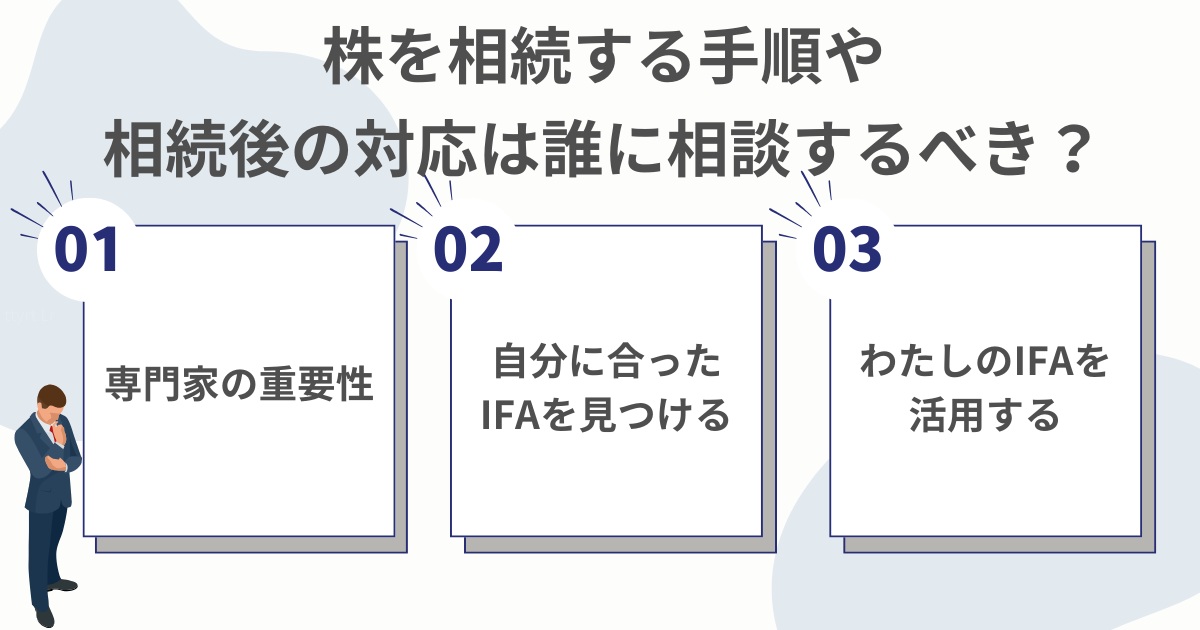
相続によって手に入れた株を売る際の方法および注意点を確認していく。
個別売却・一括売却の概要及び注意点
複数の相続人が相続財産として株式を相続する場合、株式のまま保有を続けたい人もいれば、すぐに現金に変えて預貯金などに預けたいという人もいるだろう。
どのように保有したいかのニーズが異なる場合は、個別売却がおすすめだ。
相続人それぞれが個別に株式を保有するように名義変更の手続きを行い、売却するか保有を続けるかをそれぞれ決める。
この方法は、上記で解説した「現物分割」に該当する。
また、1人だけが株式のまま保有を希望し、それ以外の相続人は現金での相続を希望する場合などは、「代償分割」という選択肢もあるだろう。
一方で、相続人すべてが株式のまま保有したいという意向を持っておらず、現金化したいと考える場合は、「換価分割」による一括売却がおすすめだ。
相続人から代表者を決めて名義変更や売却の手続きを行い、現金化した後に相続人間で売却代金を分割することで、スムーズかつ公平に分割しやすい。
非上場株式の売却方法と注意点
証券取引所に上場していない非上場株式の場合、上場株式とは異なる方法で売却を行う必要がある。
証券取引所での売買ができないため、自ら買い手を見つけなくてはならないが、上場していない株式の場合は「譲渡制限」が設けられているケースが多い。
そのため、非上場株式を手放す場合は、まずは発行会社に譲渡制限の有無を確認し、売却方法などについても相談してみよう。
場合によっては発行会社が株式を買い取ってくれるケースもあるが、相続したにもかかわらず売却できない可能性もある。
逆に、非上場株式によっては相続で取得した際に強制的に売り渡すように請求できる権利を定めている場合もある。
その場合は、相続した非上場株をそのまま保有したいと思っても、会社に売却しないといけない。
後から見つかった相続株の売却方法と注意点
相続手続きを完了した後に被相続人名義の株式が見つかった場合などは、タイミングによって手続き方法が異なる。
相続税の時効は申告期限から5年と定められているため、相続手続きから5年以上経過したあとに見つかった財産については修正申告の必要がない。
ただし、虚偽申告やわざと財産を隠していた場合など、不正行為があった際の時効は7年となる。
一方、時効を迎える5年以内に株式が見つかった場合は、相続税の修正申告を行わなければならない。
税務署に指摘されて修正申告を行う場合は過少申告加算税の対象となるが、自ら気づいて申告を行う場合は対象外となるため、なるべく早く手続きを行おう。
通常の相続と同様に名義変更に必要な手続きを行った後に、株式を売却できるようになる。
なお、見つかった株式に受け取っていない配当金がある場合は、株式の発行会社の株主名簿管理人に指定されている金融機関で所定の手続きを行う。
ただし、配当金には3年ないし5年といった時効が定款で定められているケースがほとんどであるため、あらかじめチェックするのをおすすめする。
株を相続する手順や相続後の対応は誰に相談するべき?
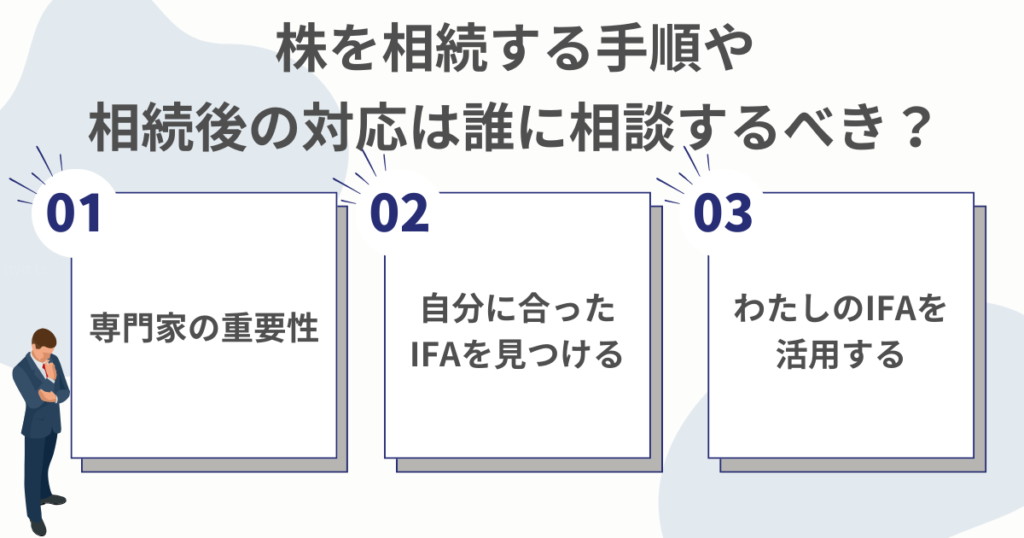
株式の相続が発生する際は、株式投資の専門家に相談するのがおすすめだ。
ここでは、おすすめの相談先や相談すべき理由を解説する。
株の相続に関する疑問や不安を専門家に相談する重要性
株を相続する際は、株式を売却するか保有を継続するかについて考える必要がある。
すでに株式投資を行っている人は、そのまま相続した株への投資を続けたいと考える人もいるだろう。
しかし、株式を保有することでそれまでの投資ポートフォリオの資産配分も変わるため、あらためて運用計画を立て直したり、投資先の再選定を行ったりする必要も生じるだろう。
また、今後成長の見込みのない銘柄については、売却して別の銘柄に投資をした方が効率よく資産形成を図れる場合もある。
このように、相続した株式をどのように取り扱うべきかは人によって異なるため、それぞれのニーズやリスク許容度に合わせて対応策を検討することが重要だ。
専門家に相談することで、相続した株式を売却すべきか保有すべきか、といった点についてもアドバイスをもらえるだろう。
IFAの役割とメリット
IFAは、独立系ファイナンシャルプランナーとも呼ばれ、銀行や証券会社などの金融機関から独立して資産運用のアドバイスや金融商品の仲介を行う専門家だ。
株式に関しても豊富な知識と経験を持つため、相続する株をどのように取り扱うかについても適切なアドバイスが期待できる。
また、投資を継続する場合の運用ポートフォリオの設計や運用銘柄の選定についても助言してもらえるため、安心して投資を任せられるだろう。
相続する株式について相談したいという方は、ぜひIFAへ依頼してみてはいかがだろうか。
IFA検索サービス「資産運用ナビ」の活用法
自分にぴったりのIFAを探す場合は、IFA検索サービス「資産運用ナビ」を活用してみよう。
「資産運用ナビ」は、住まいや年齢、金融資産などを入力するだけで、全国のIFAデータベースから自分にぴったりのアドバイザーが検索されるサービスだ。
アドバイザーの得意分野や相談実績はプロフィールページから確認できるため、相続や株取引に強いアドバイザーを選ぶと良いだろう。
相談費用は原則無料となっているため、気軽に複数のアドバイザーに相談できるのもメリットだ。
自宅や勤務先近くのカフェ、オンラインなど、希望の場所で面談できるため、普段仕事や家事などで忙しい方も隙間時間に相談しやすいだろう。
興味のある方は、ぜひIFA検索サービス「資産運用ナビ」を活用してみよう。
株を相続する手順はあらかじめ理解しておこう
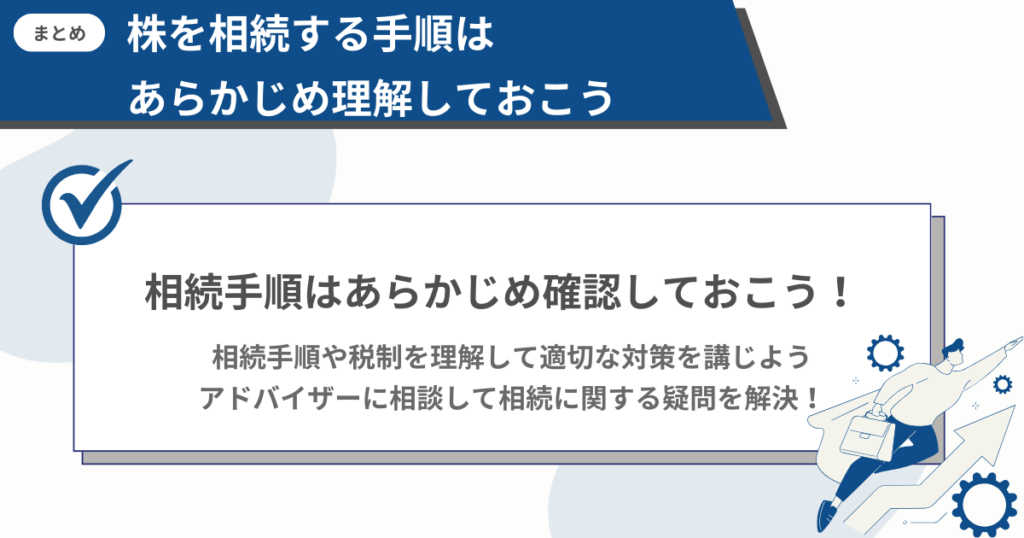
株を相続するにあたっては、評価方法や相続方法、相続の手順などをあらかじめ確認しておくことが重要だ。
相続した後は、速やかに名義変更の手続きを行い、売却や保有などニーズに応じた対応を行う。
相続した株式を売却する際は、税金や手数料なども考慮する必要がある。
株の相続について、疑問や不安があれば専門家からアドバイスを受けることをおすすめする。
特にIFAは、中立的な立場からあなたに最適なアドバイスを長期にわたって提供してくれる。
IFAへの相談を検討する際は、IFA検索サービス「資産運用ナビ」を活用して、あなたにあったアドバイザーを探してみよう。
\ あなたの資産運用を任せるプロを診断 /
株を相続する手順に関するQ&A
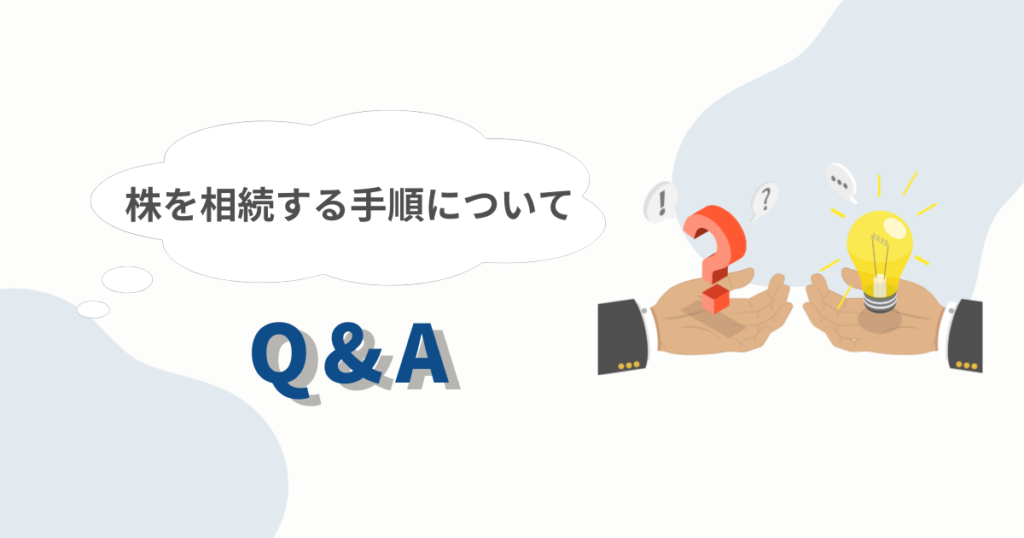
\ あなたの資産運用を任せるプロを診断 /