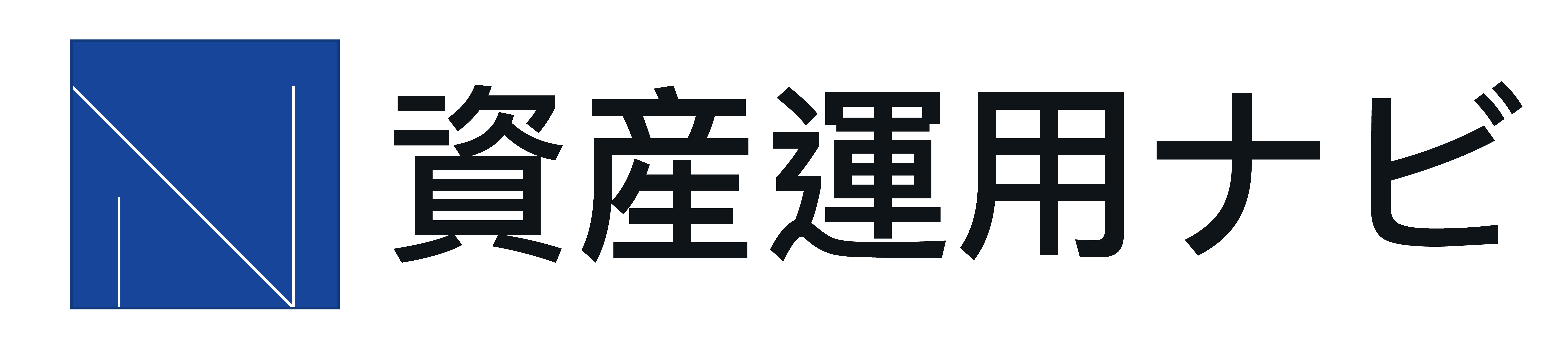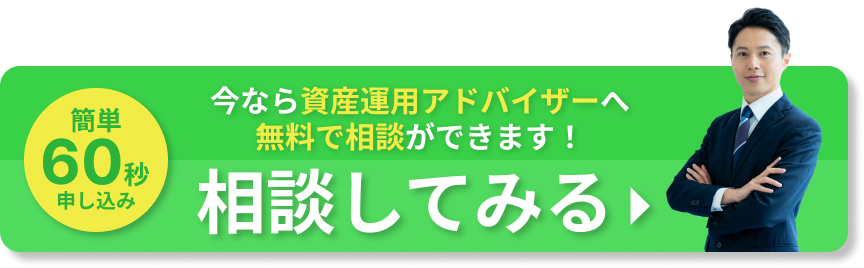※本ページはアフィリエイトリンク(広告)を含みます
- 新興国株式に投資してみたいがどの銘柄が良いのかわからない
- 新興国株式投資におすすめの証券会社が知りたい
- 新興国株式の選び方がわからない
「新興国株式投資を始めてみたいけど、どの銘柄を選択すれば良いかわからない」「新興国株式に投資すると、どんなメリットがある?」
新興国株式投資を検討している方には、このような疑問や不安を抱えている方も多いのではないだろうか。
そこで本記事では、新興国株式投資におすすめな投資方法やおすすめの銘柄、新興国株式投資を成功させるためのコツについて解説していく。
また、新興国株式投資におすすめな証券会社についても言及しているため、ぜひ最後まで読んで新興国株式投資を始めるきっかけとしてほしい。
新興国株式に投資したいなら投資信託・ETFで運用するのがおすすめ

ここでは、新興国株式投資におすすめな投資方法および新興国株式投資を行うメリットについて解説していく。
新興国株式投資におすすめな投資方法
新興国株式投資を行うにあたっては、主に以下の2つの方法がある。
- 新興国の株式そのものに投資する
- 新興国株式を投資対象としたファンドへ投資する
上記の2つの方法のうち、おすすめなのは「新興国株式を投資対象としたファンドへ投資する」方法だ。
新興国の株式そのものに投資を行う場合、どの国の株式にするのか、業種はどのようなものにするのかなど、さまざまな事柄を検討する必要がある。
一方で、新興国株式を投資対象としたファンドへ投資する方法であれば、運用会社が運用方針に応じて国や地域、業種、通貨などを分散させながら投資を行っているため、1つのファンドに投資をすることで、複数の新興国株式に分散投資ができるのだ。
分散投資は投資における基本であり、分散投資を行うことでリスクも抑えられる。
そのため、新興国株式投資を行うのであれば、新興国株式を投資対象とした投資信託やETFへ投資することがおすすめだ。
新興国株式投資を行うメリット
新興国株式投資を行うメリットは、主に以下の2つだ。
- 高い成長性が見込まれる
- ポートフォリオ全体におけるリスクを抑えられる
先進国と比較し、新興国は経済成長が著しい。株式市場は経済成長に伴って伸びていくため、新興国株式への投資は高い成長性が見込まれるのだ。
昨今では、インドのIT産業やブラジルの農業技術、中国のグリーンエネルギーなどの分野が大きく成長している。
また、高い成長性が見込まれる理由として、人口における若年層の割合が高いことも挙げられる。
若年層が多いことによって労働人口が増加するだけでなく、消費活動も活発になることが考えられるため、持続的な経済成長の可能性を高める要因となるのだ。
加えて、新興国株式へ投資することで、ポートフォリオ全体におけるリスクを抑える働きもある。
一般的に、新興国市場は先進国市場とは異なる動きをするケースが多い。
そのため、先進国を投資対象とした商品と新興国株式を適切に組み合わせてポートフォリオを構築することで、リスクを分散させることが可能となるのだ。
ただ、新興国株式投資は、高いリターンが得られる可能性が高い分リスクを伴う点には注意が必要だ。
新興国株式投資を行う際の注意点については後述する。
新興国株式投資におすすめの銘柄3選

新興国株式投資を行うにあたって、おすすめのインデックスファンドは以下の3商品だ。
- iFree新興国株式インデックス
- たわらノーロード新興国株式
- eMAXIS Slim新興国株式インデックス
それぞれの商品の特徴について解説していく。
iFree新興国株式インデックス
「iFree新興国株式インデックス」は、大和アセットマネジメントによって運用されているインデックスファンドだ。
「FTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)」をベンチマークとしており、それに連動した運用成果が得られるよう、新興国の株式を中心に投資証券やREITなどに投資をしている。
このファンドにおける上位5つの投資先(国・地域)は以下のとおりだ。
- 中国:38.7%
- 台湾:16.7%
- アメリカ:10.6%
- インド:10.3%
- ブラジル:8.9%
新興国のみならず、先進国であるアメリカを上位に組み込むことで、カントリーリスクを抑えた運用を行っているのだ。
また、このファンドの騰落率を期間別に見ると以下のとおりとなる。
ベンチマークの成長に伴って、ファンドも成長していることがわかるだろう。
加えて、このファンドを購入する際の購入時手数料や売却する際の信託財産留保額は無料で、信託報酬は年率0.374%となっている。
後述する2商品よりも信託報酬は高めに設定されているものの、騰落率は最も高いため、多少運用コストがかかってもファンドの成長性を求めたい、という方におすすめな商品だ。
なお、2025年1月10日時点におけるこのファンドの純資産総額は221億8,600万円、基準価額は23,189円である。
※出典:大和アセットマネジメント「iFree新興国株式インデックス 月次レポート」
たわらノーロード新興国株式
「たわらノーロード新興国株式」は、アセットマネジメントOneによって運用されているインデックスファンドだ。
「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)」をベンチマークとしており、主に海外市場に上場する新興国株式が投資対象となっている。
このファンドにおける上位5つの投資先(国・地域)は以下のとおりだ。
- インド:19.82%
- 台湾:18.63%
- ケイマン諸島:16.14%
- 中国:10.39%
- 韓国:9.93%
また、このファンドの騰落率を期間別に見ると以下のとおりとなる。
先述した「iFree新興国株式インデックス」と比較すると、ベンチマークとする指数に概ね連動した運用成果が得られていることがわかるだろう。
このことから「たわらノーロード新興国株式」は、安定した運用実績を目指す方におすすめのインデックスファンドだ。
ただ、このファンドの購入時にかかる手数料は無料で、信託報酬は年率0.1859%と低水準に抑えられているものの、ファンド売却の際には信託財産留保額として「換金申し込みの受付日の翌日の基準価額×0.3%」の支払いが発生する点には注意してほしい。
なお、2025年1月10日時点におけるこのファンドの純資産総額は288億6,100万円、基準価額は20,880円だ。
※出典:アセットマネジメントOne「たわらノーロード新興国株式 月次レポート」
eMAXIS Slim新興国株式インデックス
「eMAXIS Slim新興国株式インデックス」は、三菱UFJアセットマネジメントによって運用されているインデックスファンドだ。
「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)」をベンチマークとしており、ベンチマークを構成する新興国株式等にマザーファンドを通して投資をすることで、ベンチマークに連動した運用成果を目指す商品である。
このファンドにおける上位5つの投資先(国・地域)は以下のとおりだ。
- インド:19.3%
- 台湾:18.2%
- ケイマン諸島:15.7%
- 中国:10.1%
- 韓国:9.6%
先述した「たわらノーロード新興国株式」とベンチマークが同様であるため、割合こそ異なるもののファンドを構成する上位国・地域も同様であることがわかる。
また、このファンドの騰落率を期間別に見ると以下のとおりとなる。
上記を見ると、運用期間が長くなればなるほどファンドも成長していくことから、長期運用を行うことが重要だ。
「eMAXIS Slimシリーズ」は、取引コストを徹底的に抑えることを目的としたファンドであるため、購入時手数料や信託財産留保額は無料、信託報酬も年率0.15158%〜0.15180%※と、先述した2商品と比較しても最も取引コストが低い。
そのため、取引コストを抑えて新興国株式運用をしたいという方におすすめの商品だ。
なお、2025年1月10日時点におけるこのファンドの純資産総額は1,845億2,900万円、基準価額は16,510円である。
※ファンドの純資産総額が2,500億円未満の部分:0.15180%、2,500億円以上5,000億円未満の部分:0.15169%、5,000億円以上の部分:0.15158%
※出典:三菱UFJアセットマネジメント「eMAXIS Slim新興国株式インデックス 月次レポート」
新興国株式投資におすすめの証券会社

新興国株式投資におすすめなのは「SBI証券」と「楽天証券」だ。
それぞれの証券会社の特徴を解説すると同時に、新興国株式投資を行う際の注意点についても触れていく。
SBI証券
SBI証券はネット証券の最大手であるが、特徴としては以下の3点が挙げられる。
- 取引コストが安い
- 商品ラインナップが豊富
- 取引によってポイントがためられる
最大の特徴は、取引コストが安い点である。
例えば、購入時手数料がかからない「ノーロード」の投資信託を多く取り扱っているだけでなく、所定の条件を満たすことで国内株式における取引手数料が無料となるのだ。
また、株式や投資信託以外にもETFや債券、先物・オプション、FX、CFD、暗号資産といった幅広い商品への投資が可能な点も特徴の一つである。
さらに、取引によってポイントがためられる点も大きな特徴だ。以下5つのポイントから取引によって任意のポイントがためられるのである。
- Vポイント
- Pontaポイント
- dポイント
- JALのマイル
- PayPayポイント
たまったポイントは国内株式や投資信託の購入に利用できるが、その際に利用できるのは「Vポイント」および「Pontaポイント」の2種類である点には注意してほしい。
\ 累計口座数1,000万突破!手数料無料で取引するなら /
楽天証券
楽天証券もネット証券における大手の一つだ。特徴は以下の3つである。
- 楽天ポイントがためられる
- 幅広い商品への投資が可能
- 楽天銀行と連携することで普通預金金利がアップする特典がある
投資信託や米国株式の円貨決済、楽天カードを利用した投信積立など、対象の取引によって楽天ポイントがためられる点が大きな特徴だ。
たまった楽天ポイントは投資信託や米国・国内株式、バイナリーオプションなどに利用できる点は嬉しいポイントである。
また、SBI証券と同じく投資信託や株式以外にもさまざまな商品へ投資ができ、投資家それぞれのニーズを満たすことが可能だ。
加えて、楽天証券と楽天銀行を連携させることで入金・出金手続きがスムーズになるだけでなく、楽天銀行の普通預金金利がアップするという特典がある。
そのため、楽天経済圏を活用している方は、楽天証券を選択することがおすすめだ。
新興国株式投資のコツ
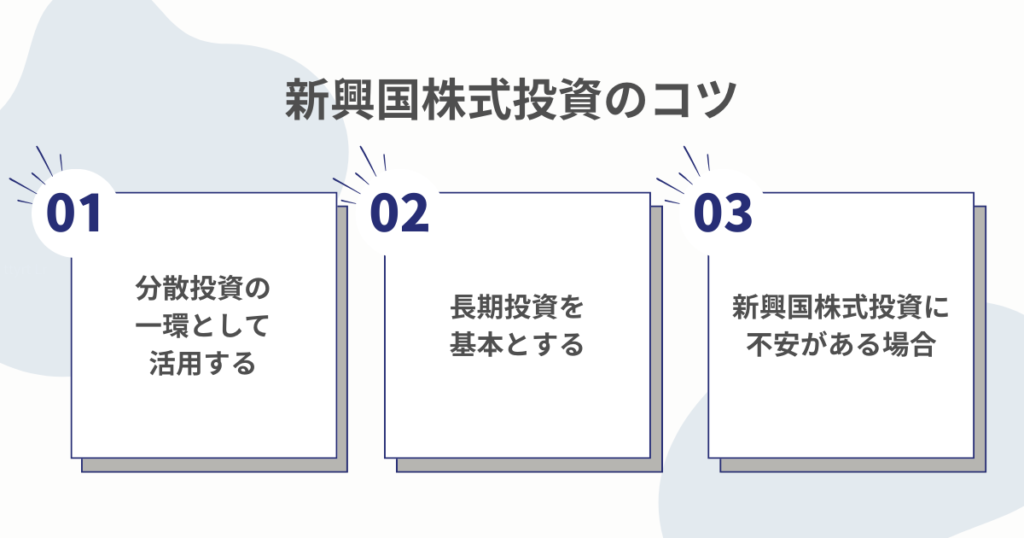
新興国株式投資の成功に向けては、以下2点を意識することが大切だ。
- 分散投資の一環として活用する
- 長期投資を基本とする
また、新興国株式投資に不安がある場合の対処法についても解説していく。
分散投資の一環として活用する
先述したとおり、新興国株式投資は比較的ハイリスクな運用となりやすい。
そのため、新興国株式のみに投資を行っていると、新興国の経済情勢が大きく変動し株式市場にも影響がでた場合に、自身の資産に与えるダメージが大きくなってしまう。
新興国に投資するのであれば、株式だけでなく債券やREITなど異なる資産クラスの商品を組み合わせること、新興国だけでなく国内や米国といった比較的安定した運用となりやすい先進国を投資対象とした株式や債券、投資信託にも分散投資を行ってほしい。
また、新興国株式のポートフォリオへの組み入れ割合は、投資家それぞれのリスク許容度によって異なるものの、リスク許容度が低い方は10%程度、リスク許容度が高い方は30%程度に抑えておくと良いだろう。
長期投資を基本とする
新興国株式市場は、短期間における価格変動が激しくなりやすい。
先述した「iFree新興国株式インデックス」「たわらノーロード新興国株式」「eMAXIS Slim新興国株式インデックス」の3商品の騰落率を見てもわかるとおり、運用期間が長くなれば、それだけファンドが成長する可能性が高くなる。
そのため、少なくとも10年は投資を継続することで、長期的なリターンにつなげられるはずだ。
新興国株式投資に不安がある場合
新興国株式投資に不安がある場合、まずは少額投資から始めてみよう。
ポートフォリオに占める割合が5%未満であれば、自身の資産にそれほど大きな影響は受けないはずだ。
新興国市場の動向がつかめるようになってきたら、少しずつポートフォリオにおける構成比率を高めていくと良いだろう。
また、自分だけで運用判断を行うのではなく、専門家の力を借りることもおすすめだ。
専門家に相談しながら新興国株式投資を進めていくべき理由や専門家とのマッチングサービスである「資産運用ナビ」の活用法については、後述していく。
新興国株式投資を始めるなら「資産運用ナビ」で専門家に相談しよう

ここでは、以下3点について解説していく。
- 新興国株式投資の難しいポイント
- 新興国株式投資をするなら専門家と進めるべき理由
- 「資産運用ナビ」のメリットと活用法
それぞれ見ていこう。
新興国株式投資の難しいポイント
新興国株式投資は、先進国を投資対象とする他の商品等と比較して、価格変動リスクが多いだけでなく、信用リスクや流動性リスクなど、さまざまなリスクが伴う。
特に、短期間における価格変動が大きくなる傾向にあることから、適切な銘柄を選定し長期運用を行うことが重要だ。
また、新興国株式を投資対象としたファンドには多くのラインナップがあるが、それぞれの商品によって投資対象としている国・地域が異なったり、運用方針が異なったりする。
それぞれの商品における違いを正確に把握し、自分に合った商品を見極めることが、新興国株式投資における難しいポイントなのだ。
新興国株式投資をするなら専門家と進めるべき理由
新興国株式投資を行う場合、さまざまな商品を比較しながら自身にとって最適な商品を選択する必要がある。
しかし、投資を始めたばかりであったり、新興国株式への投資経験がない方は、どの商品を選択すれば良いか迷ってしまうはずだ。
そのようなときは、専門家に相談することをおすすめする。
適切な銘柄選びに協力してもらえることに加え、専門家は新興国市場に関する最新の動向を常に追っているため、タイムリーな情報を提供してくれるだろう。
また、新興国株式投資においては、長期運用することはもちろん、分散投資の一環として活用することが大事である。
「どのように分散投資をするべきか判断できない」という方は、専門家の力を借りながら自身のリスク許容度に合わせたポートフォリオの構築および銘柄選定を行うようにしてほしい。
そうすることで、新興国株式投資での運用成果を最大化できるはずだ。
ただ、一口に専門家といっても、銀行や証券会社といった金融機関の営業担当者やFP、IFAなどさまざまな専門家がいる。
誰に相談すれば良いかわからないという方は、ぜひ「資産運用ナビ」の活用をおすすめする。
「資産運用ナビ」のメリットと活用法
「資産運用ナビ」とは、オンライン上にて相談したい内容や自身の年齢、金融資産の保有額といった簡単な項目を入力するだけで、あなたにぴったりな専門家が探せるマッチングサービスである。
「資産運用ナビ」に登録されている専門家のプロフィールは自由に閲覧できるため、自分が相談したい内容を得意とする専門家を選択することが可能だ。
それだけでなく、初回相談は無料であるため、信頼のおける専門家に出会えるまで何度でも面談ができる点もメリットとして挙げられる。
新興国株式投資のコツである「分散投資」「長期運用」を実践し、自身が望む運用成果が出せるよう協力してくれる専門家を「資産運用ナビ」によって見つけてほしい。
新興国株式へはファンドを通じた投資がおすすめ

本記事では、新興国株式投資におすすめな投資方法やおすすめの銘柄、新興国株式投資を成功させるためのコツを解説した。
新興国株式投資を行うにあたっては「新興国の株式そのものに投資する方法」と「新興国株式を投資対象としたファンドに投資する方法」の2つがある。
初めて新興国株式に投資するのであれば、簡単に分散投資ができる「新興国株式を投資対象としたファンドへの投資」がおすすめだ。
また、おすすめのネット証券会社として「SBI証券」および「楽天証券」を紹介した。新興国株式投資を行う際には、これらの証券会社で口座開設しよう。
ただ、新興国市場には先進国市場と比較してより大きな価格変動リスクや信用リスク、流動性リスクが伴うため、銘柄の選定や運用方法に不安を感じることもあるだろう。
そのようなときは、専門家に相談するのも一つの手だ。
専門家に相談しながら新興国株式投資を行うことで、自分に最適な銘柄で効果的な運用が期待できる。
一方で、専門家は全国に数多く存在するため、専門家選びに迷うケースもあるはずだ。
その際には、簡単な質問への回答だけで自分に合った専門家とマッチングできる「資産運用ナビ」を活用し、長期的に相談が可能で信頼のおける専門家を探してほしい。
新興国株式のおすすめに関するQ&A