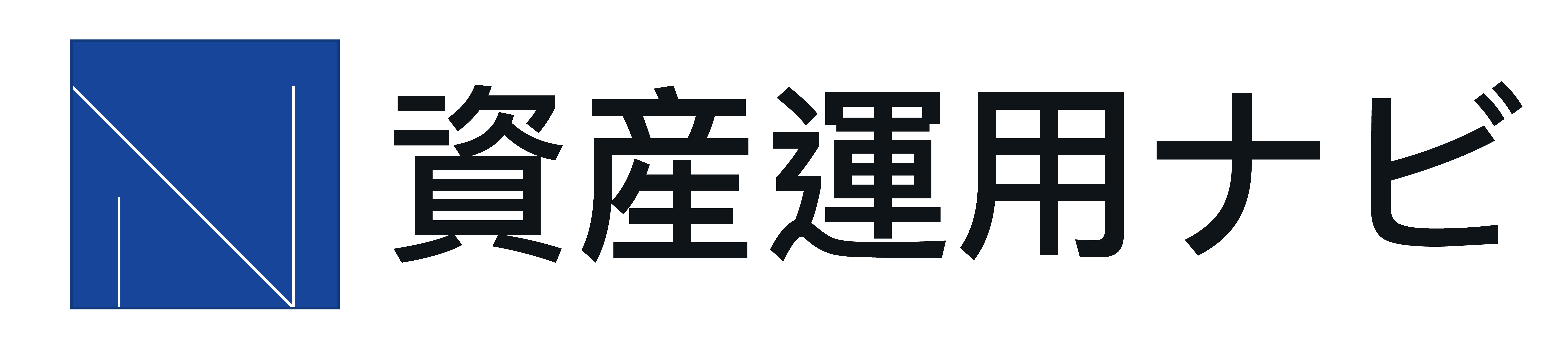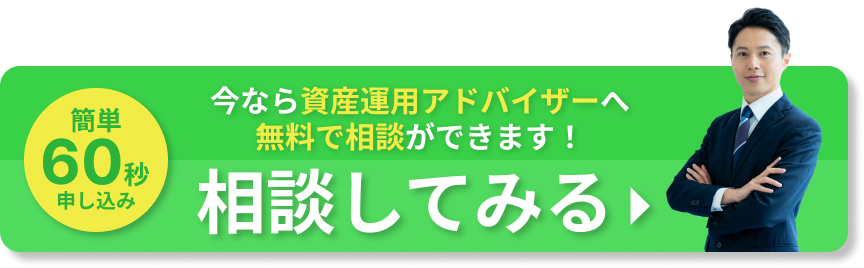- 債券の基本的な選び方を理解したい
- 自分に合った債券を選びたい
- 債券投資のポイントを理解したい
投資の世界で伝統的な資産と言われるのは株式と債券だ。
債券は株式に比べると個人投資家には馴染みがない投資対象ではないだろうか。
株式に比べて個人向けのメディアで債券は取り上げられる機会も少なく、ネット証券などでの取り扱いはあるものの、個人向けの債券は選べる種類が少ない。
また、債券は株式に比べて市場で自由に売買できる使い勝手の良い環境が個人投資家に十分に提供されていないことも、馴染みづらい原因かもしれない。
また、債券投資の概要についても分かりづらいところが多い。
しかし、債券は株式に比べリスクが相対的に低く、決まった利息を受け取れるメリットがある。
株式に比べ収支の予測が立てやすく堅実な運用に適しているのも魅力だ。
本記事では、債券投資を始める際に知っておくべき基礎知識や、自分に最適な債券の選び方、適切なリスク管理法について解説する。
この記事を通じて債券への理解を深め、債券投資への一歩を踏み出して欲しい。
また、おすすめの債券を知りたい方はこちらを参考にしてほしい。
債券を選ぶために知っておくべき債券投資の基本

債券は定期的に利子を受け取れる投資対象だ。
また、値動き次第で売却益が狙える投資対象でもある。
安定した投資先として知られているが債券の仕組みや種類、リスク、売買の基本など分かりづらい点が多く投資しづらいという方も多いのではないだろうか。
そこで、債券投資の基本を3つのポイントから確認する。
- 債券の仕組みや種類
- 債券投資のリスクとリターン
- 債券投資を始める前に知るべきこと
債券の仕組みや種類に関しては、そもそも債券とは誰がどのような目的で発行しているのかを押さえておきたい。
また債券投資でどのようなリスクとリターンがあるのかも確認しよう。
そして、債券投資を個人投資家が行うには、どこでどのように購入できるのかも知らないと始まらないので、投資前に知るべき概要も説明する。
債券の仕組みと種類
債券とは、国や企業の発行する借用証書のようなものだ。
お金を集めたい発行体とお金を貸したい投資家で成り立っている。
発行体には国や地方などの公共団体もあれば、民間企業もある。
国が発行すれば国債、地方公共団体が発行すれば地方債、民間企業が発行すれば社債だ。
国債ならば、日本国債や米国債、地方公共団体ならば、東京都債や横浜市債、社債ならばSBI債や楽天モバイル債などが挙げられる。
株式投資と債券の違いを比べてみると、債券の特徴が分かりやすい。
株式を保有するのは企業に出資をしてオーナーになることだ。
一方、債券は企業のお金の貸し手となることだ。
お金を貸すことを通して利息を受け取れて満期まで保有すると約束された金額が返ってくる。
また、債券は借用証書のようなものなので権利を売買することもできる。
そのため、既に発行された債券を市場で売買することもできる。
ちなみに既に発行された債券のことを既発債、発行体が新規に発行する債券を新発債と呼ぶ。
債券投資の魅力は企業の業績などに関係なく決まった利息を受け取れて、満期まで持っていれば約束された金額が戻ってくるところだ。
そのため、業績によって値上がり益や配当が左右される株式投資よりも収支が読みやすく手堅い投資先という位置づけになっている。
また、万一、発行体が破綻したり倒産したりしても債券は株式より優先して弁済してもらえる可能性もある。
そのかわり、株式投資のように業績次第で青天井に配当や株価が上がって儲かるというものでもない。
株主優待権や議決権などの権利も債券投資では得られない。
債券投資のリスクとリターン
債券投資のリスクについてまずは説明する。
主なリスクは以下の通りだ。
| リスクの種類 | リスクの内容 |
|---|---|
| 価格変動リスク | 金利変動等により債券価格が変動する |
| 信用リスク | 発行体の経営悪化や倒産により、利払いや元本償還がされない |
| 流動性リスク | 換金したいときにできない売買が活発ではなく不利な価格で売却しないといけないなど |
| カントリー リスク | 発行体が国の場合、政治や経済などの情勢で債務不履行になるなど |
| 為替リスク | 外貨建ての場合、円建ての価値が左右されてしまう |
債券投資は株式投資に比べると、リスクが低いとされている。
ただし、上に挙げたようなリスクはある。
特に債券の価格変動リスクに関しては分かりづらいところかもしれないので少し詳しく解説しよう。
新規に発行された債券を買い満期まで保有していれば、約束された金額は戻ってくる。
しかし、途中で換金するとなると話は違ってくる。
新規債を満期まで持てば債券価格の動向は気にしすぎなくても良いが、無視するわけにもいかないだろう。
- 金利が上がる→債券価格は下がる
- 金利が下がる→債券価格は上がる
よく債券価格と金利は逆相関と言われている。
なぜ、このような現象が起きるのかを、同じ発行体、同じ償還期限の債券を例に考えてみよう。
例えばある会社が償還期限5年の社債を利子2%で発行していたとする。
しかし、国債の金利が上昇して、国より信用がない会社が、社債を買ってもらうために利子3%で新しく発行したケースで考えてみよう。
2%の利子がもらえる古い社債を持っている人が、後から3%の利子がもらえる債券が新しく発行されたら、どのような気持ちになるだろうか。
3%の利子がもらえる債券の方に魅力を感じることだろう。
となると2%の債券を売って3%の債券に乗り換えたくなるはずだ。
しかし同じ条件で2%の利子の債券を3%の債券と同じ価格で買ってくれる気前の良い投資家はいないので、値引きして売らなければ買ってもらえない。
つまり債券価格を下げて売ることになってしまう。
かなり単純化した説明だが、債券の価格が動く仕組みの一つだ。
他にも債券には償還までの残存期間や信用度の低下などの様々な要因で売買される価格は左右される。
また、債券には発行体が約束を守ってくれないリスクもある。
例えば2010年に大手航空会社が経営破綻で社債の債務不履行がニュースになった記憶がある方も多いのではないだろうか。
記憶に新しいところではスイスの大手金融機関の弁済順位が低いAT1債の債務不履行もあった。
このように借り手次第で約束が守られない信用リスクも債券投資にはあることにも注意してほしい。
リターンに関しては、債券を保有することで得られる利子収入と売却益の2つが考えられる。
債券は決まった利子を受け取れるインカムゲインがメインの投資先だ。
しかし、先に説明したように金利の動き次第で債権価格が動くため、値上がり途中で売却益を得る選択肢もある。
債券の取引方法
債券は証券会社や銀行などを通じて購入できる。
ただし、個人投資家が株式と同じような感覚で買えるという訳ではない点に注意したい。
- 株式投資
- 取引所取引(金融機関を通して市場にアクセスして注文する)
- 債券投資
- 店頭取引(金融機関を相手に売買する)
この違いが個人投資家にとっては大きな違いだ。
つまり株式投資の場合は証券会社や銀行は仲介役に過ぎないが、債券投資の場合は取引相手となるのだ。
株式投資ならば証券会社を通じて市場にアクセスして、自由に売買できる。
例えば東証に上場されている株式なら、A証券で買えるがB証券では買えないということはない。
しかし債券は、個人投資家が購入する場合、店頭取引が基本だ。
A証券が持っている社債をB証券では取り扱っていないなど、証券会社によって取り扱いに違いがある。
株式投資の世界では、どこの証券会社を使っても取引所に注文を取り次いでくれる。
そのため東証に上場している銘柄に関しては、どこの証券会社を選んでも買える種類に差はないといっても良いだろう。
一方、債券に関しては証券会社や銀行それぞれで取り扱っている種類も数も違う。
そのため債券投資をする場合は、債券の取扱いの豊富な金融機関に口座開設をする必要はあるだろう。
また、売買の勝手についても債券投資は株式投資ほどの自由度がない。
まず、債券価格は株価のようにリアルタイムでの取得が難しい。
同じように情報を取得しようとすると法人向けの端末が必要となるため、あまり現実的ではない。
税金に関しては、債券は株式と同じように考えて構わない。
- 利子
- 売却益
- 償還差益
3つに課税されるが、利子は株式投資の配当、売却益と償還差益は売却益に相当する。
所得税と住民税、復興特別所得税をあわせ20.315%の税率がかかる。
株式投資との損益通算は可能だ。
源泉徴収ありの特定口座を選べば株式同様に確定申告不要。
確定申告をすれば、株式投資と同様に損失の繰越控除もできるため、うまく活用したい。
自分に合った債券の選び方

債券を選ぶときは、自分の目的やリスクに対する考え方に合ったものを選ぶことが大切だ。
特に、次の3つの点に注目したい。
- 誰が発行しているか
- 新しく発行されたものか、すでに発行済みのものか
- 利息はどのように支払われるか
それぞれについて、詳しく説明する。
債券を発行している組織で選ぶ
債券を発行しているのは、主に次のような組織である。
- 国
- 都道府県や市町村などの地方自治体
- 民間の会社
一般的に、国が発行する国債は、お金が返ってこないリスクが低く、安全性が高いと考えられている。
一方、会社が発行する社債は、その会社の信用力によってリスクが変わる。
国債はリスクが低い分、利回りも低く、社債は株式よりはリスクが低いので、中くらいのリスクと利回りという位置づけになる。
ただし、国や会社によっても信用力に違いがある。
そのため、発行している組織の信用度は、格付け会社などで確認するとよいだろう。
債券が発行されたタイミングで選ぶ
債券は、次の2つに分けることもできる。
- 新しく発行される新発債
- すでに発行済みの既発債
新発債は、額面金額で発行される。
一方、既発債は市場で売買されるため、価格が変動する。
新発債は、発行時期が決まっていて、決められた価格で買えるため、将来の収支予測を立てやすいというメリットがある。
しかし、人気のある新発債は抽選になったり、買いたいときに応募していなかったりすることもある。
既発債は、証券会社の店頭で買うことになる。新発債に比べて選べる種類が多く、買いたいときに買えるのが魅力だ。
ただし、株式投資のようにリアルタイムの価格を見ながら注文したりはできない。
また、取引する証券会社によって、扱っている既発債の種類が異なるため、自分の条件に合う既発債を探すのに手間がかかる点には注意が必要だ。
また、既発債には経過利子という考え方がある。
これは、前回の利払い日から受け渡し日までに発生した利子のことで、新しい買い手が負担しなければいけない。
そして、債券の額面より高い価格で買ってしまった場合、満期まで持っていても売却損が出てしまう。
そのため、利子を含めたトータルの利回りがプラスになるかどうかも計算しておく必要がある。
債券の利息の支払われ方で選ぶ
債券は利付債と割引債(ゼロクーポン債)という利息の支払われ方で分けることもできる。
利付債は利子が支払われるのに対して、割引債は利子が支払われない代わりに額面金額よりも安く発行されるのが特徴だ。
利付債のメリットは、定期的な利子によるインカムゲインが見込める点だ。
一方、割引債は利子が発生しない代わりに、利子を再投資したと考えて複利効果が期待できる。
つまり定期的に収入を受け取りたいなら利付債。
利子を元本に組み込み再投資することで複利効果を得るなら割引債を選ぶと良い。
仮に表面利率10%の利付債100万円を購入したとする。
期間10年、利払い年1回を購入した場合、償還期間まで保有すると、利子の合計が100万円になる。
元本100万円と利子の合計を足すと200万円になる。つまり2倍になる。
一方、利回り10%の割引債(期間10年)を100万円分購入した場合、現在価値は100万円/(1+0.1)10=38.6万円となる。
38.6万円の割引債が発行された時に購入し償還時まで保有して100万円で受け取ると約2.59倍のリターンになる。
再投資の手間を省いて複利運用できる点は割引債のメリットだ。
選び方を習得したら!債券投資で実践するべき戦略

債券は株式に比べてリスクが低い資産クラスだ。
しかし、投資をする場合はリスク管理が欠かせない。
例えば新興国の利率の高い債券は一見、魅力的に感じるかもしれないが為替リスクだけで利子で補えないほどの損をしてしまったり、運が悪ければ債務不履行の憂き目にあったりするかもしれない。
債券だから安全とは考えずに適切なリスク管理をしていきたい。
- 購入前の発行体信用度の確認
- 満期保有と途中売却の使い分け
- 国内債券と外貨建て債券の併用
以上3つの観点からリスク管理法を解説する。
購入前に債券の発行体の信用度を確認する
債券を購入する際は発行体の信用度を確認しよう。
例えば、S&Pグローバルレーティング、JCR(日本格付け研究所)などで発行体の信用度を閲覧できるため参考にしてみると良いだろう。
レーティングがBB以下になるとリスクが高い債券となるため、注意が必要だ。
レーティングの低い債券はハイ・イールド債と呼ばれている。
ハイ・イールド債は高い利率が魅力だが、信用リスクの観点から分散して保有するなど工夫したい。
あらかじめ分散投資された債券の投資信託などを通して買うのも有効だろう。
満期保有と途中売却を使い分ける
債券投資は基本的に買ってから満期保有で安定的な利息を受け取るバイアンドホールドの戦略をおすすめする。
債券価格は下落しても利息を受けとりながら満期保有して約束された額が戻ってくるため、無理に途中売却をする必要はない。
また個人投資家の場合、債券の途中売却は店頭取引になるため、額面金額よりかなり安い買値を提示されてしまうことも考えられるため、株式のように活発に売買する投資先とは言い難い。
ただし、金利が下がり債券価格が上昇している局面では、途中売却でキャピタルゲインを狙う手もある。
また保有している債券の発行体が何らかの形で債務不履行をする可能性がある場合は途中売却で、損切りした方が良いこともある。
満期保有を基本としつつ、途中売却できる選択肢があることが債券の良さだ。
国内債券と外国債券を組み合わせる
株式投資と同様、債券も分散投資の効果は大きい。
例えば国内債券と外国債券を組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリスクを抑えられる。
国内債券と外国債券の値動きは異なるため価格変動リスクが下がる。
また、また通貨が分散されることで為替リスクを和らげることも可能だ。
また分散投資をすることで利率の高い新興国の債券も組み入れやすくなる。
株式投資を含めて債券をポートフォリオに上手く組みこむなら、債券ファンドやETFを活用するのもおすすめだ。
債券ファンドやETFの場合、債券のように償還期限がないからこそ使い勝手が良い側面もある。
NISAでも債券そのものは買えないが、成長投資枠なら債券に間接的に投資している投資信託やETFが買える。
国内外の債券を上手くポートフォリオに組みこむことは資産運用の戦略の幅を広げるだろう。
債券の選び方に迷ったら誰に相談するべき?

債券投資は株式投資と異なり店頭取引が基本で、証券会社によって扱っている種類や数に大きな違いがある。
また株式投資に比べると債券投資はリアルタイムで価格を確認できないなど勝手の違うところも多い。
しかし、債券は株式に比べて計画的な資産運用がしやすく魅力のある投資先だ。
債券に投資をするならプロに相談することをおすすめする。
株式投資以上に債券投資はプロの力を活かせる投資先かもしれない。
債券投資を専門家へ相談する重要性
株式に比べて債券は個人投資家が情報を得づらい資産クラスだ。
どこで、どのような債券が取り扱われているのか探すことすら難しいかもしれない。
債券投資の仕組みも少し分かりづらいところがあり、たしかな知識がなければ、リスクが低いと言われる債権でも投資対象にするのは不安があるだろう。
しかし、プロに相談すればどのような債券が投資対象に向いているのかを、リスク許容度に応じて個別具体的に提案してもらえる。
自分ひとりでは思いつかなかった債券も見つかるかもしれない。
IFAの役割とメリット
IFAは特定の金融機関に所属しない中立な立場で提案ができる資産運用の専門家だ。
特に債券投資では、この中立性に強みがある。
個人投資家が債券投資をする場合、店頭取引となるため証券会社や銀行が本当に投資家の利益になる債券を提案したり販売してくれたりするとは限らない。
金融機関の儲けにしやすい仕組み債などを提案してくるところもないとは言い切れない。
実際に金融庁が金融機関のEB債と言われる複雑な仕組み債の販売を問題視していたこともある。
店頭取引が基本の債券だからこそ、金融機関と雇用関係がないIFAの中立な立場からの提案の方が心強く安心できるのではないだろうか。
債券投資をする前に「資産運用ナビ」を活用しよう
債券のことを相談できるIFAを探すなら「資産運用ナビ」を使ってみてほしい。
簡単な質問と悩みに答えれば、あなたに合ったIFAのプロフィールが提案される。
登録されているIFAは証券会社をはじめとした金融機関出身のプロばかりだ。
気になるIFAがいたら無料で債券投資に関する相談をオンラインでできる。
もし、相性が合わなければ違うIFAにも無料で相談できる。
債券投資以外にも資産運用全般の総合的なサポートも任せられる。
債券投資に困ったら「資産運用ナビ」でアドバイザーを探してみてほしい。
債券の選び方を理解して、自分に合った商品を見つけよう

債券投資の基礎について解説した。
債券は株式と並ぶ伝統的な資産クラスだが、個人投資家には株式ほどには馴染みがないかもしれない。
株式投資に比べると債券そのものの仕組みが分かりづらい、店頭取引が中心で情報が得づらいなどの理由から興味があっても手を出せないという人もいるだろう。
しかし、証券会社や銀行などで債券投資の相談をしても、本当にあなたに合った債券を提案してもらえるかどうかは分からない。
中には金融機関に都合の良い複雑な仕組み債などを提案されてしまうこともあるかもしれない。
IFAは中立な立場で資産運用の提案ができる専門家だ。
債券のように株式よりも取引の自由度が低く情報も得づらい資産クラスこそ、プロのIFAからの中立なアドバイザーに相談することをおすすめする。
「資産運用ナビ」で債券投資のことを相談してみてほしい。
債券の選び方に関するQ&A