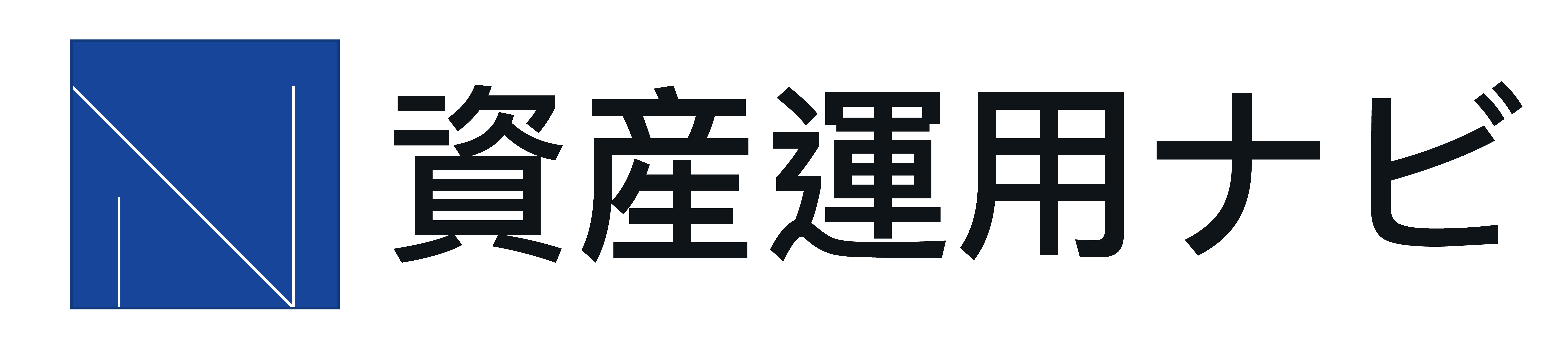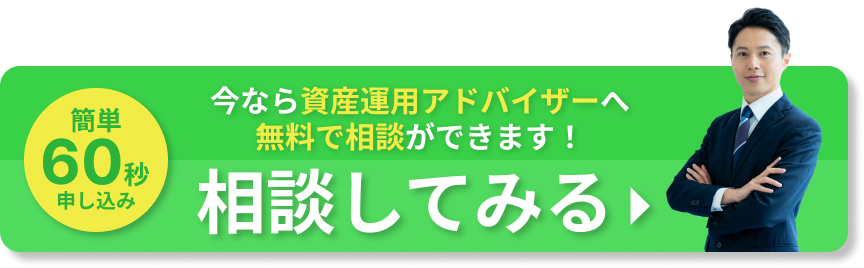※本ページはアフィリエイトリンク(広告)を含みます
- インデックスファンドのおすすめ銘柄が知りたい
- インデックスファンドを始めるならどの証券会社が良いのか知りたい
- どのようにインデックスファンドを選べば良いのか知りたい
インデックスファンドは、低コストで分散投資を行えることから高い人気を集める投資商品だ。
しかし銘柄数が非常に多いため、自分に合った銘柄を探すことは容易ではない。
商品選びのポイントを理解し、最適なインデックスファンドを選択しよう。
本記事では、インデックスファンドを選ぶ際のポイントやおすすめのインデックスファンド、インデックス投資におすすめの運用戦略を解説していく。
インデックス投資におすすめの証券会社や運用相談先も解説するので、ぜひ本記事を参考にベストな投資先を探してほしい。
インデックスファンドはどう選ぶ?

インデックスファンドを選ぶポイントとして以下の5点を押さえておこう。
- 資産クラス
- 投資対象の地域
- 対象指数
- 運用コスト
- 純資産総額
それぞれのポイントを解説していくので、ぜひ参考にしてほしい。
資産クラス
まず、インデックスファンドが投資対象としている資産クラスをチェックしよう。
資産クラスとは投資対象となる資産の種類・分類のことを指しており、株式や債券、不動産、金などが代表的な資産クラスである。
資産クラスによって値動きの特徴やリスクの大きさが異なるため、自分に合ったものを選ぶことが大切だ。
例えば株式は比較的値動きが大きい資産であるため、リスク許容度が高い人におすすめの投資先である。
一方、債券は比較的値動きが落ち着いており、堅実に運用したい人におすすめの投資先だ。
また、不動産や金などの資産クラスは株式・債券とは違った値動きの特徴があるため、分散投資先に向いている。
すでに株式・債券で運用している場合、リスク分散効果を高める目的で不動産や金を対象としたインデックスファンドを選んでも良いだろう。
自分自身のリスク許容度や資産状況に合わせ、適切な資産クラスを選択しよう。
投資対象の地域
投資対象の地域についてもチェックしておきたい。
特定の国・地域に限定されているのか、あるいは複数の国・地域に分散されているのかという点をよく確認しておこう。
例えば、日経平均株価をベンチマークとするインデックスファンドの場合、投資対象地域は日本のみとなる。
そのファンドは日本のリスク要因に影響を受けやすく、何らかの事情で日本が経済的に落ち込むとファンドの価格も大きく下落する可能性が高い。
一方、世界中の株式市場の動きをベンチマークとするインデックスファンドであれば、投資対象地域は世界中に分散されている。
特定の国・地域のリスク要因に左右されにくく、安定した値動きとなるケースが多い。
また、一般的な傾向として先進国を対象とするファンドより、新興国を対象とするファンドの方がリスクは高くなる。
新興国は大きな経済成長が見込まれる一方、政治的・経済的リスクが先進国よりも高い。
新興国を対象とするファンドは値動きが激しくなりやすいことを頭に入れておこう。
対象指数
インデックスファンドは、株式や債券などの市場指数との連動を目指して運用を行う商品だ。どういった指数をベンチマークとしているのかも事前にチェックしておこう。
代表的な指数には以下のようなものが挙げられる。
| 指数 | 内容 |
|---|---|
| 日経平均株価 | 東証プライム市場に上場する銘柄のうち、代表的な225銘柄で構成 |
| TOPIX(東証株価指数) | 東証プライム市場上場銘柄や旧第一部に上場していたスタンダード市場上場銘柄で構成 |
| ダウ平均株価 | 米国のさまざまな業種の代表的な30銘柄で構成 |
| S&P500 | 米国の代表的な500銘柄で構成 |
| ナスダック総合指数 | 米国のNASDAQ市場に上場するすべての銘柄で構成 |
選ぶ指数によって構成銘柄数が異なるため、リスク分散の度合いも変化する。
また、対象とする市場によって値動きの特徴も変化するため、自身の投資目的やリスク許容度に合わせて対象指数を選択しよう。
運用コスト
インデックスファンドなどの投資信託は、基本的には長期間にわたって運用を続けることが前提となる。
運用期間が長くなるほどコストの差が広がっていくため、できるだけ運用コストが低い商品を選ぶことが大切だ。
投資信託におけるコストは主に以下の3つである。
- 購入時手数料
- 信託報酬
- 信託財産留保額
購入時手数料や信託財産留保額が無料のファンドは増えてきているが、信託報酬は保有期間中に信託財産から引かれ続ける。
商品を選ぶ際は信託報酬の料率に注目し、低コストなファンドを選択しよう。
インデックスファンドは比較的手数料が安い傾向にあるが、似たような仕組みの商品でも信託報酬に差が生じているケースはある。
各商品の信託報酬をしっかりと比較し、低コストで運用を行える商品を選ぶことが大切だ。
純資産総額
商品を選ぶ際、ファンドの純資産総額も確認しておこう。純資産総額は運用している資産の時価総額であり、ファンドの規模を表すものとして用いられる。
ファンドの純資産総額が少ない場合、運営ができなくなって繰上償還されるリスクが出てくる。
繰上償還とは、設定された信託期間が終了するよりも前にファンドの運用が終了してしまうことを指す。
純資産総額の目安として「100億円」を超えている場合、繰上償還のリスクは低いと言える。
事前にホームページ等でファンドの純資産総額をチェックしておき、極端に純資産総額が少ないファンドは避けた方が良いだろう。
なお、インデックスファンドは「ファミリーファンド」と呼ばれる仕組みで運用される商品が多い。
投資家が「ベビーファンド」に投資を行い、そのベビーファンドは「マザーファンド」に投資を行うという仕組みだ。
ファミリーファンド方式で運用されている場合、ベビーファンドの純資産総額が少なくてもマザーファンドの純資産が十分にあれば繰上償還のリスクは低い。
ファンドの運用方式も確認しておこう。
インデックス投資におすすめの証券会社

次に、インデックスファンドへの投資でおすすめの証券会社を紹介していく。
インデックス投資を始めるのであれば、以下の2つの証券会社に口座開設をすると良い。
- SBI証券
- 楽天証券
それぞれの証券会社について特徴やおすすめの理由を紹介していく。ぜひ参考にし、自分に合った証券会社でインデックス投資を始めよう。
SBI証券
SBI証券は、個人投資家から高い支持を集める大手のネット証券会社だ。
SBIグループの証券口座開設数は1,300万口座(2024年7月16日時点)を超えており、2025年オリコン顧客満足度調査ではネット証券第1位に選ばれている。
SBI証券の強みとして主に以下の3点が挙げられる。
- 商品ラインナップが多い
- 投資信託の購入時手数料がすべて無料
- 好きなポイントを貯められる
SBI証券では2,500本以上の投資信託を取り扱っており、インデックスファンドも521本(2025年1月時点)を取り揃えている。
豊富な商品ラインナップから自分に合った投資先をじっくり探せることが特徴だ。
また、取り扱っているすべての投資信託の購入時手数料が無料となっている。コストの負担を抑えてインデックス投資を行える点もSBI証券の強みだ。
そして、SBI証券では国内株式や投資信託などの取引でポイントが貯まる仕組みとなっている。
VポイントやPontaポイント、dポイントなど、さまざまなポイントから好きなものを選んで貯められる点も大きなメリットだ。
「さまざまな選択肢から投資先を選びたい」「取引でポイントを貯めたい」という方は、SBI証券の口座開設をおすすめする。
\ 累計口座数1,000万突破!手数料無料で取引するなら /
楽天証券
楽天証券は、SBI証券と並び立つ大手ネット証券である。
総合口座数は1,100万口座(2024年4月時点)を超えており、口座開設時のアンケート調査(2024年1月〜6月実施)では投資未経験者の割合が83.4%だった。
投資初心者から高い人気を集めているのが楽天証券の特徴だ。
楽天証券の強みとして主に以下の3点が挙げられる。
- 楽天ポイントを貯めやすい
- NISAの手数料が無料
- 投資情報コンテンツの充実度が高い
楽天証券では、楽天カード・楽天キャッシュを利用した投信積立で最大1.5%の楽天ポイントが貯まる。
さらに一部の投資信託は、保有残高に応じてポイントが付与されるプログラムが提供されており、効率的に楽天ポイントを貯められる。
普段から楽天ポイントを貯めている楽天ユーザーにとっては嬉しい特典だ。
また、楽天証券のNISAでは国内株式・米国株式・海外ETF・投資信託の購入手数料が無料となっている。
さらに日本円と米ドルの為替手数料も無料となっており、コストを抑えて取引できる点が大きな魅力だ。
さらに、楽天証券の総合口座を開設していれば、おすすめのマネー本・マネー雑誌を無料で読める。
日経テレコン(楽天証券版)の利用も無料となっており、充実した投資情報コンテンツを利用できる点も楽天証券の強みである。
「普段から楽天ポイントを貯めている」「投資についてしっかりと学習したい」という方は、楽天証券の利用がおすすめだ。
おすすめのインデックスファンド10選

次に、インデックスファンドのおすすめ銘柄を紹介していく。
SBI証券と楽天証券で取り扱っているファンドをそれぞれ紹介するので、ぜひ参考に自分に合った銘柄を選択しよう。
SBI証券でおすすめのインデックスファンド5選
SBI証券で投資家から人気を集めているインデックスファンドは以下の通りだ。
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
- 〈購入・換金手数料なし〉ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
- SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
- eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
各ファンドの特徴について解説していく。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は、日本を含む先進国および新興国の株式に投資するインデックスファンドだ。
「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」と連動する投資成果を目指して運用される。
信託報酬は0.05775%と非常に低い水準となっており、コストを抑えて運用できる点が魅力のファンドだ。
投資対象も世界中に分散されているため、安定した値動きになりやすい。
「低コストで全世界の株式に分散投資をしたい」という方には本ファンドがおすすめだ。
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
SBI・V・S&P500インデックス・ファンドは、米国の代表的な株価指数「S&P500」と連動する投資成果を目指して運用されるインデックスファンドだ。
「バンガード・S&P500」を実質的な主要対象として運用されている。
信託報酬は0.0938%となっており、運用コストを抑えられる。
世界をリードする経済大国である米国の大企業に分散投資できるため、高いリターンを期待できる点も大きな魅力だ。
「低コストで米国企業に分散投資したい」という方に本ファンドの活用をおすすめする。
〈購入・換金手数料なし〉ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
〈購入・換金手数料なし〉ニッセイNASDAQ100インデックスファンドは、米国の株価指数「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」と連動する投資成果を目指して運用されるインデックスファンドだ。
NASDAQ100指数は、NASDAQ市場のなかから金融銘柄を除いた時価総額上位100銘柄で構成される株価指数である。
NASDAQ市場には人々の生活を変えるようなテクノロジー企業が多く上場しており、成長性が期待される市場だ。
信託報酬は0.2035%となっており、低コストで成長性が高い企業に投資を行える点が魅力となっている。
「成長性があるテクノロジー企業に投資したい」という方は本ファンドがおすすめだ。
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
SBI・V・全米株式インデックス・ファンドは、米国の株式市場の動きを捉えることを目指す「CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)」と連動する投資成果を目指して運用されるインデックスファンドだ。
米国株式市場のほぼ100%の銘柄をカバーしている。
中小型の銘柄までカバーしているため、今後大きく成長する可能性を秘めた銘柄にも投資を行えることが特徴だ。
信託報酬は0.0938%と低水準になっており、長期投資にも向いている。
「米国株式市場全体に投資をしたい」という方には本ファンドを推奨する。
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)は、日本を除く先進国および新興国の株式に投資を行うインデックスファンドだ。
先ほど紹介したオール・カントリーから日本を除外して運用されている。
すでに日本株で運用している場合のリスク分散先として効果的なファンドだ。
信託報酬は0.05775%と非常に低い水準であり、コストを抑えて投資先を分散できる点が魅力である。
「日本以外の国・地域に投資をしたい」という方は本ファンドがおすすめだ。
楽天証券でおすすめのインデックスファンド5選
楽天証券で投資家から人気を集めているインデックスファンドは以下の通りだ。
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド
- iFree NEXT FANG+インデックス
- 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
各ファンドの特徴について解説していく。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)は、米国の代表的な株価指数「S&P500(配当込み、円換算ベース)」と連動する投資成果を目指して運用されるインデックスファンドだ。
先ほど紹介した「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」と並んで個人投資家から人気を集めている。
信託報酬は0.09372%となっており、低コストで米国の大企業に投資できる点が魅力のファンドだ。
長期投資によるコストを抑えられ、中長期的に高いリターンを期待できる点が人気を集めている理由である。
「米国経済の成長に期待している」という方は本ファンドへの投資がおすすめだ。
楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド
楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンドも「S&P500(円換算ベース)」と連動する投資成果を目指して運用されるインデックスファンドだ。
信託報酬0.077%と低コストで運用できる点が魅力の商品である。
本ファンドは楽天証券において「投信残高ポイントプログラム」の対象となっており、保有残高に応じてポイントが付与される。
残高が増えるほど多くのポイントを得られるため、楽天ポイントを貯めたい人におすすめだ。
「米国株に投資しながらポイントを貯めたい」という人は、楽天証券で本ファンドに投資を行うと良いだろう。
iFree NEXT FANG+インデックス
iFree NEXT FANG+インデックスは「NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)」との連動を目指して運用されるインデックスファンドだ。
NYSE FANG+指数は、人々の生活に大きな影響力を持つ米国テクノロジー企業で構成される株価指数である。
AppleやMicrosoft、Amazonなど、グローバルに事業を展開するテクノロジー企業を中心に構成されており、今後の成長性も期待されるファンドだ。
信託報酬は0.7755%と本記事で紹介したファンドのなかでは高めだが、大きなリターンも見込まれる。
「成長性が高いテクノロジー企業に投資をしたい」という人は本ファンドがおすすめだ。
楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド
楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンドは、日本を含む全世界の株式市場の動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンドだ。
信託報酬は0.0561%と極めて低い水準となっており、低コストで全世界に分散投資を行える点が魅力の商品である。
本ファンドも楽天証券の「投信残高ポイントプログラム」の対象であり、保有残高に応じてポイントが付与される。
低コストで長期的な資産形成をしつつ、資産残高が増えていくことで効率的にポイントを貯めていける点がメリットだ。
「全世界に分散投資をしながらポイントを貯めていきたい」という人は、楽天証券で本ファンドに投資を行うことを検討してみよう。
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは、先進国の株式市場と連動する投資成果を目指すインデックスファンドだ。
日本を除く先進国の約1,300銘柄に分散して投資できることが特徴となっている。
信託報酬は0.09889%と低い水準で提供されており、投資コストをしっかりと抑えられる。
米国株を中心とした先進国の経済成長の恩恵を受けられ、安定的なリターンを期待できることが魅力のファンドだ。
「先進国に低コストで分散投資をしたい」という人には本ファンドへの投資を推奨する。
インデックス投資におすすめの運用戦略

インデックス投資は比較的リスクが小さい投資先だが、投資である以上は価格が変動するリスクが伴う。
市場全体が下落するとファンドの基準価額も下落し、元本割れを起こす可能性がある。
インデックス投資におけるリスクを軽減し、効果的にリターンを得るためのポイントとして以下の3点を押さえておこう。
- 長期・積立投資
- 新NISAの活用
- 専門家への相談
それぞれのポイントを理解し、最適な運用戦略でインデックス投資を始めよう。
長期・積立投資
インデックス投資を行う際は、長期・積立投資による運用戦略の構築をおすすめする。
いずれも運用におけるリスクを軽減し、効率良くリターンを得るために重要なポイントだ。
「長期投資」を行うことで、短期的な価格変動の影響を受けにくくなる。
価格変動リスクが軽減され、安定したリターンを得られる可能性が高まるため、運用期間はなるべく長く設定しよう。
また、定期的に一定額を買い続ける「積立投資」を実践することで、購入するタイミングを分散できる。
価格変動による高値掴みのリスクが軽減され、平均取得単価を抑え込める。積立投資と長期投資を組み合わせることで、価格変動のリスクを大きく軽減することが可能だ。
長期的に積立投資を続けていくと、得られるリターンと追加投資額によって元本が膨らんでいき、効率的にリターンを得られるようになる。
リスクを回避しつつ投資効率を高められるため、インデックス投資をする際には長期・積立投資を心掛けよう。
新NISAの活用
新NISAを上手く活用することも重要なポイントだ。新NISAとは、年間一定額までの非課税投資枠が与えられる制度のことである。
本来、株式や投資信託で得られる売却益・配当金には20.315%の税金が課されるため、仮に100万円の利益が出ても約20万円は税金で引かれてしまう。
しかしNISA口座内では一切利益に課税されず、100万円の利益をそのまま受け取ることが可能だ。
非課税投資枠は「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類があり、つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円まで投資できる。
合計で年間360万円、生涯で1,800万円の非課税投資枠が与えられており、税制面での優遇を受けながら投資を行えることが特徴だ。
いずれの投資枠でもインデックスファンドを購入できるため、新NISAの非課税投資枠を上手く活用して効率的に資産形成を行おう。
専門家への相談
インデックス投資を成功させるポイントとして、投資助言を行う専門家への相談も検討してみると良いだろう。
自分に合った投資戦略の構築や最適な投資先商品の提案など、豊富な知識を持つ専門家にサポートしてもらうことをおすすめする。
近年は高校などで金融教育がスタートしているが、以前は学校で投資や資産運用について学習する機会はなかった。
そのため、多くの人が金融リテラシーを身に付ける機会がなく、投資に対して漠然とした不安を抱えている。
そうした不安を軽減するためには、豊富な知識を有するアドバイザーに助言してもらうほかない。
投資・資産運用について相談できる専門家に依頼し、最適なインデックス投資の戦略をアドバイスしてもらうのもひとつの手だ。
インデックスファンドに投資するなら「資産運用ナビ」で専門家に相談しよう

インデックスファンドへの投資で悩んでいる方は、資産運用アドバイザーとマッチングできるサービス「資産運用ナビ」の利用がおすすめだ。
自分に合った信頼できるアドバイザーを探し、インデックス投資の悩みを相談してみると良いだろう。
ここでは、インデックスファンドへの投資で難しいポイントや専門家に相談すべき理由を解説していく。
「資産運用ナビ」の特徴や利用方法も紹介するので、ぜひ本記事を参考にしてほしい。
インデックスファンド投資の難しいポイント
インデックスファンドへの投資で難しいポイントとして、以下のような点が挙げられる。
- 最適な商品を見極めることが難しい
- 適正な投資額が分からない
- どのタイミングで売却すべきか分からない
「インデックスファンド」と一口に言っても、非常に多くの商品が各運用会社から提供されている。
数ある商品のなかから自分に合ったものを選ぶことは容易ではなく、最適な商品を探し出すことにハードルを感じるケースは多い。
また、自分にとって適正な投資額を把握できずに迷うケースも多くある。
投資額は本人の資産状況や収入、運用目標、リスク許容度によって異なるため、自分に合った投資額を導き出すことは容易ではない。
そして、投資において意外にも難しいのが「いつ売却すべきか」という点だ。
「もっと上がるかもしれない」と考えて売却の時期を迷ったり、「資産を売却するのがもったいない」と感じて売却を決断できなかったりするケースは多い。
上記のような点から自分ひとりでインデックス投資を行うことが難しいと感じている人は少なからずいる。
専門家に相談すべき理由
インデックス投資を専門家に相談すべき理由として「最適な投資戦略を提案してもらえる」という点が挙げられる。
自分の状況にマッチした投資戦略を助言してくれるため、効率的に資産運用を始められることが利点だ。
近年はインターネットやSNS等で投資情報にアクセスできるようになった。
しかしインターネット等の投資情報は「一般向けにおすすめの情報」であり、個々の状況を考慮したものではない。
得られる情報が自分にとって合っているとは限らない。
投資助言を行う専門家は、あなたの資産状況や運用目的、リスク許容度をヒアリングした上で投資戦略を構築する。
あなたの状況に合わせてカスタマイズされた投資戦略を提案してもらえるため、安心して資産運用を始めることが可能だ。
自分にぴったりの投資戦略で効率良く資産運用を行うためにも、専門家への相談を検討しよう。
「資産運用ナビ」を活用しよう
信頼できる専門家を探したい方は、資産運用アドバイザーを検索できるサービス「資産運用ナビ」がおすすめだ。
あなたに合った資産運用の専門家を自動で診断し、マッチングさせるオンラインプラットフォームである。
「資産運用ナビ」を利用する方法は以下の通りだ。
- 専用フォームに希望条件を入力する
- 希望条件に合ったアドバイザーが自動で診断され、相談先を選ぶ
- 初回面談の日程を調整する
「資産運用ナビ」ではアドバイザーのプロフィールが公開されており、事前に経歴や得意分野、保有資格を把握した上で申し込める。
自分と相性の良いアドバイザーを見極めた上で相談できる点が魅力だ。
アドバイザーの紹介は全国47都道府県どこでも対応しており、オンラインでの面談にも対応している。
アドバイザーの紹介料・相談費用は無料となっており、気軽に専門家とマッチングできることが特徴だ。
ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を活用し、自分に合ったアドバイザーを探してみよう。
ランキングを参考に最適なインデックスファンドを選択しよう

本記事では、インデックスファンドを選ぶ際のポイントやおすすめの商品を紹介してきた。
投資対象の資産クラスや地域、運用コストなどを基準として、自分に合った商品を見つけることが大切だ。
また、本記事ではインデックス投資におすすめの証券会社も紹介した。
ぜひこの機会にSBI証券・楽天証券で口座を開設し、インデックス投資を始めてみよう。
ただし、インデックス投資は商品選びや適正な投資額の見極めが難しく、売却する時期を検討することも容易ではない。
専門家に相談し、自分に合った投資助言をもらうことを検討してみると良いだろう。
「資産運用ナビ」では、あなたにぴったりの資産運用アドバイザーを無料で紹介するサービスを提供している。
ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を活用し、信頼できる相談先のアドバイザーを探してみてはいかがだろうか。
おすすめのインデックス投資に関するQ&A