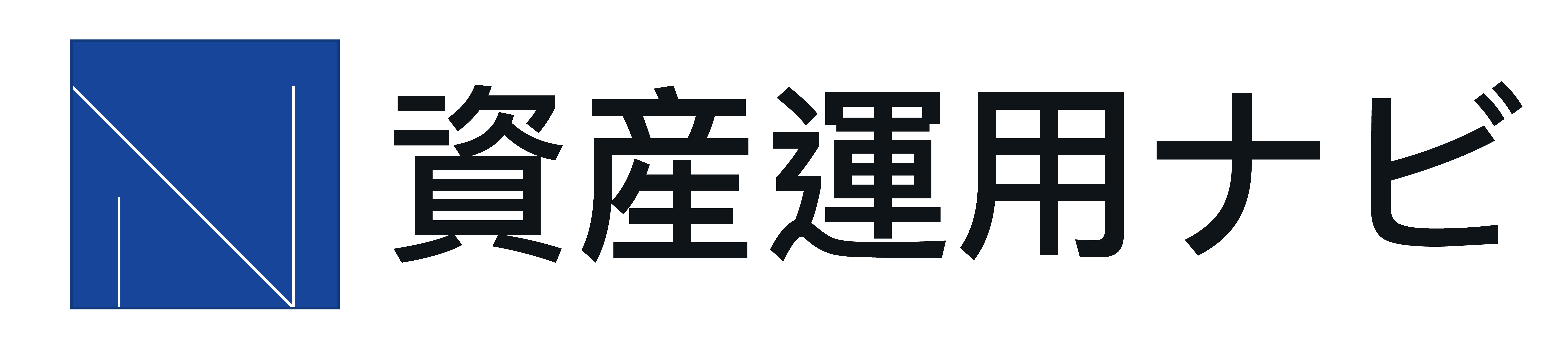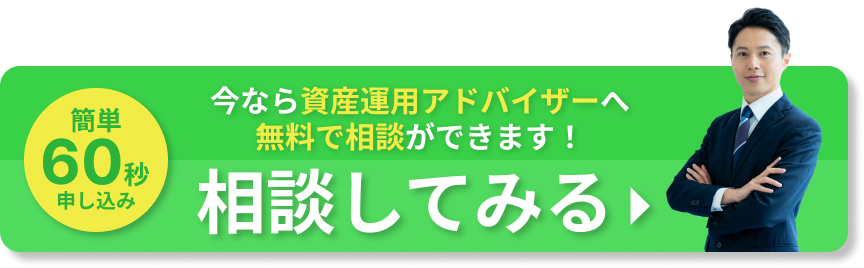※本ページはアフィリエイトリンク(広告)を含みます
- 1,000万円を投資信託で運用したらいくら増えるのか知りたい
- 1,000万円を投資するのにおすすめの投資信託が知りたい
- 投資信託で利益を出すためのコツが知りたい
1,000万円の資金を投資信託で大きく育てるなら、その運用には慎重さと知識が必須だ。
しかし適切に運用すれば、大きなリターンが期待できる。
そこで本記事では、1,000万円を投資信託で運用する際の重要なポイントと、成功への道筋をご紹介する。
具体的におすすめな銘柄も紹介するので、これから投資信託に挑戦する人は、参考にしていただきたい。
投資信託に1,000万円投資した時のリターンは種類によって変わる

投資信託に1,000万円投資した場合のリターンとリスクは、投資対象の資産や地域、また運用方法など様々な要素によって変動する。
ここでは、主な分類方法と、それぞれのリスク・リターン特性について説明する。
投資信託は投資対象の資産や地域・運用方法(方針)などによってさまざまな種類がある
投資信託は主に、次のような種類に分類できる。
| 分類基準 | 種類 | 主な投資先 |
|---|---|---|
| 投資対象資産 | 株式投資信託 | 主に株式 |
| 債券投資信託 | 主に債券 | |
| 不動産投資信託(REIT) | 不動産 | |
| 投資対象地域 | 国内型 | 日本国内の資産 |
| 海外型 | 海外の資産 | |
| 内外型 | 国内外の資産 | |
| 運用方法 | アクティブ型 | 運用者が銘柄選択 |
| インデックス型 | 指数に連動 |
それぞれについて説明する。
投資対象資産による3つの分類
投資信託は、投資対象資産によって、次の3つに分類できる。
- 株式投資信託
- 債券投資信託
- 不動産投資信託(REIT)
一つ目の株式投資信託は主に株式に投資する。主に株価の値上がり益と配当金が、株式投資信託の収入源だ。
二つ目の債券投資信託は主に債券に投資をし、利子収入と債券価格の変動による収益を目指すのが特徴だ。
三つ目の不動産投資信託(REIT)は、投資家から集めた資金で不動産に投資する金融商品だ。
REITは取引所に上場しており、株式と同様にリアルタイムでの売買が可能である。
投資家は数万~数十万円程度の少額から投資でき、多様な物件・地域に投資できるため、リスクが分散しやすい。
また不動産の賃貸料を原資とするため、比較的安定した配当が期待できる。
さらに、日本の不動産投資信託であるJ-REITの場合、利益の90%超を配当することで実質的に法人税が免除されるため、多くの利益を投資家に還元できる。
加えて流動性が高く容易に換金できるのもメリットだ。
投資対象地域による3つの分類
投資対象地域による3つの分類は以下の通りだ。
国内型とは、日本国内の資産に投資する投資信託だ。国内経済の成長や企業業績の向上による利益が期待できる。
為替変動リスクがないため、為替の影響を受けずに国内市場の動向に連動したリターンが得られる可能性がある。
また、投資家にとって身近な企業や経済情報を活用しやすいという利点がある。海外型とは、海外の資産に投資する投資信託だ。
グローバルな経済成長や新興国市場の発展による利益が期待できるのに加えて、為替変動による為替差益の可能性もある。
国内市場とは異なる動きをする海外市場に投資することで、分散投資としても活用可能だ。
特に、日本にはない産業や成長セクターへの投資機会を得られる点が魅力である。
内外型とは、国内と海外の両方の資産に投資する投資信託だ。国内外の市場動向を組み合わせたバランスの取れたリターンが期待できる。
地域分散により、リスクを軽減しつつ、様々な市場の成長機会を捉えられる可能性があるのが特徴だ。
一つの投資信託で国際分散投資を実現できるため、効率的なポートフォリオ構築が可能という特徴がある。
運用方法による分類
運用方法による投資信託の分類には、主にアクティブ型とインデックス型の2つがある。
アクティブ型投資信託は、市場平均を上回る運用成果を目指して運用される。
専門家が独自の調査や分析に基づいて銘柄を選定し、積極的に運用するのが、アクティブ型投資信託の特徴だ。
アクティブ型投資信託では、運用者の判断や能力が重要な役割を果たす。アクティブ型の特徴は、以下のとおりだ。
- 市場平均を上回るリターンの可能性がある
- 運用コストが比較的高い
- 運用者のスキルに依存する
- 市場の変化に柔軟に対応できる
一方のインデックス型投資信託は、特定の指数(インデックス)に連動する運用成果を目指す。
例えば、日経平均株価やTOPIXなどの指数と同じ値動きをするように設計されているのが、インデックス型投資信託の特徴だ。
インデックス型の主な特徴には、次のようなものがある。
- 市場平均と同等のリターンを目指す
- 運用コストが低い
- 運用者の判断に依存しない
- 透明性が高く、運用方針が明確
インデックス型は、指数を構成する銘柄をほぼ同じ比率で保有するため、運用の手間が少なく、結果として運用コストを抑えやすい。
アクティブ型投資信託とインデックス型のいずれを選択するかは、投資家の運用目標やリスク許容度によって異なる。
ただ長期的な視点では、コストの低さからインデックス型が支持される傾向だ。
ただし、優れたアクティブ型ファンドが市場平均を上回るリターンを提供する可能性もあるため、一概にどちらが優れているとはいえない。
種類によってリスク・リターンも異なる
投資信託の種類によって、リスクとリターンは異なる。概要をまとめると、下の表の通りだ。
| 分類基準 | 種類 | リターン | リスク |
|---|---|---|---|
| 投資対象資産 | 株式投資信託 | 大 | 高 |
| 債券投資信託 | 中程度 | 中程度 | |
| 不動産投資信託 (REIT) | 中~大 | 中~高 | |
| 投資対象地域 | 国内型 | 小~中 | 低~中 |
| 海外型 | 中~大 | 中~高 | |
| 内外型 | 中程度 | 中程度 | |
| 運用方法 | アクティブ型 | 大 | 高 |
| インデックス型 | 中程度 | 中程度 |
投資信託は、お金の運用方法によって、リスク(損をする可能性)とリターン(儲かる可能性)が変動する。
まず、投資対象資産による違いを見ていこう。株式投資信託とは、会社の株を買うことだ。
したがって、会社の業績によってリターンとリスクは大きく変動する。儲かる可能性は大きい反面、損する可能性も高い。
債券投資信託では、国や企業が発行する債券に投資するので、株式よりは安定している。しかしその分、儲けも控えめだ。
不動産投資信託(REIT)は、建物や土地に投資するので、不動産市況によって変動する。
ただ不動産投資信託(REIT)では家賃収入などがあるため、中程度の安定性が期待できる。
次に、投資対象地域による違いをみていこう。
国内型は日本国内だけに投資するので、比較的安定している。その分、大きな儲けは期待しにくいのが弱点だ。
海外型は外国に投資するので、為替の変動があり、リスクは高めだが、儲かる可能性が大きい。
内外型は国内と海外の両方に投資するので、リスクとリターンは中程度である。
最後に、運用方法による違いを確認する。アクティブ型は、運用のプロが積極的に投資先を選ぶので、うまくいけば大きな儲けが期待できる。
しかし失敗すると大きな損失になる可能性がある点は否めない。
インデックス型は市場全体の動きに合わせて投資するので、極端な損失や利益は出にくく、中程度の安定性がある。
投資を始める際は、自分がどれくらいのリスクを取れるか、どれくらいの儲けを期待するかをじっくり検討し、自分に合った投資信託を選ぶことが大切だ。
種類別に見る投資信託を1,000万円運用した時のシミュレーション
投資信託の種類別に、元本1,000万円を設定し、運用期間5年、10年、20年の3期間での見通しをシミュレーションしたものが、下の表だ。
なお以下表では、複利計算を用いて運用成果を計算している。また、それぞれの資産のリスクとリターンの特性を加味して、異なる想定利回りを設定した。
投資対象資産別
| 種類 | 想定年利回り | 5年後 | 10年後 | 20年後 |
|---|---|---|---|---|
| 株式投資信託 | 6% | 13,382,256円 | 17,908,477円 | 32,071,355円 |
| 債券投資信託 | 3% | 11,592,741円 | 13,439,164円 | 18,061,112円 |
| 不動産投資信託(REIT) | 5% | 12,762,816円 | 16,288,946円 | 26,532,977円 |
投資資産ごとの特徴で見ていくと、株式投資信託は長期的な成長が見込める反面、価格変動のリスクが高く、短期で大きな損失を被る可能性がある点は留意したい。
債券投資信託は安定性が高くリスクが低いため、堅実な資産運用に向いている。
ただ、ローリスクローリターンであるため、長期運用しても大きな運用成果は期待しにくい。
投資対象地域
| 種類 | 想定利回り | 5年後 | 10年後 | 20年後 |
|---|---|---|---|---|
| 国内型 | 4% | 12,166,529円 | 14,802,443円 | 21,911,231円 |
| 海外型 | 6% | 13,382,256円 | 17,908,477円 | 32,071,355円 |
| 内外型 | 5% | 12,762,816円 | 16,288,946円 | 26,532,977円 |
国内型の場合為替リスクがない分、安定した運用が可能だ。ただしリターンが控えめな点と、日本経済の成長に大きく依存する点に注意しよう。
海外型は、高い成長が期待できるのが特徴だ。しかし為替リスクや地政学リスクを十分に考慮しなければならない。
内外型を選択し国内外に資産を分散して投資することで、国内外に資産を分散して投資することでリスクとリターンのバランスが取れた運用をしやすくなるのでおすすめだ。
運用方法別
| 種類 | 想定利回り | 5年後 | 10年後 | 20年後 |
|---|---|---|---|---|
| アクティブ型 | 7% | 14,025,517円 | 19,671,514円 | 38,696,845円 |
| インデックス型 | 5% | 12,762,816円 | 16,288,946円 | 26,532,977円 |
アクティブ型は、市場を上回るリターンを目指すため高い成果が期待できる。
しかし運用コストやリスクが高いため、その成果は運用する専門家の腕に委ねられている。
一方のインデックス型は、コストが低く安定しており長期的に市場平均のリターンを得られる。
堅実に投資したい人におすすめできるスタイルだ。
全体的な傾向としては、運用期間が長いほど複利効果による運用成果が大きくなることがわかる。
また想定利回りが高い株式投資信託やアクティブ型では、長期的に資産が大きく成長する一方で、リスクが高いのが懸念点だ。
【投資目的別】1,000万円から始めるのにおすすめの投資信託

1,000万円から始めるのにおすすめの投資信託について、投資目的別に具体的な銘柄を紹介する。
1.安全第一で資産を守りながら運用したい(リスク許容度:低)
手堅く資産運用するなら、国内型の債券投資信託がおすすめだ。
例えばeMAXISSlim国内債券インデックスなら、国内債券市場全体に分散投資し、価格変動リスクを抑えながら安定した収益が期待できる。
また、国内債券インデックスの信託報酬率は0.139%以内(年率・税抜)と低いので、長期的な運用でコストを最小限に抑えられる点が魅力だ。
- 出典:MUFG「eMAXISSlim」・「eMAXISSlim国内債券インデックス」・MINKABU「投資信託人気ランキング」
2.長期でコツコツ資産形成を目指したい(リスク許容度:中)
長期でコツコツ資産運用するなら、内外型のインデックス型がおすすめだ。
例えば楽天・全世界株式インデックス・ファンドは、世界中の株式市場に広く分散投資し、地域や国ごとのリスクを軽減しながら成長の恩恵を受けられるファンドである。
毎月積立に対応しているため、ドルコスト平均法を活用した資産形成に最適だ。
なおドルコスト平均法とは、価格が変動する金融商品を一定金額で定期的に購入し続ける投資手法だ。
一定金額を定期的に投資するため、価格が高いときは少ない数量を、安いときは多い数量を購入する。
これにより、平均購入単価を抑える効果が期待できる。
- 出典:楽天証券「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」
3.定期的な収入を得たい(インカムゲイン重視)
定期的な収入を期待するなら、不動産投資信託(REIT)がおすすめだ。
iシェアーズ・コア日本リートETF(1476)は、国内の不動産投資信託(REIT)に分散投資し、安定的な賃料収入を配当として受け取れるETFである。
流動性が高いので、価格変動の影響を抑えながら定期的な収益を得られるのが魅力だ。
- 出典:ブラックロック「iシェアーズ・コア日本リートETF(1476)」
1,000万円を運用する投資信託の選び方

1,000万円を運用する投資信託を選ぶ際は、次の5つのポイントを慎重に検討することが欠かせない。
1.運用実績
運用実績を確認する際は、以下の点に注目したい。
1.長期的な成長
運用実績を見るときは、投資信託がどれだけ成長したかを長い期間で見ることが重要だ。
短期的な実績は、一時的な要因で変動しやすい。
例えば、ある投資信託が1年だけよい実績を出していたとしても、3年5年10年といった長い期間で比較した場合に成果を出せていないとすれば、一時的な市場の変化の影響があっただけの可能性がある。
選ぶべきは、5年、10年といった長期的なスパンで良い成績を出し続けている投資信託だ。
過去の実績がすなわち将来の成果を保証するものではない点に、注意したい。あくまでも投資信託を選ぶ際の一つの判断材料として、検証しよう。
2.ベンチマークとの比較
ベンチマークとの比較は、投資信託の運用成績を評価する上で重要な指標だ。
なおベンチマークとは、投資信託の運用成果を測るための基準となる指数である。
例えば、日本株式を主な投資対象とする投資信託であれば、日経平均株価やTOPIXがベンチマークとして使われることが多い。
投資信託を選ぶ際は、その投資信託がベンチマークと比べて、どの程度の運用成績を上げているかを確認することが大切だ。
ベンチマークとの乖離が小さいほど、ファンドの運用目標が達成されていると判断できる。
ただしこの時も運用実績と同様に、短期的な成績だけでなく、3年や5年といった中長期的な期間でベンチマークとの比較をすることが重要だ。
市場環境によって短期的な成績は大きく変動することがあるため、長期的な視点で評価することで、より信頼性の高い判断ができる。
また、ベンチマークを大きく上回る運用成績を上げている投資信託を、無条件に過信するのは危険だ。
高いリターンが期待できる反面、リスクが高い可能性がある。自分のリスク許容度に合わせて、ベンチマークとの乖離幅を考慮しながら選ぶことが賢明である。
ベンチマークとの比較は、投資信託の目論見書や運用報告書で確認できる。
これらの資料を丁寧に読み込み、ベンチマークに対する運用成績を把握することで、より適切な投資信託を選択しよう。
3.リスク調整後リターン
1,000万円を運用する投資信託を選ぶ際、リスク調整後リターンは重要な指標だ。
リスク調整後リターンとは、投資のリスクに対する収益性を評価するものである。
単純なリターンだけでなく、そのリターンを得るために取ったリスクも考慮するのが特徴だ。
代表的な指標としてシャープレシオがある。これは、リスクフリーレートを超える超過リターンを、リスク(標準偏差)で割って算出する。
シャープレシオが高いほど、リスクに対して効率的に収益を上げていることを意味する。
例えば、2つの投資信託を比較する際、リターンが12%と14%だったとしよう。一見すると、リターン14%の投資信託の方が好ましく見えるだろう。
しかしこの場合のリスクがそれぞれ5%と10%だった場合、無資産の利回りが2%だとしてのシャープレシオを計算すると、前者の方が効率的な運用だと判断できる。
他にもトレーナー比率やソルティーノ比率といった指標がある。いずれも、リスクに対してどれだけ効率的にリターンを得られているかを示すものだ。
これらの指標を活用することで、単純なリターンの高さだけでなく、リスクを考慮した上でより効率的な投資信託を選択できる。
ただし、過去の実績が将来の成果を保証するものではないことに注意が必要だ。
2.純資産総額
1,000万円を運用する投資信託を選ぶ際、純資産総額は重要な指標の1つだ。
一般的に、純資産総額が大きいほど安定性が高く、運用の効率性も向上するためである。
目安として、純資産総額が100億円以上のファンドを選ぶことが望ましい。
これにより、十分な分散投資が可能となり、運用コストの効率化も期待できる。
ただし、純資産総額が小さくても、長期的に増加傾向にあるファンドは検討の価値がある。
また中小型株を対象とするファンドなど、純資産総額が大きすぎると運用が難しくなる場合もあるため、投資対象や運用方針も考慮に入れる必要がある。
純資産総額は変動するため、定期的にチェックすることが大切だ。仮に純資産総額が30億円を下回るようであれば、繰上償還のリスクに注意が必要だ。
3.手数料
1,000万円を運用する投資信託を選ぶ際、以下の手数料をチェックしよう。
- 購入時手数料
- 信託報酬
- 信託財産留保額
- その他の費用
購入時手数料は、多くの場合0〜3%程度だ。ノーロードファンドを選べば、無料である。
信託報酬は、年率0.1〜2.5%程度である。インデックスファンドは0.1〜0.3%、アクティブファンドは1.0〜2.0%が目安となる。
信託報酬は長期投資では大きな影響があるため、できるだけ低いものを選ぶことが欠かせない。
また、信託財産留保額として換金時に0〜0.5%程度かかることがあるが、無料の銘柄も多い。
この他の費用としては監査報酬や売買委託手数料などもチェックしておこう。
手数料は、投資成果に直接影響する。特に信託報酬は重要だ。
ただし、アクティブファンドの場合は運用実績とのバランスも考慮する必要がある。
目論見書や運用報告書で詳細を確認し、長期的な視点で選択することが大切だ。
4.投資対象や運用方針などのファンドの特徴
1,000万円を運用する投資信託を選ぶ際は、投資対象と運用方針を確認することが重要だ。
投資対象については、株式や債券、REITなどの資産クラスや、国内外の地域を確認し、自身のリスク許容度に合わせて選択する。
運用方針ではインデックス運用かアクティブ運用かを確認し、ベンチマークの有無や運用目標を把握しよう。
また、信託報酬などの運用コストや過去の運用実績、純資産総額なども重要な判断材料だ。
さらに、複数の資産クラスや地域に分散投資されているかを確認し、リスク軽減を図ることも大切である。
これらの特徴を総合的に評価し、自身の投資目的に合ったファンドを選択することが、1,000万円という大きな資金を運用する上で欠かせない。
5.投資目的とリスク許容度
1,000万円を運用する投資信託を選ぶ際は、自分自身の投資目的と、どの程度のリスクまで許容できるかを、明確にすることが重要だ。
まず投資目的では、「いつまでに」「どのくらいのお金が必要か」を具体的に設定する。
これは、投資期間や目標リターンを決定し、適切な投資信託を選択する指針となるので、慎重に検討しよう。
リスク許容度は、年齢、家族構成、収入、保有資産などから総合的に判断する。
リスク許容度が低ければ債券中心の安定運用、高ければ株式中心の積極運用を検討できる。
これらを踏まえて、自身の状況に合った投資対象や運用スタイルのファンドを選択し、分散投資を行うことで、効果的な1,000万円の運用が可能となる。
投資信託を1,000万円から始めるならどの証券会社がおすすめ?

投資信託を1,000万円から始めるのにおすすめの証券会社として、以下の3社を紹介する。
- SBI証券
- 楽天証券
- マネックス証券
SBI証券
SBI証券は1,000万円から投資信託を始めるのに最適な選択肢だ。
豊富な商品ラインナップを誇り、低コストのインデックスファンドから高配当株ファンドまで幅広い選択肢がある。
特にSBI・Vシリーズなど、業界最低水準の信託報酬を誇るファンドを提供しているのは、SBI証券の大きな魅力だ。
使いやすいウェブサイトや取引ツールも特徴で、初心者でも直感的に操作できる。
さらに、クレジットカード積立や投信マイレージサービスなど、投資を継続するための魅力的な特典も充実している。
日本最大級のオンライン証券会社として安定した運営と高いセキュリティを提供しており、初心者から上級者まで幅広い投資家のニーズに応えられる点で、SBI証券はおすすめできる。
\ 累計口座数1,000万突破!手数料無料で取引するなら /
楽天証券
楽天証券の大きな特徴は、楽天が展開する各種サービスとの連携にある。
投資信託の購入や保有で楽天ポイントが貯まり、ポイントを使った投資信託の購入も可能だ。
また多くの投資信託で購入時手数料が無料という、手数料の安さも魅力である。
さらに、初心者にも分かりやすいインターフェースを提供している点でも評価されている。
投資信託の品揃えも豊富で、低コストのインデックスファンドから積極運用型のファンドまで幅広く取り揃えている。
NISAやiDeCoにも対応しているため、長期的な資産形成を目指す投資家にもおすすめだ。
マネックス証券
マネックス証券の特徴は、投資教育に力を入れている点にある。初心者向けのセミナーや動画コンテンツが充実しており、投資の基礎から学べる。
また、独自の分析ツール「銘柄スカウター」を提供しており、投資判断の参考になる。
投資信託の品揃えも豊富で、特に外国株式に強みを持つのも、マネックス証券の特徴だ。
手数料も比較的安く、多くの投資信託で購入時手数料が無料となっている。
さらに新規公開株であるIPOの取扱いが多いため、IPO投資に興味がある投資家にとってマネックス証券は魅力的な選択肢だ。
1,000万円を投資信託で運用する時の5つのポイント

1,000万円を投資信託で運用する際は、次の点に注意しよう。
コストの低い商品を選ぶ
1,000万円の運用では、コスト管理が重要だ。特に信託報酬は長期的な運用成果に大きく影響する。
例えば、年率0.5%の信託報酬の差は、20年間で約100万円の差になることもある。
低コストのインデックスファンドを中心に選び、信託報酬が0.5%以下の商品を探すことで、運用成果を最大化できる可能性が高まる。
長期目線で運用する
投資信託は、長期保有が成功の鍵だ。短期的な市場変動に惑わされず、5年、10年、あるいはそれ以上の長期で運用することで、リスクを軽減しつつ安定的なリターンを得られる可能性が高まる。
特に重要なのは複利効果の活用だ。例えば年利5%で20年間運用すると、元本は約2.7倍になる。
さらに、定期的な積立投資を組み合わせれば、ドルコスト平均法の効果も得られ、市場の上下に左右されにくい安定した資産形成が可能だ。
長期目線での運用は、1,000万円という大きな資金を着実に成長させる、重要な戦略である。
運用成果や市況を定期的に確認する
1,000万円の投資信託運用では、定期的な運用状況の確認が不可欠である。
年に1〜2回程度、または大きな市場変動があった際に、運用成果をチェックしよう。
確認時には、運用方針との整合性、市場環境の変化、資産配分のバランスなどを点検する。
必要に応じてリバランスし、長期的な運用目標に沿った調整を行うことが重要だ。
ただし、頻繁な確認は短期的な変動に一喜一憂する原因となるため、避けなければならない。
定期的な確認と適切な対応により、安定した資産成長を目指そう。
非課税制度を活用する
非課税制度を活用することで、効果的な資産形成や節税が可能になる。主な非課税制度は、次の2つだ。
NISA(少額投資非課税制度)
NISA(少額投資非課税制度)は、投資初心者でも気軽に始められる税制優遇制度だ。次の特徴がある。
- 投資による利益(配当金、売却益)が非課税
- 年間投資枠は最大360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)
- 非課税保有期間が無期限化(2024年以降)
- 18歳以上の日本居住者が利用可能
- 株式、投資信託などの金融商品に投資可能
NISAは、1人1口座、1つの金融機関でのみ開設できる。金融機関によって取り扱う商品や手数料が異なるため、あらかじめ比較検討したうえで選びたい。
ただ、投資で得られた収益に税金がかからず、購入回数に上限がないため、長期的かつ効率的な資産形成に適している。
- 出典:投資信託協会「NISAってなに?」
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後の資金準備に特化した制度だ。主に次のような特徴がある。
- 掛金全額が所得控除の対象となるため、所得税・住民税が軽減される
- 運用で得た収益に税金が課されない
- 掛け金は任意に設定できる
- 少額からの積立投資が可能
iDeCoは、国民年金や厚生年金といった公的年金とは別に給付を受けられる、私的年金制度だ。
iDeCoの運用で得た利益(分配金や譲渡益)はすべて非課税となり、再投資もできる。
また、掛金の全額が所得控除の対象となる「小規模企業共済等掛金控除」が適用されるのが特徴だ。
原則として60歳まで解約できないが、将来への備えとして、また税金対策として効果的である。
- 出典:iDeCo公式サイト
専門家に相談するのも手
1,000万円の投資信託運用では、専門家のアドバイスが有効だ。
特にIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)は、中立的な立場で適切な助言を提供できる、心強いサポーターである。
専門家は、リスク許容度に応じたポートフォリオ構築や、税制を考慮した運用戦略の提案など、個々の状況に合わせた専門的なサポートを行う。
長期的な資産形成の道筋を立てる上で、専門家の知見は大きな助けとなるだろう。
投資信託で効率的に資産を増やすなら「資産運用ナビ」で専門家に相談しよう

1,000万円の資金を投資信託で効率的に増やすなら、専門家のサポートが欠かせない。
そして自分にぴったりの専門家を見つけるなら、「資産運用ナビ」の活用が効果的だ。
投資信託の難しさはどこか
投資信託の難しさには、次のようなものがある。
- 商品数が多く(2024年時点で約6,000点)自分に合ったものを選ぶのが困難
- 手数料体系が複雑
- 分散投資されているため個々のリスク評価が難しい
投資信託は長期的な資産運用を前提とする金融商品であり、その選択に際しては過去から現在の実績を分析しつつ、市場の動向を加味しながら、未来の成長度合いを予測しなければならない。
そのため、一朝一夕に身に着けた金融に関する知識だけでは、成長可能性が見込め、さらに自分の目的に合った商品を選ぶのに困難を伴うのだ。
投資信託は専門家と進めるべき
投資信託で成功するまでの過程では、数々の困難を伴う。
しかしこれを専門家と進めると、次のような局面で適切なアドバイスを受けられるので、おすすめだ。
- 適切な商品選択
- 運用戦略の立案
- 市場変動時の冷静な判断へのサポート
- 個人のライフプランに合わせた提案
これらは、長期的な視点で投資信託を進める際に欠かせない。
投資信託運用の相談先は「資産運用ナビ」で探せる
投資信託の運用にかかる相談先をどうやって見つければよいか悩むときは、「資産運用ナビ」をおすすめしたい。
「資産運用ナビ」は、投資家の悩みや目標に合わせて最適な専門家を紹介するオンラインプラットフォームである。
簡単な質問に答えると、条件に合うIFAがランキング形式で提示される。
アドバイザーのプロフィールや過去の相談事例も確認でき、専門分野や実績を参考に選択することも可能だ。
「資産運用ナビ」は全国対応で、オンライン面談も可能である。例えば地方在住者や忙しい人でも、気軽に利用できる。
初回相談は無料で、専門家から中立的な立場でアドバイスを受けられるのが特徴だ。
「資産運用ナビ」に早速申し込みして、自分にぴったりの専門家を探そう。
「資産運用ナビ」で見つけた専門家と1,000万円の投資信託を始めよう!

1,000万円を投資信託で運用したときの利益は、運用方法や銘柄によって変わる。
一般的には、リスクが高い方法ほどリターンが大きい。ただし投資信託での成功を目指すなら、長期投資が前提となる点は、いずれの方法でも同様だ。
1,000万円を投資信託で上手に運用するコツは、慎重に銘柄を選ぶこと・運用コストを抑えること・非課税制度を活用することだ。
そして投資信託を選ぶ場合は、投資の目的リスク許容度に合わせて、最適な商品を選ぶことが重要である。
このとき専門家に相談しながら進めれば、より効果的な運用が期待できる。
自分にぴったりの専門家を探すなら、無料で専門家を探せる「資産運用ナビ」の利用は欠かせない。
「資産運用ナビ」にすぐに登録して、専門家と一緒に、1,000万円の投資信託を早速スタートしよう。
投資信託1,000万円に関するQ&A