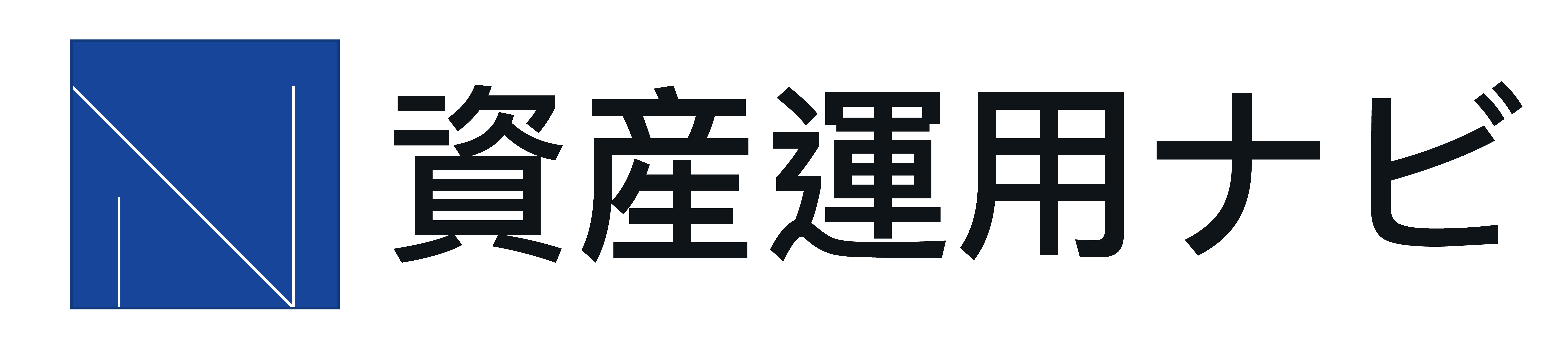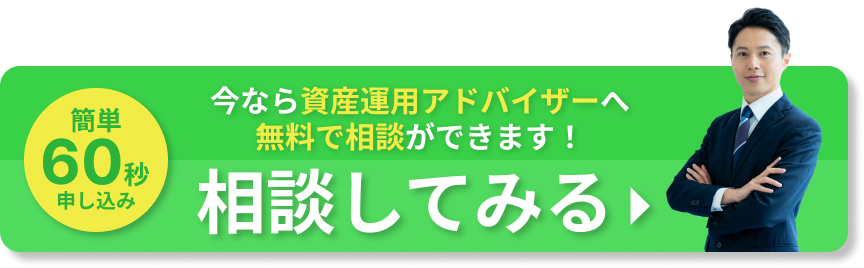※本ページはアフィリエイトリンク(広告)を含みます
- 100万円を投資信託で運用したらいくら増えるのか知りたい
- 100万円を投資するのにおすすめの投資信託が知りたい
- 投資信託で利益を出すためのコツが知りたい
近年、NISAなどの普及によって投資信託での運用を始める人が増えてきた。
「100万円を投資信託で運用したい」「100万円を投資するのにおすすめのファンドが知りたい」などと考えている方も少なくないだろう。
今回の記事では、100万円を投資信託で運用するとどのくらいのリターンが見込めるのかについて、投資信託の種類別に詳しく解説していく。
投資信託で運用を行う際のコツやおすすめファンドについても紹介しているため、これから投資を始めようと考えている方は、ぜひ参考にしてみてほしい。
投資信託に100万円投資した時のリターンは種類によって変わる

「投資信託に100万円投資したらどのくらいお金が増えるのか」と気になる方も多いだろう。
しかし、投資信託での運用によって得られるリターンは、投資信託の種類や運用期間などによって変わってくる。
まずは、投資信託の仕組みや種類について理解した上で、種類別に運用シミュレーションを行っていこう。
投資信託の特徴・仕組み
投資信託は、投資家から集めたお金を一つにまとめて、運用のプロであるファンドマネージャーがさまざまな資産に分散投資をしながら運用を行う仕組みの金融商品だ。
運用パフォーマンスが好調であれば、投資信託の基準価額は上昇していき、運用パフォーマンスが悪化すると、投資信託の基準価額が下落していく。
個人で世界中の資産に直接投資を行いつつ運用の管理を行うのは難しく感じられることもあるが、投資信託の場合は一つの銘柄に投資を行うだけで、複数の国や地域の資産に手軽に分散投資が行える。
金融機関や銘柄によっては100円といった少額から投資を始められることもあるため、投資初心者の方や、なかなか投資にお金を回せないという方にも適している。
投資信託の種類
投資信託の運用方法は、大きく分類すると「インデックス運用」と「アクティブ運用」の2種類に分けられる。
インデックス運用は、株価指数等のベンチマークに連動する運用成果を目指す運用方法で、値動きがわかりやすく運用コストを抑えやすいというメリットがある。
一方、アクティブ運用は、株価指数等のベンチマークを上回る運用成果を目指す運用方法で、情報収集や分析に基づいた運用が行われるため、インデックス運用に比べてコストがかかりやすい。
それぞれの特徴を理解して、自分の運用スタンスに合った運用方法を選ぶのが重要だ。
また、投資信託の投資対象は、株式や債券、不動産、原油や金といったコモディティなど多岐に渡り、投資する国や地域もさまざまだ。
例えば、株式は債券に比べてハイリスク・ハイリターンになりやすく、大きな利益を狙える一方で、大きな損失が発生する可能性も高い。
また、先進国に比べて新興国はリスク・リターンの度合いが高く、情報収集も難しいという特徴がある。
「投資信託」と一口に言っても、どのような国や地域のどんな資産に投資するかによって、リスク・リターンが変わってくる点に注意が必要だ。
投資信託を100万円運用した時のシミュレーション
投資信託を100万円分運用した場合、数年後資産がどのくらいに増えるのかシミュレーションしてみよう。
ここでは、「全世界株式型」「米国株式型」「国内株式型」「バランス型」「外国債券型」の5つの種類別にシミュレーションを行う。
全世界株式型
全世界株式を対象とする代表的な投資信託である「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」のトータルリターンを参考に、100万円を運用した際のシミュレーションを実施した。
想定利回り(年率):18%での運用シミュレーション
| 運用期間 | 投資元本 | 運用益 | 元本+運用益 |
|---|---|---|---|
| 5年 | 1,000,000円 | 1,287,758円 | 2,287,758円 |
| 10年 | 1,000,000円 | 4,233,836円 | 5,233,836円 |
| 20年 | 1,000,000円 | 26,393,035円 | 27,393,035円 |
出典:SBI証券「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」
全世界の株式にまんべんなく投資を行った場合、投資元本が100万円であったとしても、5年後には約220万円、10年後には約520万円、20年後には約2,740万円に資産が大きくなるという結果となった。
全世界の株式に分散して投資を行っているものの、株式に投資を行っている以上、それなりにリスクはある点に注意が必要だ。
米国株式型
続いて、米国株式を投資対象とする代表的な投資信託である「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」のトータルリターンを参考にシミュレーションを実施した。
想定利回り(年率):23%での運用シミュレーション
| 運用期間 | 投資元本 | 運用益 | 元本+運用益 |
|---|---|---|---|
| 5年 | 1,000,000円 | 1,815,306円 | 2,815,306円 |
| 10年 | 1,000,000円 | 6,925,246円 | 7,925,246円 |
| 20年 | 1,000,000円 | 61,820,622円 | 62,820,622円 |
出典:SBI証券「eMAXIS Slim米国株式(S &P500)」
全世界株式型に比べてさらに運用利回りが高い分、大きな収益が期待できるのが特徴だ。
ただし、上記のシミュレーションはあくまでも過去の運用結果をもとにしたものであり、実際に将来の運用成果を約束するものではない点に気をつけよう。
堅調に経済成長を続ける米国経済ではあるものの、金融危機やテロ、紛争といった経済にダメージを与えるような出来事が発生すれば、投資元本が大きく毀損される恐れもある。
国内株式型
次に、国内株式を投資対象とする代表的な投資信託である「eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)」のトータルリターンをもとに、運用シミュレーションを行った。
想定利回り(年率):13%での運用シミュレーション
| 運用期間 | 投資元本 | 運用益 | 元本+運用益 |
|---|---|---|---|
| 5年 | 1,000,000円 | 842,435円 | 1,842,435円 |
| 10年 | 1,000,000円 | 2,394,567円 | 3,394,567円 |
| 20年 | 1,000,000円 | 10,523,088円 | 11,523,088円 |
出典:SBI証券「eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)」
10年運用を継続した場合は約340万円、20年運用を継続した場合は約1,150万円の運用成果が見込まれる。
ただし、日本のみに集中して投資を行った場合、日本経済が悪化した際の資産全体に与えられるダメージが大きくなる点に注意が必要だ。
国内株式タイプの投資信託に投資を行う際は、全世界型や米国株式型の投資信託にも分散して投資を行うのをおすすめする。
バランス型
バランス型の代表的な投資信託である「eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)」のトータルリターンを参考に、運用シミュレーションを実施した。
想定利回り(年率):8%での運用シミュレーション
| 運用期間 | 投資元本 | 運用益 | 元本+運用益 |
|---|---|---|---|
| 5年 | 1,000,000円 | 469,328円 | 1,469,328円 |
| 10年 | 1,000,000円 | 1,158,925円 | 2,158,925円 |
| 20年 | 1,000,000円 | 3,660,957円 | 4,660,957円 |
出典:SBI証券「eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)」
バランス型はさまざまな種類や国の資産に分散投資を行うことを目的とした投資信託だ。
全世界型や米国株式型の投資信託に比べると年率リターンは低いものの、運用期間が長くなるほど複利効果によって資産の増加が見込まれる。
リスクを分散することを重視したいという方や、1本の投資信託でバランスよく投資をしたいという方におすすめだ。
外国債券型
外国債券型の代表的な投資信託である「eMAXIS Slim先進国債券インデックス」のトータルリターンを参考に、運用シミュレーションを行った。
想定利回り(年率):5%での運用シミュレーション
| 運用期間 | 投資元本 | 運用益 | 元本+運用益 |
|---|---|---|---|
| 5年 | 1,000,000円 | 276,282円 | 1,276,282円 |
| 10年 | 1,000,000円 | 628,895円 | 1,628,895円 |
| 20年 | 1,000,000円 | 1,653,298円 | 2,653,298円 |
出典:SBI証券「eMAXIS Slim先進国債券インデックス」
株式型に比べると期待リターンはかなり低いものの、長く運用を続ければ資産増加が見込まれる。
運用期間中に資産が大きく増減するのが嫌だという人や、リスクを抑えて運用したい人、使う予定の決まっているお金で運用したい人などに適しているだろう。
【投資目的別】100万円から始めるのにおすすめの投資信託

投資信託で運用を始める際は、投資目的や運用期間に応じて、適切な商品を選ぶことが重要だ。
ここでは、投資目的やタイプ別におすすめの投資信託を紹介していく。
長期的にじっくり資産形成をしたい人向けの投資信託
コツコツ時間をかけて資産形成を図りたいという人には、以下のような投資信託がおすすめだ。
- eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
- 楽天・オールカントリー株式インデックスファンド
- SBI・V・全世界株式インデックスファンド
上記に取り上げたのは、いずれも全世界型のインデックスファンドだ。
全世界の株式にまんべんなく投資を行うことで、世界経済の成長を味方につけつつ、幅広い国や地域の株式への分散投資も同時に行える。
相場の状況によっては年率20%を超える高いリターンも見込めるため、資産をどんどん成長させていきたいという人にも適しているだろう。
ただし、株式市場の状況によっては年間リターンがマイナスになるタイミングもあるかもしれない。
そのため、すぐに大きなリターンを期待するというよりは、時間をかけてじっくりと資産を育てたいというニーズに適している。
NISAやiDeCoといった非課税制度とも相性が良い。
なるべくリスクを抑えて運用したい人向けの投資信託
なるべくリスクを抑えて運用できる投資信託が良いという方は、以下のようなバランス型や外国債券型のファンドがおすすめだ。
- eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
- たわらノーロードバランス
- eMAXIS Slim先進国債券インデックス
バランス型の投資信託に投資を行うと、一つの銘柄に投資を行うだけで、複数の資産への分散投資が実践できる。
例えば、「eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)」は、国内株式・先進国株式・新興国株式・国内債券・先進国債券・新興国債券・国内リート・先進国リートの8つの資産に12.5%ずつ均等に分散投資を行うことを基本的な投資戦略としている。
また、株式に比べて価格変動の小さい債券ファンドに投資を行うことで、運用期間中の価格変動リスクを抑えやすくなるだろう。
成長企業に投資してリターンを狙いたい人向けの投資信託
今後成長していく企業に投資を行って、大きなリターンを得たいという人には、以下のようなファンドがおすすめだ。
- eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
- iFree NEXT FANG+インデックス
「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」のように、S&P500を参照するインデックスファンドに投資を行えば、米国株式を代表する500銘柄にまとめて投資を行うのと同じような効果が得られる。
また、米国企業の中でもさらに成長性の高い企業に絞って投資を行いたいという方は、「iFree NEXT FANG+インデックス」もおすすめだ。
このファンドが参照するNYSE NEXT FANG+指数は、次世代テクノロジーをベースに、グローバルな現代社会および人々の生活に大きな影響力を持つ著名な米国企業を対象とする株価指数だ。
個別企業の株価がパフォーマンスに与える影響が大きいため、業績やマーケット動向によっては価格が大きく変動する可能性もある点に注意が必要だ。
日本企業に投資をしたい人向けの投資信託
日本企業に投資をしたいという方には、以下のようなファンドがおすすめだ。
- eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
- 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド
- ニッセイ日経225インデックスファンド
上記で挙げた銘柄は、日本株式を対象とする株価指数であるTOPIXや日経平均株価を参照するインデックスファンドだ。
TOPIXや日経平均株価は、日々のニュースなどでも情報を得やすいため、値動きをチェックしやすいというメリットがある。
定期的に分配金を得たい人向けの投資信託
値上がり益だけでなく定期的なインカムゲインも得たいという方は、以下のような投資信託がおすすめだ。
- アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型 予想分配金提示型
- 日経平均高配当利回り株ファンド
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型は、成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行う投資信託だ。
企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づくアクティブ運用を実施しており、定期的に分配金を支払いながらも安定した運用を続けている。
分配金目的で投資信託を選ぶ際は、分配金利回りの高さだけではなく、基準価額の動向にもしっかりと注意するようにしよう。
100万円を投資信託で運用するなら非課税制度も活用するべき

100万円をこれから投資信託で運用しようと考えている方は、非課税制度も積極的に利用しよう。
ここでは、NISAとiDeCoの2つの非課税制度についてそれぞれポイントを解説し、比較してシミュレーションを行っていく。
NISAのメリットと投資信託運用のポイント
NISAは、投資によって得られる利益が非課税で受け取れるという制度だ。
18歳以上であれば誰でも始められて、資金の引き出しも自由に行える。
2024年から新NISAでは、成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能となり、年間最大360万円まで投資ができるようになった。
iDeCoに比べて資金の出し入れを自由に行いやすいため、コツコツ積立投資を行うのはもちろん、少額だけ投資をしたいハイリスク・ハイリターンな投資信託の購入や、ボーナスなど余剰資金での投資信託の購入にも適している。
iDeCoのメリットと投資信託運用のポイント
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で老後に向けて年金を作る私的年金制度であり、国民年金の加入者であれば誰でも利用できる制度だ。
NISAと同じく投資によって得られる利益は非課税となることに加えて、掛金の全額が所得控除の対象となったり、資金の受け取り時に控除が適用されたりするなどの税制優遇を受けられる。
ただし、iDeCoで運用する資産については、原則60歳まで引き出すことができないため、NISAよりも長期で運用することをイメージしておく必要があるだろう。
iDeCo・NISAでの運用シミュレーション
iDeCo・NISAで運用を行った際に、それぞれどのように資産が増えていくのかをシミュレーションしてみよう。
全世界株式型(年率18%)をNISA口座で運用した際の、運用シミュレーションおよび節税効果は下記の通りだ。
想定利回り(年率):18%での運用シミュレーション
| 運用期間 | 投資元本 | 運用益 | 節税効果 |
|---|---|---|---|
| 5年 | 1,000,000円 | 1,287,758円 | 261,608円 |
| 10年 | 1,000,000円 | 4,233,836円 | 860,104円 |
| 20年 | 1,000,000円 | 26,393,035円 | 5,278,607円 |
出典:SBI証券「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」
NISAの場合は、100万円を一括で投資することも可能だが、iDeCoでは一括投資はできない。
加入している国民年金の種類によって毎月の掛金上限が異なる点に注意が必要だ。
例えば、企業型DCのない企業の会社員の場合、月額23,000円が上限となる。
仮に、40歳・年収700万円の人が毎月23,000円iDeCoに拠出して、65歳まで運用を続けた場合のシミュレーションは下記の通りだ。
| 掛金/月 | 23,000円 |
|---|---|
| 年収 | 700万円 |
| 積立総額(年率18%で計算) | 43,708,308円 |
| 運用益(年率18%で計算) | 38,188,308円 |
| 運用益分の節税効果 | 7,757,954円 |
| iDeCoによる所得税軽減額/25年 | 1,380,000円 |
| iDeCoによる住民税軽減額/25年 | 690,000円 |
出典:iDeCo公式サイト「かんたん税制優遇シミュレーション」
運用益に対する税金および所得税や住民税を合わせた税制優遇額は約980万円にも及ぶ。
100万円分を一括で投資できなくても、長期間投資を継続することで節税効果が大きくなることがわかる。
投資信託を100万円から始めるならどの証券会社がおすすめ?

投資信託の運用を始めるなら、ネット証券がおすすめだ。
ここでは、初心者から経験者までさまざまな投資家におすすめの証券会社を紹介する。
総合力で選ぶならSBI証券
| 成長投資枠対象ファンド | 1,305本 |
|---|---|
| つみたて投資枠対象ファンド | 250本 |
| 積立頻度 | 毎月・毎週・毎日 |
| クレカ積立 | 三井住友カード、Olive |
| ポイント還元率 | 最大3% |
出典:SBI証券「投資信託パワーサーチ」
SBI証券はネット証券最大手の一つで、NISA口座での株式・投資信託の取引手数料が全て無料となっている。
クレカ積立を行う場合は、三井住友カードやOliveが利用できて、毎月の積立額に応じて最大3%のVポイントが貯まる。
取扱商品や銘柄数も多く、コストも抑えて運用しやすいことから、幅広い投資家に人気のあるネット証券だ。
初めて投資に挑戦する初心者の方や、すでに三井住友カードを持っているという方におすすめだ。
\ 累計口座数1,000万突破!手数料無料で取引するなら /
楽天経済圏を利用しているなら楽天証券
| 成長投資枠対象ファンド | 1,305本 |
|---|---|
| つみたて投資枠対象ファンド | 241本 |
| 積立頻度 | 毎月・毎日 |
| クレカ積立 | 楽天カード |
| ポイント還元率 | 最大2% |
出典:楽天証券「投信スーパーサーチ」
楽天証券もSBI証券と並ぶネット証券最大手の一つに数えられる証券会社だ。
NISA口座での株式・投資信託の取引手数料は全て無料となっているため、SBI証券と同様にコストを抑えて取引しやすい。
クレカ積立や投信マイレージで楽天ポイントが貯まり、貯まったポイントは投資信託や米国株式などの購入に充てられる。
楽天グループのサービスを普段からよく利用している方は、「楽天ポイントが貯まる→楽天ポイントで投資する」というサイクルを作りやすいだろう。
クレカ積立でポイントを貯めるならマネックス証券
| 成長投資枠対象ファンド | 1,200本 |
|---|---|
| つみたて投資枠対象ファンド | 234本 |
| 積立頻度 | 毎月・毎日 |
| クレカ積立 | マネックスカード、dカード |
| ポイント還元率 | 最大3.1%(キャンペーン期間中は最大10%) |
出典:マネックス証券「ファンド検索・商品一覧」
マネックス証券では、マネックスカードやdカードでのクレカ積立が可能だ。
dカードのキャンペーン期間中は最大10%、年会費無料で発行できるマネックスカードでも最大1.1%の高還元率となっているため、効率よくポイントを貯めたいという方におすすめだ。
貯まったマネックスポイントおよびdポイントは投資に利用できるほか、Amazonギフトカードやマイル、Vポイント等に交換できるため、利便性が高いというメリットもある。
100万円を投資信託で運用する時の5つのポイント

100万円を投資信託で運用する際は、以下の5つのポイントに注意しよう。
- 投資目的やリスク許容度にあった商品を選ぶ
- コストの低い商品を選ぶ
- 長期目線で運用する
- 運用成果や市況を定期的に確認する
- 資産運用の専門家に相談するのも手
投資目的やリスク許容度にあった商品を選ぶ
まずは、自分の投資目的やリスク許容度をしっかりと把握することから始めてみよう。
「老後に向けて十分な貯蓄を得るため」「子供の教育資金を確保するため」など、人によって投資目的は異なる。
「いつまでにいくらお金を貯めるのか」を明確にすることで、具体的な運用計画を立てやすくなるだろう。
また、どれくらいリスクを許容できるかを明らかにして、リスク許容度に適した投資信託かをチェックすることも重要だ。
銘柄ごとの過去の運用パフォーマンスを確認し、過去にどのくらい価格変動があったか、どのくらいの損失なら許容できそうか、をしっかりとイメージしておくことで、ミスマッチを防ぎやすくなる。
長期目線で運用する
上記でシミュレーションした通り、投資信託での運用は長期で実施するほど期待リターンが大きくなる。
これは、複利効果と呼ばれるもので、運用で得られた利益を再び投資することで、利益が利益を生んで資産が雪だるま式に増えていく効果のことだ。
将来に向けて資産を効率よく増やしていくためには、短期目線で運用するのではなく、長期でじっくりと運用を続けることが肝心だ。
コストの低い商品を選ぶ
投資信託での長期運用を実践する際は、運用コストも意識しよう。
投資信託の運用コストには、売買手数料や信託報酬、信託財産留保額などがある。
特に注意したいのが、投資信託の運用期間中ずっと必要となる信託報酬だ。
同じ運用戦略の投資信託を比較する際は、なるべく信託報酬の安い銘柄を選ぶことで、運用コストを抑えやすくなる。
運用成果や市況を定期的に確認する
投資信託での運用を行う際は、運用パフォーマンスやマーケットの状況を定期的に確認しよう。
ほとんどの投資信託は、毎月「月次レポート」という運用状況が記載されたレポートが発行されるため、どのように運用されているかを手軽にチェックできる。
月次レポートを参考にしながら運用状況を確認して、どのような要因で価格が変動したのかを理解しておくことで、価格変動にも焦らず対応しやすくなるだろう。
資産運用の専門家に相談するのも手
自分に合った銘柄選びの方法がわからないという方や、定期的に運用パフォーマンスをチェックするのが不安だという方は、資産運用の専門家に相談するのも一つの手だ。
経験豊富なプロに運用を相談することで、初心者でも無理なく投資信託での運用を継続しやすくなるはずだ。
些細な疑問にも丁寧に答えてくれるため、不安なことやわからないことがある方は、ぜひ専門家を積極的に活用してみよう。
投資信託で効率的に資産を増やすなら「資産運用ナビ」で専門家に相談しよう

投資信託での運用を始める際は、資産運用の専門家への相談がおすすめだ。
ここでは、専門家を活用するメリットや、自分に合った相談先の選び方について解説する。
投資信託運用の難しさとは
投資信託運用において特に難しいのは、自分の運用ニーズに適した銘柄選びだ。
日本では数千種類の投資信託が販売されており、それぞれ投資先や運用方法、リスクなどが異なるため、自分の求める商品を探すのは難しく感じられるだろう。
自分の投資目的や資産運用の方針を正しく見極め、自分の許容できるリスクや求めるリターンに合致した商品を比較して選んでいくのは、投資経験者でもなかなか簡単には行えない。
また、投資信託についての情報や運用状況を知るためには、交付目論見書や運用報告書などをしっかりと読み込む必要がある。
しかし、これらの資料には金融用語などが多く用いられているため、投資初心者では理解に時間がかかる可能性もある。
こうしたことから、初心者が自分一人で最適な商品選びを行う場合は注意が必要だ。
投資信託運用を専門家と進めた方が良い理由
投資信託運用に挑戦したいという方は、資産運用の専門家への相談がおすすめだ。
資産運用の専門家には、証券会社や銀行の営業担当者、FP、IFAなどが挙げられる。
これらの専門家は金融や経済、投資信託についての豊富な知識を持っているため、自分ではわからないことや運用にあたって不安なことなどにもしっかりと対応してくれる。
自分のリスク許容度も的確に判断してくれて、最適な商品を紹介してくれるため、初心者でも安心して運用商品を選べるだろう。
「そもそも投資信託についてよくわからない」「自分に合った銘柄を知りたい」と悩んでいる方は、資産運用の専門家への相談を検討してみよう。
投資信託運用の相談先を探すなら「資産運用ナビ」がおすすめ
投資信託の運用について相談できる専門家には、金融機関やFP、IFAなどいくつかの選択肢がある。
それぞれメリット・デメリットがあるため、相談先を選ぶ際もそれぞれの特徴を理解しておくことが重要だ。
自分に適した相談先を手軽に探したいという方は、「資産運用ナビ」というマッチングサービスの利用がおすすめだ。
「資産運用ナビ」は、年齢や金融資産、投資目的などを入力すると、自動で自分にぴったりのアドバイザーが診断・検索されるというサービスだ。
全国のIFAデータベースからあなたのニーズに適した相談先が簡単に検索されるため、相談先選びに困っている方はぜひ活用してみてほしい。
相談料や利用料などは無料となっているため、ぜひこの機会に「資産運用ナビ」を利用してみてはいかがだろうか。
100万円で投資信託運用を始める場合は投資目的に合わせた銘柄選びが重要

100万円を投資信託で運用したときのリターンは、どんな商品で運用するかやどのような相場の状況かによって異なる。
大きなリターンが期待できるものはリスクも大きく、リスクが抑えられるものは期待できるリターンも小さいため、自分の理想とするリスク・リターンに合わせた商品を選ぶことが重要だ。
本記事では、100万円を投資信託で運用する際のコツやおすすめの商品などを紹介した。
初心者でも失敗せずに投資信託での運用を進めるためには、資産運用の専門家への相談が重要だ。
「資産運用ナビ」を利用すれば、簡単な手順であなたに最適な相談先を見つけられるだろう。
投資信託での運用をプロに相談したいという方は、ぜひ「資産運用ナビ」を利用してみてほしい。
100万円から始める投資信託に関するQ&A