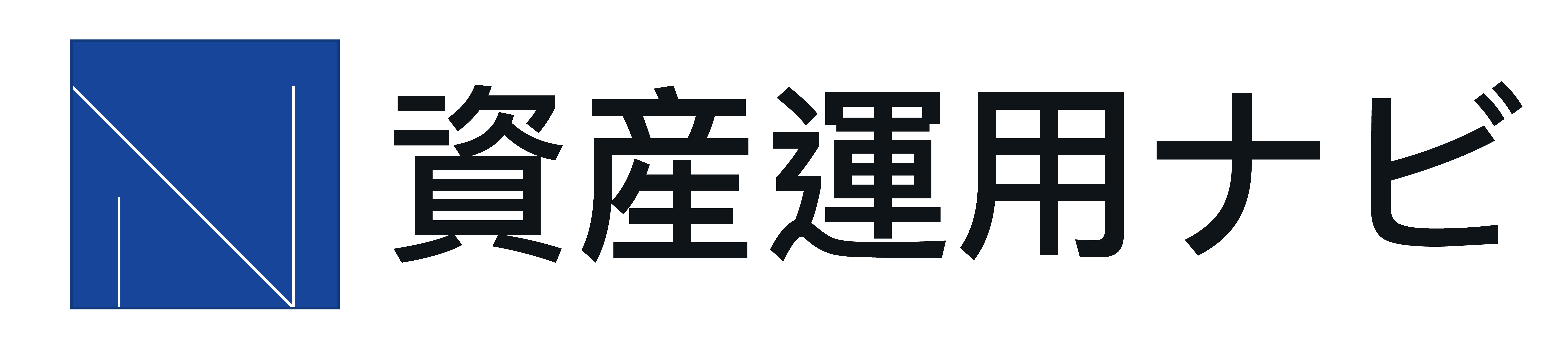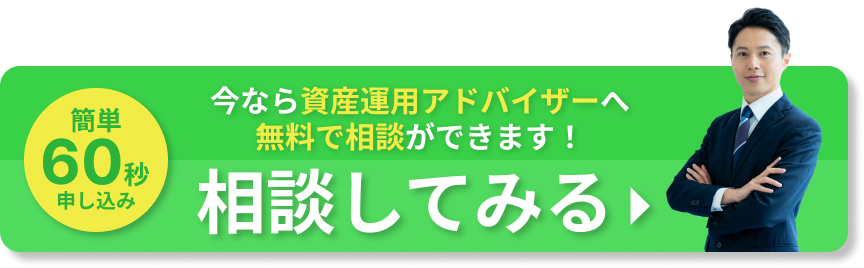- インデックスファンドを運用したいが、何から始めればいいかわからない
- インデックス投資のメリット・デメリットを理解したい
- インデックスファンドを運用する時のコツが知りたい
投資に興味がある初心者におすすめしたいのがインデックスファンドだ。コストが低く、少額から始められるとあって「初心者でも購入しやすい」と評判だ。
しかし、仕組みやメリット、デメリットなどについて理解している人は少ない。
インデックス投資で損をしたくないのであれば、インデックスファンドの理解が必須だ。
本記事では初心者でも分かるように、インデックスファンドのメリットとデメリット、運用のコツなどを解説していく。
インデックスファンドとは?

まずは、インデックスファンドの定義や分類などについて見ていこう。
また、代表的なインデックスや分類を把握しておくと、より具体的にイメージができるようになるだろう。
インデックスファンドとはどのようなファンドなのか
「インデックスファンド」とは、特定の指数の値動きに連動した運用成果を目指す投資信託のことだ。
「インデックス投資信託」や「パッシブファンド」と呼ばれるケースもある。
インデックスファンドと似た言葉に「インデックス投資」がある。インデックス投資とは、特定の指標の値動きに連動するように運用される投資手法のことだ。
インデックス投資の代表的な投資先はインデックスファンドである。よって、インデックスファンドとインデックス投資は、同じ意味で使われるケースがほとんどだ。
インデックスの分類
インデックスは種類が多いため、投資対象地域や投資対象資産を分類している。
こちらに分類表を作成したので、参考にしてほしい。
| 投資対象国 | ・先進国 ・新興国 ・国別(日本、アメリカ、インドなど) |
|---|---|
| 投資対象地域 | ・全世界 ・アメリカ地域(北米) ・ヨーロッパ ・アジア など |
| 投資対象資産 | ・株式 ・債券 ・REIT など |
代表的なインデックス
インデックスファンドは、日経平均株価やS&P500指数などを指標としているケースが多い。特徴とともにまとめた表はこちらだ。
| インデックス名 | 特徴 |
|---|---|
| 日経平均株価 | 日本経済新聞社が選んだ日本の225の企業から構成される平均株価のこと |
| TOPIX(東証株価指数) | 東証プライム市場に上場している全株式の時価総額を指数化した指数のこと |
| ダウ・ジョーンズ工業株価平均 (ダウ平均株価・NYダウ) | 米国を代表する30銘柄から構成されている株価指数のこと |
| S&P500指数 | 米国の大手企業である500社の時価総額をもとに算出される株価指数のこと |
| NASDAQ(ナスダック)指数 | 米国の新興企業向けの市場であるNASDAQに上場している全銘柄から構成されている指数のこと |
| MSCI世界株指数 | ・モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社が算出している株価指数のこと ・日本を含めた23か国の株式市場が対象 |
インデックスファンドのメリットとデメリット

インデックスファンドにはメリットがある一方で、デメリットもある。それぞれの内容を比較してから、投資をするかどうかを検討しよう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 運用の手間がかからず初心者でも始めやすい 保有コストが低い 長期的な運用に適している | 市場平均以上のリターンは望めない 短期的に利益を得るのはむずかしい |
インデックスファンドのメリットとは
インデックスファンドでは、複数の銘柄に分散投資をすることとなる。
自分で投資する銘柄を選択する必要がないので、銘柄選定ができない投資初心者も安心して始められるだろう。
また、分散投資により、特定の銘柄が暴落するリスクを抑えられる。簡単に分散投資ができるのは大きなメリットだ。
インデックスファンドを購入する際は、保有コストを考えておくことが重要だ。
「保有コスト」とは、インデックスファンドを保有している間に支払う手数料を指す。
この保有コストが高いと、ある程度のリターンを得られなければ、手数料負けすることとなってしまう。
インデックスファンドは、保有コストが低い傾向がある。思うようなリターンが得られない時期があったとしても、焦らずに保有できるだろう。
インデックスファンドで利益を出すには、長期目線で投資を続けることが重要だ。
一時的な下落で含み益が減少したとしても、そのまま保有することが求められる。
インデックスファンドは少額から購入できるため、資金が少ない人でも積立投資を続けやすい。
また、先述したように、低コストで運用できる銘柄も多くある。長期投資に向いている特徴を活かせば、数十年後も運用し続けられるだろう。
インデックスファンドのデメリットとは
インデックスファンドは安定的なリターンを望めるファンドだが、市場平均を大幅に超えるリターンを得ることはむずかしい。
また、指標が大幅下落した場合、インデックスファンドも連れ安となる可能性がある点に注意が必要だ。
インデックスファンドでは分散投資をするため、特定の銘柄が暴騰しても、ファンド全体の基準価額に与える影響は少ない。
そのため、短期的に大きな利益を出すことには向いていない。
インデックス投資は、時間をかけて利益を積み重ねていく投資手法だ。長期的な目線で見守るようにしよう。
インデックスファンドと他の投資手法との比較

インデックスファンドには多くのメリットがあるので、気になっている人も多いだろう。ただ、世の中にはインデックス投資以外の投資手法も存在する。
インデックスファンドと比較されるケースが多い金融商品には、アクティブファンドやETFがある。
インデックスファンドに投資をする前に、アクティブファンドやETFとの違いを理解しておけば、どの投資手法が自分に合っているのかが分かるようになるだろう。
インデックスファンドとアクティブファンドの違い
インデックスファンドとアクティブファンドの違いは、こちらの表を参考にしてほしい。
| インデックスファンド | アクティブファンド | |
|---|---|---|
| 運用方針 | 特定の指数の値動きに連動するように運用する | 特定の指数を上回ることを目指して運用する |
| 組入銘柄 | 特定の指数と同様の銘柄が選ばれる | 独自の調査により優秀だと判断される銘柄が選ばれる |
| コスト | 比較的低い | 高い傾向がある |
| リターン | 市場の平均と同じくらい | 市場の平均を上回るリターンが得られることがある |
インデックスファンドは、日経平均株価やNASDAQ指数などの特定指数の値動きに連動するように設定されている。
たとえば、日経平均株価が右肩上がりでチャートを描いている場合、日経平均株価をベンチマークとしているインデックスファンドも、同じような値動きをするケースが多い。
リターンは市場の平均と同じくらいであるが、コストは比較的低いため、長期投資との相性がよい。じっくりと腰を据えて投資をしたい人に適している。
「アクティブファンド」とは、特定の指標を上回るように設定されているファンドのことだ。
運用を担当するファンドマネージャーが市場や企業のデータを徹底的に調べ、優秀だと判断される銘柄に投資をする。
ファンドマネージャーの手腕によっては、市場の平均以上のリターンを得ることも可能だ。大きなリターンを得たい人に適している。
ただし、コストは高い傾向がある。また、リターンの大きさは魅力的だが、リスクも高くなる点に注意が必要だ。
インデックスファンドとETFの違い
それぞれの違いをまとめた表はこちらだ。
| インデックスファンド | ETF | |
|---|---|---|
| 上場しているか | 上場していない | 上場している |
| 取引価格 | 1日1回算出される基準価額 | リアルタイムで変動する市場価格 |
| 注文方法 | 口数指定もしくは金額指定 | 成行注文や指値注文など |
| 売買時の手数料 | 販売手数料(手数料のかからないファンドもある) | 売買手数料 |
| 保有時の手数料 | 信託報酬 | 信託報酬 |
| 取引窓口 | 証券会社や銀行など | 証券会社のみ |
インデックスファンドは、上場していない投資信託のことだ。リアルタイムでは売買できず、1日1回算出される基準価額で取引が成立する。
注文方法は、口数指定もしくは金額指定のどちらかを指定する。指値注文や逆指値注文などには対応していない。
購入する際は、販売手数料がかかるケースがある。しかし、ノーロードと呼ばれる販売手数料のかからない銘柄も多く販売されているので、必ずしも手数料がかかるわけではない。
保有時は信託報酬の支払いが発生する。
購入できる場所は証券会社をはじめ、銀行や信用金庫などがある。取引場所が多い点がメリットだ。
一方のETFは、上場している投資信託を指す。株式と同じように、市場が開いている時間帯であれば、自由に取引ができる。
また、成行注文や指値注文などの注文方法に対応しており、戦略的な売買も可能だ。取引価格はリアルタイムで変動する。
ETFの売買時には売買手数料が発生するが、証券会社によっては無料の銘柄も多い。
また、売買手数料は利用する証券会社によって異なるため、事前にチェックしておこう。なお、保有時はインデックスファンドと同じように信託報酬がかかる。
ETFの取引ができるのは証券会社のみだ。すでに証券会社の口座を開設しているのであれば、すぐに取引ができる。
インデックスファンドの代表的な商品と選び方

インデックスファンドの商品数は非常に多く、それぞれ特徴が異なる。そのため、自分で投資するインデックスファンドを選べない人も多い。
そのような人のために、ここからはインデックスファンドの代表的な商品を紹介していく。
また、インデックスファンドの選び方のポイントについても言及するので、銘柄選びの参考にしてほしい。
インデックスファンドの代表的な商品
インデックスファンドの代表的な商品を10本厳選した。インデックスファンド10本分の簡易比較表はこちらだ。
なお、こちらの記載内容は2025年1月7日時点の情報となる。
| ファンド名 | 基準価額 | 信託報酬(年率) |
|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 27,769円 | 0.05775%以内 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 34,226円 | 0.09372%以内 |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 73,167円 | 0.7755% |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 34,051円 | 0.09889%以内 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 20,218円 | 0.2035% |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 19,349円 | 0.143%以内 |
| iFreeS&P500インデックス | 38,018円 | 0.198% |
| たわらノーロード先進国株式 | 36,672円 | 0.09889%以内 |
| iFreeNEXT インド株インデックス | 15,148円 | 0.473% |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | 19,683円 | 0.0938%程度 |
それぞれのインデックスファンドの特徴について、順番に解説していく。
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)の基本情報は、こちらを参考にしてほしい。
| 基準価額 | 27,769円 |
|---|---|
| 純資産総額 | 5,173,554百万円 |
| カテゴリ | 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
| ベンチマーク | MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
| 信託報酬(年率) | 0.05775%以内 |
| トータルリターン | ・-0.14%(1か月) ・+6.37%(6か月) ・+29.13%(1年) ・+17.55%(3年) ・+18.54%(5年) |
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」は、日本を含む世界中の株式に投資をするインデックスファンドだ。
全世界株式とあるが、投資先の50%以上は米国企業となっている。
さまざまな国の株式に分散投資をするため、リスクを抑えた運用が可能だ。また、安定した成績を残している点も評価できる。
インデックスファンドで迷った際は、この1本を選んでおけば確実だろう。
ただし、株式に投資をするファンドなので、大きな値動きが生じる可能性があることを覚えておいてほしい。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の基本情報は、こちらにまとめてある。
| 基準価額 | 34,226円 |
|---|---|
| 純資産総額 | 6,562,059百万円 |
| カテゴリ | 国内大型グロース |
| ベンチマーク | 日経平均トータルリターン・インデックス |
| 信託報酬(年率) | 0.09372%以内 |
| トータルリターン | ・+1.34%(1か月) ・+10.79%(6か月) ・+36.65%(1年) ・+21.05%(3年) ・+22.79%(5年) |
「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」は、米国の代表的な指数であるS&P500をベンチマークとしたインデックスファンドだ。
アップルやマイクロソフトなど、米国の代表企業に分散投資ができる。
信託報酬は年率0.09372%以内と、低コストで運用できる点もメリットだ。
米国経済の成長を期待している人や、信託報酬の低いインデックスファンドを選びたい人におすすめのファンドだと判断できる。
iFreeNEXT FANG+インデックス
iFreeNEXT FANG+インデックスの基本情報はこちらだ。
| 基準価額 | 73,167円 |
|---|---|
| 純資産総額 | 443,869百万円 |
| カテゴリ | 国際株式・北米(F) |
| ベンチマーク | NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
| 信託報酬(年率) | 0.7755% |
| トータルリターン | ・+0.62%%(1か月) ・+14.08%(6か月) ・+52.57%(1年) ・+27.40%(3年) ・+41.45%(5年) |
「iFreeNEXT FANG+インデックス」は、NYSE FANG+指数の値動きに連動する運用成果を目指すインデックスファンドだ。
世界を席巻するビッグテック企業に投資ができる。
NYSE FANG+指数の成長は目を見張るものがあり、当インデックスファンドのトータルリターンも非常に高い。
今後も大きな成長が期待できるため、ポートフォリオに組み入れたいインデックスファンドだ。
ただし、iFreeNEXT FANG+インデックスの構成銘柄は10銘柄しかない。
分散投資の面にやや不安が残るため、ほかのインデックスファンドと組み合わせて運用することをおすすめする。
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスの基本情報はこちらだ。
| 基準価額 | 34,051円 |
|---|---|
| 純資産総額 | 890,550百万円 |
| カテゴリ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
| ベンチマーク | MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
| 信託報酬(年率) | 0.09889%以内 |
| トータルリターン | ・+0.60%(1か月) ・+7.78%(6か月) ・+31.79%(1年) ・+19.08%(3年) ・+20.31%(5年) |
「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」は、日本を除いた海外株式に投資をするインデックスファンドだ。
米国への投資割合が7割を超えており、アマゾン ドットコムやエヌビディアなどの企業に分散投資をする。
業種構成比は「コンピュータ・通信機」や「ソフトウェア」が比較的高いものの、バランスよく構成されている。
信託報酬も低めなので、おすすめしたいインデックスファンドのひとつだ。
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンドの基本情報は、こちらを参考にしてほしい。
| 基準価額 | 20,218円 |
|---|---|
| 純資産総額 | 270,433百万円 |
| カテゴリ | 国際株式・北米(F) |
| ベンチマーク | NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
| 信託報酬(年率) | 0.2035% |
| トータルリターン | ・-0.11%(1か月) ・+7.87%(6か月) ・+33.67%(1年) ・-%(3年) ・-%(5年) |
「<購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド」は、米国のハイテク企業に分散投資をするインデックスファンドだ。
NASDAQ100指数は、NASDAQ市場で時価総額の大きい上位100銘柄で構成されている。
NASDAQ100指数の構成銘柄は、年1回更新される。それぞれの時代ごとに活躍している企業に投資ができる点がメリットだ。
本記事を執筆している時点では、1年分のトータルリターンしか確認できないが、優秀な運用成果を残している。
今後も成長が期待できるインデックスファンドだと判断した。
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)の基本情報はこちらだ。
| 基準価額 | 19,349円 |
|---|---|
| 純資産総額 | 144,724百万円 |
| カテゴリ | 国内大型グロース |
| ベンチマーク | 日経平均トータルリターン・インデックス |
| 信託報酬(年率) | 0.143%以内 |
| トータルリターン | ・-2.23%(1か月) ・+0.01%(6か月) ・+15.94%(1年) ・+13.23%(3年) ・+12.35%(5年) |
「eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)」は、日経平均株価の値動きに連動した運用成果を目指すインデックスファンドだ。国内の大型株に分散投資をする。
2025年1月7日時点の日経平均株価は、4万円の心理的節目にある。この心理的節目を突破すれば、更なる上昇が期待できるだろう。
また、eMAXIS Slim 国内株式(日経平均)では、ファーストリテイリングやソフトバンクグループなどの知名度の高い企業に投資をする。
国内の有名企業に分散投資をしたい人におすすめしたい。
iFreeS&P500インデックス
iFreeS&P500インデックスの基本情報は、下記の表を参考にしてほしい。
| 基準価額 | 38,018円 |
|---|---|
| 純資産総額 | 370,275百万円 |
| カテゴリ | 国際株式・北米(F) |
| ベンチマーク | S&P500(配当込み、円換算ベース) |
| 信託報酬(年率) | 0.198% |
| トータルリターン | ・+1.34%(1か月) ・+10.70%(6か月) ・+36.44%(1年) ・+20.88%(3年) ・+22.63%(5年) |
「iFreeS&P500インデックス」は、S&P500の値動きに連動するように設計されたインデックスファンドだ。海外株式や海外REIT、海外投資信託に分散投資をする。
信託報酬は0.198%と低コストである。また、トータルリターンも安定しており、ポートフォリオに組み入れたいインデックスファンドのひとつだ。
たわらノーロード先進国株式
たわらノーロード先進国株式の、基準価額やトータルリターン等をまとめた表はこちらだ。
| 基準価額 | 36,672円 |
|---|---|
| 純資産総額 | 752,819百万円 |
| カテゴリ | 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
| ベンチマーク | MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
| 信託報酬(年率) | 0.09889%以内 |
| トータルリターン | ・+0.60%(1か月) ・+7.73%(6か月) ・+31.71%(1年) ・+19.03%(3年) ・+20.27%(5年) |
「たわらノーロード先進国株式」は、アセットマネジメントOneにより運用されるインデックスファンドだ。
アセットマネジメントOneはアジア最大の資産運用会社であり、多数の運用実績があることから、安心して運用をお任せできる。
また、購入時および売却時に手数料がかからない。さらに、信託報酬も低めに設定されており、低コストで運用できる点は大きなメリットだ。
iFreeNEXT インド株インデックス
iFreeNEXT インド株インデックスの基本情報は、下記の表にまとめてある。
| 基準価額 | 15,148円 |
|---|---|
| 純資産総額 | 149,707百万円 |
| カテゴリ | 国際株式・インド(F) |
| ベンチマーク | Nifty50指数(配当込み、円ベース) |
| 信託報酬(年率) | 0.473% |
| トータルリターン | ・-4.34%(1か月) ・+0.51%(6か月) ・+18.83%(1年) ・-%(3年) ・-%(5年) |
「iFreeNEXT インド株インデックス」は、インドを代表する株価指数である「Nifty50指数」をベンチマークとしているインデックスファンドだ。
このインデックスファンドに投資をすれば、インドの成長企業に分散投資ができる。
インドは急成長を遂げており、今後の世界経済をけん引する国になり得るポテンシャルを秘めている。
今後の成長を期待して、ポートフォリオに組み入れておけば、大きなリターンをもたらしてくれるかもしれない。
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド
SBI・V・全米株式インデックス・ファンドの基本情報は、こちらを参考にしてほしい。
| 基準価額 | 19,683円 |
|---|---|
| 純資産総額 | 318,482百万円 |
| カテゴリ | 国際株式・北米(F) |
| ベンチマーク | CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
| 信託報酬(年率) | 0.0938%程度 |
| トータルリターン | ・+2.15%(1か月) ・+11.57%(6か月) ・+37.14%(1年) ・+19.77%(3年) ・-%(5年) |
「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」は、世界有数の資産運用会社であるバンガード社のETF「VTI」をおもな投資対象としている。
およそ4,000銘柄に分散投資ができるので、リスクを抑えた運用をしたい人におすすめだ。
比較的新しいインデックスファンドなので、5年間のトータルリターンは公表されていない。
しかし、直近3年間のトータルリターンは良好なので、ポートフォリオに組み入れてみてもよいだろう。
インデックスファンドの選び方のポイント
インデックスファンドを選ぶ際は、下記の5つのポイントをチェックしよう。
- 信託報酬の低さ
- 連動する指数(ベンチマーク)の見通し
- 投資対象地域と投資対象資産
- 純資産総額の大きさ
- トータルリターン
信託報酬の低さ
インデックス投資は短期的に大きなリターンを得られる投資手法ではない。そのため、原則として購入してから数年から数十年は運用し続けることとなる。
インデックスファンドの実質的なコストは信託報酬だ。
そのため、長期で保有しても運用成果に大きな影響を与えないためには、信託報酬の低いインデックスファンドを選ぶことが重要だ。
連動する指数(ベンチマーク)の見通し
インデックスファンドは特定の指数の値動きに連動するように設計されている。
将来的に成長が期待できる指数に連動するインデックスファンドを選ばなければ、リターンを得られる可能性が低くなる。
そのため、連動する指数(ベンチマーク)の見通しを立てておくことも欠かせない。
もちろん、指数が成長するかどうか確実なことは誰にも分からない。それでも、投資をする際の判断材料のひとつとしてチェックしておくことが重要だ。
投資対象地域と投資対象資産
それぞれのインデックスファンドは、投資対象地域と投資対象資産に違いがある。
国内の債券に投資をするものもあれば、国内外の株式がを投資対象資産とするものもある。
ここでえ、たとえば国内の株式に投資をするインデックスファンドのみに投資していたとしよう。
日経平均株価等の指数が暴落した場合、運用しているインデックスファンドも大きく値を下げる可能性がある。
このように、特定の投資対象地域と投資対象資産に偏った投資をすると、リスクヘッジができない。
そのため、投資対象地域と投資対象資産のバランスを考えたうえで、投資するインデックスファンドを選ぶようにしよう。
純資産総額の大きさ
純資産総額とは、インデックスファンドに投資されている資金の合計額のことで、そのファンドの規模を示している。
純資産総額が大きいファンドは、多くの投資家から資金を集めていると推測できる。また、繰上償還される心配も少ないので、安心して投資ができるのだ。
ただし、純資産総額の大きさと運用成績は必ずしも比例するわけではない。
純資産総額が小さいながらも好成績を残しているファンドがあれば、反対に純資産総額が大きくてもパフォーマンスがよくないファンドもある点には注意しよう。
トータルリターン
トータルリターンをみれば、特定期間の成績を確認できるため、チェックしておきたいポイントのひとつだ。
長期的にリターンが出ているインデックスファンドであれば、今後も利益を出せる可能性がある。
将来的に同様のリターンを得られる保証はないものの、一定の参考となるだろう。
【実践】インデックスファンドの始め方

インデックスファンドを購入して、資産運用を始めるまでの手順を解説していく。
ステップごとにやるべきことを紹介するので、ぜひ参考にしてほしい。
まずはインデックスファンドの始め方をイメージしやすいように、こちらの図解を見てほしい。
| ステップ1 | ・現状把握:投資に使う余剰資金を計算する ・目標設定:インデックス投資をする目的や運用期間等を明確にする |
|---|---|
| ステップ2 | ・証券口座の選定:複数の証券会社を比較して、自分に合うものを探す ・口座開設:証券口座の口座を開設する |
| ステップ3 | ・インデックスファンドの選定:インデックスファンドの選び方のポイントを参考にして選ぶ ・購入:インデックスファンドを購入する |
ある程度の流れを把握できたら、各ステップの説明に進もう。
現状を把握して目標設定をする
インデックス投資に限った話ではないが、投資は余剰資金でおこなうことが原則だ。
そのため、まずは投資にまわせる余剰資金がいくらあるのかを明確にしておこう。
続いて、具体的な目標設定をする。たとえば、毎月1万円を積立投資して、20年後にすべて売却すると仮定しよう。
リターンの目標設定はむずかしいところだが、年率4.0%程度にしておけば、下回る可能性は低いだろう。
このように具体的な目標を設定すると、購入するインデックスファンドや運用方針などを決めやすくなるのだ。
目標設定する際は、はじめから厳しい条件を決めてしまわないようにするのがポイントだ。
たとえば、余剰資金がない状態で、多額の積立金額を設定するのはよくない。目標を達成するために、余剰資金以外のお金を投資に充ててしまう可能性があるからだ。
無理のない長期投資を続けるためにも、ある程度の余裕がある目標を設定するようにしよう。
取引する証券口座の選定と口座開設をする
インデックスファンドを購入する証券口座を探そう。近年では、インターネットを通じてインデックスファンドの取引ができるネット証券が人気だ。
投資初心者におすすめのネット証券には、SBI証券と楽天証券がある。
SBI証券は、投資信託の取扱銘柄数が多い特徴がある。豊富な商品数の中から自分に合うインデックスファンドを選びたい人におすすめだ。
また、三井住友カードを使った投信積立にも対応している。
使用するクレジットカードや投資するインデックスファンドにもよるが、最大3.0%分のVポイントが貯まるのはうれしいポイントだ。
楽天証券は、セミナー情報や投資情報などの投資情報が豊富だ。投資についての勉強をしながらインデックス投資をしたい人におすすめしたい。
また、楽天証券は楽天グループに属しており、楽天ポイントを貯めやすいメリットがある。クレカ積立をすると、最大2.0%分のポイント還元を受けられる。
インデックスファンドを購入したい証券会社が見つかったら、口座開設手続きに進もう。
マイナンバーカード等のマイナンバー確認書類と、運転免許証等の本人確認書類を用意しておくと、スムーズに手続きができる。
オンラインでの口座開設を選択すれば、最短翌営業日に開設できるネット証券もある。
ただし、申込内容に不備があると、口座開設に時間がかかってしまう。入力内容や提出書類に不備がないように気をつけよう。
インデックスファンドを選び購入する
証券口座の口座開設が完了したら、投資をしたいインデックスファンドを選ぼう。
先述したように、信託報酬の低さや連動する指数の見通しなどのポイントをチェックすると、自分に合うインデックスファンドが見つかりやすい。
インデックスファンドの選定後は、購入に進む。インデックスファンドの購入資金を、証券口座に入金しておこう。
クレカ積立でインデックスファンドを購入する場合、事前入金は必要ない。
インデックスファンドの買付方法や決済方法などを選択して、目論見書の内容をチェックしよう。
目論見書には、購入するインデックスファンドの構成比率や運用方針などが記載されている。
目論見書の内容を理解するのはむずかしいかもしれないが、経験を積んでいくうちに分かるようになる。重要事項が記載されているので、必ず確認しておくこと。
確認画面で設定内容を確認し、間違いがなければ注文を完了させよう。
インデックスファンドを活用した運用のコツ3選

優秀なインデックスファンドを購入するだけで成功できるほど、インデックス投資は甘くない。
インデックス投資を成功させるには、運用のコツを実践することが重要だ。
ここからは、インデックスファンドを活用した運用のコツを3つ解説していく。
インデックスファンドを購入する前に読んでおけば、インデックス投資の成功確率が高まるだろう。
時間を味方につける
指標は、時間をかけてゆっくりと成長するケースが多い。
早いタイミングでインデックスファンドを購入しておけば、市場の成長とともに安定したリターンを得られる可能性が高まる。
時間を味方につけるためにも、長期投資を前提としよう。また、長期投資を続けていると、必ず市場が暴落するタイミングに遭遇する。
市場の暴落を予測することは不可能だ。そのため、一時的に保有しているインデックスファンドが含み損となるケースも考えておく必要がある。
しかし、一時的に市場が暴落したとしても、長期的に見れば回復するケースが多い。短期的な価格変動が起きても、感情に任せて売却しないことが求められる。
はじめから長期投資としてインデックスファンドを購入していれば、慌てることはなくなるだろう。市場変動を乗り越え、長期投資を継続していこう。
ドルコスト平均法を活用して投資タイミングを分散する
投資で利益を出すには、安く買って高く売却すればよい。
しかし、市場の暴落が予想できないように、インデックスファンドを安値で購入できるタイミングを当てられる人はいない。
また、購入する時期によっては、高値掴みをしてしまうこともあるだろう。そこでおすすめしたいのが、ドルコスト平均法を活用する積立投資だ。
「ドルコスト平均法」とは、毎月決まったタイミングにインデックスファンドを一定額購入する方法のことだ。
購入するタイミングを分散することで、購入価格の平準化が期待できる。
また、ドルコスト平均法を活用すれば、インデックスファンドを購入するタイミングについて悩むことがなくなる。感情に左右されず、淡々と積立投資ができるのだ。
さらに、市場が暴落したときは、安値で購入できる。再び市場が上昇トレンドに突入するときは、大きなリターンを得られるだろう。
定期的にポートフォリオを見直す
インデックスファンドを購入してしばらくすると、資産配分の変動が生じる。
値上がりするインデックスファンドもあれば、値下がりするインデックスファンドもあるだろう。
そこで、ポートフォリオを見直して、リバランスをすることが重要だ。「リバランス」とは、ポートフォリオの投資配分比率を見直すことだ。
具体的には、値上がりしたインデックスファンドを売却し、値下がりしているインデックスファンドを購入する。
リバランスをすれば、より安定したリターンを得られる可能性が高まるのだ。
なお、ポートフォリオを見直すタイミングは、1年に1回程度でよい。インデックスファンドを購入したあと、数年以上放置をしないことが重要だ。
インデックスファンドの運用がむずかしければ資産運用の専門家に相談する方法も有効
インデックスファンドを運用するコツを3つ紹介したが、初心者が実行するのはむずかしいだろう。
特に、リバランスをするには、ある程度の知識と経験が必要だ。適切なリバランスができなければ、思うようなリターンを得られない可能性が高まる。
もし「インデックスファンドの運用はむずかしそう」と不安に感じているのであれば、資産運用の専門家に相談する方法も有効だ。
資産運用の専門家は、豊富な知識を有している。資産運用の専門家に相談をすれば、相談内容に応じた的確なアドバイスを受けられるので、心強い味方となるだろう。
インデックス投資を始めるなら「資産運用ナビ」で専門家に相談しよう

インデックス投資を始めるのであれば、資産運用の専門家に相談することをおすすめする。特におすすめしたいサービスが「資産運用ナビ」だ。
ここからは、「資産運用ナビ」とはどのようなサービスなのかを、具体的に解説していく。
資産運用に関する悩みや不安を抱えている人は、ぜひ読み進めてみてほしい。
インデックス投資をする際は資産運用の専門家に相談するのがおすすめ
インデックス投資は、初心者でも取り組みやすい投資手法だ。しかし、投資初心者が銘柄選定やポートフォリオの見直しをするのはハードルが高い。
そこで、銘柄選定やポートフォリオの見直しをする際は、資産運用の専門家に相談することをおすすめしたい。
資産運用の専門家に相談すれば、適切なアドバイスを受けられる。また、気になることを相談することで、不安を取り除きながら運用ができる。
資産運用ナビの概要
「資産運用ナビ」は、資産運用の専門家を紹介してくれるマッチングプラットフォームサービスだ。
いくつかの質問事項に答えるだけで、自分にマッチするアドバイザーを簡単に見つけることができる。
もちろん、「資産運用ナビ」に登録しているアドバイザーはインデックスファンドの運用に関する相談だけではなく、ライフプランの作成や資金のシミュレーションなどに対応している。
そのため、インデックスファンドを含むあなたの資産全体の管理も任せることができるはずだ。
資産運用ナビのメリット
「資産運用ナビ」のメリットには、下記の3つがある。
- 専門家のプロフィールを確認できる
- オンライン相談に対応している
- 無料相談が利用できる
「資産運用ナビ」の公式サイトでは、紹介される専門家のプロフィールを確認できる。
業務概要や担当顧客層などが詳しく記載されているので、自分に合うアドバイザーを見つけやすい。
気になるアドバイザーがいれば、自己紹介などを確認してみるとよいだろう。
また、「資産運用ナビ」には、WEB面談に対応しているアドバイザーも在籍している。
WEB面談を利用すれば、地方に住んでいる人も、東京で相談業務をおこなっているアドバイザーに相談できるのだ。
プロフィール欄に「WEB面談対応」という項目があるので、WEB面談を希望している人はチェックしてみよう。
そして、「資産運用ナビ」からの相談はすべて無料だ。自分に合うアドバイザーが見つかるまで、無料で繰り返し相談ができるのは大きなメリットだろう。
資産運用ナビの活用法
「資産運用ナビ」を活用したい人は、下記の2つの活用法を試してみることをおすすめする。
- おすすめのインデックスファンドを教えてもらい、銘柄を選ぶ手間と時間を削減する
- 投資に関する不安や疑問があるときはすぐに相談する
投資するインデックスファンドを調べるのは大変だ。信託報酬や投資対象地域などの条件を比較して、自分に合うインデックスファンドを見つけなければならない。
そのため、仕事や育児などに追われている人は、なかなか時間がとれないだろう。
そこで、インデックス投資を始める際におすすめのインデックスファンドを教えてもらえば、すぐに資産運用を始められる。
また、運用期間が長くなれば、安定したリターンを得られる可能性が高まる。
インデックス投資をすぐに始めたい人は、アドバイザーに銘柄相談をしてみよう。長期投資を続けるのは意外とむずかしい。
「このインデックスファンドを保有し続けてもよいのだろうか」「この暴落から回復するのはいつになるのだろうか」など、さまざまな不安が押し寄せてくる。
自信を持って投資を続けられないと、大きなストレスとなるのだ。アドバイザーに相談をすることで、投資に関する不安や疑問を解消できる。
また、アドバイザーにはインデックス投資以外の相談も可能だ。
資産運用について相談に乗ってもらいたいことがあれば、アドバイザーに話してみよう。最適なアドバイスを受けられるはずだ。
「資産運用ナビ」を利用して、自分に合うアドバイザーを探してみよう。
インデックスファンドとは指数の値動きに連動した運用成果を目指す投資信託のこと

インデックスファンドは、投資初心者でも挑戦しやすいおすすめの手法だ。
事前に投資計画を立ててから、投資したいインデックスファンドの取り扱いがある証券会社の口座を開設して取引をしてみよう。
インデックスファンドに投資をする際は、長期投資を前提として積立投資をするとよい。時間分散が可能となるドルコスト平均法を活用してみよう。
ただし、インデックスファンドの種類は非常に多く、投資初心者が銘柄選定をするのはむずかしい。
銘柄選定やインデックスファンドの運用に不安があれば、資産運用の専門家に相談する方法も有効だ。
資産運用の専門家に相談しながら投資をすることで、より効率的な運用が可能となる。
資産運用の専門家を紹介するサービスのひとつが「資産運用ナビ」だ。
「資産運用ナビ」では専門家のプロフィールを確認できるので、自分に合うアドバイザーを見つけやすい。
また、オンライン相談に対応しており、場所を問わずに相談できる点がメリットだ。
「資産運用ナビ」の相談料は無料だ。インデックスファンドの運用に不安を覚えている人は、「資産運用ナビ」を利用してみてはいかがだろうか。
インデックス投資のメリット・デメリットに関するQ&A