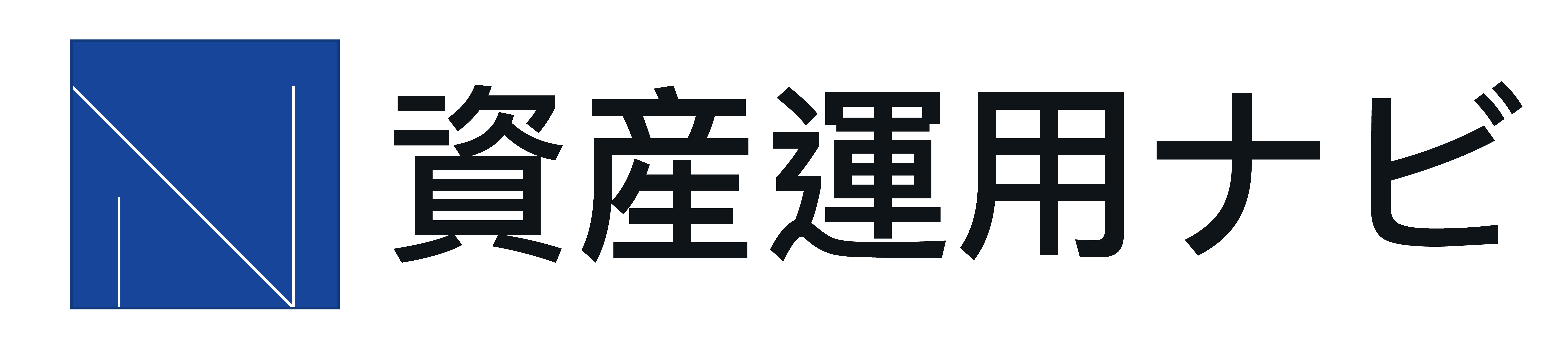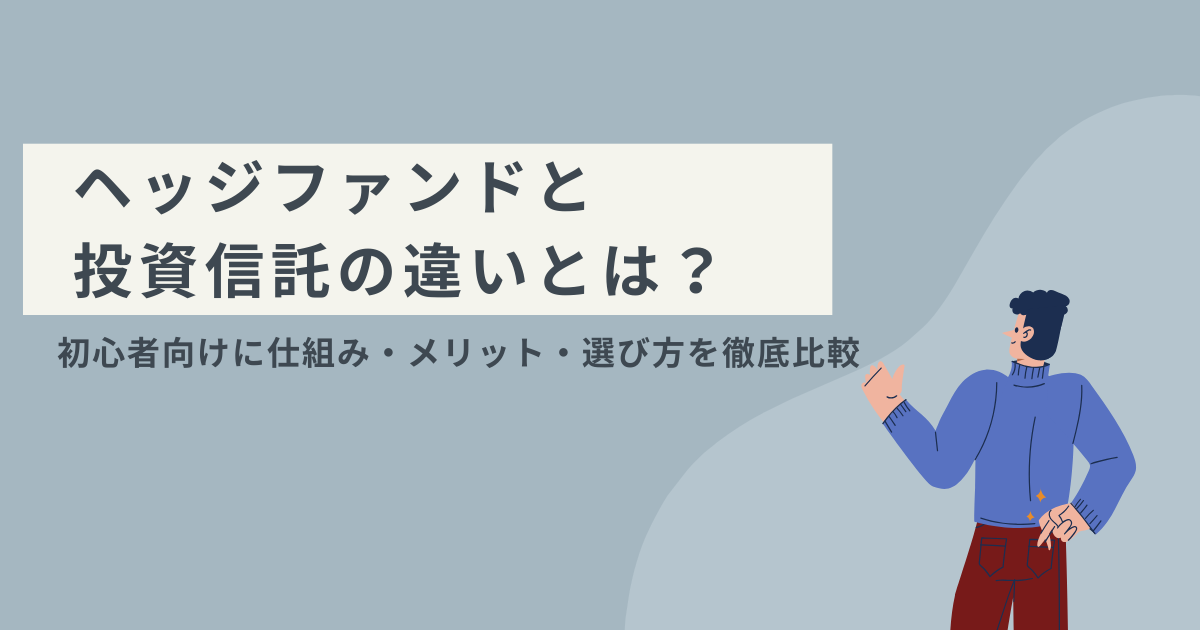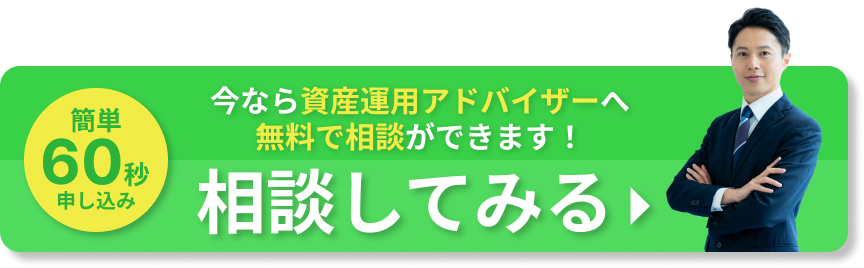- ヘッジファンドと投資信託の違いが知りたい
- それぞれどのような投資家におすすめなのか知りたい
- ヘッジファンドと投資信託の運用方法が知りたい
富裕層をターゲットとしたヘッジファンドは、しばしば投資信託と混同されることが多い。
自分の投資意向に合った運用先を見つけるためには、類似している金融商品の違いをしっかりと理解しておくことが大切だ。
本記事では、ヘッジファンドと投資信託の違いやそれぞれ向いている人、購入方法について解説していく。
ヘッジファンドと投資信託の違い

ヘッジファンドと投資信託には、主に次のような点に違いがある。
- 募集方法
- 最低投資金額
- 運用対象
- 手数料
それぞれくわしく解説していこう。
ヘッジファンドと投資信託は募集方法が違う
ヘッジファンドと投資信託で大きく異なるのが、募集方法についてだ。ヘッジファンドは私募によって募集され、一定以上の資産を持つ富裕層を中心に、限られた人にのみ案内が行われる。
勧誘には条件が定められており、一般の投資家には購入の機会が限られていることが特徴だ。
一方、投資信託は公募によって募集され、基本的には証券口座を持つ人であれば誰でも購入することができる。
オープン型の投資信託であればいつでも購入できるので、さまざまな投資家が気軽に購入しやすいといえる。
ヘッジファンドと投資信託は最低投資金額が違う
ヘッジファンドと投資信託は、最低投資金額も大きく異なる。ヘッジファンドは少数の投資家を対象に募集が行われるため、最低投資金額が高く設定されている。
具体的な金額はファンドによって異なるものの、500万〜1,000万円ほどで設定されることが一般的だ。
一方、投資信託は少額投資から始めることができる。スポット購入の際は1万円から購入できることが多く、積立投資になると100円から購入できる証券会社もある。
少額から投資できるので、投資経験がない人でもチャレンジしやすいことが特徴だ。
ヘッジファンドと投資信託は運用対象が違う
運用対象も押さえておきたいポイントだ。ヘッジファンドは、株式や債券などの現物取引に加えて、先物取引や信用取引を取り入れて運用を行う。
これにより、金融市場が下降局面に入ったときでも利益を追求することができる。
「ヘッジ」とついているのはこのためで、下落局面でのリスクをヘッジ(回避)することで、下落相場でも利益を狙えることが特徴だ。
一方、投資信託は株式や債券などの伝統的資産で運用を行う。中にはデリバティブ取引を用いて運用を行うものもあるが、大多数は現物取引で運用するファンドとなっている。
そのため、ヘッジファンドと違って、投資信託は市場が上昇局面にあるときのみ利益を享受することができる。
下降局面に入ったときは、基準価額が下がり続けることを理解しておこう。
ヘッジファンドと投資信託は手数料が違う
資産運用を行うときは、手数料も必ずチェックしておきたいポイントだ。ヘッジファンドでは、主に「管理手数料」と「成功報酬」の2種類の手数料がかかる。
管理手数料はファンドの運用にかかる手数料で、2%程度で設定されることが多い。
成功報酬は運用益の中から徴収される手数料で、運用益が出ているときのみ発生する仕組みとなっている。
また、ファンドによっては購入手数料や解約手数料がかかることもある。一方、投資信託では「購入時手数料」と「信託報酬」が主な手数料だ。
購入時手数料は購入時にかかるコストで、最近は無料化している金融機関も多い。信託報酬はファンドの運用・管理にかかる手数料で、ファンドによって料率が異なる。
また、ファンドによっては「信託財産留保額」といって解約時に手数料がかかることもある。
手数料については、一般的にヘッジファンドの方が高くなりやすい。購入する際は、必ずどれくらいの手数料がかかるかよく確認するようにしよう。
ヘッジファンドと投資信託のメリット・デメリットに違いはある?

ヘッジファンドと投資信託にはそれぞれメリット・デメリットがある。投資する際は、それぞれの特徴を理解したうえで投資先を選定することが重要だ。
ここからは、ヘッジファンドと投資信託のメリット・デメリットを比較してみよう。
ヘッジファンドのメリット・デメリット
ヘッジファンドのメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 下落相場でも利益を狙える プロに運用を任せられる 幅広い金融商品に分散投資できる | コストが高い 投資のハードルが高い |
ヘッジファンドは、信用取引や先物取引を用いることで下落相場でも利益を追求することができる。
投資先もプロが選定してくれるので、投資に手間をかけたくない人にとってはメリットが大きい。
また、投資信託に比べて投資先の対象が幅広いのも特徴だ。
一方、投資にまとまった金額が必要となることや、限られた投資家のみに募集されることから、投資のハードルが高いのがヘッジファンドのデメリットである。
また、解約についても制限があり、解約日の45日前までに申し出なければならない「45日ルール」が導入されているファンドが多い。
ヘッジファンドに投資する際は、運用にかかるコストやリスクをよく理解しておく必要があるだろう。
投資信託のメリット・デメリット
投資信託のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 少額投資から始められる プロに運用を任せられる いつでも解約できる | 上昇局面でしか利益を狙えない 投資先が伝統的資産のみ |
投資信託の最大のメリットは少額投資から始められることだ。これにより、投資経験が浅い人でも気軽にチャレンジすることができる。
また、毎月一定額を積み立てていく積立投資にも利用できるので、まとまった投資資金がない人にはおすすめの金融商品と言える。
加えて、投資信託は基本的にいつでも解約できるので、資金の拘束性が低いことも特徴である。
一方、投資信託は株式や債券などの現物取引をメインに運用するため、上昇局面でしか利益を狙えない。
下落相場に入ったときは含み損が続くことをあらかじめ留意しておこう。
ヘッジファンドは下落相場でも利益を狙いたい投資家におすすめ

ここまで、ヘッジファンドのメリットやデメリットについて解説してきた。では、ヘッジファンドはどのような投資家におすすめの金融商品なのだろうか。
ここからは、ヘッジファンドはどのような目的を持った投資家におすすめの運用法なのかについて解説していく。
また、ヘッジファンドに投資をするための具体的な方法についても言及していくので、ぜひ参考にしてほしい。
ヘッジファンドをおすすめする投資家の特徴
ヘッジファンドをおすすめする投資家の特徴には、下記の3つがある。
- 下落相場でも利益を狙いたい
- 運用をプロに任せたい
- 柔軟なポートフォリオを構築したい
ヘッジファンドは株式や債券のほかに、先物取引や信用取引なども組み合わせて利益を追求する金融商品だ。
市場の雰囲気が悪く、下落相場に突入したとしても、買いと売りを混ぜながら運用することで利益を出すことが可能だ。
ヘッジファンドの運用は、専門的な知識を有しているプロがおこなう。投資に関する知識がなくても、安心して始められる。
また、プロは常に相場に関する最新情報を収集している。そのため、投資家は本業に集中できるのだ。
相場情報をチェックする時間がない人も、ヘッジファンドの運用が適していると判断できる。
ヘッジファンドをポートフォリオに組み入れることで、投資する金融商品の分散が可能となる。
リスクをおさえながら運用ができるため、投資元本を毀損する確率を下げられるのだ。
相場に関係なく運用できるポートフォリオを構築したい人は、ヘッジファンドへの投資を検討するとよいだろう。
ヘッジファンドに投資する方法
ヘッジファンドは、一般的な投資信託の購入方法と異なる点に注意が必要だ。
ヘッジファンドへの投資に興味を持っている人は、下記の3つの投資方法を検討してみてほしい。
- 証券会社を経由する
- プライベートバンクを経由する
- IFAなどの資産運用の専門家にアドバイスをもらいながら運用する
国内の証券会社を経由すれば、ヘッジファンドに投資ができる。
証券会社を経由してヘッジファンドに投資をする場合、和製ヘッジファンドもしくは輸入ヘッジファンドのどちらかを選択しよう。
「輸入ヘッジファンド」は、海外のヘッジファンドを投資信託のような形式として販売している。
輸入ヘッジファンドは比較的少額から投資ができるので、ヘッジファンドの購入が初めての人におすすめしたい。
「和製ヘッジファンド」とは、ヘッジファンド型投信のことだ。相場状況に関係なく利益を狙える投資商品となっている。
手元資金に余裕がある人は、プライベートバンクを経由してヘッジファンドの購入ができる。
最低投資金額が高額ではあるものの、顧客のニーズに合う柔軟な対応をするのがメリットだ。
IFAなどの資産運用の専門家にサポートを依頼して、ヘッジファンドに直接投資をする方法もある。
IFAは、中立的な立場からアドバイスをする資産運用の専門家だ。投資家は顧客目線のアドバイスを受けられるため、信頼性が高い点が大きなメリットだ。
自分に合うIFAを探している人におすすめしたいのが「資産運用ナビ」
「IFAに相談したいと考えているものの、探し方が分からない」と悩んでいる人は多くいる。日本ではIFAの知名度が低いため、仕方がないことだろう。
もしIFAに相談したいのであれば「資産運用ナビ」の利用をおすすめする。「資産運用ナビ」は、自分に合うアドバイザーを簡単に探せるサービスだ。
相談内容や年齢などを入力すれば、自分に合うアドバイザーを紹介してもらえる。相談料もかからないので、気軽に相談できるのはうれしいポイントだ。
「資産運用ナビ」を利用して、アドバイザー選びをしてみてはいかがだろうか。
ヘッジファンドに似た特徴をもつ投資信託もある

ヘッジファンドの購入はハードルが高いと考えている人は、ヘッジファンドに似た特徴をもつ投資信託を選択する方法も有効だ。
ここからは、ヘッジファンドに似ている投資信託の具体例や、運用するポイントについて解説していく。
ヘッジファンドに似た投資信託に投資をする方法も有効
ヘッジファンドに投資をするには、潤沢な資金が必要だ。また、コストの高さがネックとなっているケースも考えられるだろう。
しかし、ヘッジファンドに似た投資信託も存在する。投資信託であれば少額から購入できるため、チャレンジしやすい。
ヘッジファンドに似た投資信託の一例
ヘッジファンドに似た投資信託の一例を紹介していく。
SBI-Man リキッド・トレンド・ファンドの基本情報は、こちらにまとめてある。
| 基準価額 | 11,252円 |
|---|---|
| 純資産総額 | 17,158百万円 |
| カテゴリ | ヘッジファンド |
| ベンチマーク | なし |
| 信託報酬(年率) | 0.998%程度 |
| トータルリターン | ・+6.20%(1か月) ・-%(6か月) ・-%(1年) ・-%(3年) ・-%(5年) |
「SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド」は、世界各国の株価指数や債券、コモディティなどを投資対象としている投資信託だ。
買い戦略だけではなく、売り戦略も組み合わせることで、さまざまな相場状況でも利益を狙える投資信託となっている。
SBI-Man リキッド・トレンド・ファンドは「SBI」とあるように、SBI証券専用の投資信託だ。
当ファンドに興味がある人は、事前にSBI証券の口座を開設しておこう。
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の基本情報はこちらだ。
| 基準価額 | 8,318円 |
|---|---|
| 純資産総額 | 406百万円 |
| カテゴリ | ヘッジファンド |
| ベンチマーク | なし |
| 信託報酬(年率) | 1.21%±0.2%程度 |
| トータルリターン | ・+2.19%(1か月) ・+5.50%(6か月) ・+15.82%(1年) ・+5.54%(3年) ・+5.59%(5年) |
「ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1」は、複数の投資信託証券に投資する投資信託だ。
投資元本のリターンを追求する「絶対収益追求型」で運用する特徴がある。
投資信託証券へ分散投資をすることで、リスクをおさえつつ安定したリターンを狙う戦略となっている。
トータルリターンを見ても安定した成績を残しており、投資妙味があると判断した。
投資信託の相談先も「資産運用ナビ」で探せる
ヘッジファンド型投信の一例を紹介したが、ほかにも投資対象の銘柄はある。自分に合うヘッジファンド型投信を見つけるのは大変だ。
もしヘッジファンド型投信選びに迷ったときも、「資産運用ナビ」の利用をおすすめする。
「資産運用ナビ」で信頼できるアドバイザーを見つけられれば、銘柄選びや運用についての具体的なアドバイスを受けられる。
また、疑問点や不明点を相談することで、不安を取り除きながら運用できるのはメリットだ。
投資信託の悩みも、アドバイザーに相談してみよう。
ヘッジファンドと投資信託の違いを理解すれば自分に合う投資商品を見つけられる

ヘッジファンドと投資信託には、募集方法や最低投資金額などに違いがある。
| ヘッジファンド | 投資信託 | |
|---|---|---|
| 募集方法 | 私募 | 公募 |
| 最低投資金額 | 100円~1万円 | 500万円〜1,000万円 |
| 運用対象 | 株式や債券などの現物取引や先物取引、信用取引などを組み合わせる | 株式や債券などの伝統的資産 |
| 手数料 | ・管理手数料 ・成功報酬 | ・購入時手数料 ・信託報酬 ・信託財産留保額 |
それぞれの違いを正しく認識し、投資目的やリスク許容度に応じて自分に合う投資商品を選ぶことが重要だ。
もしヘッジファンドへの投資がむずかしいと感じているのであれば、似ている特徴がある投資信託を選ぶ方法も有効だ。
ヘッジファンドや投資信託の運用に悩みや心配がある人は、IFAなどの資産運用のプロに相談してみよう。
IFAは、中立的な立場からアドバイスする資産運用のプロだ。IFAに相談すると、商品選びや運用に関する助言を受けられるので、安心しながら投資を続けられるのがメリットだ。
「資産運用ナビ」を利用すれば、投資家と相性のよいアドバイザーを紹介してもらえる。
相談は無料となっているので、まずは自分が抱えている悩みを相談してみることをおすすめする。
ヘッジファンドと投資信託の違いに関するQ&A