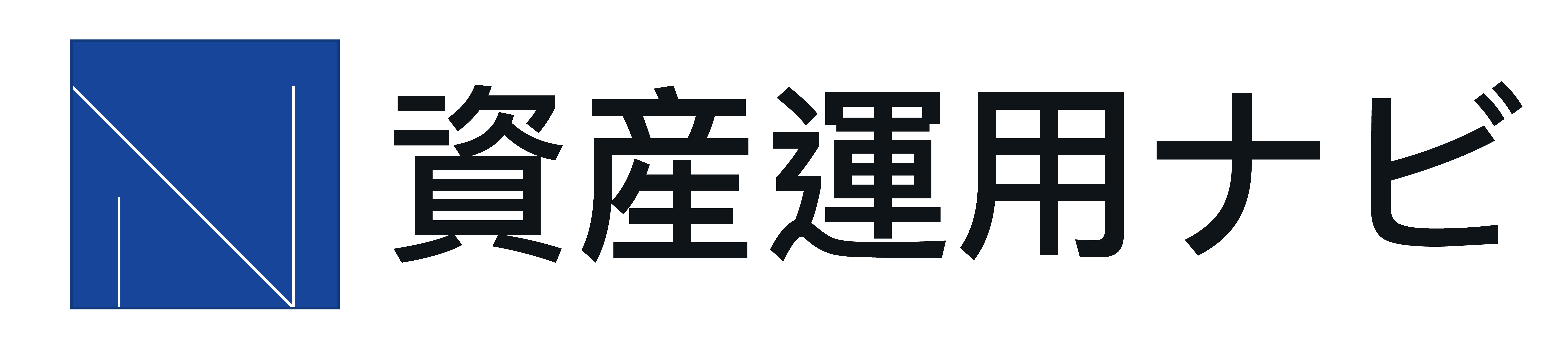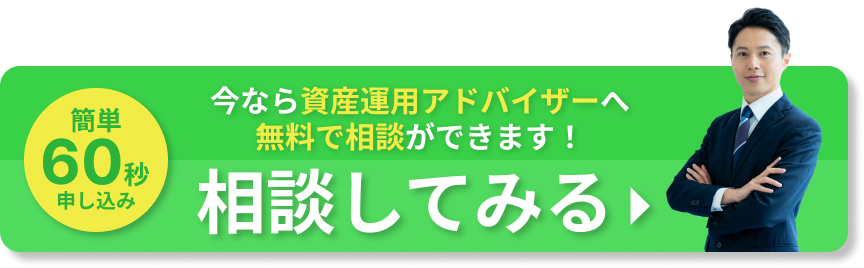- 自分に適したヘッジファンドを選びたい
- ヘッジファンドがどんなものか知りたい
- おすすめのファンドが知りたい
投資信託は、投資家から集めたお金を一つの大きな資金としてまとめて、運用のプロが株や債券などに投資を行う仕組みの金融商品だ。
ヘッジファンドとは、さまざまな取引手法を駆使して、市場の動向に左右されずに一定の利益を目指すファンドのことだ。
本記事では、そもそもヘッジファンドとはどのような仕組みのファンドなのかを詳しく解説しつつ、ヘッジファンドの選び方やおすすめのヘッジファンドについて紹介していく。
ヘッジファンドへの投資に興味のある方は、ぜひ参考にしてみてほしい。
ヘッジファンド選び前に!知っておくべき基礎知識

まずは、そもそもヘッジファンドとはどのような仕組みの運用商品なのか、ヘッジファンドで用いられる運用戦略、メリット・デメリットについて確認していこう。
ヘッジファンドの仕組みや他のファンドとの違い
ヘッジファンドとは、投資家から集めた資金をさまざまな資産に投資して、収益を得ることを目指す投資ファンドのことだ。
「ヘッジ(hedge)」は日本語で「避ける」という意味で、相場が下落したときに資産の目減りを防ぐといった意味から用いられている。
一般的な投資信託とは、相場が上昇または下落のどちらかに動いたときのみ利益が生じる仕組みになっているものがほとんどだ。
しかし、ヘッジファンドの場合は比較的柔軟な運用が可能なため、先物取引や信用取引を活用して、相場の上昇・下落にかかわらずリターンを得られるという特徴がある。
変動する相場に対して運用リスクをヘッジしながらも、積極的にリターンを狙っていくというスタンスが一般的だ。
一般的な投資信託は「公募投信」と呼ばれ、一般投資家にも広く販売されるが、ヘッジファンドは「私募投信」といって一定の条件を満たす限られた投資家のみが投資できるファンドだ。
ヘッジファンドを購入できる投資家は適格投資家と言われ、一定以上の資産や投資経験を有する投資家が対象となる。
ヘッジファンドの投資戦略の種類
ヘッジファンドでよく用いられる投資戦略には、下記のようなものがある。
- マーケット・ニュートラル戦略
- バリュー株投資
- アクティビスト投資
- 株式ロング・ショート戦略
- グローバルマクロ戦略
マーケット・ニュートラル戦略は、割安株を購入して割高株を売却するという、株式の買いと売りを組み合わせる戦略だ。
株価動向によらずに安定的にリターンを狙えるのが特徴といえる。
バリュー株投資は、本来の企業価値より割安に放置されている銘柄を選定して購入する投資方法だ。
企業本来の価値まで株価が上昇したタイミングで売却して、利益を確定する。
株価が安いタイミングで購入するため、比較的リスクを抑えた運用となりやすい。
アクティビスト投資とは、一定の株式を取得して、投資先の企業の経営に積極的に助言を行なって株式の価値を高める投資戦略だ。
通常の運用と異なり、自ら株価を上げるために企業に働きかけるのが特徴的だ。
株式ロング・ショート戦略とは、株式の買い(ロング)と売り(ショート)を同時に保有する運用手法のことだ。
上昇が期待できる銘柄を買い、下落が見込まれる銘柄を売ることで、両建てのポジションを構築する。
株式市場全体の上昇・下落に左右されにくいという特徴がある。
グローバルマクロ戦略とは、さまざまな国や地域のマクロ経済指標や社会情勢などを総合的に分析して、株式や債券、為替などさまざまな資産への影響を考慮して投資する運用手法のことだ。
個別の企業の分析ではなく、マクロ経済の動向から投資判断を下すというのが特徴的だ。
運用成果を上げるためには、高度な分析力やリスク管理能力が求められる。
このように、ヘッジファンドが用いる投資戦略にはさまざまな種類がある。
このほかに、ヘッジファンド独自の運用戦略によって運用方針が決められる場合や、複数の投資戦略を組み合わせて運用が行われる場合もある。
ヘッジファンドのメリット・デメリット
ヘッジファンドの大きなメリットは、専門家に運用を任せられる点だ。
投資家の代わりにプロが運用を行うため、忙しくて運用に避ける時間がない方や、投資に関する知識に自信のない方も気軽に運用を始めやすい。
一般の投資家では得にくい情報をもとにハイレベルな分析を行うため、相場の分析や銘柄選定が面倒だと感じる方にも適しているだろう。
また、ヘッジファンドは一般的な投資信託と異なり、相場の上昇・下落のどちらでもリターンを狙える可能性がある。
リスクヘッジを行いながら長期的に安定したリターンを得たいという方にとっても、魅力的な運用手法といえるだろう。
一方、ヘッジファンドは運用期間が決まっていたり、解約時期や金額に制限があったりするため、資金を必要なタイミングですぐに現金化できない可能性がある。
広く取引される公募投信に比べて、流動性が劣る点はデメリットと言える。
また、出資できる投資家が限定されているため、金融資産や投資経験によっては希望するヘッジファンドに出資できない場合もある。
投資方針や投資戦略が詳細に公開されないケースも多々あるため、上級者向けの運用方法とも捉えられる。

ヘッジファンドの選び方

ヘッジファンドへの投資を考える際に、いくつか注意したいポイントがある。
以下では、最低投資金額、運用実績、投資戦略の3つの観点から選び方を紹介する。
ヘッジファンドの最低投資金額で選ぶ
まずは、最低投資金額がどのくらいかを確認しよう。
最低投資金額は運用先によって異なるが、数百万円程度から投資できるものもあれば、数億円程度ないと運用できないものもある。
自分の投資可能な金額を考慮した上で、ヘッジファンドを選ぶのも重要だ。
ヘッジファンドの運用実績で選ぶ
ヘッジファンドへの投資を検討する際は、必ず過去の運用実績をチェックしよう。
特に、長期にわたってしっかりと実績をあげているかが重要だ。
直近1〜2年だけでなく、5年・10年という長いスパンでの運用実績も確認しよう。
短期的に運用実績が良かったとしても、長期的に見るとあまり運用実績が芳しくない場合もあるため、複数の期間で運用パフォーマンスをチェックするのをおすすめする。
しかし、ヘッジファンドは十分に情報公開が行われていないケースも多いため注意が必要だ。
運用実績を詳しく確認したいヘッジファンドについては、直接連絡して運用実績を問い合わせるのも一つの手だ。
ヘッジファンドの投資戦略で選ぶ
ヘッジファンドの投資戦略や運用方針にも注目しよう。
ヘッジファンドによって取り入れている戦略や得意とする戦略が異なるため、自分の希望する投資戦略からヘッジファンドを選ぶのもおすすめだ。
投資戦略には先述の通りさまざまな種類があるため、それぞれの運用戦略を理解した上で、自分の運用ニーズやリスク許容度に併せたものを選ぶのが重要だ。
選び方を習得したら!おすすめのヘッジファンドから自分に合ったものを探してみよう

続いて、戦略の違いを踏まえて、おすすめのヘッジファンドをいくつか紹介する。
各ヘッジファンドで主に採用されている投資戦略と方針は下記の通りだ。ヘッジファンドと言っても採用している運用戦略と方針は様々だ。
| ヘッジファンド名 | 運用戦略・方針 |
|---|---|
| ストラテジックキャピタル | アクティビスト型 |
| ハヤテインベストメント | ロングショート戦略 |
| GCIアセット・マネジメント | 絶対収益戦略でベンチマークにとらわれない多様な戦略 |
以下では、それぞれヘッジファンドがどのような運用ニーズに適しているかもあわせて紹介していく。
ただし、ヘッジファンドは性質上、投資家が限定された私募投資信託で勧誘・販売自体を行っていないことも多いため注意してほしい。
アクティビスト運用なら:ストラテジックキャピタル
ストラテジックキャピタルは元村上ファンドの幹部、丸木強氏が2012年に設立したヘッジファンドだ。
村上ファンドと言えば「物言う株主」として企業に対して問題を指摘したり提案したりするアクティビストの象徴だ。
ストラテジックキャピタルも同様にアクティビスト型のファンドだ。
公式サイトの運用方針の中に「企業が持つ潜在的な価値を顕在化させる」とあるが、顕在化させる際に企業への情報開示や提案を行う。
具体的な活動はストラテジックキャピタルのプレスリリースを追うと確認できる。
例えば2025年1月には、スマホゲームやMMORPGで有名なガンホーに報酬ガバナンスや資本政策などの問題点の追求などを株主総会で実施することを公表している。
同ファンドのプレスリリースを追えばアクティビストがどのようなことをしているのかを理解しやすいはずだ。
割安に放置されている株を買い対話や権利行使などで「企業が持つ潜在的な価値」を向上させることで、結果的にファンドの保有する株価も上昇する。
- 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2786号
- 出典:ストラテジックキャピタル
ロングショートなら:ハヤテインベストメント
ハヤテインベストメントは杉原 行洋氏が2005年に設立したヘッジファンドだ。
代表の杉原 行洋氏は外資系投資銀行のゴールドマンサックス出身で、27歳の若さで同ファンドを設立。
日本株のロング・ショート戦略を得意とするファンドとして注目されてきた。
ロングは買い持ち、ショートは売り持ちで、市況が上昇局面でも下落局面でも絶対的なリターンを追求する戦略だ。
一般的な投資信託だと投資対象はどうであれロング中心の戦略のため、下げ相場では運用成績を振るわないが、絶対リターンを追求するヘッジファンドなら下落局面でもリターンを高められる可能性がある。
The Eurekahedge Asian Hedge Fund Award 2018ではハヤテインベストメントのロングショート戦略のファンドは、最優秀の日本ヘッジファンドとして高い評価を受けた実績がある。
現在は静岡県の野球の球団運営や人工知能、バイタルテック事業などヘッジファンドだけにとどまらない起業家、研究開発集団としての活動も注目されている。
- 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第963号
- 出典:ハヤテグループ
個人向け投資信託もある:GCIアセット・マネジメント
GCIアセット・マネジメントは2000年に山内 英貴氏が設立したヘッジファンドだ。
代表は日本興業銀行に入行し、為替、デリバティブ関連業務に従事した経歴で『オルタナティブ投資入門-ヘッジファンドのすべて』などの金融関係の著書もある。
運用戦略は個別株のリサーチをメインにしたボトムアップではなく、主にマクロ市場、マクロ経済全体を分析したトップダウン型の運用戦略を主としている。
公式サイトによれば日本ハイブリッド戦略、グローバルマルチ戦略、システマティック・マクロ戦略など多様な戦略を扱う。
また、市況に左右されない市場に即したリスク管理、学会との交流を通じた最先端のリスク分析、管理法、イベントリスクに強いポートフォリオ構成によって安定的なリターンを目指す。
受賞歴も豊富だ。例えば個人投資家向けの投資信託「GCIエンダウメントファンド(成長型)」は2019年「一億人の投信大賞」3位を受賞。
この投資信託はネット証券でも購入できる。
ヘッジファンドへの投資はハードルが高く、個別に問い合わせをしたり、紹介されたりしなければ投資自体が難しいこともあるが、個人投資家にも手が届きやすい、このような商品もあるので参考にしてほしい。
- 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第436号
- 出典:GCIアセット・マネジメント
ヘッジファンドの選び方や運用の相談は誰にするべき?

ヘッジファンドでの運用を検討する際は、資産運用の専門家に相談するのがおすすめだ。
以下で、専門家に相談すべき理由や、おすすめの相談先について解説する。
ヘッジファンドを活用した資産運用における専門家の重要性
ヘッジファンドへの投資を検討する際は、運用の専門家に相談してみよう。
ヘッジファンドは限られた投資家を対象とするもので、ファンドによって活用する戦略やリスク・リターンの度合いは全く異なる。
自分の運用ニーズに適した運用先かを見極める場合には、専門家の助言も必要となるだろう。
また、人によってはヘッジファンドのような私募投信ではなく、インデックスファンドなどの公募投信の方が運用目的に合致しているケースもあるだろう。
具体的にどのような運用商品が自分に向いているかを把握するためにも、まずは資産運用の専門家への相談がおすすめだ。
IFAの役割とメリット
ヘッジファンドについて相談したい、自分に合った運用商品を知りたい、といったニーズをお持ちの方は、ぜひIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に相談してみよう。
IFAは、銀行や証券会社といった金融機関から独立して、金融商品に関する助言や提案を行う資産運用の専門家だ。
特定の金融機関に属していないため、会社の営業方針や販売ノルマに左右されず、顧客に寄り添ったアドバイスが期待できるというメリットがある。
会社都合の転勤なども原則として発生しないため、長期的に長く信頼関係を築けるのも特徴だ。
資産運用全般の相談に対応してくれる専門家を探すなら、ぜひIFAへの相談を検討してみよう。
IFA検索サービス「資産運用ナビ」の活用法
IFAへの相談を検討する際は、自分に適したアドバイザー選びが重要となる。
しかし、自分に適したアドバイザーとは具体的にどういったものなのか、なかなかイメージがつかない人も多いだろう。
そのような方は、IFA検索サービス「資産運用ナビ」を利用することで、手軽に自分に適したアドバイザーを選べる。
住まいや年齢、運用ニーズなどを画面の指示にしたがって入力するだけで、全国のIFAデータベースから自分に最適なアドバイザーが検索される仕組みだ。
IFAの検索から相談まですべて無料で利用できるため、複数のアドバイザーと会ってみて、最も自分に合うと感じたアドバイザーに資産運用を任せる、といった使い方もできるだろう。
自分にぴったりのアドバイザーを探したいという方は、ぜひ「資産運用ナビ」を活用してみてはいかがだろうか。
ヘッジファンドは運用目的やリスクを再確認してから選ぼう

ヘッジファンドは、さまざまな運用商品や投資戦略を駆使して、市場の動向に関わらず絶対的なリターン追求を目指す私募の投資ファンドだ。
さまざまな投資家に広く販売されているインデックスファンドなどの公募投信とは異なり、投資できる金額や投資家の金融資産などに一定の制限が設けられている。
ヘッジファンドへの投資を検討する際は、投資戦略や最低投資金額、運用実績などのポイントをしっかりと確認し、自分の運用ニーズに適しているかを判断しよう。
本記事では、具体的なおすすめヘッジファンドもいくつか紹介したが、これらはあくまで一例であり、実際の運用の最適解は人によって異なる。
そのため、自分に適した運用方法を知りたい場合は、資産運用の専門家からアドバイスを受けるのがおすすめだ。
IFAは、中立的な立場からあなたに最適なアドバイスを長期にわたって提供してくれるというメリットがある。
IFA検索サービス「資産運用ナビ」を活用して、あなたに適したIFAを探してみよう。
ヘッジファンドの選び方に関するQ&A