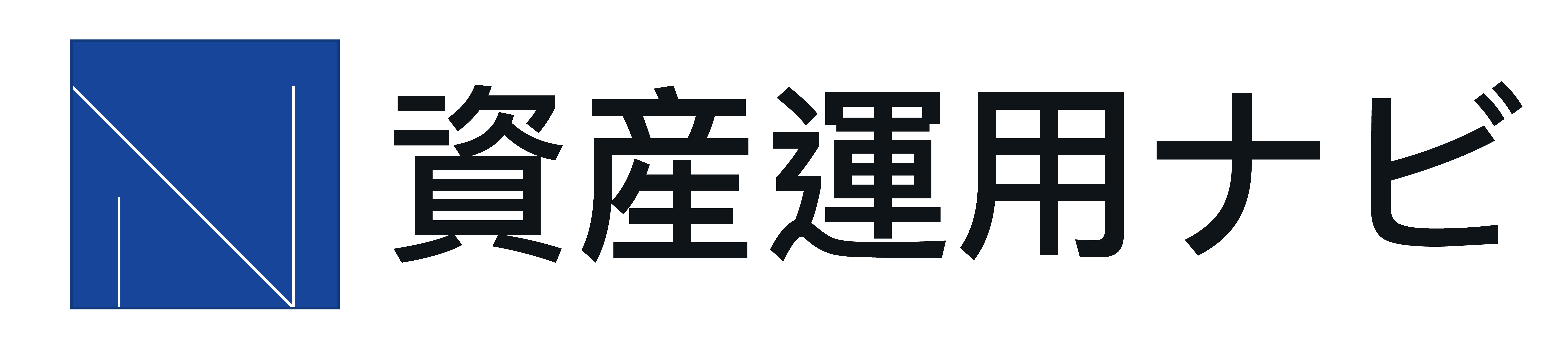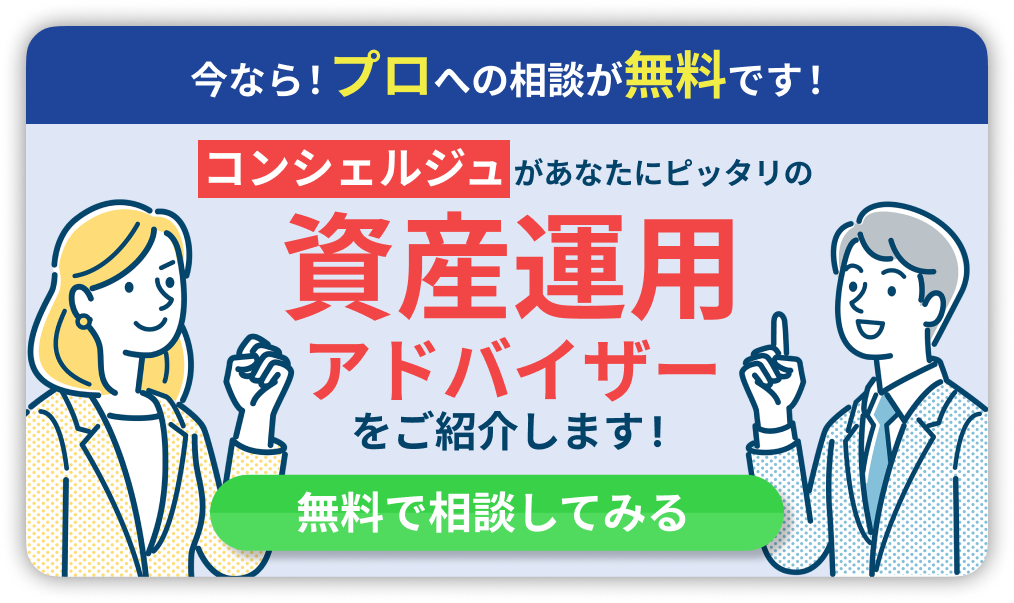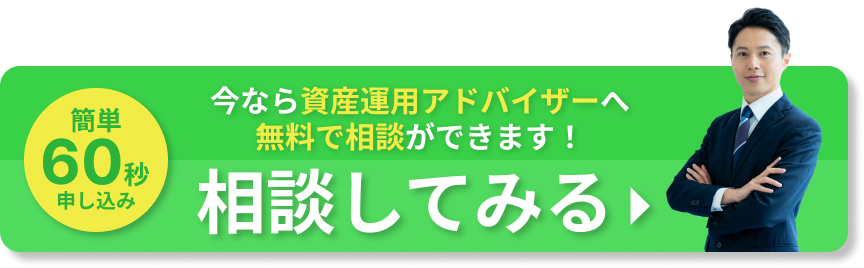- 積立投資におすすめの銘柄やその選び方が知りたい
- 積立投資の上手な活用法が知りたい
- 新NISAにおすすめのつみたてファンドが知りたい
「どの商品を選択すれば良いかわからない」「積立投資におすすめの運用法はある?」
積立投資を始めようか検討している方の中には、このような疑問や不安を感じている方もいるのではないだろうか。
そこで本記事では、積立投資に関する基本情報やおすすめの運用法、商品選びのポイントについて解説していく。
また、新NISAとiDeCoの使い分け方や積立投資を成功させるためのポイントに関しても触れているため、ぜひ最後まで読んで理解を深めてほしい。
積立投資とは?

ここでは、以下3点について解説していく。
- 積立投資の仕組み
- 積立投資をすることで得られる効果
- 積立投資の主なメリット
それぞれ見ていこう。
積立投資の仕組み
積立投資とは、自身が指定した金額を指定した商品に定期的に投資していくことをいい、長期的な資産形成を行うにあたっておすすめな投資方法だ。
積立投資に利用される商品としては、投資信託やETF(上場投資信託)、株式などが一般的である。
また、一度設定すれば銀行口座やクレジットカードから積立額が引き落とし・決済され、自動的に投資が行われるため、自身で投資タイミングを見極める必要がない点が特徴だ。
積立投資をすることで得られる効果
積立投資を行うことで投資時期が分散されるため、ドル・コスト平均法の効果が得られる。
ドル・コスト平均法とは、投資する商品(投資信託や株式など)の価格が低いときに多く、高いときに少なく購入することで、平均購入価格が抑えられることをいう。
例えば、毎月10,000円の積立投資を行うとしよう。その場合、月々の投資商品の価格によって、以下のとおり購入口数が変動する。
| 投資商品の価格 | 購入口数 | |
|---|---|---|
| 1月 | 2,500円 | 4口 |
| 2月 | 1,000円 | 10口 |
| 3月 | 1,250円 | 8口 |
| 4月 | 625円 | 16口 |
| 5月 | 2,000円 | 5口 |
上記の例を見ると、最も価格が高いときは2,500円、最も価格が低いときは625円と大きく差があるが、5ヶ月分の平均購入価額を計算するとおよそ1,163円となる。
ドル・コスト平均法を活用することで、商品の価格が高いときに一括投資をしてしまう「高値掴み」のリスクを軽減できるため、自身の資産における価格の変動幅が抑えられるのだ。
積立投資の主なメリット
積立投資の主なメリットとしては、以下の3点が挙げられる。
- 購入のタイミングに悩まない
- 少額から始められる
- 市場の変動に強い
先述したとおり、積立投資は一度設定してしまえば自動的に指定した商品の買付が行われるため、購入のタイミングに悩まないのは大きなメリットだ。
投資を行う場合、自分自身で市場動向を見極めて運用するケースもある。しかし、積立投資は精神的な負荷も少ないことから、資産形成のハードルが低い。
また、少額から始められる点もメリットの一つだ。100円から投資できる商品も数多く存在するため、初心者でも取り組みやすいのである。
加えて、積立投資を継続することによってドル・コスト平均法の効果が得られ、市場の変動に強い点もメリットといえる。
積立投資におすすめの運用法5選とおすすめ銘柄

積立投資を行うにあたっておすすめの運用法は以下の5つだ。
- 新NISA(つみたて投資枠)
- iDeCo
- 投信積立
- るいとう(株式累積投資)
- ロボアドバイザー
それぞれ解説していく。
新NISA(つみたて投資枠)
新NISAとは、株式や投資信託などの運用で得られた配当金や分配金、売却益が非課税となる「少額投資非課税制度」のことをいう。
例えば、新NISAにて運用を行い、10万円の利益が得られたとしよう。
その場合、利益に対する課税はされないため、10万円がそのまま手元に入ってくることとなる。
一方で、新NISA以外の一般口座や特定口座にて運用し10万円の利益が得られた場合は、10万円に対し20.315%が課税され、手元に残るのは79,685円まで減ってしまう。
そのため、運用成果を最大化するためにも、新NISAを活用して積立投資を行うことが重要だ。
また、新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つの枠が用意されている。
「つみたて投資枠」では、長期投資に相応しい一定の基準を満たした投資信託に対する積立投資のみが可能で、年間120万円(月10万円)まで非課税で投資ができる。
投資初心者は「つみたて投資枠」を活用して運用することがおすすめだ。
もう一方の「成長投資枠」では、投資信託のほか上場株式やREIT、ETFに対して積立投資もしくはスポット投資が可能で、年間240万円(月20万円)まで非課税で投資ができる。
ただ「つみたて投資枠」と「成長投資枠」を合わせて1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)が限度となる点には注意してほしい。
つみたて投資枠のおすすめ銘柄
なお、つみたて投資枠で運用可能なおすすめの銘柄として、以下2商品を紹介する。
- eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」は、三菱UFJアセットマネジメントによって運用されている。
ベンチマークである「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に連動した運用成果を目指すインデックスファンドだ。
先進国である日本やアメリカをはじめ、インドや台湾などの新興国の株式も投資対象として含まれており、全世界に幅広く分散投資ができるのが大きなメリットである。
また、期間別に見たこのファンドにおける騰落率は以下のとおりだ。
| 期間 | ファンド | MSCI オール・カントリー・ ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース) | 差 |
|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | +4.7% | +4.7% | ー |
| 1年 | +32.5% | +32.3% | +0.2% |
| 3年 | +63.1% | +62.8% | +0.3% |
上記の表を見ると、過去1年・3年においては、ベンチマークを若干上回る運用成果を出しており、安定した運用が行われていることがわかるだろう。
加えて、このファンドにおける購入時手数料および信託財産留保額は無料で、運用期間中支払い続ける必要がある信託報酬は、年率0.05753%〜0.05775%※と非常に低コストで運用が可能な商品だ。
※ファンドの純資産総額が5,000億円未満の部分:0.05775%、5,000億円以上1兆円未満の部分:0.05764%、1兆円以上の部分:0.05753%
そのため、全世界を対象に幅広く分散投資をしたい、運用コストを徹底的に抑えたいという人は、このファンドで積立投資を行うことがおすすめだ。
なお、2025年1月17日時点の純資産総額は5兆3,031億400万円で、基準価額は27,102円である。
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
続いて「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」は、前述のファンドと同じく三菱UFJアセットマネジメントが運用しており「S&P500指数(配当込み、円換算ベース)」をベンチマークとしたインデックスファンドだ。
名前のとおり、投資対象はS&P500を構成する米国株式で、世界最大の経済規模を誇る米国の経済成長の恩恵を享受できるというメリットがある。
それだけでなく、米国にはさまざまな業種の企業が存在するため、幅広い業種に分散投資ができるのもメリットの一つだ。
また、期間別に見たこのファンドにおける騰落率は以下のとおりである。
| 期間 | ファンド | S&P500指数 (配当込み、円換算ベース) | 差 |
|---|---|---|---|
| 6ヶ月 | +7.5% | +7.5% | ー |
| 1年 | +40.8% | +40.6% | +0.2% |
| 3年 | +78.0% | +77.0% | +1.0% |
このファンドにおいても、安定した運用成績を収めていることがわかるだろう。
加えて、このファンドにおける購入時手数料・信託財産留保額は無料で、信託報酬も年率0.09240%〜0.09372%※とコストが抑えられている。
そのため、運用コストを抑えながら米国企業に幅広く投資したいという人におすすめのファンドだ。
なお、2025年1月17日時点の純資産総額は6兆6,685万6,600万円、基準価額は33,378円である。
- ファンドの純資産総額が5,000億円未満の部分:0.09372%、5,000億円以上1兆円未満の部分:0.09306%、1兆円以上の部分:0.09240%
iDeCo
iDeCoとは、自分で設定した掛金を自身で運用していく年金制度で「個人型確定拠出年金」と呼ばれる。
原則20歳以上65歳未満の方が加入可能で、自身が拠出し運用した金額を一時金もしくは年金として受け取れるのは原則60歳以上だ。
iDeCoを利用する最大のメリットは、税制優遇措置にある。
拠出時は掛金の全額が所得控除となり、所得税や住民税の軽減効果があることに加え、運用によって得られた利益に対する課税もない。
また、給付を受け取る際には、公的年金等控除(年金受取の場合)または退職所得控除(一時金受取の場合)が受けられるのだ。
課税所得を減らしながら資産形成を行いたい人にはおすすめの制度といえる。
ただ、拠出額の上限は国民年金の被保険者区分によって異なり、例えば、第1号被保険者であるフリーランスや自営業の方などは年間816,000円(月68,000円)、第3号被保険者である専業主婦(夫)の方は年間276,000円(月23,000円)となる点には注意が必要だ。
iDeCoへの加入前には、自身の加入区分を確認し、いくらまで拠出できるのかをあらかじめ把握するようにしてほしい。
投信積立
投信積立とは、任意の金額を設定し、定期的に投資信託を積立購入していく運用法だ。
100円などの少額から始められるため、誰でも始めやすいというメリットがある。
一方、投資金額が少額であると短期間での大きなリターンは見込めないため、少なくとも10年以上の長期投資を心がけることが重要だ。
るいとう(株式累積投資)
るいとう(株式累積投資)とは、月々1万円から100万円(1,000円単位)の範囲内で、指定した株式に積立投資を行っていく運用法をいう。
配当金の受け取りも可能で、受け取った配当金は自動的に再投資される。
通常、株式への投資は1単元(100株)からの取引となり、銘柄によっては数十万円以上の元手が必要となるケースもある。
その点、るいとう(株式累積投資)を活用することで単元未満での取引が可能となると同時に、少額から株式投資が始められる点が大きなメリットだ。
また、るいとう(株式累積投資)によって持株数が100株を超えると購入者自身の名義へと変更され、議決権が行使できたり、株主優待が受けられたりするようになる。
ただ、全ての株式に対してるいとう(株式累積投資)が活用できるわけでなく、証券会社によって対象となる銘柄が異なる点には注意してほしい。
ロボアドバイザー
ロボアドバイザーとは、投資の目的や自身のリスク許容度、何年間の投資期間を設けられるか等、いくつかの項目に回答することで、最適な投資方針・ポートフォリオの作成などを行ってくれるものだ。
投資の知識が不十分な初心者であっても、気軽に始められる点が大きなメリットである。
ロボアドバイザーは、どの範囲まで自動化させるかによって「投資一任型」と「アドバイス型」に分かれる。
まず、投資一任型とは、ポートフォリオの作成や商品の選定、運用まで全て自動的に行ってくれるサービスだ。
ウェルスナビや楽天証券が提供する「楽ラップ」などが有名である。
運用成果を定期的に見直し、自動でポートフォリオの組み替え等も行ってくれるため、自身で運用するという手間は一切かからない。
ただ、その分手数料が高くなる点には注意が必要だ。
一方、アドバイス型とは、ポートフォリオの作成や商品の選択方法に関するアドバイスのみを行うサービスで、マネックス証券が提供する「マネックスアドバイザー」などがある。
商品の買付やポートフォリオの見直し等、投資一任型と比較すると自身で行わなければならない範囲が広いため、ある程度投資に関する知識を有していないと、アドバイス型での運用は難しいだろう。
自分で投資する商品を選択して運用したり、ポートフォリオを定期的に見直してリバランスを行ったりすることに不安を感じている方は、ロボアドバイザーの「投資一任型」を活用して積立投資をすることも検討してみてほしい。
積立投資の商品選びのポイント

積立投資の商品選びを行う際のポイントは、以下の4点だ。
- 信託報酬の水準
- 投資対象の分散
- 自身のリスク許容度
- 過去の運用実績や投資家からの評価・口コミ
これらを意識しながら商品を選択してほしい。
信託報酬の水準
投資信託やETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)などにて積立投資を行う場合、信託報酬の支払いが発生する。
信託報酬とは、運用会社や商品を販売する証券会社などに支払うコストのことで、商品を保有している限り支払い続けなければならない。
そのため、信託報酬が高いとそれだけ運用成果が圧縮されてしまうのだ。
信託報酬の水準は商品によって異なることから、投資対象が同様のファンドを複数比較し、最も信託報酬が低い商品を選択することが重要である。
投資対象の分散
積立投資によって投資時期の分散が可能となるが、投資対象の分散も意識するべきだ。
投資対象を分散するためには、投資地域を分散させる方法と資産クラスを分散させる方法がある。
まず、投資地域を分散させることで、カントリーリスクを抑えることが可能だ。
投資対象となる地域によって、経済情勢や政治動向などが異なるため、商品も値動きが異なるケースが多い。
例えば、中国やインドなどの新興国は、アメリカや日本などの先進国と比較して経済情勢等の変動が大きくなる傾向にあり、それに伴ってボラティリティも大きくなる。
そのため、カントリーリスクによる価格変動リスクを抑えるためにも、投資地域を分散させることが重要だ。
また、資産クラスを分散させることも意識してほしい。
資産クラスの分散とは、株式のみに投資するのではなく、投資信託や債券なども組み合わせて投資することをいう。
そうすることで、異なる値動きをする商品に投資ができ、価格変動リスクを抑えられるというメリットがあるのだ。
自身のリスク許容度
自身のリスク許容度を把握することも、積立投資を行う商品を選定するにあたって重要なポイントだ。
リスク許容度とは、運用によって発生するマイナスをどれだけ許容できるかといった程度を表すものだ。
例えば、以下に当てはまる方はリスク許容度が高いといえる。
- 収入が多い
- 今までに投資をした経験がある
- リスクよりもリターンに目を向けている
- 長期の投資期間が確保できる若年層
反対に、以下に当てはまる方はリスク許容度が低い。
- 今までに投資の経験がない
- 収入に余裕がない
- 近い将来に大きなライフイベントが想定される
- 感情に左右されやすい
上記の基準に照らし合わせながら、自身のリスク許容度を把握してみよう。
なお、リスク許容度が高い方は、ハイリスクであるものの高いリターンが見込める新興国を投資対象とした商品、リスク許容度が低い方はローリスク・ローリターンである先進国を投資対象とした商品や、全世界を投資対象とした商品を選択することをおすすめする。
過去の運用実績や投資家からの評価・口コミ
過去の運用実績を見ることは、以下の点から重要である。
- その商品におけるリスクやリターンを把握するため
- 長期投資に適切な商品であるか見極めるため
- 他の商品と比較するため
過去の運用実績は、将来のリスクやリターンと一致するわけではない。
それだけでなく、半年前や1年前からの運用実績を確認したとしても、一時的なものである可能性があり、信頼性の高い情報とはいえない。
信頼性の高い情報を得るためには、最低でも過去3〜5年程度の運用実績を確認するようにしよう。
また、投資家からの評価や口コミもチェックしてほしい。
ただ、オンライン上にはさまざまな情報があふれているため、信頼できるページ(証券会社等の公式ホームページや投資に関する比較サイトなど)にて情報を収集し、あくまでも補助的要素として活用しよう。
積立投資でNISAとiDeCoはどう使い分ける?

積立投資におけるNISAとiDeCoの使い分けについて、ここでは以下4点を解説していく。
- NISAのつみたて投資枠を最大限に活用する方法
- 長期投資の重要性
- 新NISAとiDeCoの比較と上手な使い分け方
- 併用という選択肢もある
それぞれ見ていこう。
NISAのつみたて投資枠を最大限に活用する方法
NISAのつみたて投資枠を最大限に活用するためには、まず具体的な投資目標の設定を行う必要がある。
何のために投資を行うのか、何年間の運用でいくらまで増やしたいのかを明確にしよう。
そうすることで、自ずと設定するべき積立額やリスク許容度に合わせた商品選定ができるはずだ。
また、NISAのつみたて投資枠は、年間120万円(月10万円)、非課税保有限度額1,800万円という2つの限度額が設定されている。
自身の投資目標と余裕資金額に合わせて、最適な投資戦略を検討してほしい。
長期投資の重要性
積立投資によって長期投資を行うことによって、ドル・コスト平均法の効果が得られるだけでなく、複利効果を得ることも可能だ。
複利効果とは、運用によって得られた利益(配当金や分配金など)を投資元本に組み込んで再投資することによって利益に対しても利息が付き、雪だるま式に資産が増えていくことをいう。
例えば、100万円の投資元本を年利5%で複利運用した場合、資産は以下のとおり増加していく。
| 運用年数 | 投資元本 | 利息 | 元本+利息 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 100万円 | 5万円 | 105万円 |
| 5年 | 121万5,506円 | 6万775円 | 127万6,282円 |
| 10年 | 155万1,328円 | 7万7,566円 | 162万8,895円 |
上記の表を見ると、どれだけ長期投資が重要となるかがわかるだろう。
新NISAとiDeCoの比較と上手な使い分け方
新NISAとiDeCoについて、簡単に制度の概要を比較してみた。
| 新NISA | iDeCo | ||
|---|---|---|---|
| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | ||
| 年間投資限度額 | 120万円 | 360万円 | 816,000円※1 |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円(うち成長投資枠1,200万円まで) | ー | |
| 最低積立額 | 100円〜 | 5,000円〜 | |
| 運用期間 | 無制限 | 65歳まで | |
| 運用商品 | 長期投資に適した一定の投資信託 | 投資信託・上場株式・ETF・REITなど | 定期預金・保険商品・投資信託 |
| 税制優遇措置 | 運用益が非課税 | ・運用益が非課税 ・拠出額の全額所得控除 ・給付受取時に所定の所得控除※2 | |
| 備考 | ・投資額はいつでも変更が可能 ・引出しに関する制限はない | ・拠出額の変更は年1回 ・投資対象となる商品は3〜35商品 | |
※2 年金受取時:公的年金等控除、一時金受取時:退職所得控除
上記の表を見ると、年間の投資(拠出)限度額や最低積立額、運用期間において大きな違いがあることがわかるだろう。
また、新NISAにおける税制優遇措置は運用益に対する非課税のみであるが、iDeCoは運用益に対する非課税のみならず、拠出額の全額所得控除や給付受取時の所得控除などが受けられる。
一方、新NISAはいつでも投資額の変更や引出しが可能であるというメリットがあるが、iDeCoは拠出額が年に1回しか変更できないことに加え、選択できる運用商品数が少ないといったデメリットがある。
そのため、自身の運用目的に合わせて新NISAとiDeCoを使い分けるようにしてほしい。
併用という選択肢もある
新NISAは、自身の任意のタイミングで引出しが可能であることから、短期的な資金需要も視野に入れつつ老後資金に向けた長期投資を行うのであれば、新NISAを活用すると良いだろう。
一方で、iDeCoには原則として60歳まで引き出せなかったり、拠出額の変更が年に1回しかできなかったりと制約が多いものの、新NISAと比較して税制優遇措置が充実している。
そのため、運用期間中における柔軟性よりも税制優遇措置にメリットを感じる、運用目的が老後資金の準備である、といった方は、iDeCoを利用すると良いだろう。
また、新NISAとiDeCoを併用してはいけないといった制限はないため、資金に余裕がある方は、2つの制度を併用して効率的な資産形成を目指してほしい。
積立投資を成功させるためのポイント

積立投資を成功させるためには、以下の3点を意識してほしい。
- 少額から始める
- 短期的な市場変動に振り回されない
- 定期的にポートフォリオを見直す
それぞれ解説していく。
少額から始める
積立投資によるドル・コスト平均法や複利の効果を得るためには、無理なく継続して投資をしていくことが重要だ。
投資はあくまでも余裕資金で行うものであって、生活資金を切り崩してまで行うものではない。
生活資金を切り崩して始めから高額な積立額を設定してしまうと、損失を被ってしまった場合に自身の生活にダメージを与えてしまうだけでなく、積立投資が継続できない可能性がある。
自身が資産運用に回せる余裕資金を把握するために、収入と支出を振り返ると同時に、今後想定されるライフイベント(マイホームの購入や子どもの進学など)を確認しよう。
その上で、無理なく継続投資できる金額を算出してほしい。
短期的な市場変動に振り回されない
市場はさまざまな要因が複雑に絡み合って変動を繰り返しているため、短期間で大きな市場変動が起こるリスクもある。
しかし、短期的な市場変動に振り回されて運用を途中でやめてしまうと、長期投資によって得られる複利効果が十分に得られないというデメリットもある。
市場は上昇と下落を繰り返しながらも、右肩上がりに成長していく可能性が高い。
そのため、長期投資を行っていくことで、一時的に大きな損失を被ったとしても資産の回復が見込まれるのだ。
また、投資商品によって価格変動リスクも異なることから、自身のリスク許容度にマッチした商品を選択し、長期投資を意識することが大切である。
定期的にポートフォリオを見直す
積立投資は、一度商品を選択して積立額を設定するだけではなく、定期的にポートフォリオを見直すことが重要だ。
自身が目標とする運用成果は出せているか、積立額は適切かなどを確認するようにしてほしい。
また、年数が経過していくことによってリスク許容度が変化している可能性もあるため、改めて自身のリスク許容度を把握することも忘れないようにしよう。
運用成果などを振り返った上で、必要に応じて商品の組み替えや積立額の調整をすることで、より効果的な運用が可能となるはずだ。
ただ、適切なポートフォリオの見直しは市場動向の見極め等も必要となり、投資に関する一定程度の知識が求められる。
そのため、ポートフォリオの見直しに不安がある方は専門家に相談することも検討してみよう。
積立投資は「資産運用ナビ」で見つけた専門家と進めるのがおすすめ

ここでは、以下2点について解説していく。
- 積立投資を専門家に相談しながら進めるべき理由
- 「資産運用ナビ」のメリットと活用法
それぞれ見ていこう。
積立投資を専門家に相談しながら進めるべき理由
積立投資によって自身の運用目標を達成するためには、適切に投資戦略を立案しなければならない。
それだけでなく、定期的なポートフォリオの見直しも重要なポイントだ。
しかし、投資初心者の場合、投資戦略の立案に向けて欠かせない「リスク許容度の把握」や「適切な運用資金の算出」ができない可能性がある。
そのようなときに、専門家に相談することで、運用目標の達成に向けた最適な投資戦略の立案に協力してくれるだろう。
自身のリスク許容度に合わせた商品を選定し、より効果的な運用を行うためにも、専門家に相談しながら積立投資に取り組むことがおすすめだ。
「資産運用ナビ」のメリットと活用法
「資産運用ナビ」とは、相談したい内容や自身の年齢、金融資産保有額などの簡単な項目に対してオンライン上で回答することで、専門家とマッチングできるサービスだ。
また、このサービスに登録されている専門家の中から、今までに対応してきたお客様層や対応可能な曜日、提携している証券会社などのフィルターをかけて検索することも可能である。
それだけでなく、それぞれの専門家のプロフィールも閲覧できることから、自分のニーズに合った専門家と出会える可能性が高いのだ。
専門家への初回相談は無料でできるため、自分に合う専門家が見つかるまで何度でも面談可能なのは魅力的なポイントだろう。
ここまで繰り返し述べてきたとおり、積立投資は「長期投資」が重要だ。
「資産運用ナビ」を活用し、ともに長期的な資産形成に取り組んでくれる専門家を探そう。
積立投資におすすめな運用法で長期的な資産形成を目指そう

本記事では、積立投資に関する基本情報やおすすめの運用法、商品選びのポイント等について解説した。
積立投資を行うにあたっておすすめな運用法は「新NISA(つみたて投資枠)」「iDeCo」「投信積立」「るいとう(株式累積投資)」「ロボアドバイザー」の5つである。
それぞれ特徴が異なるため、自身にあった運用法を選択してほしい。
また、積立投資を成功させるためには、少額から始めることに加え、短期的な市場変動に振り回されずに長期投資を継続し、定期的にポートフォリオを見直すことが重要だ。
これらを意識することで、ドル・コスト平均法による市場変動に強い資産形成が行えるほか、複利効果が得られるというメリットがある。
さらに、積立投資においては自身のリスク許容度にマッチした商品選定や適切な投資戦略の立案が大切なポイントとなるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめする。
そうすることで、より効果的に資産形成が可能となるはずだ。
ただ、専門家は全国各地にいるため、どのように選べば良いかわからないという方もいるだろう。
そのような方は、投資家と専門家のマッチングサービスである「資産運用ナビ」を活用し、長期的な資産形成に協力してもらえるパートナーを見つけてほしい。
積立投資のおすすめに関するQ&A